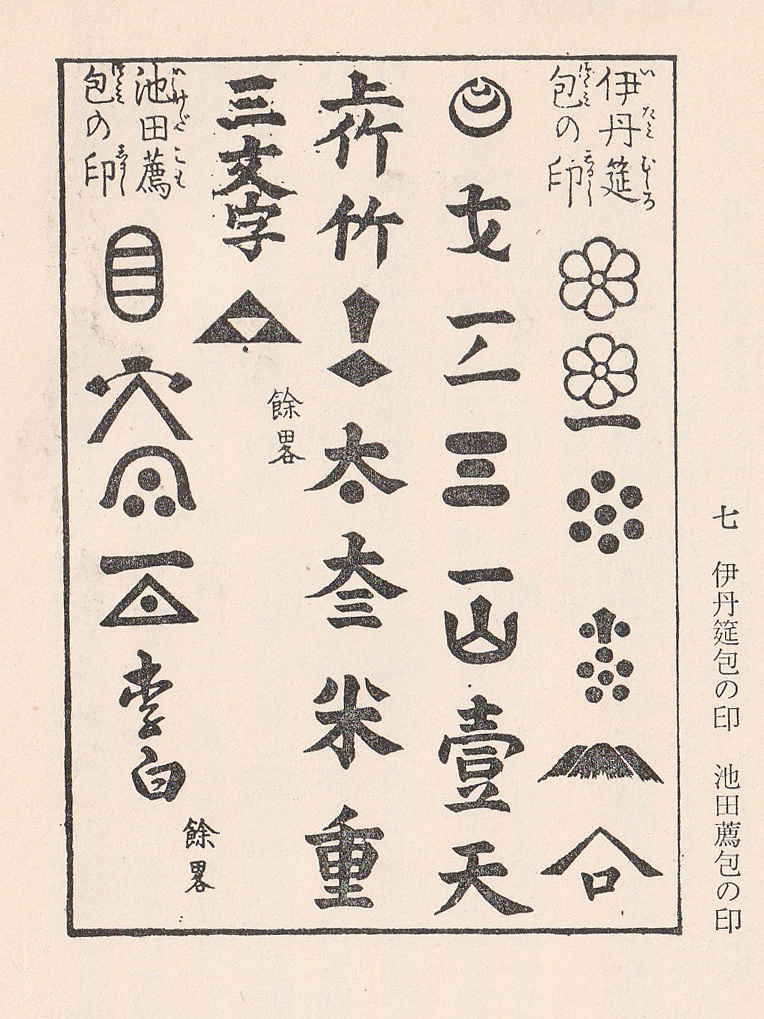
鯛の潮煮の方 フーデックスでの試飲に関する感想 多聞 一本〆 白子宿 (九)すが〻きかはり 玉子の前 奈良流之事 管巻太平記 本役・半役 柳橋の店々 芋の煮ころがし、おでん 暗愚 滝野川 上澄 うわずみ 冷酒 いばらき【茨木】 断食問題 山形県西村山郡谷地町沢畑 満を持する苦節三年の大酒飲み 3A 格言、ことわざ、種々の言いまわし 56 霊妙な数秒間 至急送ってほしい を飲みに行く旅(2) 大みつ、富士屋 酒はたべもの 婆娑羅 果実酒の否定 灘酒の精米歩合 麦 むぎ 鴈治郎椀久 冷酒 れいしゅ 図表3-5 主な各県の開発酵母 元禄十年の酒造株改め 三白酒 みそ【味噌】 伊丹諸白と灘酒 狂言鶯蛙集 おまえは実に悪にして善だ 父のスケツチ ウィンストン・チャーチル 櫂類(かいるい) 銘酒各種の値段 酒に二枚の舌 「バー學校」閉校さよならパーティー 妊娠中の母親の飲酒 剣菱 けんびし 狂歌才蔵集(2) 鳥久 朝起きたら 鉄橋の上で寝た 非常の太鼓 酒を飲む瞬間は オーストラリアで造る「豪酒」 ネット時代の居酒屋 与謝野晶子の酒歌 対酒 剣菱 遊び酒 ▽ビリー・カーター 酒盛り唄 閑居 寒山詩 吉田集而の説 ルバイ第四十 せんせい[先生] 伊丹、池田筵菰包の印 (増)盃を伏せて置く はせがわ酒店 酒税増税 安倍川の川越 (八)なる川 五百万石 世界一統 ワインに似て非なる妙味 酒の肴 ちろり[銚釐] 梅酒 うめしゅ 酒屋・土倉 頭に酒のくる句(4) 玉子酒 濁酒之事 玉子たまご 「米百俵」 いはない【岩内】 狂い酒 小鍋立 山鯨 食物年表1800-1850 灘の明治維新 奥殿諸白 秋田県仙北郡中川村ほか 近江商人 頭に酒のくる句(3) 酒盆の行儀 飲むときの挨拶 川升 街灯 酒を飲みにゆく旅 原始の混沌か、未来の大破局 とろる[動] 上戸 境界守のゲシク・パトゥ 水とぶどう酒 少彦名命や三輪明神 柳風呂 酒肆内田屋紋処のこと 冷や奴 ひややっこ 禁酒宣言 鄭玄 庄七の忍術 青山椒 あをさんせう 伊丹酒 寒造り集中政策 みぎ【右】 美少年酒造にて 薏酒 水に含まれる成分と酒への影響 周恩来 福田氏 アナクレオンとアルカイオス 落第事 伊丹諸白 下戸 げこ 昔の男ども 六波羅殿御家訓 酒価の変遷 目張紙 ドブロクとオマンズシ 子どもの急性アルコール中毒 蛇の肝 足一本丸ごとタコ焼き 秋田屋(浜松町) 狂歌才蔵集 友人会宿 裏通り 長酔 自然災害 酒食は人の好む物 デカダンス 秋風起りて蟹を思ふ 自賛 犬 甘党 燗と冷や 酒のなる木 仕事の分担 △製灰 しゅ-ぎょう[修業] 酒の字 ルバイ第三十九 米だけの酒 介入を成功させるには ちよき[猪牙] 東西の味かげん 白鷹 南米では受けると思う 坂口記念館 増税 (七)むら田 若竹屋酒造場 盃の織部形 餅米酒之事 鰭酒 酒屋土倉 推はちがうた 石川弥八郎賞 いなだひめ【稲田姫】 梵妻 豆腐田楽 ワインのことわざ 日本の酒 れろれろ 三白酒-さんすさびのあととめあっれなぱくしゅ 食物年表1700-1800 玉山已ニ倒レテ 花見 はなみ ぬけ酒と収税さん 酒銘江戸一の始め 信州酒と注文のコツ 柳の酒 振り酒 定年書店 まんぢゆう【満仲】 久里浜病院 池田酒 詩酒徒 淡白を上 味わいのバリエーション 節度ある酒 宮城県名取郡秋保村 ムスタファ・ケマル 新夕刊新聞社 あてこすりの歌 家飲み 後撰夷曲集(10) 西国、猩々を獲 南都諸白 怪猫 酒の値 火の車、學校の肴 鯨 くじら 酒の飲み方 くつ石 酒造資本と酒造経営 技の受け継ぎ 冬はやっぱりイカ大根 やき屋(荻窪) コカ・コーラ アルコール性痴呆 どぜう飯田屋 居酒屋GPS! 67醴を勧む 柴 晩年の父 勧酒と返杯 わかさぎの木の芽焼き 7日 湯豆腐 古文書から元禄の酒を再現 安飯屋、居酒屋 三分の酒二分の水 火落酸 眼前 一杯の酒 古酒の幅 しゃ-しん[写真] △家言 宴席の伏兵 〇詩ヲ賦シテ志ヲ言フ 洒落言葉・隠語 日本酒を温める理由 玲瓏随筆 良寛の詩 【山梨県北杜市・山梨銘醸】 (六)しよがえぶし 酒飯論 新潟清酒研究会 花、果実、木質などの風味 日本盛 大酒の戒め アルコール症者の子供 その方の父は毎年死んだか ちやびん[茶瓶] 食物年表1600-1650 熱燗(燗酒) 酒屋名簿 小米酒之事 いなだ【稲田】 (増)盃事の式 上戸 寄鍋 よせなべ 狂言と擬音語・擬態語 ルバイヤート(抄) 清酒酒質の様変わり
鯛(たい)の潮煮(うしおに)の方
鯛、身もほねも、常の如く切り候(そうろう)て、古酒をひた/\に入、火を細くして煮申候(もうしそうろう)。酒の匂(にお)ひ無之(これなき)時、其(その)上へ水を入、しほばにてかり仕立申候。鱒(ます)などの汁は醤油少加吉(すこしくわえるがよし)。 『合類日用料理指南抄』巻之五 魚類、雑の類
鮮度のよいタイ、スズキ、アマダイなどの頭やアラ、または骨つきの切身、ハマグリなどを使い、そのものの持ち味で、薄い塩味に仕立てた吸い物が潮(うしお)だが、塩だけの味であることが特徴。酒でほどよく煮て、アルコール分がなくなったときに水を入れ、最後に塩で味をととのえる。椀にタイを入れ、ウドの短冊切りか、よりウドなどと木の芽をあしらい、熱い汁を張って鯛の潮煮の出来上がり。あつあつのうちのいどうぞ。(「料理名言辞典」 平野雅章編)
フーデックスでの試飲に関する感想
過去三年間にこのフーデックスで試飲してもらった感想を総合的に見ておきたい。①初年度は、7割以上の外国人が日本酒をはじめて飲んだといっていたが、それが昨年では6~7割程度と減った。そして今年の場合、日本酒初体験者は6割前後と徐々に少なくなっている。地道な各方面での海外への進出の努力が実っているのだろう。②燗酒については好き嫌いがはっきりしているものの、ベルギーやギリシアなどで好まれはじめたというのは興味ある現象だ。アメリカなどでの従来のぐらぐらのHOT・SAKEではなくて、ぬる燗の妙味がなんとか伝えられないものだろうか。③吟醸酒の分かりやすさの一方で、熟成酒に対する評価の高さは根強いものがある。いずれもステイタスある酒としてのイメージを喪うことなくひろげていけば先は明るいと思われる。④三種の味(本醸造の燗酒、吟醸酒、20年の熟成酒)を試すだけでも、外国人の多くが日本酒のバラエティに関心を示した。これに生酒、純米酒などを添えればさらに注目度は増すだろう。海外市場はまさにこれからが愉しみではないか。(「知って得するお酒の話」 山本祥一郎) 平成15年の出版です。
多聞
多聞は、そう歴史の古い蔵ではありません。当時、西宮銀行の頭取だった八馬兼介氏が、不景気のあおりで倒産した四つばかりの蔵の負債を、個人のポケットマネーで処置し、それがもととなって出来たのです。八馬兼介氏は、のち一県一行になった折、神戸銀行となった県下八行の初代頭取としても知られていますが、信貴山信仰に大変厚いところから、その守護神多聞天を銘柄にしたようです。業界では14位。9万3千石の出荷を昭和52年度にはしましたが、北海道と長崎では滅法強い銘柄です。堅実な営業政策をとっている蔵ですが、10万石前後の出荷量から、もう一歩伸び悩んでいるところが、つらいところ。戦後、菊正宗の方から、技師や杜氏が来たようで、酒の味は、菊正宗とよく似ているといわれています。53年末に"辛口"を一部贈答用に販売したのが、予定を上回る好評だったようで、今後の売れ行きが注目されています。ワンカップタイプの「乾杯多聞」は、ラベルの裏側にヌードの写真を入れていて、地味な社風の割りに時折り思い切ったことをやるのも、おもしろいところです。(「灘の酒」 中尾進彦)
一本〆(いつぽんじめ)
「一本〆」は新潟県農業試験場で「五百万石」(母)と、「豊盃(ほうはい)」(父)の交配によって誕生した。栽培する上で「倒伏しやすく収量性が不十分」「耐冷性に劣る」、また醸造する上では「精米歩合を高めると砕けやすい」といった五百万石の欠点を克服した品種を開発するために、新潟県農業試験場で育を成された。一九九三(平成五)年に「一本〆」と命名され、新潟県の奨励品種となった。耐冷性に優れ、精米歩合が低くても割れが少なく、吟醸酒(ぎんじようしゆ)などの原料米として使われている。しかし、倒れにくく作りやすい栽培特性が肥料を多用して収量を上げる栽培につながり、米質の低下を招いたため、次第に使用量が減少した。現在は厳格な契約で米質を維持した少量の栽培が行われている。(「新潟清酒達人検定」 新潟日報事業社)
白子宿
「イヤ、八ねぎまのふろふきか、そいつアよかろう」と北八、手を拍って喜べば、亭主うち消し、「インネ、ふろふきじゃアござらない。たんだ醤油で煮たのだアのし」と言いながら、銚子、盃に、鮪の煮たのを皿に盛って持ってくる。「ハゝア、ねぎまというから、江戸でするようなやつだと思ったら、コリャア雉子焼(きじやき)のように、串にさしたやつを煮たのだ。こいつアうまかろう」「サア弥次さん、初めよう。オットゝゝゝ」一猪口(ちよこ)あけて、肴に箸をつけた北八、一口食うと、たちまち顔をしかめて、「イヤ、この肴はお陀仏だぜ。オイ、コリャア昨日(きのう)の鮪だナ」「インネ、ハア昨日(きんによう)の魚(いお)じゃアござらない」「それでもさっぱり、食えねえ/\」と、弥次郎兵衛も文句をつければ、「ハア、昨日(きんによう)が悪かア、一昨日(おとつい)のを進ぜましょうか。その代り、酔うこたア請合いだアもし」「エゝ、肴に当って酔っぱらってたまるもんけえ、そしてこの酒は半分水だの。ペッペッペッ。弥次さん、行こう。サア幾らだの」「ハイ、肴が六十四文、酒が二十八文」「イヤ、うめくねえ代りにゃ高えもんだ」と、銭をはらい、茶店を出る。
八 ねぎま(葱と鮪)と、ねりま(練馬大根)とを掛けて洒落たもの。ふろふきは大根を厚く輪切りに煮て、熱いうちに食する料理。(「東海道中膝栗毛」 十返舎一九 三好一光訳)
(九)すが〻きかはり
今時(いまどき)ふられぬ床(とこ)のうち、御くらゐ諸訳(しよわけ)もらちがない、ねぬけの女(ぢよ)らう身あがり紋日(もんび)はとむねが、又(また)してお茶(ちや)をひき質(しち)まで置(お)きはて札(ふだ)ばかり、古金買(ふるかねかひ)も我(が)を折(を)つた、遣手(やりて)の穿鑿(せんさく)うるさし、くるわは物思(ものおも)ひ、此里(このさと)のがれたや、料理にかまはぬ茶漬(ちやづけ)に焼味噌(やきみそ)心がけ、こ〻らはよい燗一(かんひと)つと、納戸(なんど)をうろ/\さがせど、朝酒(あさざけ)のまうにも貧(ひん)なる揚屋(あげや)でござせない
くるわ-くつわの誤か ござせない-ござんせぬ(「若みどり」 藤井紫影校庭)
玉子の前
玉子を好んで毎日食ひけるに、ある夜美しき娘来たる。ふしぎに思ひ「お前はどこからござりました」と問へば「私は日ごろお好きなさるゝ玉子の精でござんす」「さて/\さやうでござるか。まづ酒でも参れ」と盃などいだし、さま/"\と話けるに、八つ半時分になりて、一番鶏(どり)、こけこふと鳴けば、娘「もうお暇申します」といふ。「それはどふぞ、まそつと遊び給へ」といへば「あそこで、おやぢがしきりに呼ばれます」(かす市頓作巻五・宝永五・玉子の前)(「江戸小咄辞典」 武藤禎夫編)
(2)奈良流之事
(二)夫レ奈良流ハ可レ謂フ二酒ノ根源ト一。故諸流自レ是起而其家ヲ立、尤大切ナル流也。掛四ツヨリ五ツ迄也。
一、元ハ三斗ヲ大元とし、壱斗五升を半元とす。
一、元水壱斗弐升、麹六割。半切三枚仕込様、掻様以下当流同前。
一、元日数十四、五日過、半切弐枚に(3)入込、廿四、五日過て一枚に入込、其後小泡立時{上:草冠、下::陪」め申也。惣而奈良流ハ元泡立間ハ不レ{上:草冠、下::陪」候。是若き元を嫌ふ故也。但し日数三十日さへ過候へハ、泡不立とても{上:草冠、下::陪」て不苦。
一、{上:草冠、下::陪」様、当流同前。温め入様ハ朝・晩両度宛入へし。入替る度毎に温め樽にて掻廻し、群なく温ミ入渡る様に仕へし。温めハ何本成とも好次第、大泡一面に立上(あが)る時引也。此時も能掻合せ、蓋・包莚ともに取除候也。
一、枯し日数、当流同然也。
(2)奈良流の造り方
奈良流は酒造りの根源というべきものである。だから諸流派がここから起こり、それぞれ流派を立てた。最も大切な流派である。奈良流の掛は四回から五回行なう。
○酛の量は、三斗を大酛として、一斗五升を半酛とする。
○酛水は一斗二升、麹は蒸米の六割である。三枚の半切への仕込み方、櫂の入れ方以下は当流と同じである。
○酛を仕込んで十四、五日過ぎたら、半切一枚に集め入れ、二十四、五日過ぎてからさらに一枚に集めるその後、小さな泡が立ったときにつぼめるのである。概して奈良流では、酛に泡が立たない間はつぼめないものである。これは若い酛をきらうからである。しかし、日数が三〇日を過ぎさえすれば、泡が立たなくてもつぼめてかまわない。
○つぼめ方は当流と同じである。暖気樽は朝と晩と一日二回の割合で入れる。入れ替えるたびごとに暖気樽でかき混ぜ、むらなく温かみが行き渡るようにすること。暖気樽の本数は何本でも好きなようにし、大泡が一面に立ち上がったときに引き上げる。このときにもよくかき混ぜ、ふたのむしろ、包んだむしろをともに取り除くのである。
○枯しの日数は当流と同じである。
(2)奈良流 奈良の僧坊酒にはじまる諸白造りの先進流派。ふつう掛は三回であるが、四、五回行うのが奈良流の特徴。 (3)入込(いれこむ) 酛の内容物を半切に集めていくこと。
[書き下し](二)それ奈良流は酒の根源と謂(い)いつべし。故に諸流是より起こりて其の家を立つ。尤も大切なる流なり。(「童蒙酒造記」 吉田元校注・執筆) 酛の造り方です。
管巻太平記(くだまきたいへいき) 七珍万宝
本書の主題としたのは、燗(かん)をして飲む一群と冷(ひや)でくむ一群との合戦であるが、燗党は剣菱など関西生産の下りの銘酒であり、冷酒党は特に銘柄は記していないが、焼酎・泡盛が援軍となっている。この二者の合戦は、、下り酒の第一人者満願寺の仲介で和睦となるが、この合戦は二日酔の夢であった、と黄表紙常套の結末となっている。この冷酒(ひや)とは、どんな酒を指しているのか、燗党と冷酒党とが合戦をするという趣向の発想が、奈辺にあったか。-
天明七年の新酒発売の九月十日頃に江戸の酒類販売業界には事件(トラブル)があって、その内紛をとりあげたのが本書のウガチとなったのではあるまいか。そう考えると燗党と冷酒党の争いは、「下り清酒対江戸中汲」の販売合戦と見做すことができる。(「管巻太平記」 花咲一男)
本役・半役
次に酒屋役は定期的課役と臨時課役の二つに分類せられる。而して定期課役の徴収は一年一度或は数回徴収せられるところの、いわゆる「年役」ではなくして、毎月これを酒屋に徴した。即ち年十二回の徴収であったのである。またこの定期的酒屋役は酒屋の営業状態に応じて、本役・半役(或は半公事)の別が存在した。本役は本来の標準課役を指すものであり、半役とは本役の半額に相当するものである。半役制度に関してその成立年代はこれを明確にすることは出来ないが、管見によれば、嘉吉元年十(1441)一月二十日懸納並進納分注文に、「酒屋参百拾七ヵ所但此内新加共廿五ヵ所半公事分沙汰之、」とあるをもって初見とする(古文書第十二集)。-
即ち、第一条に於ては、新加酒屋は営業開始より爾後六回に亘って、従って半箇年半役制を適用し、以後本役を適用すべきことを規定し、第二条に於ては、火災の被害を受けたる酒屋も半役制の適用同前たることを規定している。(「中世酒造業の発達」 小野晃嗣)
柳橋の店々
酒楼の夥(おびただ)しき 、亦(また)都下に冠(くわん)たり。曰く川長(カハチヨウ)、曰く一八万八(まんぱち)、橋の北に在り。曰く梅川(うめがは)、曰く亀清(カメセイ)、曰く一九河内(カハチヤ)、曰く柳屋(やなぎや)、橋の南に在り。平三(ヒラサン)や、深川(フカガワテイ)や、草加(さうかや)や、皆二〇帘(れん)を米沢街(よねざはちやう)の側(がは)に張る。而して柏屋(カシハヤ)・中村・青柳(アホヤギ)三楼、亦二一咫尺(しせき)水を隔つるのみ。其の他、丸竹(マルタケ)・若松(ワカマツ)・和泉佐(イズサ)・小松亭(こまつてい)の若(ごと)き小店子肆(デミセ)、指僂(かがむ)るに暇(いとま)あらず。中に就(つ)く、酒肴(シユカウ)最も佳なる者は、二二川長なり。柏屋之(これ)に次ぐ。万八・河内・中村等の店は、則ち属に貸席(カシザシキ)と称する者にして、二三右軍道子(シヨカエカキ)の書画会(しよぐわくわい)、二四陶朱猗頓(カネモチ)の醵金(ムジン)会、及び歌舞(オドリサミセン)・挿花(ハナ)の師匠(ししよう)、業を開(ヒロメ)き技を試(サラヰ)むる者、仮りて以て筵(むしろ)を排(なら)べ、衆を募(つの)る為(ため)にす。聞く、二五更代(キンバン)藩士の始めて都(エド)に来る者は、必ず先(ま)づ梅川若(も)しくは青柳(アヲヤギ)に飲むと云ふ。其の名の世(よ)に播(し)く、已に久しきを以てか。然れども、梅・青の二戸、近時漸(やうや)く冷にして(ケチニナリ)、酒肴香味(しゆかうかうみ)、殆(ほとん)ど亀清(かめせい)の徒に及ぶこと能はず。鮓舗(スシヤ)は則ち二六安宅(アタケ)・二七与兵(ヨヘイ)・中川(ナカガハ)あり。鱣肆(ウナギヤ)は則ち玉甚(タマジン)・山口(ヤマグチ)・舟治(フナヂ)あり。客若(も)し一たび手を拍(う)てば、則ち二八珍羞芳饌(ちんしうはうせん)、纍乎(るいこ)として陳(ナラブ)す。
一八 柳橋の北東にあった料理屋、万屋八郎兵衛。貸座敷で有名で、書画会などがよく行われた。江戸名物詩にも「万八書画会」と題する狂詩が収められている。 一九 柳橋の南西にあった料理屋、河内屋半次郎。同じく書画会の会場によく使われた。 三〇 酒旗。中国で酒屋が標識として立てる旗。漢文的文飾。日本の実景ではない。 二一 わずかに川を隔てている。この三軒は両国橋の東側にあった。 二二 「柳橋北の川長、宅広からずと雖も美食なり」(守貞謾稿)。 二三 右軍は晉の王義之の官職が右軍将軍であったことから書家の意。道子は画聖と称せられた唐の呉道玄の字。画家の意。- 二四 陶朱は春秋時代、越の范蠡(はんれい)が官を退き、山東省の陶に赴いてからの変名。、商人に転じて巨富を築いた。猗頓は春秋時代の魯の人、塩を扱って富豪となった。カネモチが無尽講の集まりを行う。 二五 勤番侍。江戸屋敷勤務が当たって出てきた田舎武士。 二六 松の寿司ともいう。柳橋の北、浅草第六門前町にあった。 二七 両国橋の東側にあった。江戸名物詩に「与兵衛鮓(向両国元丁)流行の鮓屋町々に在り。此の頃新たに開く両国の東。路地の奥名は与兵衛。客来たり争い坐す二間の中」。 二八 珍しい御馳走、かぐわしい料理。(「柳橋新誌」 成島柳北 日野龍夫校注)
芋の煮ころがし、おでん
江戸の居酒屋では、芋の煮ころがしを肴にして酒を飲ませる店があり、「いも酒屋」といった。里芋を醤油と味醂で味付けし、転がしながら汁がなくなるまで煮切ったものである。当時、ジャガイモはまだない。江戸時代の居酒屋では、豆腐や芋、コンニャクの味噌田楽が人気であった。やがて、野菜やハンペン、油揚げを開いて具材を巻いた信田(しのだ)巻きなどを醤油と味醂で煮込んだものを「おでん」と呼ぶようになり、田楽に取って変わった。江戸の町中を「おでん燗酒、甘いと辛い」と売り歩く荷売りも現れた。甘いは煮込みおでんで、辛いは味噌田楽である。おでんは、現在も居酒屋の定番であるが、もう一つの定番「モツ煮込み」はまだない。(「江戸の居酒屋」 伊藤善資)
暗愚(あんぐ) 高村光太郎(たかむらこうたろう)
金がはいるときまったやうに
夜が更けてから家を出た。
心にたまる膿(うみ)のうづきに
メスを加へることの代りに
足は場末の酒場に向いた。
-お父さん、これで日本は勝てますの。
-勝つさ。
-あたしは昼間は徴用でせう。無理ばつかし言はれるのよ。
-さうよ。なにしろ無理ね。
-おい隅(すみ)のおやぢ。一ぱいいかう。
-歯ぎり屋もつらいや。バイトを買ひに大阪行きだ。
-大きな声しちゃだめよ。あれがやかましいから。
-お父さん、ほんとんとこ、これで勝つんかしら。
-勝つさ。
午前二時に私はかへる。
電信柱に自爆しながら。(「酒の詩集」 富士正晴編著)
滝野川
吟醸酒は品評会から生まれた。歴史的にいえば、全国清酒品評会と全国新酒鑑評会というのがその母体である。それはどこであったか。東京都北区滝野川にあった国立の醸造試験所である。明治三七年以来、九〇年の歴史を持つ試験所が東広島に移る。この年(平成六年)は吟醸酒の揺籃であった滝野川を離れる最後の年になる。品評会、鑑評会で名をあげ、銘醸といわれるようになった酒蔵たち、またそのようになりたいと吟醸の技を磨き続けた蔵や酒づくり男たちにとって、「滝野川」という言葉はある種の聖地を意味するものでさえあったのだ。私が滝野川に立ち会ったのは昭和三四年のことであった。以来、私はここに四〇年近い年月を注視してきた。今年でここを去る。この滝野川最後の全国新酒鑑評会に、私はどのような形で別れを告げるのか迷っていた。きき酒会場である四階建ての建物に一礼するのか、杜氏たちの嬉し涙、悔し涙を吸った敷地に伏せて謝意を表すのか、そのような思いの男たちのために何か儀式が行われるのか。もやもやした気持を抱いてきき酒の列に並んだ。この十数年間と同じように列は長蛇をなしていた。やがてきき酒のところへ辿り着き、いつもと同じように速いピッチできき酒を終え、滝野川を離れた。建物に最敬礼をする者も大地に伏せる者もいなかった。特別な儀式も何もなかった。人々の列は三々五々、王子駅へと向かって消えていった。(「「幻の日本酒」酔いどれノート」 篠田次郎)
上澄 うわずみ
濁酒の上溜まり、その澄んだ部分。原酒に木灰や水を加えるなどして沈殿を速め、その上澄みをすくい取ったものである。諸白以前の上酒は皆これで、中汲みや滓(おり)にくらべ値段も張った。▽お上の御酒ゆゑ拙者が普段たしなむ上澄などとは各段の違ひ、はらわたへ沁み渡るやうぢゃて○『宇都宮釣天井』序幕 ▽まず濁酒を作り、その上澄みを、更に何かの方法で精製するということがあったのかも知れなくて-吉田健一「酒」○「日本の名随筆 酒」(「日本の酒文化総合辞典」 荻生待也編著)
冷酒 れいしゅ ひやざけ
日本酒は燗をして飲むものだが、口あたりがよいので、夏は冷で飲む人が多い。特に冷酒用に醸した酒もある。
冷し酒夕明界となりはじむ 石田波郷
冷し酒世に躓きし膝撫ぜて 小林康治
冷凍酒旅にしあれば妻ものむ 森川暁水
教師づら失せ痩身に冷酒飲む 山下率賓子(「合本俳句歳時記新版」 角川書店編)
いばらき【茨木】
①茨木童子の略称。-
二三杯吞むと茨木頭痛がし 大江山で毒酒(「川柳大辞典」 大曲駒村編著)
断食問題 二・一八-二二(マタ九・一四-一七 ルカ五・三三-三九)
一八ある断食日(だんじきび)に洗礼者ヨハネの弟子(でし)とパリサイ人(じん)が断食(だんじき)をしていると、人々が来てイエスに言う、「ヨハネの弟子とパリサイ人の弟子は断食をするのに、なぜあなたの弟子は断食をしないのか。」一九イエスは言われた、「婚礼(こんれい)の客は花婿(はなむこ)がまだ一しょにいるうちに、断食をして悲しむことが出来ようか。もちろん花嫁と一しょにいる間(あいだ)に断食は出来ない。二〇しかしいまに花婿を奪(うば)いとられる時が来る。その時、彼らはいやでも断食をするであろう。二一真新(まあたら)しい布切(ぬのぎれ)で古い着物に継(つ)ぎをあてる者はない。そんなことをすれば、新しい当(あ)て切(ぎれ)は古い着物をひきさき、裂(さ)け目(め)はますますひどくなる。二二また新しい酒を古い皮袋(かわぶくろ)に入れる者はない。そんなことをすれば、酒は皮袋を破って、酒も皮袋もだめになる。」(「福音書」 塚本虎二訳)
山形県西村山郡谷地町沢畑
70酒盛の後でさらにアト祝イとかウチ祝イというようなことがありますか。それを何といいますか。残りものはどうしますか。
アトフキ・アトブルマイ-酒盛の時、主として料理係とか給仕係になった、いわゆる当番衆というものが、酒盛終了後改めて酒盛を行なう。
71酒盛に参加する人はどういう人ですか。酒盛の性質によって違いますか。男ばかり、女ばかりという場合がありますか。それはどんな場合ですか。参加すべき人がしなかったらどうしますか。
とくに確然と区別された酒盛はなし。ただし地蔵講のごときもので簡単な酒盛をする場合は女だけのものもあることがある。参加すべき人がしなかった時は、代理人を出す。代理も出なかった時は料理だけ送る。
87甘酒を作りますか。どんな場合に作りますか。作り方はどうしますか。ほかに異なった名称がありますか。祭礼などの場合、昔の濁酒の代わりに作ることはありませんか。甘酒と濁酒との相違する点はどこにありますか。
甘酒
作る時-正月・三月節句・伊勢参り帰着の日。 昔の濁酒の代わりである。 作り方-糀(こうじ)三升に餅米五升の割で米だけの粥を炊き、やや冷えた頃これに三升の糀を入れ、よく攪拌して冷やす。よく冷えたものをさらに釜に入れて火クレを行ない、沸騰しない程度まで温め、攪拌して冷やす。この操作を五回くらい繰り返して行なう。
○濁酒-ミゴリ酒という。
五十年くらい前まではどこの家でも造り、お茶の代わりに飲んだが、今ではこの風習はまったく止んだ。とくに田植酒・正月酒などは多く造った。
甘酒と濁酒の違い。
甘酒は糯米を粥に炊き、それに糀を入れるが、濁酒はウル米をふかして、それに糀と素(もと)を入れ水を加えて火クレをする。
88醸造業者でなく,濁酒が造られていましたか。それはどんな時に造られたでしょうか名称は何といいましたか。村祭りの時には今でも造りますか。どうしてつくりますか。芋酒、焼酎など造られましたか。これらの酒類は個人個人で造りましたか、村とか組とかが共同で造りましたか。女は関与しませんでしたか。
前項のとおり五十年くらい前まではどこの家でも造った。
○造る場合は、時を構わない。
○芋酒・焼酎は造らない。
○個人で造った。
89一年のうち酒を飲む機会はどれくらいありますか。平均一戸当たりどれくらいの量を用いますか。どんな種類の酒ですか。毎日常用する人が何人くらいありますか。飲酒家と酒嫌いの比率はどれくらいですか。大酒家というのはどれくらい飲みますか。軽い程度の酒の肴には何を用いますか。
酒を飲む機会-平均して三日に一回くらい。一年の量-一ヵ月三升平均で三斗六升。
○種類-並み以上の清酒。三斗六升のうち五升くらいは焼酎。
○飲酒家とそうでないものの率-飲酒家は六割、そうでないものは四割。
○大酒家-一升から一升五合。
○軽い酒の肴-漬物(菜・大根)。(「日本の食文化」 成城大学民俗学研究所編)
満を持する苦節三年の大酒飲み
都内の民放テレビ局のCM部にいるFさん(三八)は一升酒を飲む。酔うと腕こそ振り上げないが、からむ、大声を出す、食器を割るの三拍子がいつもついて回る。だから、一度つき合った新人社員が二度つき合うことはまれである。Fさんの酒癖の悪さは忘年会でも衰えることはなかったが、この二年間は精彩を欠いていた。実は、三年前のつけがずっとついて回っていたのである。その年の忘年会は、一泊で草津温泉で開かれた。宴会がはねた後、同僚たちは部屋に消えたのに、一人Fさんは浴衣(ゆかた)姿のままふすまに蹴(け)りを入れ、窓ガラスを割った。Fさんはすっかりできあがっており、同僚も宿の従業員もだれも止めなかった。翌朝、しらふに戻ったFさんは、宿から弁償金の明細を示された。その中に玄関前のフロアに飾ってあった大きな花瓶(かびん)も含まれていた。Fさんはその場では清算できず、三年ローンによる支払いで許してもらった。同僚たちはこの額を五十万とも百万とも噂(うわさ)したが、Fさん自身は明かしたことはない。ただ、このローンがやっと終わることは胸を張って宣言した。「この三年間、Fさんはお銚子を割るときには、さっと品定めをしてから行動に移っていた」と証言する同僚たちのいまの関心は、今年の忘年会である。三年間のエネルギーが一気に爆発するか、それとも本当に普通のレベルの酔っぱらいに変身したのか、一部では賭(か)けが成立しているのである。(「デキゴトロジー ホントだから勘弁できねえ!の巻」 週刊朝日風俗リサーチ特別局編著)
3A
アメリカには「3A」というサラリーマンの三悪があります。事故(Accident)、欠勤(Absenteeism)、アルコール中毒(Alcoholism)の三つだそうです。こうしてみると、三に話をしぼるのはなにも日本人の特許ではないらしい。そうそう、アチラ生まれの野球も三が基本になっていますね。三(スリー)ストライクで三振、三死で攻守交代、九人の選手で九回攻守を行って試合終了、たしかに三に基づいたゲームです。(「井上ひさしの日本語相談」 井上ひさし)
格言、ことわざ、種々の言いまわし 56
朝早く酒を飲んで酔えば一日の苦労。
布長靴がきゅうくつなのは一年の苦労。
二人の妻をめとれば一生の苦労。(「オルドス口碑集」 A・モスタールト 磯野富士子訳)
霊妙な数秒間
酔いの経過は、いったい、どのようなものであろうか。心臓の鼓動が早くなってくると、何処か暗い森の遠い奥で皇帝ジョーンズを追っているリズミカルな太鼓が鳴りはじめるような気がしてくるが、そのリズミカルな膊動(はくどう)が次第に胸をのぼってきて、耳許で暫く停まっていると思うまもなく、やがて、数秒間、その耳許の太鼓は不意にまったく軀と同じ大きさになり、そして、軀全体が一枚の霊妙な震動板となって宇宙の何処かから発せられている意味も解らぬ神秘音に繊細に共鳴しているような感に襲われる。この感覚は僅か数瞬である。従って、酒が体内の運河を廻ってゆくのに凝っと気をつけている性癖のものでないと、この瞬間は容易には捉えがたいが、もし気づけば、これが酒のみの味わう最も霊妙な数秒間の時間でもあろうか。その数瞬が過ぎてしまえば、軀と同じに大きくなった太鼓は、さらに軀を越えて行ってしまってもはやもとへもどってこないのである。つまり、その数瞬のあとには、体内感覚はなくなり、絶えず外交的な酔っぱらいの状態がやってくるのである。(「酒と戦後派」 埴谷雄高)
至急送ってほしい
1941年9月、ドイツ軍がレニングラードに侵攻し、たちまち包囲されてしまった。ソ連軍の善戦のもと、戦いは長びいた。一日も早くレニングラードが解放されることが期待されていたが、ある日、守備隊長から、至急送ってほしい、という電報が届いた。武器が足りなくなったのかと思ったら、「もっと度の強いウォッカを送って下さい。戸外の温度は零下45度。ここにあるウォッカは40度。とても戦争になりません」というものだった。(「ジョーク「ロシア革命史」」 歴史探検隊)
酒を飲みに行く旅(2)
次に飲んだ酒は秋田の「高清水}。市内川反(かわばた)の、看板もない小料理屋「なか」。常連だけの、商売気の全くない、気持ちのいい店であり、女主人と、その妹さんの美しさはそれだけでウットリする。この時は男鹿の海岸でブリコ、つまりはたはたの卵を拾ってきたのをかじりながら飲んだ。勿論、丼のフタを杯がわりに酒よりも空気を吸うという宮崎流の飲み方である。飲んだキッカケは、大好きな「秋田長持唄」をたっぷりときいていい気持になっていたからである。この時もうまいと思った。その後美しい妹さんは結婚し、僕は花を届けた。大変にアッケない話だが、僕が酒をうまいと思ったのは以上の二度だけである。つまり、僕にはそれほど、酒を飲むチャンスがないし、うまいからといって、また、飲みたくなるということもないのである。「高清水」はさげて帰って来たのだが、家の猫がひっくり返して割ってしまった。それでも別に残念だとは思わない。我が家には「酔心」がいつでもある。但し、これは僕のではなく、女房ならびにお客様用である。要するに僕は酒が目の前にあってもの飲まないわけで、もし今後、飲むとすれば、また、宮崎サンをお訪ねした時か、秋田の川反へ行く時であろう。(「酒を飲みに行く旅」 永六輔) 酒を飲みに行く旅
大みつ、富士屋
(浅草の)観音堂に向かって右が三社権現、それから矢大臣門(随身(ずいじん)門)、その右手の隅に講釈師が一軒あった。門を出ると直ぐ左に「大みつ」といった名代な酒屋があった。チロリで燗(かん)をして湯豆腐などで飲ませた。剣菱(けんびし)、七ツ梅(うめ)などという酒があった。馬道へ出ると一流の料理屋富士屋があり、もっと先へ出ると田町(たまち)となって此所は朝帰りの客を招(よ)ぶ蛤鍋(はまなべ)の店が並んでいる。馬道から芝居町(しばいまち)へ抜けるところへ、藪の麦とろがあり、その先の細い横町が楽屋新道(がくやしんみち)で、次の横丁が芝居町となる。猿若町は三町目まであって賑(にぎ)わいました。(「名高かった店などの印象」 高村光雲)
酒はたべもの
読者からの質疑はこのほかにも「お前は酒のことを"ふしぎなたべもの"と書いたがその理由如何」-などがあったが、これには次に少しくコメントさせて頂くこととしたい。-人は皆噛むことなくのどを越すものを飲みものと呼び、水分と他の成分との混否の割合には関心をもたない。その意味では酒をたべものと言うのは一寸おかしく感ずるのに無理はない。しかし昔から万国を通じて一国の主食の原料はおおむねその国の酒の原料と一致するとされているから、醗酵は主食または主穀の調味のための調理法の一種とも見られる。その意味では酒は料理された主食物で、「たべもの」であるといっても少しもさしつかえない。おかしいという方が反っておかしい。酒の主成分のアルコールが人の体内に入ってからの化学的変化の経路についてはこの書の本文に述べておいたから御理解いただけるとおもう。もっとも微生物学者の栄養学は信用できぬということならこちらも一言もない。
婆娑羅
婆娑羅(ばさら)を代表する人物に高師直(こうのもろなお)、土岐頼遠、佐々木道誉があげられるが、「身ニハ五色ヲ飾リ、食ニハ八珍ヲ尽シ、茶ノ会酒宴ニ許多(ここだ)の費(ついえ)ヲ入、傾城(けいせい)田楽ニ多量ノ財ヲ与ヘ」(『太平記』)という生活を送り「綾蘿錦繍(りようらきんしゆう)精好銀剣(せいこうぎんけん)、風流服装目を驚かさざるものなし」(『建武式目』)とまでいわれる状況を呈していたのである。それは大名ばかりではなかった。「近頃は庶民や市(いち)の商人まで綾絹や薄物で身をよそおい、美しい色彩の着物をふだん着にしている。上下の差別はなくなったのにひとしい」と当時の書物に記されるほどであった。(「京都故事物語」 奈良本辰也編)
果実酒の否定
果実酒とは、今更申すまでもなく、果実にふくまれている糖分を、そのまま発酵させてアルコールにかえたものである。この果実酒が成立するためには、当然、糖分を充分に含有し、しかも酸味の余り強くない果実の存在が要求される。しかし、残念ながら、わが国のような風土ではそのような果実は育たない。典型的な温帯国なる日本では、春夏秋冬の四季がほぼ三ヵ月ずつ、実に正確にくりかえす。春美しく咲き乱れた花は、真夏にはその強烈な陽光を利用してドシドシ糖類を同化、合成する。出来た糖類は次々と果実に貯えられて行くが、その果実、いな植物自体も活発に新陳代謝をつづけるので、その副産物なる有機酸もドンドン生成される。そのため、甘さはずい分甘いはずだのに、舌の上ではいかにも酸っぱい果物ができている訳だ。ところが、もし高緯度の地方で春秋が非常に短かく、夏がすぎた途端に気温や陽光が急激に降るとすれば、糖合成はそこそこでサッとストップするが、有機酸の生成は-植物が冬眠に入るので-なお更そうそうにやんでしまう。従って、糖分そのものの絶対量は温帯にくらべて少ないかは知らないが、酸が比べものにならぬ程少なく、とても甘い果実を秋の実りとして期待できる。だからこそ、地中海岸から中部ヨーロッパにかけて、あのおいしい葡萄酒がつくられる所以である。日本は、さきに述べたように、酒精原料になるほど果実が糖分を含んでいる時には、産もまた多すぎる。酸が頃あいになると糖分が薄くなりすぎる。河内堅上あたりの葡萄酒造りは、原料に砂糖を沢山混ぜるし、良心的に果実だけで造る山梨のそれはいかにも酸っぱい。わが国の果実で、果実酒が造れるほどの糖分をつくるのは柿ぐらいでは無いかしら。ところが柿渋はいかにも渋い。(「日本酒の源流」 篠田統)
灘酒の精米歩合
十八世紀後半、灘では六甲山から流れ下る急流に水車を仕掛け、この動力で杵を上下させる水車精米法(図4)を開発し、天明八年(一七八八)には、すでに六五輛もの米搗き水車が稼働していた。『続灘酒沿革史』(一九〇七)によれば一臼一斗(二五キログラム)の玄米を、夜通し約二日かかって一割八分(精米歩合八二パーセント)まで搗いたという。酒米は白く搗けば搗くほど酒の香味はきれいになることから、八分搗きの伊丹諸白と一割八分搗きの灘酒との品質の差は明白であったろう。(「江戸の酒」 菅間誠之助)
麦 むぎ 麦の穂 穂麦
わが国で普通栽培されている麦は大麦・裸麦・小麦・ライ麦・燕麦などでいずれも秋まいて初夏に刈り取る。四月半ばには、六-九センチの粗大な円柱形をした穂状の花一割八分穂を直立する。これを穂麦という。五月ごろ、熟して黄色くなった麦畑は美しい。
麦の穂に夕雲沁みる地酒よし 高島茂(「新版俳句歳時記」 角川書店編)
鴈治郎椀久
そのあとは、鴈治郎を主役とする椀久の芝居であった。正確な外題は、記憶しない。節分の夜、茶屋というのか、揚屋というのか、とにかくそうした場所である。商人の一座が乱雑にさわいでいる。封印を切ってはならぬ金をふところにした鴈治郎の椀久久兵衛だけが、つつましやかに、疎外されて、すわっている。こまかい筋は忘れたが、何か約束事があり、不安をかくしきれない。ときどき立ちあがって、窓の外をのぞく。人人は、酒をしい、久兵衛は、つつましやかに、巧妙に、ことわる。しかし、しだいに呑まされ、しだいに酔い、とど、ふところの封印を切って、鬼は外、とわめきながら、小判をばらまく。人人は争ってひろい、羽織の袖が、さんざんにはねあがる。下座のはやしは、高潮の極にある。ふいに美しい色彩のものがあらわれ、舞台中央につったち、うちかけで久兵衛をおおい、かばう。松山太夫である。役者は中村梅玉(ばいぎよく)、今の大阪の福助の祖父にあたろう。うちかけの中の久兵衛は、松山に見とれる。鴈治郎の顔は、恍惚そのものである。最後の小判の一枚が、久兵衛の手を放れる。そうしていう。福は内。小判は、生あるもののように、きらきらとかがやき、華麗に舞いおりる。そこで柝(き)がはいり、幕になった。子どもの心魂は又もや動蕩した。
二つの動蕩は、子供がその後年において求める美と真実の方向を、何ほどか規制しているように思われる。それから五十何年、しかしその人の足は、歌舞伎の劇場へは、まだときにおもむいても、能舞台からは、ほとんど全く遠ざかっている。己酉六月九日。(「帰林鳥語」 吉川幸次郎)
冷酒 れいしゅ
夏は燗をした酒よりも、冷たい酒のほうが口あたりがよい。そのため冷やで飲む人が多い。特に冷酒用に醸造した酒も市販されている。
冷や酒をあふって情に疎くなる 山本翠公
妻として言い分はあり冷凍酒 池田可宵
冷や酒を飲むのも家庭砂漠かも 山田正業
道なき道登り分けあうワンカップ 松永渓路朗(「」川柳歳時記) 奥田白虎編
| 名称 | 発見された場所・年 | 特徴 |
| AK-1 | 秋田・平成元年 | 通称「秋田流花酵母」。現在「きょうかい15号」として頒布も行われている。そのほかに秋田では「AK-3F」等の酵母の開発も進められている。 |
| 山形KA | 山形・昭和62年 | 県内酒蔵の熊本酵母の醪からの分離。大吟醸のほか、純米吟醸にも広く利用されている。通称「山形酵母」。 |
| YK-2911 YK-0107 |
山形・平成2年 | ともに細胞融合、遺伝子操作で開発した低アルコール酒向け酵母。純米吟醸「やまがた清々」に使用。 |
| F701 | 福島・平成3年 | 通称「うつくしま夢酵母」。酸が低く香りが穏やか。平成6年よりこの酵母を使用した純米大吟醸が県下の酒蔵からいっせいに販売されている。 |
| アルプス酵母 | 長野・平成3年 | 吟醸香の成分であるカプロン酸エチルの生産量が高く、華やかな香りが特徴。長野県内だけでなく鑑評会の即戦力のように目されている酵母で全国各地で吟醸酒向け、純米酒や本醸造のブレンド用に利用されている。 |
| HD-1 NO-2 NEW-5 |
静岡・昭和50年~ | 県の工業技術センターが開発した一連の酵母で、総称して「静岡酵母」と呼ばれている。酸が低く爽やかですっきりとした酒質を生む。吟醸酒向けの酵母。 |
| せとうち21 | 広島・平成7年 | 酸が低くみずみずしい洋梨のような香りが特徴の吟醸酒向けの酵母。 |
| CEL-19 | 高知・平成5年 | 香りの高い吟醸酒向けの酵母。カプロン酸エチルの華やかな香りが特徴。この他にも高地には「A-14」「AC-17」等の酵母がある。 |
| KW-77 | 高知・平成2年 | 熊本酵母とワイン酵母を細胞融合して作った酵母。 |
(「日本酒のテキスト」 松崎晴雄)
元禄十年の酒造株改め
西鶴が「軒を並べて 今のはんじょう」(『織留』)としたのは伊丹・池田の発展であったが、元禄十年には、池田には三八軒の酒造家が存在し、この年の株改めでは一万一二三二石の造酒株石数を請株していた。池田にはいわゆる千石造りの巨大な酒造家と一〇〇石未満の酒造家とが混在していた。軒数からすれば後者は一八軒に及び、とくに三〇石未満のものが一一軒を数えた。そして最高一一三五石を請株した一酒造家の株高は、これら一八軒の請株高合計よりも大きかった。すなわちこれら有力酒造家によって推進されていく特産地の成立であったが、ここでは有力酒造家が土産的規模の酒造家を駆逐していく競争も激化していた。このように展開した事態を前提として幕府は元禄十年にはじめて全国的規模で酒造株改めを実施した。この株改めを実施した表面上の政策は一つには米価調節に必要な造石制限の基準を定めることにあった。しかしこの底には競争の契機を除き発展を一定度の高さで凍結し、酒造業を体制的な分業の一環として包摂しようとする狙いがあった。そして幕府は同十三年からはこの株改めを基準として五分の一造り令を発し、減醸規制を強化した。この減醸規制の強化は一見抑圧政策の実施のごとくにみえるが、未曾有の江戸入津量を記録している元禄十年段階では需要を上廻る供給の制限調整を意味し、このかぎりでは減醸規制の強化は酒価の騰貴を結果していったから、株仲間の営業特権を上から保証したものであった。幕府はこの特権付与に対して五割の運上を賦課した。そして、同十五年には「田畑造り候百姓」の酒造営業への参加を禁じた。特産地酒造株仲間との結合関係を強化したなかで施行されていく一連の政策であった。(「灘の酒」 長倉保)
三白酒
一〇九一 江南の三白酒は素早く流行して中国の半分の地域にまで及んでしまった。しかし、呉興(今の浙江省湖州市)で造る酒は金昌(今の浙江省杭州市昌化県)で造るのより勝れており、蘇州の人がこれを買い求めるのに急であるのは、水と米とを精選することができないからである。泉が清冽であれば、酒は香りがよい。呉興の碧浪湖・半月泉・黄龍洞などの諸泉はいずれも甘味があり清らかなこと尋常でない。富民の家では恵山まで出かけて水を運んで来て醸造しているのが多い。それ故、珍しくて勝れているということになる。(「五雑組」 謝肇淛 岩城秀夫訳注)
みそ【味噌】
②北条時頼が、生味噌で酒を飲んだ故事。(さけ②参照)
人知らぬ酒盛味噌で名が残り 生味噌で飲む
味噌をなめなめ時頼も数献なり 平宣時と共に
愚者の知る風味に非ず味噌の酒 賢者のみ知る
執権のうま味は味噌で飲んだ所 味のある話
味噌で治まり田楽にて乱れ 田楽は高時の所好(「川柳大辞典」 大曲駒村編著)
伊丹諸白と灘酒
寒造りへの集中は、「仕込日数は長くかかるが、できた酒はよい」という『図会』ですでに指摘されていた諸白造りの特化のうちに求められる。それは稼働期間を短縮しながら発酵技術を発展させ、仕込水を増量していったことである。そこで前掲第2表では南都諸白と伊丹諸白との仕込み方法の差異を述べたが、ここでは伊丹諸白と灘酒とを比較することによって、灘酒造業発展の技術的指標を明らかにしよう。第3表は、前と同じく伊丹諸白の仕込み方法を伝える『図会』からの引用であり、灘酒の資料は上灘郷の御影村嘉納治郎右衛門家の実際の仕込方法を書きとめた資料からの引用である。そこでまず寛政期の伊丹諸白と灘酒を見ると、(1)仕舞高(蒸米+麹)は『図会』が八石五斗で灘酒は八石となっているが、寛政四年は減醸令が発令されたための減石かと思われる。(2)蒸米に対する麹の割合は『図会』が四割三分に対し、灘酒は三割三分と少ない。(3)蒸米一〇石に対する水の使用量は、『図会』が五斗一升、灘酒が五斗五升となって、灘酒の方が吸水率ママは高い。以上三点が注目されよう。さらにこれと嘉永元年の灘酒を比較すれば、(1)糀(こうじ)割合が灘酒が三割とさらに少なくなっている。(2)仕舞高は八石五斗仕舞から九石仕舞となり、同じ酛量に対する醪量(白米高+水)が『図会』の一二石九斗から灘酒の一八石へと増大している。(3)水の使用量がさらに増え、「十水(とみず)」(蒸米一〇石に対し水一〇石《こくみず》ともいう)が果たされている。以上、三点である。とくに糀割合は、南都諸白の六割三分(元禄八年)からみれば、ここではいずれも三割台となっていて、この糀割合の減少がすでに伊丹諸白によって克服され、元禄期から寛政期にかけての仕込方法の第一の改良点であった。それに対し、寛政期と嘉永期における注目すべき改良点は、水の使用量の増大という点である。この「十水」は以後の標準的な汲水率となり、灘目がこの改良に成功した意義は大きい。なかんずく、伊丹諸白の酛仕込から留添までの汲水率は漸次減少しているのに比べて、灘酒はむしろ上昇させている点が目立っている。(「酒造りの歴史」 柚木学)
狂言鶯蛙集
唐衣橘洲
生酔はねよげに見ゆる若草に 夢を結ばんことをしぞ思ふ
下戸曲水 あこきのひく網
下戸ならばあちらこちらへ盃を やり水草や餅につきぬる
春の歌とて あから
酒のみつ花をながめついたづらに すぐる月日は一日もなし
五月雨ふりつゝく頃したしき友とひ来りて酒のみけるに軒の板まより雨もりければ 自分斎子璉
五月雨のふる家なれば酒もりの もるをおさへてさし板にせん
隅田川納涼 節松嫁々
涼しさはすゞのとくりのすみだ川 まだきに秋の音をきゝ酒(「新群書類従」)
おまえは実に悪にして善だ
後はやむなく贅言を一切省いて、前六世紀の詩人テオグニスの『箴言詩集』から酒に関わる興味深い詩句を抜き出し、それをもって上代ギリシア詩人と酒との関わりについての詩話を終えることとしよう。
酒はこれ度を過ごせば災いの種、
節度を心得て飲めば災いならずしてまさに良薬。
工匠(たくみ)は火に投じて金銀の別を識る。
されど人の性(さが)を顕(あらわ)すものは酒。
愉しみは心ゆくまで飲み、笛の音に合わせて
歌うこと、響きよき竪琴をかなでること。
酒よ、わしはおまえを讃えもするが、
また咎(とが)めもする
憎みはせぬが、愛するわけにもいかぬ。
おまえは実に悪にして善だ。節度を知る者なら
誰がおまえを謗(そし)ろうか、誰が讃えようか。(「讚酒詩話」) 沓掛良彦
父のスケツチ
林(房雄)さんは酒を飲みながら本の話をし、立つて行つて書庫から話題の本を出して来て下さるばかりでなくて、夢二のスケツチ・ブツクとか黒田清輝の風景画とか、その時々の掘り出しものを披露される。いつだつたか、清水崑氏の得意の、豊麗な唐風の美人を描いた絵馬があつて、これは欲しくてたまらなかつたが、その時は大英百科辞典を盛大に引き散らした揚句に、他に本を五、六冊拝借して持つて帰る矢先だつたので、その絵馬も下さいといふ勇気がなかつた。さう言うことが重なるうちに、いつだつたか、酒の為か、本の為か、恐らくは例によつてその両用を兼ねて伺つた所が、同じく清水崑氏画く所の父のスケツチを出して見せて下さつた。漫画ではなくて、スケツチであり、何とも爽やかな出来栄えのものである。-
といふことは、これを見てゐて、大概の写真よりも私には懐かしい感じが湧いて来るといふことであつて、大いに懐しがつてゐると、林さんはこのスケツチを私にくれると言はれた。それで、その時旅行に出掛けるので拝借しに行つた鞄の中に入れて抱へ、千鳥足で家に帰つて来て開けて見ると、スケツチはくちやくちやになつてゐて、コンテの粉が白い部分になすり付けられ、全体が黒ずんでしまつてゐた。併し重しをして皺を伸ばし、ゴム消しで黒いしみを取つて見れば大体もとに戻り、今、額縁屋にやつて額を作つて貰つてゐる。(「父のスケツチ」 吉田健一)
ウィンストン・チャーチル
酒好きが多い英国の政治家の中でも、逸話の多いのはウィンストン・チャーチルだろう。名宰相として知られ、名文家としても名高く、ノーベル文学賞も受賞している。「酒を飲んで失ったことより、得たことの方がずっと多かった」と豪語していたのは有名だ。酒にまつわる発言は多いが、何かしでかしたような記録は多くない。本人も「他人の前に酔った姿をお見せするほど情けないことはないというしつけを受けた」と述べている。チャーチルが好んだのは薄い水割りかソーダ割り。それをちびちび飲んでいたというから、「泥酔しない」と本人が語るのもわからなくはない。とはいえ、酒量は尋常ではない。薄い水割りとは言え、チャーチルはそれを一日中飲んでいる。「薄い水割りならば一日中飲んでいても大したことがないだろう。チャーチル恐れるに足りぬ」と、英テレグラム紙の記者が真似したところ、「だるいわ、炭酸の飲み過ぎで苦しくなるわでつらかった」と振り返っている。恐ろしいのは水割りだけではないところだ。水割りとは別に、昼と夜の食事のときに食前酒としてシャンパン一本。食中はワイン。食後や夜食にブランデー約一リットルを飲み干した。朝から飲んでいることもしばしばで周囲の者は控えるように言い続けたが、聞く耳を持たなかった。「チャーチルは酔っ払いではない。なぜなら酔っ払いならばあれほど飲めるわけはない。」という者もいた。彼にとって酒は生命維持飲料であった。チャーチル自身、「若い頃はランチの前に強い酒は飲まないと決めていた。今の私は朝食の前に強い酒は飲まないと決めている」と語っている。-
有名な話がある。国会内を足元をふらつかせて歩いていると、ベテラン女性議員から「あなたはひどく酔っているわね」ととがめられる。チャーチルは「あなたは正しいよ。そしてあなたはブサイクだ。しかし明日の朝になればどうだろうか。私はシラフになる。そして君はブサイクのままだ」とやり返した。なんともいけすかないが、それもそのはず。チャーチルが高慢で皮肉屋なのは、彼の生まれとも関係しているのだろう。貴族社会全盛時の英国の名門貴族の出身なのだ。ヴィクトリア時代の申し子と自称していたのもあながち的外れではない。(「政治家の酒癖」 栗下直也)
櫂類(かいるい)
櫂とは容器中において液体、または液体と固体とを混合攪拌(かくはん)し均一にするために使用する道具である.使用目的によりいろいろな種類がある.
1)蕪階(かぶらがい)(大櫂(おおがい)・三尺櫂(さんじやくがい)・酛櫂(もとがい)) もっとも一般に使用される櫂で、竹棒の先に木製のいわゆる蕪(台)を取付けたもので、酒母・もろみや酒の攪拌、物量の溶解促進に使用される.大櫂(長さ約2.3m)、三尺櫂(長さ1.8m)、酛櫂(長さ1.5m)などがある.
2)棒櫂(ぼうかい)(へら櫂(かい)) 棒櫂とは、攪拌部分が平たいへら状で柄の部分が棒状の櫂で、生酛(きもと)で半切に仕込んだ後「山起し」や「山卸し」をする際、半切のすみずみまで攪拌できるようになった櫂である.山廃酛が普及し仕込後の物量をつぶすのに棒状の鬼櫂が使用されるようになって、これと区別するためにヘラ櫂とも呼ばれるようになった.醸試報告(明治39年)に「棒櫂は檜材にて製し、長さ約1尺6寸(約49cm)、幅3寸6分(約11cm)柄の長さ1尺9寸位(約58cm)にして棒状を為(な)す」とある.天保6年「千石酒造場の入用道具控」に「棒櫂12本」と記されており、その時代にこの櫂が使われていたことが立証される.
3)鬼櫂(おにがい) 鬼の金棒の形状をした木製の棒状の櫂で、山廃酛の仕込後、物量が固くてつぶれにくい時に鬼櫂でつぶし攪拌するのに用いる.上部にT字型の把手(とって)がついているものもある.
4)つめ 生酛(きもと)の仕込時に両手に持って半切中の物量を攪拌するのに用いる小さい板状のもので、中央上部の穴に親指を入れて使用する.
なおこれらの櫂類を使用後充分に洗浄し乾燥保存するのに櫂受(かいう)け(櫂棚(かいだな))が用いられる.(「」灘の酒用語集) 灘酒研究会
銘酒各種の値段 『諸国板行帖』所掲
大坂道頓堀芝居側半町下 砂屋五郎兵衛 一合より御望次第、御進物切手出申し候。 名酒直段付 小売仕候。
一、十六味地黄 保命酒 代五匁七分 各一舛に付。
一、白酒 代三匁六分
一、忍冬酒 代七匁五分
一、甘露酒 代三匁七分
一、養気酒 代五匁七分
一、梅酒 代八匁七分
一、美林酒 代五匁四分
一、菊酒 代六匁六分
一、焼酎 上代六匁 並代三匁
薬種 順気養元酒 一舛に付代十三匁 第一中風都而男女不段の病其外諸病に用いてよし。委く効能別紙に御座候ゆえ略之。
右御当地へ出店仕候所、御贔屓厚年々相増御用等被仰付、日々繁盛仕雑有奉存候。右銘酒之儀は外々に有之候酒製とは格別違い、第一風味宜敷、別而日数いか程相立候共味ひ変不申、依而御進物暑気御見舞遠方御土産等、随分御勝手宜敷様いかようにも仕立差上申候間、多少にかぎらず不相替御用被仰付可被下偏に奉希上候。已上。(「江戸物価事典」 小野武雄編著)
酒に二枚の舌
兼好は、酒を好み、「下戸(げこ)ならぬこそ、男(おのこ)はよけれ」(一段)、といっている。ただ、酒宴のような場所で酒を飲むのは嫌っていて、「大方(おおかた)、聞きにくゝ見ぐるしきこと」の一つに、貧しい人の家で酒宴を好み、お客をもてなそうと、派手にふるまうことをあげている(一一三段)。お独りさま暮らしの兼好は、心が通う人と和やかに酒を酌み交わすことを好んだ元祖家飲み愛好者だった-。兼好は、『徒然草』のなかで、酒のもたらすデメリットとメリットを説いているのだが、何にでも関心を寄せる江戸っ子は、
○「兼好は酒に二枚の舌を出し」(柳七五 文政五年)
と茶化したりしている。兼好が聞いたら苦笑いすることであろう。(「晩酌の誕生」 飯野亮一)
「バー學校」閉校さよならパーティー
草野心平が「道はどろんこ。だけんど。燃へる夢のほのほ。」(火の車の歌)と歌って橋本千代吉を助手に居酒屋「火の車」をはじめたのが昭和二七年。六〇年安保デモのさなか心平さんが「バー學校開店」のビラをくばってからでも茫々二十九年、夜学の扉は見事ひらきつづけ、お互いよく学(の)んだもんだと思います。酒に別腸あり、酒は詩を釣る色を釣るなどといいますが、眼前に酒、横に友あれば哀感こもごもいたり、人生ヨカヨカ塞翁が馬の桃源郷でもありました。僕達、卒業見込のまるでない酔諸生は、刻の凍結したあの大時計の真下、時に深夜下校を告げる鐘をきき、足利学校の大扁額にみつめられカンカンガクガクの春秋をすごしたものです。忘れ難き多くの個性がゆきあい、通り過ぎていきました。園生裕一郎の協力と辻一の設計で開かれた「バー學校」のカウンターの向うにいた校長草野心平もいつか酔客の一人となり、山田久代から井上禮子へと飾り気のないふしぎな色香を人気につづいてきました。そしていま、「火の車」以来の灯がついに消えるといいます。創業以来の庶民的な寺子屋流を守り、ビル化の波をしりぞけ、自ら灯を消そうというのです。名残りはつきませんが、酒呑童子・スッテン童女・終電小僧に有明おんななど、OB、OL、現役あい集い、師走の一夜、終業式の盃を盛大にあげようではありませんか。新旧こもごも懐かしい顔の、ふるっての御参加をお待ちしております。
一九八八年十一月 「バー學校」終業式発起人一同
だが太郎さんは、案内状の原稿を書いた直後、六十ニ歳の若さで急死する。珍しく人前で涙を流してその死を嘆いたという心平さんも、それから一週間後、追いかけるようにあの世へ行ってしまった。こちらは八十五歳。だから初代學校の開校式は二人の重要人物を欠いたまま執り行われたのだった。(「酒場學校の日々」 金井真紀)
妊娠中の母親の飲酒
母親が妊娠中に大量に飲酒をすると、血液中のアルコールは胎芽にも入ります。妊娠早期ですと流産の危険があります。胎児性アルコール症候群は、胎児が妊娠中にアルコールにさらされて発生した障害の総体なのです。胎児性アルコール症候群の症状の一つは、成長障害(低体重や低身長)です。これは栄養障害を表しています。二番目には、知能障害を中心とした中枢神経障害です。これはアルコールによる脳の発達障害です。三番目には、特有の顔つき(短い眼瞼裂や鼻の形成不全)やさまざまな奇形です。これは、妊娠初期の器官形成の時期のアルコールによる障害を示しています。この三つのサインが揃っているのをFASと呼び、三つ揃っていない場合はFAE(Feal
alcohol effect)と呼びます。FASとFAEを合わせて、アメリカでは一〇〇〇人の出生で一人いると推定されています。これは、先天障害の中で発生率の高いダウン症と同じくらいの発生率なのです。FASやFAEの子どもは成長しても身体が大きくならないとか、知恵遅れや落ち着きのなさなどの障害が残ります。FASやFAEは、アルコールが胎児に対する毒性を持っていることを示しています。(「子どもの飲酒があぶない」 鈴木健二)
剣菱 けんびし
剣菱を墓にかけたき呑仲間 一一五1
【語釈】○剣菱=酒の代表的銘柄。他に七ツ梅、満願寺、男山、隅田川、滝水などがあった。
【鑑賞】浴びるほど呑んだ酒好きの墓に、上等な酒をかけてやりたいと呑み友達の哀悼の心はどこまでも酒を離れない。
【類句】
下戸に剣菱つんぼうに時鳥 九一32
からしするそばへけんびし持て来る 安六鶴1
(からし↑酢の初鰹を肴にして飲もうという仲間)
剣菱の大紋を着る俄雨 二六6
(四斗樽の包み菰をかぶって走る)(「江戸川柳辞典」 浜田義一郎編)
狂歌才蔵集(2)
一つぶり光
69花の山二色紙(しきし)短冊(たんざく)酒さかな三入相(いりあひ)のかねにしめて何程
69 一- つむり光。桑楊庵と号する。通称は岸宇右衛門。亀井町の町代。寛政八年(一七九六)没、四一歳。巴人亭の号を南畝に譲られて二世となる。 二 花見の席で画や詩歌に使用した色紙・短冊と、宴の酒と肴。 三 「入相の鐘」-「金」。また「入」は「入用」に意味も掛ける。たそがれ時に鳴る鐘の音にはっと現実に戻り、はて今日はいくら金を使ったことやらと思う。 ▽本歌「山里の春の夕暮来てみれば入相の鐘に花ぞちりける」(新古今集・春下・能因法師)のような春の夕暮が、享楽の果の光景と出費の多さに転じるおかしさ。
人〻花の歌よむときゝて、よみて遣(つかは)しける 一一鳳斎
75下戸なればけふのことばの二花角力(はなずまう)三こまたとつても四かちんとぞ思ふ
75 一 「一風斎」と同人か。芝三島町住(江戸方角分)。 二 春秋以外に催される相撲興行をいうが、ここでは花を詠み合う歌合を意味する。 三 諺「小股取っても勝ち」に拠る。多少卑劣な手を使っても勝つ方がよいの意。「小股取る」は小股すくいとも。「角力」の縁で出した。 四 「勝ち」-「かちん」。「かちん」は餅。初句の「下戸」と照応。 ▽下戸なので、今日の歌合では多少卑劣な方法を使ってでも勝って餅を手に入れようというのである。(「狂歌才蔵集」 中野三敏校注)
鳥久
瓶ビールに続いては燗酒を注文します。燗酒は「菊正宗」の上撰で、小さい徳利が三五〇円で、大きいのは六五〇円です。さあ出てきました。焼き鳥です。まずはその名も焼き鳥(一一〇円)という串からいってみましょうか。これは、他の店では正肉(しようにく)とかネギ間(ま)という名前で出されていることが多いですよね。肉二切れと、ネギ二本を交互に刺して焼いた、焼き鳥屋さんの常番メニューです。続いてつくね(一一〇円)。カリッといい焦げ目がついたツクネが三個並んで一串です。ツクネ自体にはほとんど下味はつけていないようで、非常に淡白な味わい。これはタレ焼きもいいかもしれません。レバー(一一〇円)がまたいい味わいです。大きな肝が三個、絶妙なミディアムレアの状態に焼き上げられていて、トロリととろけるのです。鶏の肝も、変な店で食べると苦かったり、臭かったりするのですが、このレバーはそんなところがいっさいありません。あぁ。いっしょにいただくお酒も、よりうまく感じますねぇ。そしてしんぞう(一一〇円)。鶏のハツは私の大好物の品。切り開かれた心臓が三個で一串になっています。絶品なのはくび肉(一一〇円)。小さいながらも脂ののった肉がずらりと串に並んで、肉表面の脂もつややかに、まさにジュゥ~ッと音がしそうな感じの外見なのです。口に含めば、まさにこちらの期待どおりに肉の旨味がウァ~ッと広がります。他の品々もそうでしたが、焼き加減がとってもいいですねぇ。(「ひとり呑み」 浜田信郎)鳥久は東京都杉並区阿佐谷北2-21-22です。この本の出版は平成20年です。
朝起きたら
というわけで、ここではそんな世の女性たちに、とっておきの二日酔い対策をお教えしよう。それは、お酒を飲んで目覚めた翌朝、とにかく何もせずに一五分、鏡の前にじっと座ることだ。映っているのは、まぎれもなくあなた、である。その現実を逃げることなくトコトン直視するのだ。「美」とはほど遠い自分のその姿は、きっと、頭痛や吐き気などよりもよっぽど深い苦しみをあなたにもたらすに違いない。お酒を飲むたびに欠かさず実行すれば、「もうこんなに飲むのはやめておこう…」となることうけあいだ。(「二日酔いの特効薬のウソ、ホント。」 中山健児監修)
鉄橋の上で寝た
あるとき、気をつけて呑んでいたつもりだけれど、新宿でかなり酔ってしまって、連れと一緒に中央線に乗った。飯田橋でおりて、そのときは生家に帰るつもりだったけれど、それからどうしたのかさっぱりおぼえていない。連れともいつのまにか別れ、どこかで京浜線に乗りかえたらしく、気がついてみたら、六郷川の鉄橋の上で寝ていた。どうしてだかはわからないが、多分、蒲田止まりの電車に乗ってそこでおろされたのであろう。起きあがって線路づたいにそそくさと駅に引き返したが、その途中で始発が向うから走ってきた。もう少し寝ていたら、鉄橋の上で轢(ひ)かれるところだったのである。そういう失敗をするたびに、一層また酔わないようにセーブして呑む。ますます呑んだ気がしないが、やむをえない。だから私は酒に関してだけはわりにお行儀がよくて、よく呑むけれどもめったに酔っ払わない。考えてみると実に無駄なことをしているようである。(83.5)(「地下道や鉄橋の上で寝た」 色川武大)
非常の太鼓
楚の厲王(れいおう)は、非常の場合は太鼓を打って人民とともに守りを固めることにしていた。あるとき、酒をのんで酔い、あやまって太鼓を打った。人民はすわこそと色めきたったが、王は人をやってそれをとめさせた。「わしが酔って左右のものとたわむれ、あやまって打ったのだ」人民は皆帰っていった。数ヵ月たって、いよいよ事が起った。太鼓を打ったが、人民はだれも守りにつかない。そこで改めて命令を明らかにしたので、漸く人民も信頼するようになった。(外儲説左上)(「古代寓話文学集 韓非子篇」 高田淳訳)
酒を飲む瞬間は、生きつづけたその人の到達したある一点である。
<出典>現代、武田泰淳(たけたたいじゆん)(一九二一-七六)「杜甫の酒」。田村隆一(たむらりゆういち)編「日本の名随筆」『酒』。
<解説>酒を飲んでいる人間がいる。その瞬間はその人間のおかれている状況のぎりぎりの説明であるということである。中国唐代の詩人・杜甫には酒の詩が多い。それだけを取り出して味わえば、泰然として酒に楽しみ、一酌(いつしやく)して千愁を散らしむの境地。金があれば飲み、酔ってはそのまま伏せて目を覚ましてふたたび飲む。杜甫は地方官吏の家に生まれた。二四歳のとき、出世の早道である進士の試験に落第、放浪生活。李白らと詩酒の交友をもった。杜甫は生活の安定のため、政界の要路に手を尽くして仕官のことを頼んだが実現せず、悶々(もんもん)とした日々を過ごした。安禄山(あんろくざん)の乱に巻き込まれ、賊軍の手に落ちろという苦汁をなめた。脱出して新帝により左拾遺となったが、それも続かなかった。失意と貧困、老齢の悲壮感の中でぎりぎりに歌ったのが杜甫の酒の詩だった。作家・武田泰淳は人肉食の重いテーマの「ひかりごけ」や去勢されて生き恥をさらした男としての「司馬遷(しばせん)」などの傑作があり、人生のふとしたところにぽっかりと口を開ける深淵を描く。泰淳は、「詩人には、唐代社会に於(お)ける自分の位置、混沌(こんとん)世界の中に占める自分の一点が明確に意識されている」と書き、「酔歌はたちまちきびしい意味をもって迫り来る」という。(三浦隆夫)
オーストラリアで造る「豪酒」
私どもは"世界に羽ばたく白雪"でありたい、ということをずっと言ってきております。日本料理店とか日本食というのが、世界に広がってきています。そういう中で、日本酒もアメリカを中心にどんどん広がっているのですが、私どもはちょうど十年前からオーストラリアに進出し、オーストラリアのお米と水で、現地でお酒造りをしております。オーストラリアのニューサウスウェールズ州の、シドニーから南に行く途中にペンリスという町があります。その先がブルーマウンテン国立公園で、オーストラリア観光では有名な所です。蔵のすぐ横に、ネビアン川が流れています。そこでサンマサムネ社として、お酒造りにチャレンジしているのです。お酒は白雪ではなくて、オーストラリア、豪州のお酒ということで『豪酒』と命名しています。(「トップが語る現代経営」 小西酒造株式会社代表取締役社長・小西新太郎) 平成19年の出版です。
ネット時代の居酒屋
ネット時代の現在、真の「穴場」は、すべて消滅してしまったと言えるかもしれない。-とりわけ、地元の常連客で賑わっている老舗があまりにも人気になった場合、厄介な矛盾が生じる。すなわち、常連客の足が遠のき、従来の雰囲気ががらりと変わる。それに加えて、店の前で行列ができたり、または予約しないと入れないような状態になったりして、「ふらっと立ち寄る」ことがほぼ不可能になる。この問題をどのように解決したらよいか、私には分からない。「一見客お断り」にすれば済むかもしれないが、それでは敷居の低いはずの赤提灯の魅力が損なわれるだろう。かといって、店がテレビや雑誌の取材依頼をすべて拒否したとしても、一度しか入ったことのない客が勝手にネットで感想を書いてしまえば、情報がどんどん広がる恐れがある。この大きな矛盾をいったいどうしたらよいのだろうか。さすがに居酒屋探訪をきっぱり諦める気は起きないが、時間をかけて築き上げられてきた、ローカルな店の貴重な雰囲気も害したくない。居酒屋愛好家ならば、この問題を真剣に考えなければならないと思う。いや、何も居酒屋に限る現象ではない。まさに、現在の日本の飲食文化全般が直面している問題だと言ってよいだろう。(「日本の居酒屋文化」 マイク・モラスキー)
与謝野晶子の酒歌
蓮の花船
春はただ盃にこそ注(つ)ぐべけれ智慧あり顔の木蓮や花
はたち妻
やれ壁にチチアンが名はつらかりき湧く酒がめを夕に秘めるな
このおもひ真昼の夢と誰か云ふ酒のかをりのなつかしき春
舞姫
くれなゐの襟にはさめる舞扇(まひあふぎ)酔のすさびのあととめられな
春思
酔に泣くをとめに見ませ春の神男の舌のなにかするどき
その酒の濃きあぢはひを歌ふべき身なり君なり春のおもひ子(「現代日本文学大系 与謝野晶子」)
対酒 酒にむかって-
(二)
昨来 朱顔ノ子 昨日は紅顔の少年も
今日 白髪催(うなが)ス。 今日は白髪が迫り来る。
棘(キヨク)ハ生ズ石虎ノ殿 棘(さんそう)は石虎の殿下に生じ
鹿ハ走ル姑蘇ノ台。 鹿は姑蘇の台上を走る。
古自(いにしへより)帝王ノ宅ト 古(むかし)から帝王の宅や
城闕(ケツ)トハ黄埃ニ閉(とざ)サル。 城の闕(やぐら)は黄塵に閉される。
君若シ酒ヲ飲マ不(ざ)レバ 君が若し酒を飲まなければ
昔人安(いずこ)ニ在リ哉。 昔人は何処に居るか。
-○昨来 通行本には「昨日」となつてゐる。同義らしい。○棘ハ生ズ石虎ノ殿」 東晋時代、後趙王石虎の故事で、石虎が群臣を大武殿に饗応した時、「殿ヤ殿ヤ、棘子 林ヲ成シ、将ニ人ノ衣ヲ壊(やぶ)ラントス」と吟じた者が有つたので、礎石の下を掘つて視させたら、棘の子(み)が生えてゐたと云ふ。(十六国春秋)是は後趙石氏のやがて滅ぼさるべきを諷刺したのであると云ふ。「棘」はナツメの一種、酸棗と云つて、実は酸ぱく、木にとげが多い。○鹿ハ走ル姑蘇ノ台」 春秋時代、呉の忠臣伍子胥の故事で、子胥が呉王を諌めて用ゐられなかつたので、乃ち曰く「将来姑蘇の台に麋鹿の遊ぶ時の来るべきは、今から見えすいてゐます」と。(漢書、伍被伝)姑蘇台は呉王が造ったもので、其の荒廃は呉国の滅亡を意味する○昔人安ニ在リヤ」昔人は死んで何処にも居ないではないか、と云ふことである。此の末二句の間には甚だしき飛躍が有つて解りにくいが、内面の意には、現世に生きる吾々も、やがて死を免れない、だから生有る中に歓を尽くすべきだ、との考が含まれてゐるやうである。即ち君が若し今酒を飲まなければ、昔の人のやうに死んだら、其れきり、もう飲めないではないか、と勧めたのである。(「中華飲酒詩選」 青木正児) 李太白の詩です。
剣菱
辛口を代表する酒に、「剣菱(けんびし)」がある。この酒は、永正年間(一五〇四~二一)に伊丹(いたみ)の稲荷屋が発売したもので、五〇〇年近い伝統をもつ名酒。徳川八代将軍、吉宗の御膳酒だったことでも知られている。さて、この「剣菱」という風変わりな名前には、かなりエッチな由来がある。「剣」は男性のシンボルを表し、「菱」は女性自身を表すというのだ。-なぜ、こんなマークが採用されたかというと、道祖神信仰などと由来はかわらない。当時、男女和合には若返りの意味があり、この酒を飲むと若返り不老長寿の妙薬になるということで、こうした名前がつけられたのだ。(「」SAKE面白すぎる雑学知識) 博学こだわり倶楽部編
遊び酒
日本は四季がはっきりと区別されているので、四季それぞれの美しさを生かした優雅な「遊び酒」が昔から行われてきた。冬の代表は雪見酒。『十訓抄(じつきんしよう)』にある白河院の風情あふれる雪中盃はあまりにも有名で、これ以後雪見酒の宴は雅遊・粋遊の極とされる。春は花見酒。古くは奈良、平安の宮廷貴族中心の風流な観花宴がある。桃山時代、豊太閤の醍醐の花見などは歴史に残る豪華な園遊の宴であった。徳川時代に入ると、家族や友人、隣近所による大衆的なお花見の宴会、「花より団子」どころか花を肴に酒を飲み「酒なくてなんの己れが桜かな」と相なる。夏は川の流れを木陰でながめ、川辺の舟での遊び酒。秋は月見酒である。上杉謙信は春日山での陣中の宴を張り、即興で「霜は軍営に満ちて秋気清し 数行の過雁月三更 越山併せ得たり能州の景 遮莫(さもあらばあれ)家郷の遠征を憶ふは」(『九月十三夜』)と歌った。秋口は九月九日の「重陽の宴」(菊見の宴
)、一〇月五日の「残菊の宴」などもあった。野外酒は今日でも花見や芋煮会、月見会の形で残っているが、自然の美しさ、雄大さの中で酒を飲むことにより、少しでも自分が自然に溶け込み、一体となることに目的があるのは、今も昔も変わらない。(「日本酒の世界」 小泉武夫)
▽ビリー・カーター
何ともやりきれない大統領は委員会を任命する。アルコール症委員会の委員に指名された、当の医者が、毎日のようにベイリウムを処方している。それとこれとは別だと、彼らは言う。教育など、問題外だ。皆がアルコールを飲んでいるのに、アルコールは問題だと認めるわけにいくかね、冗談じゃない、と言う。若者が、一五グラムのマリファナを所持していると、ただちに監禁され、それがウイスキーのボトルだと笑いとばされる。親たる者は、麻薬を恐れるあまり、子供たちをアルコール中毒者にする一番の存在になっている。彼らは、アルコールが麻薬であることを知らないのだ。マリファナさえ用いなければ、アルコールはけっこうだと彼らは言う。私がロングビーチで治療を受けていたとき、マリファナ常用の重傷者が二人いたが、彼らは大酒飲みほど駄目になってはいなかった。(「アルコール依存症」 デニス・ホーリー) ビリー・カーターは、ジミー・カーターの弟です。
酒盛り唄
このように祝宴の座開きには必ず決った祝儀唄を歌うところは多い。東北地方の「御祝」「さんさ時雨」、関東地方の「はつうせ」「これさま」、北陸地方の「松坂」「まだら」「布施谷節」、四国地方の「よいやな節」、九州地方の「しよんが節」などが有名である。元来、祝儀唄には相手の繁栄を寿ぐとともに、目出度い文句の中に籠る言霊の力によって祝福を祈念するといった呪術もあった。座開きの唄がすむと次々と芸を廻して行く無礼講となる。今日ではカラオケの伴奏で日頃鍛えた喉を披露する人が多くなったが、昔はその地方独特の酒盛り唄があって歌った。美浦村の「さあい」、新利根村の「じんのめ」、石下町や谷田部町の「酒盛り唄」などがそれである。-
「酒盛り唄」
〽ハアー飲めよ騒げよ出た時ばかり
ソラソラ家へ帰れば籠の鳥
〽酔うた酔うたよ五勺の酒に
一合飲んだらどうしゃんしょう
〽唄を頼みます皆さんに頼む
うまい文句を二つ三つ
〽唄を頼まれ歌わぬ奴は
馬鹿か聾かものやすか
〽唄の先生に唄頼まれて
唄も出ませぬ汗が出る(谷田部町高良田)(「茨城県の民謡」 河野弘)
閑居 田能村竹田(たのむらちくでん)
偶(タマタ)マ秋色ヲ探ツテ疎林(ソリン)ヲ過グ
戸ニ入リテ唯(タダ)聞ク弦誦(ゲンシヨウ)ノ音
客ヲ愛シテ施(オモムロ)ニ花下ノ径(コミチ)ニ除(タヲ)リ
杯(ハイ)ヲ停(トド)メテ疾(イソ)ギ草(ソウ)ス酔中ノ吟
寒蘂(カンズヰ)ヲ携ヘ来ルコト朝露ト連(トモ)ニシ
芸窓(ウンサウ)ヲ植向(タテオ)イテ素琴(ソキン)ニ伴(トモナ)ハシム
瞥眼(ベツガン)ノ浮雲 安(イズク)ンゾ問フニ足ラン
高懐 此レニ対シテ遂ニ幽沈ス
たまたま秋の彩りを探ろうとして、まばらな林の中を過ぎて帰って来た。戸に入ってただひとり、琴を弾じ、唄(うた)を口ずさんでいた。たちまち客恋しくなり、思い返して立ち上がって秋の草花を手折り、杯を停めて即座に酔中の吟を草した。手折った秋草は朝露を伴ったまま、香草の匂う窓辺に活けて、琴の清掻(すががき)の相伴をさせる。眼をかすめて、俗世の浮き沈みが見えないわけではないが、関心の外にある。わが高い志は、それに対しては、黙して答えない。
ひとり生花、弾琴を楽しむ静かな侘(わ)び住宅(ずまい)を語りながら、客を愛して吟詠を楽しもうとする心を述べる。豊後竹田荘(ぶんごちくでんそう)の幽居の図である。ちなみに「芸(うん)」はヘンルーダという香草だが、ここでは香り高い草花というほどのことであろう。(田能村竹田全集(「古典詞華集」 山本健吉)
寒山詩
田家暑を避くるの月
斗酒誰と共にか歓ばん
雑々として山果を拝し
疎疎として酒罇(しゆそん)を囲む
蘆莦(ろせう アシとヨシ)将(も)つて席に代へ
蕉葉且(しばら)く盤(さら)に充(あ)つ
酔後頤(あご)を搘(ささ)へて坐すれば
須弥(しゆみ)も弾丸より小なり(「飲食雑記」 山田政平)
吉田集而の説
「国立民俗博物館教授の吉田集而という人が、面白い説を書いているんだ」と、小生。「ほーっ」と酔夢庵と呑嬉亭が吟醸グラスを手に持ちながら身を乗り出してくる。「ほら、お酒の歴史なんか見ていると、神様に供えておいたご飯にカビが生えて、それからお酒が出来たというようなこと書いてあるじゃん」酔「おーっ、おーっ、確かにそう書いてあるよな」「だけど吉田氏は、穀物に生えたカビからお酒へと短絡的に考えていいのか、って疑問を呈しているんだ。カビには、酒造りに適したものもあれば、単に腐敗をもたらすだけのカビだってあるわけだろ。古代人が、これは有用、これは毒だから駄目、なんて認識出来たかというわけさ。現代の、ある程度カビのことを知っている我々でさえ、もし、ご飯にカビが生えてたら捨てるよな。ましてや何も科学的知識のない古代人が、カビの生えたご飯やお粥などを口にするか、ということさ。そこで、吉田氏はインドとミャンマーの国境近くの地方で「稲芽酒」が造られていることに注目するわけさ」呑「稲芽酒?」「うん、稲の芽で酒を造るんだけど、稲芽自体にはほとんど澱粉を糖化する酵素はないから、酒にはならないんだ。そこで、稲に芽を出させるために湿らせることでカビが生えて、これが糖化のもとになるっていうんだな。稲籾や稲藁には麹菌が付いているからね。ほら、見たことないかな。田圃なんかで稲を見ると、黒い小指の先ほどの塊が付いているの…あれ、稲麹というんだけで、江戸時代はこれで酒造ったという話もあるくらいなんだ。」「そういや、昔、田圃でそんなの見たことあるな」と酔夢庵と呑嬉亭が子どもの頃の記憶を引き戻すようにうなずき合っている「稲に芽を出させるために、保温や保湿をする段階でカビも生え、そのカビが生えたときに上手くお酒が出来ることを知った彼らの先祖が、酒造の主役が稲芽ではなく『カビ』であることを経験的に知ったということさ」「カビによる発酵の酒造りの始まりっていうわけか。だけどさ、その彼らっていうのは、カビの生えたご飯やお粥から、酒造りを思い付いたんでないとすれば、どうやって…」皮をむいた焼きナスに醤油をかけながら酔夢庵が口を挟む。「西方から伝わった麦芽の酒、つまり原始的ビールからのアイデアじゃないかというんだ」(「ツウになるための日本酒毒本」 高瀬斉)
ルバイ第四十
さて鬱金香(うつこんかう)の、天(てん)の美禄(びろく)を朝酌まむと
地(つち)より振り仰ぐが如く、
心籠めて酌み給へ、空(うつろ)なる盃のごと、
天に依りて汝地(なんぢつち)に伏せらるるまで。
[略儀]チュウリップは、盃の形をして居るが、其の、朝開く様は、ネクタ(nectar 神の酒)を、天より受けようとするかの如くであるように、心を籠めて酒を飲むが好い。亡き人の盃は伏せて置く習(ならは)しであるが、丁度其のように、天が地にお前を伏せる迄、飲んだが好い。
[通解]意味は極めて明瞭。「死ぬまで飲むが好い。」と云うのである。チュウリップの盛り短きを、人の命に譬えて居る事は云う迄もない。此のルバイの結句"like
an empty Cup"(空(うつろ)なる盃のごと)は最終のルバイ第百一の結句"turn down empty Glass"(伏せて置けかし、空(うつ)ろなる盃を)の伏線である事に注意す可きであろう。(「留盃夜兎衍義」 長谷川朝暮)
せんせい[先生]
<名>①人を指導する立場にある人。学芸の優れた人。医師や議員などにもいう。 ②学校の教師。
処方箋書く先生も酒が好き 八木蛙生(「川柳表現辞典」 田口麦彦編著)
伊丹、池田筵菰包の印
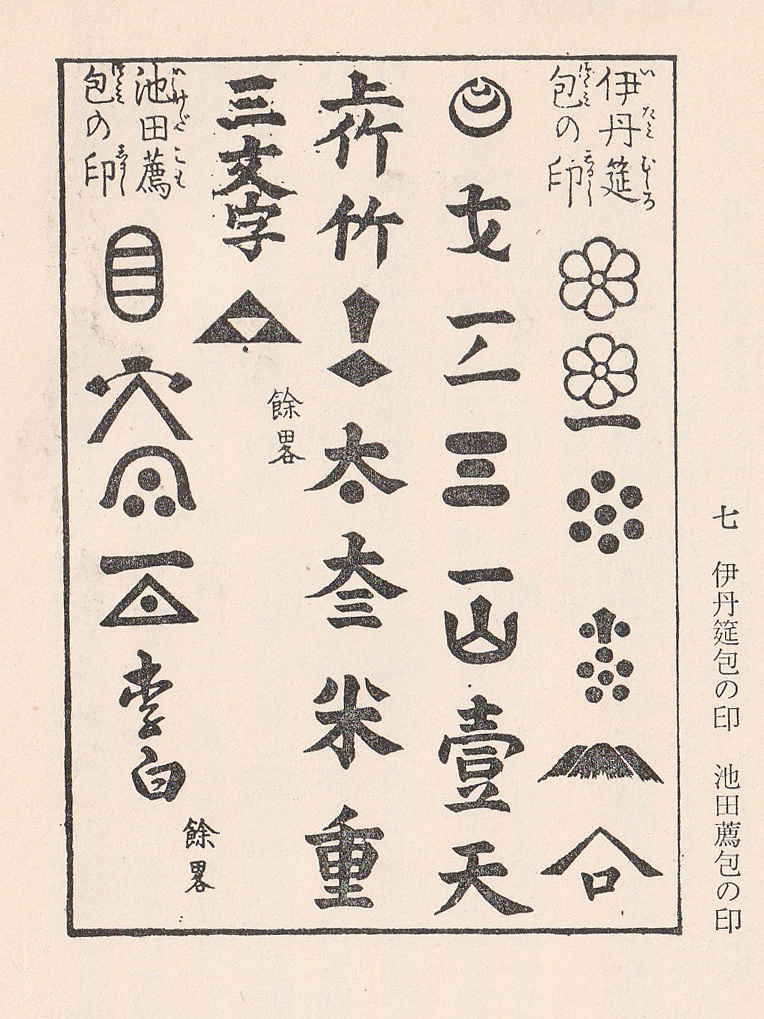
(「日本山海名産図会」 千葉徳爾註解説)
増)盃を伏せて置く
四季草云盃を伏せ置く事前にいふ如く甚いむ事也 今世ハ吸物の膳に盃をふせて置て出す事はやる武家にてハいむ事也(「増補俚言集覧」 村田了阿輯 井上頼囶、近藤瓶城増補)
はせがわ酒店
東京駅構内の一角に、「はせがわ酒店」という酒販店がある。限られたスペースながら、日本各地の日本酒から焼酎、ワイン、リキュール、はてはつまみや酒器まで、酒にまつわるあれやこれやが揃う店内は、のんべえにとってこの上ない至福の景色なのだ。そもそも『はせがわ酒店』は、長年にわたり旨し酒や新たな銘柄を発掘し続け、酒業界をリードしてきた先駆的酒販店のひとつ。酒ファンはその動向に熱い眼差しを注ぎ、全国の蔵元さんたちからも一目置かれてきた。駅ナカのこの店でも、たとえば日本酒なら新潟の「越乃寒梅」や宮城の「浦霞」といった王道から、和歌山の「紀土」ほか、ここ数年話題を集めている酒まで、その多彩なセレクトに頼れるのがなによりも嬉しい。「東京駅限定銘柄」もあり、お土産探しにもひと役買ってくれるのだ。心迷う場合は、店内にカウンターバーで一杯やりながら重ねて熟考する…そう、ここは買うだけではなく、呑めるんですよ!銘柄は季節により変わるが、最近では埼玉の麻原酒造の「東京駅ラベル 純米吟醸」にうっとりとなった。口当たりがやさしく、ふわっとミルキーな旨味が立つものだから、期せずしてお代わり。合わせた漬け物がまた絶妙な旨さで、その後は、改札まで走る運命が待っていたのだが。(「ニッポン「酒」の旅」 山内史子)
酒税増税
しかし、酒税の増税が計られ、これが実現した(明治二九年)のは、「財政の玉手箱」と呼ばれたように、酒税が徴収しやすい税であったからであろう。当時の国税のなかでは地租が大きなウェイトを占めていたが、帝国議会では地主が選挙権者であり、議員にも地主が多かったから、地租の引き上げは政治的に容易ではなかった。酒造家も地主、地方名望家が多かったが、この時代では酒造家の数は一万九〇〇〇人程度、地主全員を相手にするよりは遙かに楽であった。(「酒と経済」 宮本又郎)
安倍川の川越
川越しは一人ずつ肩車に乗せると、川へざぶ/\はいって行く。北八はふるえながら、「ア、南無阿弥陀(なんまいだ)、なんまいだ、目が廻わようだ」「しっかりわしが頭に取りつきなさろ。アゝコレ、そんなにわしが目を塞がっしゃるな、向こうが見えない」「イヤ成程、深いワ/\、コレ、落として下さるなヨ」「アミ落すもんかえ」ならんでわたる弥次路兵衛も、ひやひやしながら、「それでもひょっと、落ちたらどうする」「ハレ、落ちたところが、たかがお前が、流れてしまわっしゃるだけのことサ」「エゝ、流されてたまるものか」肝を冷す身には、この川幅が十町余もあるように思われたが、ようように向こう岸に着き、「ヤレ/\御苦労/\」と、肩車からおりて賃銭をやり、「ソレ、別に酒手が十六文ずつ」「ヘイ、コレハ御機嫌よう」と、川越しはすぐに川上の浅い方を渡って帰る。「アレ弥次さん、見ねえ、あんな浅い所を行きゃアがる。おいらたちをば深い所を渡して、六十四文ずつふンだくりゃがった」「なるほど、酒手までとはいい面の皮よ。こうもあろうか」川越の肩車にてわれ/\をふかいところへひきまわしたり(「東海道中膝栗毛」 十返舎一九 三好一光訳)
(八)なる川
酒(さけ)は酒屋(さけや)に茶(ちや)は茶屋(ちやや)に、ぢよろは木辻(きつじ)のなる川に、木辻(きつじ)のぢよろは、ぢよらうは木辻(きつじ)のなる川に(「若みどり」 塚本哲三編輯)
五百万石
「五百万石」は一九五七(昭和三十二)年、新潟県農業試験場(現・新潟県農業総合研究所作物研究センター)で「菊水」(母)と、「新200号」(父)の交配によって誕生した、新潟の代表的な酒造好適米である。品種名「五百万石」は、同年に新潟県の米生産量が五百万石を突破したことを記念して命名された。七三(同四十八)年に新潟県の奨励品種となった。五百万石は「麹をつくりやすく醪にしても溶けすぎることがない」「清酒にしたときに味がくどくならず、すっきりした軽い清酒に仕上がる」「辛口の清酒に仕上げてもマイルドな味わいになる」など、酒造好適米として優れた特質がある。昭和五十年代から平成にかけて起きたコシヒカリブームの際は、農家の五百万石栽培が低迷し、酒造業界に原料米確保の危機感が広がった。このため、新潟県酒造組合は経済連と提携し、県内各地で五百万石を栽培する団地化の推進や種もみの助成など、幅広い対策に取り組み、この危機を乗り切った。二〇〇四(平成十六)年現在、酒造好適米としての新潟県内での作付割合は九割を超え、第一位となっている。新潟県をトップに福井・富山・兵庫・石川各県が主要な栽培県で、山田錦と並んで酒造好適米の代表的な品種となっている。(「新潟県清酒達人検定 公式テキストブック」 新潟日報事業社)
世界一統
世界一統は、明治17年、紀州侯の籾倉を譲り受けて創業。今は㈱世界一統と社名を変えていますが、一万五千石の蔵です。世界一統の銘柄名は、明治40年に大隈重信が命名したもの。灘(西宮)へは、昭和41年に進出したようです。大関本社の前に蔵はあります。製品中では純米吟醸原酒・吟醸一(いち)と、超特撰・手造りなどが特色のあるもの。他に、花柄プリントの「フラワーカップ」などがあります。東京、大阪にも出回っていますが、やはり和歌山のほうが、手に入りやすいかも知れません。(「灘の酒」 中尾進彦)
ワインに似て非なる妙味-オーストラリアの男性グループ
カンガルーやウヅラの一種のクウェイルなどの肉を扱っているブースでは、ひと仕事終えた四人の男性が興味深げに試飲した。「この吟醸酒は、普通の日本酒とは違うね。はじめて飲んだけど、ワインに似ているようで違うところが面白いな。熟成酒というのは豊かな味で喉のところが温まるよ。スコッチウィスキーみたいだ」この、スコッチウィスキーに通じるといったのはガーナ人の評価以来で、ほかにも「ポルトワインのようだから食後にゆっくり飲りたい酒だ」という人もいた。(「知って得するお酒の話 日本酒の味は世界に通用するか」 山本祥一郎)
酒の肴(さかな)
長き夜は灯あかるく良き友と 酒はしづかにのむべかりけり 結城哀草果
すべて酒を嗜(たしな)む人々には、酒の肴のむずかしい人と、なんでも構わない人とがある。しかし酒は肴によって、うまくもまずくもなる。酒をひと口ふくむと、その芳香は口中にひろがり、とろりとした甘味は、舌の上を快くころがって、のどへ行く。甘味のある酒に、砂糖を使った料理は酒をまずくさせる。酒を美味しく飲むのには、どうしても味つけしたものがよろこばれるのは当然である。街の居酒屋では今でも枡(ます)のモッキリに浪の花(塩)をつまみ、枡のへりをぐっと、かみしめながら飲んでいる姿を、よく見かける。酒の肴は、なめる程度に食べるものほど、酒がうまくなるようだ。だから塩辛類や漬け物で飲む酒は、いちばんうまいわけである。酒飲みはわがままで、飲みたいとなったら子どもと同じようで、おかずを作るのも待ち切れないで、なんでもいいから一品だしておいて、酒を早く出さないと、怒り出す人が多い。そんなときには、いつでも手早く出せる保存のきくものを、一品だけでもおいておくと、とてもごきげんよく、たのしい食卓を囲むことができる。それがどこでも売っている加工食品であっても、ちょっと手を加えると、味がぐんと生きてきて、酒の肴にはすばらしくうまくなるものが数多くある。
結城哀草果(ゆうきあいそうか) 明治二六年~昭和四九年(一八九三~一九七四)。大正・昭和期の歌人。山形県生まれ。本名光三郎。斎藤茂吉のアララギに参加。歌集『山麓』を昭和四年に出版し、素朴で健康な生活歌を特色とし、この傾向から、農村生活の実態を歌う社会詠へと発展させた。その後、歌調の洗練に伴い、自然詠へと傾斜した。歌集は他に『すだま』『』群蜂『まほら』『おきなぐさ』がある。随筆集に『村里生活記』正続、『農村歳時記』がある。(「料理名言辞典」 平野雅章)
ちろり[銚釐]
銅または錫製の燗徳利。ぜいたくなのは銀で造る。○ソレ爰に燗ちろりが有りさいわい燗銅子もわいて居る云々(滝亭鯉丈・滑稽和合人初編上巻)。
①いみぶくをいふなとちろり二つ出し (樽八)
②お妾のすゝめで銀のちろり出来 (樽一三)(樽二五)
③こしらへ喧嘩ちろりが二つ見えず (樽二一)
④袂からちろりを出してくらはされ (樽二六)
⑤下女白衣で出して叱られる (樽二九)
⑥色男ちろりのような羽織を着 (拾八)
⑦居酒屋のちろり大きな迷子札 (逸)
⑧ぶたばぶてなどゝちろりを投り出し (同)
①喪中の男を誘惑。いみぶくは忌服。 ②銀のちろりを欲しがる贅沢。 ③喧嘩のあとをしらべたらちろりが二本なくなっていた。こしらへ喧嘩はこしらえ事の喧嘩。 ④御馳走の帰り道。 ⑤はかまをつけぬ銚子。白衣-そのままの姿。類句-居酒やのちろりは客へ白衣で出(逸)。 ⑥ちろりは小判のように叩き目のある打ち出し造りであるから、これをカベお召のような羽織地に連想した句。 ⑦紛失の恐れがあるので大きな木札をつけてある。 ⑧物騒な夫婦げんか。(「古川柳辞典」 十四世根岸川柳)
梅酒 うめしゅ 梅焼酎
焼酎二リットルに実梅・氷砂糖約六〇〇グラムの割合で、壺等の器に密閉してたくわえておく。古いほど味がよく珍重される。
たくはへて自づと古りし梅酒かな 松本たかし
梅酒に身を横たふる松の風 前田普羅
わが死後へわが飲む梅酒遺したし 石田波郷
とろとろと梅酒の琥珀澄み来る 石塚友二
酒屋・土倉
酒屋・土倉の金融的進出は、当時のあらゆる階級に浸潤し、下は農民より、上は公家・武家に、さらに中世の最高実権者たる幕府にも及んでいる。長享三年七月幕府仏事の要脚五万疋(五百貫)を必要とするに際し、幕府所持の現銭は僅に百七十貫に過ぎなかったため、不足額三百十余貫を下京酒屋土倉に借用せんとしたことは、これが一例である。(蔭涼軒日録長享二年六月六日条)酒屋は醸造業に於ける独占的利益に於て、また土倉兼業による高利によって、中世に於ける有徳者即ち資産階級の代表的存在となったのである。(「日本産業発達史の研究」 小野晃嗣)
頭に酒のくる句(4)
酒さびて 螽焼く野の草もみぢ 其角 五元拾遺(秋)
酒尽きて しんの坐につく月見かな 一茶 おらが春
酒つきて 臂のさぶさや後の月 長父 千鳥掛・故続五百(秋)
酒作る 蔵のつゞきや葡萄棚 史邦 故続五百(秋)
酒造る 隣りに菊の日和かな 白雄 句集(秋)(「近世俳句大索引」 安藤英方編)
玉子酒
元禄二年刊の『番匠童(わらわ)』旧十二月に、「玉子酒、俳」とあるのが初見で、その後享保元年刊の『通俗志』は三冬とする。後期の天明三年刊の『華実年浪草(かじつとしなみぐさ)』も三冬とし、「鶏卵酒(たまござけ)。本朝食鑑(元禄十年刊)ニ曰ク、鶏卵酒ハ精ヲ益シ気ヲ壮(さかん)ニシテ、脾胃ヲ調フ」とある。現代歳時記は虚子の『新歳時記』が十二月また三冬。山本の『季寄せ』は三冬で「玉子酒。酒を熱く煮、マッチの火でアルコール分を除き、玉子を入れてほぐし、砂糖で味を調える。下戸向きの寝酒や風邪気味の時に嗜まれる」とある。
親も子も酔へば寝る気よ卵酒 太祇
我背子(せこ)が来べき宵なり卵酒 紅葉
かりに着る女の羽織玉子酒 虚子(「酒の歳時記」 暉峻康隆編)
濁酒之事
濁酒(にごりざけ)のつくりかた
一、成程花付たる麹よく候。扨、大体より少し水を詰へし。
○なるべく花のついた麹がよい。そしてふつうより少し水を控える。
一、新酒口ならハ掛留ゟ(より)三日め程、寒造りならハ六日、七日め、春造りハ四日、五日程にて石磨にて醅共に引へし。如此未沸中に引者、最早勢抜て沸ぬ物也。依之、後迄につとりと盃ゟ落ぬ程濃く甘口也。
○立冬になって造る新酒口であれば掛留から三日目ぐらい、寒造りであれば掛留から六、七日目に、また春造りの酒は掛留から四、五日もたったら、石臼で醪ごとひく。このようにまだわからないうちに醪をひけば、もう勢いが抜けてしまってわかないものである。このため、のちには盃から落ちないほど濃い甘口の酒になる。
一、新酒口ならハ、添にて掛留へし。春造りも同然也。寒中二ツも掛へし。
○立冬になって造る新酒口であれば添で掛留にする。春造りの酒も同じである。寒中は二回掛ける。
一、大元ハ勢強く湧過候。何時も五升元ゟ壱斗元迄に成へし。如此造りてハ旨(うま)ミある物也。
○大量の酛は勢いが強くてわきすぎる。酛はいつも五升から一斗以内にすべきである。このように造れば、旨味のある酒になるものである。(「童蒙酒造記」 吉田元校注)
玉子たまご
世度卑(せとひ)なる出家あり。一人の弟子にいふ。「明日は吉野の花見に行かん。先途程遠し。暁より起きて出立を用意せよ」「心得たり」と夙(つと)に起き、酒飯をとゝのへ戸を叩きければ、坊主「未だ夜深(ぶか)なり」とて起きず。さるほどにつね/"\弟子にかくし、いねざまには焼味噌と号して、鶏の玉子をとゝのへ、肴に用ひて酒をのむ事を心に無心に思ひゐけるが、その時こらへかね「夜が深いかは知らぬ。焼味噌がてゝは、もはや三番鳴いた」(醒酔笑巻三・寛永五・無題)-
【語釈】○世度卑=世度扉の当字らしい。小庵。
【鑑賞】生臭坊主への皮肉。玉子を焼味噌といいつくろっていたが、見事しっぺ返しされた。(「江戸小咄辞典」 武藤禎夫編)
「米百俵」
【第二二八回 平成六年二月】 *『米百俵物語』出版お祝い *米百俵(新潟) *ゲスト 高瀬斉さん 栃倉酒造㈱社長 栃倉恒栄さん *会場 兆屋
酒友である高瀬斉さんは酒と料理のまんがでつとに有名である。それも手近な材料を手早く調理できる新しい料理や、ウィットに富んだメニューを作ったりしてわれわれを喜ばせてくれる。それが山本有三の戯曲で有名な「米百俵」をまんが作品に仕上げた。原作は明治維新で徳川幕府軍に組みし、官軍に手ひどくやられた長岡藩の生き残りが、寄せられた支援の米百俵を、のちのものの教育に使うといういい話である。それを「米百俵」という酒銘の栃倉酒造のために、酒の話としてまとめた。これもささやかだがお祝いパーティーの形で「米百俵」を飲んだ。(「「幻の日本酒」酔いどれノート」 篠田次郎)
いはない【岩内】
口留された下郎の擬人名。仲間、折助などによく可内(べくない)の通り名がある処から来たもので、然かも云はないに利かせたのである。
出合茶屋下に岩内飲んで居る 口留として一杯(「川柳大辞典」 大曲駒村編著)
狂い酒 富士正晴
青眼 白眼 阮籍(げんせき)の
年中飲んでた狂い酒
狂うたところが 正気なり
正気なりゃこそ 狂うなり
ごんごん ごんごん 飲む酒は
俗人避ける酒の幕
煙幕もどきでありました
血の匂(にお)いするあの頃(ころ)の
狂い酒こそ すさまじい
狂い酒ある 悲しさは
これぞ この世の歪(ゆが)みなり
この世は歪む いつの世も
狂い酒のむその人は
世々の鏡か 天才か
あるいは この世の救世主
崇拝こめて 眺めるが
狂い酒のむ 悲しさの
姿みるのは 辛いもの
狂は侠なり しゃれてるか
手前免許はどうだろか
狂は侠なり しゃれてるか
狂は侠なり しゃれてるか(「酒の詩集」 富士正晴編著) 一部です。
小鍋立
江戸の食事は身分制が守られており、銘々が箱膳で食べたので、大鍋を囲んで食べることもなく、鍋は一人用の小鍋(こなべ)仕立てが多かった。当初は土鍋が使われていたようだが、大田南畝(おおたなんぽ)は「安永の頃から、鋳物の浅い鍋が作られ、土鍋はすたれた」としている。小鍋立(こなべだて)は家庭だけでなく、遊里や外食の場でも供された。居酒屋で出される小鍋立は、醤油とカツオ節で味付けされていた。調味料で欠かせないのは、油、酢、味噌、塩、味醂(みりん)、砂糖などだが、その大半は江戸中期になっても上方からもたらされていた。体を使って働くことが多い江戸っ子は、上方の薄口醤油に物足りなさを感じていたが、江戸中期から後期にかけて下総(しもうさ)の銚子(ちようし)や野田(のだ)で醤油の生産が本格化し、小麦を多く使った香りの高い濃口醤油の量産に成功した。現在も大メーカーとして知られるヤマサ、ヒゲタ、キッコーマンなどの銘柄が生まれ、産地が東西で逆転した。江戸の味覚に欠かせない味醂も、下総の流山(ながれやま)が一大産地となった。江戸っ子の味覚に合った調味料が江戸近郊で開発され、料理の幅が広がっていき、あらゆるものが小鍋立で食べられるようになっていった。(「江戸の居酒屋」 伊藤善資編著)
山鯨二六
凡そ肉二七は葱(ねぎ)に宜(よろ)し。一客一鍋(いつくわ)。火盆(ヒバチ)を連ねて供具(きようぐ)す。大戸(ゼウゴ)は酒を以てし、小戸(ゲコ)は飯を以てす。火活して肉沸く。漸(やうや)く二八佳境に入る。正に是れ樊噲(はんくわい)二九肉を貪(むさぼ)りて、死も亦(また)辞せず、花和尚(くわをしやう)三〇酔へり。争論大いに起こる。
二六 猪鹿などの獣の肉を憚っていい換えた語。獣肉を食することは忌まれてきたが、幕末にはこれを供する店が増えた。 二七 「山鯨…三都ともに葱を加へ鍋煮也」(守貞謾稿)。 二八 だんだん美味しくなる。顧凱之が砂糖きびを尾から食べ始めて本へ至って言った言葉(晋書・顧凱之伝)。 二九 劉邦の家来。鴻門の会-の時、項羽の与えた肉を食い、酒を飲むかと問われて、「臣死すら且つ避けず。巵酒安(いづく)んぞ辞するに足らん」と言った(史記・項羽本紀) 三〇 水滸伝の登場する豪傑。酔って暴れて五台山を逐われた。(「江戸繁昌記」 寺門静軒 日野龍夫校注)
食物年表1800-1850
1804・幕府が醸造酒について冥加金を徴収する
1806・米価の低下により、造酒制限を解き、勝手造りを許可する
1814・堀切紋次郎が白味醂をつくる
1815・江戸千住、中屋六右衛門宅で酒合戦
1822・灘の酒の江戸への移送量が67万樽(23万石)となる
・酒造工程の短縮化などの工夫が盛んになる
1835・千石酒造建設見積書を奉行に提出し、大手工業化がはじまる
1840・山邑左衛門ママが宮水を発見(「日本史分類年表 食物年表」 桑田忠親監修)
灘の明治維新
江戸時代に莫大な出血によって獲得してきた酒造株に対し、当初維新政府はそれを踏襲してゆく目的で、まず酒造鑑札書替料として株高一〇〇石につき金二〇両を徴収する政策をとった。当時灘五郷で株高五〇万石余として一〇万両以上の巨額の出費であった。それでも酒造家がこの書替料に応じたのは、それによって江戸時代から保持してきた酒造鑑札を、あらためて新政府によって「永世の家督」として保証されることを期待してのことであった。ところが明治四年になってその期待は裏切られ、「永世の家督」であるべき旧酒造鑑札が没収された。そしてこの新鑑札に対し、新規免許料金二〇両、免許料として造石高に関係なく、酒造稼人一人につき毎年五円を納めれば、誰でも酒造業を始めることができるようになった。ここに江戸時代からの酒造特権は全く反古(ほご)同然となり、酒造鑑札はもはや有効性を失って、自由に営業できるようになった。これを機に、全国的に地方の地主たちが一斉に酒造業を営むようになり、ここに地主酒造家が「雨後の筍」のように現れてきた。江戸時代に寄生地主として成長し、その小作米の加工を目的として利殖の道を模索していた地主たちは、ここにおいて恰好の投資対象を見出して、酒造業に傾斜していった。明治五年には全国の酒屋が三万軒近くにまで急増し、地酒としてそれぞれの地方市場を販路として営業を始めた。地主酒造家の台頭は、つまり灘酒造業の受難期であり、勢い全国的な競争体制のなかに投げ出されることになった。灘酒造業における造石高も五〇万石から一五万石にまで激減し、上方からの江戸入津樽もかつての一〇〇万樽から五、六〇万樽にまで減少していった。酒を造ってもそれだけ赤字となり、やむなく酒蔵を取り壊して材木にして売ったといわれるのも、この時期のことである。灘の酒造家は、むしろ酒造経営を縮小して、海運業や金融業など、できれば新たな事業への投資対象を求めて模索の時代が続いていった。(「灘の歴史」 柚木学)
奥殿諸白-おくでんもろはく
奥殿とは酒造家の奥に位置する蔵建物をさし、「奥殿諸白」とはそこで造られた諸白をいう。左掲の挿話にしても、一休在世の時期に「諸白」の言葉はまだなかったはずで、次の上澄みの言い誤りか後世人の作り話であろう。▼一休和尚あるかたへ斎に御出ある次に川前の又六といへる酒屋へ立より一ツふたつ物語し給ふに又六馳走まうしかの奥殿諸白とり出ししたしひにしひければ◎『類聚名物考』(「日本の酒文化総合事典」 荻生待也編著)
秋田県仙北郡中川村ほか
69酒盛の時にとくに定まった食法がありますか
盃はどういう順に廻しますか。酌は誰がしますか。食物はどういう順序に出されますか。廻されるものを各自が随意に取りますか、それとも一定の人が分配しますか。料理は特定の食器に盛られますか。
○祝儀や仏事の席は親疎の関係による。村の若者の飲み方は結婚して名披露目をした席順、つまり若衆に結ばった順に着席することになっている。老親らの酒盛はたいてい年の順によるが尊者は上座にすえる。
○盃は三つ組などの時は上から順であるが、ふつうは順はない。お酌は女か子供らである。
○祝儀などには料理をお皿に取って上から順に配るが、若者などの飲み方は勝手である。
70酒盛の後でさらにアト祝イとかウチ祝イというようなことがありますか。それを何といいますか。残りものはどうしますか。
後祝いとは、御祝儀の後に、若い男女が入り交じってやるもの。大義(たいぎ)振舞などは、媒酌人・料理人その他活動した人たちを慰労する意味の振舞。
酒盛の時は二次会という。御祝儀の時は後見(あとみ)の祝儀という。
アトフキ-祝儀や酒盛のあとで手伝いの人だけに、アトフキといって慰労の意味で馳走する。
71酒盛に参加する人はどういう人ですか。酒盛の性質によって違いますか。男ばかり、女ばかりという場合がありますか。それはどんな場合ですか。参加すべき人がしなかったらどうしますか。
酒盛には気持のあった者ばかり男女一同でする時と、集会の時やる場合とある。
○祝儀・仏事とも男女に関係なく参加する。しかし、孫祝いには多くは女の方である。
○参加すべき人が来ない時はお膳をおくることもある。
72共同食事、酒盛の費用は誰が負担しますか。村、組ですか。各自の負担ですか。あるいは物を皆が持ち寄りますか。
若者の飲み方の費用はたいていその家の主人が出してやる習わしになっている。
88醸造業者でなく,濁酒が造られていましたか。それはどんな時に造られたでしょうか名称は何といいましたか。村祭りの時には今でも造りますか。どうしてつくりますか。芋酒、焼酎など造られましたか。これらの酒類は個人個人で造りましたか、村とか組とかが共同で造りましたか。女は関与しませんでしたか。
明治の頃までは税金を出してほとんど毎戸濁酒を醸(かも)したし、神社でも祭礼の酒を造ったものである。若者方の春の野ガケ、秋の八皿などの時は前もって共同して醸(かも)したものであるが、今では法のため醸されなくなった。寒中に造るのをムンヅクリといい、雪室の中に造るものを雪モロ酒という。粟・稗・米のコザキなどで造るのもある。
89一年のうち酒を飲む機会はどれくらいありますか。平均一戸当たりどれくらいの量を用いますか。どんな種類の酒ですか。毎日常用する人が何人くらいありますか。飲酒家と酒嫌いの比率はどれくらいですか。大酒家というのはどれくらい飲みますか。軽い程度の酒の肴には何を用いますか。
年に十五回ぐらい。普通の年では二、三斗。
昔濁酒のあった時は三度に三度飲んだし、その上、夜眠る前には寝酒といってたいていひと鍋(カンジリ)飲んだ。したがって量はたいへん多かったのである。この大戦前までは平均一戸年二斗ぐらいは飲んだようであるが、今は平均したら七、八升のものである。
○角館町では晩酌をやるものが相当あるが、農村ではごくまれになった。酒嫌いという者はほとんどまれで、飲めばたいてい飲めるが強いて欲しない程度の者が多いようである。
○大酒家は一人で一時に三升ぐらいは平気で飲んだものであるが、今では清酒であるから一升五合ぐらいは大酒の方だろうという。
○昔はただ大根漬一種ぐらいでも寝酒を飲んだものだが、今では漬物にしても二、三種、時には煮肴、果物などで飲む。簡単な酒席ではするめ一種かみかんぐらいで飲むこともある。(「日本の食文化」 成城大学民俗学研究所編)
近江商人
近江商人が酒、醤油、味噌の醸造を全国で展開したことはよく知られている。特に、日野商人には圧倒的に多く、しかも現在も健在であるものが多い。近江商人がなぜ酒蔵経営をしたかについて、従来言われていたのは、土地の酒蔵に金を貸して、抵当に酒蔵あるいは酒造株が差し入れられていたところ、回収不能となったので、抵当権を執行して、やむを得ず酒造をはじめたとか、商品代金として大量の米を手持ちするが、米相場が下落したときは酒を造ったなどというのである。例外としてそのようなケースが実在したかもしれないが、一般論としてはどうも信じ難いし、事例のほとんどが、積極的に、努力して酒造株を入手した上での開業である。もともとこの醸造業は不本意ながら開業するような性質のものではない。また、米相場を操縦するために造石(ぞうこく)数を随時増減するというような操業は考えられない。真の理由は、酒の需要が安定している上に、利益が大きい、しかも、当時脚光を浴びはじめた成長業種であったからにほかならない。また、当時酒造は、米の消費量が大きいのと、酒蔵に課される運上銀は藩の財源の一つであったから、各藩主は造石高を厳重に統制した。そこで、酒造株は簡単に増減されないのが一般であり、譲渡にも藩が規制を加えていたから、新規開業は難しかった。ところが、もし倒産する者が出れば、藩の収入源にもなることから堅実経営で聞こえた近江商人が、そのあとを経営するよう慫慂(しようよう)をうけたこともあった。その上、江戸は大消費地である。その酒の消費量は大変なもので、灘などからも仕向けられていたが、必ずしも全体の需要を満たせなかった。地場の需要をあてにしていた多くの酒蔵と異なり、近江商人は江戸の人口に依存して江戸出しをしたのである。酵母菌を扱う製造工程は専門技術者たる杜氏(とうじ)にまかされ、販売過程を商人が担当したのであるから、商人が経営する工場としては、もっとも手がけやすかったのも一因である。(「近江商人の系譜」 小倉榮一朗)
頭に酒のくる句(3)
酒臭き 黄昏ごろや菊の花 一茶 句集(秋)
酒くさき 鼓うちけりけふの月 其角 韻塞・五元拾遺(秋)
酒くさき 人の寝がほや松の露 暁台 句集(秋)
酒くまん あまりはかなみ枝の露 白雄 句集・台叢(秋)
酒啖(くら)ふ 蝦夷もくもらじけふの月 暁台 句集(秋)(「近世俳句大索引」 安藤英方編)
酒盆の行儀
酒盆の良さを知ったのは、大塚の名居酒屋「江戸一(えどいち)」だ。ここはカウンター席も机席も、盃と箸を置いた一人一盆が並んで客を待つ。客は盆内で盃を傾け、肴をつつき、空いた徳利や皿は盆外に置く。東京駅八重洲口の古い居酒屋「ふくべ」も同じように角盆が並ぶ。これはおのずと、自分の領域はここまでと、むやみに置き散らさない行儀を生み、静かに飲む空気も生んでいる。江戸一の亡くなった年配女将は、盆外に空き徳利が五、六本も並ぶと「あんた、もうお帰んなさい」と算盤(そろばん)を手にとり、そうなれば常連も、皿を片づけ、空き徳利を一列に揃(そろ)え、おしぼりで机を拭くと、本当にもうやることがなくなったと惜しみながら席を立つ。店は盆を下げ、新しい一盆を置く。帰った客は翌日また来る。(「家飲み大全」 太田和彦)
飲むときの挨拶
この原稿のはじめに書いたのは、アルコールを飲むときの挨拶(あいさつ)である。その国の名前を明かしておこう。まずスコールは、アイスランド、スウェーデン、デンマーク。スロンチェは、アイルランド。チアーズは、アメリカ。サルーテは、イタリアではよく使われている。イタリアの公式の席ではチンチンというのだが、ぼくはまったく逆だとおもっていた。だからいつもレストランでは、チンチンとごく親しい仲間にいっていたようにおもう。アラックは、インド。ニニュオは、ケニア。ヤン・センは、シンガポール。コンペは韓国。チャイ・ヨーは、タイ。干杯は、中国の北京(ペキン)。同じ干杯でも広東(カントン)では、ゴンプイと発音する。プローストは、ドイツ人の口から、しばしば発せられる。乾杯は、日本である。お祝いや公式の席でないと、あまり口にしたことがない。盃に酒を注がれるとそのまますぐに口にする。ビバヒバ、またはアコーレマルナ、もう一つカマウというのは、ハワイである。マブヘイはフィリピン。サウージはポルトガル。サウージはブラジルでも使われている。サンテとプロ・ストは、ベルギーである。ヨーは、もっとも短いがベトナムでよく使われている。このなかで一番、簡潔で好きな言葉だ。それにイタリアのようにチンチンも使われている。飲む前に発する言葉で、もっとも気落ちのいいのはメキシコのサルーだ。サルーといって、テーブルに叩(たた)き付けても割れないような底の厚いグラスでテキーラを呷(あお)る。どうして叩きつけるのか分からない。モンゴルのゲルでは飲む前に、ひっかかるような言葉、トルヤガーを発し飲んだものだ。フランスでは、サンテだった。うすい大きめのグラスを軽く当て、サンテというのは、やはり小粋(こいき)な気分にしてくれる。ぼくは、まだ、ロシアの国は知らない。ぜひ、ザ・ワーレ・スダローヴィエといって、ウォッカを口にしたい。(「世界ぐるっとほろ酔い紀行」 西川治) ロシア語は、あなたの健康のためにといった意味のようです。
川升
さて、駒形堂から後(あと)へ退(さが)って、「川升(かわます)」という料理屋が大層流行(はや)り、観音の市の折など、それは大した繁盛。客が立て込んで酔狂な客が、座敷に出てる獅噛火鉢(しがみひばち)を担(かつ)ぎ出して持っていったのさえも気が付かなかったという一ツ話が残っている位、その頃はよく有名なお茶屋などの猪口(ちよこ)とか銚子袴(ちようしばかま)などを袂(たもと)に忍ばせて行ったもの、これは一つの酒興で罪のないわるさであった。(「土地の記憶 浅草」 山田太一編 「名高かった店などの印象」 高村光雲)
街灯
酔っ払いが千鳥足で夜の街をやってくると男が街灯にしがみついて立っていた。「おい、おい、なにをしているんだよ」酔っ払いが声をかけると、街灯の男も酔っているらしい、ロレツの廻らぬ舌で答えた。「バ、バ、バスを待ってるんでぇい」すると訊ねた酔っ払いが偉そうに言った。「バカだなあ、お前。そんな高い台つきランプを持って、バスに乗せてもらえるわけがないじゃねえか」(「ジョーク「ロシア革命史」」 歴史探検隊)
酒を飲みに行く旅
島原に宮崎康平サンをお訪ねした時、当然の如く酒をすすめられた。「実は、僕、一滴も飲めないんです」「飲んだことないんですか」「あるんですが、うまいと思ったことがなくて、で、飲まないことにしたんです」「じゃ、これはうまいから飲みなさい」僕が素直に猪口をとったのは、宮崎サンは失明していらっしゃるから飲み干さなくても大丈夫だと思ったからである。「永サン、酒は杯やコップで飲むものじゃない、皿でも、丼のフタでもいい、要するに平らで大きいもので飲まなきゃ駄目です。酒呑童子や弁慶の飲む大杯、あれで飲まなきゃ意味がない。いいですか、それも冷やです。そして酒をわたってくる風を飲むように、酒と空気を吸い込むように飲みなさい」僕は大変なことになったと思いながら、それでも、狂言や歌舞伎で大杯をあおって、大きく息を吐き出す演技を思い浮かべていた。そして、宮崎サンの指示通りその場にあった大皿を猪口がわりに酒を受け、酒よりも空気を吸うようにして口にふくんだ。その時、生まれて初めて酒をうまいと思った。そして、生まれて初めて酔った。酒の名は「黎明」。(「一泊二食三千円」 永六輔)
原始の混沌か、未来の大破局
飲みはじめれば必ず、原始の混沌か、それとも、未来の大破局のなかへ踏みこんで、記憶も消えいりそうな暗黒の奈落の底で、自分が自分でなくなった確認をいちどしてみなければ気が済まないのである。これは、一方で、この世に無数の小さなシャボン玉のような果てなき鬱憤(うつぷん)があり、他方、同じ泥酔をするにしてもけたはずれに強いロシヤ人の五十分の一ぐらいの量で忽ち朦朧(もうろう)としてくる天性哀れな容量しかない魂と現存の躰とのアンバランス、謂わば荒涼たる砂漠の砂を小さな硝子(がらす)の砂時計のなかに無理やり全部おしこんで永劫の時間の秘密を測ってみようといったやけのやんぱちで向こう見ずな意志に支えられた途方もないバランスの不均衡にも由来するが、さらにまた、日常生活的には、エティケットをまもりながら御婦人相手のパーティでのむ秩序的、制約的、騎士道的習慣など白と朱に燻(いぶ)し銀のかかった泰西絵物語のなかの縁なき異国の風習としてこれまでつゆさら身にしみて知る必要などなかったことも大きな理由になっているのだろう。(「酒と戦後派」 埴谷雄高)
とろる[動]
酩酊する。フーテン・不良のことば。◇『週刊読売』(1968年9月20日号)「フーテン用語には『ラリる』『トロる』といったのがある。(略)『トロる』はアルコールで酩酊すること」◇『サンデー毎日』(1979年6月10日号)「トロる 酒類を飲んで酩酊状態になる」(「日本俗語大辞典」 米川明彦編)
上戸
上戸(しやうご)、友達(ともだち)の所(ところ)へ酒(さか)もりによばれ、盃(さかづき)か出(で)るを見(み)れハ、小(ちい)サナ小盃(こさかづき)故(ゆへ)、たちまち泣(なき)てむせび(二ウ)入る。ていしゆ肝(きも)をつふし、どうした事(こと)で泣給(なきたま)ふといへハ、〽客物(もの)を見(ミ)て、かなしミを思(おも)い出(だ)しました。わたしがおやじに死(し)なれました時(とき)、何(なに)も病(やまヒ)ハこざりませなんた。てうど今日(こんにち)の(三オ)ことく、外へふるまひによばれましたところに、こなた様(さま)のやうに小(ちい)サキ盃(さかづき)が出ましたを、ついさかつきぐるミ吞(のん)で、咽(のど)につまり、死なれましたゆへ、俄(にわか)に思(おも)ひ出(だ)し、かなしうござる(三ウ)(「新作狂話 笑顔(えがお)はじめ 上戸」 武藤禎夫・編)
境界守のゲシク・パトゥ(原注一)
ソノム・ラシ(原注二)がドゥグイーラン(原注三)に捕らえられてアイルランド・ドゥガン(原注四)につながれていた時に、一人の男をやって境界守のゲシク・パトゥに、「わしがこの危難からのがれる方法はあろうか?」とたずねさせると、ゲシク・パトゥは言った。
「ああ! 私にどんな方法がありましょうか?今の世は、
わが影におそれ
わが尾におののく時。
どんな暴力も役立たぬ時。
酒と肉とが役立つ時。
智も賢も役立たぬ時。
疑い抗(さから)うが役立つ時!
わたしに何を言うことがありましょう?わたしに方法はございません!」
と言って帰してしまった。
そう言って帰してしまうと、ソノム・ラシはそのいくつかの言葉を聞いて、一頭のよく肥えた羊を買って殺して、また何斤かの酒を買って、見張りをしていた男たちに、たっぷりと酒をのませて酔わせ、肉を食わせた。そうして、そいつらは酒を飲んで酔っぱらい、肉を食らってねむくなり、みんな眠ってしまった。ソノム・ラシはローチン(原注五)をつれて夜中に逃げて行ってしまった(№47)
原著者注 一 ゲシク・パトゥ ウシン旗の役人で、有名な文士歌人。ジャルクチはここでは、漢人が耕作しているモンゴル人の土地に関する問題を処理する役人。 二 ソノム・ラシ オトク旗の役人で、一九二一年、革命派によって殺された。彼は台吉(タイジ*)であった。 三 ドゥグイーラン 革命的結社- 四 アルライン・ドゥガン オクト旗のラマ廟の名。 五 ローチン ソノム・ラシの弟。
[解説]この逸話および歌は、実在の人物が伝承のなかに織りこまれてゆく過程を考える上で興味深い例である。(「オルドス口碑集」 A・モスタールト 磯野富士子訳)
水とぶどう酒
料理は私たちが決め、ぶどう酒はギーセンさんに選んでもらった。私はついでに、びん詰めの水も注文しておいた。料理はピータン、くらげのあえもののオードブルに始まり、杏仁豆腐のデザートに終わったのだが、その杏仁豆腐が運ばれてきた時のことだ。私はぶどう酒も空になったので、注文してテーブルにおかれたままになっていたびん詰めの水を、自分のグラスに差そうとして、儀礼上、彼にもすすめてみた。すると、彼はにこやかに笑って、「いや、結構です。私は水を全く飲みません。」「え?」「私は、水というものを呑んだことがないんですよ。少なくとも、これまでに水を飲んだという記憶はない。それだけはたしかですね。」これには少々驚いた。「喉がかわいた時はどうするんですか。」「牛乳、果物、それに、ぶどう酒がありますよ。」四〇数年間、一滴の水も口にしたことがないというのも、ずいぶん変わった人だが、「特に水を飲む必要もないから。」と彼にいわれてみれば、それはそうにちがいない。(「食生活と文明」 NHK取材班)フランスでの話です。
少彦名命や三輪明神
いずれにせよ、以上の事実から、この口嚼酒が古代日本において行われていたこと、多分黒潮にのった南太平洋系の航海民(または漁業者)によって伝えられたこと、そして、おそくとも奈良朝初期には日常生活から脱落して終ったろうことなどは、想像に難くない。しかし、その原料がアワ・キビ・トーモロコシ、何でもかまわず、必ずしも米に固定していない点、今日の清酒の祖先とは考えにくい。もう一つ、『古事記』仲哀紀に、神功皇后の歌として、 此の御酒(みき)は吾が御酒ならず、酒(くし)の首長常世国(かみとこよ)に坐す石(いわ)立たす少名御神の神寿(ほ)ぎ… というのが載っている。その他「大和なる大物主の神の御酒(みき)」「味酒(うまさけ)三輪の殿の」など、三輪明神と酒をむすぶ歌は、記・紀、万葉に数々見え、少しおくれると美酒(うまざけ)は三輪の枕言葉にもなっている。このように、酒が少彦名命や三輪明神とむすびついていることは、同時に出雲族、乃至は朝鮮半島と縁の深いことを示す。何も、口嚼酒の人々の中に須須許理が顔を出したとするよりも、すでに行われている半島風酒造りの改良法を持ちこんだもの、と見ても一向に差支えはないだろう。(「日本酒の源流」 篠田統)
柳風呂
しかし京都でも一条堀川のあたりにあった柳風呂というところは、ちょっとした名物であったようだ。「洛中洛外図屏風」にも、この大きな風呂屋で、大あぐらをかいて湯女に背中を流させて気持ちよさそうにしている男の姿が見える。『鹿苑日録(ろくおんにちろく)』という、相国寺の日記のなかにも、この柳風呂のことは出てくる。 慶長九年六月晦日、午後柳風呂ニ赴キ、各々同途ス。浴室ニ於テ粽(ちまき)ニテ酒有リ、酒了テ帰院。 慶長十年十月十七日豊光ニ於テ斎(とき)有り。今度ノ骨折衆ノ振舞也。斎了テ柳風呂ニ赴キ、各会ノ衆残ラズ、浴後風呂ニ於テ酒有リ、酒了テ帰院。 このように、風呂屋で酒茶の接待をすることについては『色道大鑑』にも出てくるが、こうなると湯女(ゆな)という特殊な職業が、たんなる「垢掻き女」として終るわけがなかったのは当然である。(「京都故事物語」 奈良本辰也編)
酒肆内田屋紋処(もんどころ)のこと
『東山素柳坂物語』に云う、ある老人曰く、いつの頃にやありけん、内田屋清右衛門先祖は上方者(かみがたもの)にて江戸へ下り、神田辺に商売なしで夫婦暮しけるところ、清右衛門急死にて死にしゆえ、近辺の者寄り合うて火葬にせんとて浅草焼場へ遣わしける。しかるところ清右衛門、桶の内にて蘇生なせしかど、火屋の習いにて蘇生(よみがえ)りたりとも打ち殺すと聞きしゆえ、透(すき)を見合せ遁れ出でければ、おんぼう*の者追い掛け、内田屋は浅草駒形堂まで遁げ来れども、追いつめられしかば、詮方(せんかた)なく川へ走り入りて隠れしかば、追い来りし者ども終(つい)に見失いしゆえ帰りける。清右衛門はからき命を助かり、川より上がらんとせしところ、足にからまるものあり、引き上げて見れば財布にて、金三十両あり、これは不思議なり、これすなわち観世音のご利益なりとおし頂き、ようようわが家に来りしところ、家内近辺の者ども、やれ幽霊が来りしとみなみな驚きける。清右衛門はだんだんの始末、かつ河にて拾いし金を語りて誠に珍しきことどもなり。それよりこの金を元手となして酒屋を始めしところ、おいおい繁盛なせしゆえ、子孫にこのことを伝えんため、家の紋、早桶の蓋(図○に二)図の如く、さん外へ出でありしが、いつか角を取って丸に二つ引両(ひきりよう)とはなししとかや。政運が云う、今は早桶の蓋に算なし、この時分には算ありしことにや。
おんぼう 隠亡。墓守り、また火葬の際、死体焼亡を職とす。(「俗事百工起源」 宮川政運 神郡周校注)
冷や奴 ひややっこ
豆腐を四角に切り、冷水や氷で冷やして、七味唐辛子または紫蘇・生姜などを加えて食べる。
一日を 無口で酒と 冷や奴 上田千路(「川柳歳時記」 奥田白虎編)
禁酒宣言
先般、私は知友の間に、左の如き禁酒宣言の手紙を発送した。 小生、この度感ずるところあって、酒を止めることにしました。断然止めたいと思います。飲み屋の需めに応じて、「酒は私の一の友二の友三の友である」と、色紙に書き殴ったのは、つい数日前のことですが、毎夜々々飲んだくれて、家に帰るのは二時三時、おひる過ぎにならなくては頭の上がらぬ宿酔の胸苦しさは、遂に、「酒は私の一の仇二の仇三の仇である」と、思わせるに至りました。あれほど愛好した酒を止めるのは、自分でも生き甲斐を失うように淋しいし、諸君もまた、今日以後小生の酔態に接することの出来ないのを淋しいと思われるでしょうが、小生の苦しい胸の中を察して、何卒小生の我が儘を許していただきたいと思います。酒が、小生を滅しそうなのです。酒が、小生の健康、小生の生活、小生の人間全体を駄目にしそうなのです。最近の小生の小説と言えば、酒のことばかりだから、友人や読者はそれを心配して、「余り酒を飲まずに文学に精進して下さい」、「お体を大切にして、余りお酒を召上がりませんように」などと、繁く言ってくる始末です。小生が自滅しないように、皆が憂えてくれるのです。小生も、自戒したいと思うのです。(「新版禁酒宣言」 上林暁 坪内祐三編)
鄭玄
この人(鄭玄(じょうげん))が大儒とされるのには、前後漢四百年の「経学(けいがく)」を集大成して、儒家の経典のほとんどすべてに註釈を書いたからである。ことに「三礼(らい)」、すなわち「周礼」「儀礼」「礼記」の三古典については、遙遙二千年、今日ただいまいまに至るまで、この人の註釈が唯一の権威であり、ある西洋人が
mal du siècle と評した今世紀の擬古派の学者たちも、古代の礼制の研究に関する限りは、しぶしぶながらも、無視しない。もしこの文章についての恩人、石川氏のために、余談を一ついうならば、酒豪でもあった。身長八尺、飲酒一斛(こく)、愁眉明目、容儀温偉、大将軍袁紹(えんじよう)の招待に応じたときには、なみいる文化人たち、なんの百姓出身の野暮な田舎儒者と、つぎつぎに議論をふっかけたのを、みな見事にいなしたと、「後漢書」の鄭玄伝にいうのを、「殷芸(いんうん)小説」なるものには、更に拡充して、招待を辞しての帰るさ、袁紹の門客三百人、町の東郊の別宴で、かわるがわる杯をさし、酔いつぶそうとはかったのを、旦(あした)より暮れに及ぶまで、みごとにうけて三百余杯、而かも温克の容(すがた)、怠るなし、と記す。杜甫がみずからの身世にひきあてて、 江上徒(イタズ)ラニ逢ウ袁紹ノ杯、というのも、それを典拠とする。学問の豪傑は、酒の豪傑でもあったわけだが、といって鄭玄の著述は、その全部が今に伝わるわけではない。(「帰林鳥語」 吉川幸次郎)
庄七の忍術 [幡多郡]
とんとむかし 今から百五十年ぐらい前のことよ。幡多中村岩田の山王さまの近くに庄七という若い衆がすんでおった。ある日、庄七が後(うしろ)川へ鯉をつきにいくと、川向こうに白い装束(しようぞく)の行者(ぎようじや)がおって、この川を渡してくれというそうな。漁師は川で人を渡してやると漁がないけにいやがる。庄七が返事もせんとおると、行者は「そこに舟をおいてあるではないか、渡してくれ」と、せがむけんど庄七がうんといわんき「ほんなら、渡してくれんちかまんけん、その舟のひき綱をといてくれんか」「といたら流れるぞ」「いやいや、心配せんち流れはせん。といてくれたら、そっちへ渡って忍びの術を教えちゃろ」「なに、忍びの術…そりゃ面白い。ほんならといちゃろ」庄七は面白半分、舟のひき綱をといたそうな。ほいたら行者がなにやらぶつぶつ言いながら、パンパンと手を打つと、あーら不思議…舟は綱でひかれるように行者のもとへ行ったと。やがて行者は、舟にのって庄七のところへくると、「それでは術を教えてやるが、絶対に悪いことはせられんぞ」こうして庄七は、行者から忍術を教わったそうな。それから何年かたって-。あるとき庄七は、足摺さんへお詣りに行っての帰り、下の店屋(てんや)で弁当をつかって休んでおった。ふと見ると、そこに陶器の一升どっくりが置いてある。そこで庄七は店屋の婆さんに「この一升どっくりに入ってみようかのう」というと、婆さんは「入れるもんか」「いんにゃ、入れる」と言い争っていると、店の客、近所の人も集まって黒山のようになっておったが、そこへ一荷あきんどが清水の方から、ブリを二本にのうて通りかかり、この騒ぎを見て「人間がどうしてとっくりに入れるか」とせせら笑うので、庄七が「ほんなら入ったら、そのブリを呉れるか」「よし、やる…」と言うことになったそうな。庄七は、印を結んで九字を切り、えいと叫ぶととっくりに頭の方から入りはじめた。人々があれよあれよという間に、頭、胴、足とスッポリ入ってしもうた。そうしていつまでたっても出てこんので、みんなは狐につままれたような顔をして騒いでおったと。そこへ中村の方から飛脚がとおりかかってわけを聞くと「そんならおまん、さっき伊豆田の坂を、ブリ二本ひっかついで、行きよったぜよ」という。みんなは夢からさめたような気になって、とっくりをのぞくと中にハシが二本、入っておったそうな。こんな事を、ときどきやるので、庄七の忍術は幡多郡中に知れ渡った。あるとき庄七が一条さまのお祭りにやってきて、中村の酒屋の前を通りよると、蔵男たちが「おい、庄七がきよるぞ。なんぞやらかしてみんか」ということになり、庄七をつかまえ、術をみせえとねだったそうな。すると「おまえらぁが、何もせんとじっと見よったら見せちゃろ」「よし、何もせん」というので、そんならと庄七が手まねきすると家の奥の方から大きな雄牛がつのを振りまわして、蔵男たちの方へやってくる。みんな大あわてで逃げまわるが、牛は逃げる方へやってくる。もう恐ろしくてたまらんようになり、とうとう叩き殺せという事になって、皆なが棒をもって力一杯、叩きかかってゆくが、牛は一向に平気じゃけん、蔵男たちは泣き声をはりあげて、「庄七さーん、早う牛を止めてくれーッ」と頼んでやっと術をといてもらった。ところが大事(おおごと)、酒米のむし釜を叩きわっておったと。酒蔵の旦那が、庄七の家へねじこんできた。「あしたから、酒米がむせんき酒ができん。いったい、どうしてくれりゃ…」これには庄七の親父もめりこんで(弱って)、人に迷惑をかけるようでは家においておくわけにはいかん、出ていけ-という事になり、親子で別れの盃をかわしたそうな。やがて庄七が「ほんなら、今からいくぜ。おとやんも達者でのう」と言いながら、パンパンと手を叩くと、みるみる庭まで海の水が打ちよせてきた。そうして大きな舟が縁先へギイと横づけになったので、庄七はこれに飛びのると、沖へこぎ出していったと。するとおとやんは急に息子と別れるのが悲しうになってきて、泣き声をはりあげて「庄七よーい、もう許すけん、もんて来いよーッ」と叫んだ。庄七も出ていくのはイヤじゃったけん、じきに引っ返してきた。そこで術をといたけん、今まで海のように波うっておった水はスーッと引いて、元の庭先きになったと。このとき庄七の「おとやん、わしゃここにおるぜよ」の声に、おとやんがうしろを振りむくと、なんと庄七は長持の上に坐って、ニンニンしよったそうな。むかしまっこう、さるまっこう。 話 故小松茂久(「土佐の民話」 市原麟一郎編)
青山椒 あをさんせう
葉が青く、実も十分熟さないもの。煮て食い、焼肴にあしらいなどする。
青山椒 雨には少し 酒ほしき 星野麦丘人(「俳句歳時記 夏の部」 角川書店編)
伊丹酒
池田の南、西摂津平野の中央に位置する伊丹は幕府年貢米の蔵所であった関係で、原料面、輸送面で酒造に有利な環境にあった。寛文元年(一六六一)五摂家の一つである近衛家の領地に替わってから、幕府の度重なる酒の減産令にもかかわらず、近衛家の計らいで他所より有利な生産高を確保できた。『日本山海名産図絵』(一七九九)では秋の彼岸前後に仕込まれる新酒が伊丹の名物と紹介されているが、十七世紀後半ころから伊丹では大きな仕込桶を使って寒の前後九〇日間に集中的に量産する態勢に変わっている。こうして正徳年間(一七一一~一五)伊丹酒の生産量は池田酒を抜き、元文五年(一七四〇)伊丹阪上氏の《剣菱》が将軍吉宗の御膳酒に選ばれた。その後、安永三年(一七七四)池田酒の旧勢力満願寺屋と新勢力大和屋との争いのもととなっていた御朱印状が幕府に没収され、以後池田酒は衰退していった。江戸向けの伊丹の酒は、まず神崎(現在の尼崎市)または広芝まで馬で駄送し、つぎに天道船で伝法(現在の大阪市此花区)の船問屋まで運ばれ、一〇人乗り以上の大型船(伝法(でんぽう)船、のちに樽廻船といわれた。図2)に積み込まれて江戸に運ばれた。(「江戸の酒」 菅間誠之助)
寒造り集中政策
三段掛けの仕込技術については後述するが、ただここで見落としてならないことは、諸白酒のうちでも寒造りのものが商品性も高く、銘酒として珍重されていたこと、そして市場においては自家醸造的な「ぼだい」を駆逐し、ここに特産地成立の技術的条件が胚胎していったことだ。幕府も、このような近世酒造業の動向にそって寛文十年(一六七〇)には、秋彼岸以前の酒造を厳禁し、酒の寒造り集中化政策を明示した。この禁令が寛文期から享保期前後にかけてしばしば布達されたが、これは近世酒造業の技術的特質としての諸白酒の寒造り集中が幕府をはじめ封建領主の体制維持の原則の上からも要請されたからであろう。(「灘の酒」 長倉保)
みぎ【右】
②餅の異称。酒を左と云ふに対したのである。
能因は右の手 李白左なり 雨乞の歌で餅(「川柳大辞典」 大曲駒村編著)
美少年酒造にて
同じような現象は、清酒と焼酎の違いこそあれ、熊本の美少年酒造でも体験することができた。何万リットルもある貯蔵タンクの上に乗り、巨大なプロペラで攪拌する前の酒とよく攪拌したあとの酒を飲み比べてみたのだが、量が巨大なぶん、増幅効果が効いてくるのか、一升瓶の比ではなかった。「蔵の酒を飲んでしまうと、家で飲む一升瓶にはなかなか手を出しにくい」という職人さんたちの声も納得できる。ついでに、圧搾機(あつさくき)にかけられる前の清酒のモロミ(ドブロク)や、圧搾機から流れ出る清酒をご馳走になったが、これまた甘露(かんろ)甘露でこの世は天国。動いている酒はたしかにうまい。甘露甘露ばかりでは仕事にならないので、美少年酒造の研究室で振り酒の実験会。超音波洗浄機も、ちゃんと東京から持ってきてある。今回はお二人の「きき酒」のベテランに登場願った。きき酒のことを、専門用語で「官能テスト」というが、お二人とも熊本国税局鑑定官室のOBである。「いろいろな酒類を試してみたのですが、手で振ったかぎりでは、多少の差はあるものの、顕著な差であるとまでは言いにくい。しかしながら明確に差があると言えます」お二人の共通し体験であった。「しかし、このままにしておくと元に戻ってしまうんでしょう。安定してくれればありがたいんですがね。やはり酒の熟度には時間をかけるしかないんでしょうか」美少年の佐々木(ささき)常務の「安定」という言葉に、思わずはっとさせられた。佐々木さんが言いたかったのは、超音波をかけると、たしかに酒の中の成分は分子レベルで均一に分散し、自然熟成に近い状態になると考えられるが、その状態は残念ながら数分間しか保たれない。願わくは、分子の均一分散した状態が無限に続いてほしいものだ。(「うまい酒は、なぜうまい」 浅倉俊博)
薏酒
一〇八九 帝都には薏(よく)酒というものがあり、薏苡(よくい)(はとむぎ)の実で醸造する。淡泊な味で、こくがあるが、酒飲みの口を快くするには至らない。易州(今の河北省易県)の酒はこれより勝っていて、はなはだしく淡白である。荊軻(けいか)(1)や高漸離(こうぜんり)(2)たちが楽しんだのが、果たしてこれかどうかわわからない。襄陵(今の山西省臨汾市)の酒ははなはだ強烈であり、潞州(今の山西省長治市)の酒は一風変わった苦味がある。南和の刁(ちよう)氏・済上の露・東都の桑落は、濃淡に差異があるが、次第に甘口になっているようだ。だから大衆の口には合うけれども、評判は振るわない。
(1)荊軻 戦国、斉の人。燕の高漸離と親しく交わり、高漸離が筑(ちく)(楽器の一種)をうつと、荊軻が歌って楽しんだ。燕の太子丹のために秦王(始皇)を刺そうとしたが、却て殺された。『史記』巻八六「刺客列伝」。
(2)高漸離 戦国、燕の人。筑をうつのが上手であった。荊軻の死後、鉛を筑の中に入れておいて、始皇に近づき、筑で始皇を打とうとしたが、あたらずして誅された。『史記』巻八六「刺客列伝」。(「五雑組」 謝肇淛 岩城秀夫訳注)
| カリウム | ○ | 酵母や麹菌の増殖、発酵にとって不可欠。 |
| マグネシウム | ○ | 酵母や麹菌の増殖、発酵にとって不可欠。 |
| リン酸 | ○ | 酵母の増殖、発酵促進作用に役立つ。 |
| カルシウム | ○ | 微生物の生育には特に必要ではないが酵素の生産、抽出を促進する。割水にはある程度の硬度があったほうが味くずれを防ぐといわれる。 |
| クロール | ○ | 麹からの酵素の抽出を助け、酵素作用を促進する。 |
| 硝酸・亜硝酸 | ○ | 生酛系酵母においては、硝酸還元菌が生育し重要な役割を果たす。 |
| 鉄 | × | 異常着色を起こす上に香味を悪くするので、醸造用水に鉄は禁物である。 |
| マンガン | × | 日光による着色を促す因子となる。 |
| 銅 | × | 混濁の原因となる。 |
(「日本酒のテキスト」 松崎晴雄)
周恩来
中国の政治家で酒豪として知られるのが周恩来だ。同じく中国の革命第一世代の毛沢東が酒をそれほど好まなかったのとは対照的だ。といっても、毛沢東もリチャード・ニクソン米大統領を白酒でもてなしたというから全くの下戸ではなく、周恩来が強すぎたのだ。ちなみに、白酒はコーリャンでつくる蒸留酒で、アルコール度数が四〇度~六〇度と強烈だ。中国では国酒の地位を占めている。周恩来の酒はまさしく「海量」だったが、決して飲まれることはなかった。外交手腕を評価する声は生前から高く、一九七〇年代初頭には国連に復帰するなど、西側諸国との関係改善に努めた。外交の場での振る舞いも一流だった。-
とはいえ、周恩来もかつては失態を犯したことがある。一九五八年一一月武漢で毛沢東を筆頭に、劉少奇など最高幹部や全国党地方委員会書記らが出席した祝宴が開かれた。その席で、毛沢東が「周恩来は酒が強い。周総理に乾杯しようじゃないか」と呼びかけ、毛沢東の主治医が乾杯の音頭をとった。乾杯、乾杯の嵐で周恩来も「みんなで祝わなくっちゃ」とノリノリで「乾杯、乾杯」と所かまわず乾杯しまくった。顔色一つ変えず、浴びるように飲み続けたが、さすがにその晩、泥酔したらしく、真夜中に、鼻血が止まらなくなる。一国の首相が泥酔して鼻血とは少しばかり格好が悪い。周が悪いのだが、とばっちりを受けたのが乾杯の音頭をとった主治医。公安相から「医師たる者、他人に酒を勧めるよりもっとましなことを心得るべきだ」と叱られたというが、周にいってくれという話だろう。(「政治家の酒癖」 栗下直也)
福田氏
福田(恆存)氏と鉢の木で付き合ひ出して最初に解つたのは、氏が殆ど酒を飲まないといふことだつた。これは、それまでの経験から得た一つの結論にとつては非常な打撃であつて、原稿を書く仕事の疲れは並大抵の方法では取れず、それでさういふ仕事をする人間はそれだけ酒に対しても強いのだから、酒を飲まない文士などといふのは三流なのだと決めてゐた(併し勿論、酒を飲む五流の文士だつてゐる訳である)。所が福田氏は余り飲まなくて、その仕事に就ては文句の付けやうがなかつた。それで残された方法としては、実際を理論に近づける他なくて、毎月会つて飲んでゐるうちには、少しは福田氏も飲み出すだらうと思つてゐると、確かにそれ程飲めないのではないといふことは解つた。併しまだそれ位でこちらが満足してゐるといふ訳ではない。一つだけ期待出来るのは、福田氏の酒量が僅かづつながら増して来るのに対して、我々のが年とともに減つて行くから、いつかは両方が一致するだらうといふことである。福田氏に酒を強ひられたら随喜の涙が出るだらうと思ふ。(「福田恆存」 吉田健一)
アナクレオンとアルカイオス
アルカイオスにも劣らぬ豪飲の士だったろうと思われるアナクレオンであったが、水で割らぬ生酒を喰らって酩酊乱酔し、放歌高吟して酒池肉林を楽しんだ蕃異スキタイ人流の酒宴はお気に召さなかったらしい。「酒はしづかに飲むべかりけり」ということで、この詩人が良しとしたのはこんな酒境であった。
わしの嫌うのはな、なみなみとこう
酒を満たした酒壺を据え
美酒を汲みながら、
争いだの涙しげき戦いだのを
口の端に上せるやから。
好ましいのは詩女神(ムーサ)らと愛の女神より授かった
うるわしい賜物をとくとないまぜ、
陽気な浮かれごとに心遣る人。
つまりアナクレオンは、酒を汲みつつ陽気に恋(アフロディテ)と詩女神に戯れるおのれの姿を良しとしているのであって、アルカイオスの酒境のごときはこれを厭(いと)い、認めようとしないのである。同じギリシアの詩人として酒の詩によって詩名高かったとはいえ、仮に同時代に生を享けていたとしても、これではアルカイオスとアナクレオンは酒席を共にすることはできなかったろう。(「讚酒詩話」 沓掛良彦)
落第事
あられ酒のむ盃の数つもり 更に座敷にたまられもせず
此歌も又畢竟酒に酔て座にたまられぬといひはてたる歌なり、題の意趣いさゝ4かもみえず、あられ酒とつゞげたればとて、霰にはなりがたかるべし歌つらねん人は、かかる事よく/\思惟あるべき歟(「後撰夷曲集夷歌式目録」 新群書類従)
伊丹諸白
南都諸白は、いわば室町末期から近世初頭にかけての銘酒であったが、江戸時代になると、伊丹諸白が台頭してきた。伊丹諸白はとくに江戸積酒造業として発展し、江戸市場での好評を博していった。元文五年(一七四〇)に伊丹酒が将軍家の「御膳酒」となる頃には、"丹醸"ともてはやされ、銘酒のゆるぎない座を占めていた。元禄期はその繁栄のピークに到達していた。なかでも山本氏(木綿屋)の「老松」、筒井氏(小西)の「富士白雪」、八尾氏(紙屋)の「菊名酒」は有名であった。この伊丹の酒造地を実地に訪れて、寛政一一年(一七九九)に大坂の木村孔恭が著した『日本山海名産図絵』によると、当時醸造する酒を、新酒・間酒・寒前酒・寒酒にわけ、さらにそれに春酒を加えて、寒酒がとくによい酒であるとのべていることについては、既述のとおりである。そして昔は新酒の前に菩提という醸法があってこれを新酒とよんでいたが、この残暑の候につくられる速醸酒は、いまでは山家に受けつがれ、大阪などではたまたま嗜む者は、その家で自醸していると書いている。(「酒造りの歴史」 柚木学)
下戸 げこ
下戸の礼者に消炭をぶんまける 一26
【語釈】○礼者=正月の回礼をする人。
【鑑賞】下戸に向って消炭をあびせるような句作りだが、消炭を火鉢へたくさん入れて、急いで火をおこし、餅を焼いてご馳走しようというのだ。表現のおもしろさの句。
下戸へ礼言って女房はそびき込み 二二11
【鑑賞】正体なく酔って連れて来られた亭主を、女房が礼を言いながら家の中へ引きずり入れる。「そびき込み」という表現に、女房の心境やちょっと手荒な扱い方がうかがわれる。
【類句】下戸の首二ツかゝへて世話になり 一五11
生酔をまきつけて来る下戸の首 三五2
下戸恩にかけ/\一ツぐっとのみ 傍二21(しかたがない、一ツだけ、など恩に着せて)
下戸の客膳は急げとおっぱじめ 一〇六31(善は急げ、膳は急げ、早く飯を食おう、酒の終るのを待っていられない)
下戸向きの神様牛の御前也 拾四4(向島の牛島神社を俗に牛の御前。御飯に縁がある)(「江戸川柳辞典」 浜田義一郎編)
昔の男ども
当時の學校(草野心平経営)は新宿一町目でしょ。ノラは新宿二丁目にあって。「道草」は二幸裏にありました。そこを男たちはぐるぐる巡って飲んでいたのよ。なかには一晩で二周する人もいたりした。あの頃は男たちが毎晩飲むから、どこのお店もそれなりに儲かったのよ。儲かったというのも違うのかな、収入で困るなんていうお店はなかった気がする。でも家族や親族や養わなきゃいけない人が多かったから結局はぴいぴいしていた。ま、あたし(禮子)はそんなこと関係なくてのんきだったんですけど。結局何か月かすると、學校のお手伝いの人がいなくなってしまって。合わなかったんでしょうかねぇ。あたしは心平さんと山田さんを手伝って學校で働くようになりました。
こうして禮子さんは、開校から数か月遅れで學校の住人となる。以後、心平さんとその恋人の山田久代さん、そして禮子さんの三人で店を続けていくことになる。はじめ二十八歳だった禮子さんは、心平さんを見送ったとき五十六歳になっていた。その後、六十三歳の冬にゴールデン街に場所を移して酒場學校を再開する。私(金井)がであったとき七十六歳だった。人がやってきて、酒を飲んで、帰っていく。幾星霜、學校のカウンターのなかからその風景を見守って、禮子さんの人生は過ぎていった。
酒場(バア)学校のシンボルは 時代遅れの大時計
二十一世紀を告げる鐘 さらばで御座る
酒はぐいのみ ビールは泡ごと
酒場(バア)学校の常連は 世にも稀なる美男美女
落第つづけの優等生 しからばそうれ
酒はぐいのみ ビールは泡ごと(『バア「学校」の校歌』作詞は草野心平、作曲は小山清茂)
禮子さんのゆっくりとした口調で語られる昔の「優等生」たち。はなしを聞いているうちに、時間軸がふとねじれて、彼らの背中や掌や横顔が見える気がする。なーんて、酔いがまわってきただけか。(「酒場學校」の日々) 金井真紀
六波羅殿御家訓
(北条)重時は「六波羅殿御家訓」(十三世紀中頃)において、次のように飲酒上の注意を示している。 (一)「一 酒宴の座敷ニテハ、貧ゲナラン人ヲバ、上ニモアレ、下ニモアレ、コトバヲ懸テ、坐ノ下ニモアランヲバ、「是へ/\」ト請ズベシ。(下略)」 (二)「一 酒ナドアランニ、一提(ひさげ)ナリトモ、一人シテ飲ベカラズ。便宜アラン殿原モラサズ召寄(めしよせ)テ、一ドナリトモ飲マスベシ。サレバ人ノナツカシク思付ク也」 (三)「一 イカニ入ミダレタル座敷ニテモ、我前ナラデ、人ノ前ナル酒・肴・菓子躰物(ていのもの)トリテ食(くう)ベカラズ」 (四)「一 酒ニ酔イテ、カホノ赤□ラムニ、大道ヲトヲルベカラズ。(下略)」 (一)では、酒宴の席では、人の差別をしてはいけない、と酒席での気配りを、(二)では、酒を飲むならば一人で飲むのではなく、仲間と一緒に飲むように。そうすれば仲間から慕われるようになる、と独り飲みを戒め、(三)では、酒宴の席が乱れても、人の前の酒や肴に手を付けてはいけない、と酒宴でのマナーについて注意を促し、(四)では、酒に酔って赤い顔をして大道を歩いてはいけない、と今でも通じるような教訓を示している。この「御家訓」は全四十三条より成り、重時が若年の嫡男・長時に対して、「一家の主人としての心得、ひろく世間に交わるときの注意を事細かに記したものである」という(『中世政治社会思想』上「解題」昭和四十七年)。このなかで、重時は、宴席での気配りやマナーなど飲酒の際の心得を示しているわけだが、独り飲みについても、「一提(ひさげ)ナリトモ、一人シテ飲ムベカラズ」と禁じている。長時は、やたらに酒が強いられる宴席の酒より、独り静かに嗜む酒を好んでいたからであろう。(「晩酌の誕生」 飯野亮一)
酒価の変遷 志賀忍著『三省録』諸掲
南川語っていう「津の国(摂津)鴻の池の酒屋勝菴(三郎右衛門)という者、酒二斗ばらり入った樽二つを一荷とし、その上に草履数足をおき、これを担って江戸に下り、大名の家々を訪ねて、一升を銭二百文づつで売った。そのころは、まだ、麁酒(粗製の酒)があっただけで、彼の持参したような美酒がなかったので、奪い合いで売れてしまった。彼は大坂と江戸の間をしきりに往復して、おびただしく利潤を得た。当時は米は安く、木賃宿の宿泊料は十二文であったから、鴻の池と江戸との一往復の旅費も銭三百五、六十文ですんだし、お客たる大名たちからの注文も殺到したので、自身一人の肩で担いで来るだけでは、はかがゆかなくなり、遂に工夫して 一荷四斗(二斗入り桶二つ)の酒を一樽として、二樽を馬一駄として 数十駄づつ、馬で江戸へ運んできた。その理由で末代まで、問屋仲間で酒の値をきめるときには、十駄(二十樽)金何十両とする習慣になった。やがて、江戸における酒の需要がふえて、何十万樽を数えるようになったので、大きな船で運ばれるようになった。
酒小売値段変遷について『守貞謾稿』は、「慶安年中、東叡山塔頭の吉祥院の古帳面に 酒一升、四十文 とある。別掲引札(古報帖)は年号不詳。酒四十二銭がら百三十二銭まである。後考を俟つ。余(守貞)文化七年(一八一〇)の生まれ、幼年のころ大坂にて売る酒、極上一升の酒百六十四文であった。そのころ江戸では一升の値は二百文ないし二百四十八文であった。天保(一八三〇-一八四三)のころから値三百五十文、あるいは四百文になった。(下略)」 同じく『守貞謾稿』諸掲に 「江戸、文政(一八一八-一八二九)中、上酒一升二百四十八文ばかり、いま安政(一八五四-一八五九)に至り、一升三百四、五十文より、あるいは四百文なり。」(「江戸物価事典」 小野武雄編著)
目張紙(めばりがみ)
火入後、熱酒を入れた貯蔵容器が開放タンクの場合、蓋とタンクの間に隙(すき」)間ができるので、予めふのりを染み込ませた和紙で隙(すき)間を詰めて密封する.この紙を目張紙といい、断面が三角形の細い紐状のもの(芯子(しんこ)という)と3~4枚重ねた板状のものをいずれもふのりをつけて乾かして用意する.密閉タンクの場合も、マンホール、検尺口など通気の恐れのある個所に目張りをする蔵もある.(「改訂灘の酒」 灘酒研究会)
ドブロクとオマンズシ
先年、脳卒中で亡くなった父親は、意識が混濁して寝たきりの状態になってからも、酒の味だけはわかるらしく、栄養剤を溶かし込んだ牛乳を哺乳瓶で与えると、すぐさま吐き出し、酒だと、チュチュと音をさせて吸った。夏冬問わず、日本酒一本やりの酒好きだった。そういう親父(おやじ)のそばで、晩酌の相手などさせられていたから、正確には何歳ごろから酒を口にしたのか、分からない。が、自分の意志で呑み、酔うという感覚を知ったのは、中学二年のときだった。私が育った島根県の寒村では、煙草はともかく、酒に関しては未成年でも大目に見られる風潮があったから、それに乗じて、そろそろ鼻ヒゲなど目立つようになったその年の秋、中間試験が終わった晩に、仲間五人が集まってドブロクを呑んだ。村のよろず屋で、竹輪とオマンズシ(イワシの腹にオカラと山椒の実を入れたもの)と、ゴールデンバット一箱を買い、仲間の家の、納屋の二階の物置部屋へ、カンテラを持ち込んで車座になった。ドブロクは誰がどこから持ってきたのか、記憶にない。恐らく、仲間の一人が家からくすねてきたのだろう。竹輪をかじり、オマンズシを頬張(ほおば)りながら、五人は一つきりの湯呑み茶碗を順ぐりに回して、ドブロクを呑んだ。渋いような、酸っぱいような白濁した液体を、みんなはいっぱし、大人ぶった顔付きで口に運んだ。「トシミ(私の本名)とこは、父(と)っつぁんが酒呑みだけに、われも強いはずでや」「そがあだい。呑め呑め」仲間に煽(おだ)てられ、私はいい気になって、次々とあおった。甘酒の出来そこないのようで、うまいとは思わなかったが、呑めばいくらでも呑めた。そのうち、尿意を催して、立ち上がったとたん、天井へ頭を打ちつけた。それが利いたのか、アルコールのせいか、急に目の前がくらみ、カンテラに浮かぶ仲間の顔が分からなくなった。ここでするけに、と、転がったまま喚くのを、引き止められ、片隅にしまってあった火鉢を当てがわれたのを、覚えてゐる。その後、何日かして、「トシミは、もう、生えとるだで」と、言いふらされて、恥ずかしい思いをした。(「ドブロクとオマンズシ」 難波利三)
子どもの急性アルコール中毒
急性アルコール中毒がなぜ若い人に起こりやすいのかという理由は、次のように考えられます。①子どもはアルコールの代謝酵素が未完成で、吸収されたアルコールの濃度が急激に高まること。②飲酒経験のない人は、アルコールの代謝酵素の働きが悪く(活性が低く)、また中枢神経のアルコールへの感受性が高いので、中枢神経がすぐにマヒすること。③子どもは自分が飲めるタイプなのか、フラッシャーなのか知らないことが多く、飲めないタイプなのに大量に飲んでしまうこと。④集団場面での飲酒において急性アルコール中毒は発生しやすく、子どもは集団場面で、調子に乗って大量に飲むことが多いこと。⑤イッキ飲みは、集団によるいじめ的要素が大いにあり、飲めない子に無理強いして飲ませること。 このように理由をあげていくと、急性アルコール中毒が増加している理由は、子どもの飲酒が増加していること、世の中に安いアルコールがあふれていること、子どもの飲酒を抑制する力が何もないこと、子供同士の殺伐とした関係などの現代の問題が、集中的に現れていることがわかります。(「子どもの飲酒があぶない」 鈴木健二)
蛇の肝
そしてその中で、特に香港で一番人気の二日酔い用食材だといわれているのが、ここでも登場、蛇の肝である。これを乾燥させたものを、お酒を飲む前、あるいは飲んでいる最中に、パクパクとやる。こうすると、翌朝頭痛がしたり吐き気が襲ってきたりすることがまったくなくなるのだとか。ちなみにこれは、ホメオパシー(同種療法)という考え方に基づくものあり、例えば目が悪ければ、何か動物の目を食べて、その目の病気を治す。心臓が悪ければ心臓を、胃が悪ければ胃を、といった感じで、自分の悪いところを食材として取り入れて食べれば病気にいい影響を与えることができる、という考え方が、伝統的な東洋医学には基本的なスタンスとして存在しているのだ。(「二日酔いの特効薬のウソ、ホント。」 中山健児監修)
足一本丸ごとタコ焼き 秋田屋(浜松町)
大門(浜松町)にある「秋田屋」。大通りに面したこの店は、通りかかるたびに店内はもとより、店外に置かれた立ち飲みテーブルにまで大勢のお客さんがあふれ返るようにして飲んでいます。そんな「秋田屋」の開店時刻は、午後三時半。その時刻に着くように向かったのに、地下鉄の出口を出るのに手間取ってしまい、店に着いたのは開店の五分後。たった五分しか経っていないのに、入口左の直線カウンター席はすでに一番手前側一席分しか空いていない状態で、右手に並ぶテーブル席もすでに半分くらいお客が入っています。そうかぁ。この店も開店と同時にこんなに埋まっちゃうんですね。ひとつだけ空いているカウンター席に座り、ビール(キリンラガー大ビン、五五〇円)をもらって、名物・たたき(肉だんご、二二〇円)を注文します。(「ひとり呑み」 浜田信郎) 港区浜松町2-1-2
狂歌才蔵集
一朱楽菅江(あけらくわんかう)
11二土器(かはらけ)の三土性(つちしやう)ならば屠蘇の酒四ひとつは過せやまとだましゐ
11 一- 山崎氏、名は景貫。寛政十年(一七九八)没、六十一歳。幕臣で和歌を能くし、狂歌・雑俳・川柳・洒落本と、殆ど南畝と共に天明調の騎手として活躍した。- 二 素焼きの器。儀式に土器を用いるのは神道の風俗。 三 かわらけが土製であることと五行の土性を掛ける。 四 一杯位は飲み過ごしてもよかろう。
一千里亭白駒(せんりていはくく)
14きのふまでふりむきもせぬ餅なれどけさは上戸もいはふ二はがため
14一- 牡丹花松柏。宗祇門の連歌師として著名。大永七年(一五二七)没、八十五歳。騎牛の肖像に描かれること多く、花・香・酒を愛した風柳生活を「三愛記」と題して書いたものが有名。 二- ▽下戸は餅好きが通念。(「狂歌才蔵集」 中野三敏校注)
友人会宿 友達が集つて泊る-
滌蕩(デキタウ)ス千古ノ愁 千古の愁を洗い流さんと
留連ス百壺ノ飲。 百壺の酒を飲みつづける。
良宵 清談ニ宜シク 宵も良し話もはずんで
皓月 未ダ寝(イヌ)ル能ハズ。 白い月に まだ寝るのが惜しい。
酔ヒ来ツテ空山ニ臥スレバ 酔ひが廻はつて人気なき山中の臥すれば
天地ハ即チ衾枕。 天地は そのまゝ夜着と枕だ。
○千古ノ愁 永く積り積つた憂鬱。万古愁などとも云ふ。支那的誇張である。 ○留連 さまようて去るに忍びない有様。江戸時代の粋人はヰツヅケなどと訓じた。遊里の語である。(「中華飲酒詩選」 青木正児) 李太白の詩です。
裏通り
概して言えば、渋い呑み屋を探すときは裏通りを目指せばよい。車の交通量が少ない道は開発が少し遅れていることが多く、したがって比較的古く、小ぢんまりした店が残っている可能性が高い。とくに歴史を感じさせるような店を探すなら、表通りよりも裏通りの方が見つかりやすいのは間違いない。もちろん例外はある。たとえば、北千住のように宿場(しゆくば)町から発展した場所だと、昔は旅籠(はたご)や茶店などが並んでいた街道に、いまだにいい赤提灯が見られる。門前仲町にも同じことが言えるが、最近は主要街道である永代(えいたい)通り沿いにチェーン店が急増していて、裏通りに個人経営の店が密集していることは変わりない。(「日本の居酒屋文化」 マイク・モラスキー)
長酔
わりなくも
まどふにまどへ
花の散るに
春寒からずや
人の泣く
我れとどめあへず
恋はそれ
顧みるに栄(は)え
名はそれ
仰ぐに燃ゆ
追懐(おもひで)なくば
恋今苦(にが)し
希望(のぞみ)なくば
名は昨日(きのふ)に朽ちぬ
世に酔ふもの
世に活(い)きざらんや
君何を疑はん
ここに二人恋ふ
つよくつよく
泣くに王者(おうしや)も憚(はばか)らず
襟は冷(つめた)きも
色紫なり
病む子を責むな
痩せて酒嘲(あざけ)る(「紫」 与謝野寛)
自然災害
さて、十一年前のことになりますけれども、あの阪神淡路大震災がありました。皆さんの中にも、被災された方がいらっしゃると思います。特に、灘五郷と言われる西宮から神戸にわたる地域は、甚大な被害を蒙りました。この地域では残念なことに、工場・酒蔵の全半壊、設備の損壊、木造の工場・蔵は、ほぼ全壊、被害総額は約千百二十三億円に及びました。それは、思い起こしたくない話なのですが、その地震を蒙った時、冒頭でお話しさせていただいたように、四百五十六年の歴史って何だろうな、と思ったのです。私は、そんなに歴史・伝統が重荷になるタイプではなかったのですが、ただこの時はさすがに、長い歴史の中でもこういう自然災害を乗り越えて今というものがあるのかなあ、とつくづくと思ったものです。そういう意味で、困難に直面したことによって、逆に自然に対する畏敬の念と、長く続いてきた歴史の重みというものを感じました。いくら商売が上手くいっていても、自然災害に負けてしまうこともあるわけで、そういうものを乗り越えて今までやらせていただいていることを、改めて感謝しないといけないと思ったわけです。(「不易流行の革新経営をめざす!」 小西酒造株式会社代表取締役社長
小西新太郎)
酒食は人の好む物
酒食(しゆしょく)は人の好む物なれば、人辞退してふせげども、しいて飲ませくらわしむることは、世のならいなり。是れ人の真実に酒食を好むことをしればなり。
<解釈>酒食は人が好む物だから、さされた人が断っても、無理強いして飲ませるのは世の中のならいである。これは本当は人が酒食が好きなことを知っているからである。
<出典>江戸、貝殻益軒(かいばらえきけん)(名は篤信(あつのぶ)、字(あざな)は子誠(しせい)、益軒は号 一六三〇-一七一四)『大和俗訓(やまとぞっくん)』巻之七(「食の名言辞典」 平野・田中・服部・森谷編)
デカダンス
陶淵明は酒好きで知られた人で、辞世の試作にも、自分はこの世で何も思い残すことはないが、ただもう少し酒を飲み足りなかったことが、唯一つの心残りだ、という意味の詩を残したくらいの人であります。中国には飲酒の詩がたくさんありますが、いずれも深刻な虚無感かそれでなければ無常観が底を流れているように思われます。日本でも有名な大伴旅人の唄など典型的といえましょう。オマル・ハイヤームのルバイヤットに出てくる酒の歌など、とかく酒の詩歌はその数の多いことでも、質のよいことでも、東洋がすぐれているのも、何かインド思想に根ざすものがあるのではないでしょうか。酒はしょせん寂しい人、悲しい人のためのものであるようです。「酒はやけ酒」などというのもたしかにその一面かもしれません。引き合いに出しては、少しおそれがありますが、かつて私の詠んだ、 うるはしきいのちいきなむとおもふかな またあひがたきこれのよにして という歌をみた友人に、すごいデカダンスだなあといわれて、ギクリとしたことなども思い出されます。(「酔話の魔力」 坂口謹一郎)
秋風起りて蟹を思ふ
秋風がさやさや街をわたる頃になると、江南の喰いしん坊達は何よりも先づ蟹を思ふ。愈々蟹が市に上れば待ち兼ねたやうに、どこの酒家にも「右手に酒杯を持ち左手に蟹螯(かに)を持つ」今様畢卓(ひつたく)の居並ぶ風景を見る。その頃上海に遊ぶ人は、酒家の店頭に沢山の蟹が金網を伝つて上下する様を見るであらう。江南一帯殆ど此の無腸公子(かに)を産せざる処はなく、蘇州の羊腸蟹、常熟の金爪蟹は最も珍重せられるが、この種の蟹の名称は頗る多く、とても覚へきれない程である。蟹諺に「九月団臍、十月尖」といふのは、雌は九月が最も旨く、雄は十月が最も旨いといふ意味であつて、古人も蟹にうつつを脱(ぬ)かした人が相当多かつたのであらう。雌は腹甲が丸いから団臍と謂ひ、雄のは尖つて居るから尖と謂ふ。食単に「酔蝦(ツイシア)」を載せて「酔蟹(ツイシエ)」を無視したの片手落ではあるまいか、酔蟹は年中どこの食品店にもあり、且つ小菜として多くの狂嗜者さへある。その製法は、先づ小蟹の腹部に塩を摺り込み、脚を藁(わら)で括つて、酒若しくは酒と醤油の合せた液中に活きながら漬け込む。随分残酷な方法であるから、君子ならずとも現状を看ては惻隠の情を催すに違ひない。(「飲食雑記」 山田政平)
自賛(自贊) 一休宗純(いつきゆうそうじゆん)
風狂(フウキヤウ)ノ狂客 狂風ヲ起シ 風狂狂客起狂風
来往ス婬坊(インバウ) 酒肆(シユシ)ノ中 来往婬坊酒肆中
具眼ノ「衤内」僧(ナフソウ) 誰ゾ一拶(イツサツ)スルハ 具眼「衤内」僧誰一拶
南ヲ画シ北ヲ画シ東西ヲ画ス 畫南畫北畫東西
もの狂いの風流僧が、狂風を起し、女郎屋と酒屋とのあいだを徘徊(はいかい)している。見識めかした禅坊主が来て、問答を仕掛けてきたが、そんなことに答えられるものか。東か西か方角もないのに、わしは自分で決めて行くだけのこと。これが一休の面目の真骨頂(しんこつちよう)と言うべきか。(狂雲集)(「古典詞華集」 山本健吉)
犬
居酒屋を経営している男がびっくりするほど大きな犬をつれて、家へ戻ってくる。それを見て、そんな犬をどこからつれてきたのかと、女房がたずねる。男は事の次第を話して聞かせる。「今日、おれたちの店の権利を延長してもらおうと思って、伯爵のところへ行ったんだ。すると、伯爵はべろんべろんに酔っぱらっていて、おれにこう言うんだ、もしこの犬にヘブライ語が話せるようにしたら、権利金はただにしてやる、だが、それができないなら-この場でおまえを撃ち殺す。そんなわけで、おれはとっさに考えたんだ、もうどうしようもないと。そこで、やっと、その犬を五年間預からせてください、その間にだんだんしゃべれるようにしてみましょう、ということで話をまとめてきたんだ。」女房は嘆きはじめる。「なんてことをしたの。気でも狂ったんじゃないの。五年間で何とかできると思ってるの。この犬がしゃべれるようになる前に、あんたがわんわん吠えはじめるわよ。」「まあ、落ちついてくれ」と、男は言う、「五年の間には、三つのことのどれかが起こることだろう、まず、この犬がくたばる、でなければ、伯爵が死ぬ、でなければ、おれがこの世におさらばする。」(「ユダヤの笑話と格言」 ザルチア・ラントマン編 三浦靱郎訳)
甘党
酒は酢の物の如[ごと]き類とよく調和して、菓子や団子と調和しにくい事は一般に知つてゐる所である。南瓜[かぼちや]、薩摩[さつま]芋、胡蘿蔔[にんじん]などは野菜中の最も甘味多き者であるので酒とは調和しにくいのであらう。酒飲みでも一旦[たん]酒を廃すると汁[しる]粉党に変る事がある。して見ると女は酒を飲まぬが為に南瓜などを好むのに違ひない。(病牀六尺)(「飲食事辞典」 白石大二) 「病牀六尺」は正岡子規の著書です。
燗と冷や
ところで最近は、燗にこだわる人が少なくなってきた。冷蔵庫の普及で日本酒を冷やして飲むことが長く続き、これまでの習慣にとらわれずに日本酒とつきあう人が増えてきたためである。かつて日本酒には、「燗上がり」のする酒(燗をすることにより酒が良く感じられる)と、「燗下がり」のする酒(燗をすることにより酒が不味に感じられる)とがあるといわれていたが、今日のように高い精米歩合と低温発酵で造った酒は、燗の有無にかかわらず常に安定した香味を発揮できるので、従来のようにそう燗にこだわる必要はない。むしろ吟醸酒のように上品な味と高い芳香を持った酒は、冷やしてすばらしい酒なのである。冷やでも燗でも、好みによって自由に日本酒とつき合って、そのすばらしさにふれてほしいものである。(「日本酒の世界」 小泉武夫)
酒のなる木
金のなる木があれば、いちばんいいのだが、さすがにこれは実在しない。しかし、酒飲みからすれば、金のなる木も同然の"酒のなる木"はほんとうにある。それは、アフリカ中部、ハシ川の流域に生育する「シロ」という木。この木の樹液は相当のアルコールをふくんでいて、集めて飲んでみると、味のほうもかなりいける。そこで、アフリカでは「ブララ酒」として市販されているという。「ブララ」とは、ハシ川流域の町の名だ。(「SAKE面白すぎる雑学知識」 博学こだわり倶楽部編)
仕事の分担
子産(しさん)が鄭の宰相のとき、簡公(かんこう)が子産にいった。「酒をのんでうまくなく、俎豆(そとう)(食事の器具)が大きくなく、鐘鼓竽瑟(しようこうしつ)(楽器)が鳴らぬのは、わしの罪だが、国が不安で民が治まらず、耕作や戦争に協力一致を欠くのは、お前の方の罪だ。お前にも仕事があるが、わしにも仕事がある。たがいにその仕事を守ろうではないか」子産は退出して、政務に励むこと五年。国には盗賊がいなくなり、路上のおとしものはだれも拾わず、道一杯になった桃やなつめもとる者がなく、錐のような小さなものを落として、三日たって行って見ても見付けることができるほどになった。こうして三年たって、民には飢えるものがいなくなった。 (外儲説左上)(「古代寓話文学集 韓非子篇」 高田淳訳)
△製灰(はいのせい)
豊後灰(ぶんごはい)四二壱斗に本石灰(ほんいしばい)四升五合入れよくもみぬき、壺へ入れ、さて、はじめふるいたる灰粕(はいかす)にて、たれ水(みず)をこしらえ、すまし灰のしめりにもちゆ。尤(もつとも)口伝あり。
△なおし灰
本石灰壱斗に豊後灰四升、鍋にていりてしめりを加え用ゆ。囲酒(かこいさけ)にひをいるるは入梅(つゆ)の前をよしとす。
四二 豊後灰 今の大分県地方は江戸時代以前は炭焼で各地に出稼する者が多く、、木炭を焼く際に出る木灰も多く生産されて染物の灰汁用、肥料用として船で瀬戸内海経由で積出された。これを国の名で呼んだので、必ずしも豊後産でないものもあったろう。(「日本山海名産図会」 木村孔恭 千葉徳爾註解)
しゅ-ぎょう[修業]
(名)①学問や技術・武芸などを練り磨くこと。②仏法を修め善行を積むこと。
樽の中で修業しているウイスキー 吉川一郎
じゅん[順]
(名)①順位。順序。②順番
杯の順日本の祝いごと 増井不二也
ジョーク
(名)冗談。しゃれ。
ジョークだよ友もお酒も赦しあう 山倉洋子(「川柳表現辞典」 田口麦彦編著)
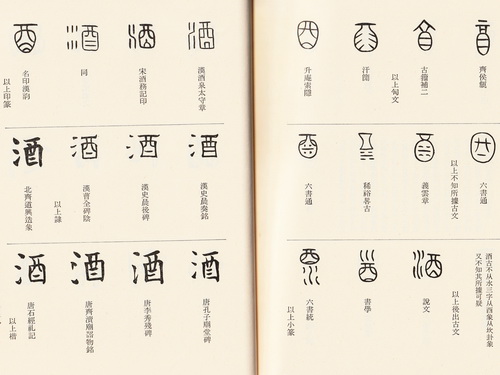
露伴全集にある、幸田露伴が集めた酒の字の一部です。(「幸田露伴全集第40巻」)
ルバイ第三十九
盃より投げて地(つち)に吸はす
一雫(ひとしずく)だに、浸(し)み入りて、
遙か下、遠き昔、其処(そこ)に隠れし
或る眼(まなこ)の悩みの火をば消さぬは有らじ
[略義]酒は、現に地上に生きて居る我々の胸中に在る悩みの火を消すだけでは無い。我々が地上に濺(そそ)ぐ酒は、其の一滴たりとも、地中に浸(し)み入って、昔、しかも、土中深く、埋(うず)められた祖先の、今だに浮ばれぬ魂の悩みの火を、消さないものは無い。
[通解]ライベイション(libation灌酒(かんしゆ) と云って、神に酒を供える時、これを地上に灌(そそ)ぐ習慣が有るが、此の習慣にも、此のルバイに歌われて居る所の意味の含みが、満更(まんざら)、無いとは云えない。何となれば、死者の霊と神とは、密接な関係が有るから。此のルバイは”some
Eye”「目」と云っている所が面白い。安らかに眠って居る事が出来ないから、目を開いて居るのだ。
米だけの酒
その日本酒造組合中央会はまたぞろ手前勝手なことをやろうとしてきています。皆さんももうご承知だと思いますが、先だって日本酒造組合中央会から各組合員と申しますか、各蔵元に通達が廻りまして、それを見た心ある蔵元は「何じゃこれ」と思ったようでございます。今日のお話のタイトルにもあります「純米酒要件の見直し」というのがその通達なのですが、その内容はといいますと、①純米酒の要件として「精米歩合七〇%」とあるが、その制限を撤廃する ②精米歩合の表示は義務付けることとするが、その表示については一〇%の幅による表示も可能とする。例六〇%~七〇% ③本醸造酒についても純米酒と同様の表示要件とする といったものです。これを見てまず感じたことは、「あっ、大手の『米だけの酒』を純米酒として売りたいのだな」ということです。-
まっ、このことに関しては後で確認したところによれば、「屑米、破砕米、米粉」を使用した場合は「純米、米だけの酒」などという表示は出来ないのだそうで少し安心したのですが…。-
しかし、これらの屑米、破砕米、米粉を使用した場合、原料表示として「米、米麹」がOKなんだそうです。オイ、オイの世界です。今まで、表示に「原料:米、米麹」とあったら純米酒だよと教えられてきた消費者が、これから原材料表示を見て、屑米や米糠利用のお酒でも純米酒と誤解することが目に見えていますよね。「わかりにくさ」是正のはずが、余計迷ってしまうではないでしょうか。(「ツウになるための日本酒毒本」 高瀬斉)
介入を成功させるには
まず、きっかけはだいたい近親者からの相談である。ひとりでやって来て「主人のことがとても心配なのです。けじめなく飲むようになりました。初めて私を殴ったのです」というような話をする。カウンセラーは問題の人物の生活に関わる主な人たちに事情を説明し、介入に参加してもらいなさい、と相談者に話す。参加者は事前に説明書を読み、カウンセラーからこの方法について精しく説明指導を受ける。さらに各自が、当人から受けたむごい仕打ちや困惑した最近の体験を三例挙げ、その日付け、時間、そして印象を書いてくるよう指示が与えられる。その後、皆がそのメモを持ち寄って話し合うのだが、介入のために自分たちのしていること、その意味と理由を全員が確実に理解するまで、何度も会合を開く。介入の会には、本人が出席するので、一同は緊張する。各参加者は、問題の当人が自分についてどう考えているのか、引き出そうと真剣である。そのために、前もって冷静な状態でメモを書いてもらう。こうすれば忘れない。時には緊張のあまり的確な応答ができない人がいるが、書いているうちに、その人はアルコール症者との苦い実体験を再確認するとともに、当人の振る舞いがアルコールによるのだということを納得して会に臨める。それがすべり出しで、家族の心は癒やされはじめる。だが家族が受けた傷の手当ては後回し。介入の最中に傷を開いたまま放置してはならない。家族の一人一人もこれに参加しながら、さらに自分で治す方法を探っていかなければならない。家族の全員が、アルコール症者の生活のかぎを握る人とされる。ただ座っているだけの五歳の子供でも、アルコール症者の生活を構成している存在であり、それを示す権利がある。雇い主なり上司の参加も、非常に重要である。呼ぶのをためらう人もいるが、本人の言い分はともかく、雇い主は社員に飲酒問題があることを知っている一人だからだ。聖職者が本人にとって重要な関わりをもっているなら、当然その人にも加わってもらう。親友は、まさに適任者である。酒飲みであってもよい。アルコール症者でも、自分が見えなくても他人は見えるもの。介入の妨げになる恐れのある人がグループにいれば、カウンセラーは理由を説明し、参加を控えさせる。酒のせいの振る舞いにすっかり腹を立てているような人は、むろん加われない。この判断は、カウンセラーの大切な役目の一つである。というのも、アルコール症者は非常に敏感で、その場の雰囲気を直ぐかぎ分ける。敵意を排し、愛情のこもった温かい雰囲気で迎えてやらなければならない。家族側が怒っていれば、カウンセラーが説いて会合を開けるムードづくりをする。介入が成功しなかった場合、つまり愛情をもって助けたい一心で接しても、当人が治療を拒んだ場合、参加者はこの先どうするつもりでいるかを、その場ではっきりと話す必要がある。ときには一時的な別居という深刻な提案も出てくる。相手は家や職場を離れ、飲んだくれて事故を起こし、命を落としかねない。いささか厳しい話だが、それでも介入には効果がある。介入のおかげで断酒している人も多い。ただし、この会を本人の家で開いてはいけない。陣地内では気楽になりすぎる。本人を治療センターに呼べる見込みがなければ、掛りつけの医者のところなど、双方にとって中立的な場所を選ぶのがよい。会合場所は、前もって打ち合わせ会でセラピストと相談し、決めておく。そして日時を決め、リハーサルを行なう。それには各自が用意した体験メモを使う。そして当人を本番に連れてくる。その前に、治療を受けさせる病院に予約しておき、入院のための荷造りもすませる。家に帰るすきを患者に与えてはいけない。また勤務先の上司に事情を説明して、同僚に仕事を代行してもらえるよう承諾を得ておく。これで準備は整い、当人に残された余地はぐっと狭まった。上司は彼を呼んで「よし、あの件のことは忘れろ、後を引き受ける人間を見つけてあるから」と言う。当人にしてみれば、愉快なお達しではないのだが、この際、いたしかたない。いよいよ介入の会が開かれる。問題の人、ビルが入ってくる。まず彼に言葉をかけるのはカウンセラー。「私たちが今日ここに集まったのは、皆あなたに話を聞いてもらいたいからです。皆が話し終わった後、あなたも質問していいのですが、相手の話を中断しないで、終わるのを待ってください。協力してくださいね」と釘を刺す。話の腰を折ろうとすれば、カウンセラーが注意する。「約束どおり、どんな正当な理由があっても、いらいらしても、全員の話が終わってから発言してください。話し合いはそれからです」前もって定められた順序で、一人一人がアルコール症者への愛情と心遣いをこめて本人との体験を話す。当人は「それで私にどうしてほしいのだ」と、たびたび食ってかかるだろう。このときカウンセラーは「私たちはあなたに〇○病院に三、四週間入院してほしいのです」と答える。承諾すれば、望みが達せられたも同然、介入は終わる。(「アルコール依存症」 デニス・ホーリー)
ちよき[猪牙]
舳の尖った快速の小舟で遊所通い専用、俗に薬研とも勘当舟などともいい、柳橋にこの船宿があつた。柳橋から山谷堀まで片道百四十八文で急ぎは百文増し。もと生魚の運送-長吉舟から思いついたもの。長吉舟を略してチヨキといつたので、船の形が猪の牙に似ているところから猪牙舟とこじつけたのだという。船宿を猪牙が大川へ出て、左に蔵屋敷の首尾松を見て行くのは吉原、右手に浜松河岸松浦家下屋敷の椎の木を見て行くのは深川櫓下へ向かうものである。-
⑫立たぬ約束で生酔を猪牙に乗せ (樽一八)(「古川柳辞典」 14世根岸川柳)
東西の味かげん
今世三都共ニ士民奢侈(しやし)ヲ旨(むね)トシ特ニ食類ニ至リテハ衣服等ト異ニシテ貴賤貧福ノ差別ナキガ如(ごと)シ。而(しかし)テ三都自ラ異ナル所アリ。京坂ハ美食ト雖(いえど)モ鰹節ノ煮ダシニシテ是(これ)ニ諸白(もろはく)酒ヲ加ヘ醤油ノ塩味ヲ加減スル也。故ニ淡薄ノ中ニ其(その)物ノ味アリテ是ヲ好(よし)トス。江戸ハ専ラ鰹節ダシニ味醂酒ヲ加ヘ或ハ砂糖ヲ以テ代レ之(これにかう)。醤油ヲ以テ塩味ヲ付ル也。故ニ口ニ甘ク甞カシト雖モ其物ノ味ヲ損スニ似タリ。然レトモ従来ノ習風トナリ今ハ味リン或ハサトウノ味ヲ加ヘザルヲ好マズ、必ラズ用レ之テ京坂ノ食類更ニ美ナラズト云。又京坂ノ人ハ江戸ニテ甘味ヲ用フヲ、タルシト云テ忌レ之テ美食トセズ。各互己レガ馴タルヲ善トシ、馴ザルヲ不善トスル而已(のみ)。 喜田川守貞『守貞謾稿』
さすがに上方人だけあって、上方料理の特質について、喜田川季壮守貞の解説は詳細である。しかし、上方の昆布出汁(だし)の利用について、一言も触れていないのはどうしたわけだろう。すでに『料理物語』(寛永二〇年・一六四三刊)にも、精進出汁の材料として、「干瓢、昆布、干蓼、干蕪、干大根」などが挙げられており、使用量において昆布が群を抜き、守貞も熟知しているはずなのに、片手落ちである。(「料理名言事典」 平野雅章編)
白鷹
白鷹の創業は文久二年(一八六二)で、明治元年の七年前です。初代の辰馬悦蔵以来、一貫して一流主義を通してきているところに脱帽すべき企業姿勢を発見できます。こういう話があります。品質をよくするために、手間がかかっても生酛(きもと)の一種であるすり酛方式を採用していること。しかも、創業以来の仕来たりとして、四斗だるに酒を詰める時、水でたるを洗わずに、白鷹の酒で洗っていたというのです。普通、水でたるを洗うと、終わりの徳利ニ、三十本は、酒の質が悪くなるようですが、白鷹に関しては、そんなことがありませんでした。酒で洗ったからだというのです。したがって、灘の代表銘柄が二円前後の時は、三円三十銭くらいしていたといいます。こういう酒に対する神経の使い方は、よい米を作るための農家への資金援助という行為にも表れましたし、たるの材料の杉にも、最高の部分を選んで出荷したのです。戦中、戦後、他の蔵元がある意味で酒質を犠牲にしたり、桶買いで、販売量を拡大した折りも、ここだけは頑固に品質を守り続けてきた、といいます。大正十三年六月、宮内省から伊勢神宮のご料酒の指名を受けて以来、今日でも毎朝神前に備えられているのです。もちろん、自醸酒100%は今でも守っていますので、大手の蔵からは、出荷量で随分遅れをとり、現在、出荷量50位以内には入っていません。知名人のファンは、昔から多いのですが、関西では、あまり強くなく、東京のほうで人気のある酒だと聞いていますが、自醸酒100%を守るために、問屋の要求に応えられずに、大阪を中心とする市場を失ったのだということです。しかし「桃李ものをいわず、下おのずから蹊を成す」を社訓として、頑として節をまげない姿勢は、敬服に値しますし、一方、昨年秋には、夙川右岸に「辰馬考古資料館」をオープンするなど(明治の異色画家富岡鉄斎とも、往来があったという)酒造りだけでなく、広く一流の物を人々に還元しようとする気風は、特筆したいところです。(「灘の酒」 中尾進彦) 昭和56年の出版です。
南米では受けると思う-アルゼンチンの男性
はじめに熟成酒を傾けて、「とっても旨い酒だね」と表情をゆるませ、「これが日本酒ねえ」と感慨深げなのだ。これまでは吟醸酒、熟成酒の順でテイスティングしてもらっていたのを、ここでは逆にやってみた。次に吟醸酒を飲んで、「おやっ、これはまた違うね。これも日本の酒?へーえ、驚きの味覚だ」と言葉を添えた。このブースのファイサール社は農業、畜産の企業だが、中でもキジは年間に数千羽を飼育しているとか。「うちのキジ料理にも合う味だよ、この二つのタイプの酒はどちらも好きだね。こういう酒は南米での受けはいいんじゃないの?チリやブラジルなんかでもどんどん広がると思うよ」と、同社専務のフェデリーコ・ステペルリンクさんは自信をもって推薦してくれた。今回のインタビューで最もうれしかったコメントである。なにしろはじめて口にした日本酒に対して、「わが地元の南米では受けるのではないか」というのがいいではないか。他所ではなく「地元でこそ受ける」というのがあちこちにひろがればいいのである。(「知って得するお酒の話」 山本祥一郎)
坂口記念館
上越市頸城区に建つ坂口記念館は、同地出身の坂口謹一郎博士の功績をたたえ、頸城杜氏の酒造り文化を今に伝える施設である。正式名称は「香り高き樂縫庵(らくほうあん)と酒づくりの里 坂口記念館」。旧頸城村の大肝煎(おおきもいり)(庄屋・名主とも呼ばれる村の長)であった坂口家の堂々たる旧家の雰囲気を漂わせる「樂縫庵」には、坂口博士が好んだ囲炉裏(いろり)のある書斎が再現され座敷で清酒の試飲ができる。敷地内は、蔵人や地元文化人との交流の場として使われた「留春亭(りゆうしゆんてい)」や、百種類もの雪椿が植えられた「雪椿園」がある。坂口博士の業績を展示品やビデオ映像によって紹介する「酒杜(さかも)り館」には、博士が受賞した勲章や直筆の講義ノート、折に触れて詠んだ歌の数々と愛用の筆、硯(すずり)、落款(らつかん)などが展示されている。また、同館では、蔵人が酒造りの工程で歌った「酒造り唄」の保存・継承を目的に、かつての酒造り道具が多数展示され、酒造り道具を使った酒造り唄の実演が行われている。(「新潟清酒達人検定」 新潟清酒達人検定協会)
増税
酒税法に大きな変更が加えられたのは日清戦争後の一八九六年(明治二九)のことである。日清戦争には勝利し、賠償金も得られたものの、いわゆる「三国干渉」があり、政府は「臥薪嘗胆」のスローガンのもと、対ロシア戦を想定して軍備拡張を進めようとしていた。そしてその有力な財源として増税が計画され、酒はとくにねらい打ちの対象となった消費財であった。こうして一八九六年に酒造税法が制定された。この税制一つの特徴は、従来の免許税が廃止され、造石税一本となったことである。同時に税率は大幅に増税となった。さらに重要なことは、図10に示した通り、日露戦争、第一次大戦期まで、酒税は度々引き上げられた。増税のテンポという点では歴史上、最も早いものであった。また、一九〇一年(明治三四)には、麦酒税が初めて導入された。こうして、一八九九から一九〇三年には、酒税が地租を抜き、国税のトップとなった。なぜこの時代に酒に対する大増税が可能となったのか。当時の政策論争でも様々な議論がなされているが、酒税引き上げ論者の主張は次のようなものであった。(1)酒は奢侈品、嗜好品であり、一般消費者に苦痛を与えるところ少ない。(2)酒税は間接税ゆえ、消費者に転嫁され、酒造業者に負担を与えない。(3)速やかに多額の税収を期待できる。徴税コストが安い。(4)国民衛生上、課税によって酒消費を抑えることは望ましい。(5)奢侈品といえども、国民多数が消費する財であり、税負担が偏することはない。(6)消費に対する税で、資本蓄積を妨げるところ少ない。(「酒と経済」 宮本又郎)
(七)むら田
酒(さけ)はのん飲(の)みたし、のん飲(の)むことはなんならず、おさかおはんがはやしを見て、おとんど通る、おはりはおとこにお中の町、こずはこく町のはん恥(はぢ)しらず、やれこのほしたてよい此とのごでござる、ずんど恥をしらぬはあほうほう、むら田はんぴやうゑを見(み)たか、いかななんぼう夜(よ)も日(ひ)もなんぼうなんぼう/\、やれしりよはせをて、なんぼうかちで通(かよ)ふた〻いきおほのかけられおはやるかくしいなばを見(み)たかやまふしふきりやうねんななんぼうあいだになんぼう/\なんぼうやどのもめやい、なんぼう見られぬにくいつら、向ひ饅頭屋(まんぢうや)にもさ、半兵衛やれこりやぜいをつくとの、うそをつくとの、つく/\つくつ〻てんこじ、有(あ)ること無(な)い事(こと)ふんだいた、ありもせう無いにぢよらうくどくさ、それで人が悪(わる)くいふにさ、あのかぴたんめ茶屋のそうびやうゑ、誓文(せいもん)あき風(かぜ)が
このぼしたて-このぼうさての誤か しりよはせをて-尻はし折て(「若みどり」 藤井紫影校訂)
福岡県久留米市・若竹屋酒造場
1699年(元禄12年)から酒造りを手がけてきた若竹屋酒造場では、創業時のままの姿が残る蔵「元禄蔵」で唎き酒を楽しみつつ、日本酒造りの歴史をたどるタイムトリップのような体験を楽しんだ。元禄時代の古文書をもとに再現した琥珀色の「馥郁元禄之酒」は、甘やかな香りと奥行き深い旨味がふくらみつつ、後口は実に清々しい。室町時代の文献から製方をたどった純白の「博多練酒」は、見た目そのままにヨーグルトのような酸味となめらかな口当たりにここちよさを覚える。その昔は、お殿様や殿上人しか体験できなかった贅沢だ。(「ニッポン「酒」の旅」 山内史子)
(増)盃の織部形 日根野織部正高吉が好みにて製せしむる盃也
(増)盃の開眼 [俳諧藤の実]盃の開眼をはやけふの月之道
(増)盃影 月をいふ (増)酒盃にそへて月をいひ入たる也 酒盃すでにまた丸き物なればことによせ有べし
(増)盃二ツ重る 四季草云 盃二ッ重る事 今世年始なとに 何方にても 三方に二ッ盃をかさねて出す事あり 武家にてハ 甚いま/\事也 腹切るべき人に 酒すゝむるにハ
必二ッ重ね出して 二度つゝ二献のまする也 のみたる盃ハ ふせて置 又敵の大将の首取て 実検してかの首に酒を手向る時も 盃二ッ重ぬる也 されハ盃二ッ重ね置事
二献飲む事をいむ也 武家にて是を知らざるハ あさましき事也 又年始なとに人を、切腹人、首切られたる者と同じあつかひにする事甚無礼なる事ならずや(「俚言集覧」 村田了阿編輯)
餅米酒之事(7)
一、餅米沸強き物也。風味辛く薄口也。足弱くして火を早く乞、油断すれハ替る物也。勿論片白に造るへし。造り様以下粳米(うるしね)同前。但し、醒し切て造るへし。
もち米酒(7)
○もち米酒はわき方が強いものである。酒の風味は辛く、薄口である。日持ちがわるく、早く火入れを求め、油断していると変質するものである。もちろん片白で仕込む。造り方はうるち米の場合と同じであるが、蒸米を冷まし切ってから仕込むこと。
(7)餅米酒 ふつうのうるち米のかわりにもち米で造る酒。
鰭酒
ひれ酒やすこしみだれし女かな 朴亭
鰭酒や逢へば昔の物語 年尾
鰭酒も春待つ月も琥珀色 秋桜子
例句一の小糸朴亭(ぼくてい)(昭和五十三年没)の本名は小糸源太郎。上野の生家は有名な料亭「揚出し」。画家として芸術院会員で、久保田万太郎らの「いとう句会」の同人。「なあに、コップ一ぱいぐらい、どうってことはないさ」と勧められて、気軽に傾けた鰭酒の酔が発して、いつのまにか横座りになった女は、座持ちの芸妓の一人であろう。ちょっと色っぽいスナップ。例句二の高浜年尾(ちおしお)(昭和五十四年没)は高浜虚子の長男。昭和二十六年三月号から、病中の虚子に代って「ホトトギス」を主宰するようになった。久しぶりに旧友と逢って囲んだ河豚ちりの仕上げに飲んだ鰭酒が利いて、懐旧談に花が咲く。例句三の水原秋桜子(昭和五十六年没)は下戸だったと見えて、御自分の『現代俳句歳時記』(昭和五十三年)には「熱燗」も「鰭酒」も登録されていない。だが昭和二十七年に医業を廃して吟遊詩人となり、九州方面にも旅しているので、この句は河豚ちりの俳席での所見であろう。だから鰭酒の酔いを言わず、視覚的に抒情しているのである。(「酒の歳時記」 暉峻康隆編)
酒屋土倉
次に酒屋が酒屋営業により幾何の利潤を獲得し得たかに関しては、これを算出すべく商業帳簿の現存せざるため、不可能のことに属するのである。しかしながら、当時の日記を見るとき、「一献」「燕酔」等酒宴に関する記事が至るところに散見せる点よりして、当時の酒需要の程度が相当の額に上ったと考えられるから、酒屋の利潤もまた莫大なものであったと推定せられる。既にして室町時代に於ては、醸造酒屋の以外にも、これより酒を購入し、消費者への小売転売を目的とするいわゆる「下売所」「請酒屋」「小酒屋」なるものが発達し、酒屋の経営形態の上に多少の進展を見せるに至ったのである。(3)しかしながら、その営業によって蓄積せる資本を、商業資本として経営組織の上に大なる進展をもたらしめんがためには、当時の社会経済組織は、あまりにも多くの制約に満たされていた。すべての商業は立場即ち商品販売地域に於て、また商品販売種目に於て、いわゆる座法によって制限せられ、自由なる活動と発展とを阻止せられていた。酒屋はここに於てその資本を転用して、中世金融界へ進出し、当時に於ける金融界の覇者たるの地位に登ったのである。当時に於ける金融業者は、主として土倉の名称をもってよばれ、酒屋とは純粋の意義に於て別個の存在であったが、酒屋がその蓄積せる資本をもって、酒造業の傍ら、金融業を営むに至ったため、中世に於て一般に酒屋土倉と一連に呼称せられるように至ったのである。(「中世酒造業の発達」 小野晃嗣)
推はちがうた
○堺の港から、作城(いち)という座頭、讃岐に渡る。ころは霜月、寒夜の旅なのに、船の広間にうす衣で寝ることをいたわって、局の方から、酒の燗をいかにも熱くし、十一二の女房に持たせてやり、「これをふすまに着てお寝みなさい」と言ったが、作城は本当の夜着と思い、年がよっているから、起きふすのも大義なので、寝たまま、「ついでのことに、着せて下さい」と申したので、「はい」といって、直接頭へかけたとは。(「醒酔笑 推はちがうた」 安楽庵策伝 小高敏郎訳)
石川弥八郎賞
ところが平成五年の夏ごろ、電話がかかってきて「石川弥八郎賞を差し上げたいが受け取ってくれるか」という。醸造協会の表彰は三つの部門があって、この「市川弥八郎賞」というのは酒や酒造技術の専門以外の分野で表彰されるものだ。まずびっくりした。だがうぬぼれ心が素早く働いて、もしやこれまでやってきた酒蔵の設計に対して褒めてくれるというのかなと思った。「いったい何の理由で賞をくれるんですか」と聞いた。「篠田さんが吟醸酒についていろいろやってくれたことに関してですよ」という。吟醸酒で賞をもらえるのか、「それじゃかたじけなくいただくことにします」と答えた。せっかく賞をくれるというんだから、これを肴に飲むのもいいんじゃないか。そこで石川賞のこれまでの受賞者を調べてみた。コチコチの酒の専門的な功績ではなくみなユニークな功績ばかりだ。蒸し上がった米を強制的に冷やす機械の発明者、地酒ブームを巻き起こした酒問屋などもいる。それに比べると、私は酒を飲んで表彰されたのだと一人笑うしかなかった。(「「幻の日本酒」酔いどれノート」 篠田次郎)
いなだひめ【稲田姫】
素戔嗚尊が簸川上で、八岐の大蛇を退治して得た奇稲田姫。手麾乳、脚麾乳(てなづち、あしなづち)と云ふ夫婦の女で、大蛇の生贄としてあはや生命を捧げんとした処を尊に助けられたのである。尊はこの時、大蛇の為に八塩折の酒を造り、八つの酒甕に入れて姫を其傍に置き、大蛇を釣出して遂にこれを退治したと伝へられる。
既の事 酒のさかなに 稲田姫 大蛇の酒の肴-
稲田姫 こはい中にも 酒鏡 水鏡と云ふ処を(「川柳大辞典」 大曲駒村編著)
梵妻
久しう檀那寺へゆかぬと参る道にて、寺の小野郎(こやろう)が重箱を風呂敷包にしたを提げて帰るに逢ひ「今そちへゆくが、その包んだ物は何だ」「これは大事の物。御目には掛けられませぬ」「ハテおれは格別懇(ねんごろ)な旦方(だんかた)、見せてもよい」「そんなら黙つてござりませ」と解いて見せれば、蒲鉾(かまぼこ)」、酢章魚(すだこ)、切身、その外色附旨(うま)いものだらけ。「よし/\、何もいふ事ではない。先へゆけ」さて墓詣して和尚に対面。おしきせの肴で盃の廻る時、「和尚様、この肴や吸物では飲めぬ。彼をお出しなされ」「寺にはこれより外の御馳走はない」「ハテ、見かぢった事もござる。余人とはちがひます。私にはおかくしには及びませぬ」「さうあれば出しませふ。コレ出てお近付きになりやれ」(飛談語・安永二・寺詣)(「江戸小咄辞典」 武藤禎夫編)
豆腐田楽
「江戸三白」という言葉がある。これは江戸っ子が大好きな三つの食材で、白飯と大根、豆腐のことだ。三白に加えられた豆腐の人気は、天明(てんめい)三年(一七八三)に『豆腐百珍』という本がベストセラーになったことでもわかる。この本を書いた祖谷学川(そだにがくせん)の本業は篆刻(てんごく)家で、料理家でない人の料理本である。百品の料理を「尋常品」や「奇品」など六つのカテゴリーに分けて紹介しているのが、一種の仕掛けになっている。もちろん、オカラ料理も出てくる。オカラを炒(い)って醤油で味を付け、それをふりかけにしたり、焼き魚にもかけて食べたりしていた。京都の八坂(やさか)神社の楼門と大鳥居の間に、西側に藤屋、東側に中村屋という茶店があった。京の水茶屋の起こりとされるこの「二軒茶屋」は、薄く切った豆腐を二本の竹串に刺し、軽く焼いて味噌をつけた豆腐田楽で知られていた。豆腐は中国帰りの留学僧が持ち帰ったもので、寺院の多い京都の方が豆腐作りには一日の長があったのだろう。江戸の豆腐は固く、京の物はやわらかく、味では京都が優っていた。享和(きようわ)二年(一八〇二)に滝沢馬琴(たきざわばきん)が二軒茶屋の豆腐田楽を食べており、京、大坂、、伊勢をめぐる旅の記録『羈旅漫録(きりよまんろく)』に「祇園(ぎおん)豆腐は真崎(まさき)の田楽に及ばず」と素気(そつけ)ない感想を記している。真崎とは、隅田川右岸の白鬚橋(しらひげばし)北の石浜(いしはま)神社内にある真崎稲荷のことで、境内に田楽茶屋が数軒あった。馬琴の食べた祇園豆腐は、豆腐を炙(あぶ)って白味噌の木の芽味噌を塗り、もう一度火にかけたもので、馬琴はその味噌が口に合わなかったらしく、「白味噌といふもの塩気うすく甘ッたるくしてくらふべからず。田楽へもこの白味噌をつけるゆえ江戸人の口には食ひがたし」とし、味が濃い赤味噌を好む江戸っ子の馬琴には物足りなかったのだろう。鎌倉河岸の豊島屋の田楽は、大きくて安いと評判だったが、旨いとされた真崎稲荷の田楽を食いながら「豊島屋の方が大きくていい」などという野暮な男もいたようで、江戸の庶民には値段と大きさから豊島屋の田楽が好まれたようだ。
(「江戸の居酒屋」 伊藤善資編著)
ワインのことわざ
49.燕麦で栄養をつけた馬、干し草を与えられた牛、そして葡萄酒で力を得た男は抵抗力がある
葡萄酒は「百薬の長」。厳しい労働には不可欠の薬だ。 スイス
50.ワインは年寄りのおっぱいだ
子どもに乳が必要であるように、ワインは年寄にとってなくてはならないものだ。 スイス
乳とワインは吐き気をもよおさせる
乳を飲みすぎた赤ん坊の様から、ワインの飲み過ぎをたしなめていることわざと思われるが、「水と油」のように相いれない二つのものを言ったものとも考えられる。 スイス
52.乳とワインはよい結末を生まない
上のことわざと同じ戒めと思われるが、こんなに乳が用心されているここが不思議である。 スイス(「世界ことわざ大事典」 柴田・谷川・矢川)
日本の酒 草野心平
去年私はミラノやポンペイで日本酒をのみ、今年はホノルルでその独特な味をたのしんだ。
大きなエイ型の北の島から。
開聞岳(かいもんだけ)の見える海辺の村まで。
ニッポン全土に。
ニッポンの酒はゆきわたる。
舌の上からまるまっておちる。
琥珀の液体の。
もやのような芳香と芳醇(ほうじゆん)と。
よき哉。
讃(たた)うべき哉。
古事記(こじき)の人々
その独自な発明の知恵。
その陶然(とうぜん)と浩然(こうぜん)と歌と踊りを。
現代の。そして未来の友よ。
賞(ほ)めたたえよ。
美しいニッポンの。
ニッポンの酒を。(「酒の詩集」 富士正晴編著)
れろれろ
ひどく酒に酔っていたり、緊張していたり、あるいは幼いために不慣れだったりして、言葉や態度が不明瞭である様子。「いかにもレロレロの酒酔い状態」(朝日新聞94・1・25)、「僕は、指輪を口に放り込み、舌の裏に潜ませてから、カメラの前に跳び出した。台詞がレロレロしているように聞こえたとしたら」(朝日新聞夕刊02・9・25)。なお、同じような意味で「ろれつが回らない」という表現もあるが、これは雅楽における音階名「呂律(りよりつ)」が不明瞭な様子からとされ、「れろれろ」とは無関係。◇参考 笛の形容として用いられた例もある。「横笛の声がれろれろ、ひーひゃらりと面白く聞こえて」(*田山花袋『重右衛門の最期』) 江戸時代、幼児をあやす様子を、「れろれろ」と表すことがあったが、泣く子を黙らせるのに、「遼来遼来(りようらいりようらい)(=怖い魏の武人の遼が来るぞ)」と脅したのが訛って「れろれろ」となり、そこからきたという。また、室町末期の『*日葡辞書(につぽじしよ)』には「れろれろ」に音の似た「ろりろり」という項があり、「恐怖などのためにおちつかないさま、またはうろたえるさま」という説明がなされている(高崎みどり)
❖田山花袋 小説家。江見水蔭に師事。明治三九年、博文館発行の『文章世界』の主筆となる。翌四〇年『蒲団』を発表、私小説の出発点となる。作品『重右衛門の最期』『田舎教師』など。(一八七一 一九三〇
❖日葡辞書 一七世紀初頭の、ポルトガル語で説明した日本語辞書。イエズス会の宣教師によって成る。室町末期の口語を中心に方言、文書語、歌語、女性語など、三万余語を収録。慶長八~九年(一六〇三~〇四)刊。)
三白酒-さんぱくしゅ
酛米・麹米・掛米の三者を精白して造った酒。原料米のすべてを精白して用いる点では、「三白」も「諸白」も同じである。別に、左掲のように「水白」を含めていうこともある。▼四部稿に三白酒ありて、米白、麹白、水白によりて名つく、我国の諸白も三白なれども、水を云わずして、諸白と云ふ-「昆陽漫録」◎『百家説林』(「日本の酒文化総合事典」 荻生待也編著)
食物年表1700-1800
1732・吉宗が曲水宴を再興する
1740・伊丹剣菱が将軍御膳酒に指定される
1782・甘藷焼酎が現れる
1785・諸国酒造実績の調査(天明稼高)、灘から江戸への移送量が36万樽となる
1788・密造酒厳禁を布告(「日本史分類年表 食物年表」 桑田忠親監修)
玉山已ニ倒レテ
その前夜、石川淳氏は、だいぶ酩酊の模様であった。かつてその人に贈った私の詩に、玉山已(スデ)ニ倒レテ猶オ杯ヲ挙グ、といい、酒裏ニ真有リ沈酔該(ウベ)ナリ、というような事態にあった。翌朝、東京の宿を出て、ある人のところへ立ち寄ると、さっき石川先生から電話をほしいとのことでしたと知らされ、ゆうべの沈酔についての御挨拶かと思って電話すると、それもあったが、それからねと、いつか書いた羅漢の言葉、自然に天地のへだたりあるごとく、「人ニモマタ君ハタットク、臣ハイヤシキゾ」、出所はわかったかと、問われた。いやまだだというと、小島祐馬先生の「中国の社会思想」、一〇四ページを見なさい、と教えられた。昨宵の沈酔にはふさわしからぬ話題として、今朝の親切な電話となったのであろう。(「帰林鳥語」 吉川幸次郎)
花見 はなみ
古い時代には花見といえば梅を指したが、平安時代以後は観桜になった。当時はもっぱら貴顕の行楽とされ、山野に酒肴を携え、詩歌を賦したものである。桜よりも酒興になった庶民の花見は元禄以降のもので、会社や近隣が誘い合わせて行楽として盛んなことは、日本の伝統的行楽の一つである。
花見酒隣の茣蓙が注ぎにくる 中庭卓也
からみ役とめ役もいる花見酒 松本舎人
さかずきにひとひら浮いた花の宴 佐々木芳正
値上げどうあろうと花に酒うまし 矢須岡 信
春風によき酒徒たらん花の下 高木柳風
中企業長屋の花見ほどの宴 新海照弘
お花見のあとは野となれゴミの山 佐々木れい女(「川柳歳時記」 奥田白虎編)
ぬけ酒と収税さん
とんとむかし 明治の頃のことよ。戦争のあと、政府は金に困って、酒にどっさり税をかけたそうな。そこで庶民は、税を飲むような酒が飲めるかとばかり、さかんにぬけ酒-つまり密造酒を作ったと。ところが、ぬけ酒を飲まれると政府は収入がはいらん。そこで収税さんと呼ばれる役人が、躍起(やつき)になって密造酒の摘発(てきはつ)にやってきたそうな。この収税さんとぬけ酒づくりの人たちの間で交わされた、面白いかけ引の話が県下のあちこちに残っておるが、今日は須崎と窪川の話をしてみようかのう。ある日、ある時のことよ。須崎の池の内のある農家へ、収税さんがやってきたそうな。ぼっちり留守番をしよったおばあさんは(ははーん。こりゃ収税じゃのと感づいたと。収税さんは、たいてい二、三人で連れだってくるき、じきにわかる。つかつかと、家の庭に入ってくると「ばあさんや、ここな辺に酒を作っちょる所をしらんかのう」と聞くと。お婆さんが「ああ、わたしんくも作っちょりますが」「どこへ作っちょるぜよ」「そりゃのうし、とっとの(はるか)奥のやぶの中ヘ作っちょりますらぁ」こう答えたそうな。収税さんは(こりゃ、まっこと正直なおばあさんじゃよ)と、めっそう感心して、精一杯、やさしげな声をだしていうたと。「ばあさんや。そこへわしらを連れていてくれんかや」「あいあい、よござす」お婆さんは、先に立ってひょこひょこ行きだしたき収税さんは、しめたと胸をわくわくさせながらついて行った。やがてお婆さんは「ここが、わしんくのやぶじゃがのうし」と、手をふりまわすと。ほんで収税さんが合点(がてん)いかんという顔できいた。「どこへ作っちょるぜよ」「どこち、このやぶはみんな私んくのがじゃけん、どれでもええがへ(のへ)、しるしをしてつかあされ」収税さんはたまげて、「ばあさんよ。おまさん、そりゃなんの事ぜよ」「なんのことち、おまさんら、竹を買いに来たのじゃろ」「竹じゃない。酒を作っちょりゃせんかと問うたに」「ありゃ、酒のことかのうし。わたしゃまた、竹というたかと思うて。こないだも二、三人つれこって(だって)竹買いがきたけん、また竹を買いにきたかと思うたわえ」と、まじめくさってお婆さんがいうと。ほんで収税さんは苦笑いして、怒ることもできんと、すごすごと引きあげてきたそうな。(「土佐の民話」 市原麟一郎編)
酒銘江戸一の始め
文政六七年の頃、新川(しんかわ)*へ酒積み込みしところ、そのうち無銘の酒おびただしくありしかども、銘なければ買う人さらになし。ここに本郷追分に酒肆高島屋長右衛門と云えるもの、この酒を残らず買い入れて、この酒に銘を号(なづ)けんことを、予が生父理斎翁の友なる馬島氏に酒銘を撰びくれと乞いしかば、家翁馬島子に代りて筆をとって、 ○江戸一その文に ことし新製の酒あり、これが銘乞われけるにぞ、直様(じきさま)左のごとく記し送りぬ、さりとてはおこがましき名なりと云う人あり、これ己れを高うするところにあらず、また他と一二を争う心もあらず、またこの党ならぬ三国一の醴(うまざけ)、日本一の黍団子(きびだんご)に敵せんとにもあらず、古市、今市、四日市などの地名を慕うにもあらず、こは座頭の亀一鶴一などの唱えに擬するものなり、それをいかにと云うに、配当の一名より、勾当(こうとう)*、検校(けんぎよう)、惣録(そうろく)*にも至り、それ一つは万物の始めなり、これこの酒を売り始めてより、日にまし夜にまし月にまし、ますます売ります買いますとて、升のはかりも限りなく、酒の誉れも惣録にて、跡引き上戸(じようご)の長々と店繁盛は幾よろずようもう酒と祈るものなり。 猩々(しようじよう)も酒のうまみは江戸一と のめや唄えや汲めやくめくめ この文によりて江戸一と号けて売りはじめしところ、存のほか評判宜し、そこでも江戸一、かしこにても江戸一江戸一と云う、今は酒のみならず醤油にも江戸一ありて高島屋の別製とはなりぬ。
新川 現中央区新川一丁目附近に運河あり新川と称す、河岸に酒問屋あつまりし事、第二次大戦前まで続く。 勾当 盲人の官名なり。検校に次げり。 惣録 盲官の名にして検校の上に立ち盲官を統括す。(「塵塚談 俗事百工起源」 小川顕道 宮川政運 神郡周校解説)
信州酒と注文のコツ
ここ二年ほど集中しているのは私の故郷、長野県の酒だ。昔はたいしたことはなかったが、「夜明け前」「佐久之花」あたりから信州酒ルネッサンスのように名酒が生まれ始め、今や新潟、福島、長野は新酒鑑評会不動のベストスリーとなった。私の姪の夫は大の日本酒好きで、送ってくれる酒から最近の信州酒の質の高さを知り、彼がなじみにしている上田の信州酒専門店「地酒屋 宮島酒店」に注文するようになった。一本取り寄せるだけでは送料がもったいないから「まとめて注文」するのがコツ。私はいつも一升瓶六本。届いた大きなダンボールを開けて六本が並んだ豪勢さ。さあしばらく楽しめるぞとわくわくする。(「家飲み大全」 太田和彦)
柳の酒
この"柳の酒"というのは、五条坊門西洞院の南西面に店をかまえた作り酒屋で、当時の室町幕府に将軍用として、毎月六十貫の美酒を献上していた。将軍義政などというのは、酒ばかり飲んで、いつも酔っぱらっていたというから、きっと、この六十貫の酒の中の大半を飲みくらしていたのであろう。江戸時代に将軍が飲んだ酒は、伊丹の"男山"と"剣菱"にきまっていたが、そのころは"柳の酒"であったのである。将軍などというものは、それほど舌が肥えているはずはない。自ら主体的に食べ比べ、あるいは飲みくらべて、そしてこれがよい、あれがよいと決めるのではないからだ。本当の食通とか酒通というやつは、如何なる労苦も惜しまないで、その美味を自ら探求する努力を惜しまない人間のあいだから出てくる。だから、将軍が愛用したといったところで大したことはないかも知れないが、しかし、御膳役というのがついており、一流の料理人がついている。これがえらぶのであるから、将軍家愛用といえば、いちおう信用はしていいだろう。さきの頼山陽も、伊丹の"剣菱"をもっぱら愛用したというから、将軍と同じ酒だった。だから、室町時代の後期は"柳の酒"の全盛時代で、値段も、普通の酒の二倍くらいはしたらしい。そのころ、新酒よりも古酒の方がいくらか値段が高かった。古酒といっても、百年ものとか三十年ものといったのではない。当時は、夏と冬との二回に醸造していたが、せいぜい一年か半年古いものが古酒だった。その古酒が、普通の酒屋で売っているのは価百文につき五杓、柳の酒はそれが三杓だったという。枡ではなくて、柄杓ではかって売るのである。新酒の方は、双方ともに百文につき一杓ずつふえる勘定になる。つまり、六杓と四杓。だから、当時の公家や上級侍のあいだでは、もっぱらこれが贈答品として珍重された。しかし、そうなれば偽物もまたまかり通るので、これが樽には、六星紋がえがかれ、それの盗用が禁止されたということである。"柳の酒"屋は、姓は中興、名は四郎衛門を名のっているが、この名の出所は、恐らく最初に売買に樽を使ったところからきたものであろう。そのころの酒は、陶製の壺のなかで醸造したもので、普通二石から、大きいのは三石入りくらいであった。(「京都故事物語」 奈良本辰也編)
振り酒
なんだかんだとわれわれが、得体の知れない実験を続けているのを聞きつけてか、各地からいろいろな振り酒情報が届くようになっていた。
・買った酒を、車の中にうっかりと置き忘れたまま、知らずに何日も走ってしまった。どうせ駄目だろうとあきらめ顔で飲んでみたが、驚いたのなんの、以来車のトランクは動く酒庫と化している。(セールスマン・京都)
・江戸時代に、灘(なだ)の酒が陸路より海路が好まれたという話はほんとうだと思う。自分の漁船にいつも酒を乗せておくが、やはり日にちが経ったほうがはるかにうまい。(漁師・気仙沼(けせんぬま))
・酒はよく振ったほうがうまいというのは事実であるジャズ喫茶を営業しているから、店のスピーカー-JBL-4043は格好の酒棚である。(ジャズ喫茶経営者・鎌倉(かまくら)市)
・フランスでも、連中がよくワインを振っているのを見かけた。(詩人・東京都)
・ヨーロッパではいまでも酒樽を船に乗せ、長く航海させては特別品として売っているようだ。(酒マニア・東京都)
等々、やはり蛇(じや)の道はなんとやら、生活の知恵というのはたいしたもので、振り酒実行者は各地に点在していたのである。(「うまい酒は、なぜうまい」 浅倉俊博)
定年書店
多少の知識は身についたとはいえ、実験を主とする自然科学の研究者にとっては、実験の場を追われることは、手足をもがれるようなもので、木から落ちた猿のたとえに等しい。しかし、そんなぜいたくより、まず一家の家計である。そこで考えついたのは、長年買いだめて置き場に困っている駄本のたぐいをもって、元勤務先の学校の付近に古本屋を開業しよう、というアイデアである。これについてはすでに、戦時中に知人の東大教授が範を示されたことがあった。枕頭に本をつみあげねば眠れぬ店主は、買い上げた本を催眠剤がわりに役立てたのち、店頭に並べる。店には学生や教師たちが寄って来るはずであるから、気が向けば後輩諸君の勉学の一端にも役立ってやることができる。時にはなつかしい連中がまいこんでこよう。コーヒーや酒がなくてはつまらない。そこで店の奥にはイスとテーブルを用意する。酒は長年の研究と関係深いのだから、寄贈も少なくなかろう。ささやかな恩給で餓死する心配はなさそうなので、おおもうけする必要はないのだから、客には注文をつける。「酒を飲んで放歌高談して他人に迷惑をかけることはいっさいいたしませぬ」という誓約書を印刷しておき、これに署名した者にのみ酒を出す。約束を守ってくれれば、何時までねばって飲んでいてもいっこうにかまわぬ。日々是好日ではなかろうか…。退官直後、ある新聞社から原稿を依頼されたので、さしあたっての心境としてこのようなことを書き送った。世間には親身になって考えてくださる人もあるもので、さっそくどこに適当なあき店舗があるから世話しようとか、開店のあかつきにはぜひ私を雇って下さい、などの手紙が舞いこんできた。ありがたい話である。それにもましてありがたかったことは、カルピスの三島海雲翁から、身の置き場所に困っているようだからおれの所の研究所の室を貸してやろうとか、生活に困るようだから浄財を寄付してやろうとか、親切な申し出をいただいたことである。おかげで、定年書店の開業が見送りになったばかりでなく、家内などは大学時代より暮しが楽になったと、ありがた涙にむせんでいる。お布施を受けているようなもので申しわけないが、やはり坊さんには縁があったのかもしれない。(「私の履歴書」 坂口謹一郎)
まんぢゆう【満仲】六孫王経基の長子、多田満仲。(ただのまんぢゆう参照)
まんぢゆうの子が酒呑をぶっつぶし 頼光の鬼退治
まんどりあし【萬鳥足】千鳥足の甚だしいものゝ戯称。千鳥の十倍だから萬鳥だと云ふのである。
づぶ七が萬鳥足になつて来る づぶ六を越して
みかはざけ【三河酒】三州酒の事。(さんしうざけ参照)
鷲津丸根は三河酒に酔つたやう 家康の武勲
三河酒四天で擔(かつ)ぎ山へ行き 頼光大江山入り歟(「川柳大辞典」 大曲駒村編著)
久里浜病院
日本で唯一のアルコール専門病院・神奈川県にある国立久里浜病院も、一九六四年の東京オリンピックを契機につくられた。外国からのオリンピック観光客の眼に、酔っぱらいが街に溢れている光景は好ましくないものとして映るのではないかという危惧がその理由であったという。日本の経済が急カーブを描いて上昇するのと国民一人当たりのアルコール消費量の増大とが比例していくのだ。さらにその五年遅れぐらいでアルコール性肝硬変の受診者、死亡者が増えていく。(「依存症」 信田さよ子)
池田酒
現在の大阪府池田市産の酒も伊丹鴻池の酒と十七世紀の江戸市場を争っていた。池田史談会編『池田酒史』によれば、池田の衆が『大坂御陣之節 闇峠 御陣中へ池田名酒奉差上候』とあり、兵粮や軍資金も届けていたようで、その見返りとして慶長十九年(一六一四)十月、江戸へ酒を運んだときの上納金免除の特権をあたえた御朱印状が池田へ下付されている。それ以来『摂津名所図会』(一七九四~九八)に「朝の市 暮の市とて商家の賑わい特に酒造りの家多くありて 猪名川の流水を汲て造る味ひ美にして官家の調進とす これを世俗池田酒と賞して名産とす」とあるほどまでに発展した。寛永年間(一六二四~四三)になると、池田の満願寺屋はこれまで馬で運んでいた酒樽を菱垣廻船(図2)に積んで江戸へ運び、大量輸送の道を開いた。貞享五年(一六八八)井原西鶴は『日本永代蔵』で、大和龍田の酒造家が親戚の反対を押し切り、百両の金を元手に江戸呉服町で造り酒屋を開いたが「鴻の池 伊丹池田 南都 根づよき大木の杉のかおりに及びがたく」四斗樽の菰を被って故郷へ逃げ帰った話を採り上げているところからみても、当時の江戸でこの四産地の酒がいかにもてはやされていたかがわかる。元禄十年(一六九七)初版の『本朝食鑑』にも「和(大和)の南都および摂(摂州)の伊丹池田鴻池豊田等の処 諸白を造り難波(大坂)江都(江戸)に運転す 最も極上品也」とある。(「江戸の酒」 菅間誠之助)
詩酒徒
アルカイオスにはまた、 酒と、愛い酌童(こども)よ、それに真実は… なる小さな断片があり、その意味するところをめぐって学者たちがあれこれと詮索し、議論を重ねている。密かに愚考するに、酒と真実とを併置させているところから推せば、この詞句は酒中にこそ人生の真実ありとする観念をあらわしたものかもしれない。とすればこれはおのずと「酒中有真」(陶淵明)、「酒中有全徳」(権徳輿)のごとき中国の詩人の一節を脳裏に喚び起こさずにはおかない。これに連なるもので、 酒はこれ人間の明鏡(かがみ)なれば… というよく知られた断片がある。この詞句にもまた孟郊の「酒是古明鏡」に通じるものがある、と見るのは必ずしも酔人の僻目ではなかろう。いずれの国でも詩酒徒の考えることは同じらしく、詩酒を詠った東西の古詩に通い合うものがあるのは、興味深くまた嬉しい。(「讚酒詩話」 沓掛良彦)
淡白を上
一〇八八 酒は味の淡泊なのを上とする。辛口はその次で、甘口のものは最も下級である。清州従事(酒名)は以前に名声をほしいままにしたが、現在伝わっているのは、色も味もことのほか劣っていて、とても平原督郵(酒名)に及ばない。(1)しかし、従事という名は清州に斉郡があるのに因んで、借りて名としたのであって、いまはそのまま清州の酒にその名をあてているのであるが、おそらく作った人の本意ではあるまい。
(1)清州従事は… 『世説新語』「術解篇」にみえる桓温故事による。桓温の主簿に利き酒の名人がいて、酒が手に入ると、いつも味を見させることにしていた。よい酒のときは「清州の従事」であるといい、悪いときは「平原の督郵」ですといった。清州には斉郡があり、平原には鬲(かく)県があり、従事とは生(臍(へそ))まで届くという意味であり、督郵とは鬲(かく)(隔膜)で止まるという意味であったという。清州は今の山東省清州市のあたりに役所のおかれた州の名。従事は州の属官。あとの平原は今の山東省平原県の西南に役所のおかれた郡の名。督郵は郡の属官で、郡内の諸県の行政を監察した。(「五雑組」 謝肇淛 岩城秀夫訳注)
味わいのバリエーション
そこでさまざまなタイプの日本酒の香りや味わいの特徴を端的な単語で捉え、AからKまでの11のタイプで分類してみたのが口絵のチャートです。AからJまでの10タイプはその流れに沿って、若い酒質から熟成感を伴ったほうへ、また食前、食中、食後と飲み進めていくうえでの順序や、冷や、燗といった適切な温度帯との関連性も示しています。味覚には個人差があり、酒の飲み方も嗜好性の強いものではありますが、味や香りの特徴を分類してみるということは、それぞれに合わせた楽しみ方を整理するということにもつながると思います。では11のタイプについて、個別にその酒質の特徴や飲み方を探ってみることにしましょう。
A ライト(Light)タイプ 酸の存在に裏付けられたアルコールの低い軽いタイプ-
B フレッシュ(Fresh)タイプ 口あたりのみずみずしいフレッシュなタイプ-
C フルーティー(Fruity)タイプ 華やかな果実用の香りをまとったフルーティーなタイプ-
D ドライ(Dry)タイプ すっきりとしてスマートな辛口タイプ-
E ソスト(Soft)タイプ 雑味の少ないソフトな甘辛中間型タイプ-
F メロウ(Mellow)タイプ ふくよかな旨口タイプ-
G スウィート(Sweet)タイプ 濃厚な甘口タイプ-
H フルボディ(Full-bodied)タイプ 醇味にとんだコクのあるタイプ-
I リッチ(Rich)タイプ 酸味や苦味を沈ませた奥行きのあるタイプ-
J エイジド(Aged)タイプ 深い熟成感のあるタイプ-
K エクストラ(Extra)タイプ どれにも属さない番外タイプ-(「日本酒のテキスト1」 松崎晴雄)
節度ある酒
医師の芝田祐祥は、「酒は素早く気血を廻らすので、これに過ぎたるものはない。血脈を通じ精神を盛にし、脾胃を温める。少しずつ飲むべし。多く飲むべからず。上戸は三、四、五盃、下戸は半盃に限るべし。こうすれば極上の良薬」となるが、酒を飲む場合は「夕飯、夜食の後少しずつ飲むべし。今の人、寝酒といって寝しなに酒を飲み、酔に乗じて熟睡するのは心神を傷(いた)める大毒」と主張している(『人養問答(じんようもんどう)』正徳五年)。酒の効用を認めながらも、寝酒を否定する意見もあった。 ○「長生の補薬寝酒に五夕づつ」(柳一五六 天保九~十一年) といった句も詠まれている。五夕(勺)は約九〇㏄である。(「晩酌の誕生」 飯野亮一)
宮城県名取郡秋保村
69酒盛の時にとくに定まった食法がありますか
盃はどういう順に廻しますか。酌は誰がしますか。食物はどういう順序に出されますか。廻されるものを各自が随意に取りますか、それとも一定の人が分配しますか。料理は特定の食器に盛られますか。
○座席は正面が一番上の人。左右と相互になって行く。
○盃は祝儀の時は順々に廻すがほかはやらぬ。
○酌は儀式の時は一定の人が出るが、ほかは不定。食物は膳をならべて坐る。分配は女がやる。
70酒盛の後でさらにアト祝イとかウチ祝イというようなことがありますか。それを何といいますか。残りものはどうしますか。
後祝いとは、御祝儀の後に、若い男女が入り交じってやるもの。大義(たいぎ)振舞などは、媒酌人・料理人その他活動した人たちを慰労する意味の振舞。
酒盛の時は二次会という。御祝儀の時は後見(あとみ)の祝儀という。
○御祝儀の時は、残り物は包んで各自に渡す。
71酒盛に参加する人はどういう人ですか。酒盛の性質によって違いますか。男ばかり、女ばかりという場合がありますか。それはどんな場合ですか。参加すべき人がしなかったらどうしますか。
酒盛には気持のあった者ばかり男女一同でする時と、集会の時やる場合とある。
○参加するべき人がしなくても、しない人の数より多い時はする。
72共同食事、酒盛の費用は誰が負担しますか。村、組ですか。各自の負担ですか。あるいは物を皆が持ち寄りますか。
酒盛は各自の負担。
88醸造業者でなく,濁酒が造られていましたか。それはどんな時に造られたでしょうか名称は何といいましたか。村祭りの時には今でも造りますか。どうしてつくりますか。芋酒、焼酎など造られましたか。これらの酒類は個人個人で造りましたか、村とか組とかが共同で造りましたか。女は関与しませんでしたか。
昔は造った。それをドブロクといった。
89一年のうち酒を飲む機会はどれくらいありますか。平均一戸当たりどれくらいの量を用いますか。どんな種類の酒ですか。毎日常用する人が何人くらいありますか。飲酒家と酒嫌いの比率はどれくらいですか。大酒家というのはどれくらい飲みますか。軽い程度の酒の肴には何を用いますか。
年に十五回ぐらい。普通の年では二、三斗。
○飲酒家と酒嫌いの比率は五分五分。
○大酒家は一升ぐらいから(一回につき)。
○軽い程度の酒の肴は漬物。(「日本の食文化」 成城大学民俗学研究所編)
ムスタファ・ケマル
トルコ人は数百年前から「ラク」と呼ばれる蒸留酒を愛飲している。国民酒としての位置づけだ。薬草入りのブランデーの一種で、フランスの「アブサン」に近い。アルコール度数が五〇度もある強い酒だが、(ムスタファ・)ケマルは後に大統領になり、トルコ一忙しい男になっても、この酒を一日一本(七〇〇cc)は少なくとも飲み干した。強い酒を飲みまくり、睡眠時間は四、五時間、朝七時には起床して政務に励む。特に晩年は酒量は増し、ラクを毎晩二本以上飲み、昼飯は簡単な豆料理、夕食は前菜のようなものしか食べなかったというから、どう考えても身体に良いわけがない。一九三八年一〇月、臨時の大統領官邸としていたイスタンブールのドルマバフチェ宮殿で執務中に倒れる。病状は一時、奇跡的に回復に向かうが、一一月一〇日に臨終を迎える。享年は五七歳。当時としても早すぎた死だった。(「政治家の酒癖」 栗下直也)
新夕刊新聞社
まだ新橋から芝に掛けて一面に焼け野原の中に、闇マアケットが出来てゐた頃で、両側がやはり焼け野原の電車通りを新橋から浜松町の方に行くと、左側に一軒の焼けビルがあり、それが新夕刊新聞社だった。ビルの中も焼けたままで、それでも一階に輪転機があり、その脇の小さな部屋で林(房雄)さんに会つた。本の話はすぐに片付いて、それから林さんは、飲まうと言つた。まだ飲むといふことが決死的な行為でなければ、非常な贅沢だつた頃で、林さんが新聞社に持つて来てゐる酒が又、何でも入るやうになつた今日でも、滅多にない種類のものだつた。白乾児(パイカル)といふ高粱で作つた中国の強い酒に薔薇の花の匂ひを染み込ませたもので、それが甕に一杯入つていた。つまり、それからはこの酒が飲みたくなれば、新夕刊新聞社に行けばよかつたのである。林さんは素人の実業家が新聞を一つ手に入れて勝手が解らなくて困つてゐるので、手伝ひに頼まれて行つてゐたらしい。初めのうちは嘱託の形で、他にも林さんにくどかれて手伝ひに来てゐる文士や漫画家が多数ゐた。小林秀雄、永井龍男、今日出海、横山隆一、泰三、清水崑、田河水泡、さういふ諸氏が嘱託で来てゐて、林さんがどこかで嗅ぎつけて手に入れたその酒がある間は社に集まり、甕が空になつてからは、近所のに飲み屋に行つて飲んだ。(「世にも不思議な新聞社の話」 吉田健一)
あてこすりの歌(全二十五篇中より)
2
北の店の酒は
大杯でのんでも酔わぬ。
ジュンニー・ラマの(妹の)ムー・オヒンは
ただでくれても貰わぬよ。
南の店の酒は
半斤飲んでも酔わぬ。
若い小さなムー・オヒンは
ただでくれても貰わぬよ。
ぶちの馬があったとて
乗るに耐えるは少ないよ。
若い小さいムー・オヒンは
ただでくれても貰わぬよ。
何人もの殿(ノヨン*)がのぞんでも
かなったjことはなかったよ(原注一)。
ウーシン殿(ノヨン)の大公爺(ダー・グン・イエ)が
貰うと言うたは本当よ。
若い小さなムー・オヒンを
ずいぶん皆がばかにした。
まんざらでもない公の殿(ダン・ノヨン)が(原注二)
ばかにもせずに貰ったよ。
薄鹿子馬(サーラル・モリ)(原注三)があったとて
一ヵ月行程の乗馬。
評判のよいグン・ノヨンに
ぐずぐずせずに稼ごうよ。
二人の人を仲にたて(原注四)
羊を殺して来た(原注五)のだよ。
二日の間話しあい
二つ返事(註一)で決まったよ。
-「ゆるゆるととのお話です(原注六)」
-「つまらぬことをおっしゃって(原注七)」
心のはやるムー・オヒンは
明日もまたず(原注八)に押しかけたよ。
原著者注 原注 一 …なたったよ これは皮肉である。 二 殿 公の称号を持つ高官。 三 薄鹿子馬 くわしくは、「灰色から明るい鹿子色までの地色で、尾とたてがみは灰色がかった黒、背骨にそって黒い筋がある馬」。 四 仲にたてて パイルジュール公(グン)がつかわした仲介人のこと。 五 …殺して来た 仲介人は婚約の際に娘の家に、しきたり通り、羊のシュース*を持って来る。 六 …とのお話です これは仲介人の言葉、「おいそぎになる必要はありません。公は婚礼はいずれそのうちにと言っておられます」の意。 七 …をおっしゃって 右の言葉に対してムー・オヒンが言ったとされている返事。 八 明日もまたずに 文字どおりには、「夜を過さずに」。
訳者注 一 二つ返事で 原文通りには、「たった二つの言葉で合意に達した」。(「あてこすりの歌 オルドス口碑集」 A・モスタールト著 磯野富士子訳)
家飲み
酒なら家で飲めるのに、わざわざお金を払って外で飲むのは「世間」に身をおくこと、他人の中に自分を放り込むことが目的だからだ。それゆえ、入った店に客は自分一人だったらつまらなく、ある程度混んでいる方がよい。人との「密」が必要だ。そこには自分が「人好き」の要素もある。注文した、家では食べられない料理もまた世間。酔っぱらうのが目的ではなく、「世間との絆(きずな)を確認する」ことでもある。家飲みはその真逆だ。「世間との関係を断って」一人で飲む。「密」ではない「個」の世界。酒も料理も注文できない、いつも同じもの。しているのは、世間の観察、世間との連帯ではなく、自分の観察、自分との連帯。普段は忘れている「自分との絆を確認する」営為(えいい)だ。コロナ禍(か)で居酒屋飲みができず「オンライン飲み会」というのが出現したが、すぐすたれたのは、公的な場でも私的な場でも、どちらでもない中途半端とわかったからだ。(「家飲み大全」 太田和彦)
後撰夷曲集(10)
寄酒述懐
世中は 何にたとへん 麻地酒 甘きやうにて 辛きいとなみ 宣就
酒屋 本歌
よき酒ぞ かひにもござれ 我宿は ならの町屋に 杉出せる門 久友
養性
膏梁の 食をつゝしみ 酒ひかへ 色遠ざかれ 病あるまじ 贈法印道三
三笑
三笑の 名はかくれぬや のむ酒に 酔てこけいの はしはづれ迄 清勝(「後撰夷曲集」)
三二西国(さいごく)、猩々(しやうじやう)を獲(う)
天保六年、三三猩々、西国より至る 豊前(ぶぜん)小浜村に出ず。謂(い)ひつべし、珍と。按ずるに、此の物古(いにし)へ未だ其の果(はた)してありや否(いな)やを詳(つまび)らかにせず。今安(いずく)んぞ其の真仮(しんか)を弁ぜん。但(ただ)し止(た)だ頭髪のみならず、眉毛(びもう)を連ねて皆(みな)赤し。真に異物、真に奇種。善(よ)く舞ひ善く歌ひ、善く言ひ善く飲みて、我が邦(くに)古へより瑞物(ずいぶつ)と為(な)すや、一散楽中(さんがくちゆう)に猩々舞(しやうじやうまひ)あり。乃(すなは)ち二賀筵慶席(がえんけいせき)、此(これ)を演じ之を祝(しゆく)す。於戯(ああ)、此の世にして此の物を出だす。我未だ其の真偽如何(いかん)を知らずと雖(いへ)ども、要するに亦(また)大平の三祥(しやう)と為(な)して可なり。繁昌の瑞(ずい)と為して可なり。古語に云ふ、「四猩々、猩々を笑ふ」と。静軒も亦静軒を笑ふ。笑つて筆を投ずと云ふ。
三二 春秋哀公十四年に、「春、西に狩して麟を獲たり」とあるのを踏まえる- 猩々は想像上の動物で猿の一種。人語を解し、酒を好むという。 三三 豊前小浜村の猟師の子供二人が赤い頭髪に生まれ付いたのを、山師が猩々と称して見世物に出した。「同年秋の末頃か、両国にて兄弟共に見世物にいたす。能の猩々にこしらへ、装束附けて少しばかり舞をいたせし由、評判もなかりし也」(巷街贅説・天保六年条) 一 能楽の「猩々」。猩々が孝行者に酒の尽きない壺を与え、酒の徳を称えて舞う。祝言曲。 二 共にめでたい席の意。 三 祥も瑞もめでたいしるし、の意。 四 未詳。諺「猿の尻笑い(猿が自分の尻の赤いのに気付かず、他の猿の尻の赤いのを笑う)」の漢訳か。(「江戸繁昌記」 寺門静軒 日野龍夫校注)
南都諸白
南都諸白の特徴については、『本朝食鑑』では、(1)米と水の精選を重視し、(2)のちの育酛の流儀によって前述の煮酛や水酛による速醸酒とは異なった酛立法を行ない、仕込みに際しては陀岐(だき)(いわゆる暖気《だき》樽のことで、『和漢三才図会』では湯婆《たんぽ》と書かれている)を使用し、(3)さらに酛仕込に続く掛仕込は初添・中添・留添の三段階になっており、(4)酒造用具がこれまでの中世的な壺・甕にかわって桶が使用されていた、などと指摘している。そして酛仕込の割合は、蒸米一斗に麹七升、それに水が一斗四升で酛をつくり、これにさらに蒸米一斗、麹六升、水八升を、初添・中添・留添の各段ごとに単純に三回かけている。できた醪(もろみ)量は、したがって、一石一斗五升で、量的にもまだそんなに大量生産されておらず、麹割合が六割、水の吸水率五・八水(米一石に対し水五斗八升)と、のちの伊丹諸白や灘酒にくらべると、いずれもまだ高い割合を示していた。(「酒造りの歴史」 柚木学)
怪猫
有馬猫騒動には種本がある。『想山著聞奇集』の中に、猫が人に化けて現れる話が出ている。屋根葺きを渡世とする男があった。この男は、生来律儀で、一人の老母に対して、大変な孝行者であった。貧民のことなので、老母を家に残しておいて、日々職に励み、そこかしこと稼いで歩いていた。老母はかなり酒好きであったので、男は、帰りには酒を二合ばかり、必ず土産にした。ところが、この孝行息子に対して、老母は、齢を重ねるにつれて、根性がいやしくなり、ひどくあしざまに罵りわめくようになった。男は、しかし、一言も口をかえさず、常に、穏かな態度を保って、いかに口ぎたなく罵られても、二合の酒の土産を絶やすようなことはなかった。ある時、何かの事があって、屋根葺き仲間が、この家に集まって、酒盛りする約束になった。そこで、男は、昼すぎから仕事を休んで、酒肴をととのえて、わが家へ戻って来た。ところが、さる大名屋敷にいそぎの用事ができ、仲間全部がそっちへ行ってしまい、酒盛りはお流れになった。手当てした酒も、そっくりのこってしまったが、男は、かえって、それを悦び、平常貧しさゆえに、母に充分酒を飲ませることができなかったが、さいわい、今日は、思うさますすめることができると、いそいそとすすめた。老母は、大悦びで、酒も肴もあまさずに、くらって、心地よげに、臥牀に入った。男も、いささかの酒で、睡魔にさそわれ、あと片づけもそのままに、臥した。そのうちに、老母の呻く声に、男は、目をさました。年寄があまり度をすごしたので、苦しがりはじめたのであろう、と心配して、戸ごしに声をかけたが、返辞はなく、呻き声だけがつづいた。-さては、毒に中ったか!と、男は、不安のつのるままに、夜は、絶対に開けてはならぬと禁じられている戸を開いてみることにした。老婆は、近年、明りをきらって、寝所はしんの暗闇であった。手さぐりでは何事も行きとどくまい、と思って、燭台をかかげて、戸を開いた。愕然となった。牀に臥していたのは、母ではなく、怪しく巨大な黒猫だった。深酒に酔い痴(し)れて、熟睡し、不覚にも正体をあらわして、高鼾をたてていたのである。きもをつぶした男は、しかし、元来沈着分別のある人間なので、胸をしずめるや、そっと、縄をもって来て、怪猫の四肢をしばりあげた。それから、近隣の人びとを呼び起こして、集めると、事情を説明して、老母の行方をさがしてもらった。老母は、怪猫に食われて、骨となって、囲炉裏の下の床下にころがっていた。男は、代官所へ訴え出て、怪猫の処置をうかがったところ、心まかせにすべしと下知があったので、小刀で、こなごなに斬りきざんで、村の入口、道の分れ角に瘞(う)め、猫俣城という石碑を建てた、という。これが種本になって、有馬猫騒動は、でっちあげられたものらしい。(「江戸八百八町」 柴田錬三郎)
酒の値 大田南畝著『金曾木』所掲
「酒の価 一升 百二十四文から百三十二文を定価としていた。低級は八十文、百文もあった。その後、百四十八文、百六十四文、二百文に至り、二百四十八文ともなってしまった。これは明和五年(一七六八)から南鐐・四文銭が出来て、銭相場賎(やす)く、物価が貴くなったからだ。」下り酒屋への入荷量は、元禄十五年(一七〇二)三月の記録『入津見区書上』によれば、上方から江戸新川の問屋へ到来した酒の量は、樽(四斗入り)数で、 元禄十年(一七〇二) およそ三十万駄程此樽六十万樽 元禄十四年 およそ十六万駄程此樽三十二万樽 (註)元禄六年(一六九三)の江戸の人口は純町民だけで三十五万三千五百八十八人という。このほかに武家の人口(ほぼ同数)と人別外の人口(非人等)があったというから総計では九十万前後と考えられる。寛政(一七八九-一八〇〇)ごろの九州方面の場合の一例は橘南谿著『西遊記』(寛政七年・一七九五)序の一節に「西国(九州方面)にて酒の売買一升、二升といわず、一ぱい二はいとて売ることなり。その一ぱいというもの大抵四合二、三勺ばかりなり。球磨郡などは酒下直(安値)にして、一杯の価銭八、九文より十二、三文ほどなり。此所は格別下直の地なり。薩摩は余程高直なり、一ぱい二はいの名は琉球までも皆かくのごとしとなり。」(「江戸物価事典」 小野武雄編著)
火の車、學校の肴
そもそも(草野)心平さんは、酒の肴をつくる天才だったと聞く。詩を書くだけでは家族を養うことができず、焼き鳥屋の屋台を引いたり居酒屋を開いたり、生涯にわたって飲食業で糊口をしのいだ。それはつまり、いかに安い材料を仕入れいかに貧しい酒飲みが喜ぶ肴に変身させるか、を研究する仕事でもあった。「心平さんの作品で好きなものをひとつ選べ」と言われたら、迷った挙げ句に、詩ではなく「火の車のメニュー」と答えるかもしれない。居酒屋「火の車」は、一九五〇年代に心平さんがやっていた店。言わば學校の前身だ。そのメニューを挙げると、 満月(卵の黄身の味噌漬け) 冬(豚のにこごり) 白夜(キャベツとベーコンが入った牛乳ベースのスープ) どろんこ(かつおの塩辛。柚子とパセリ) 五月(きゅうり、うど、玉ねぎの和え物、カレー味) 丸と角(カルパスとチーズ) 赤と黒(品川巻き) ぴい(ピーナツ) 天(特級酒) 耳(一級酒) 鬼(焼酎) 麦(ビール) 泉(ハイボール) 息(サイダー) あぁ、いいなぁ。日常の言葉たちが素顔のまま並んでいて、なのにこの豊穣。學校初期の頃は、これら火の車時代のメニューを出すこともあったらしい。もっとも、(井上)禮子さんにいわせると「満月なんか、今の人の口には合わないねぇ」。禮子さんが用意する肴の定番は、しらたきと玉ねぎと鶏肉を甘辛く炊いて卵でとじた「親子煮」、手羽先と里芋とこんにゃくを酒と醤油で炊いたもの。卵と練り物のおでん。そういうものを鍋にいっぱいつくっておいて、やってきた客ひとりひとりに、お母さんみたいに聞くのだ。「お腹は?」空腹の客にはたっぷりとよそってくれる。禮子さんはハイカラ好みなところもあって、中村屋のアグレッツィや、伊勢丹のクリームチーズなんかも常備していた。桃の節句には潮汁をつくり、土用の丑の日には「おうな」を出し、冬至にはかぼちゃを炊く。あるとき、「季節の行事を大事にするのは、心平さんの時代からなんですか」と尋ねたら「心平さんは、そんなことはあんまり気にしなかったわねぇ」という返事だった。郡山の商家で生まれた禮子さんは、十歳のときに秋田で鉱山経営をしていた養父母のところへもらわれていった。そこが季節ごとのしきたりをきちんとする家だったらしい。心平さんと禮子さんがこだわりの肴を出してきた歴史をまるで無視して、わたしが供するのはきゅうりと味噌である。お客さんたちはさぞがっかりしただろう。(「酒場學校の日々」 金井真紀)
鯨 くじら
くせのある酒でくじらの太刀をはき 拾十9
【語釈】○鯨の太刀=くじら身、鯨の歯に銀箔を塗って刀身にかえた刀。
【鑑賞】なにごとぞ花見る人の長がたな、と去来の句があるが、花見酒に酔って人切り庖丁を振回す危険があるので、くじら身の刀をさして行く。酒癖の悪さを自分で知っていてもどうにもならないらしい。
【類句】わるい癖のむとはつかへ手をかける 一三5
生酔にあした切りゃれとおさめさせ 一三38(「江戸川柳辞典」 浜田義一郎編)
酒の飲み方
私が酒をはじめたのは京都の高校へはいってからのことである。三高にはいって、一年間寮に入ることになっていたが、中寮に入寮したその夜、室長と先輩が、歓迎会を開いて、酒を飲ましてやると言い、熊野神社近くの小さいバーに新入生の私たちを連れて行き、テーブルについて、女の子の運んできたビールを飲みはじめたが、「よし、酒の飲み方を教えるよ、いいか、よく見るんだな」と言って、大コップを傾けはじめた中背の室長が、コップを半分も、飲みほさないうちに、顔青ざめ、椅子に背をつけ、呼吸の乱れを見せはじめたのを見て、私は嘆じないわけにはいかなかった。私は出来るだけ見て見ぬ振りをしていたが、室長はやがて、自分でも、だらしないと思ったのか、背を真直(まつすぐ)にのばし、コップを取り直し、再び、飲みはじめ、私を安心させた。しかし、それも、僅(わず)かの間のこと、今度は、ついに、力尽きたかのようにテーブルの上に上体を投じ、やがてその身をテーブルから、はずして、吐きはじめた。私は驚かないわけにはいかなかった。これが、「酒の飲み方を教えるよ、いいか、よく見るんだな」という言葉の意味だったのかと私は思い、その室長の背を撫(な)でながら、ビールを飲みほして、新入寮者連の手で室長を、かつぐようにして寮へ帰ったのである。私は高校一年の時、結核になりその後酒を飲むことは少なくなったが、酒に弱くなったわけではなく、兵隊になってから、酒にきたえられ、そのため、新橋の「蛇の神」の焼チュウ、バクダンなど、いかに飲みあかしても酔いつぶれるということにはならなかった。(「酒との出逢い 蛇の新」 野間宏)
くつ石(いし)
桶またはタンクは床面に直接置くと、呑口から酒を取り出すのに不便であり、またタンクの下部の腐食を防ぎ、庫内を清潔に保つ目的でタンクの底の周辺に沿って3~6個所に台を置きタンクを浮かせて据える.この台のことをくつ石またはくつという.古くは石や木の丸太を切ったものを使用したが、現在では木形の金型にコンクリートを流しこんで固めたものやブロックにコンクリートを詰めたものなどが使用されている.(「改訂灘の酒用語集」 灘酒研究会)
酒造資本と酒造経営
いま実際の酒造経営を考えてみると、一九世紀初頭でまず酒造蔵・酒造道具・酒造株一式を購入するのに銀一〇〇貫目の設備資金を必要とし、生産資本として充用される流動資本は一〇〇〇石造りで、やはり銀一〇〇貫目であった。このうち約六五%が酒造米購入費、一三%が酒樽で、賃金などは飯米・菜物(副食)を含めて七%にしかすぎない。この流動資本は一年を通じて分散して投入されるわけではなく、冬季仕込みの性格上、ほとんど一一、一二月に集中するため、一時に多額の資金を確保しなければならなかった。しかもこうした投下資本に対し、酒が仕込まれて清酒となり、江戸へ送られて酒問屋に売りさばかれたあと、酒荷代金が酒造家の元に回収されるのは、約一年のちとなる。つまり生産資本の投下より資本の環流まで最低一ヵ年を要することになり、ここに酒造経営における資本の回転が問題となってくるのである。一般に資本の回転期間は、生産期間と流通期間からなる。前者は生産資本の投入期間であり、後者は生産資本が市場において商品資本から貨幣資本に再転形して環流してくる期間である。この資本の回転が円滑にいって最低一ヵ年としても、現実に江戸酒問屋との取引き条件によって売掛金の回収が延長されたり、酒造米の購入時期と清酒の販売時期とでは相当の時差があり、その間の米価や酒価の変動を考えあわせると、酒造経営における利潤形成には、かなりの投機性と不安定性の要因がひそんでいた。この不安定な経営のもつ投機性を克服するために、酒造資本の一部は確実な利殖手段としての貸付資本に運用された。酒造資本が貸付機能と結合し、酒造経営のための生産資本部分と貸付資本部分とに分散投資されることが、じつは酒造収益の投機性を克服するための知恵でもあった。この分散の仕方(割合)が、江戸積み酒造業における経営を左右する重要な要因であった。江戸時代を生き続けた酒造家は、時の相場や商況をみてこうした資本の運用、回転でもって上手に景気を切り抜けてきた企業のらつ腕家であったといえよう。(「灘酒の歴史」 柚木学)
技の受け継ぎ
重光には分析を何年かやってもらった後、「麹室」を任せて、「酛場」を任せて、「次長」ということで「頭(かしら)」にした。だすけ、あのがんは、「洗米」や「釜場(かまば)」を任されたことがないままで、「次長(頭)」になり、「杜氏」になったわけですて、他の蔵も知らんし、やっぱり昔の杜氏とは違うわけですよ。だども、おらは心配はしてないんですて。まず蔵内に「物差し」がぴしっと通っていますからね。それに加えて、重光が他の蔵を知らないということも、むしろよかったんでないかね。酒造りの「さ」の字も知らないところから、おらとこの酒造りを覚えたわけで、真っ白なところから教えたすけ、重光は、余計なことを考えずに、おらとこの蔵の考え方や、やり方を覚えたわけさ。それこそ、「蔵癖(くらぐせ)」から何から、おらが知っていることは全部教えたわ。重光は生まれも育ちも六日町だが、実質は野積杜氏と言えるんでないかね。立派に野積杜氏の技を受け継いでいるわね。これが、よそから来た杜氏さんだったら、そうはいかんかったろう。よそから来た杜氏さんは、その杜氏さんなりの考え方もやり方もあるすけ、余計な心配もしなくてはならないわけさ。蔵の主人にしてみれば、一年や二年は夜もよく眠れないぐらいに心配になるんでないかね。せっかく積み上げた八海山の酒というものが、どんなふうに変わってしまうか。下手をすれば、たいへんなことになってしまうわ。だすけ、重光のように、自分のところの蔵で育った杜氏というのも悪くないんですて。安心して任すことができるすけね。蔵に初めて来た時から勘定(かんじよう)したら二五年の上も、おらのそばに置いて教えこんだんだすけ、おらの後は重光に任すと決めた時は、何の心配もしていなかったわ。(「杜氏千年の知恵」 高浜春男)
冬はやっぱりイカ大根 やき屋(荻窪)
黒光りするほど濃い飴色に煮込まれた大きな大根が二切れに、エンペラとゲソを添えて、最期にツユが入ります。どうです、このボリューム。今日び、おでんの大根だってひとつ三〇〇円も四〇〇円もしたりするのに、同じような大きさの大根が二個入って一五〇円ですよ!その大根の中に、よーく染み込んだイカの味がうまいなぁ。イカそのものを食べるよりイカらしい。-
新しく入って来たお客さんたちからイカなんこつ焼き(一五〇円)やウナギ肝焼き(一串一五〇円)などの注文が入ったので、私もイカしょうが棒(一五〇円)を焼いてもらうことにしました。イカしょうが棒は串に刺した棒天ぷらで、ゆっくりと時間をかけて炙ったものをおろし生姜といっしょに出してくれます。イカしょうが棒ができあがったタイミングで燗酒(二三〇円)もおかわりです。ん-。やっぱり練りものもいいですねぇ。できるだけチビチビと食べて長持ちさせようと思うのに、やめられない止まらない。あっという間に食べ終えて、次なるつまみはイカわた和え(一五〇円)。イカわた和えは、イカ下足を、その名のとおりイカわたで和えたもの。とはいうもののできあがったイカわた和えは、塩辛のような赤っぽい色ではなくて、黒いのです。しかも味はやわらかく甘い独特なもの。これが不思議と、どのお酒にも合うんですよねぇ。四五分ほどの立ち飲みタイムは九五六円。今年もおいしいイカ大根でした。(平成一九(二〇〇七)年一月一三日(土)の記録)(「ひとり呑み」 浜田信郎) やき屋 東京都杉並区上荻15-6
コカ・コーラ
一九世紀末、コーラ発祥の地、アメリカでは、客の注文に応じて、飲み薬を調合して提供するスタイルの薬局が流行した。薬剤師たちは、より効果のある万能薬の開発を競い合っていた。『コカ・コーラ』を開発した、ジョン・S・ベンバートン博士も、そんな一人であった。そしてそんな中、水と砂糖、コーラナッツエキスなどを配合し、頭痛や二日酔いの薬となる飲み物を開発したのだ。これはフレンチ・ワイン・コカといって、もともとは水で飲むシロップとして開発したものだった。しかしあるとき、店員がこのシロップを、水と間違えて炭酸水で割って客に出してしまう。これが美味だったために、評判はすぐさま広がり、『コカ・コーラ』として売り出されるようになったというわけ。(「二日酔いの特効薬」のウソ、ホント。」 中山健児監修)
アルコール性痴呆
アルコールによる中枢神経障害の終着駅は、アルコール性痴呆です。アルコール性痴呆は、早い人では四〇才くらいで出現します。単なる健忘症だけでなく、自分が何者であり何をしているのかもわからなくなり、奥さんを知らない人だといったり、ベッドをトイレと間違えてオシッコしたり、お箸で食事することを忘れて手づかみで食べたり、食事が済んだばかりなのに、まだ食事をもらっていないと怒ったりと、完全なボケ症状になるのです。治療によって日常生活は何とか出来るようには回復しますが、社会的活動が出来るまでに回復することは困難です。老人性痴呆とアルコール性痴呆との違いは、症状では区別出来ませんが、老人性痴呆はどんどん悪化したり、悪化したりよくなったりを繰り返すのと比較して、アルコール性痴呆は、お酒さえ飲まなければ進行はしないことです。痴呆においてはあらゆる知的機能が低下します。また脳のCT(コンピュータートモグラフィー)で脳の断層写真を撮れば、痴呆の脳は萎縮し、脳の皺が広がり、脳室も拡大して脳全体が縮んでいることがわかります。前頁の写真は、頭部のCT写真で、正常な人(四〇代)の脳とアルコール性痴呆(四〇代)の萎縮した脳とを比較しています。アルコール性痴呆の脳は皺が広がったため脳のまわりの空間が広がっていること、脳の中の空間である脳室が拡大していることなどが観察出来ますが、結局脳が萎縮していることがわかります。この知的機能の低下、つまり知能指数の低下や脳の萎縮は、アルコール依存症においては、痴呆に至らない人でも発生していることが多いことが知られています。大量飲酒を長年続けていると、知能障害や脳の萎縮が発生するわけです。(「子どもの飲酒があぶない」 鈴木健二)
どぜう飯田屋
明治三十年頃、初代三次郎が創業した飯田屋は、もともと甘味屋であった。すぐ奥に名刹(めいさつ)の二院があり、ちょうど参道に面していたから結構繁盛していたらしいが、女子供相手の甘味屋では酒が売れない。そこで三次郎は一膳飯屋に商売替えをし、川魚や蜆を肴に一杯やれる店にした。その中からだんだん「あそこのどぜうはうまい」と評判になり、いつの間にか名代のどぜう屋になった。関東大震災と戦災とで二度も焼けている飯田屋の現在(いま)の店は、戦後に建てられた和風の二階家で、ビルの谷間で「どぜう」の大看板が異彩を放っている。一階も二階も小部屋はなく、藤筵(とうむしろ)を敷きつめた広い入れこみで、飴色に艶(つや)が出た藤筵が老舗の歴史を物語る。(「うまいもの職人帖」 佐藤隆介) 西浅草3-3-2のどぜう屋です。
居酒屋GPS!
ある夕方、よく知らない町を友だちとふたりで歩いていた。その友だちが以前、知り合いに連れていってもらった居酒屋に案内したいと言ってくれたのはよいが、店名も場所も覚えていないという。ただ、駅の南口からそれほど遠くないということは記憶にある、と。普通なら、しばらく探し歩いて見つからなければ諦めるだろう。実際に十分ほど、ありそうなところを歩きまわったが、いっこうに埒が明かない。だが、友だちがちょうど諦めようとしたところで、私は「どんな店なのか、教えてくれる?」と頼んだ。「女性ひとりでやっている、落ち着いた小ぢんまりした店で、ちょっと小料理屋っぽい」と言うから、私は「もしかしたら、まっすぐ行って、あの角を左に曲がったらあるかもしれないから、行ってみないか」と提案した。もちろん、その辺りを歩いたこともなく、どんな場所なのかも知らない。でも、実際に行ってみたら、ずばりだった。これゾ、居酒屋GPS!-と自慢したいところだが、超能力でも偶然でもないと思う。店の輪郭と雰囲気を思い浮かべたら、街のどの辺りにありそうか見当がついただけだからだ。たとえば、大型チェーン店はだいたい駅周辺の大通りに面しているが、小ぢんまりした一戸建ての小料理屋は、呑み屋街のなかでも、ガヤガヤした店やスナックが並んでいる道ではなく、少し閑散とした小道にある場合が多い。それは、いままでの街歩きや居酒屋探訪の経験から知っていたし、私が当てられたのは、そこが何となくそういう雰囲気の小道だったから、というだけのことである。(「日本の居酒屋文化」 マイク・モラスキー)
67醴(あまざけ)を勧(すす)む 七不風雅(ふふうが)
君(きみ)に勧(すす)む 八三国一(さんごくいち)
甘酒(あまざけ) 九辞(ぢ)することを須(もち)いず
胸焼(むねや)けて 皆迷惑(みなめいわく)
一〇先生(せんせい) 別儀(べつぎ)なし
○三国一醴 1浅草門跡前の名産なり。下戸飲レ之。2かん気をしのいでのむ時は、むね大にやける。されども3やけほこりなどといふて、まけおしみをいつて、せうもこりもなく又のむ気なり。4おたふくこれにゑふときは、けげんなかほをす。
七 酒ではなく甘酒を勧めるのでいう。 八 日本、唐土、天竺を通じて一番。特に甘酒屋が宣伝にこの語を用いた。 九 遠慮しなさんな。相手が迷惑がっているのを遠慮していると勘違いしての語。 一〇 勧める御本人は下戸なので沢山飲んでも平気。
1 浅草の東本願寺(準門跡寺院)門前に伊勢屋、大坂屋などの甘酒屋があり、それぞれ三国一を称した。 2 寒気を防ごうとして熱い甘酒を飲む。 3 焼け誇り。焼け太り。火事に逢った後、かえって以前よりも豊かになること。だから胸が焼けるのも結構という負け惜しみ。 4 「お多福」は醜女の意。この一文の意味未詳。(「通詩選笑知」 大田南畝 日野龍夫校注)
柴
酒をあげて地に問ふ誰か悲歌(ひか)の友ぞ二十万年この酒冷えぬ
みなさけに涙こぼれぬさらば我師この子とこしへ酔へりとおぼせ
屠蘇すこしすぎぬと云ひてわがかけし羽織のしたの人うつくしし
酒のまへに酒の歌なき君ならば恋するなかれ市に入るなかれ
われにまづ毒味せよとは云ひ得たり許せさかづき二つに割らむ
人ならば酒をも強ひん杖がたなさびし幾とせ善き仇もあらず(「柴」 与謝野寛)
晩年の父
父は盗み飲みの時代からずっと日本酒党だった。一度胃を悪くして酒を控えたとき、ウイスキー紅茶にしたことがあったようだが、そのときを除いては、ずっと日本酒を貫いた。だいたい辛口が好きで、灘の白鹿や白鶴が好みだったようだが、私が知る晩年の晩酌には伏見の招徳というのを用いていた。これは伏見の酒にしては辛口だった。これを一日二合と決めて計量カップできっちりと量り、ガラス製の徳利と杯で飲んだ。杯はリキュールグラスの流用だったと思う。ガラス製だったのは酒の色が楽しめるし清潔でもあるからで、陳ねた焼物の徳利や猪口は、侘びとか寂びの茶人好みとして嫌った。そのガラス製の徳利を、左脇に据えた火鉢の鉄瓶で燗をし、ちびりちびりと手酌でやる。私も若い頃、父の真似をして日本酒を飲したが、少しだけ反抗して徳利と猪口は焼物にした。いろいろな焼物が楽しめるからである。しかしあるとき、一口含むと、何とも言えない嫌な味がした。で、酒を全部空けて見てみると、黒い点々としたものが混じっている。おそらく、ゴキブリの卵だか糞なのであろう。よくよく洗って使わなかったからと言われればそれまでだが、父のガラス製愛好を成る程と思い、以来、焼物は止めてガラス製にした。ガラス製もその当時は種類が少なく安物臭かったが、段々と良いものが出るようになって、洗練されたものが手に入るようになった。その後、私はダイエットのために、糖分の多い日本酒を避けてウイスキーの水割りにし、さらには酎ハイに、今は生ビールといった具合に、まことに一貫しない鬼っ子で、生涯日本酒を貫き通した父には、敬意を表する。(「中華飲酒詩選 思い出」 青木正児)
勧酒と返杯
唐の詩人、王翰が「葡萄の美酒」を「夜光杯」でどう飲んだか、李白が「詩百篇」を生み出した「一斗」の酒の飲み方はどうだったかについては諸説あるものの、清代あたりの酒席についての記録を見れば献杯と返盃、罰杯などが一般的だったことがわかる。前者は、めいめいが使っている盃とは別に、銀や錫で作った足つきの爵盃(しやくはい)を使って主人が客に酒を勧め、のみ終わったあとの同じ盃で客が主人に返杯する、といった方式で、日本流の「お流れ頂戴」は見当たらない。これと比べると、自分の盃だけを使う中国での今のやり方は、たぶんに様式化されている。(「北京そぞろある記」 田所竹彦)
わかさぎの木の芽焼き(ワカサギ、木の芽)
ワカサギは頭と尾をそろえて、串にさしておく。はじめは強火で、ワカサギに火がとおるまで焼き、弱火にして、はけでタレ(みりんと醤油同割ずつ混ぜたものを一割ほど煮つめる)を塗って、照りをつけながら焼きあげる。タレは1~2回つけると、きれいに仕上がる。器に盛ったら、粉サンショウを軽くふりかけ、木の芽をかざる。ワカサギは、身がやわらかいわりに、火を通すと身がしまり、型がくずれないのが特徴。みりんの照りと木の芽の青味のコントラストが美しい酒肴だ。ワカサギの淡泊な味が、タレでひきたち、日本酒の友としては最高。ブリやハマチの照り焼きとくらべ軽いので、いくらでも食べられる。(「酒肴(つまみ)のタネ本」 ホームライフセミナー編)
7日 湯豆腐
もう、二年前のことになる。昭和三十七年のきょうのことだ。久保田万太郎さんの誕生日のお祝いが銀座の辻留で、あった。そのとき久保田さんは京都の樽源さんに贈る俳句を用意して来られた。それが、 湯豆腐や。持薬の酒の一二杯 という句であった。花柳章太郎さんのすすめで、久保田さんはそのあとに「寒うおすな」と付け加え、小唄が出来上がった。同席しておられた山田抄太郎さんが、あいにく手をわるくしておられたので、芝小百合さんがかわりに三味線をとって、即席の「口述作曲」が始まり、たちまちにして、万太郎作詞、抄太郎作曲の、小唄「湯豆腐」が出来上がった。湯豆腐は元来上方のものだ。だから先生は京都弁で「寒うおすな」と付けた。そして山田さんは京都のあけぼのという手と壬生(みぶ)狂言の手をいれて曲をしたてた。楽しい思い出である。(「私の食物誌」 池田弥三郎)
古文書から元禄の酒を再現
先ほどの近藤勇の礼状ではありませんが、赤穂浪士が討ち入りした年の元禄十五年(一七〇二年)、今から三百四年前の古文書『酒永代覚帖』が残っています。それを紐解いて再現したのが、『復刻酒 江戸元禄の酒』であります。元禄時代の製法を再現した場合、どんなお酒ができるのか、二つの結果を予想していました。一つは、当時はまだ発酵技術が進んでいなかったので、やはりアルコール度数の低いお酒ができるのではないか。もう一つは、甘いお酒ができるのではないかと予想したのですが、結果は後者でありました。(「不易流行の革新経営をめざす!」 小西酒造株式会社代表取締役社長
小西新太郎)
安飯屋、居酒屋
問題はその下の安飯屋で、これらは不潔を極める。
第一目に立つのはその家にして、檐(のき)朽ち柱ゆがみて平長屋の板庇煤烟(いたびさしすすけむ)に舐(なめ)られて黒ずみ、…なかんづく厨房の溷雑(こんざつ)は実に伝染病の根源にして一面芥捨場(ごみすてば)を打拡げたるが如く…およそ世に不潔といへるほどの不潔は悉皆茲(しつかいここ)に集めたるが如く、蓮根・芋・筍子の皮・鰯・鯖・鮪等の敗肉(あら)は皆一所に掃溜めて数日間も厨房の片隅に寝かし、それより発する臭気、移り香、蒸発する厨婢の体臭、海苔のごとき着物を被(き)たる下男…酔漢(のんだくれ)、恫喝男(どうまごえ)、貪食者(くいつぶし)等を以て終日喧声涌(けんせいわく)が如きこの最下等飲食店は、浅草、芝辺の場末に最も多く三河町の界隈比々(かいわいひひ)皆これなり
こうした下等飯屋にあっては、材料費を安く上げるため、かなりの工夫がなされており、一食三銭以下の値段で満腹できたという。また彼らの食事内容については「朝餐には一汁一菜極めて淡薄(たんぱく)なれども、晩餐には間々濃味の鳥肉を呼びて口腹(こうふく)を肥やす。蛤蜊鍋(はまぐりなべ)、葱鮪(ねびま)等なり」という状態で、彼らはまた居酒屋での濁酒や焼酎をもっとも好んだ、としている。(「江戸の料理史」 原田信男) 引用は明治26年刊行の松原岩五郎の「最暗黒の東京」です。
三分の酒二分の水
牛肉を買ふの法を説いて「先づ宜しく各舗に定銭(手付金)を下(お)き、腿筋夾肉の処、無精不肥なるを湊(あつ)め取り、然る後家中に帯(も)ち回(かへ)れ」と料理法は「皮膜を剔去(てつきよ)し、三分の酒、二分の水を用(もつ)て清煨す。極爛なれば再び秋油(醤油)を加へて収湯せしむ。此れ太牢、独味孤行する者なり、別物の配搭を加ふべからず」と。肉は直股筋即ちシンタマと称する処であらうが、買入れる分量が何程か判らぬけれども、何軒かで買ひ集めよと謂ふからには一軒の店で間に合ふ程の大きな牛肉屋が無かつたからであらう。之れが清朝中頃に於ける南京の実情だつたのである。大切りの儘の肉を「三分の酒、二分の酒で充分軟らかになるまでゆつくり煮込み、そこへ上等の醤油を加へて、汁が無くなる迄煮る」とは相当贅沢な料理で、即席料理の及ばぬ滋味があらう「此れ太牢であつて独味孤すべき者だ」と、さもありなんであるが、牛肉など久しく見たこともない今(戦争末期)の私達には縁なき者、一場の夢物語に等しい。昔飲ん兵衛の汝陽王は道に麹車(きくしや)(酒を積んだ車)に逢ふて口に涎を流したといふが、私達は耐乏生活に馴れたとは謂へ、決して美味を忘れた訳ではない。美味に縁遠くなればなる程、凡下の浅ましさは愈々美味を憶(おも)ふ、浅ましくても恥かしくても憶(おも)はざる得ない。だから二三人集まれば必ず食べものの話が出る。そして最後には、昔旨かつた思出を並べるに堕ちる。けちな気休めではあるが、画餅でも口振舞でも、幾らかの慰めになる昨今では、汝陽王の涎もまことに他人ごとではない。(「飲食雑記」 山田政平)
火落酸
日本酒を腐敗に導く細菌として明治以来その道の学者に知られた火落菌という乳酸菌の一種がある。江戸時代から酒の腐ることを「ひおち」という。この菌には奇妙な性格があって、肉汁とか植物体の煮汁とか普通の細菌の好んで生える培養基には、決して生えない。酒に生えてこれを腐らせて困らせるくせに、研究室でこれを生やすのには大苦労をする。然るにこれらの培地に日本酒をちょっと一割くらい加えると、たちまち猛然として生えてくる。まるでその辺の我らの酒の友のような不思議な生理の持ち主である。これは不思議な現象であるから、ある時これを手掛りの研究がはじまり、まず第一にこの原因となる新物質は、麹菌という日本酒を造る時に使うカビが造ることがわかった。そうなると、これの分離の材料には、酒のような金のかかるものを使うよりは、この未知物質を沢山造る麹菌を選んで、それを造らせる方が、よほど効率的であることがわかった。これで大量の未知物質をたやすく入手できるようになった。それが研究の第一歩である。次にはその新物質を純粋に分離することに成功し、化学的に研究してみると、それは炭素原子六個から成る従来知られなかった新化合物であることがわかった。これを火落酸(ひとちさん)(のちにメバロン酸と命名)という名で発表した。一九五六年の春のことであった。この新物質は、始めに想像されたヴィタミンのような作用をする物質ではなくて、火落菌が自分で造ることができない栄養素の一種であることも判明した。この新物質メバロン酸が発表されると、これがたちまち世界の生化学界に伝わり、世界中でその研究がはじまり、忽ち第二次大戦後の全世界の生化学者の研究の寵児となって、各国で競って研究が進められた。前述のノーベル賞問題は、ここから出たのである。それらのうちで西ドイツのリネンは、メバロン酸の炭素数に着目して、それが三分子の酢酸(二炭素原子から成る)から生成する生理的な筋道を研究した。その後これと前後して米国のブロッホ兄弟が、更にメバロン酸からコレステロールのようなステロールの類いを生成する生理的筋道を照明して、いずれもその研究に対してノーベル賞が与えられたのである。その後、一九七五年にこれらの生成経路についての立体化学的解明がイギリスのコンフォースによって研究されて、これに対してもノーベル賞が出されることになったのである。以上が酒の研究からノーベル賞が三箇生まれたといういきさつである。研究の基礎になる物質の発見には、何の関心も払われずに、その発見のおかげで生まれた研究のみが賞の対象となるとは、一体いかなるものさしによる判断であるか、腑におちない。(「愛酒楽酔」 坂口謹一郎)
眼前 一杯の酒、誰(たれ)か身後(しんご)の名を論ぜん。
<解釈>月の前に一杯の酒があれば、死後の名声など関係ない。
<出典>北周、庾信(ゆしん)(字(あざな)は子山(しざん) 五一三~五八一)の「詠懐(えいかい)」詩二七首<其の一一>の第一一・一二句。『庾子山集』巻三。『古詩源(こしげん)』巻一四は「擬詠懐」と題する。
<解説>庾信が南朝の梁(りよう)の使者として北朝の西魏(せいぎ)に滞在中、祖国の梁は、こともあろうに西魏の攻撃を受けて滅亡してしまう。「詠懐」詩は、異国に仕えることを余儀なくされた庾信が、亡国を恨み、自身の悲しみを詠じた長編の連作である。ここに挙げた二句のみを見れば、死後の名声など気にしない、快楽主義的で豪放な庾信像が浮かび上がるだろうが、実はそうではない。この二句は、「揺落、秋の気為(た)り、凄涼(せいりよう)、怨情多し、啼いて湘水(しようすい)の竹を枯らし、哭(こく)して杞梁(きりよう)の城を壊(やぶ)る」という、華北の秋の寂しげな情景描写から始まり、舜の二妃である娥皇(がこう)と女英(じよえい)が舜の死を悼んで竹に涙した故事、戦死した杞梁を妻が慟哭(どうこく)して悼んだ故事などを交えつつ、梁の亡国とそれによって悲劇を体験した自分を含む多くの人々の怨みを述べたあとの二句なのである。したがって、この詩には作者の深い絶望感が潜んでいる。確かにこの二句は張翰(ちようかん)の故事をふまえている(李白(りはく)「且(しばら)く楽しまん生前一杯の酒、何ぞ須(もち)いん身後千載(ぜんざい)に名」の「解説」参照)が、二人の酒の味は正反対のものであったに違いない。また、一説にこの句は、梁の皇帝と臣下が酒びたりで、国家の将来について思慮がなかったことを批判する意がこめられていると言うが、これこそ牽強付会というものであろう。(後藤秋正)
古酒の幅
呑嬉亭も出した冷奴の上に塩辛を乗せながら、「そういえば、同じ古酒でも、醤油みたいな色がついたものから、うっすら山吹色がついたものまでいろいろだよな」と切り出す。「うん、貯蔵するお酒の種類や、貯蔵温度で差が出てくるね。長期熟成酒研究会では、吟醸酒なんかを低温で熟成させて、あまり色のつかないものを『淡熟タイプ』、一定の温度(一〇~二〇℃)で熟成したものを『中間タイプ』、常温で熟成させたものを『濃熟タイプ』と分けているけどね。濃熟タイプが茶色くなるタイプさ。普通酒や純米酒なんかは色がつきやすいよね」酔「しかし、その『淡熟タイプ』と、『濃熟タイプ』じゃまるで別物だよな」「古酒とか長期熟成酒とか、一緒くたにするのもなんか違う感じがするけどな」呑嬉亭も古酒の現状に不満があるようだ。数年前、宮城県の気仙沼で「古酒の会」が開かれ、呼んでもらったことがあった。主催は地元で店を開く「おけい茶屋」という酒販店。「前日から入って、マンボウの刺身や、卵巣、真子、それに地元では『巨人の星』とよばれているモウカザメの心臓、ホヤなどの珍味を肴に一杯やって、翌日市内のホテルで古酒の会さ。古酒一つ一つ取ってみればそれぞれ個性があって美味しいんだけれど、宴会の最初から最後まで古酒で攻められるとちょっと疲れるというか…しんどいってことはあるね。料理の中の一部を古酒と合わす形の方がいいな」(「ツウになるための日本酒毒本」 高瀬斉)
しゃ-しん[写真]
師と語る写真のどれも酒の上 佐藤 正敏
しゅ-ぎょう[修業]
②仏法を修め善行を積むこと。
樽の中で修業しているウイスキー 吉川 一郎(「川柳表現辞典」 田口麦彦編著)
△家言(かげん)三九
杜氏(とうじ)四〇(酒工の長なり。又おやじとも云。周の時に杜氏の人ありて其後葉杜康という者、よく酒を醸するをもって名を得たり。故に擬(なぞら)えて号(なず)く)
衣紋(えもん)(麹工の長なり。花を作るの意をとるといへり。一説には、中華に麹をつくるは架の下に起臥して暫くも安眠なさざること七日、室口に勝るの意にて衣紋と云か。)
三九 家言 一家言。個人的見解。
四〇 杜氏 酒造技術者の長。同時に技術出稼グループの組織者、責任者でもアル。刀自すなわち古代の女性醸造時代の主婦の名称をうけつぐという見解もある。早く発生したのは丹波杜氏であるが、後に越後、広島、秋田等の出身者が増加した。
宴席の伏兵
費無極(ひむき)は楚の令尹の近臣であったが、郄宛(げきえん)というものが新たに令尹に仕え、令尹に大いに寵愛された。そこで、無極は令尹にいった。「宛をいたくご寵愛のご様子ですが、一度、宛の家で酒宴をお開きになられてはいかがです?」「それはよかろう」そこで、令尹は費無極を郄宛の家に酒宴の準備を命じていかせると、無極は宛に教えた。「令尹は剛腹で武事がおすきだから、謹んでその御意に沿うように。まず直ちに軍兵を座敷の外に配置し、門口まで居並ぶようにしておきなさい」宛はいわれたようにした。令尹は行ってみて驚いた。「これは何事だ」すると、無極がいう。「危険です。すぐお帰り下さい。どんなことになるか分りません」令尹は大いに怒り、兵をさし向けて郄宛の罪を責め、遂に殺してしまった。(内儲説下)(「中国古典文学全集 韓非子」 高田淳訳)
〇詩ヲ賦シテ志ヲ言フ
春秋列国ノ士大夫、会盟燕享ニ皆詩ヲ賦シテ其志ヲ言フ。実ニ殊勝ナル事、千載ノ下ヨリコレヲ想見スベシ。然スニ戦国ニ至リテハ、此事ナカリシト見エテ所見アル事ナシ。我幼カリシ時、先人ノ友ト飲宴スルニ、必ズ小謡アリ。多クハツハモノ、交リ頼アル中ノ酒宴哉、ナド云ヲ唱ヘテ、酒ヲ侑ム。今ハ其事ナシ。今ヨリ是ヲ想ヘバ、又殊勝ナル事ニテ、士風ヲ観ルニ足レリ。世ノ風俗移リ変ル事如レ此。戦国ノ詩ナキモ怪ムニ足ラザルナリ。(「諼草小言」 小宮山昌秀)
洒落言葉・隠語
・甘酒をなめさせる…譲歩すること
・大人のミルク…どぶろく
・五合徳利…つまらない人生
・むねはらい…胸の憂いを払ってくれるもの=酒
・待ち膏…宴会の前に少し酒を入れておくこと
・山芋を掘る…酔っぱらってくだを巻くこと
・霜消し…酒のこと(霜が消えるほどに温まるという意味)
・けずり友達…身代を削ってつきあう友達(飲み友達)
・スミマセン…どぶろくのこと(濁っているから)(「SAKE面白すぎる雑学知識」 雑学こだわり倶楽部編)
日本酒を温める理由
ところで日本酒をなぜ温めて飲むようになったのかは、明らかではない。ただ、中国では、寒い時には温酒、夏には冷酒で飲んだことが多くの書に記されている。たとえば白楽天は「薬銚夜傾残酒暖」「林間暖酒焼紅葉」とうたい、また趙循道(ちようじゆんどう)は「紅火炉温酒一盃」と詠み、そして元結(げんけつ)も「焼柴為温酒」という有名な詩の一節で、晩秋から冬にかけて酒を温めて飲む情景を詠んでいる。白楽天の「小盞吹醅嘗冷酒」にみられるように、春から夏にかけては冷酒を飲んでいた。李賀(りが)が「不暖酒色上来遅」といっているように、おそらく寒いときには、はやく体が温まるように酒を温め、夏に熱い酒はさらに暑さをよぶから冷酒にしたという単純な理由からだろう。日本での暖酒もはじめはこのような理由から行われだしたものと思われる。日本酒を温める第二の理由は、東洋的な医学思想を背景にした自然な食法、たとえば『養生訓(ようじょうくん)』などにもみる教えも根底にあったのだろう。貝原益軒は次のように戒める。「およそ酒は冷たくして飲んではよくないし、熱くしすぎて飲んでもよくない。生ぬるい酒を飲むのがよい。冷たい酒は痰を集め、胃をそこなう。丹渓(たんけい)は酒は冷飲に宜しといったが、多く飲む人が冷酒を飲むと脾臓をこわす。少し飲む人も、冷酒を飲むと食気をとどこおらせる。およそ酒を飲むのはその温かい気をかりて、陽気を補助し、食のとどこおったのをめぐらすためである。冷酒を飲むとこの二つの利益がない。ぬる酒は陽を助け気をめぐらすのに及ばない」。すなわち冷酒は身体によくないという考え方も、燗をする要因の一つになったのだろう。第三の理由は、客に対する温かいもてなしという心づかいから出た飲酒法であるということだ。燗をしてもてなすという習慣が一度出来上がると、「燗をした」という行為が、酒に手を加えてから客にさし上げるという礼儀として定着する。そうすると手を加えない冷酒を出すのは失礼であるという考えに結びつき、燗をする習慣が続いてきたのであろう。このほか、日本酒は麹を使った酒であり、冬造られたものが夏を越すと熟成して風格を増すところから、そういう酒を温めると、口当たりがまろやかでコクが乗るといった理由で燗を好んだ人もいたのだろう。さらに、燗をすると刺身や酢のもの、煮魚との相性が良くなるという人も少なくなかった。そして最後の理由は、飲む速さと酔いの速さを調整するためでもあったのではないか。「親の意見と冷酒(ひやざけ)は後からきく」の譬(たとえ)の如く、冷酒は喉(のど)ごしがよいからどんどん入っていって、後から急に酔いが来ることが多く、悪酔いの原因にもつながるが、熱い酒であると、味も香りもアルコール分もとても強く感じるので、チビリチビリとやることによって、酔い加減にバランスがとれるからである。(「日本酒の世界」 小泉武夫)
玲瓏随筆
酒後に紅柿[べにがき]を多く食すれば、はなはだ酔いて正儀を失うと。傍(かたえ)なる人曰[いわ]く、柿は酔[え]いを醒[さま]すとこそいえ、柿にて酔うとは心得ずといえり。曰く、諸楽ともにこれを用いるに時あり、時を得ざる時は、すなわち薬かえって毒と成る。その時を得る時は、すなわち毒も、またかえって薬と成る。寒は熱に勝つといえども、時を得ざる時は、すなわちかえって熱を助けて人をして熱殺せしむ。けだし酒を飲む事数盃[はい]にして、酒胃にありていまだ順ならざる時、柿を食する時数顆[か]なる時は、すなわちその酒を覆留して酒気順ならず、胃中に留[とど]まりて悶[もん]絶す。酒後紅柿を食えば、心痛するも、またこれに譬[たと]うるなり。酒ようやく半醒[はんせい]に至りて、喉[のど]口乾[かわ]きて湯を思う時、熟柿[じゅくし]を喫する時は、すなわち端的に醒め渇を治す。(玲瓏随筆)(「飲食事辞典」 白石大二)
良寛の詩
日々日々 又(マタ)日々 日〻日〻又日〻 良寛
閒(コノゴ)ロ児童ニ伴ツテ此身ヲ送ル 閒児伴児童送此身
袖裏(シウリ)ノ毬子(キウシ) 両三箇 袖裏毬子両三箇
無能ニシテ飽酔ス大平ノ春 無能飽酔大平春
毎日毎日、のんびりと童(わらべ)たちと一緒に、遊び暮らしている。袖(そで)の中には何時(いつ)も手毬(てまり)が二つ三つ。能無しで大平の春に堪能(たんのう)している。芭蕉の「能なしの寝(ねむ)たし我をぎやう/\し(行々子 ヨシキリ)」(嵯峨日記)にも似た心境がうかがわれるが、それよりも良寛自身の手毬唄、「つきて見よ一二三四五六七八九(ひふみよいむなやここ)の十十(とをとを)とをさめて又(また)始まるを」(二三六㌻)の無心の唄を、いっそう鮮やかに連想させる。(良寛詩集)(「古典詞華集」 山本健吉)
【山梨県北杜市・山梨銘醸】
同じ首都圏なら、山梨県北杜市、旧甲州街道沿いに建つ創業1750年(寛延3年)の山梨醸造も、多様な楽しみが待つ。まず直行すべきは、試飲コーナー。銘酒「七賢」はなめらかな喉ごしの純米吟醸「天鵞絨(びろーど)の味」やさらりとした裾捌きの純米大吟醸「絹の味」など、奥ゆかしい旨味のなかに名前に込められた個性を感じられる。さらには、仕込みに使われる水をたっぷり試飲できるのも、この蔵の魅力。酒の原材料を問われれば「米!」と答える方が多いと思うが、その8割は水。輪郭を描いたり、背骨となったりと、水は酒の味わいに大きく関係しているのだ。この蔵の仕込み水は、南アルプス甲斐駒ヶ岳の伏流水。ふんわりやわらかく、軽やかな余韻を舌に残して喉を過ぎる。酒と呑み比べてみれば、そのしなやかさと清々しさがしっかり生きているのがわかるだろう。敷地内には和食処「臺民(だいみん)」があり、「鮭の麹漬け」や「甲州豚の塩麹漬け焼き」といった、発酵の魔法で旨さを増した美味なる品々が揃う。「七賢」にぴたりと寄り添うのは、言うまでもない。すいすい呑んでしまうのだ.。(「ニッポン「酒」の旅」 山内史子)
(六)しよがえぶし
東坡(とうば)山谷(さんこく)淵明(えんめい)李白(りはく)晉(しん)の七賢(けん)白楽天(はくらくてん)も、ずんとてうじてあいせしといの、それはもろこし我朝(わがてう)にては心よし田の兼(けん)もじ様も、酒を飲めとてゆるされた、しよんがえ
てうじて-長じてにて、すぐれての意か 兼もじ-兼好をさす(「若みどり」 藤井紫影校訂)
酒飯論
さて酒と何かと対立させて上戸下戸の論争を面白く描こうとした試みは、どうやら『酒飯論』にはじまる。『酒飯論』の上戸、下戸、仲裁者のそれぞれが一向宗、日蓮宗、天台宗の立場を表明するので、三者が対立を深める一五二〇年代に『酒飯論』の成立をみる説もあるが、なお議論すべき余地はあろう。現存の『酒飯論』は十六世紀初期の成立としてよいが、その原形は十五世紀にさかのぼる可能性がある、いずれにしても十六世紀後半に成立する『酒茶論』よりはかなり早く、室町時代後期には誕生している。さて内容は、造酒正糟屋朝臣長持と称する大上戸と、飯室律師好飯という僧で、「こづけを好む最下戸」、さらに中左衛門大夫中原仲成といって酒も小漬も好む、名前からして仲裁役の三者である。まず造酒正長持は酒の徳を説明し、風流の酒、百薬の長たる酒、神に供える酒等を延べ、最後に念仏を誦して終わる。その中に出る「下戸のたてたる蔵もなし」というのは当時の俚諺(りげん)であったが、対句は「上戸はあはれ丸裸」というもので、貧福は生まれつきのもの、上戸は酒で身上を潰すことがあっても、下戸だからといって金持になれるわけではない、という。つづいて下戸の飯室律師は、まず酒の害を説き、それに対して飯のいろいろをあげて飯尽くしを述べ、茶会の面白さにふれる。最期は日蓮宗の妙号を唱えて終る。三番目の仲成は、文字通り中庸の酒を主張し、「飯をも酒をもよき程に、すへならべつゝのみくひて、一ごはかくてぞよかりける」という次第。面白いのは酒飯ばかりでなく、貧福も年齢も、姿かたちも役職も、官位も威勢も中位が一番よいものだという仲成の主張である。日本人の中産階層志向は室町時代からあったのか。この中庸の酒こそ、今日の酒の源流なのである。(「酒と社交」 熊倉功夫)
新潟清酒研究会
新潟清酒研究会(通称「酒研」)は、一九七三(昭和四十八)年、当時の新潟県醸造試験場長・島悌司(ていじ)氏の提案によって創立された。それまでは、大学で専門教育を受け、企業に雇用された酒造技術者は企業内で研鑽(けんさん)を積むことがもっぱらであったため、将来の新潟清酒を担う技術者を組織化して交流を活発化にし、企業横断的な情報交換の場を設けることが会創立の目的であった。同会は、県内各酒造会社に在籍する酒造技術者によって構成、運営され、若い技術者にできるだけ自由な発言と活動を保証しようと、規約には「正会員は五十歳以下」と明記されている。発足以来、同会はさまざまな研究プロジェクトや講演会などの活動を精力的に行い、主なものに、七七(昭和五十二)年に新潟県酒造組合から委託を受けた酒造好適米の新品種の醸造研究、八一(同五十六)年に新潟県技術賞を受賞した肉食に適する新しい清酒の開発プロジェクトなどがある。こうした目覚ましい成果を上げ、二〇〇三(平成十五)年には創立三十周年を迎え、県酒造業界の技術的基礎を担う重要な存在となっている。同会の運営は会員である酒造技術者個人の自主的な参加に負っているが、この背景には彼らが在籍する各酒造会社の理解と協力の上に成り立っている。技術者同士が互いに切磋琢磨を重ね、酒造技術の研鑽を積むことで新潟県酒道業界全体のレベルアップを図ろうという、一企業の利益だけにとらわれない懐の深さがうかがえる。(「新潟清酒達人検定公式テキストブック」 新潟日報事業者)
花、果実、木質などの風味-スペインの男性
「日本酒はこれまでに飲んだことはあるけど、喉から食道にかけてカ-ッとした感じだね。でもこれはスムーズで飲み易いな」飲んだ酒というのは熱燗で?ときけば、「燗の酒も常温の酒も」といい、吟醸酒の優しさは女性向きだという。熟成酒については「フィノのシェリーのような味がする。花や果実を思わせるところもいい。木質の風味も感じるし、スムーズで旨い。私はこちらのほうが好きだな」と、熟成酒がことのほか気に入った様子である。さらにその上、アペリティフとしても申し分ない、とつけ加えた。この人のブースはツナなどの加工食品を扱っているところだが、スペインのそのような食べものにもよく合うともいっていた。やはり、シェリーに馴れた味覚とすれば、それにより近い熟成酒のほうが親しみ易かったのだろう。花や果実を思わせるという表現が、吟醸酒ではなくて熟成酒のほうを指したのにも興味をひかれた。(「知って得するお酒の話」 山本祥一郎)
日本盛
日本盛は、元禄の頃には「盛」という名で出ていたようで、日本盛となったのは、幕末の頃からといいます。今でも、酒屋さんの間では、サカリと呼ばれていて、その積極的な販売政策が、しばしばウワサにのぼります。とくに、白鶴との二位争いは、激しいので、よく知られるところですが「酒類食品統計月報」の調べでは、昭和52年度の出荷は第三位で、39万1千石でした。白鶴は40万5千6百石です。ちなみに、一位は伏見の月桂冠で、65万3千石でした。日本盛の製品では、ホームタイプの製品が、他の蔵にさきがけて、売り出された特色あるものの一つですが、山村聡を中心に、芸能人をたくさん使ったPRで、ブランド売り込みに熱心な点は、際立っています。最近は、屋外式の調合タンクが設置されましたので、蔵の感じも変わりました。(「灘の酒」 中尾進彦)
大酒の戒(いまし)め
貴丈常に大酒せられた候故(そうろうゆえ)、此(この)文句を写して大酒は無用に存候(ぞんじぞうろう)、仍(よつて)一句
朝かほにわれは飯食う男かな 芭蕉
この貴丈(相手の男性に対する尊称)というのは有名な其角(きかく)で、この文句云々と言っているのは、尊朝親王の御作と伝えられる飲酒一枚起請(きしよう)と言われるものが前に付してあるが、ここでは句だけを記すにとどめる。句意は、「自分は世人と全く変わらず、朝早く起き、小庭の朝顔を眺めて飯を食う平凡な男なのだ」ということで、俳句に託して、芭蕉が宝井其角の豪酒を戒めたものと、ふつう解釈されている。其角は性豪快、江戸に生まれ家業の医を学んだが、一四、五歳の頃、蕉門に入った。照降町に住んでいたころは、嵐雪(らんせつ)、破笠(はりつ)なども同居して、大いに飲み、かつ遊んだ。芭蕉はこれに対して色々心配したのだろうが、それで禁酒するような其角ではなく、その後もますます大酒したらしい。もっとも、芭蕉自身酒を飲まなかった人ではない。「宵のとし空の名残おしまむと、酒のみ夜ふかして、元日寝わすれたれば、 二日にもぬかりはせじな花の春」(元日は寝過ごして大しくじりをやったが、二日にはしくじらぬよう心懸けて、めでたい正月を祝いたいものよ)という句があるほどの酒呑みで、 呑明(のみあけ)て花生(はないけ)にせん二升樽(だる)(さあ皆の衆、この二升樽を余さず飲みあけて、ちょうど真盛りの桜を活(い)ける花活けにしよう)という句もあるくらいだ。これで見ると、大酒に見えるが、この詞書(ことばが)きに「尾張の人より濃酒一樽に木曽の独活茶一種を得られしを、ひろむるとて…」とあるから、いずれ、門人たちに振る舞ったのであろう。二升樽を飲み開けると言っても、もちろん芭蕉の酒量ではない。また、 花にうき世我が酒白く飯(めし)黒し(世間は花に浮かれて楽しむ春だが、貧しい自分にはむしろ心憂(う)い世の中だ。飲む酒は濁り酒、飯は玄米飯という暮しでは。)などという句もあり、世捨て人のわが身の境涯を嘆じている。当時の芭蕉の生活状況が眼に見えるようだ。(「料理名言辞典」 平野雅章編)
アルコール症者の子供
子供たちがベッドの下や押し入れの中に隠れる、という話をよく耳にする。子供たちは連れ立って屋根裏部屋に行き、父親の帰りを待つ。父親がどんな状態か見当もつかない。やさしくしてくれるだろうか、たたかれるだろうか。決まってそのどちらかで、そのような境遇では、子供たちは落ち着いた生活は送れない。しばしばこのような子供は、標準以上の成績をおさめる。人より優れていなくてはいけない、自分自身を強化するよりどころが必要なのだ。しばしば、そのエネルギーは、学校で一番になることに注がれる。グリー・クラブや、バンドに入り、学校新聞で活躍する。多くの活動にかかわって、並み以上の成績をおさめる。しかし、孤立しがちで、他の子供とうまく付き合えない。リーダーになるが、独りぼっちである。アルコール症者の子供は、友達を家に連れてこなくなる。境遇が不安定なので、家についたら何が起こるかわからない。それが恐ろしいし、恥ずかしくもあるので、どぎまぎするような立場にならないよう、極力努める。長期にわたって受ける影響は、男の子でも女の子でも、同じであろう。ほとんどの子供は、長じて異常な生活を送る。アルコール症となるケースも多い。アルコール症者と結婚する者も、かなりの数にのぼる。ほとんどの者は、逆境の生活を体験する。円満な人間とはならないのである。アルコール症の子供は、成人しても自己評価は低く、他人を信用できず、敵意、怒り、恐れ、恥、自責の念と対処しなければならない。すべてに対する自責の念は、まったく何の根拠もない。しばしば、両親のアルコール症をはじめ、すべての否定的なものに責任を感じる。結婚について歪んだ考えを抱き、満足な結びつきができず、現実にも想像上も、性的に常軌を逸しやすいという問題を抱えている。アルコール症者の子供はマイナスの見本を見て育つだけでなく,驚くほどの暴言、肉体的、また、しばしば性的陵辱を受けて成長する。子どもたちは誰にでも喜ばれようとする。異常な環境での成長は、異常な生活となる。それをのり越え、家を離れて初めて、他の人はそのような生活を送っていないことに気がつく。(「アルコール依存症」 デニス・ホーリー)
その方の父は毎年死んだか
義公(徳川光圀)はあるとき、誰であったか、ご前で酒を賜った。そしてお肴(さかな)も下さった。ところが某は、これをそばに置いたままで、箸をとらなかった。「なにゆえに食しないのか」とお尋ねがあった。某は待っていましたとばかりに、「きょうは亡父の忌日でございますので精進いたしております。」と申しあげた。すると義公は、「それなら、その方の父は毎年死んだものと見えるな。」と、おたわむれなさった。すると某は負けていず、「公には毎月二十九日ご精進あそばさせる。先君威公(徳川頼房)には毎月ご逝去なさったと見えまするが。」と申しあげたところ、公もお笑いなさったという。こういう義公のおたわむれのうちにも、やはり教訓があるのを見出せるのである。「其の方は父の忌日で精進だから肴は食わぬと言いながら、酒を飲んでいるではないか。その点で、その方の行為は矛盾している。これははたして、心からの精進と言えようか。儒教徒の多くがするような、虚偽の形式にとらわれたものではあるまいか。」と義公は申された。(「人間義公」 大内地山)
ちやびん[茶瓶]
花見や野掛などに弁当などと組みに持つて行く道具、引いては下僕、弁当持ちの下男をいう。-
⑤人同じからず 茶びんと 貧ぼう樽 (樽三八)
⑤唐の劉廷芝七言律、悲白頭中の一節、年年歳歳花相似たり、歳歳年年人同じからずの文句取りであるが、茶瓶と貧乏樽とは似て非なるものだということ。-(「古川柳辞典」 十四世根岸川柳)
食物年表1600-1650
1608・呂宋王が将軍にいそぱにや酒を献上
1612・島津家久が将軍に琉球酒を献上
1619・堺商人が大坂から江戸へ油、酒、酢、醤油などを回送し、菱垣廻船がはじまる
1642・忍冬酒、延命酒を将軍に献上(「日本史分類年表 食物年表」 桑田忠親監修)
熱燗(燗酒)
江戸時代までは冷酒を原則としていたので、「熱燗」が季語となったのは幕末の『季寄新題集』(嘉永元年)で、冬之部・旧十月に、「あつ燗」とあるのが初見である。それを承けて、明治四十二年刊の『新修歳時記』が冬之部に、「熱燗。冬寒気を防がん為に、殊に燗の熱きを用ふるものあり」とあり、例句がないから、まだ公認されていなかったようだ。昭和二年刊の『新撰俳諧辞典』には、「熱燗・燗酒」の記載はないが、同五年刊の『最新俳句歳時記』と九年刊の虚子の『新歳時記』が十二月また三冬で取上げて、「酒うすしせめては燗を熱うせよ」という、つまらない自句を例句としている。その後山本の『季寄せ』が三冬で「熱燗。燗酒」とした。さらにその後、秋桜子の『現代俳句歳時記』は、秋桜子が下戸だったせいかこの二つの季語をカッとしているが、その他は冬の季語として定着している。
燗熱し獄を罵(のの)しる口ひらく 不死男
熱燗や男同士の労はりあふ 春一
熱燗や討入りおりた者同士 展宏
例句一の秋元不死男(ふじお)(昭和五二年没)は、新興俳句論者であったが、昭和十六年に俳句事件に連座して、二年間の獄生活を送った。終生庶民精神を貫いた。例句二の滝春一(しゆんいち)(平成八年没・九十四歳)は秋桜子門で、俳誌『暖流』の主宰者。同県人か、うだつの上がらない同士が愚痴をこぼし労り合うには、ボルテージの上がる熱燗が必要なのだ。例句三の川崎展宏(てんこう)は現役のぱりぱり。『寒雷』の同人で明治大学教授。朝日俳壇の選者である。ところで、この句を正直に解釈すると、元禄十五年十二月の払暁、赤穂浪士の大石良雄らが、本所の吉良邸に討入って本望を遂げた時、それぞれ退っ引きならぬ理由で脱藩した小山田庄左衛門、毛利小平太、田中貞四郎らが集まって黙々と熱燗を、という場面を想像するに違いない。だが、「熱燗」に限らず季語というものは、その句を詠んだ季節と時代(リアル・タイム)を保証するものだ、と私は考えている。だからこの句は一見、忠臣蔵の世界のようでも実は比喩句であって、老害の政治家や社長を諫止しようと決起した若手の議員や社員が、あと先を考えて中止した世の憂さ晴らしの熱燗、と私は解釈するのだが、私の勘繰りだったら、展宏さん御免なさい。
熱燗や屋台で飲めば雪となり 桐雨(「酒の歳時記」 暉峻康隆編)
酒屋名簿
而して当時に於ける洛中洛外の酒屋の全数が幾何であったかに関しては、奇跡的にも、応永三十二年、同三十三年の調査になる一巻の『酒屋名簿』が、『北野神社文書』中に保存せられている。この名簿によるとき、洛中を中心に、北は嵯峨谷、東は粟田口に亙る間に於て、三百四十七軒の酒屋が存在していた(国史学第十一号「北野麹座に就きて」参照)。この酒屋数は爾後応仁の乱に至るまでの約四十年間、さしたる増減を見ることなく存続したのでる。この三百有余の酒屋こそ、室町幕府の財源の一部を構成せる酒屋の全数に外ならなかったのである。ここでいわゆる酒屋とは、小売専門の小売酒屋ではなくして、「本酒屋」と時に称せらるるところの醸造酒屋である。(「日本産業発達史の研究」 小野晃嗣」)
小米酒(5)之事
一、小米勿論片白に造るへし。造り様諸事本米同前。但し小米ハ夥敷く沸く物也。大体より一限強く覚醒し切へし。当分呑口濃き様に候へとも、追日薄口に成、火を早く乞、足弱き物也。早く売払うへし。油断すれハ替る物也。
小米(こごめ)酒(5)
〇小米酒はもちろん片白で造ること。造り方はすべて粒米の酒と同じである。ただし、小米は非常に強くわくものであるから、ふつうの造りよりひときわ冷まし切るべきである。小米酒は、造りたては飲んで濃く感じられるが、やがて薄口になり、早く火入れを求め、日持ちしないものである。早く売り切ってしまうこと。油断すると変質するものである。
(5)小米(こごめ)酒 砕け米で造る酒。(「童蒙酒造記」 吉田元翻刻・現代語訳・注記・解題)
いなだ【稲田】
①鰤(ぶり)の異称。初期の称で、大きくなり鰤となるのである。
八杯の 酒でいなだの 生づくり 稲田姫に掛く
②稲田姫の略称。(いなだひめ参照)
八樽くらつて 稲田をも 呑む所 八岐大蛇(「川柳大辞典」 大曲駒村編著)
(増)盃事の式
[四季草]云 盃事と名付て 今世祝事にハ 親兄弟或ハ君臣盃をさして 乾魚なとを肴に挟み遣ハす 又 返盃して 右の如く 肴をはさむ事 是 甚略式也 本式にハ 先二三こんを出す 是にハ盃取かはしなしに 三献終て初献烹雑を出す、烹雑終て次に幾献も出す時 惣坐中酒宴になりて盃を取りかハし 肴をはさみ遣し 座中盃めくりて賑に興を催す 今世盃事と名づけてするハ 此酒宴の躰をかたばかりにまねてする也 今世ハこのまね事を 却て本法式生の事と思ふハあやまり也 是も戦国の頃世の中貧しくなりて 賑々しく真の酒宴の興を催す事もならずして そのかたばかりしたるハ伝りて 却て本式の如くなりいなるべし(「増補俚言集覧」 村田了阿編輯)
上戸
〇師走の十日ごろ、一条の辻に、大酒に酔い、ひどく寝こんでいる者がある。また、その日鳥羽から用をたしに上ってきた男がいた。これも少し酔っていたが、その男を見つけ、「お前の住居はどこ」と問うに、舌がまわらず、たわいもない声で、「あまがさき」と言うようである。気の毒だなあと車にのせ、鳥羽(京都の南郊)につれてゆき、便船をたずねて乗せてやった。この者を、ついてから、旅人の宿に舟からあげておく。酔がさめ、「これは何事か、私は京の六条の者で、あまがさき屋という者です」と、あっけにとられてたたずむ。ことのわけを語り聞かせると、肝をつぶし、どうにもならず、船賃、旅籠(はたご)の料金にと胴着を売り払い、みっともない姿で家にかえったのも一笑。(「江戸小説集 醒酔笑」 安楽庵策伝 小高敏郎訳)
寄鍋 よせなべ
魚貝・鶏肉・野菜など季節の材料を酒・味醂を加えた醤油汁で、煮ながら食う鍋料理。昔はたのしみ鍋ともいった。贅沢にも簡易にもできるのが特徴。
寄鍋や母にまいらす小盃 山本(「合本俳句歳時記新版」 角川書店編)
狂言と擬音語・擬態語
室町時代から栄えた狂言ほど、擬音語・擬態語の活躍する舞台芸術は見あたらない。なぜ、狂言では、溢れるばかりの擬音語・擬態語が用いられるのか?狂言は、滑稽感をかもし出して観客を笑わせくつろがせるために発達したセリフ劇。笑いをとるための王道の物まね。とぼけた梟の鳴き声と仕草のまねを見所にする狂言『梟山伏』は、言葉の通じぬ外国人でさえ笑わせることができる。梟をはじめ、蚊・烏・鳶・鶏・千鳥・犬・猿・狐・牛の鳴き声を写す擬音語が、狂言では、笑いをとるための必須アイテムなのである。さらに、狂言に擬音語・擬態語の多用される原因が、もう一つある。それは、擬音語・擬態語に状況説明の役割が負わされていることである。場面が良く変わるのに、狂言は大道具が全くない。家も、戸も、そんな舞台で、他人の家の玄関前にいることを観客に分かってもらうにはどうしたらいいのか?演者が、戸を開ける仕草をして「サラ サラ サラ サラ」と言うのである。これで、戸が開いた。(「擬音語・擬態語辞典」 山口仲美編)
ルバイヤート(抄) オマル・ハイヤーム 小川亮作(おがわりようさく)訳
酒をのめ、土の下に友もなく、またつれもない、眠るばかりで、そこに一滴の酒もない。
気をつけて、気をつけて、この秘密、人には言うな-
チューリップひとたび萎(しぼ)めば開かない。(「酒の詩集」 富士正晴編著)
清酒酒質の様変わり
①揺籃期=甘酸混交 僧坊酒とくに奈良酒系を引いた清酒(すみさけ)は、甘口なわりに強い酸味を発揮した。アルコール分も比較的低く、清酒とはいえ醸造酒としての若さが目立った。②鴻池・池田・伊丹=辛口醇酒成長期の清酒で、酒精度が高く辛口の味わいが江戸などで歓迎された。剣菱・七つ梅など銘柄酒が席巻し、地酒は田舎酒として精彩を欠いた。③灘五郷時代=淡白上品 伊丹酒に変わり灘酒が台頭したのは天保期とみられている。水車の採用で米の精白度が格段に高まり、名醸水をも得て、磨き抜かれた上品(じようほん)酒がもてはやされた。④近代=芳醇吟醸 諸白から清酒へと名が変わり、甘くてコクがあり芳香の高い酒が好まれる。酒格も高級車から安酒まで層が厚くなり、格差の拡大が目立った。⑤昭和戦前期~終戦直後=酒質の凋落 物資の不足や統制経済の影響を受け、酒類の堕落が際だった時代。清酒も金魚酒や模造酒が巷に氾濫し、粗悪で危険な密造酒が出回るなど、酒質云々以前の状態にあった。⑥現代=百花繚乱 いま、清酒も個人嗜好による選択の時代に入った。酒造業界もハイテク時代に入り、あらゆる酒種・酒質・グレードの酒が出回り、すでに左党天国の時代を迎えている。(「日本の酒文化総合辞典」 萩生待也編著)