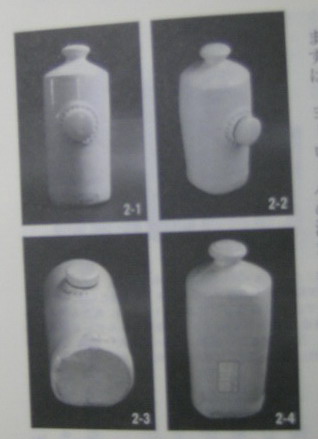表紙に戻る
フレーム付き表紙へ
御 酒 の 話 14
七月八日(土)晴 淇園の酒十徳 ギルガメシュ叙事詩 煮売茶屋 昭和二十八年七月 七十一の婆々芸者 ハーフィズ 七月四日 押上潜伏 別腸 独酌党 金田一さん 飲みかつ食う ぽ庵おすすめの酒 ブランデー一本 尻摘み祭り 六月三十日(金) 豆腐のせい 地獄 六月二十八日(水) 利佳 牢屋 サイダー瓶入り特級酒 五斗兵衛 ウエスキー 呑酒百杯 煎り酒は九二一が伝 はせ川 ベトナム戦争時代 高村光太郎の酒歌 ヴェルレーヌ 離し注ぎはせぬもの 庭園学派 酒を少々 鴻池屋 アンゴスチュラ・ビターズ あげ癖 大すじ 夜ハしらじらと 料理持参 シャンパンにおから 六月二十日。金曜日。 アジアの「地酒」 卒業生 玉杯 町人ぶくろ 無害 流頭日 気圧のせい 梅瓶 ロケット燃料 昭和二十五年六月 珉里隠居 白墮の酒 萩の花盛はよき酒なし 清酒の防腐効果 梅に鶯 「日本酒の定義」の結論 石本省吾 神様の涙 坂口安吾、畢卓 曹源寺 バロン 嫌酒権 杯にあたった 喝将 六月一日(木) 花嫁 伊丹酒から灘目酒へ パブ・クロール 三パイントのラム酒 一句ぬき玉へ 箕作と稲垣 日々疲々 いやいや三盃 酒のよき夜は 酒一元説 飲み友達 「養生訓」食べ合わせ例 「遊仙窟」の酒器 「遊仙窟」の酒器2 絶えいの会 ワインの鑑定 「下級武士の食日記」 男の酔い方 「三田文学」の時 J・ブース 酒茶論 酒の功徳 五姓田芳松 石川島燈明台 盃中の蛇影 狗に肴の番 仮説 アブサントは悪魔の酒 ラッカ 食客三千人 酒の給仕 エビスビールあります。 卓袱料理 数字 大空式左衛門 晩酌のある風景 ビール工場 関矢酒店 梅崎春生、ニュートン コップ半分の甘口ワイン 25~70グラム 「あまカラ」 権蔵 瓢正とますだ タテ看のタンカ 登高亭等の酒句 五月十一日(東京) 酔つ払ひは大嫌ひ 因幡堂 はい杓に勝えず 明治七年の物価 サリチル酸 ばけもの スコッチ、ポート 文は人なり ウォッカ瓶詰め水 放哉の酒癖 一滴万粒 三醸酒の試醸 ビーラー 鶴歩町と平野町 夫婦に大切なものは一杯のお酒 馬乳葡萄 ケルト語ウイスキー お出ッきりでござい 明日より禁酒 酸素パーティー やっぱりそうか いい話だが 水割りブランデーと中国料理 岩谷松平 式三献 ボトル・ネック奏法 年寄り 夜明けあと(2) 飲むには減らで吸うに減る 旨味 ワインは究極の酒なり 四月二四日 荻流松前焼 解僧卒 牧水・弘元・謙信 未亡人 猩々と組打ち 一献酒は飲まぬもの 四月二十二日(土) 十面 鶏卵の味噌漬 小島喜逸 月下の一群 童子絵扇面あらすじ 搾酒場 The spirit is out バッカス号 鍵の穴 銀子さん 海藤花 今日この頃の酒の味 飲まば朝酒 死なば卒中 麹がない 乃木大将 四月十二日(水)晴 縮緬で失礼 思いついた順 買うこと 主客心得の事 巡査商売仁王と按摩 酒というもの アルコールの作用 医者いらず 薑酒 消腸酒 相酌はせぬもの うなこうじまつり 錦木 お神酒のふるまい ウイスキイーフロート 張蛸 料理用二級酒 酒の先生 飲まぬ酒には酔わぬ ひつかいてとめがす売はまけて行 独裁者の酒量 伊勢神宮の神酒(1) 枕元にビール 小野忠重 自序 ときのかね 酒飲むは、罪にて候か 初代川柳の酒句 お銚子十本 宮廷の花宴における饗宴の儀 拳相撲 美娘と秦重 飲まぬ酒に酔う 日本酒の原点 焼きめしとウイスキー 造り酒屋 しとぎ センダイムシクイとホオジロ 酒は少し飲んでたばこはやめる 清酒一升とスルメ一匹 初鰹 9対1 星 下戸の知らねえ、うめえ味だなァ。 大叔父メッケル 伊豆酒 町内の若衆 三月十七日(金) 豆腐食い 伊豆酒 死人に口なし 強清水 ビールのアワからノーベル賞 固めの盃事 歯のこと とっときの酒 大槻磐渓と頼山陽 のけて通せ酒の酔い お流れちょうだいとお酌 メリー女王 大飯食いまつり ニッカウヰスキー 乞食 タダ酒 宴会 紅葉にはたがをしへける酒の間 西洋の湯たんぽ 日本の湯たんぽ ことわざ(2) アブサン禁止 ヤマブドウの酒 【ゆだねる】 酒楼へ 夜明けあと 大粒の雄町 北島雪山 向嶋の花見 花見の薬 花折 サイダサクラ 酔せた先を呵る女房 小金井桜
七月八日(土)晴 暑 〔御殿場ロケ旅館泊り〕
寝ていると新宿紀伊之國屋の老主人が、大変に酔払って乱入してくる。これから何処とかへ飲みに行こうと言う。私はテンから断わる。なかなか退却しないので、これは早く酔わすに限ると思い、アルコールを大コップに水で割って出す。ウンこいつは強いや、と流石に辟易の態。何とかという店へ行けば、鮪が五貫目あって、酒があって大したもんだという事を何回でも言う。ムーランの佐々木千里が、この土地の忠魂碑に何千円寄附して好い顔になったという話も三回ぐらい。コップを口へもって行ってから飲むのかと思うと、それを茶ぶ台において、また喋る。実に迷惑千万であった。でも竟(つい)に、アルコールを一息に飲み干し、フラフラになって帰って行った。翌朝聞くと、老人のガラガラ声で宿屋中眼をさましたという。(「夢声戦争日記(抄)」 徳川夢声)
昭和19年です。 戻
淇園の酒十徳
柳沢淇園(きえん)(一七五八年)の『雲萍(うんぴょう)雑誌』には、<飲酒の十徳 礼を正し、労をいとい、憂いを忘れ、鬱を開き、気をめぐらし、病を避け、毒を解(げ)し、人と親しみ、縁を結び、人寿を延ぶ。>を掲げる。①飲酒には作法があり、それを守ることによって、礼儀を正しく実行する。②酒を供することによって、他人の骨折りをねぎらう。③心配事を忘れる。④ふさいだ気持ちを晴らす。⑤心をよく働かす。⑥病気にならないようにする。⑦毒を消す。⑧人とよく付き合う。⑨人といろいろ関係を付ける。⑩人間としての生命を長くする、長生きする。(「飲食事辞典」 白石大二) 戻
ギルガメシュ叙事詩
最も古いワインの記録としては『ギルガメシュ叙事詩』がある。これは十二枚の粘土板に楔形文字でビッシリと刻み込まれているのだが、ティグリス、ユーフラテスの二つの大河の河口あたりに栄えた古代バビロニアの王、ギルガメシュの事跡をたたえた英雄詩だ。そのなかに、ワインのあけぼのを読みとることができる。これは『オデュッセア』と並び語られる古代オリエント最大の文学作品だが、バビロニアの遺跡から発掘された、およそ紀元前二十一世紀のものとされている。その十一枚目には『その昔、ユーフラテスが洪水に襲われ、船大工たちは赤ぶどう酒、油、白ぶどう酒を飲み、七日目には船を完成させた』という記述がある。"バビロニアのノア"と呼ばれるウトナピシュティムが、どんな具合にして洪水から逃れたかを語っており、これがのちに旧約聖書へ引きつがれて『ノアの方舟』の物語になるのだが、この洪水がいつ頃あったかについては、わかっていない。<旧約聖書・創世記第九章二〇-二一節>には、「ここにノア農夫となりてぶどう畠とつくることをはじめしが、ぶどう酒を飲みて酔い、天幕のうちにありて裸になれり」の一文がある。(「洋酒こぼれ話」 藤本義一) 戻
煮売茶屋
江戸に零細な屋台や小屋掛けが多かったことは事実であるが、一方で常設の店舗を構えた食べ物屋もしだいに増えていった。これは系譜的には、先に『東海道名所記』で見たような煮売茶屋の類に属し、もともとは道中に設けられた休息所である茶店に、その起源が求められる。すなわち客に茶を出して休息させる茶店は、やがて宿場や門前町にもできて、茶や菓子のほかにも酒や肴を提供し、さらには大都市の盛り場にも出現するようになったのである。これを出茶屋と呼び、はじめは葭簀張(よしずばり)の床店のような簡便な施設であったが、徐々にしっかりした店を構えるものが増えたため、茶を販売する葉茶屋に対し、茶菓や酒肴を出すものを水茶屋と称して区別した。なかでも酒を置き、調理した食べ物や食事を提供する店が煮売茶屋と呼ばれるようになり、元禄期(一六八八-一七〇四年)になると、京都は祇園の二軒茶屋、江戸浅草では金龍山の奈良茶店屋が知られるようになった。 戻
昭和二十八年七月
実際、市場は目まぐるしく動いていた。だが、それは酒類消費の拡大による活況ではなかった。停滞した売上げをいかに維持するかに腐心する姿であった。食糧危機を乗り越えたあと、一本調子に伸びてきた酒の課税移出数量は昭和二十九年、一転して全種類が前年実績を割る事態となったのである。種類間の消長はしばしば起こる。しかし、すべての酒が減少したのは、戦後五十年間、たった一回、この年しかない。昭和二十五年六月に勃発した朝鮮半島の戦争は、三年におよんで、昭和二十八年七月ようやく休戦協定が調印された。それとともに、日本経済に大きな活力を注入し続けた特需景気も去った。(「酒・戦後・青春」 麻井宇介) 戻
七十一の婆々芸者
-又大阪北の新地の免税拍子重吉と云ふは、是も本年七十一才にて顔にこそ年の争はれぬ皺の寄て居れ、座敷の取扱に皺は見えず、客待遇のまめまめしき事、若手拍子の及ぶ所にあらず、同人は文政五年七月の出生にて、十才の春平野町の豪商炭彦へ腰元奉公に住込み、十八の時より二三の席へ移り、其後出来山和市と云ふ力士と夫婦になりしが、重吉が三十四才の時、夫出来山病死せしにより、其後は世の味気なさをかこち、綠なす黒髪を剃髪して余生を読経の中に終らんとしたるを、或人に止められて望みなき花街に留り、泪(なみだ)を酒に呑みて客の機嫌をとる事に弱りを見せぬ松の振、綠の色は髪になけれど、今尚客の座に招かれては一升酒さえ苦なしに傾け、本年に至るまで只の一度も医者にかかりし事なく稼ぎの上は兎も角も、老て益す壮健なる両妓の身こそ目出度けれ。<明二七・一・七、都>(「新聞資料 明治話題事典」 小野秀雄
編) 戻
ハーフィズ
現在のイランでは、娯楽のための音楽まで禁止されている。コーランに定められている禁酒が厳守されているのはいうまでもない。違反者は鞭打ちの刑に処せられるという。だが、イスラム法をきびしく施行したのは、ホメイニ体制がはじめてではない。十四世紀中葉、シラーズを支配したムバーリズ・ウッディーンは、酒場を閉鎖したことで知られている。だが、彼の息子のシャー・シュジャーが即位すると、酒場は再開することを許された。「葡萄の娘への弔辞(ナーメタージーブ)を書けば 友みな睫毛より流す血の涙 酒肆(しゅし)の門は閉じられても神よご安心を 虚偽(タズウイール)と偽善(リヤー)の店の門が開かれますから」 右は酒場閉鎖令が出たときに、ハーフィズがよんだ詩の一節である。そして、彼は解禁のしらせをきいたときに、いくつかの詩をよんでいるが、そのなかにつぎのような句がある。 「よき晨(あさ) 我が耳に届きたるふしぎの声 シャー・シュジャーの世ぞ、酒は遠慮無用 識見ある人 千万の言葉を呑み 口とざし世にかくれし時代は終わりぬ」 解放感はよくわかる。戦争が終わって、さまざまな統制、とくに言論の統制が解除されたときのよろこびは、、私などにはまだ忘れることができない。文革が終焉を告げたときの解放感を、私は多くの人からきいている。(「六甲山房記」 陳舜臣) 戻
七月四日
明治三十二年七月四日、日本麦酒会社がビアホールを開店した。そのころ、たくさんの地方ビールがあったが、その銘柄を見てみるとじつに日本的なのである。※
浪花、富喜、野田、テング、大橋孔雀、九重、加東、半田、キマル、孔雀、上菱、カイゾル、東陽、大阪、ラガー、布引、ライオン、達磨、日本、函館、三菱、白山、富久、キツネ、日の丸、ミヤコ、テーブル、ボック、マルコ、浪速、大黒、コック、ニシキ、旭
これだけの銘柄があったというのも日本酒の地酒と同じ理屈である。(「ことばの情報歳時記」 稲垣吉彦) 戻
押上潜伏
上原(仙之助)は元柳河の立花飛騨守鑑寛(あきもと)の家来であったが、実兄木下の進退に同感して脱藩して彰義隊に加わった。なかなか才知縦横という快男子で、彰義隊敗走後は、たちまち髪を剃って墨染めの衣の托鉢僧に化け、市中を潜行して同士との連絡をとった。向島の押上に四、五軒の居酒屋を開いた。上野の「敗走」をここに忍ばせ、早朝から田舟(たふね)で二人三人と釣りに出した。舟の中で、酒をのみ安心してねむらせた。夜はみんな居酒屋へ帰った。潜伏に必要ないろいろな服装や金も上原が工夫して与えた。上原は少なくとも五百人位の人数を集めたら、もう一遍旗をあげる考えであった。しかしかく成り果てては事悉(ことごと)く志と違う。苦心して百七十人だけは同盟を得たが、その上はもうどうにもならなかった。さすがに彰義隊再挙は思いとどまらざるを得なかった。がっかりしていると、榎本が艦隊を率いて蝦夷へ行き、ここで新しい一国家を建てる計画ありと耳にした。仙之助は手を打って快哉を叫び、一夜身辺の同士三十余名と大茶舟に乗って、竪川を下って隅田川へ出て、品川沖の榎本艦隊に投じた。上原は後鷹羽玄道と改名したが、「自分の生涯で、一番苦しい思いをしたのは押上に潜伏していた時で、到底語ることは出来ない」といっている。(「よろず覚え帖」 子母澤寛) 戻
別腸
ところで、新しく唱えられた説ではない。昔から「酒に別腸、碁に別智」という格言がある。一升酒飲む人はいくらでもいるが、ではそういう人が同じ液体だからといって水や茶やジュースなどを一升のめるかというと、これは駄目。また腹一杯チャンコ鍋なんかを食べて、これ以上お茶一杯飲めない、というような時でも、酒ならなんとか腹におさめることができる。何とも不思議な話で、これはきっと飯や魚や水、茶など普通の食べ物を入れる腸とは別に酒だけ入れるためのもうひとつの腸があるに違いない、と推測したのが、「別腸」という言葉の生まれたゆえんである。『五代史』という約一千年前の中国の書物にこんな逸話が記されている。今の福建省にあたる?(びん 門+虫)の国に維岳という大酒飲みがいた。それが評判になり、王様の目にとまった。「維岳とやら、そなたは体が小さいのにどうしてそんなに大酒がのめるのじゃ」と王様が問いただしたのに対し、維岳は威張って、「酒に別腸あり、と申します。体の大小には関係ないのです」と答えたばかりに「それは珍しい。その別腸とやらをぜひみたいものじゃ」とつかまえられて腸を断ち割られてしまった、というのだが、これからみると、ずいぶん昔から「別腸」説があったらしい。(「言葉の雑学事典」 塩田丸男) 戻
独酌党
夜は六時ごろから晩酌をはじめる。ぼくは独酌党でね。客が来ても徳利をあてがって、手酌でやってもらうんだ。人によっては、注いでもらいたそうな様子がみえるけれど、それでも頑固にささないんだ。適量はいちおう二合ということになっている。客があればもちろん便乗するさ。銘柄は菊正。むろん樽が好きだが、飲み口のつけられる人がだんだんいなくなって来たもんで、瓶詰で我慢している。肴には、豆腐が一番いい。近所にいい清水が出るせいか、うまい豆腐を売っている。めしは握り鮨の一個分ほどしか食わない。その代り、蒲焼きや刺身をよく食べる。食後テレビをつけるが、これはぼくにはいい睡眠剤だ。(「里見弴随筆集」 紅野敏郎編) 戻
金田一さん
その時の金田一さんの話は面白いんですよ。鹿児島の日教組によばれたとき、酒飲みが非常に多い。しょうちゅう飲みですね。とくにその方面で有名な人がひとりいたそうです。その人と一緒になると、とにかくしょっちゅう注ぎにくる。そういう人は目の前にあぐらをかいて注ぐ。ところが金田一さんには「手」があるんだそうです。僕に教えてくれたのは、そういう時にまず、「今日司会をしてくれた方はなんというお名前でしたかね」と聞くんだそうです。そうするとだいたいは後ろを振り返って席を見渡して司会者を捜す。その間に盃洗を用意しておいて捨てる。ただね、鹿児島というところはかならずいれかわりたちかわり注ぎにきますから、またまた別な人がやってくる。こんどは「先ほどここに坐っていた人はなんという方ですか」と聞く。その間に盃洗へ…。それをずーっと続けてやっていた。金田一さんは少しでもお酒が入ると眠くなるので、ほんのわずかだけ口につけても、席にいたままうとうととする。やってくる人を適当にあしらっているうちに、夜明けに過ごしたそうです。まだ戦後間もない時期で、悪い酒でしたから、みんな市場のマグロみたいに寝てしまった。ところが、さっき申し上げた大酒のみで天下に名だたる男と、金田一さんだけが起きていたんだそうです。それで後々、金田一博士は彼に劣らない大酒豪だ、というので、新聞の記事になったという話です。それ以来、鹿児島へは怖くて行けないとおっしゃいました。やはり飲まない人というのは、いろいろと苦労しているんですよ。(「下戸の酒癖」 玉村豊男編) 下戸友達の大河内昭爾の語る、金田一春彦の話です。 戻
飲みかつ食う
私は酒のみの部類にはないれない。酒がなければ生きていけないというほどの身の入れかたもしていないし、それに酒をのむと胃の腑が刺激されるためじゃないかと思うのだが、ひどく食欲が増進して来て、酒のさかなでもなんでも、めちゃくちゃに食うようになってしまう。私を招待してくれた人は、何から何までいんな食べてくれて、つくった者としては、ほんとうにはりあいがあるといって喜んでくれる。だから私はますますいい気になって飲み進み、食い進むということになってくる。ところが、友人はこれをはなはだいやしいことだという。入江はどうもさもしいところがあっていかんというのがその非難である。しかし私は多少の批評があることはもとより覚悟の前であって、そんなことは気にかけずに、今後も従来どおり、飲みかつ食うという態度をつづけていこうと思っている。(「侍従とパイプ」 入江相政) 戻
ぽ庵おすすめの酒
イタリアンな十割蕎麦にあうキリッと美酒 秋鹿 特別純米酒 山廃 無濾過生原酒 雄町
トキシラズのすき焼きにあうコク深い美酒 小笹屋竹鶴 純米大吟醸
キャベツと蛤のミルフィーユ風にあうダンディーな辛口美酒 春鴬囀 純米辛口ぷらす9
アナゴの広島風お好み焼きにあうふわっとまろやかな美酒 龍勢 吟造り特別純米酒
ヒラメの白身にあう貴公子たる凛々しさのすっきり美酒 貴 純米吟醸備前雄町50
夏野菜にもあうどすーんと滋味深いしっかり美酒 旭菊大地 純米酒 (「おかわり のん de ぽ庵 1」 漫画/なかはらももた 原作/イタバシマサヒロ) 戻
ブランデー一本
午後になって、日活の宣伝部の人が吉永小百合を連れてきた。吉永小百合が『伊豆の踊子』に出演するので、宣伝を兼ねて、やはり、挨拶に来たのである。川端(康成)さんは、部屋のなかと庭で何枚も写真を撮られた。宣伝用の映画の撮影にも応じられた。私はそれを見ていて、川端さんが何人もの美人女優と親しくしているという話は本当だということがわかった。それはそのなかの誰かに思し召しがあるというのとも違うし、美女をはべらすというのとも違っていた。いくらかミーハーの気味があり、もちろん、それとも違う。私は、やはり、すぐに女と同化できてしまう人という印象を払拭することが出来ない。川端さんは、吉永さんや日活宣伝部の人を近くの中国料理店に招待した。私も誘われたけれど、お断りして、ブランデーを飲みながら、お帰りを待っていた。中国料理店から、私のための料理が届いた。川端さんの奥様が、こう言われた。「うちの主人は、あれで、油断がならないんですよ」「まさか。…じょうだんじゃない」それは冗談が半分で、本気が半分であったろう。川端さんは、ずいぶん遅くなって帰ってこられた。昔のことであるから、遅くまでお邪魔するのには馴れていた。私は上等のブランデーを一本空にしてしまった。
(「旦那の意見」 山口瞳) 戻
尻摘み祭り
伊豆、伊東の尻摘み祭りは、日本でも珍しい奇祭の一つとして知られている。これは伊東市伊豆宇佐見の音無神社(祭神 豊玉姫命、安産の神)の例祭で、十一月十日に行われる。-
十日の夜は、社殿の灯明を消し、鼻をつままれてもわからぬ闇の中で祭典が行われる。式典の済んだ直会(なおらい)になると、暗中無言のうちに手さぐりで隣の人の尻をつねって合図し、神酒を土器についで、次々と回すことから、尻摘み祭りの名が生まれたのである。当夜は境内に集まる氏子たちが、互いに尻をつねり合って騒ぐのだが、そうつねられていては、尻も赤くなろうというもの。若い女たちは尻に座布団をあてがったりして、つねられても痛くないようにして来る。もっとも、つねってもらいたいなんて勇敢な女性も中にはいるだろうし、どうせつねるなら手触りの良い女性をねらうのが常である。とにかく尻に触れるのだから、高い金を出してバーの女の子の尻を触るよりはずっと安いことは請け合い。何ともはやユーモラスなお祭りである。また、この祭りは、一説にはこの神社の森陰で若き日の源頼朝と伊東祐親の娘、八重姫がひそかに会い、恋をささやきあったと伝えられ、その故事にならったとも言われている。(「日本の奇祭」 湯沢司一・左近士照子共編) 戻
六月三十日(金)
上野駅、一時四十分頃ホームへ入り、発車は二時四十五分。又もやロケーションなり。行く先は、石岡のグライダー場。五時頃、石岡着。K泉屋旅館。早速、スパイを放って、食の道を開かんとせしが、とても、坂下町のようなわけに行かないらしい。でも二軒ばかり開通したので先ず、すし長という料理屋へ。酒が水酒だ、これは駄目だ。鯖の天ぷら、さしみ、オムレツと並んだが、オムレツしか食えず。もう一軒、みどりというのへ。此処も水酒、ビール、又オムレツ。月田一郎と行ったが、話も弾まず、到底、坂下町の足下へも及ばぬが、でも、東京よりましなり、オムレツ位は、いくらでも食わせる。(「ロッパの悲食記(抄)」 古川綠波) 昭和19年です。 戻
豆腐のせい
それ以来先生(里見弴)の酒は「黒松白鷹」だった様である。昭和の初めに「菊正」を飲む様になられたのは、友人の水上瀧太郎に「八巻岡田」ですすめられてからだそうだ。「はじめて酒というものを飲んだのは中学生の頃で、出入りの酒屋の小僧にそそのかされて、目盛りのある薬瓶に入れた焼酎を飲んだ。八勺位を一度に飲んだので朦朧となってひっくり返ってしまったんだ。家人に知れて大騒ぎになり、可哀相に酒屋の小僧は出入りを禁止されてしまったよ」永年酒を飲んでいても先生がベロベロに酔ったのは一度だけだと聞いた。どんなに飲んでも赤電(終電)の一つ前の青電で帰ったらしい。一度だけのベレベレは自宅(麹町)のすぐそばまで来てから路上に寝込んでしまい翌朝日が射してから目が覚めたそうである。当時は酒友も多かったらしいが、『白樺』の仲間では正親町(おおぎまち)君とよく飲んだかナ、あとは『人間』の同人吉井(勇)君や久米(正雄)君などと飲んだよ。また泉鏡花先生を中心にして集まる九・九・九会というのがあってね、先輩では岡田三郎助、鏑木清方さん、若手では水上瀧太郎、久保田万太郎、小村雪岱、三宅正太郎(判事)に僕などだった。しかしこの会で鏑木さんだけは酒を召し上がらなかったナ。こんな昔の話を伺っていると、先生の記憶力のたしかさは驚くばかりである。戦後三十年近くも先生の酒と酒の肴での大好物は冷やっこで、一年を通じて先生の食卓に出ない日はほとんどない。先生の御長命も案外豆腐のせいかもしれない。(「わが酒中交遊記」 那須良輔) 戻
地獄
カルロスが死んだ。彼には、地獄には酒樽と女があると聞いて地獄の方を選んだ。行ってみると、実際、女がいて酒樽があった。だが、女には穴がなく、酒樽には穴があいていた。(「ポケット・ジョーク」 植松黎
編・訳) 戻
六月二十八日(水)
曇つてゐる。父上が御頂戴になつた金杯三重二組と他に一つとの合計三点を持つて出勤。今度拝受者が返納の手続きをとればお上でそれをお受けになることになつたからである。大金さんの所へ持つて行く。途中本省の薄暗い廊下を通り乍ら胸に金杯の包を抱いてしみじみと父上の御苦労を思い出す。御辛労に対する恩賞を胸に抱いてゐると思ふと胸が一杯になつた。午後一時半御進講、チエコ国情に就いて。内大臣、宮内大臣、侍従長、武官長陪聴。予は清宮様の御写真を持つて大宮御所へ行く。当直は戸田、沢本、塚原、遠藤。遠藤、戸田君の合戦最中に出御。そのあと遠藤をお相手に一寸途中まで遊ばす。塚原、沢本の囲碁戦が武官府で十一時頃まで行はれたらしい。雑誌を読んで寝る。(「入江相政日記」 入江為年監修) 同年(昭和十五年)七月四日皇后の金供出箇所の注に「政府の金総動員運動に垂範の意味で腕環、金鎖など数十点を3日、お渡しになった。鋳つぶして地金として日銀に提供される。天皇はすでに前年夏に約七十点を供出されており、金ぶちの眼鏡もお止めになった、という。 戻
利佳
新宿歌舞伎町に「利佳」というおでんやがある。文字どおりのおでん屋で、十二、三人もつめたら、どうにもならぬくらいせまい店である。おでん屋として、別にとりたてて特徴のある店でない。造作もいと簡単なものである。ただこの店に、夜ごとになんとなしに「無産有知識階級」が集まるのである。この言葉は、わたくしの発明にかかるものである。わたしは仕事のうえからも、おのが好みの上からも、いうところのバー民族である。バーを愛するものである。キャバレーというものを好まない。ただひたすらにバーが好きである。そこで、わたくしは作家に会い、彼らと会話を交え、時として、つぎの仕事をおねがいする。文字通りの仕事場である。ところが、銀座の一流バーは、いまや「有産無知識階級」の人士でみちみちている。大臣あり、有名実業家あり、流行作家ありである。無知識階級ではないかもしれぬが、要するに彼らが、社費で飲み、国費でたのしむかぎり、わたくしは、これを「有産無知識階級」の集会所といわざるを得ない。これに反して、新宿のおでん屋には、社用族は一人もいない。ただ「無産」である大学教授という「有知識階級」が夜な夜な相会して、おのれのサイフで、好きな酒をのむクラブであることを、わたくしは深く尊重するものである。六大学の先生で酒徒と名のつく方は、全部ここに集まる。名前はあげきれない。名誉教授も不名誉教授もここに集まれば、みな同じである。学部長も。ホヤホヤの助教授も、同じ資格である。この家の女主人は、安藤リカ女史。往年の新橋妓院の出身。女学校は二年で退学しているが、耳学問はおそろしいもので、独仏語をいささかたしなむ。長男がことし三つの大学の受験生である。(「歴史好き」 池島新平) 戻
牢屋
「おれは天下のシュウコウだ-」藤沢秀行の、その昔。浴びるように飲んではそうほえた。ギャンブルなどで作った借金の額は、本人も把握しきれないほど。女を作って三年間、家に帰らなかった。「飲む」それに「打つ」。そして「買う」わけではないが、女遊び。棋聖戦六連覇をはじめとする輝かしい戦跡を残す一方で、男の悪行を三拍子そろえてやってきた。悪太郎ぶりを反省するそぶりは、本人にはあまりない。失敗と思っていないのだ。だが世間的には「失敗」だらけの人生だった。まずは酒。三十代は酒豪でならした。いつしか浴びるような飲み方になり、四十代で四六時中の酔っ払いに。公開対局だろうがテレビの収録だろうが、酔っ払って現れた。で、「おれは天下の-」という冒頭のあいさつ。好き放題にほえ、みだらな言葉を連発した。酩酊して警察の世話になることもしばしばだった。沖縄の店で飲んだ時のこと。気が大きくなって、手持ちの十万円をそっくり店の女の子にあげ、タクシーに乗った。「朝、目が覚めたら留置場だった。泊まっているホテルの名前は忘れるし、お金はないし」東京都杉並区に住んでいたころは、地元の警察でも有名人。酔っ払って連れて行かれた署で、お構いなしに暴れ、わめき散らした。酒にまつわる失敗はとにかく尽きない。最近、藤沢が出した回顧録『野垂れ死に』から箇条書きしてみる。 ・スリッパだけの裸で交番に保護される ・新宿歌舞伎町でプロボクサーとけんかしてボロボロになる ・家の玄関を壊す、風呂の戸を壊す、台所の戸を壊す、ガラスを割る ・交番が家に電話しても妻は一言「牢屋に入れておいて」(「わたしの失敗」 産経新聞文化部編) 戻
サイダー瓶入り特級酒
昨年のことになるが、東大新聞研究所の卒業生の祝賀会に招かれた。一年間つまらぬ講義をしたためである。ちょうど知人から灘の銘酒三升をもらったので、幹事の学生にこれを寄附して、会の方には少し遅れて出席したところ、無惨や、灘の銘酒はサイダーの空ビンにつめれらて、冷酒のまま飲まれていた。会場は本郷の「白十字」であった。会が進行して、「先生、一つスピーチを…」というので、私は立ち上がって次のようなエンゼツをした。諸君、サイダー瓶には入れられているが、この酒は特級の銘酒である。これから社会に出てゆく諸君を象徴しているようである。秀才街道をバクシンして来た諸君は、自分では特級酒とうぬぼれているかもしれぬが、社会に一歩ふみ出せば、みんなサイダー瓶につめられるのである。社会は決して上等の徳利につめてはくれぬ。覚悟はよろしいか。そして飲まれてみてみてはじめて、特級か一級か二級かを、社会がきびしく判断してくれるのである。それからもう一つ、それは酒の飲み方の注意である。学生時代に飲む酒は、財布の加減で、どうせ二級酒か焼酎である。ところがセビロを来て社会へ出ると、しばしば特級酒を飲む機会にぶるつかるわけである。申すまでもなく、この時は、公用か社用かで飲む時である。特級酒はうまいし、自分のサイフがいたまないから、この公用酒、社用酒の味は格別である。しかし同時にこれからは「飲むべからざる」公用酒があり、社用酒があることを、厳に知ってもらいたい。 ガラにもない説教をして、少々テレた。学生諸君は酒がまわって、聞いていたのか聞かぬのか分らなかったが、、わたくしの気持ちはサッパリしていた。(「歴史好き」 池島新平) 戻
五斗兵衛
五斗兵衛は、大阪の陣に活躍した後藤又兵衛基次ががモデルで、一日に五斗の酒を飲むことから「五斗兵衛」といい、ゴトウに音を通わせてある。-
前半の義経の堀川御所の場を「五斗三番」といい、後半の和泉三郎の館の場を「鉄砲場」という。前半で酒を勧められてつい手が出るところ、後半で酔って帰って、鉄砲の音を聞いて本性を取り戻すところが見どころである。九代目は、この酔って帰ってくるところ、空鉄砲を聞いてキッとなるところで、あたりに酒くさい匂いがパッと立ちのぼるようなうまさだったという。本性をあらわしてからはむろん酔っていないのだが、それでも幕が閉まるまで酒の気がのこっているように見えたというから、大変な芸である。もっとも九代目は、出の前に冷酒を茶碗に一杯キューッとあおって舞台へ出たという説もある。芝居を出来るだけ自然にという主張をもっていた九代目らしい逸話である。しかし、むろん実際に酒を飲んだから酔態が出来るといううわけではない。あくまで九代目の芸は芝居のうまさだったのだろう。九代目は、このほかにも「忠臣蔵」七段目の由良助の酔態、「勧進帳」の弁慶の酔態と、酔態の当たり芸をいくつか持っている。(「芝居の食卓」 渡辺保) 戻
ウエスキー
言うなればウイスキーまがいの酒精酒。胴のくびれた分厚いガラスの安コップにつがれた一杯、大体三勺入り位。「支那そば」(今は中華そば)の屋台店や下等の「赤提灯」の店で出した。「ウエ」と発音するところに表現の妙がある。「ウエ助」という下等語もあった。(「明治語録」 植原路郎) 戻
呑酒百杯
慶応二年(一八六六)、彼が下関で薩長合弁カンパニーをプロモートしていたときだ。一夕、関係者が用件ぬきで料亭に集まった。薩摩からは五代才助、黒田了助ら、長州は桂小五郎、広沢兵助など。それに竜馬たち亀山社中のスタッフ。芸者をあげて、にぎやかな酒になった。シンガー・ソング・ライターは出番を迎える。大熱演が展開された。くり返すが、竜馬の歌唱は、「その声調、すこぶる妙」五ヵ条誓文の三岡八郎が、仰天している。福井の三岡家で、飲んで歌ったのだ。それはさておき、下関。竜馬が喝采を浴びていると、だれかが知らせてきた。中岡慎太郎が白石別邸にいるという。よし、呼ぼう、となった。竜馬が筆をとり、遣いを走らせた。こいつがいまも、保存されているのだった。幸い、写真がある。せっかくだから、ご真筆どおりをお目にかけよう。あえて、手は加えぬ。「翁亭(おきなてい)ニヲイテ兵站(へいたん)ヲ開キ候処、女弊(じょへい)意外ノ嘯集(しょうしゅう) 攻口(せめぐち)数々ノ処 軍議多端 是非共(ぜひとも)参軍御出張ノ上 御英議ナラデハ大切如何ト上存(ぞんじあげ)候間 千里の良馬ヘ御一鞭御来臨 伏而(ふして)相待(あいまち)候也 呑酒(どんしゅ)百杯」
(「幕末酒徒列伝」 村島健一) 呑酒百杯は、頓首再拝のもじりだそうです。 戻
煎り酒は九二一が伝
煎(い)り酒を作るのには、酒を九、醤油を二、醋(す)を一の割合で交ぜて作るしかたである。松葉軒東井(しょうようけんとうせい)の『譬喩尽(たとえづくし)』(一七八六年)に掲げ、<酒九醤二醋一これなり。>と注する。「煎り酒」は、古くなった酒に、鰹節、煎り塩、醤油、酢などを入れて煮詰めて、刺し身・膾(なます)などの味付けとしたという。(「飲食事辞典」 白石大二) 戻
はせ川
夕飯を頂いて夜遅くお暇をしたが、井伏さんは二十年来の宿望を果したと言って悦んでくれ、僕も東道の甲斐があったと思って嬉しかった。井伏さんはまた志賀さんがお酒をたしなまれないことを言って、荷風でも白鳥でも、偉い作家はみな酒を飲まないなあ、と感慨ぶかげであった。その夜は志賀先生の紹介して下さった宿屋に泊まった。その翌日の夕刻、帰りの汽車が新橋に近づくと急に井伏さんはそわそわし始め、これから荻窪まで帰ると電車が込んで不愉快だから、”はせ川”へ行って一ぱいやろうと言い出した。そして、少してれて、「なに、溺れなければよかろう」とつけ足した。まだ宵の口だったが、”はせ川”には先客に石川淳さんがいて、もうご機嫌だった。そこで僕らも楽しく飲み出したが、名山を仰いだためにやっぱり緊張していたに違いない。急に疲れが出て、その晩はすっかり酔ってしまった。(「井伏鱒二随聞」 河盛好蔵) 戻
ベトナム戦争時代
つい先日那覇に行った私は、旧知の喜屋武(きゃん)幸雄氏とビールを飲んだ。彼は「スクランブル」という、おそらく日本で一番設備の整っている那覇のライブハウスで音楽プロデューサーをし、沖縄ロックシーンの演出をしている。「マリー・ウィズ・メデューサ」のメンバーでもあったが、最近現役の演奏者を退いたのだ。彼はこんな話をしてくれた。マリーはボーカリストで、彼の夫人である。「ベトナム戦争時代のドロドロした中で、酒かっくらって、こんなでっけいやつが、入墨したやつがボロボロ泣いてるんだ。明日ベトナムに行くことになった。最後にお前らの演奏聞かしてくれ。マリーの歌聴きたいよって、三人ぐらいできた。いくら飲んでも酔えないよ、恐怖で。もう泣きながら飲んでんだ。で、彼たちがベトナムにいってしばらくして帰ってきたんだよ。怪我しているんだけど、帰ってこれたってすごい喜んでるわけ。ところで残りの二人はと尋ねたら死んじゃったというんだ。僕らのところにくれば、何か助けてくれると思ってるんだ。」(「ヤポネシアの旅」 立松和平) 戻
高村光太郎の酒歌
酒歌(さかうた)に千とせみじかき舌なめずひがしに越えよ伯父李青蓮(りせいれん)(M35)
酔ひて泣く杜甫が背に笑む李太白ふたり歩めば京(みやこ)の震撼(ゆる)る(M35)
ともすれば酒に離れし李青蓮われと詩筆のうつけに病まる(M36)
だんだらに魚がし抜ける幕ほめて茶屋酒ほめて人に及ばぬ(M38)
一力の小てるとわれと酒のめば飯をつぐとて盆を出すひと(M42)
夜の空気かすかにふるへ電線のうなりもきこゆ酔ひたる耳に(M43)
このみきをたうべてよはなこのみきはみきのあぢしるきはよりはこし(S24)
山形によき酒ありてわれをよぶのまざらめやも酔はざらめやも(S24)-
与謝野先生つていうのは、「明星」調を世の中へひろめるために、集まった若い人の歌を根本的に直しちやうんですよ。ぼくなんか、一字だけ、自分の書いた「白」つていう字が入つてたから、これは自分の歌か、と思うくらいで、あとはみんなちがうんだ。
(「高村光太郎全集」) 戻
ヴェルレーヌ
河盛 ヴェルレーヌは一生涯別れた細君に、未練がありました。大へんな恋女房でしたから、それまでは身持ちも悪く、大酒飲みだった彼も、結婚してからは家庭生活を大事にして、役所からも早く帰るし、飲酒も慎むというふうでした。ところがそのうちに普仏戦争が始まって、フランスが敗北します。パリはプロシャ軍に囲まれて、国民軍兵士になったヴェルレーヌは夜は歩哨に立たなければならなくなる。十月頃まではまだよかったが、だんだん寒くなってくると、歩哨がすんで帰る途中、居酒屋に寄って一杯飲まずにはいられない。そのために結婚と同時に慎んでいて飲酒癖が、また戻ってくる。酒に酔うと彼は前後の見境がつかなくなるんですな。そのために、細君に乱暴したり土足のままベットに寝たりする。それが細君の両親の家なんですね。ヴェルレーヌの母親は別の家で暮らしています。細君は我慢に我慢を重ねていますが、だんだんひどくなる。(「井伏鱒二随聞」 河盛好蔵) 戻
離し注ぎはせぬもの
【意味】杯は銚子から離さずにつぐものである。 【参考】置きつぎはせぬもの(「故事ことわざ辞典」 鈴木棠三・広田栄太郎編) 戻
庭園学派
ギリシャの哲学者エピキュロスは、紀元前三四一~前二七○年代の人だが、アテナイ(アテネ)に住み、庭園に門人を集めて講義していた。そのために庭園学派などとも呼ばれた。彼は感覚的快楽を退け、簡素な生活の中に魂の平静を求める、というもしろ倫理的な人柄だったが、どこでどう間違われたか、享楽主義者とされ、エピキュリアンとは食物や酒の味のうるさい人、などという意味になった。エピキュロスは、自然学、心理学、倫理学、神学の諸学に通じ、原始論的自然学では大家であったのだが、美食の哲学にも長じていると誤解された。まあ現在になってみれば、エピキュロスの偉大さは、学者の間では理解されているのだから、私たち美食に関心を持った者は、エピキュロスをして、美酒、美食の大先輩に祭り上げてもいいのかも知れない。
(「美食に関する11章」 井上宗和) 戻
酒を少々
御廻領とよばれている藩主の巡回に先立って、各村へ通達がだされた。これには、
一、新居郡を御廻領の時には、御供の者達への食事は、一汁一菜で小魚を用いてもかまわないというのは一昨年の通達である。去年は日照り続きで、村々も困っているときいているので、今回は小魚を用いず、鰹節でよいことを通知する。これをよく守るようにせよ。ただし、御目見得(正月に御館へ礼に参上することを許された者達)以上の者には、酒を少々飲むことを許可する。これ以下の者は酒をかたく禁じる。
一、夜具をそろえるのは困難であろうから、粗末な品でもかまわない。
一、全体にわたってがさつな態度をとらないようにせよ。
と書かれていた。(「伊予小松藩会所日記」 増川宏一、原典解説:北村六合光) 戻
鴻池屋
鴻池屋は酒造業で基礎をすえ、ついで海運業に携わって漸次鞏固になり、その後は両替屋として発展したものであるが、それと共に市内の土地を買得し、更には新田の開発にまで進んだもので、このような資本の運動法則は、江戸時代においての常道であったといってよい。鴻池屋はその最も典型的な例であるといえよう。(「鴻池善右衛門」 宮本又次) 戻
アンゴスチュラ・ビターズ
ドイツの軍医がヴェネズエラの英国陸軍病院でつくった…そもそもの発端から、アンゴスチュラ・ビターズにはえらく複雑なイメージがからんでいるようだが、私は、何年か前にこのリキュール酒にまつわる、なかなかいい話を聞いたことがあった。世界各国の、一応ちゃんとしたバーの棚の一角には、かならずこのアンゴスチュラ・ビターズが置いてあるというのだ。このリキュールは、さまざまな薬草が入った薬酒という感じで、何に効くかといえば宿酔(ふつかよい)のむかつきや胃のもたれだという。そして、そんな症状に悩む者がカウンターに坐り、アンゴスチュラ・ビタースのソーダ割りを注文すれば、それに対してバーテンダーはかならず無料でサービスすることになっているというのだ。これがつまりはいい話なわけで、こういう気分はいかにもカウンター・バーらしいダンディズムを感じさせるではございませんか。-
すると、私の正面にアンゴスチィラ・ビターズの瓶が見えた。とっさに、私はビター・ソーダを注文した。あれだけ数多い、複雑な薬草の入ったビターを飲めば、その中のどれかがノドに効くかもしれないと思った、つまり散弾銃的効果があるかもしれないと期待したからだった。そして、私の直感通り、それから一時間くらいしてノドにからまった啖を感じなくなり、ホテルでベッドへ入る頃には完全に治っていた。酒はやっぱり百薬の長という言葉を、私は初めて素直に受け入れたのであります。(「酒の上の話」 村松友視) ハウスシック症候群でノドをやられたときの話だそうです。 戻
あげ癖
酔っ払って他人に物を渡す癖の人がいるらしい。開高健が新宿西口の飲み屋にいると、隣にいた酔漢が「おまえが気に入ったが、なにもやるもんがない。これを持ってけ」といって、履いている靴の紐を一本抜いてくれたという話がある。吉行淳之介は、印鑑を渡してしまったそうだが、さすがにこれは必要なので、相手をおぼえていたから取り返すことができた。吉行がこの話をして、「受け取るやつも、どうかと思うねえ」といっているのが、じつにおかしい。(「最後のちょっといい話」 戸板康二) 戻
大すじ
まず大すじをたどってみると、明治維新のころわが国には、濁酒(どぶろく)と清酒が共存していた。両者の割合は県によっていろいろであるが前者の方が多いところもあったように記憶する。そして濁酒の方は、室町時代以前、おそらく平安朝のころから、わが国の家庭や酒屋で行われてきた「水もと」とか、あるいは「ぼだいもと」とかいわれる一種の安全醸造法によって、春夏秋冬随時随所で造られてきた方法によったものであり、それに対して清酒の方はもとよりそれらの方法に源を発してはいるが、主として江戸時代の初期以来、関西地方で工夫発達した手のこんだ醸造法によるのであった、冬期に適した方法であるから「寒造り」などともいわれ、その代表的なものは灘地方の「生(き)もと」の方法である。このような状態で明治初年にうけつがれた古来の酒造りは、その後明治四十年前後になって、大蔵省醸造試験所で「生もと」法を合理化した「速醸もと」法が発明され、それ以来わが国の清酒はこの二つの方法、すなわち灘流と大蔵流の二流の酒として並び行われて来たのである。それでは、これらの両法の酒には一体どのような特徴があるか。一言にしていえば、灘流の酒は多少「くせ」はあるが「こく」があってうま味深く、大蔵流の酒は概して風味淡麗であって、さわやかさに勝っているとでもいえようか、その特徴は一長一短である。これらの二法のほかに、伏見流とか、京流とでもいえる方法で、最後に米と麹を加えて甘口の酒を造る方法があるが、この方法は今では、前の二法に結びついて採用されているようである。また大蔵流の酒はさらに一段の工夫を重ねて、いわゆる「吟醸酒」という、従来の酒には見られなかった一種の果実香を放つニュー・タイプの酒を生み出すに至った。この酒は米の精白を極度に高める必要があるので価格が高く、これまでは新潟、大分そのほかわずかのメーカーで市販されるのみであったが、筆者の紹介などがきいたせいか、去年あたりから増加する傾向があるようである。高精白によって、もし全国の酒がすべてこのようになると仮定すれば、おそらく百万石以上の米の消費を上げることにもなろう。上述の諸流の明治以来の酒の上での消長を見ると、「水もと」流は大正の末年まで尾を引いて消え去り、灘流優位時代から灘流大蔵流並位時代、合成清酒優位時代を経て、清酒合成酒結婚時代に入るような順序で、それにしたがってわが酒質もさまざまに移りかわっているのである。(「いずこへ行くかわれらの酒」 坂口謹一郎) 戻
夜(よ)ハしらじらと生残(いきのこ)る下戸
かなりの人数が集まった宴席かと思われる。飲みすぎた上戸たちはいぎたなく横になって死んだように眠っている。もう間もなく夜が明けるころである。
酔(よう)て戻(もどっ)た妻を見上げる
祝いごとか法要か、そういう席へ妻だけが出て夫が留守という場合もあるのだろうか。見上るという動作には、おや、どうした、だいぶん酔っているなと少し驚いた気分がある。妻が酔うのがこの家では珍しいことなのであろう。(「『武玉川』を楽しむ」 神田忙人) 戻
料理持参
下北には結婚の祝いの席に参列する人が、各おの自分で食べる料理をお膳にのせて持参して来て食べ、酒だけを、祝いの家でご馳走になるという部落がある。貧しい日日の暮らしの中で、一年に一度か二度の部落内での祝い事を派手に振舞ったりして、生活を犯さないようにという心づかいからの部落のきまりである。ただし来賓者である駐在さんや学校の先生の分は、部落内で持ち廻りとしていた。(「みちのく民俗散歩」 田中忠三郎) 戻
シャンパンにおから
相手がゐなくても、酒興に事は欠かないコツプを二三度取り上げる内に、すつかり面白くなつて来るから面白い。頭の中がひどく饒舌で、次から次へといろんな事がつながつたり、それたなり元へ戻らなかつたり、そこから又別の方へ辷つたり、実に応接にいとま無しと云ふ情態になる。傍にだれもゐない方が面白い。シャンパンの肴におからを食べる。おからは豚の飼料である。豚の上前をはねてお膳の御馳走にするのだから、いつでも食べたい時に買ひに行けばあると云ふ物ではない。少し遅くなると、もうみんな豚の所へ持つて行つてしまつて、豆腐屋の店にはなくなつてゐる。その以前に馳せつけて、少少お裾分けを願ふ。
(「御馳走帖」 内田百閒) 戻
六月二十日。金曜日。
晩酌で菊正宗二合。そのあと葡萄酒にする。これがどうもよくわからない。五月に南洋に行ったとき、仏領だから葡萄酒ばかり飲んでいた。それが馬鹿に具合がよくて、このままアル中になってしまうかもしれないが、南洋で絵ばかり描いているアル中の爺さんというのも悪くないと思ったものだ。それを思い出して、あの気分を取り戻したいと無意識に考えたようだ。二時間足らずで一本飲んでしまって、次にブランデーを飲んだ。貰いものの上等のブランデーを探した。以前、山梨に行ったとき、朝から葡萄酒とブランデーを交互に飲み、少しも宿酔しなかったというのが頭にあったようだ。葡萄酒とブランデーは原料が同じなので宿酔しないと教えられた。そのブランデーをどのくらい飲んだか憶えていない。私の場合、飲めば飲むほどにおいしく戴けてしまうのがよくない。(その翌日は気分は悪くなかったが、アルコールが抜けないので弱った。陶然として仕事にならず、ビールを少し飲んだ。思えばこれが変調の前触れであったようだ)(「また酒中日記」 吉行淳之介編) 山口瞳です。 戻
アジアの「地酒」
これらの国には、もちろん地酒にあたる酒がある。が、それらは、輸入物のウイスキーの間に忘れられたように置かれている。どうも現地の人にしたら、地酒など酒にあらずと考えているふしがあり、その値段も、「持っていっていいよ」と思ってしまうぐらい安い。だいたい一本が一ドル相当である。最近、僕はこの種のわけのわからない地酒をこそこそと買ってきてはホテルで飲むのをちょっとした楽しみにしている。「おッ、これはいけるじゃない」「なんだこれは。酒は酒なんだが」とひとり遊びを繰り返しているのだ。先にお話ししたように、これらの国には、大都市のツーリストエリアを除いて、ひとりで酒を飲めるような店はない。治安に問題が残る国も多く、そう簡単に出歩けないのだ。勢い、夜はホテルで過ごすことになるのだが、その時間を救ってくれるのがこの地酒たちなのである。ベトナムのフエで飲んだラムもどきは、軽い口当たりのなかなかの逸品だった。プノンペンで売られていたロイヤルというウイスキーにインドのウイスキーを思い出す、といった具合である。こういうことを書きながら、申し訳ないのだが、その銘柄のほとんどを伝えることができない。ラベルが英語で書いてあればまだわかるのだが、この種の酒のほとんどは現地語の世界なのである。困ったことに、これらの国は流通システムが未発達で、ひとつの街で見つけた逸品がそこからバスで二時間の街では見つからない、といったことは珍しくない。要するに旅の夜を楽しませてくれる瞬間の酒なのである。(「アジア漂流紀行」 下川裕治) 戻
卒業生
昭和三二年に設置された吉川高校醸造科は、同三四年を第一回として、平成一〇年度(一一年三月卒業)ですでに四〇回も卒業生を世に出した。その数一二八一名、うち三〇〇名余りが県内外の酒類製造関係の仕事に従事している。その他多くの方々が、酒類、調味食品、製薬などの会社で活躍している。一〇名規模の吉川高校卒業生が従事している大手企業をいくつか拾ってみると、酒類関係では、大倉酒造(月桂冠)、黄桜酒造、白鶴酒造、菊川酒造などの清酒メーカーや、サントリー、三楽オーシャン、キリンビールなど。食品関係ではキューピー醸造、信州味噌、敷島製パン、山崎製パン、また製薬関係では大正製薬など錚々たる企業が並んでいる。また近時は、大学に進んで引きつづき醸造を学ぶ者も多くなった。最近三ヵ年をみても、平成八年度二名、九年度三名、一〇年度一名が、東京農業大学醸造科に進んでいる。これら若き俊英が、醸造学の研究をいっそう深めるとともに、低落傾向にある日本清酒界の今後の発展に寄与されんことを願ってやまない。(「高校生が酒を造る町」 首藤和弘) 吉川高校自体が平成20年3月に閉校してしまったそうです。 戻
玉杯
玉杯というと三高卒業生私でも一高の寮歌を思い出す。あの歌はいってみればそれほど、何高などと限定しない、旧制高校全体の寮歌みたいなものらしい。ところで、当然のことかも知れないが、私にとってかねてから矛盾に感じられることは、あの歌の冒頭の、名文句である。「ああ玉杯に花浮けて、緑酒に月の影宿し」という一対が、弊衣破帽を誇った作者にとっては軽蔑すべき栄華の巷の一形容に過ぎないにもかかわらず、当時の青年達は、少なくともその頃の私はこの冒頭のリズムを誠に快適に朗々と、まるでこの一連の名句に理想の生活が表現されているかの如く吟唱するのがつねだったことである。(「詩酒おぼえ書き」 高木市之助) 戻
町人ぶくろ
『法師が母』といふ狂言は、酔狂する人をいましめたりと見えたり。狐狸にとりつかれたる人は、はなれても後も諸人いやしめ、一分すたれて人まじらいもかなはず。酒にとりつかれて狂乱せしは、醒(さめ)てのち、人もいやしめず、その人もいつものごとくにて恥るいろもなし。ものゝ為に本心を失ふ事は、狐狸と酒と何ぞことならん。つくづくと酒に酔る人を見るに、おのおの本心の病をあらはすなり。生得柔和正直なる気質の人は、物にしたがひながれやすき事ありて、酒の為に気血うごき、よろこび笑ひ舞()まふ)なかで、うつゝなき時は寝(いね)てひとりわらひ独(ひとり)うたふ。或は気質情こはく、内心に高慢ありて瞋毒(しんどく)内に蟠(わだかまれ)る人、酒酔に依て気血浮み動き、内心の毒気外にも出、怒気傲慢顔色にあらはれ、何の事なきに罵怒り、座席の人を敵とし、甚しき時は剣力を抜ひらめかし、無礼狼藉たとゆるにものなし。平生の人品威儀温良に見えしも一時に亡失す。まことに上戸本性あらはすとは是等にや。此故に聖人も仏祖も、飲酒(おんじゅ)の戒め甚だ強しといへども、末代の儒者仏者酒を嗜まざるなし。さなきだに好む人多き世に、吉田法師『下戸ならぬこそおのこはよかれ』といひ、『色好まざらんおのこは玉の盃の底なきがごとし』と書置るを見て、下地はすきなり仰(おほせ)はおもしと、さかんにもて興ずる世とは成しなり。つくれる草子を時の人にもてあそばしめんがため、偏屈なく見て倦(うま)ざらしめんとして、先(まづ)発端に興ある体に書たり。奧には又酒と色とをいましめたるもあれど、見る人発端の初一念を執して、奧に心を留る事なし。後文初文を償ふにたらず。三百年以来に世の幾(いくばく)人をかそこなひきつらんと、いといぶかし。(「町人ぶくろ」 西川如見) 戻
無害
スコットランド人にとってスコッチ・ウイスキーが無害なのは、ちょうど、ミルクが他の人類にとって、と同じだ。(「また・ちょっと面白い話」 マーク・トウェイン) 戻
流頭日(ユドイル)
六月十五日を流頭日といいます。流頭という名称は「東流頭沐浴」の略称です。流頭日には渓流に行き沐浴し、頭髪を洗って一日を清遊します。そうすると禍を追い払い、夏季に暑気負けしないといわれています。流頭の民俗は新羅時代からあり、東流に行って髪を洗うのは、東は清く陽気がもっとも旺盛なところだからです。流頭日には文人たちが酒と肴をもって、渓谷または景色のよい亭子(あずまや)を訪ねて、風月を詠じて一日を楽しく過ごしました。これを流頭宴といいました。(「韓国歳時記」 金渙) 戻
気圧のせい
井伏鱒二さんが、「酒ってものは午後一時から、うまくなるね」と述懐した。「なぜでしょう」と編集者がいったら、「気圧のせいだろう」(「新ちょっといい話」 戸板康二) 戻
梅瓶
先日、青山和子夫人に会った時、ジィちゃんが最後まで忘られずにいた陶器があることを知った。それは宋の梅瓶(めいぴん)で、梅瓶というのは中国の各地で造られた細長い形の壺に、小さな口のついた酒瓶のことである。梅の花をいけるのにふさわしいとか、梅の枝のように清楚だともいわれるが、これは当てにならない。この梅瓶の場合は磁州窯の白磁に、牡丹の花か何かが描いてあったらしい。それは昭和十五、六年の頃、一万円もした逸品だそうで、ジィちゃんは日本橋の壺中居で見たが、高いので誰にも手が出せなかった。そういう時、骨董好きは、見も知らぬ他人の所有物になるのがしのびなくて、何とかして友達に持たせようとする。そこで当時流行作家で、一番実入りのよかった横光利一氏に電話をかけたところ、二つ返事で引き受けたという。横光さんは、ジィちゃんの眼を信用して、不見転(みずてん)で買ったものとみえる。(「いまなぜ青山二郎なのか」 白洲正子) 戻
ロケット燃料
宇宙科学者が二人、ケープ・カナベラルでまもなく二人をのせて、、宇宙に飛び立つことになっているロケット燃料のテストをしていた。二人は、ロケットの外側に、奇妙な水滴のようなものが付着しているのを見付けた。指でそれをすくってみるとやはり液体だった。ひとりが匂いをかぎ、それからなめてみたのだった。「おい」彼は思わず叫んだ。「こりゃあ、いい味だぞ!」それを聞いて、もうひとりもなめた。「こりゃあ、パンチ酒そっくりじゃないか」そこで二人は、その水滴を清潔なタオルにぬぐいとり、タオルをしぼってバケツにその液体を収集したのだった。そして、物陰にかくれて、いわゆる彼らの”発見物”をゆっくり賞味したのだった。二時間ほどたったようか。すっかり眠りこんでしまった化学者のひとりは、相棒からの電話を受けた。驚いたことに、その電話の声は、かなり遠くからのようにきこえた。「とっても遠くにきこえるぜ」彼はたずねた。「いったい何処にいるんだ?」「サンディエゴからだ」相棒が答えた。「ヒェー、いったいどうやってそんな遠くまで行ったんだ。ついさっきまで、此処にいたのに?」「さっき、オレたちが飲んだシロモノがあるだろ」サンディエゴの男が言った。「ちょっと注意しとこうと思ってな。まちがっても屁はひるなよ」(「ポケットジョーク」 植松黎編・訳) 戻
昭和二十五年六月
ショウチュウの値下げ以降、密造のカストリは影をひそめたが、まだ全般に何しろ高い。小売値段で清酒の特級が一升一、一七五円、ビールは一本一三二円、いずれもその大部分は税金である。四月一日改訂の自由販売酒価格の内訳は上の表の通り(ビール以外は一升の値段。単位円)。まさに税金を飲んでいる形である。二四会計年度では二八六万石、七五二億円の国庫収入があったが、今年はさらに千三十億円の大増収もあてこんでいる。
|
小売値段 |
製造原価 |
酒税 |
| 清酒(特級) |
1,175 |
129.40 |
926 |
| 合成清酒 |
670 |
85.10 |
509 |
| ショウチュウ |
450 |
78.10 |
314 |
| ビール(大びん) |
132 |
21.79 |
82.14 |
だから懐さびしい大衆にしてみれば、戦前の高級酒は高ねの花。戦後、酒の世界最大の変わり方はショウチュウがのして来たことだろう。-
○清酒 昨年から特級酒の制度ができた。地方国税局の鑑定にパスした一級酒から自信満々の銘酒が滝野川の国税庁醸造試験所に送られてきてこれまた全国から選りすぐった十数名のエキスパートの舌さきで採点される。四月初め二日がかりの審査をぱすした本年度前期分の銘柄は百十二種。その特級酒なら、まず昔の銘酒と変わりはない。しかし、清酒も新しいのがいい。山地の酒を産地で飲むのが上の上。名前にひかれて、新潟に出かけながらわざわざ遠くの灘の酒を取りよせるなど愚の骨頂だとここの通人はいう。(『朝日新聞』昭和二十五年六月十五日)(「酒・戦後・青春」 麻井宇介) 戻
珉里隠居
珉里は名にしおう蔵前一八大通の一人、並みの飲み食いはとっくに食傷している有閑階級だから、時代に先がけて趣向に凝る余裕があったのだろう。珉里は根岸に隠居して大酒を好み、その名も根岸の酒呑童子と称された。江戸中の酒呑みが伝え聞いて道場破りにやってくる。どうれご免と案内を乞うと、手下の小鬼が出てきて、まずはこれへと座敷に通し、小手調べの酒盛りに及ぶ。大方出来上がったところへ珉里隠居がようやく登場して、ふらふらしているやつをさんざんに打ちのめしてしまうのである。武者修行ならぬ酒修行だから演出も荒っぽい。「能(よ)き時分に童子対面せんと、珉里隠居は二人の妾にいざなはれて、のさのさ出来りて、能(よう)こそ珍客、是より酒宴催さんと大酒盛になる。夜明比(ごろ)にはさすがの酒修行も酔ひつぶされ、たわいなくおそれをなして帰りける。」『一八大通 一名御蔵前馬鹿物語』はそう報告している。(「食物漫遊記」 種村季弘) 戻
白墮の酒
後魏の劉白墮は河東(山東省の南部)の人。善く酒を醸造した。彼の造つた酒は夏の六月の暑く照り付ける時、甕に酒を貯へて日中に曝し、十日経(たつ)ても酒の味が変らない。之を飲むと香美であり、酔つたら一月経つても醒めない。京師(洛陽)の朝臣貴族が、地方へ出張する折など、遠方まで贈物として携へて、千里の外まで持つて行ける。其れが遠方まで送れると云ふので鶴觴と号し、亦た騎驢酒とも名づけられる。永煕年間(西紀五三二頃)南清州の長官毛鴻賓が、白墮の酒を携へて蕃地に赴く途中、盗賊に逢つた。賊は酒を奪つて飲んだので、皆酔うて擒(とら)へられてしまつた。因(よ)つて擒姦(かんきん)酒(姦賊を捕へた酒)と名づけられた。遊?(やくざ)の語に曰ふ「張弓抜刀は畏(おそ)ろしくないが、ただ白墮の春醪(ろう)が畏ろしい」(「酒顛(しゅてん)」 明・夏樹芳・著 明・陳継儒・補 青木正児・訳) 戻
萩の花盛はよき酒なし
【意味】酒が夏を越して味がおち、まだ新酒も出ないので、秋にはよい酒がない。【出典】琳賢が許より酒を送るとて、萩の花盛はよき酒世の中になし〔藤原顕輔集〕(「故事ことわざ辞典」 鈴木棠三・広田栄太郎編) 戻
清酒の防腐効果
衣川館(たて)で殺害された源義経の首級が、鎌倉腰越浦に到着したのは一一八九(文治五)年六月一三日であった。首実験ママを命ぜられた和田義盛、梶原景時が目にしたのは「件(くだん)ノ首黒漆櫃(しっき)ニ納メ、美酒ニ浸ス」(『吾妻鑑』)といった凄惨な情景であった。この美酒とは、まぎれもなく清酒であろう。死後一か月半を経過した首級を納めた漆櫃のまわりを氷詰めにしたのか、宋渡来の防腐剤を酒中に入れたかなどについてはわからないが、盛夏の候にもかかわらず清酒の防腐的効果があった実例である。(「日本の酒5000年」 加藤百一) 戻
梅に鶯
春のおとずれとともに各地の梅だよりがぼつぼつ聞かれるようになる。「梅に鶯」といえば、美しく調和する二つの物あるいは仲のよい間柄などのたとえとして用いられる。梅の花が咲いている枝に鶯が飛んできてさえずるの意でできた言い方。取り合わせのよいものの意で、川柳にもいろいろよまれている。『柳多留』十八編、「梅に鶯 桜に生酔ひなり」 「梅に鶯」がきまり文句であるように、花見には酔っ払いがつきものであるというのである。(「江戸ことば 東京ことば辞典」 村松明)
「日本酒の定義」の結論
しかし、この辺でそろそろ正気に返らなければならない。ここに書いたことを、何から何まで信じる必要はないのである。英語は、日本酒のようなものについて公平に語るのに適した言葉ではない。その点は、正しく室温に合わせたシャトー・ラフィットの絶妙な味わいを、日本語では適切に言い表すことができないのと同じである。しかし、シャトー・ラフィットについて語るとしても、できるのはただそれについて語ることだけで、だから、しまいには何か別の葡萄酒、たぶんヨハニスベルガー・ヘルあたりにでも話題を移す以外にない。ところが日本酒のことなら、いくらでも語り続けることができる。なぜなら、この主題が決して語り尽くされることのないものであることは間違いない。それにまた、日本酒はいつまででも飲み続けることができるもので、どうやら筆者にとってはそっちの方がずっといいようである。(「日本酒の定義」 吉田健一(磯野宏訳))
「日本酒の絶妙さ」 戻
石本省吾
植村さんは、幻の酒といわれる新潟県「越乃寒梅」のご主人石本省吾さん(昭和六十年六月逝去享年七十五歳)とは、明大山岳部の先輩後輩という仲で、植村さんのスポンサーでもありました。私も石本さんとの出逢いによって今日があるようなものですから、折にふれて植村さんの冒険に心を痛めていました。「彼は、きっと山で死にますよ、死ぬまで山へ登ることをやめませんね」と石本さんは見透しておられたものです。植村さんは、量をのむという人ではなくやさしいお酒の飲み方をされていました。薄口の盃で越乃寒梅をいとおしそうに口に含んでこういいました。「佐々木さん、ボクは冒険者でも探検家でも何でもありません。唯のエゴイストなんです。だから、誰も登ったことのない山へ登りたいだけなんです。偉いなんていわないで下さいね。そんなボクに比べ、石本先輩は凄いです。こんな素晴らしいお酒をかもし出し、多くの人たちに飲ませ、日本酒のよさを再認識させているんですから…」淡々としみじみとひとりごとのように語って、寒梅を飲みつづけた植村さん。あの夜のキラキラと輝く澄んだ植村さんの瞳を私は忘れることができません。何時間一緒にいても、世間の汚濁にみちた男の匂いなど全くしない人でした。石本さんもまた、寝食を忘れ、財を傾けて美酒造りに生涯を賭けられた酒神でありました。植村さんは四十三歳の若さで逝かれ、その一年後、彼の後を追うように石本さんも逝去されたのです。(「今宵も美酒を」 佐々木久子) 戻
神様の涙
信心深くて純朴なシュワーベン出身の男がローマへ巡礼の旅に出かけました。イタリアに着くと、男はある宿屋に泊まりました。宿の亭主は男を丁重に迎えました。というのは男が飲み食いする金をじゅうぶんに持っていたからです。亭主はありったけのごちそうを食卓に出し、さらにイタリア産の極上のワイン、例えばヴェルテリーンやラインファルや、その他の上等ワインを出しました。シュヴァーベンの男にはこれらのワインがとてもおいしく思われました。それで最後に男は、これはどういう飲み物かと亭主に尋ねました。亭主も生粋のドイツ人で、人をからかうのが大好きでしたので、すぐにいい鴨を見つけたと思って、言いました。「お客さん、お尋ねの飲み物は私たちの神様の涙なんですよ。」シュワーベンの男は言いました。「おお、神様、なぜあなたはシュワーベンでも泣いて下さらなかったのですか。」こういう純朴な人々は今日ではもう多く見出せません。(「道中よもやま話」 イェルク・ヴィクラム 名古屋初期新高ドイツ語研究会訳)
坂口安吾、畢卓
坂口安吾は締切を守らないので、編集者の鬼門だった。しかしその気になれば、一晩で小説を書き上げることもあった。ある日も編集者が原稿をとりに来たが一枚もできていない。その上その日は「水曜会」といって、安吾の家に桐生での彼の知人たちが集まって飲む日だった。安吾は十時過ぎまで知人と飲んでハラハラさせていた、急に切り上げると書斎に入り、徹夜して、翌朝十時頃までに七十枚の「安吾捕物帳」を一篇書き上げた。
晋に畢卓(ひったく)という者がいた。彼は酒好きで、彼が知人にいつも語った夢は「大きな船に酒をいっぱい注ぎこみ、船首と船尾にうまい肴をたっぷりのせ、右手に杯を持ち、左手に蟹のはさみをもって、その酒船の中を、自由自在に泳げたらな!」(「世界史こぼれ話」 三浦一郎) 戻
曹源寺
川本幸民(一八一○~一八七一)は摂津(兵庫県南東部と大阪市西部)の人。蘭学を刻苦研鑽して修め、幕府の洋学校「蕃書調所」の教授兼化学部門の指導者をつとめた。蕃書調所は安政三年(一八五六)に開所。外交文書や洋書の翻訳もおこなった。のち、洋書調所、さらに開成所となり、東京大学に吸収される。幸民は、オランダの専門書を訳して『理学原始』『化学初教』等を著わし、その体験からビールを自宅で醸造したといわれている。そもそも、幸民がビールを知ったのは、前記したように、嘉永六年六月にペリーが浦賀に来航した時であった。接伴役に幸民も同行、米艦上でビールの饗応をうけ、その爽快な味にひかれ、アメリカ人から製法を聞き出したのが事のはじめである。浅草の松葉町の曹源寺は、難工事となった文化年間(一八一○前後)の治水工事に近辺の河童たちが協力したことから河童寺と呼ばれている。この寺は、川本幸民の菩提寺であった。この寺で。幸民が作ったビールを、多くの人々と試飲した、という話が残っている。(「江戸風流『酔っぱらい』ばなし」 堀和久) 戻
バロン
バロンというのは酒の名ではなくて、町角のビストロやカフェあたりで、カウンターのところで立ちのみする赤葡萄酒のことで、それを入れるコップの形が、まるい風船型で、脚がついているために、バロン(風船)とよばれるわけだ。一杯三十五旧フラン。コーヒーが五十旧フランから、七十旧フランだったか、ちょっとカフェによって、パトロン(おやじ)とだべってゆく労働者、おかみさん学生たちは、大ていこれを愛用する。(「ロマネスクとワイン」 辻邦生) 戻
嫌酒権
嫌煙権が定着して久しいアメリカで、今度は大衆娯楽の王様・プロ野球(大リーグ)に、”嫌酒権”なるものが広がりを見せているそうです。左党にとってビール片手の野球観戦は、こたえられない楽しみですが、酔っぱらいのヤジや罵声はムードを壊すし、周りに迷惑となることも事実。そこで、球場にアルコール類持ち込み禁止区域が誕生したというわけ。ニューヨーク・ヤンキーズが一九八七年六月、この禁酒席の採用を発表すると、ロサンゼルス・ドジャース、フィラデルフィア・フィリーズなど、十以上の球団が続々とこれにしたがって「アルコール・フリー(禁酒)シート」の設置を決めてしまいました。さらに、シカゴ・ホワイトソックスでは、チームに対して「選手は試合後のクラブハウス内ではビール厳禁」という、この流れに輪をかけたお達しまで出されたのです。愛煙家同様、飲んべえにも住みにくい世の中となりつつあるようです。(「雑学おもしろ百科」 小松左京・監修) 戻
杯にあたった
フランケンの大酒飲みの男が毎日酒の飲むのが癖になって、酔っぱらうのがつとめだと思うようになってしまった。それでとうとう重い病気になり、生きる喜びも望みもすっかりなくしてしまいました。男は友人たちから、そんな気の弱いことではだめだ、医者にかかって薬と助言をもらえ、この病気が治れば元気になれると忠告されました。男はこの忠言に従って、医者を呼びにやりました。医者は病人に病気の助言をしようと、急いで診察しにやって来ました。医者は病人の尿を見て、脈を取ると、すべての徴候から見て、この男の病気が飲み過ぎのせいだとわかりました。病人は医者が自分の病気をどう診断したのか知りたがりました。医者はとても冗談好きな男でしたので、こう言いました。「まあ、わしの見たところ、あんたは杯にあたったとしか言いようがないよ。治りたいなら杯やグラスはてにしないことだね。」病人は言いました。「はい、先生、どうかしっかり診て下さいよ。これからは杯やグラスはいっさい手にしませんからね。たとえ居酒屋や飲み仲間たちのところへ行っても、びんからたっぷり飲むことにしますから。」この言葉に回りにいた人々はみな大笑いしました。医者も笑って、別れを告げて家に帰って行きました。(「道中よもやま話」 イェルク・ヴィクラム 名古屋初期新高ドイツ語研究会訳) 戻
喝将
宴会に出れば、必ずひとりは「喝将(ホージャン 酒豪)」と呼ばれる人がいるものである。ビールから始まって、白酒が次から次へと注文され、横倒しになった空瓶がテーブルに並ぶ。注しつ注されつ、酒が深まり、もう飲めないよ…とでも言おうものなら、日本と同じように、こうした喝将(酒豪)のおじさんは、「てめえ、オレの酒が飲めねえっていうのかよ!」と、怒りだす。「てめえ、オレの酒が飲めねえってか!」これを普通の中国語で言えば、「「イ尓」不可能我的酒?(ニーフークーナンウォーダチュー)」ところが、こんなとき、中国人は「養金魚」という表現を使う。日本語に訳せば、「瓶の底で金魚を飼えって言うのかよ」となるだろう。そんなときはすかさず、「イヤイヤ、龍を飼おうと思っているよ(養龍阿!(ヤンロンア)」などと答えれば相手も笑って許してくれるかもしれない。(「漢字ル世界 食飲見聞録」 やまぐちヨウジ) 戻
六月一日(木)
毎晩一升以上飲んでいるのに、朝何ともないのは、当地の酒、よっぽどいいのだろう。今日も校庭にて仕事。その最中、南方の島々に敵上陸のニュース。若し負けたら-なんてことを言い出すようになった。昼食は、ロケ弁(ロケーション用の弁当。内容は筆舌に尽くし難し)で済ませる。四時頃迄に、校庭へ、あんころ餅を届けるという、藤田氏よりの伝言あり。三時頃より、心ときめき、腹しんしんと減り、あんころの幻浮ぶ。四時少し過ぎ、重箱二つ届く。「ああ来たか」と思わず相好をくずす。搗き立ての餅に、あんころをまぶしたのと、枝豆も来た。皆で食った。(「ロッパの悲食記(抄)」 古川綠波) 昭和19年です。 戻
花嫁
和宮降嫁のとき、灘では「花嫁」という新銘柄の酒をつくった。これがなかなかの評判でよく売れた。商売のコツはこういうところにある。(「日本史こぼれ話」 奈良本辰也ほか) 篠田鉱造の「幕末百話」にあります。 戻
伊丹酒から灘目酒へ
上方酒の主導権争いは、寛政の末年ころ(一八○○年)が伊丹酒の最盛期であり、文化文政年間(一八二○年ころ)には灘目酒が主役にのぼった。それまで大阪の安倍川からも行われていた新酒番船の西宮出帆が確定したのは、一八四七年である。江戸という市場を見据えての競争に勝利することで、灘は質と量において清酒の主産地となった。酒蔵の裏の浜から消費地に直送できる交通手段、動力革命の水車精米、山邑太左衛門の宮水の発見など、努力と工夫を積み上げた結果の勝利である。この起業家精神を引き出したものは、熾烈な競争のほかのなにものでもない。(「酒と日本人」 井出敏博)
パブ・クロール
パブ・クロールという言葉がありますパブからパブへクロールで泳ぎ渡る、すなわちハシゴ酒のことです。二十年ほど前に、在日アイルランド人グループから実践しながら習った言葉です。酒豪ぞろいの彼らと一緒にパブ・クロールををやるのは命がけでしたね。このとき一緒に習ったのが、ラウンドという飲み代の支払い方法です。まず、誰かが全員の一杯目の勘定を払います。ですから、十人いれば十杯飲んでやっと全員の支払いが均等になるというシステムです。彼らの愛飲するギネスの標準的な一杯は一パイント、約五百五十ccです。十杯なら五リットル強にもなります。つまり、全員大酒豪であることが大前提なのです。私は一軒目のサード・ラウンドくらいに金を払い、二軒目までは何とかつきあって先に帰るのがほとんどでした。この支払い方法は、先に帰った人の割り勘負けです。しかし逆に考えれば、余計に払っているからこそ、好きなときに堂々と帰れます。(「もっと美味しくビールが飲みたい!」 端田晶) 戻
三パイントのラム酒
ニューサウス・ウェルズ(オーストラリア)の首相に選ばれたジョン・ロバートスン卿(一八一六-九一)は、三五年のあいだ毎朝一日も欠かさず、三パイント(一・四リットル)のラム酒を買いつづけた。彼はこの酒買いにいつも馬の背を借り、三パイントのうち一パイントは、ただちに自分で飲み、一パイントは愛馬の労に報い、のこりの一パイントは保革のため、乗馬用の長靴にふりそそいだ。彼はこれといった趣味道楽もなかったが、死ぬ日まで医者の世話にはならず、一日一日をたのしくすごした。(「奇談 千夜一夜」 庄司浅水 編著) 戻
一句ぬき玉へ
霽月(せいげつ)に酒の賛を乞はれたるとき
一句ぬき玉へとて遣(とか)はす五句
飲む事一斗白菊折つて舞はん哉
憂ひあらば此酒に酔へ菊の主
黄菊白菊酒中の天地貧ならず [承露盤]
菊の香や晋の高士は酒が好き (落第?)
(酒名を凱歌といふ)兵(つは)ものに酒ふるまはん菊の花(「漱石全集」)
注解に「-村上霽月氏の委嘱によって作られたもので、村上氏の縁戚に岡といふ造酒屋があり、日清戦争に勝利を得たのに因んで『かちどき』といふ銘酒を売り出すに当つて、漱石先生の賛を求めたものである」とありまっす。 戻
箕作と稲垣
十七八の頃上洛して、漢医の学を修め、二十一歳で帰藩して、大村市の女(むすめ)登井(とい)を娶り、本高七人扶持を頂戴した。文政五年(一八二二)二十四歳で抜擢されて、藩校松平斉孝(なりたか)の侍医となり、翌年藩侯にしたがって出府した。津山侯の上屋敷は鍛冶橋内、今の東京駅構内となっている辺にあって、阮甫も一旦そこへ落着き、御用のほかは専心修学した。おそらくこの時のことであろう。林家の写本に、須川賢久君実話として、面白い挿話がのこっている。阮甫は、同藩の学寮に入ったのはいいが、稲垣はズボラの隊長で、年中ピーピーだったから、無断で阮甫の衣類を持出し、質に入れて酒を飲んだ。もちろん、寮内では酒は法度だったから、彼は屋根にのぼって、冷酒を呷り、酔えば放歌高吟する。そこで生徒監が呼びつけて叱ると、「寮内は禁制ですから、私は寮を出て屋根にのぼり、天と与(とも)に飲んでいたのです」と強弁して、面白がるというような豪傑であった。しかるに阮甫はそういう肌合いではなく、一生まじめで、ほとんど脱線的逸話をつくらなかった人だから、稲垣がひそかに着類を持出すのを知っても、あえて咎めず、笑って済ませた。それを徳としたものだろう。稲垣が郷里の友に送った手紙に、「箕作君も、毎度故郷御妻孥(さいど)のことを申出でられ候。しかしこの人は、古今の豪傑故、私共とは違ひ、一向望郷の情も少く、血気盛んに出精され候云々」と豪傑のお株を譲り、自分は大いにへりくだっている。(「江戸から東京へ」 矢田挿雲) 戻
日々疲々
なぜか、テレビ・ドラマに出演の声がかかる。作家の役でチョイ出はいやだと辞退すると、出番も台詞も少なくない脚本が届いた。なぜか、警察署長の役である。オーケーするほかはないが、二日ほど大船まで通わなければならない。片平なぎさ君と岡田奈々君、この二人とのカラミのシーンばかりというのが、せめてもの慰めだ。二日とも、朝は早いが午前中で終わるというので、原稿料の赤字も考えないことにする。だが、参った。厳しい残暑とライトによって、水を浴びたのかと言われたほどの汗。それに神経の消耗と精神的疲労、しかも歩いたり横須賀線に乗ったりで疲れ果てた。帰って来てからの仕事なんて、まったく不可能であった。どうして、このように疲れるのか。汗のかきすぎに違いない。だったら水分を補給すれば、疲れが恢復することになりはしないか。とかなり非科学的な結論に達し、ビールを飲むことにする。ビール瓶に五本の汗はかいただろうと勝手に推定して、早いピッチで飲み始める。三本までは、たちまち飲み終えたが、疲れはまったく恢復せず。そのせいか三本までで、それ以上は飲む気になれない。ビール五十三本の新記録が、泣くというものだ。もっとも、五十三本を飲んだのは、同じ自分でも十五年前の話。(「また酒中日記」 吉行淳之介編)笹沢佐保です。 戻
いやいや三盃
いやそうにして、勧められるままに、三杯酒を飲む。いやそうにして飲み食いし過ぎること。太田方(ほう)(一八二九年)の『諺苑(げんえん)』(一七九七年)に掲げる。(「飲食事辞典」 白石大二) 戻
酒のよき夜は
私は今年の賀状に、歌らしきものを一首書きつけてみた。
はまゆふの鉢を炉辺に護りつつ 酒のよき夜は物書き散らす -
「酒のよき夜は」つい物書きちらしてしまう貧乏学者の天国がここに出現するものらしい。おっとどっこいあぶなく第四の友情のことを忘れるところだった。つい最近になって東京の友人からあの歌はまちがっていると、とんでもない訂正が舞い込んで来たのだ。それによると「物書きちらす」はまちがいで、正しくは「酒のよき夜は酒のみ明かす」だろうというのだ。私はこの第四の友情の前に強い抵抗を感じながらもついほろりとなってしまった。年をとると涙もろくなるのだろうか。(「詩酒おぼえ書」 高木市之助) 戻
酒一元説
石毛 酒のつくり方というのは、結局糖分からアルコールができるわけで、果実酒とかハチミツ酒は初めから糖分があるものを利用する。あとは三つしかないんです。一つは口噛み酒で、口で噛むことによって唾液のなかのアミラーゼによってでんぷんを糖分にする。あとは西側の世界で発達したモヤシの酒、つまり麦芽みたいに穀物の発芽するときの糖化させる力を利用する。
小松 あれは酵素ですか、やっぱり。
石毛 酵素です。それから東側の世界ではそれをカビでやる、麹を使う。東と西の大きな違いというのを、私の同僚の吉田集而さんが、今度本に書きましたが、彼は大変大胆な説を出しています。それは一元説なんです。つまり西側の世界でできた麦芽を主にしてモヤシの酒が、東側にその原理が伝わってきて、稲もみを発芽させて酒をつくる。アッサムにそういった酒がちょっとあるんです。
小松 そうですか。
石毛 ところが、発芽させても稲もになんかは、稲の発芽したときの糖分はたいしたことはないので、ろくな酒にはならない。ところが、稲を発芽させるためには水につけなければならない。水分がついて芽が出るときはカビの繁殖にものすごくいい条件で、それで麹の酒が始まったのだというのが、彼の説です。(「にっぽん料理大全」 小松左京・石毛直道) 戻
飲み友達
藤原道隆は大変な酒呑みで、摂政になっても痛飲泥酔の性癖はあらたまらなかった。酒の上での失敗譚は、数々ある。さて、臨終の枕頭でのことである。導師から念仏を勧められた道隆は、頷いて念仏を称えたあと、うっとりとしてこう言った。「極楽には、飲み友達の(藤原)済時(なりとき)らが待っていてくれるのだろうな」極楽へ行ってからの酒盛りを楽しみにしていたわけだが、呑んべえもここまでくると、一種達人の観がある。まさに、酔生夢死の生涯であった。(「日本史こぼれ話」 奈良本辰也ほか) 戻
「養生訓」食べ合わせ例
○酒後、茶を飲むべからず。腎をやぶる。-
○酒後、芥子及及辛き物を食へば、筋肉を緩(ゆる)くす。(「食の文化考」 平野雅章) 戻
「遊仙窟」の酒器
即(すなわ)ち香児(カウジ)を喚(よ)んで酒を取らしめ、俄爾(しばらく)の中閒(あひだ)に三升可(ばか)りを受くる一大鉢を擎(ささ)げて已(すで)に来れり。金盞銀盃(キンサンギンパイ)、江螺(カウラ)海蚌(カイボウ)(二八〇 揚子江の螺と南海の蚌の飲器)、竹根の細眼(二八一 ホソメアルウツハモノ)なる、樹えい(ジュエイ やまいだれ+櫻-木)(二八二 古樹のコブなどでつくった器財らしい)蝎脣(カツシン)(二八三 毒虫のくちびるか)、九曲(二八四)の酒池、十盛(二八五 重ねる漆器)の飲器。觴(さかづき)は則ちじ(凹+にんにょう)こう(角+光)(ジクワウ)(二八六 野牛に似た一角獣の角でつくったサカヅキ)犀角(サイカク)(二八六)あり、「瓦王」 「瓦王」然(ワウワウゼン)(二八八 フカクヒロクシテ)として座中に置けり。杓は則ち鵞項鴨頭(ガケイアフトウ)(二八九 鵞の項や鴨の頭の形につくった杓)なり、汎汎(二九〇 浮かぶ様)焉(えん)として酒上に浮べり。少婢細辛をして酒を酌ましむるに、並先んじ提(二九一 とりあぐる)ることを肯(あ)へてせず。(「遊仙窟」 張文成 漆山又四郎訳注 昭和22年) 唐時代の小説で、中国では早く散逸し、伝わった日本に残った小説だそうです。 戻
「遊仙窟」の酒器2
さて、香児を呼んで酒を取りに行かせた。まもなく、三升以上ははいる大きな鉢をささげてきた。鉢には、金の鈕(つまみ)と銅の鐶(みみがね)があり、金の小杯と銀の盃が添えてあった。さらに、みつがいやはまぐりの器、竹の根に細工した器、木のこぶを蝎(かつ)の口にえぐった器があり、まったくまがりくねった形の酒池(しゅち)、大小とりどりの酒器であった。とりわけ、大きい杯としては、七升入る野牛の角の杯、四升入る犀の角の杯があり、酒をなみなみとたたえて座中においてあった。白鳥の首、鴨の頭の柄のついた杓(ひさご)が、酒の上にただよって浮かんでいた。若い女奴隷の細辛(さいしん)にいいつけて酒をつがせたが、さきに杯を取ろうとしなかった。(「遊仙窟」 張文成 今村与志雄訳 平成2年) 戻
絶えいの会
董卓「あの謀反人めが、わしの気に入りの女にからかいおった。生かしておけぬ」。李儒「太師さま、それはお考え違いでございましょう。むかし、楚の荘王が諸侯をまねいた宴会の席に、気に入りのめかけを出して酒をすすめさせましたが、突然、風がにわかに吹いて、灯火のこらず消えました。そのとき座にあった一人のものが、その女を抱こうとしましたので、女は男の冠のえい(ひも 「糸+桜-木」)を引きちぎり、そのことを荘王に知らせました。荘王は『酒の上のことじゃから』と、金色塗りの盆を出させ、席にあるもの一人のこらず纓を切らせた上で、あかりをつけさせました。この会を絶えい(ぜつえい)の会と申し、王の気に入りの女にたわぶれたものが誰であるかは、とうとうわかりませんでした。そののち荘王は、秦の兵に取りまかれたとき、一人の大将が陣中に切り込んで、荘王を救い出しました。その大将が深い痛手を負っているのを見て、たずねますと、その答えに『わたくしは しょう(くさかんむり+将)雄(しょうゆう)と申すもの。むかし絶えいの会の折り、命を助かりました御恩返しを、今いたすのでございます』と申しましたとやら。-」(「三国志」 小川・金田訳) 戻
ワインの鑑定
フランス革命下、ロベスピエールが専制政治をしいて、独裁者であったときのこと…彼は敵対する政治家を処刑するために策略をめぐらしました。つまり敵対者が、毒入りワインを兵士に飲ませたという事実をつくりあげようとしたのです。この裏づけのために、当時有名な化学者、クロード・ルイ・ペルトレが、そのワインを鑑定することになりました。ペルトレが、ワインには毒が入っていなかったと報告すれば、ロベスピエールに殺される可能性もあったわけです。しかしペルトレは、ワインを解析し、毒が入っていないという報告書を提出しました。報告を受けたロベスピエールは、自分の都合のよいように報告書を直させるため、ペルトレを呼びつけました。このときペルトレは、毒が入っていない証拠ということで、独裁者の前でそのワインを飲みほしました。ロベスピエールいわく「なんと勇気のある男だ」。これに対してペルトレは「報告書にサインしたときにくらべれば、どれほどのことでしょう」と答えたといいます。(「雑学おもしろ百科」 小松左京・監修) 戻
「下級武士の食日記」
七月十三日
(略)四ツ谷へ行、直に帰り、昼拾文の蛤これあり候あいだ、それにて酒壱盃呑候ところ、蛤も不塩梅、酒も呑ずに大いに貧ほふ(乏)
七月十八日
(略)昼飯のさいに鯔(ぼら)壱疋買、残これあるをうし(潮煮)にいたしそれにて壱盃独楽をいたし候(略)
九月十八日
(略)日本橋辺えうろつきに参りおはぎを喰、京橋の手前にてかしわ鍋喰に這入り、さてかしわを出し候ところ、大にこわく其上腐り候と見へ、大にくさく油気は聊(いささか)もこれなく、誠につまらん物出し、一口喰て返し蛤鍋と替、それにて一盃呑申候、帰りにすいとんと言物試に一碗喰候ところ、これは味噌汁へうんどんを入れこれある物にて、中々我々の喰物ならす雲助の喰物なり(「下級武士の食日記」 青木直己) 戻
男の酔い方
男の酔いかたには、大別すると二通りあって、ひとつはスーパーマン型、もうひとつはドラキュラ型の本性である。スーパーマン型というのは、ちょいとまわるとやたら気が大きくなって「田中もなア、あれはあの生きかたでいいじゃないか、なにかひとつもう一度男にしてやろう、ウァッハッハ」友達のことでもいっているのかと思うと、これが田中元総理のことだったりしてア然とするわけである。興が乗るとすぐマイクをつかんで"人生劇場""柔""兄弟仁義"など、根性ものを歌い上げるのも特徴で、うるさいけれどどこやら憎めない。世界中を自分一人で取り締まっているような気分になるらしく、オイ飲め、食え、これが欲しいだと、ようし持ってけってんで、ネクタイからカフスボタン、果てはおだてあげるとシャツ、ズボンまで脱ぎかねない気前のよさ。私などこの典型的タイプのお宅に伺って、うっかり茶の間のでかい長火鉢をほめて往生したことがある。どちらかというと雰囲気酒だから、女の方は関係ないとはいわないが、男同志がなりあって騒ぎまくって満足しているようである。一方、ドラキュラタイプは、深く静かにしんみりとひとつの話題を追求し検討し、あるいは黙りこんでカウンターの片すみ、手酌でチビリとやっている-みたいなタイプ。自然こっちの方が女にモテルし、色っぽい男も多いのだが、いったん荒れると手のつけられない酒乱の気もこっちのタイプ。じっと見ているとこのふたつのタイプは終生合い交わることない仇同志。いっしょに飲んでいてもどこかで気が合わないし、スーパーマンが「へん気取りゃがって。キザで陰気な野郎だ」といえば、片や「一人でいい気になっている大風呂敷のホラ男!」という具合で決してこの二人を同席させても隣り合わせにしたり、二人きりで取り残したりしてはならない。(「ところでもう一杯②」 山口洋子) 戻
「三田文学」の時
「三田文学」の時は、慶応義塾の大ホールであった。先生に内輪だという安心感を持たせるために、水上、里見、久保田などという連中が、前座を勤めた。「素面(しらふ)じゃ恐いから、魔法瓶に例のを一つ-」前々から先生が水上さんにそう言っているのを私は小耳に挟んでいた。例のをと言うのは、先生一流の熱燗のことだろうと推察していた。この日の演題のハッキリしたことは忘れたが、三馬、一九などに対する先生の造詣鑑賞のほどを語られたものだったが、例の語り口ゆえ、どうもよく聞き取れなかった。その上、魔法瓶からコップへついでは飲みついでは飲みしているうちに、いい気持ちになって来て、太鼓持ちがするように何か言っては照れると、持っている扇子で額を叩かれたりする。だんだん酔態が明らかになり、ペロリと舌で唇を舐めるいつもの癖が出て、先生が一ト言何か喋ると、聴衆はワーッワーッと笑う。その笑いに消されて、とうとう何も聞えなくなってしまった。(「食いしん坊」 小島政二郎) 先生は泉鏡花だそうです。 戻
J・ブース
酔いにまかせての歴史的大事件はほかにもいくつかある。たとえば、リンカーン大統領を暗殺したJ・ブースは、予定の計画とはいえ、その決行の当日、ハシゴ酒をし、すくなくとも一本のブランデーと、かなりの量のウイスキーを飲んだ。二軒目の酒場には、リンカーン大統領のボディガード、J・パーカーが居合わせたが、かれも泥酔状態で、したがって大統領の身辺警護は完全に空白だったのである。(「一年諸事雑記帳」 加藤秀俊) 戻
酒茶論 酒の功徳
客人(きやくじん)酒にちとばかり。科(とが)あるをしるといへども。酒に大きな徳あるをしらず。まづ本草(ほんぞう)の主治(しゆぢ)をいはゞ。米酒(さけ)薬勢を行(めぐら)して。百邪悪毒の気を殺す。又血脈を通じ。腸胃を厚くし。皮膚を潤し。湿気を散(ちらす)とは。憂(うれい)を消し。怒(いかり)を発(おこ)し。言(こと)を宣(のべ)。意を暢(のぶ)とは。臓器の説。脾気を養ひ。肝(かん)を扶(たすけ)。風(かぜ)を除き。気を下すとは。孟「言先」(もうせん)が説(とく)ところ。馬肉桐油の毒を解(げ)し。胆石発動諸病を治す。熱(あつく)してこれを飲ば。甚(はなはだ)よしと時珍もいへり。されば仏も酒を賞(ほめ)て。甘露の良薬と宣(のたま)ひき。又波斯匿王(はしぢやくわう)の末利(まり)夫人。飲酒戒を犯せしとき。世尊これを咎(とがめ)給はず。かくのごとくの犯戒(はんかい)は。大功徳を得たりとて。却(かへつて)これを称(ほめ)給ふ。さるによつて。菩薩は酒をもつて人に施す。仏に於て過(あやまち)なし。と説給ひしも故あるかな。四天王には天漿(てんせう)あり。これを名つけて花酒(くわしゆ)といふ。阿修羅は四大海をもて。酒としてこれを飲み。なほ足らざれば無酒(むしゆ)といふ。無酒は阿修羅の翻訳也。上(かみ)は四天王より。下(しも)は阿修羅界に至るまで。酒を好まぬ仏もなく。如来蔵(によらいざう)のその中に。酒の徳夥(あまた)あれども。茶の徳は終に聞えず。(「胡蝶物語」 曲亭馬琴) 戻
五姓田芳松
ヨシマツ画伯は、安政二年(一八五五)有馬家の中屋敷に生まれた。九歳でワーグマン氏に師事し、十一歳から、非常な画才を発揮し、十五六歳の頃には、すでにその画風に、一種の特色が現れた。父芳柳画伯は、人も知るごとく、はじめて絹地に西洋画を試みた人であるが、ヨシマツ画伯は十五六歳で、父にかわって宮内省御用の画を立派に描き上げて、その道の人を驚かせた。明治天皇が北陸道東山道へ御巡幸のみぎり、供奉を仰せつかり、その写生画はお褒めにあずかったことがある。明治十三年渡仏して、当時有名なボナー師について、刻苦精励し、サロンに出品して、日本人で最初の入選の栄を得た。ところが性質が、直情径行で、少しも世におもねることをせず、それにこの西洋画家は、江戸時代の名人かたぎがあって、前金にもらった画料は、右から左へ使い果し、仕事は気がむかなければしない。画債ばかり積んで、年中金のないところまで、昔の名人そっくりであった。そのかわり彼は、千円の画をかくにも、十円の画をかくにも全力を注いだ。そして肖像画でも、風景画でも、かきかけたらかきあげるまで、毎日晩酌の時に、それを自分のそばへ持ってきて、一口飲んでは眺め、眺めては一口飲み、何升飲んでも、杯を伏せなかった。そうして曰く、「人物ならば、その人と語るがごとく、風景ならば、造化の妙を味わうごとく、我が名画を肴として飲めば、夜中飲んでも飲み飽きず、夜中ながめて眺め飽きない」(「江戸から東京へ」 矢田挿雲) 五姓田芳松(義松)のことだそうです。 戻
石川島燈明台
磯吉は、弟子どもの手前も恥じず、一生懸命に清水奉行から、自然石組立法を習得した。やがてこの一風変わった石垣の上に、六角形の燈明台ができて、夜な夜な淡紅色のあかりがともされた。燈明台というけれど、寄せ場でしぼる菜種油をとぼすのだから、まず大仕掛けの行灯(あんどん)と思えばいい。ただし燈室は、障子紙のかわりに羊の皮をはり、光力は三里外にまでとどいた。構造や材料は、どうあろうとも、過渡期の燈明台たることはたしかである。羊の皮を張ることは、長崎の真似をしたので、長崎には往々破れやすい紙のかわりに、透明な羊の皮をはった行燈が、用いられたそうである。磯吉は、この燈明台の築造に成功して、維新後、九段の燈明台と駿河台辺の屋敷の石垣とに、例の自然石組立法を応用して成功した。燈明台が落成したところで、清水奉行は、その工事費を働き出した徒役人(ずえきにん)を慰めんものと、五月十日の大潮に、彼等数百名を開放して、汐干狩を催した。徒役人は驚喜して、貝を掘り、波に戯れ、青空の下で終日遊楽した。太陽が愛宕山の後に沈みかける頃、清水奉行は、新築の燈明台の火皿のところから首を出し、扇をさっと開いて、一同を招いた。徒役人は一令の下に集合して、一人も散逸しなかった。それと共に、沖にもやっていた苫船(とまぶね)も、燈明台の下へ漕ぎよせ、苫をはねあげると、中から寄せ場役人がたくさん現れ、菰弧もかぶりの樽を陸へ運び上げた。徒役人は、清水奉行の寛猛両端に、用意の周到なるを感嘆した。下役等は大杯に一杯ずつ酒をくんで、彼等にふるまった。上戸はのどを鳴らして喜び、下戸は別に別に甘いものをもらって、これまた舌つづみをうった。それが済むと、今度は燈明台の縦覧を許した。羊の皮ではった火皿の室にも酒樽が据えてあって、ここでも一人一杯かぎりふるまった。重ね重ねの待遇に、涙の出るほど嬉しがったが、清水奉行は厳重に見張って、決して度を過ごさせなかった。彼等は房総の山々を酒の肴にして、一杯ずつ飲んでは、杯を次の者へまわした。これが例となって、毎年五月と九月の両度に、遊楽と燈明台の縦覧が行われ、徒役人は、この二日を、地獄で仏に逢うごとく待ちこがれた。(「江戸から東京へ」 矢田挿雲)石川島の人足寄せ場と、その奉行清水純畸(じゅんき)、筋違い門外に住んだ石工磯吉の話だそうです。 戻
盃中の蛇影
【意味】疑えば、なんでもない事までが神経を悩ますもとになることのたとえ。河南の長官楽広の親しい友人が、役所の壁にかけた弓が杯の酒に映るのをへびと思ってから病みついたが、楽広から説明を受けると病気が治ったという故事。 【参考】疑心暗鬼を生ず(「故事ことわざ辞典」 鈴木棠三・広田栄太郎編) 戻
狗に肴の番
犬に酒のさかなの番をさせる。犬の前にえさを置いたようなもの。太田方(ほう)(一八二九年)の『諺苑(げんえん)』に掲げ、<白氏文集六十四、渇馬守レ水、餓犬(がけん)護レ肉>と注記する。(「飲食事辞典」 白石大二) 戻
仮説
数年前、来客と話ながら夜遅くまで飲んだ後、すっかり酔っぱらってベットに入った。目を閉じると、ベットが私の周りでぐらぐら揺れているように感じられ、胃はおどっていた。次の日は締切りに間に合わせるために、一日中びっしりと書かなければならなかったので、宿酔になったら困るぞと、という思いが離れず、私は思い切って起き上がり、酔いを追い払おうとした。そして、着がえて、海岸まで歩いていった。-風の強い日だった。三十分ほどして、ふたたびベットに上がったときには大分気分がよくなり、翌朝には宿酔は薄らいでいた。しばらくして、今日もまた飲みすぎたなと思いながら床についた晩、私はまたあの方法を試みてみようと思った。そして、実際、家内がベットに来たときには、私は目をさまして起きる準備をしていた。だが、このとき気が変わり、そのまま寝込んでしまった。翌朝には宿酔は柔らいでおり、朝食後には消えてしまった。そこで、私の体を回復させたのは海岸までの散歩だったのではなく、起きて宿酔を追い払おうとした初めの行為だったのではないかという疑念が頭に浮かんだ。三十分の散歩では、宵のアルコール摂取分を実際に燃えつきさせはしない。そこで、私はこの仮説を実験してみた。次に多量のワインを飲んで寝たとき(これは)非常にまれな場合だということを強調しておく。つまり一びん以上も飲むことはめったにないからである)、私は努めて、「自分自身を暗示にかけよう」とし、自分は散歩に行こうと思っていると信じこもうとした。だが、私はそうは思わなかったらしい。翌朝、私はひどい宿酔になった。このとき以来、私は、秘訣は散歩に行くことか、あるいは、完全にそうしようと思うことにあることを発見した。もし、私が実際にそう意図したなら、効果はあるようだ。このことから、意志的行為が何らかの肉体的プロセスをつかさどり-ある時点で目をさますという能力に類似した-、そして、これは夜、無意識裡にも作用しつづけると推論した。(「わが酒の讃歌」 コリン・ウィルソン) 戻
アブサントは悪魔の酒
アブサントは一七○三年、フランスの医師オルディネール博士によって作られ、一七九七年、これをペルノー・フイス社が製品化した歴史あるお酒です。ところが一八八四年、フランス陸軍が解毒剤として採用したところ、飲んだ人に続々と異常が現われ、使用禁止となりました。もともとアブサントとは、仏語で「ニガヨモギ」のことで、このニガヨモギを主体に、たくさんの香草類をブランデーに入れて作ったのがアブサント。アルコール度六十八度という強烈なお酒なのです。このとき、ささやかれたのがアブサント中毒という言葉。一度、このお酒の魅力に取りつかれると自分では「悪魔の酒」といいながらどんどん中毒の深みにはまっていきます。当時、ヨーロッパではデカダンが流行していて、ヴェルレーヌ、ランボー、ゴッホ、ロートレックなどの狂死の原因は、じつはこのアブサント中毒だったといわれています。(「雑学おもしろ百科」 小松左京・監修) 戻
ラッカ
これにはトルコのワインが、結構なのであるが、ハッサン・ベイハ、ラッカの水割りを試みないかと、いう。私はうなずいた。ラッカなら、アンカラへ来る途中、エルズルムから増結された食堂車で呑んだことがある。日本でいうなら焼酎、外国ならウォトカ、ジンに類する蒸留酒である。透明で匂いも少ないが水を入れると、アーラ不思議。サッと白く濁るのである。後に、イラクのバクダットでも、アラクといって、ほぼ同じように白濁する酒に遭遇したことがあった。こちらは、ナツメヤシの実から造るのだそうであるが、トルコのラッカは何から造るのか、聞き漏らした。(「世界を食べ歩く」 豊田穣) 戻
食客三千人
そこで孟嘗君は馮驩(ふうかん)を近くへ呼び、頼んだ。「それがしの愚かをかえりみず、来てくだされた客たち三千人あまりある。領分の年貢だけではもてなしに足りぬゆえ、薛(せつ)のものへ金を貸しつけておいた。一年あまりになるが金はかえさず、どうも利息さえ出さぬものがおる。このままでは客たちの食事にも事かくと思われるのじゃ。ひとつ先生、取り立ててくださらんか」。馮驩は承知しましたと答えて、出かけた。薛に着くと、孟嘗君から金を借りているものをよび出し、皆を集めると、利息十万文がはいった。そこで酒をたくさん造らせ、肥えた牛を買い、借りているものを呼んだ。利息を出せたものは皆来い、出せないものも来い、すべて持ってきた借金の証文を引き合わせてしらべる、というのである。その日には牛を殺し酒もりを始めた。酒が充分まわったころ、やおら証文を取り出し、前のように引き合わせたが、利息を出せないものには元金を返す期限を定め、貧しくて利息さえ出せぬものには、証文を取り上げて焼いた。「孟嘗君が貸し付けをなされたのは、農民で本業のたつきを失ったもののためである。利息を取るのは客たちの費用が足らぬからである。このたび余裕のある者には返還の期間を定める。貧困の者には証文を焼いてすててしまうことにする。諸君、腹いっぱい飲んだり食ったりしてくれ。このような殿さまの信頼にこたえないでよいものだろうか」と言ったから、すわっていた者いっせいに立ち、再拝して感謝した。孟嘗君は馮驩が証文を焼き捨てたと聞くや、腹を立て使いをやりよび出した。馮驩が来ると、孟嘗君は言った、「わしの食客は三千人、じゃから薛へ貸し付けさせた。わしの領分は少ない。それでも領民が期限ごとに利息を出さぬものは多い。客たちの食事にも事をかくと思うたゆえ、先生に取り立てを頼んだのじゃった。先生は取り立てた銭をそっくり牛や酒の料にし、証文を焼いたと申す。何ごとじゃ」。馮驩「さようです。牛や酒をたくさん用意せねば、皆が集まるわけはございません。誰がゆたかで、誰が困っておるか、わかりますまい。ゆたかな者には期限を切りました。困窮の者に番をつけて責めたて、十年しても利息がふえるばかり。きびしくすれば逃げてしまい、こちらがすてるのと同じこと。とてもつぐないとはなりませぬ。殿さまの方には金銭の利益をこのみ、領民に情をおかけにはならぬと評判され、領民は借金の義理をかき上(かみ)にそむく悪名をとるばかり、民の心をはげまし、殿さまのおん名をあげるたねにはなりますまい。役にも立たぬ借金の証文を焼き、あてにもならぬ金の目あては投げ出しましたのは、薛の領民が殿さまのご恩に感じ、おん名も高くなりますように念じましていたしました。それをお疑いになさいましょうとは」。孟嘗君は手を打って感嘆し礼を言った。(「史記列伝」 司馬遷 小川・今鷹・福島訳) 戻
酒の給仕
私たちは教誨師として長老教会派の熱心な牧師ビーティー氏(一七一五?-七二)を一緒につれて行ったが、兵士たちが一向に彼の祈祷や説教に出て来ないと言って、氏は私にこぼしたものである。兵士たちは入隊の時、給料と糧食のほかに、毎日ラム酒一ジル(容量の名、四分の一パイント)だけもらう約束で、その酒は朝半分、夕方半分と二度に分けてきちんきちんと支給されていたが、私の見たところでは、彼らはそれを貰いにはちゃんと来ているのである。そこで私はビーティー氏に言った。「酒の給仕などをなさったりしてはあなたのお仕事の威厳を損ずることになるかも知れませんが、あななご自身が、それも祈祷がすんでから酒をお分けになるようになさったら、きっとあなたの所へやって来ましょうよ」氏はこの思いつきに感心し、この仕事を引き受けることにし、数人に手伝わせて酒を計り分ける仕事を始めたところ、そのやり方が申し分なかったもので、今までになく大勢の者がきちんきちんと祈祷に出席するようになった。それを見て私は、礼拝に出席しないからと言って軍律で処罰したりするよりも、こうした方法のほうが望ましいと考えたものである。(「フランクリン自伝」 松本・西川訳) 戻
エビスビールあります。
はじめての街の夕食時、「さて、どの店に入ろうか?」と悩むことがある。適当にラーメンでも食べて、さっさとホテルに帰るのはつまらない。地元の人と話をしたり、地物を食してみたいとも思うのが旅人なのだ。私の場合、酒場のカウンターに座り、地元の客や店主と話をするのが、夜の一番の楽しみでもあるから、夕食の店選びは大きな問題となる。店の条件はまずカウンターがあること。団体客が入っていてうるさい店は避けること。常連客がカウンターを陣取って、一見(いちげん)の客が入っていけない雰囲気を醸し出している店も避けたい。食べ物はできるだけ、地物を食べたいが値段は抑えたい。店数が少ない街も困るが、逆に多すぎても迷う。さて、どうしたものか…。こういうときに」もっとも頼りになるのが、「エビスビールあります」の看板である。ヱビスのある店に、大はずれはない。最近は以前のような確率ではないが、私は経験上、そう思っている。(「旅のらくがき」 千石涼太郎)
この著者はサッポロファンだそうです。 戻
卓袱料理
長崎の卓袱(しっぽく)というのは大変な料理である。急行「雲仙」で着いた晩に上西山町の富貴楼で食べたのを例に取ると、先ず酒が出るのは普通の料理と違わないが、それと一緒に御鰭(ひれ)というものが運ばれてくる。これは一種の吸いもので、ただお椀が大きくて中身も餅、海老、椎茸、それから海老で作った蒲鉾を海苔で巻いたものなど、色々とあって、吸いものよりも食べものの感じがするのは、茶懐石の煮ものに似ている。御鰭と呼ばれるのは、客一人に就いて鯛を一尾使った証拠に、椀毎に鯛の鰭を二つずつ付けるからだそうで、客が先ずこの鰭を取り除いて宴会が始まる。そしてこの御鰭で食欲をそそって置いて、それを酒の方に向けさせるのが狙いらしい。兎に角、前半は飲むのが主なのだそうで、その積りでこの次に出て来る小鉢と称する各種の盛り合わせ料理を見るとなる程と頷ける。日本では、酒飲みは殆ど何も食べないことになっていて、事実、いい気持ちで飲んでいれば食べる方を忘れ勝ちであるが、これは一つには後から後からと料理が運ばれるのがめまぐるしくて、それに付き合っていては飲む暇がないからでもある。そこを、卓袱料理のように或る間隔を置いて小鉢を出し、それが鮪と鯛と「魚箴」(さより)の刺身だったり、?(このしろ)と卵の黄身を鮨の形に作ったものと独活(うど)を牛肉で巻いたものと胡瓜だったり、牡丹鱧(はも)と菠薐草(ほうれんそう)とトマトの酢のものだったり、青海苔が入った羊羹と鶏の甘煮と薑(はじかみ)の甘酢だったりすれば、食べながら飲むという、食いしんぼうで飲み助である凡て健全な人間の理想をいやでも実現することになるし、食べる程に、それだけ又飲む気になる。(カステラの町・長崎) 吉田健一) 戻
数字
十七屋という商売もあった。これはちょっとむつかしい。十七屋=十七夜=立待ち月で「たちまち着き」の語呂合わせ。飛脚のことだ。ほかには闇屋のことを八百三十屋、質屋のことを三四屋とか二五屋とかいう例もある。「妾(めかけ)の一人も囲えなんで終ってしまうとは、ほんまにワシも五合徳利や」という。五合徳利にはどんなにがんばっても一升は詰まらない。つまらぬ一生、のシャレである。その妾のことを「○・四五リットル」という。二合はん=二合半である。メートル法、尺貫法入り乱れて、シャレの解読もなかなか骨が折れるのである。(「ジョーク大百科」 塩田丸男) 戻
大空式左衛門
ところで、でかい方の話にもどるが、先の身長記録で二位の二二八センチというのは、大空式左衛門という力士である。体重は一三一キロだから、ジャイアント馬場型のソップ・タイプだったと思われる。この人は、身長だけでなく、飲み食いの記録も残している。記録によると、「酒五升を飲んだあと米五升を食った」とある。ざっと考えて、一八キロくらいの物を胃の中へおさめたことになるが、人間の胃にそんな許容量があるのだろうか。どうもあるようなのだ。なぜなら、二位の大砲萬右衛門なる力士は、「焼きいも七・五キロ、ごはん三十六杯」を食べているからだ。飲む方では、雷電為右衛門が日本酒二十升、初代朝潮太郎がビール三十七本、酒六升、初代鳳凰馬五郎が酒十三升飲んでいる。…やれやれ…。(「しりとりえっせい」 中島らも) 戻
晩酌のある風景
晩酌なんてものは、昔は、身分ある者しかしなかったものなんだそうだ。晩酌というのはもちろん中国の言葉で(白居易の詩にあるから中国では古くから行われていた習慣なのだろう)、ヤマトコトバにはこれに当たる言葉はない。しいていえば、アガリザケ、オシキセなどだろうが、これは奉公人や出入りの職人に、一日の仕事の労をねぎらって与える酒なのである。-
群飲こそ正しい酒の飲み方だと柳田国男先生もおっしゃっているのだがなァ、とぼそぼそと呟きつつ今宵も老妻のお酌でさびしく飲むのは、「バァシャク」なのである。(「ジョーク大百科」 塩田丸男) 戻
ビール工場
二十数年前に日本の協力を得て作ったビール工場が老朽化して、腐ったようなビールしか作れなくなった。中国のビールの中には、無論うまいものもあるが、ときに、「これがビールか」と思ってしまうような、ひどいのもある。中国名誉のために言えば、同じようなビールはソ連にもインドにもある。「国営工場や国家管理企業のビールは万国共通の味がする」と言いたいくらいである。スッキリさわやかな点では、日本のビールが世界一だと思っているが、そのせいかどうか、中国側から日本のビール会社に、「ついては、新工場を建てたいが、協力してもらえまいか」という要請が持ちかけられた。そこで、技術者が現地に飛んで、まず実情を調べようということになった。行ってみて、その技術者は、何とその工場のビール製造施設はこの二〇年間、一度も掃除されていないことを発見した。タンクの中もパイプの中も、澱(おり)のようなものが溜まっているし、パイプの継ぎ目にも溜まっている。それがビールをまずくしている主たる原因で、ほかに大した問題はないから、分解掃除をすれば元どおりのビールが作れるはずだ。日本から来た技術者はこう判断して、早速実行した。結果は、もちろん大成功であった。この技術者の臨機応変の対応で、新工場を莫大なコストをかけて建てることなく、問題は解決した。また、中国の人たちも自分たちの落度を反省し、この日本人技術者に感謝した-こういうハッピーエンドで終わったと信じたいところがだ、私は少々違った想像をしている。たぶん、彼らはガッカリしたのではあるまいか。というのは、彼らの希望は「いいビールをつくりたい」というより、「新工場建築にあたって、大いに日本を旅行したり、日本の出資・融資にぶらさがって楽しみたい」ということにある場合が多いからだ、(「食卓からの経済学」 日下公人)
平成1年の出版ですが、今は昔といった感慨がありますね。 戻
関矢酒店
東京・台東区の東上野にある六坪ほどの小さな酒屋が、いま酒の業界で大きな注目を浴びている。外観はどこにでもあるふつうの酒屋だが、一歩店内に入ると、そこには他の酒屋ではお目にかかることのない名前とラベルの日本酒がズラリと並んでおり、その理由が納得できる。そう、この「関矢酒店」の主人・関矢健二氏は、蔵元と協力して四七銘柄ものオリジナル吟醸酒を世に送り出している、日本でただ一人の「日本酒プロデューサー」とちてつとに有名なのである。この関矢氏、一〇年少々前まではオーストリア大使館に勤務するサラリーマンであったという経歴もユニークであるが、脱サラで奥さんの実家の酒屋を継いでから独学で酒に関する知識を磨き、全国の蔵元を巡り、納得のいく酒と酒屋業の方向を探し求めたという。そして、その三年ほどの”修行”で得た結論が、「他の酒屋とは異なる独自の道を歩む」ことと「造り手ではなく、飲み手の論理で酒を造る」ことの二点であった。その結論に沿って、昭和五十八年に第一号のオリジナルブランド酒「かんなびの里」(本醸造酒:栃木・小島酒造店)以来、次々に独創的、個性的な銘柄を開発し、全国のうま酒ファンにぶつけてきた。(「日本酒の経済学」 竹内宏監修・藤澤研二著) 平成19年に関矢健二は亡くなったようです。 戻
梅崎春生、ニュートン
梅崎春生(はるお)は新調の洋服を着て家を出たが、あちこちでハシゴをして良いきげんで帰宅した時にはズボンをはいていなかった。その頃、彼ら作家や評論家がよく通った新宿のハモニカ横丁は、片側があるフルーツ・パーラーの壁で、それに向かって客たちは立小便をすることがよくあったが、彼はそこでズボンを落としてしまったらしかった。
ニュートンは若い頃、毎夜遅くまで勉強しすぎて病気になったほどだった。しかし残っている彼の小遣帳には居酒屋の飲代(のみしろ)や、トランプで負けた支払いも書いてある。(「世界史こぼれ話」 三浦一郎) 戻
コップ半分の甘口ワイン
これとほとんど同じ頃だが、毎週日曜日の朝、私は高齢で一人暮らしの母方の祖父の家に留守番をしにいっていた。祖父がミサにいっている間に火が消えないようにしておくのであった。私は村人たちの自慢話の中から、トーストしたあつあつのパンの薄切りに、パテに似たブルース[プロヴァンス地方の羊の乳から作られるフレッシュチーズ]をたっぷりと覆うように塗ったものが美味しいということを、いくたびか聞いたことがあった。このブルースは祖父の家にいつもあったので、私は好奇心と美味しいものが食べたい欲望を容易に満足させることができた。まず、暖炉の隅に腰掛けて燃え残った炭火のいくつかを手前の方に引き寄せて串を乗せ、その上で二枚のパン切れをトーストし、すぐさま例のブルースを全面に塗った。私はこのチーズトーストを、コップ半分の甘口ワインといっしょに敬虔な気持ちで賞味した。(「エスコフィエ自伝」 オーギュスト・エスコフィエ) 10才頃の思い出だそうです。 戻
25~70グラム
昨今では清酒でも甘辛論議が盛んだが、清酒は辛口と言っても1リットル当たり25グラム程度の糖は含んでいる。また甘口といってもせいぜい70グラム以下である。この範囲より糖が少なければ水っぽく感じるし、多ければいかにも甘ったるくなってしまう。これに対しワインは、ごく辛口だと1リットル中に糖が2グラム程度しか含まれないものもあるが、酸のお蔭で風味はしっかりしているし、逆に特に糖が多い貴腐ワインの場合のように250グラムもあっても、同時に充分の酸も含まれているので、美味しく飲めるのである。ワインの2~250グラムと清酒の25~70グラムという数字を見ただけでも両者の違いが判るであろう。(「ワイン手帖」 ワイン入門講座 鴨川晴比古) 戻
「あまカラ」
食味雑誌で今日になお大きい影響を残しているのは、戦後間もなく発刊された「あまカラ」であるように思います。物資不足の時代に人々にやすらぎと希望を与え、昔のおいしい食べ物の伝承を知らせてくれる、食い倒れの大阪の発案らしい月刊誌でした。大阪のお菓子の老舗、鶴屋八幡さんと清酒の菊正宗さんが後援、水野多津子さんが編集長、朝日新聞の客員だった大久保恒次さんが後見をなさっていました。超一流の文士方が執筆され、普通のPR誌とは感じが違い、食の大切さを知らず知らずのうちに教える雑誌でした。(「包丁余話」 辻留 辻嘉一) 戻
権蔵
甘酒・白酒は、女子供の好む飲み物として、奈良時代の昔から親しまれていたという。酒というくらいだから、アルコール分が無いわけではない。
甘酒に よばれ権蔵 千鳥あし
甘酒に 酔って権蔵 又ころび
権蔵(ごんぞう)は、子供用の草履で子供を指す。(江戸風流『酔っぱらい』ばなし 堀和久) 戻
瓢正とますだ
正月の食い物に飽きて、ぶらりと木屋町の馴染みの京料理「瓢正(ひょうまさ)」へ寄った。主人の正さんとは、一緒に錦小路を歩く仲である。「あっさりしたものを、少しだけ食べさせてくれないかな、正月の接待の酒で胃がくたびれてまんね」そして、出された一椀のすっぽん雑炊、これは旨かった。正さんが、私の胃の調子をお見通しのすっぽん雑炊、食い物の味なんてものは、早々に忘れるべきものであるという私が、いまだにその感覚だけを残している。先斗町の酒亭「ますだ」との交際も古い。私はこの店の京風のお晩菜、おからの炊いたのやじゃこと大根の炊き合わせ、大名炊きで、賀茂鶴の冷やを盛大に飲む、といっても五合どまりだが、この頃では、酒にすっかり弱くなり、限度を越すとコロリといかれる。(「新・口八丁手包丁」 金子信雄) 戻
タテ看のタンカ
もっとも僕にも学生時代のように近所の飲み屋で飲んだくれていた時期があった。たいてい安い日本酒で、それをガブガブ飲むものだから当然悪酔いした。悪酔いして誰かがつぶれると大学の構内から「米帝打倒」なんていうタテ看(立て看板)をとってきて、それをタンカにして下宿まで運んだ。あれはあれでなかなか役に立つものでる。一度だけ運ばれている途中に看板が割れて、椿山荘の横の階段でいやというほど背中を打ったことがあるけれど。しかしそのような馬鹿騒ぎも四カ月ばかりで終わり、それ以来みんなでわいわいと酒を飲むことはまったくといっていいくらいなくなってしまった。要するにつきあいが悪くなったわけだが、そのおかげで僕は僕のその丈夫な胃にますます磨きをかけつつ今日に至ることができたわけである。何を食べてもおいしいし、悪酔いもしないし、胸焼けもしない。実際に見ることができないのは残念だけれど、僕の胃はかなり良い色をして、イルカみたいにつるつるピチピチしているのではないかと推測する。海に放してやるとどこかに泳いでいってしまいそうな気がする。酒のことに話を戻すと、僕は今では日本酒というものはほとんど飲まないが、これは学生時代に日本酒で悪酔いをつづけていた後遺症である。その責任は百パーセント僕の側にあって、日本酒側にはない。もし日本酒を飲まないことで裁判にかけられとしたら僕は一切の自己弁護を放棄してその罪に服する所存である。-
最近どういうわけか日本酒が大好きになって、昼間からソバ屋でちびちびと飲むということが多くなってしまった。水丸氏に言わせると、「村上くん、それは人間的に成長したんだよということになるのだが、本当かなあ?」(「村上朝日堂の逆襲」 村上/安西) 戻
登高亭等の酒句
静謐の元日微酔の時流れ
酔醒めにすぐき冷たき炬燵かな
師走風酒屋早めに店を閉め
ほろ酔いの熊手かついで帰る人 登高亭
鮓を圧す我酒醸す隣あり 蕪村
おでん屋の酒のよしあし言ひたもな 誓子
冷やっこ死を出で入りしあとの酒 虚子(「味の歳時記」 吉村公三郎) 戻
五月十一日(東京)
今日、東宮から三重ねの金杯を御成婚記念に戴いた。新郎と新婦が三の杯から酒を飲むことが、挙式の主要部分にまっている。この種の杯は普通、金蒔絵(きんまきえ)のある赤いうるし塗りのものである。ところが宮廷では、金の杯が使用される。(「ベルツの日記」 菅沼竜太郎訳) 明治33年です。 戻
酔つ払ひは大嫌ひ
酒は好きだが、酔つ払ふのはいやで、特に他人の酔つ払ひは大嫌ひと云う勝手なわが儘は世間には通用しないかも知れない。しかし私はそれが本気なのだから、若い者相手の遠慮のない席などでは、杯の合ひ間合ひ間に酔つ払つてはいかんと訓戒するが、さう云ふ時の小言は相手に取つては肴の役目しかないらしく、へいへいと云つて内に虎に化けて、手がつけられなくなる様な事はしよちゆうである。酔つ払ひのしくじり話を、その当人の口から聞くのも嫌ひである。尤も、軽い座興の程度の話ならそれほどにも思はないが、さう云う話ばかりを集めた座談会の記事などで、本人が自分の失敗を得得と話してゐるのを読むと、酒飲みの外道の様な気がして、苦苦しく思ふ。その癖、私自身の文集の中に、さう云う事を書いたものがないわけでもないから、結局この感想も私の口から云つたのでは、世間に通用しないかも知れない。(「酒光漫筆」 内田百閒) 戻
因幡堂
▲男 これは、このあたりの者。某(それがし)の女は大酒飲みゆゑ、去つて(離縁すること)ござる。因幡堂(いなばどう)へ参り、(新しい)女房の事を、通夜して、御夢想次第(夢の中の神仏のお告げに従うこと)に持ちませう。参る程にこれぢや。拝みまして通夜仕(つかまつ)らう。 ▲女房 妾(わらわ)が男めが、妻の事を、因幡堂へ参り、御夢想次第に致さうと申すと聞いた。去られたは苦しうないが、心がにくい。さればよく寝た。やいやい、西門(さいもん)に立つたを女房に持てよ。 ▲男 はあはあ、忝(かたじけな)や忝や、まづ西門へ行て見やう。さればされば、これにござる。申し申し、御夢想のお妻か。 女房つま(妻)ぢやと云うてうなづく。 ▲男 もはや追付(おつつけ)宿へお供申しませう。某(それがし)は乃(すなわち)負うて(おぶって)参らう。負はれさしられませい。是でござる。おりて、そのさかづきを取らせられまうせい。 ▲女房 いやまづ、盃事(さかずきごと)しませう。 男飲みて女にさす。ひきうけひきうけ五六盃のむ。男肝をつぶして、 ▲男 また大酒飲みぢや。もはや納めませう。そのかづき(かぶりもの)取られられう。いやでもおうでもかずきを取らねばならぬ。平(ひら)にお取りやれお取りやれ。 ▲女房 やいやいをとこ、わらはをさつて、因幡堂へ ようよう妻のこと、祈念に籠(こも)つたな籠つたな。 ▲男 われは何しに来たぞ。 ▲女 何しに来た。おのれ、いやでも御夢想ぢや。添はねばならぬ。 ▲男 おれはおぬしがやうな者はいやぢや。 ▲女房 どうでも、いごかす事でもない。 ▲男 あゝかなしや。ゆるせゆるせ。 ▲女房 どこへ、卑怯者、やるまいぞやるまいぞ。 ▲男 まづ談合してから。 ▲女房 やるまいぞやるまいぞ。(「狂言記」)全文です。 戻
「木否」杓(はいしゃく)に勝(た)えず
【意味】酒を飲みすぎてこれ以上はとても飲めない。 「木否」=杯。 【出典】張良入謝曰、沛公 不レ勝二「木否」杓一、不レ能レ辞。謹使下臣良奉二白璧一雙一、再拝献二大王足下一、玉斗一雙、再拝奉中大将軍足下上〔史記 項羽記〕(「故事ことわざ辞典」 鈴木棠三・広田栄太郎編) 戻
明治七年の物価
店売諸相場、上白米十銭五厘二毛、上酒一升二十銭、上醤油一升十八銭、塩一升二銭三厘、油一升二十四銭。<明七・五・一二、新聞雑誌> 《解説》明治九年の金禄公債の発行、つづいて同十年の西南の役のために急に多額の不換紙幣が増発せられ、同十年夏頃から物価騰貴、したがって紙幣価値の下落となった。(「新聞資料 明治話題事典」 小野秀雄
編) 戻
サリチル酸
-しかし、その酒にすら、日本の「工場製」は、防腐と称して、サリチル酸などをまぜたがるわけで、サリチル酸といえば、昔は水虫タムシインキンの薬だったが、ともかく世界のどこの国だって酒などに入れないこの皮膚病の薬を、日本だけは平然と酒になげいれて恥じなかった。ま、それもよかろう、厚生省が許可しているのだから、と、こういう点についてはまだまだ寛容な向きが多いのも、日本の特色であるが、しかしそういった太っ腹な御人も、一回、目の前の酒で、実地の試薬試験をされてみなさい。げえっと渋い顔になること自明である。〇・五パーセントの塩化第二鉄の溶液を、スポイトで一押し、サリチル酸入りの酒になげいれてみよう。酒は一瞬に、インクよりも濃く青紫色に変ずる。(「男のだいどこ」 荻昌弘) これも昔の話になりました。 戻
ばけもの
「こればかりはひらによしやれ」「イヤ大事ないよ。化屋敷はおらが得手ものだ。幽霊でも出やがつたらばぶち殺して、すましの吸物にして一盃呑む」と、五升樽引きかたげて明き屋敷へ行き、化物を待てども出て来ぬゆへ退屈して「ドウダ、早く出やがらぬか。ドウ仕やがる」と悪口しながら、引きかけ引きかけのみ倒れた。グツト寝てフツト目をあいたれば、カアカア。「南無三、夜があけた」と門へ立出で、大きな声で「ドウシテ出得るもんで。おれを誰だと思いひやる。モウ重ねてから出やがるな、鼻垂らしめら」といふと、門のわきから「ベラボウメ、出る時は寝て居やがつて」(仕形噺・安永三・ばけもの)(「江戸小咄辞典」 武藤禎夫編) 戻
スコッチ、ポート
ポートとは、ポルトガルの北部ドルコ河の上流の両岸(幅一〇ないし三〇マイル、長さ三〇マイルの地域)で生産された成熟した葡萄を原料とし、製造過程においてブランディを加えてアルコールを二三パーセントに高め、オポルト港から積出されるという三条件(一九一四年のポルトガルの法律および、一九一四年のイギリス・ポルトガル通商協定)をもった葡萄酒のみをいうことに厳重に制限されている。現在ではフランスのコニャック、シャンペンおよびドイツのライン・ワインなどの名称についても、各国はポートと同じように原産地の表示について誤認の生じないよう厳重な使用制限を加えて、保護することを約束しており(一八九一年四月十四日のマドリッド協定)、日本もこの協定に加入したから(一九六五年八月)、スコッチ・ウィスキーとかポートワインという名称は、現在日本産のものに使用できなくなっている。(「趣味の価値」 脇村義太郎) 戻
文は人なり
今まで忘れていたが、洲之内さんは現代画廊の主人なのである。どうせ怠け者なのだから、毎日出ている筈はない、出てももう帰った頃だろうと思い、夕方になって会場をのぞいてみると、洲之内さんがいる。「文は人なり」というけれども、これほど文にそっくりは人もいないだろう。目が合ったとたん、お互いに「こんにちは」で済んでしまった。周囲の環境も文に似ていた。それは「気まぐれ美術館」で読んでいたせいもあるが、苦労したのは古風なエレヴェーターである。戦前の遺物なのであろう、入口にこまかい注意書きがあるのだが、私の悪い眼では読むこともできない。梅原龍三郎氏が画廊を訪ねた時も、エレヴェーターでもめた話を洲之内さんは書いているが、まごまごしている間に、ひょっとしたはずみで蛇腹戸が閉まり、私は無事に三階の画廊へ登ることができた。今時こんなおかしな画廊も、画商も、日本広しといえどもないに違いない。それが私の初印象であった。その夜は二時ごろまで飲んで家に帰った。何がそんなに面白かったのか、思い出すことはできないが、その後画廊をとずれる度に、そういう始末になる。そこには大勢の人々が入れ替り立ち替り飲みに来る。いずれも洲之内さんの友人で、中には作品を見て貰いに来る画家も交っている。(「遊鬼」 白洲正子) 戻
ウォッカ瓶詰め水
最後に訪れたプラハ市は、アラビアン・ナイトの雰囲気をとどめる、魅力的なまちだったが、ここでも放送責任者モフシン氏の自宅に招かれてご馳走になった。宴の前にモフシン氏が挨拶し、ウォッカで乾杯となった。私はそれにたいしてお礼を述べ、また乾杯である。ついで、ロシアから同行した人の挨拶、タシケントから加わった人の挨拶がつづいた。挨拶のあとは、かならず乾杯である。「私たちウズベク人は母親を尊敬します。それは女性を大事に知ることです。どうぞ奥さんもひとこと」モフシン氏は同行の私の妻を指名する。彼女も仕方なく短い挨拶をし、また乾杯となる。(おやおや、これでは宮古島のあの「おとおり」とおなじではないか)と、私は苦笑した。ちがうのはウォッカと泡盛だけである。土地はかわっても、人情はおなじだな、と妙に感動をおぼえた。ところが、宴も終わるころ、モフシン氏がことしメッカ巡礼に加わったことがわかった。メッカに巡礼すると、「ハジ」という称号が与えられ、模範的イスラム教徒とみなされる。禁酒はイスラムの戒律である。さきほどからモフシン氏が飲んでいたのは、ウォッカではなくてウォッカの瓶につめた水であったのだ。
(「雨過天青」 陳舜臣)NHK「シルクロード」撮影時の逸話だそうです。 戻
放哉の酒癖
尾崎放哉も日記に書いているのですが、この町(小豆島)の料理屋を飲み歩き、ある店では芸者さんに向かって、「芋掘りみたいな面をして…。肥桶でもかついでいる方が似合う」と毒づいたり、また別のある店へ入って、そこの初老の主人が「帝大を出られて、大会社のお偉い重役であらせられたそうですね。頭休めにこの島においでになっておられるのですか」って言うと、「頭休めとは考えたじゃないか。顔に似合わず小知恵が働くな」なんていうような調子でやるんですね。-
先ほど言いましたように、放哉には生まれたときから酒癖の悪い根があるんですね。ですからこれはどうしても治るわけはない。ただ放哉が店で悪態をついているときに、西光寺のご就職を呼んでくるぞと言うと、放哉は顔色を変えて、「勘定!」と言ってすぐ出ていっちゃう。悪態をつくのをやめちゃうんですね。(「私の好きな悪い癖」 吉村昭) 戻
一滴万粒
酒は、一しずくが、たくさんの米粒によって造られたものである。松葉軒東井(しょうようけんとうせい)の『譬喩尽(たとえづくし)』(一七八六年)に掲げ、<酒一滴盈(こぼ)さざる誡(いまし)め>と注記する。(「飲食事辞典」 白石大二) 戻
三醸酒の試醸
いま振り返ってみると、昭和二十四、五両年は、日本人の飲酒が極端に焼酎へ偏っていたことがわかる。この二年間、課税移出数量に占める焼酎の割合は、どちらの年も二九パーセント強。清酒、ビールをおさえて首位に立っていたのである。清酒は、原料米割り当てが、逐年増石されたとはいえ、昭和二十四年酒造年度においても僅か四万八五〇〇石であった。そのため、不足解消の対策として、この年から三倍醸造による試験醸造が全国二〇〇場で開始された。これを表から見れば、清酒増産とコスト・ダウンを実現する技術の追求であったが、裏から見れば、アルコールの用途開発という点で、合成清酒とは一線を画しているとはいえ、共通する思想であった。ここで、注目しなければならないのは、この三倍醸造法がアルコールの品質に厳しい要求を出し、それが高純度アルコール生産技術の進歩を促したことである。全国のアルコール工場で、アロスパス式蒸留器への転換が昭和二十六年から急速に行われたのは、清酒用に見込まれる醸造用アルコールの市場獲得競争がそこにあったからである。(「酒・戦後・青春」 麻井宇介) 戻
ビーラー
もちろん、私は大ビール徒である。大麦酒である。「ビーラー」である。「酒」の新年号の文壇酒徒番付でも、「ビールしか飲まない」という条件によっても西の横綱にしてもらったくらいだから、ビールとともに三十年の歴史と伝統とは一種の無形文化財的価値を認められたといってよいであろう。まったく、ビールのために一生を誤ったのである。そこで、ビール・シーズンともなれば気もそぞろ、ペンをとればビールのこと以外は書きたくなくなってしまうのも無理からぬところであろう。(「酒童伝」 火野葦平) 戻
鶴歩町と平野町
鶴歩町(かくほちょう)という変わった町名の由来は、案外簡単である。あの辺も、もとは潮入り地であった。享保八年(一七二三)五月、平野甚四郎忠重が、官に請うて、私費で溝を掘り、堤を築き、はじめて水田とした。平野新田がそれである。しかしそれでも潮水が侵入して、平野新田には、米の生る見込みがなかった。忠重は少しも屈せず、ふたたび官に請うて地上をして、今度は市街地とした。そうして自分の隠居名をもって、町名とした。鶴歩は、忠重の隠居名である。忠重の家は、先祖代々織田家に仕え、大阪城の没落の時の当主甚右衛門は、城を枕に討ち死した。河内の国平野村にいた妻某は、身重のまま江戸へきて、浅草旅籠町一丁目に侘住居(わびずまい)して、男の子を産んだ。それが成長して、町人甚右衛門となり、飴屋になった。平野飴がすなわちそれである。甚右衛門の子佐兵衛、孫甚右衛門はともに酒屋になり、甚右衛門の弟甚四郎が、その跡をついで、元禄十一年(一六九八)元木場の内の埋立てに関係して、二十二カ町の名主役を仰せつかり、自分のいるところを平野町と名づけた。だから鶴歩町と平野町とは、一つの腹から生まれた町兄弟であった、ともに甚四郎忠重に負うところが、多いのを忘れてはならぬ。(「江戸から東京へ」 矢田挿雲) 深川の町名だそうです。 戻
夫婦に大切なものは一杯のお酒
小泉 うらやましい。本間さんご夫婦は仲むつまじくて「夫婦の鑑」とわたしは思っているんです。夫婦円満の秘訣ってなんでしょうね?
本間 一杯のお酒じゃないかしら。というのはねぇ、日本酒でもワインでも飲むと、二枚の舌が滑らかに動くようになってくるでしょ。会話も活発になってくる。話題も縦横無尽にあちこちから出てくるので、年月を経るとちゃんとかみ合うんですね。
小泉 なるほど。まったく飲めなくても「夫婦の間で酒は重要なもの。」この文言は一つの至言かもしれない。そういう意味からも夫婦間の上手な酒の飲み方というのは、とても大切ですね。(「怪食対談 あれも食ったこれも食った」 小泉武夫) 小泉武夫と本間千枝子の対談です。 戻
馬乳葡萄
葡萄酒となると、葡萄よりもさらに貴重であった。葡萄が伝わって七百年もたっているのに、唐初にまだ葡萄酒がつくられなかったのはふしぎな気がする。それはもっぱら西域から貢物として献上された。一般の人の口にはいるようなものではない。おそらく葡萄酒づくりには秘法があって、西域のオアシス国家では、国家的な企業秘密として、外にもれるのを厳重に防いでいたのであろう。長安あたりの葡萄園の葡萄を原料にして、試作がおこなわれたかもしれないが、うまくいかなかったようだ。唐が国産葡萄酒の製造に成功したのは、高昌国を版図におさめてからであった。-
唐の太宗に攻められ、高昌は唐に併合されてしまった。独立性を失ったのだから、国家企業の機密-葡萄酒製造の秘法も、守れなかったのはいうまでもない。長安をはじめ唐の各地でいくら試作しても、西域からの献上品のようなおいしい葡萄酒ができあんかったのはとうぜんであった。原料がちがっていたのである。-馬乳葡萄。と呼ばれる酒類のものでなければならなかったという。その実はまるいものではなく、細長い形をしている。円球形ではなく楕円球形なのだ。高昌の故地であるトルファンに、私は一九七三年に訪れた。そして、案内された葡萄園の葡萄に、細長いのが多いのに驚いたものである。粒はそれほど大きくない。ふつうの人の小指の半分ほどであろうか。-これは馬乳葡萄です。という説明をうけた。(「西域余聞」 陳舜臣) 戻
ケルト語ウイスキー
"マック"は濃厚な痕跡ではないか、とウィークリーに文句をつけたくなるが、それについても、かれはじつにつめたい。「ナニナニの息子」という意味の"Mac"はケルト語であったてもナニナニのほうはみな英語なのだ、というのである。かれは、言う。英語に入ったケルト語は、地名や人名をのぞけば、つぎの数語ぐらいのものではないか。clan(クラン・氏族、一族)、flannel(フランネル)、glen(グレン・谷間)、slogan(スローガン)。四番目のスローガンというのは、もとはといえばスコットランド高地人が戦いのときにどっとあげる鬨(とき)の声(war
cry)のことだったらしい。おそらく氏族(クラン)ごとに、スローガンがちがっていたのであろう。五番目がある。スローガンと同様、英語に入って、次いで世界語になったウィスキーがある。われわれはウィスキーを飲むとき、古きケルトのひとびとを思いだすべきではないか。ウィスキーのもとのゲール語(ケルト語)は定説としては、ウシュクボー(uisgebeatha)-生命の水-ということらしい。(「愛蘭土(アイルランド)紀行Ⅰ」 司馬遼太郎) 戻
お出ッきりでござい
親類一同会しての、明治三年元旦の祝宴であった。大盃の酒を、父がうまそうに傾けた。問われて父は、獄中のことを話した。獄吏が来て入口をあけ、「何の誰殿お出ッきりでござい」というのが、吟味中揚屋での死刑の意味だった。同室の者が、飯のあまりでひそかに造った酒を酌みかわしなどして、しばらくして本人は出て行って斬られる。首を切る音が獄舎のなかに聞こえてくる。いつ誰が呼び出されるかわからない。誰も一度の吟味を受けずに、或る時「お出ッきりでござい」と呼ばれて、斬られた。磐渓は、死を覚悟した。かつて養賢堂学頭在職中は、小役人の意地悪にあってヒポコンデルに罹った父上だが、自ら義と信ずるところは、「堂々たる筋を立てられたのであるから、びくともなされず凛々乎(りんりんこ)浩々然として居られた」のである。(「言葉の海へ」 高田宏) 幕末の混乱時、獄中の人となった大槻文彦の父、磐渓が文彦の奔走で出獄した当日の祝宴だそうです。 戻
明日より禁酒
あすから酒をやめる。あすからやめるのだから、これからも毎日飲み続けることになる。奥田頼杖(らいじょう 一八四九?年)の『心学道の話』に、<息子いよいよ嘆息して、何か案じておりましたが、やがて、何と思いかえたやら、手を突いて、言いますは、「いかさま、生涯禁酒の事、きっと、得心しました。しかしながら、私も。あれほど好きな酒を、生涯呑まぬ事と思えば、どうやら精が落ちたようで、力無うも思いますし、そのうえ、もはや、今日が、酒とは生涯の生き別れと申すものなれば、せめての名残に、今日一日は、御赦(ゆる)しなされて下され。」と申すゆえ、親父(おやじ)も「もっともの事。」と思い、「そんなら、今日一日は赦して呑ますべし。明日よりは、きっと生涯禁酒ぞ。」と、申し附け、大きな紙へ墨黒に、「生涯禁酒」と書き附けてやりましたところ、息子が見て言いますは、「このとおり、已来(いらい)、きっと、相守り、生涯酒は呑みますまい。しかし、そのうち、今日は御免の事ゆえ、この脇へ、『但し今日は赦す、明日より。』と御記(しる)しくだされ」と申すゆえ、-」>
(「飲食事辞典」 白石大二) 戻
酸素パーティー
椎名 僕はアフリカのキリマンジェロで、けっこうひどい高山病にやられましてね。
佐治 どのくらいの高さですか。
椎名 約六千メートルです。非常にしんどくて、もう二度と山は嫌だ(笑)という感じでした。
佐治 高山病というのはしんどいらしいですな。
椎名 ええ。それでも四千メートルぐらいまでは僕たち酒を飲んでいましてね。
佐治 それはすごいわ。ところが四千七百メートルあたりでガクッときましてね。酸素ボンベを使うほどではなかったですが。
佐治 われわれもそういえば持っていきました。
椎名 その重たいボンベを、わざわざ持ち帰るのもばかばかしいというわけで、下山の途中酸素パーティーをやったんです。なにか気持ちのいいことがあるんじゃないかと、酒を飲みながらみんなで代わる代わる吸ったんですよ。秘密の麻薬パーティーみたいにして(笑)。
佐治 どうでしたか。
椎名 なーんにもなかったですね(笑)。二日酔いのときに酸素を吸うと治るというから、酒を飲みながら吸えば、酔いもどんどん醒めて、いくら飲んでも大丈夫だろうと思ったんですけれど。
佐治 単に吸えばいいというものでもないようですよ。吸い込む量にも一定の割合というものがあるらしいです。(「喰寝飲泄」 椎名誠) 佐治敬三と椎名誠の対談です。 戻
やっぱりそうか
パリの大通り、サンジェルマン街のとあるバーから出て来たふたりの男。「おい、おれはあのバーのこんどのマスターはあまり好かん」「どうして? なかなか感じがいいじゃないか」「感じがいい? ふむ、そうかな。実はあいつは、客を見る眼つきに一くせある。それがおれには気に入らん。いまもあそこを出るとき、しかめ面しておれを見た。まるで食い逃げでもするように、頭から足の爪先まで、うさんくさそうにジロジロ見やがるのさ」「それにきみはなんにもいってやらなかったのか」「おれも睨み返してやったよ…まるで…まるで…まるで勘定を払ったような顔をしてね!」(「ふらんす小咄大全」 河盛好蔵訳編) 戻
いい話だが
長谷川伸が街を歩いていると、馬力を曳いている中年の男が酔っ払って、馬に向い、「なア勘弁してくれよ、一緒に働いているくせに、おればかり酔ってしまって、すまねえなア」といっている。感心して聞いていたが、「いい話だが、これは芝居にはならない」(「最後のちょっといい話」 戸板康二) 戻
水割りブランデーと中国料理
料理ではないが、酒の飲み方のファッションとしては、世界的に水割りの流行がある。ウイスキーの水割りの応用として、現在フャッション化しつつあるのが、ブランデーを水で割って飲むことである。それをアメリカンと企業側では命名しているが、ブランデーを水割りにして飲むことは、ずっと以前から東南アジア華僑の宴会ではよくおこなわれる風習となっていた。中国料理を食べながら飲む酒として、中国酒ではなくコニャックを宴会に持ちこんで、水で薄めて飲むのである。ウイスキーは体を冷やす飲料であるのにたいして、ブランデーは体を温める作用がある酒なのでよいのだという、中国医学的説明がしばしばなされる。だが、なぜ中国料理に中国酒を飲まないのか。それは華僑という商業にたずさわる人びとの、宴会における富の誇示を象徴するものとして、最高級のコニャックが飲まれたということも一面では考えられるのであるが、なんといっても水で割ったブランデーが、中国酒以上に中国料理にあうものであることを、海外で生活する中国人が発見したということであろう。(「食事の文明論」 石毛直道) 戻
岩谷松平
岩谷松平は嘉永二年(一八四九年)、薩摩の国・川内(せんだい)町(現在の鹿児島県川内市)で、士族くずれの貧農の家に長男として生まれている、八歳で母親に、十三歳で父親に死別し、造り酒屋をしていた本家に、弟とともに引取られた。本家には男子の跡継ぎがいなかったためやがて一歳年長の本家の娘と結婚することになり、家督を譲り受ける。が、間もなく養父が、ついで妻が、二人の子供を残して病死し、ために店はそっくり彼の掌中に入った。そうこうするうちに明治十年、西南戦争の勃発である。すると、彼は薩摩人なのにためらうことなく政府軍に味方して、武器、弾薬、食料を調達して持ちこんだ。もともと彼の受継いだ店は、造り酒屋のほかに、地元、島津藩の御用商人も勤め、地金の調達や貢納米の運送などを業として栄えてきた。松平もまたその家業をいっそう手びろくひろげてきたのだ。だから西郷隆盛派の私学校の若者たちとも、浅からぬ因縁となじみがあった。その松平がいささも迷わず、政府軍に味方して大儲けしたのは、おそらく戦いの勝敗を見抜く独特のオポチュニスト的感覚のためだったのだろう。
(「破天荒企業人列伝」 内橋克人) 天狗煙草で有名な岩谷松平のことだそうです。 戻
式三献
式三献とは、古く、祝儀のときの基本的な酒肴の献立をいった。たとえば、平安時代の大饗のようすを記した『西宮記(せいきゅうき)』あたりに古義が読みとれる。「三献間 客人不二動座一 四献以後 諸卿起レ座 献レ盃」つまり、三献までが席を勝手に立つことができない酒儀礼、四献以後は席も自由に移して盃をやりとりする酒宴席といいかえることができよう。そのころから、三献をもって式正としたことがわかる。つまり、式三献を俗にいいかえれば「礼講」となる。(「三三九度」 神崎宣武) 戻
ボトル・ネック奏法
ブルーズ・ギターはあたかも人の肉声-うめくような、嗚咽(おえつ)するような、あるいは、しゃがれ声でわめくような音を立てて演奏された。そんなギター演奏法の一つにスライド奏法というのがある。あらかじめ一定の和音に調弦されたギターの弦を指で押さえずに、棒のようなものを弦にぶつけるようにしてこすりながら演奏する手法だ。その棒は硬くて、表面が滑らかなほど良い音が出た。B・B・キングの爺様世代にあたるキャップ・プリアンはポケットナイフを使って演奏したけれど、もっと良いモノがあるじゃないか。ほら、ちょうど指を突っ込める穴があいているし、硬さ、滑らかさの点からいったらこれ以上のものはない。空になったガラスのウイスキー・ボトルを眺めていたその誰かは、床に落ちていた麻ヒモを拾い上げるとランプの油に浸し、それを瓶の首の付け根に幾重にも巻き付けた。彼がマッチを擦って瓶に近づけると、麻ヒモが炎を上げて燃え上がった。彼は素早くガラス瓶をバケツの水の中へほうり込んだ。バケツから取り出された瓶の首には、麻ヒモが燃えた跡に沿ってヒビが入っていた。彼はその酒瓶の首を押し折り、にんまり笑うとそのガラスの円筒を左手の薬指にはめて、かたわらのギターを取り上げた…。以後、この奏法は【酒瓶の首奏法=ボトル・ネック奏法】と呼ばれ、高度なギター・テクニックとして確立している([4])(「おまるから始まる道具学」 村瀬春樹) 戻
年寄り
同じく老年になってもかくしゃくたる精力を誇っていたので有名な作家にアイルランドのジョージ・ムーアがいる。ある人がその秘訣をきいたら、作家はこともなげに答えた。「わしは酒にもタバコにも女にも決して手をふれなかったな。十七歳になるまでは」(「ポケット笑談事典」 ベネット・サーフ) 戻
夜明けあと(2)
明治十一年 浅草の男。酔って帰り、足を洗わずに寝ようとした。注意した養父母をひっぱたき、手足にかみつき、終身懲役の刑(曙)。家庭内暴力の発生と、再発への対策。
明治十三年 名古屋では市内から近郊の農家まで、西洋酒(ワイン)が流行。酒造家は減産。一方、伊丹の酒造家は釜山に支店を出し、好評。上海からも大量の清酒の注文(朝野)。
明治十三年 文武にすぐれた徳永という巡査。酒ぐせに注意し、禁酒をつづけ、昇進もした。しかし、ある日ふと飲んだ酒でとめどなくなり、吉原で男女七人を殺傷(東京絵入)。
明治十三年 長崎県のある村。戸長(村長)に当選した男、大喜びで二人の芸者を役所に呼び、飲めや歌えのさわぎ。ために免職。(「夜明けあと」 星新一) 戻
飲むには減らで吸うに減る
【意味】酒を飲む費用のために財産が減ることよりも、煙草代の損害の方が大きい。なしくずしの出費を引きしめなければならぬということ。(「故事ことわざ辞典」 鈴木棠三・広田栄太郎編) 戻
旨味
酒やワインの場合は糖分を醗酵させただけで、アルコール度数はあまり高くない。従って、ウイスキー、焼酎などよりはアルコール度数の関係で辛味も少なく、多分に甘みを残したアルコール飲料、ということが言えるのである。『味覚の補足性』からみて、辛味に乏しく旨味の豊富な酒は、塩味を要求する必然性を持ち、辛味も旨味も乏しいワインは、塩コショウした肉類を要求して当然なのである。私は『味覚の補足性』と呼んでいるが、一般には『味の相性』と言われている。意味は同じである。互いに不足している味を補いあって、綜合性を出すのである。料理の世界はトータルファッションであるともいえる。次に酒とワインの味覚上の違いは、『旨味』にある。外の『五味』は大して差はないが、ワインにかけて酒にたっぷりあるのが『旨味』といえよう。酒ファンが酒以外飲まなくなるのは、一にも二にもこの『旨味』のせいだといえるのである。旨味が酒に沢山あって、ワインにあまりないということは、ワインのために弁護して言うならば、ワインの欠陥ではないのである。簡潔に言ってしまえば、ワインは『旨味』の乏しさを利用して、素材の悪さをカバーし、人工の料理を完成させたと言えるのである。フランス料理の完成には、ワインの存在を欠かすことはできないだろう。(「異見 文化酒類学」 桜木廂夫) 戻
ワインは究極の酒なり
しからば、そのお前にとって、ワインとは何か?答はいささか陳腐です。結局ワインとは、小説家にとって、彼がいままで飲みつづけてきたところの一切合切の「酒の中の酒」、「酒の王にして女王」、「王の酒にして女王の酒」ということになりましょう。ワインとは究極の酒なのです。(「ワイン手帖」 ロナルド・サール著の開高健による序文) 戻
四月二四日
それから親しい友人と思いがけず会った時の挨拶や、友人や父や恋人との別れの挨拶を演じた。喧嘩口論の末、仲直りして再び別れる科(しぐさ)もやらされた。それから足の悪い一人の坊主がやって来た。すねに熱をもった膿瘍ができていたが、大したことはなかった。彼はヨーロッパのリンネルに厚く塗りつけた小さな円形の膏薬をその上につけていた。私は彼の脈をみ、患部を診察するように命じられた。一目見て私は、彼を健康で強靱な人間だと判断し、次によく注意して見て「危険なことはありません」、私は膏薬を半ば開けて、またすぐ元のようにもどし、「この薬はきっと効くでしょう。私が傷口を拝見しましたところ(しかし実際は彼の鼻先を見たのだが)〔鼻の先が赤かったか〕、この際ただ、酒を少し控えねばなりますまい」と言ったところ、将軍はじめ居合わせた人々は皆満足して、大笑いした。(「江戸参府旅行日記」 ケンペル) 将軍綱吉の前での体験だそうです。 酔っ払いの真似 戻
荻流松前焼
飛騨の高山へ行くと、特産の味噌を朴の葉で焼くための、いわば一人用小型七輪を売っている。義太夫の丸本がデザインしてあったり、質朴でイキな民芸品である。この七輪に小さく炭をおこし、かけた金網の上へ、酒でぬらした昆布を一枚しいて、そこへ、生ガキや蛤(はまぐり)の刺身をのせる。こではうまいぞゥ。いわゆる「松前焼」である。やがてじくじく音がたちはじめるころには、貝へ昆布の味と香りがしみ、醤油で食うだけですばらしい味になる。昆布が熱でかわきかけたら、さらにちょっと酒でしめしてやる。つい食いすぎ、腹をこわしかねないほどのうまさで、真冬の夜、ひとりか、あるいは差しで酌みかわすとき、これほど、ムードのでるサカナはないとさえおもう。-こういう単純な食いものや食いかたを、ひとつひとつ、他人(ひと)様からおそわり、ぬすみ、いちばん簡単なところから、じわじわとたのしみのレパートリーをひろげてゆくこと。私のやりかたはそれだけである。近ごろの醤油はマズくなった、と愚痴をこぼすと、かならずだれかが、「ああ、うちでは昆布の切れっ端をなげこんでおきます」とヒントをおしえてくださる。それをおぼえてきて、あとは昆布を日高のにするか利尻のにするか、そこはこちらの好みと工夫である。(「男のだいどこ」 荻昌弘) 戻
解僧卒
兵卒、罪を犯した坊主を護送して、夜やどにとまったところ、その坊主、酒を買ってその兵卒にすすめて酔いつぶさせ、兵卒の頭を剃って逃げうせた。兵卒、酔いがさめて、部屋中坊主を捜すが見つからぬ。自分の頭をなでると、髪がなく、しかも縄がかかっていたので、大声に叫んだ。「坊主はちゃんとここにいる。しかし、俺はどこにいったろう?」(「笑府」)
(「江戸小咄辞典」 武藤禎夫編) 戻
牧水・弘元・謙信
斎藤 -そこで、文学者と旅というと、まず第一に頭に浮かぶのは牧水先生だろうけれども、若山牧水はアルコール中毒ではなかったと思いますけれども、やはり肝硬変ですね。アルコール性の肝硬変で、わずか四十二歳ですよ、亡くなったの。早すぎますよ、もったいないです。それから、古いところですと毛利元就の父親の弘元、あの人は大酒飲みです。わずか三十九歳で亡くなっています。それから、上杉謙信、これはまあ昔ですから、どぶろくですよね、主に。濁り酒ですけれども、馬上盃で悠然と飲んでたらしいけども、この方も四十九歳で亡くなっています。これは、はっきり振顫譫妄(しんせんせんもう)というアルコール中毒の一番強い病気です。幻覚が出て、寝所に大蛇が入ってきたとか、そういう幻覚が出た。(「斎藤茂太VS梅原猛 旅・酒・文化のシンポジウム」) 戻
未亡人
★ミセス・マーフィーのドアをガンガンたたく音がした。彼女が開けて見ると、赤い顔をした男の一団が立っていて聞いた。「あなたが、マーフィー未亡人ですかい?」「私は、マーフィー夫人です」彼女は気を悪くして答えた。「でも、未亡人じゃありませんよ」「じゃ、ない?」男はゲラゲラ笑った。「まあ、今、連中が階段を上って持ってくるものを見てからいいなさるがいいや」(「ポケット 笑談事典」 ベネット・サーフ) 戻
猩々と組打ち
たゞ我家の系図によれば、元信州の出にして、家の紋章は真田氏の六文銭とその様相相似て、僅に丸の中に角なきだけが異なれり。而して又祖先の一人は山奉行を務めたることありて、或年の元日のこと、深山を巡視せしに、途に偶々猩々に出逢ひ、之と組打ちして難なく組伏せたりと云ひ伝へられし位にて、生憎信州は海とは縁遠き国なり。(「吐雲録」和田垣謙三) 和田垣姓の和田が、「和田つみ」「和田の原」のように、海の意味があるのではといったことの続きの部分です。 戻
一献酒は飲まぬもの
一杯だけ差される酒は飲まないようにする。松葉軒東井(しょうようけんとうせい)の『譬喩尽(たとえづくし)』(一七八六年)に掲げ、<葬家これを用いるゆえ。>と注記する。(「飲食事辞典」 白石大二) 戻
四月二十二日(土)
午後岩田豊雄氏来訪。私が調合するのを牡丹亭はニヤニヤ笑って注目している。私は自信ありげに、まず酒精を一杯、次に林檎ジュース一杯、褐色ザラメ少々、これに夏蜜柑のしぼり汁を加え、湯を注いでコップ一杯に掻き廻す。相手は仏蘭西仕込みの小言幸兵衛だから、何んと言うかと聊か心配していると、「うん、これは好い、今度は僕もこいつを手に入れよう」と御満悦の態である。日本薬局ウィスキー「どうも中々コクがあるね」と忽ちのうちに酔いが廻った様子。結局一杯半の薬局方により、マンサンたる有様となり牡丹亭は帰って行った。この頃、この薬用酒精が市場から姿を消したのは、「やっぱり先覚者があったんだね」と牡丹亭。肴は、佐渡ケ島産の赤貝と、ウドの酢のもの、燻製鮭、精進揚など、赤貝は絶品。(「夢声戦争日記(抄)」 徳川夢声)
昭和19年です。岩田豊雄は獅子文六の本名だそうです。 戻
十面
年の暮れに、米屋薪屋味噌屋酒屋、われもわれもとつめかけて「お払ひは出きませぬか」といふ。亭主、座禅したるごとくの大の眼をむき出し、一向有無の挨拶なし。掛取どもあきれはて「お払いはともかくも、なぜそのやうに十面(渋面)つくつてござります」「ハテ九面(工面)が悪いから」(鶯笛・天明頃・十面)(「江戸小咄辞典」 武藤禎夫編) 戻
鶏卵の味噌漬
擂りつぶした赤味噌を小深い器に三センチぐらいの深さに並べ入れて、その表面を平らにし、ガーゼを覆って鶏卵の尖った方を垂直にさし入れて、くぼみを次々につくってゆきます。このくぼみの中へ新鮮な鶏卵の黄身だけをつぶれないように静かに落とし入れます。全部のくぼみに卵黄が入ったら、その上からもう一枚ガーゼを覆い、味噌をひとならべ蓋になるように入れます。このまま二日間冷蔵庫に入れておくと、生の卵黄が味噌の塩分でかたまり、鼈甲(べっこう)色の半透明体になり、形はまんまるとはいえませんが、洒落た味が生まれております。二日目では中央が半熟玉子のようですが、三日目には完全な味噌漬になっています。ちょっと考えると、固まるようには思えないのに、立派に固まるところに面白さがあり、はじめて召しあがるお客さまなど、あなたの料理知識の豊富さに一驚されることでしょう。味もよく色調もよいのですが、すこしねちねちと歯につくうらみがあるのが欠点です。この欠点がどうも気になるということでしたら、色調の方はやや黝(くろず)んでしまいますが五、六日も漬けていただきます。ごく固くなりますし、味噌辛くもなりますから、二つに切ってさらにそれを薄切りにします。こうすれば歯につく感じはずっと少なくなりましょう。二日目の半熟玉子の状態は、味噌辛さが少なくて、鶏卵の旨味がいちばん味わえるときで、三日目の味噌漬けは、一個を四つに切ってけしの実や黒胡麻の煎りたてをまぶすと、これはまた別趣の口取りの一菜となり、六日目の薄切りは、酒の肴としてはむしろ最高によろこばれるものと申せましょう。(「辻留・料理のコツ」 辻嘉一) 戻
小島喜逸
灘の酒は、丹波杜氏の名人芸で天下に味を広めた。酒蔵が酒造工場になり、酒造の責任者が大学出の工場長に、蔵人が季節酒造工に名を変えてた昨今でも、杜氏は生きている。設備を合理化し、技術的に頂点を極めた感のある大手の会社も、なお杜氏の経験とカンを尊重する。丹波(多紀・氷上郡)は山奥の雪国である。耕地は狭く、裏作は難しい。冬、仕事のない農民にとって、寒造りの灘はかっこうの出稼ぎ場になった。誠実と勤勉さで実績をあげた。丹波杜氏の記録は宝暦年間(一七五一~六四)にさかのぼる。金露酒造の小島喜逸(きつ 七一)は、祖父から三代の杜氏だ。丹波杜氏組合会長をつとめる。多紀郡篠山町の生まれ。高等小学校を出て、すぐ灘の酒屋へ。飯たきから始めて、ようやく頭(杜氏補佐)になったのは三十九歳の時だった。「機械化の時代にも、手づくりの伝統の味を残してゆきたい」という。丹波の高校に醸造科をつくり、若い後継者を育てるのが夢だ。(「新人国記 兵庫県」 朝日新聞社編)昭和61年の出版です。 戻
月下の一群
一度こんなことがあった。「ハイ、休憩!」という佐藤先輩の声に全員、畳の上にあお向けに横になった。「いい音楽でも聴きてえなぁ」武田さんが口笛を吹いた。メンデルスゾーンの『バイオリン協奏曲』であった。「ああ、いいなぁ。なんて、いいんだ」疲労にあえぎながら、汗みどろの若者たち全員が身をよじってすすり泣いた。変な柔道部だった。夜。ほかの運動部の合宿にストームをかける。ストームといっても決して暴力行為はしない。挨拶に行くのだ。ただし、素っ裸で。深夜十二時、全員校庭に集合。素っ裸に、柔道の帯で襷(たすきがけ)をして。そして、輪になる。部長の中山さんが天に向かって叫ぶ。空には満月。雲一つない。「昭和ぁ、二十九年度ぉ夏ぅ、柔道部ぅ、合宿ぅ、想い出ぇ、大ストームぅ」と同時に大太鼓を鳴らし、全員フルチンでデカンショ節を唄い踊るのだ。 デカンショ デカンショで半年暮らす 歌い終えると、屋上へ駆けあがる。屋上には、バスケット部がわれわれを待っているのだ。「ワァーッ!」と気勢をあげて、バスケット部員の前を駆け回ると、お返しに彼らがうたう。 俺とお前は玉子の仲よ さのよいよい あとは、両部員入り乱れての酒宴となる。月は天に、耿々(こうこう)とまんまるだ。(「翔べ! わが想いよ」 なかにし礼)九段高校時代だそうです。 戻
酒呑童子絵扇面あらすじ
池田中納言国方(くにかた)の娘が行方不明になり(阿部)清明(せいめい)が七日七夜占う。清明は、娘は千町が嶽の鬼の住む岩屋に捕らえられていると、国方に告げる。国方は帝(みかど)に、都の娘が姿を消すのは悪鬼の仕業であると奏聞する。源頼光(よりみつ)に悪鬼追討の詔(みことのり)が下り、国方が四天王を従えた頼光に詔勅を授ける。悪鬼征伐のために神の加護を得ようと、頼光は八幡宮に参詣した。渡辺綱と坂田公時(きんとき)は、住吉神社に参詣した。碓井貞光と卜部(うらべ)末武は、熊野山に参詣した。頼光は、その四天王に藤原保昌(やすまさ)を加えた6人だけで出かけることを告げる。6人はそれぞれ山伏に扮して出立の用意をする。一行は、途中道に迷うが、二人の翁と山伏に案内されて先に進む。二人の翁と山伏は、六人と打ち解けて悪鬼が住む岩屋の様子を話した。八幡、住吉、熊野三社の化身である翁らに悪鬼退治のための毒酒を授けられる。三神の化身を先達として、深い谷では槙(まき)の大木を渡して進んだ。一行六人は、三神の助けで険しい岩山も越えていく。さらに一行は進んでいき、翁と山伏は三神の化身であるとあかし姿を消す。都からさらわれた女房が洗濯するのに出会い、鬼の岩屋の様子を聞く。酒呑童子の館に着くと、鬼とも人とも見える異形の者に出くわした。頼光たち一行は、酒呑童子の館に招きいれられた。身の丈一丈ほど、髪を禿(かむろ おかっぱ頭)にして、肌白く太った容顔美麗の40歳くらいの酒呑童子が姿をあらわした。酒宴が始まり、人血の酒や今切られたばかりの人の足が出され、頼光らは躊躇無くこれを口にした。酒宴も進み、童子は、眷属に舞をまわせた。今度は公時が舞う。酒を重ねた童子は酔ってしまった。童子は酔って一人奥に入る。眷属たちもすっかり毒酒に酔ってしまった。頼光一行は具足に身を固め、二人の女房に岩屋への案内を頼んだ。三神の化身が現れ、酒呑童子の手足を縛る鉄縄を渡し、寝所に入る鉄の扉を押し開いた。寝所の酒呑童子は二丈ほどの鬼の姿になり、熊のように毛の生えた手足を女房たちにさすられて寝ていた。頼光は酒呑童子の首を打ち、他の5人は起き上がる童子の体を散々に切り刻んだ。童子の首は空を飛び頼光の兜に食らいついた。酒呑童子の眷属の四天王を討ち果たす。門の外からもどった異形の鬼も切り捨てる。女房達を救い出すと、館は消え失せた。脚を切られて横たわる堀江中務(なかつかさ)の娘の髪を形見に持ち帰る。酒呑童子の家来で岩屋に立て籠もっていた金熊童子を生け捕りにした。さらに、石熊(いしくま)童子も生け捕りにした。一行は童子らの首を抱えて、女房達と千町が嶽から都へ帰る。頼光を先頭にして6人は山伏姿で馬に乗って都に凱旋した。(国立博物館 特別陳列 酒呑童子 解説) 戻
搾酒場(しぼりば)
酒蔵も母屋(おもや)もしづまり初夜掻(しょやがき)の「酉元」摺(もとす)りうたはすでに止みたり
酒蔵に揚槽(あげふね)しまる音たかし夜は母屋の遠くまでひびく
算用を夜(よ)おそく終へし帳場にて人手をからぬ寝酒わかすも
この家に酒をつくりて年古(ふ)りぬ寒夜(かんや)は蔵に酒の滴(た)るおと
夜を凍(し)みる古き倉かも酒搾場(しぼりば)の燈(ひ)のくらがりに高鳴る締木(しめぎ)
燈(ひ)のもとに酒槽(さかふね)のしまる音のして石を懸(か)けたる男木(をとこぎ)ふるふ
夜(よ)くだちて締木の懸石(いし)の垂(た)るおとも槽(ふね)もおはりの滴(た)りの乏(とも)しさ
槽(ふね)のしたの夜(よ)ぶかき瓶(かめ)に下りて汲む搾りたての酒粕くさきかも(「中村憲吉歌集」 斎藤茂吉・土屋文明 選) 戻
The spirit is out
文学によりて其の国々の風俗を知る事を得べきは勿論なるが、英文学中に「死骸と共に食卓の下に横はる」といふ文章あり。これは如何なる意味かといふに、此場合の死骸は飲み乾したる空壜の事なり。されば此の文章は「空壜と共に食卓の下に倒れ居る」の意味なり。何故に空壜がDead
menなるかといふに、空壜は即ちThe spirit is outにて、酒精の既に去りたる壜は、精神の已に脱却せる死人の如くなればなり。世の中には死人にはあらざれども、精神の無きこと空壜に等しき人あり。(「兎糞録」 和田垣謙三) 戻
バッカス号
一九三〇年代にいたってアルジェリアからの本国(フランス)への葡萄酒の輸出は国内生産の約二〇パーセントに達して、おりからの大不況と一緒になって、それがフランス本国で政治問題化し、ついにアルジェリアの葡萄酒の生産と輸出とを制限するにいたった。この大量のアルジェリアの葡萄酒の本国への輸送のためにフランスは石油輸送のオイル・タンカーにならった特別の装置をもつワイン・タンカー「バッカス」(一八一〇総トン)をつくって、樽に入れておくるかわりに裸で送ることをはじめたことは興味がある(アメリカでもカリフォルニアの業者はタンク・カーで東部にワインを送っている)。第二次世界大戦後になってもアルジェリアからの輸出の重大性に変化がないことは一九四九年になって戦時中喪失したもとの「バッカス」の代船として、さらに大型のワイン・タンカー「バッカス」(三六五〇総トン、ディーゼル船、速力一二ノット、ワインの積載力八一万ガロン)をつくったことでもわかる(『マリン・エンジニアリング・アンド・ネーヴァル・アーキテクト』一九四九年七月号)。(「趣味の価値」 脇村義太郎) 戻
鍵の穴
一七世紀、イギリスの有名な作曲家ヘンデルは、大のワイン好き。三度の食事のときはもちろん、書斎にもワインの瓶を置いて、ときおりちびちびやるのが、何よりの楽しみだった。ただし困ったことに、癖になってしまうと、来客があるときも我慢できなくなるのである。ある日、ヘンデルは親しい友人たちを食事に招いた。ところが彼は、食事の最中にときどき、「すまん、ちょっと曲を思いついたので…」などといっては、さも忙しそうに席をはずして、書斎に駆け込んでいく。最初のうちは友人たちも、「なんとも仕事熱心なヤツだ」と感心していたが、それがあまりたびたびなものだから、さすがに奇妙に思った友人の一人が、彼の書斎を鍵穴からのぞいてみた。するとなんと、作曲どころか、ヘンデルはソファにでんと腰をかけ、さも満足げにワインをちびちびと飲っているではないか!(「やんごとなき姫君たちの食卓」 桐生操) 戻
銀子さん
鶴岡の醸造元の若主人たちと飲んだとききてくれた銀子さんは、もう六十歳をこした地方(じかた)専門の芸妓さんである。夕刻六時すぎにお座敷に入ってきた銀子さんは、なにやら口をモグモゴさせているのだが、声は聞こえない。私の耳に口をよせて、「今晩は、銀子です」ささやくような挨拶なのである。酒屋さんの説明によると、銀子さんは、お酒をコップで五、六杯飲まないと、声が出ないのだという。ならば駆けつけ三杯…どうぞとばかり注いであげると、ゴクゴクと二口か三口でコップ酒を飲み干し、アッという間に三杯、まあ、なんという見事な飲みっぷりであろうか。つづけて二杯、合計五杯を飲み干して、やおら、「今晩は、ようこそ」はっきりと、さびのきいた、お腹にズシンとこたえる声で挨拶があり、一座からヤンヤの喝采(かっさい)をうけた。これが私と銀子さんとのそもそものなれそめである。この銀子さんの飲みっぷりと歌のうまさに惚れ込んだ私は、その夜はとうとう飲みあかすことになったのである。いつのころからか銀子さんは、朝になるとまるで声がでなくなり、夕方まではまったく口がきけない。ずい分と医者通いをしたのだが、どう治療しても、かつてのような声はでない、ええ、ままよ、というわけで放っておいた。ところが、ありがたいことに、お酒をいただくと、かつての美声がよみがえるというのである。それも、五杯や六杯ではなく、一升から二升、飲めば飲むほど佳い声がでるという発見をした時、まさに、奇跡がおこったのかと泣けてしかたがなかったという。もともと飲めて気風がよくて歌のうまい銀子さんは、数少ない鶴岡芸妓の中では売れっ妓お姐さん株である。お座敷を、一晩に五つや六つこなすのは平気の平左。昼間から夕方にかけて声が出なくなってから、座敷での酒量は上がるばかり。殆ど主食はとらず、もっぱらお酒だけで生きているという生活に変わっていったのは当然の帰結であった。(「酒と旅と人生と」 佐々木久子) 戻
海藤花
むしろ珍味として酒の肴に喜ばれている。タコの卵である。黒い糸のようなものにたくさんの卵が附いていて、海の中では藤の花のように見えるから、この名がある。塩水でびん詰にして、それを吸物にして食べる。(「舌」 秋山徳三) 戻
今日この頃の酒の味
山口瞳さんのお得意の俳句に、上の五文字を、「しぐるるや」とするのがあります。「しぐるるや 深川あたり 蛇の目がさ」とこうなるわけですけれど、私にはもっとつごうのいいのがあります。下の七五を、「今日この頃の酒の味」とやるんです。例の、「根岸の里のわびずまい」と同じテなんでして、「しぐるるや 今日この頃の 酒の味」と、山口さんにくっつけても何となくうまく行ってしまいます。(「うわさ帖」 半村良) 戻
飲まば朝酒 死なば卒中
【意味】酒を飲むなら朝酒、死ぬなら卒中で苦しまずに死にたい。(「故事ことわざ辞典」 鈴木棠三・広田栄太郎編) 戻
麹がない
私の現在の生活ではたいがいのものが間に合っていて、その上に野蛮人に対する恐怖と、自分の安全を保証するための心労は、更に生活を改善しようという意欲をいっそう鈍らせたように思われた。事実、私は前にはそのことばかり考えていたある意欲をすっかり放棄したのであった、それは大麦で何とかして麦芽(もやし)を作り、それで麦酒(ビール)を醸造することだった。これは実際いい加減な思い付きで、私は何度も私の単純さに気付かせられた。と言うのは、麦酒を醸造するのに必要なもので、とうてい手に入れることができないものがいくつかあることがすぐ解ったのであって、第一に、麦酒を入れておく樽がなく、これは前にも言ったように、何日も、何週間も、それどころか、何カ月もかかってどうにかして作ろうとしたことがあったが、結局失敗に終わった。次に麦酒を仕込むのにホップがなく、麹がなく、醸造に使用する銅缶もなかった。しかしこれだけの障害にもかかわらず野蛮人のことさえなかったならば、私は恐らくこの計画を実行に移して、あるいは成功したかもしれないのである。私はたいがいの場合、一度計画を立てたことは、何とかして実現しなければ承知できなかった。(「ロビンソン漂流記」 デフォー 吉田健一訳) パン作りでは、「第一に麹がなかった。」ともあります。 戻
乃木大将
去年のくれに見たテレビドラマ「静寂(しじま)の声」で乃木大将が善通寺師団長の時、東京から訪ねて来た静子夫人と元日の朝、汁粉を食べる場面があった。史実でないとしたら、脚本家の着想はいいと思った。何しろ三時間のあいだ、将軍は何かというと酒ばかり飲んでいるのだから。
(「最後のちょっといい話」 戸板康二) 戻
四月十二日(水)晴 温 [全線座第二日目]
柳好君から三遊亭可楽の死を聞いた。酒を飲んで帰宅し、二階で寝ていたが、具合が悪いので起き上り、梯子段を降りようとすると、前後不覚になり、転がり落ちて了った。其の時、何ともいえず、快い感じがしたそうだ。それから医者を呼び手当を加えたが、首から下はまるで動かなくなった。口だけはちゃんと利ける。入院させて、細君が一旦帰ろうとすると、水を飲ませてくれと言った。水よりも牛乳が好いだろう、と細君が言うと、そうかいと牛乳を飲み、ああウマイと喜んだ。そして、また水をくれと言った。あとで考えると、末期の水をそれとなく飲んでいたのであろう、という訳。それから細君に向い、両手を胸の上で組んでくれ、と言う。そんな縁起でもない、と細君は言った。息子さんが傍についていた。それきり死んで了ったそうだ。まことに極楽往生である。(「夢声戦争日記(抄)」 徳川夢声)
昭和19年です。 戻
縮緬で失礼
鮓屋のカウンターにならんですわり、私の左手に芸能界に詳しい女性の編集者がすわり、右側に半四郎さん、その右側に半四郎さんの友人、というようにならんでいました。私は女性編集者のほうを向いてしばらく話し込んでいたのですが、「縮緬(ちりめん)で失礼しますが、お一つ、どうぞ」と声をかけられ、あわてて半四郎さんのほうを振り向きました。私は話しに夢中になって、空っぽの盃をカウンターの上に置きっぱなしにしたままでした。その盃に半四郎さんは右手にお銚子を持って酒をついでくれようとしていました。洋酒と違って、日本酒は盃を卓上に置いたまま酌をしてもらうのは失礼なこととされています。酌をするほうもあまり姿のいいものでがありません。それで半四郎さんは、私に盃を手にするよううながしたのでしょう。私はあわてて盃を取り、半四郎さんのお酌を受けるべく、お銚子のそばに近づけました。そして、お酌を受けながら「縮緬で失礼」というのはどういうことなのか、と質問しました。半四郎さんは笑いながら、「熱心にお話をしていらっしゃるので置き酌で失礼します、と申し上げたのですよ」酌を受けるほうがその手に持たず、食卓の上に置かれたままの盃に酌をするのを「置き酌」と言います。先にも記したようにあまり姿のいいものではありません。だから酌をするほうは「置き酌で失礼」と挨拶をし、受けるほうはすぐさま盃を手に持って「いやいや、こちらこそ」と挨拶を返すのが決まりみないになっています。反物(たんもの)の寸法を測る時、ふつうは、布地の端を持って宙に高く上げ、布地をピンと張った状態にして測ります。しかし布地が縮緬の時だけはそうしません。縮緬は文字どおり縮んでいるのが特徴で、ピンと張った状態で寸法を測ったのでは、仕上げが狂ってしまいます。そこで、縮緬だけは、布地を畳の上に置いたまま寸法を測るのです。「置いたまま尺をとる」のでこれを「置き尺」と言います。「置き尺」と「置き酌」、発音が同じですね。ですから歌舞伎の世界の人たちは「置き酌」のことを「縮緬」と言うのです。この業界の隠語です。(「食べる日本語」 塩田丸男) 戻
思いついた順
思いついた順に挙げてみよう。銀座では、二丁目の並木座脇の「三州屋」、四丁目の「仙台酒場」、八丁目の「樽平」。新橋の「キンシ正宗酒蔵」、「蛇の新」、虎の門「升本」。門前仲町「魚三」、森下町「山利喜」、神田駅近くの「越中」、神田司町の「みますや」、水道橋「鶴八」。湯島の「シンスケ」、上野の「ほんもく」、浅草の「あらまさ」「松風」。神楽坂の「伊勢藤」、池袋「おもろ」、大塚「江戸一」、北千住「大はし」、新宿「樽平」、中野「第二力酒蔵」、荻窪「東菊」、自由が丘「金田」、蒲田「河童亭」。横浜野毛の「武蔵屋」。みんな共通しているのは、ある程度古い店であること。北千住の「大はし」は明治十年創業、司町の「みますや」は明治三十八年創業とか聞く。ほかにはあまり共通点はない。かなり店として個性ある店もあるが、銀座の「三州屋」、司町の「みますや」、北千住の「大はし」、中野の「第二力酒蔵」、荻窪の「東菊」などは、ごく普通の居酒屋に撤している。これらの店の多くは、居酒屋といっても、かなり店は広く、いずれも繁昌しているから、一年に一回や二回のぞいても、顔を覚えられるはずもない。それでは何がいいのかと聞かれても、説明に困るのだが、長い年月の間に、われわれのような無名の老若の飲んべいが、ある人は思い出したようにやってきて、ここでしばらく浮世を忘れ、酔を買った、その、気の遠くなるような積み重ねが、店に見えない何かを残しているようにも思える。「みますや」や「大はし」で飲んでいると、明治の人間たちはどんなことを考え、話し合いながら飲んでいたのか、気になってくる。ほかの、第二次大戦後の酒場なら、ぼくが酒を飲みはじめたののは昭和二十年代だから、そのころの客たちがどんなことを苦にし、悩み、悲憤慷慨して飲んでいたのか、大体察しがつくような気もするが、明治や大正の人の青春や中年はどうだったのかとなると、ほとんど見当もつかない。しかし、こういう伝統的なスタイルの居酒屋の場合、客たちが肴として食べているものなどは、基本的にはそう変わらないのではないか。ということで、そこから、一種の親近感がわき、昔の人と一緒に飲んでいるような気もしてくる。(「銀座の酒場 銀座の飲り方」 森下賢一) 戻
買うこと
小林さんの「買った!」という叫びは当時の道具屋さんを感激させたそうである。その頃小林さんにはまだ骨董を買う余裕はなかった筈だが、そこが日本の道具屋さんの偉いところで、喜んで出世払いを許したにちがいない。むろん小林さんを信用したからだが、支払いに苦労した分だけ覚えるのも早かったと思う。それについては面白い話がある。ある日、例によって茶碗か何かを買い、一杯機嫌で横須賀線に乗ったが、鎌倉で降りる時、大事な買物を電車の中に忘れてしまった。酔っても本性違わずで、ほんとに大事なものなら忘れなかったと思うが、そんな風に合理的に解釈する必要はない。何より「買うこと」の一事に集中していた時だから、買ってしまえばあとは野となれ山となれ、-そこに小林さんの実に端的で爽やかな一面がある。(「遊鬼」 白洲正子) 戻
一【主客心得の事】
客人は、人のもてなしに出したる物をば、うまき体をしてすすみて能(よ)く食うは、亭主へ対しての礼なり。亭主は、「もてなしの品、珍しからぬ物にてあんばいもよろしからねば、御口にあい申すまじ」とて卑下して、客にしいて参らせざる事、客人へ対しての礼なり。当世はその礼を知らぬ人多く、客人は食うまじきといい、亭主は無理にしいてすすめんとする事、田舎人の風俗なり。酒も規式(ぎしき)の時にはしいる物にあらず。さかもりの時には強いるを興(きょう)とする事、古今ともに同じことなり。但し、下戸に酒を無理に強いるは無礼なり。(「貞丈雑記」 伊勢貞丈) 戻
【「巡査商売仁王と按摩」で重禁固】
去る一日京都市松原の旅館の門前にて二人の酔漢が、「巡査商売仁王と按摩、門で暮らして揉んで食うコリャコリャ」と唄いたるは、立番せる査公を侮辱したりとて、即日京都軽罪裁判所へ送られ査問の末、重禁固二ヵ月罰金五円づつに処断せられたる由。関西の端歌何ぞ査公にたいするの無礼なる。<明二三・一〇・四、東日>(「新聞資料 明治話題事典」 小野秀雄編) 戻
酒というもの
私は、五十年近く酒を飲みつづけたきたが、それなりの歴史はある。若い頃は、いわゆるむちゃ飲みをして、安焼酎をコップ十七杯、清酒をお銚子二十八本飲んだこともある。当然のことながら、激しい二日酔いに苦しんだ。しかし、年齢を重ねるうちに酒は飲むより楽しむものだと知るようになり、酒量も程々になって、五十歳の頃から二日酔いにかかることは皆無になった。(「私の好きな悪い癖」 吉村昭) 戻
アルコールの作用
アルコールは身体のなかで代謝されてアセトアルデヒドとなるが、これが発がん性を持つ。さらにビールは微量ながらニトロソアミンを含んでいるし、バーボン、ブランディーなどはウレタンを含んでいる。厳密に言うと、アルコールは本来、発がん性物質なのである。アルコールは、細胞分裂を促進したり、がんの原因となるラジカル分子の産生を抑えるビタミンAの働きを抑えてしまう。また、アルコールは免疫系の働きも抑える。実際、高濃度のアルコールは食道がんの原因にもなるし、アルコールとタバコを一緒に摂るとがんのリスクが上昇することも知られている。また、富山医科薬科大学の加須屋実教授らによる疫学調査によると、長期間にわたって多量のアルコールを摂取すると肝臓や腎臓などの機能が低下するだけではなく、骨の量が減って骨粗鬆症を招く恐れがあることが判った。ただし、少量のアルコールなら全く飲まない人よりも骨の量が多いことも判明した。少量のアルコールなら食が進み胃腸の吸収もよくなるので骨の形成に役立つのかもしれない。アルコールに限らず、何事もほどほどが一番いいようだと、この年になってつくづくそう思うようになった。(「思いっきり体に効く話」 石川恭三) 戻
医者いらず
伊馬(春部 いまはるべ)さんと酒は、切っても切れない。昭和初期、新宿のムーラン・ルージュの劇作家として売れッ子になった伊馬さんは、夜な夜な新宿をはじめ「本郷バー」や「渋谷食堂」へくり出して、二十銭のモツ鍋やタヌキ正宗と称する八銭の安酒で気焔をあげたという。このモツ鍋は"医者いらず"と称するほど脂ぎったもので、いかにも栄養がありそうだたtらしい。晩年は魚をこよなく愛した。水銀やPCBの汚染が社旗問題になり、日本中が魚を敬遠した頃のこと。伊馬さんが出席したホテルの宴会で、いつも品切れになるのが相場の鮓屋台(すしやたい)なのに、誰も寄りつかない。そこで伊馬さん率先して、大きなマグロのかたまりにいどみかかり、「日本人は駄目だね、誰かが旗をふるとすぐその方へなびいてしまう。私は断固として魚を喰う。たとえ魚が汚染されていたとしても、酒が消毒してくれる!」と見得を切った。これにはわけがあって、大正の末に夕食でマグロの刺身をごちそうになった折、友人とその母親が食中毒でやられたが、酒を飲んだ友人の父親と伊馬さんの二人は何事もなかったからである。 戻
薑酒
生薑(しょうが)は魚の生ぐささや肉の匂いを消すためになくてはならないもので、物を炒める場合には生薑を線切りにしたものを先に炒めてから肉類その他の具を入れるのが常識だし、蒸物の場合には生薑を叩くか搾った汁をその上から注ぐことになっている。生薑と酒で豚肉を煮た薑酒(キヨンツアウ)は、お産の後の補血食料として今日でも民間に広く行われている。(「象牙の箸」 邱永漢) 戻
消腸酒
晋の張華、字は茂先。九?(オン)酒を造つた。三薇(未詳)を煮て以て麹蘗(きくげつ)を漬す。蘗は西羌(キヤウ)に出で、麹は北方から出たものである。-胡の地に指星麦といふものが有る、四月に火星が現れると麦が熟するので之を収穫する。蘗は水を用ゐて麦を漬すこと三夕にして萌芽する、それを暁の鶏が鳴く時之を用ゐるので、俗人は鶏鳴麦と呼んでいる。-之を以て酒を醸すと淳美である。久しく口に含んでゐると歯が動く、若し大酔して叫び笑ひ揺り蕩(うご)かさなければ、人の肝腸が消爛(とろけ)るので、俗人は消腸酒と謂つている。或は云ふ、是は長宵の楽しみを為すことのできる醇酒といふわけであると。両説は字(消腸と長宵)の声音は同じであるが、事柄は異なるのである。閭里(ちまた)の歌に曰ふ「寧(むし)ロ醇酒ヲ得テ腸ヲ消セン、日月與(と)光ヲ斉(ひとし)クセ不(ザ)ラン」と。その意味は、いつそ此の美酒に耽(ふけ)つて以て一時の快楽を取らう、なにも霊を保守して長久なることはいらない、と言ふのである。(「酒?(しゅてん)」 明・夏樹芳・著 明・陳継儒・補 青木正児・訳) 戻
相酌はせぬもの
人と酒を飲むのに、給仕の者がいなくて、互いにしゃくすることは、しないようにする。いっしょになって互いに酒をかわすことのないように。酒をつぎあって飲まないように。松葉軒東井の『譬喩尽(たとえづくし)』(一七八六年)に掲げ、<互いに酌支え合うなり。>と注記する。太田方(一八二九年)に、<相酌をすると中たがう>と掲げる。いっしょに酒を飲む、特に二人だけfだと、とかくけんかになる。
間(あい)は愛所(あいそ 想)の物とて
ふたりで酒を飲んでいる中にはいって杯を差したり受けたりするのは、好意ですることであって、飲んでいるどうしの者が頼んでもらうのは失礼である。松葉軒東井の『譬喩尽』(一七八六年)に掲げ、<押さえし盃の中飲みをいう。間せんと思う人進んですることなり。間を頼むは失礼なりと心得(う)べし。>と注記する。(「飲食事辞典」 白石大二) 戻
うなこうじまつり
愛知県には変わったお祭りが多いが、豊川市の牛久保神社の『うなこうじ祭り』も変わり種の中に入る珍しい祭りである。戦国時代の牛久保城主の牧野右白が、氏神である八幡社に きのうきよう若葉となりしか杉の森 という句を若葉の小枝に結びつけて神前に供え、牧野家の武運長久を祈ったところから”若葉祭”ともいわれている。四月七日から八日にかけての季節としてはいかにも若葉の呼び名がふさわしいのだが、うじ虫をあらわす、うなこうじと名づけなければならなかったところに、この祭りの面白いところがある。この祭りに参加する『やんよう神』(ヤオヨロズの神のなまりらしい)のしぐさは、牛久保城主の牧野右白のふるまい酒に酔った領民たちが、家に帰る途中の様子を表現し、道端に酔いつぶれて寝ころがる状態から、俗にうなこうじ(うじ虫)祭りの名がある。このお祭りの主体となるのは、近村の長山にある熊野神社にあるシシ頭を牛久保の八幡社へ迎える御輿渡御である。行列は、千成ばれんを先頭に、はやし車、桐葉ばれん、はやし車、神児ばれん、神児車、ささりんどばれんの順で、そのあとに笹踊りの一隊が続く。笹踊りというのは、手甲をはめ、赤い服を着、菊と桐の紋のついた黒ぬりの陣笠をかぶり、布で口と鼻を覆った一人の太鼓持ちと、同じいでたちの二人の小太鼓を持ちが、前にかけた太鼓を叩きながら踊るのである。そのまわりを五、六十人のやんよう神といわれる一隊が、笹踊りに調子を合わせて唄を歌うのだが、その唄の中に、「ヤンヨウ」というはやし言葉がある。このはやし言葉を合図に、やんよう神の一隊は、こともあろうに道路にゴロ、ゴロとひっくりかえってしまうのである。(「日本の奇祭」 湯沢司一・左近士照子共編) 戻
錦木
オカカというのは、今ではほとんど使わないが鰹節をカツオ箱で一人前を削って、ワサビとモミ海苔を少し入れて淡口醤油をかけたもの。熱いご飯ににせるとうまい。ただし出来合いの花鰹では駄目、名古屋のキシメンにたっぷりのっている花鰹も僕の回数には加えていない。京都の居酒屋[れんこんや]には、錦木というメニューがある。満腹だがお酒をもう一本という執拗な酔客用の突出しで、いま述べたオカカ一式にウズラ卵をまぜてある。お猪口に三分の一ぐらいの分量だ。この店では注文をうけてから、鰹節を削っている。(「食の体験文化史」 森浩一) 戻
お神酒のふるまい
(赤坂日枝山王神社の)祭礼の番組、神輿行列の次第は、御楽、太鼓、榊、社家騎馬、神馬、小旗、それから一番、二番…となる。三番(麹町十三丁分平河町、山元町)、御雇太神楽(新肴町、弥左衛門町、東材木町一丁目~四丁目)、四番(山王町、南大坂町、丸屋町)、五番(小舟町、堀留町一、二丁目)、六番(桶町)、等々四十五番まであった。ラストが霊岸島銀町分だ。ところで、この四十五番組が、毎年出たわけではない。毎年出るのは、二十二組だが、行列の次第を書いていると、煩雑になるので端折るが、ともかく、この豪華絢爛のパレードは、寛政ごろから、益々華美に流れたので、松平定信の奢侈禁止令の改革の対象となって屋台を大幅に減らされたりした。神田祭りの方も同様である。ところが化政度(文化・文政)になるとまた派手になった。こういう山車(だし)行列は、京都の祇園会などでもそうだが、商家などは店を開けて家宝の金屏風を飾り豪華な衣裳や調度などを見せる。宵宮の楽しみは、こうした家々の屏風や衣裳を拝見してまわることで、軒には家紋の紫の幔幕を張り、三宝を置き肴を供えて、来客にお神酒をふるまうのは、よく知られている。江戸のこれら天下祭りでも同じことだった。京都と違うところは、江戸っ子の見栄っ張りで、この金屏風をわざわざ借りてきて展示する。これが常識にすらなっていた。そこで、川柳子が、これを諷した句が少なくない。 かりものと見たはひがめか金屏風(「江戸歩き西ひがし」 早乙女貢) 戻
ウイスキイーフロート
鉄腕投手稲尾和久は酒豪として有名でしたが、酔ってはいけない日には特別な飲み方をしていたそうです。それは、水を先に入れてウイスキーを後から浮かせるように注いだ水割り。上からは濃く見えますし、香りも立つので、相手に気づかれずにアルコール摂取量をセーブできるのです。この飲み方は、カクテルブックにも「ウイスキイーフロート」という名称で掲載されています。ただし、カクテルブックでは、一杯でストレートからロック、水割りと、次第に味が変わっていくのを楽しむため、と書かれています。(「もっと美味しくビールが飲みたい!」 端田晶) 戻
張蛸
▲くわじや(冠者) はりだこではござらぬ。張太鼓が本でござる。即(すなわ)ち いぼ も沢山にござる。 ▲大名 おのれめは、都の者にぬかれて(だまされて)来た。 ▲くわじや いやいや、ぬかれはしませぬ。 ▲大名 はり蛸(たこ)と云う肴物ぢや。 ▲くわじや 肴ならば肴と、とうから 云うたいものでござらぬか。 ▲大名 その様にぬかれて、まだものを云うか。あちへ うせい うせい うせい。 ▲くわぢや 頼うだ者が叱らるゝは尤(もっとも)ぢや、これが、高盛にはならぬ筈ぢや。都者ぢや。たゞもぬかずに、この如くに、主(す)のきげんが悪うならうと思ふて、きげんなほしの囃子(はやし)ごとを教へた。急いで囃しましせう。 囃子物 張太鼓と申すは張太鼓と申すは、中に木を押し入れ、両に皮を引つぱつて、まわりに疣(いぼ)の候へば、張太鼓申すよ。げにもさあり。やよ、げにもさうよの(5回繰り返し) ▲大名 某(それがし)の機嫌直しに、囃子物をする。ことばをかけませう。いかにやいかにや太郎冠者、だまされたるは にくけれども、囃子物が面白い。内に入りて、泥鰌(どじょう)の鮨をほつばつて、諸白を飲みやれ。(「狂言記」)都へ肴の張蛸(はりだこ 干しダコ)を買いに行って、だまされて、太鼓を買わされてきた太郎冠者だったが、ご機嫌取りにと教わってきた囃子をしたところ、大名の機嫌は直ります。 戻
料理用二級酒
子供のころに見たテレビ映画でも、金髪のトロイ・ドナヒューがデッカイ冷蔵庫から氷をドサッと掴んでグラスに入れ、バーボンだろうと思われる酒をドクドクッとついで、背中でドアを閉めながらコーラを飲むみたいに立ってゴクゴク飲んでいた。そのころの私は台所の床下から、母が買い物に出かけた留守を狙って料理用の二級酒をこそっと盗んで、子供模様の湯呑みで水を飲むようなしつらえで宿題をしながら飲んでいた。が、それも実のところは「今日の試験はうまくいった。めでたい」などとひとりごちながらチビッチビッと飲んでいたものだ。(「斗酒空拳」 吉永みち子) 戻
酒の先生
私に酒というものを始めて教えてくださったのは、他ならぬこの奥野信太郎先生である。そしてそれは私が大学三年の時であった。と書くと、それまでの私がえらく堅ぶつにみえるが、実はそうではない。戦争中と戦争直後を学生生活で暮らした私には酒というものを滅多に飲む機会がなかったのである。戦争中の配給酒は乏しい食料を補う芋やカボチャと引きかえになり、終戦後、闇で手に入れる日本酒も学生にはあまりに高くて手に入らなかったからだ。大学三年の頃に私は『三田文学』の同人に加えられ、その会合にも出席を許されるようになったが、その会合の帰り道、奥野先生と既に亡くなった丸岡明氏という先輩作家に、はじめて飲み屋というものに連れていって頂いたのである。飲み屋といっても戦争が終わってまだ三年目である。東京の至るところに焼跡の残っていた時である。それは一軒の建物でも家でもなく、露店のような葦簀(よしず)ばりの小屋で、そんな小屋が今の新宿武蔵野館から国鉄の線路のあたりにかけてずらりと並んでいたのだ。そこはちょうど北アフリカのアラビヤ人町の迷路のような雰囲気があった。尿の臭い、酔漢の吐いたゲロの臭い、それに鯨肉をにる油の臭い、魚を焼く臭い、そういった様々な臭いが小屋と小屋との間に漂い、至るところから、戦争に敗れた日本人のやけのやんぱちの歌声が聞こえてくるのだった。一つの小屋は四、五人の客が腰かければ満員になる狭さで、そこに坐ると、たいていコップに入れたカストリが黙っておかれるのであるが、始めてカストリに口をつけた時、なぜ、こんなのを皆がうまそうに飲んでいるのか、ワケがわからないほど臭く、まずかった。愚かにも私は当時、焼酎ぐらい飲めないようでは一人前の小説家にはなれないのだと考えていたから、修行のつもりで、ほとんど毎晩、この闇市のような飲屋街に来るようになった。一杯のカストリが当時、三十円で、そのほかに爆弾と称して一杯二十円のアルコールも飲んだが、これはうっかりすると眼がつぶれると聞いてからやめてしまった。(「ぐうたら人間学」 遠藤周作) 戻
飲まぬ酒には酔わぬ
【意味】原因がなければ、結果は生まれないことのたとえ。(「故事ことわざ辞典」 鈴木棠三・広田栄太郎編) 戻
ひつかいてとめがす売はまけて行(ゆき) おし付けにけりおし付けにけり
留粕(とめがす)を買ったら、粕を少しひっかいておまけしてくれた。気は心というものである。 ○とめがす=板状の粕(「誹風柳多留三篇」 浜田義一郎-監修) 戻
独裁者の酒量
スターリンは飲んだ。それについて思い出話がある。一九四一年春、日ソ中立条約が成立した直後、調印場式場で乾杯を行った。ほかのものが皆シャムパンを飲むのに、始めのうち、スターリンだけは小型のグラスに手酌で桃色の酒を注いでいた。この酒は一本しかなくて、どうやら彼の専用らしかった。私は奇異の感を禁じ得なかったが、しばらくして松岡(洋右)外相が、天皇陛下のために乾杯しよう、と提議すると、スターリンは破顔一笑、「よし、それならシャムパンだ」と言って、みごとに一杯あおった。それからは、飲むは飲むは、浴びるように飲む。鯨飲とはまさにこのことだと思ったことだったが、カリーニン首相、近衛首相、モロトフ外相、と思いつくほどの人はことごとく乾杯の対象となるというわけで、乾杯また乾杯。スターリンがこのありさまだから、モロトフ以下のソ連要人は、この時とばかり、平素の酒量に物を言わせて、グイグイと杯を傾ける。しまいには、シャムパンでは駄目だ、ウォツカだという騒ぎになった。その果てが、スターリンが酔歩蹣跚(まんさん)として、駅頭に姿を現し、松岡外相を抱擁する一幕となって、全世界を驚かしたのは有名なエピソードである。(「外交官の酒」 加瀬俊一) 戻
伊勢神宮の神酒(1)
神酒は白酒(しろき)、黒酒(くろき)、醴酒(れいしゅ)、清酒(せいしゅ)の四種がある。神宮では「白黒醴清(しろくろれいせい)」とよびならわしている。これは重要な神饌であるが、醸造の発展していない時代は、三節祭の由貴大御饌祭(ゆきのおおみけさい)と正月元日など節日のほかはお供えされていなかった。古くは二種で、内宮は白酒と黒酒。外宮は火无浄酒(ほなしのきよざけ)と火向神酒(ほむけのかんみき)といった。火无(無)とは火を用いないでつくった酒で、火向とは火にかけた酒の意味。この醸造には専門の職掌があり、清酒作物忌(きよさかとこのものいみ)、酒作物忌(さかとこのものいみ)といって、清浄無垢な少女が主となって従事していた。もちろん物忌の童女だけでは困難だから、その父親が補佐して親子で奉仕したのである。 戻
枕元にビール
渡辺 ところで、それとは関係ないですが、小泉先生に聞きたいことがあります。酒を飲むと早く目が覚めてしまいませんか?それが私の悩みのタネでござんす(笑)。
小泉 それは、本邦初の小泉理論で即解決します。そういうときはコップに少々ビールを入れてカポリンコと飲みます。ビールには炭酸ガスが入っていますから、胃袋からシューっとアルコールが吸収されます。普通の酒よりビールの方が七倍速く吸収されます、ハイ。そうしますと足もとがポッポッポッと温かくなってきて、そのままスーッと眠れるのです。
渡辺 気の抜けたビールでも大丈夫ですか。
小泉 OKです。これは実績と体験で築き上げた小泉理論であります。合い言葉は「枕元にはいつもビールを」 (「怪食対談 あれも食ったこれも食った」 小泉武夫) 渡辺貞夫と小泉武夫の対談です。 戻
小野忠重
小野忠重は明治四十二年(一九〇九)、東京・向島の酒屋に生まれた。絵が好きで美術学校に行きたかったが、老舗の酒屋奉公からたたき上げた父親の許すはずがない。セッタに屋号入りの前掛けをつけ、酒瓶の並ぶ店先で腕組みをした写真が残っているが、さぞかし忠重青年は無念の思いで毎日を過ごしていたのだろう。昭和七年(一九三二)、新版画集団を結成。メンバーは芝秀夫、武藤六郎、藤牧義夫ほか。議論をかさね、小野忠重がまとめたと思われる「設立趣旨文」には、つぎのようなくだりが見える。「創作版画はあらゆる方面から大衆化を叫ばれている」浮世絵の歴史に見るとおり、版画はもととも大衆性の要素をもつものなのに、自己陶酔して高級化を目ざしていないか、自分たちは「多くの理屈より一つの制作」、「無意味な制作より強い熱意」をもって大衆の前へ出ていくだろう-。小野版画館には通観十八号に及ぶ『新版画』はもとより、この間のポスター、同人たちの手紙、交換した版画の賀状その他、一切の資料が保存されている。昭和十年、藤牧義夫は風呂敷につつんだ作品を小野に託して姿を消した。二十四歳だった。小野忠重が版画誌の収集と保存を思い立ったのは、それが時代の荒波のなかで消えてしまうのを怖れたからだろう。手づくりのおぼつかない画廊兼ジャーナリズムであって、官展のように豪華なカタログにとどめられない。版画誌が失われれば、そこに貼付されたオリジナル作品も消え失せる。『新版画』の仲間の芝秀夫は本郷の酒屋の息子で、こちらも商売がいやでたまらない。それでもせっせと商いを手伝い、貧しい版画家を助けるためだろう、ことあるごとに絵を買っていた。その粒よりのコレクションが、ある日そっくり小野に託された。『版画の青春』のあとがきに、小野忠重は愛惜をこめて書いている。「…柴じしんはなぜか自作をやめ、コレクションは私に贈与され、なかまの研究資料として呼吸をはじめたのだが、自作をやめた彼をおもうと、私はいまも涙がにじむ」-
散歩から帰ると、酒が三合。無用のハガキを捨てさせず、白や青の地塗りをして、その上にワリばしに絵具をつけてチョイチョイと描く。世間ばなしのできない人には、それが日常との対話だったらしい。(「二列目の人生」 池内紀) 小野忠重版画館は、杉並区阿佐谷北2-25-16
にあるそうです。 戻
自序
満二歳-よちよち歩きの頃、盃を持つ手にすがって、父の晩酌の上前をはねた小生だそうです。それ以来、折にふれて飲みましたが、小学校の成績は六年間優等で、アルコールの害なんてものは、別に認められなかったようであります。 十三歳-当時難関の府中四中の入試をパス、映画(その頃は活動写真)を見に行ったのがバレ、教員室に呼び出され叱られたのに憤慨して早中に転入、その時分から生意気にも枡呑みの味を知っていました。十七歳-文明館時代、館の稲荷祭に列席した際、幾ら飲んでも平気だったので、館員一同に呆れられた夜、酒に対する自信といったようなものが出来上がりました。 Enid
Markey(巨匠トーマス・H・インス監督「シヴィリゼーション」に主演、「戦時の女」で名優フランク・キーナンと共演、第一代ターザン俳優、巨漢エルモ・リンカーンの相手役などをした)が好きとなり、その彼女の名をもじって、本姓二戸を利用したペン・ネームをでっっちあげました。また、更にそれをもじったのが二斗無酒。考えてみると二斗は筆者の丁度一ヵ月分の平均酒量に当るのも一奇ですが、それから計算するともう二三年で、小生の平げる酒は大体百石に達する勘定になるようです。我ながらもよくもおあァ飲んだものだなァとも思います。(「日本酒物語」二戸儚秋) 戻
ときのかね
さる者、振舞いに行きて、いかう夜更ける迄遊びて、酒に酔ひぶらぶらと帰るに、浅草の新寺町を通りけり。門跡前の番太郎に「もはやいくつじや」と問へば「六十二になります」といふ。「さていかいたわけめ。鐘の事じや」といへば「金を持ちますれば、番太郎は致しませぬ」といふ。かの者呆れ果て「いやそのことではない。時は」と問うへば「斎は明日、お寺でございます」というた。(正直咄大鑑・貞享二・ときのかねのいひなし)(「江戸小咄辞典」 武藤禎夫編) 戻
酒飲むは、罪にて候か
酒飲むは、罪にて候か。答う。まことには飲むべくもなけれども、この世のならい。
<解釈>酒を飲むことは、罪になるのでしょうか。[法然の]答え。本当は飲むべきではありませんが、この世の習いとして仕方ないでしょう。 <出典>鎌倉、法然(諱(いみな)は源空 一一三三-一二一二)『和語灯録』百四十五箇条問答。<解説>経文の要義や日条の心得などについて問う信者に対し、法然が念仏者としての心構えやとるべき態度を答えた問答の一つ。「酒におぼれる者には六つの禍がある。」(『長部教典』)、「飲酒には十の過失がある」(『四分律』)等々、「不飲酒戒(ふおんじゅかい)」は釈迦以来の戒律であるにもかかわらず、法然は「世のならい」として飲酒を認めている。また、魚・鳥・鹿の肉食を問う信者にも、「ただおなじ」(前と同じ)と容認の答を返している。専修念仏を唱えた法然にとって、「衣食住の三は、念仏の助業(じょごう)なり。…何事もみな念仏の助業なり」、つまり念仏による往生浄土をひたすら信じているなら、必ずしも一定の生活様式を守る必要はなかったのである。飲酒は破戒行為には違いないが、「凡夫のならい、当時のまどいにひかれて、悪をつくる。力およばぬことにてこそ候え」(書状)として、根本である念仏を選び取りさえすれば、あとはすべて仏に任せて生活をすればよい。「世のならい」は誠に味わい深い言葉と言えよう。(埴岡真弓)(「食の名言辞典」 平野・田中・服部・森谷 編) 戻
初代川柳の酒句
ぶたばふ(ぶ)てなと(ど)ゝ ちろりをほうり出シ
盃に 元トハゑん(縁)ある せうぜう緋 (猩猩緋)
永の留守 女房酒屋ハ 直キばらい 眠狐
駕籠代(かごだい)は三文 酒手壱分やり 梅枝
たわいなく 寝るも生酔 ぶきび(不気味)也 五鳥
生酔ハ ぶち殺されたやうに 寝る 眠狐(「初代川柳選句集」 千葉治校訂) 戻
お銚子十本
草野さんは、私が草野さんが愛好している店を探して、そこで飲んでいるということを知っていた。私は、新潮社から「酒呑み」に関する書物を出版して貰ったのだけれど、そのなかにも『繁寿司』に関する文章があった。草野さんは、それを読んで、あまらなくなって飛んできたら、そこに私がいたということになる。草野さんが、その店に来たのは、実に、九年ぶりのことになる。私が草野さんに初めてお目にかかったのは、二十六年前、鎌倉アカデミアという学校に講演に来られた時だった。当時の私にとって、草野さんは仰ぎ見る大詩人だった。大詩人というのは粗雑な形容ではあるけれど、何かスケールの大きい包容力のある人だと思われた。草野さんを招いたのは吉野秀雄先生であるに違いない。私は『小説・吉野秀雄先生』という小説を書いた。それから後の草野さんは、会うたびに、きみはいいものを書いてくれたと言って涙を流すのが常だった。私は自分のためよりも、吉野先生のために嬉しかった。そういう経緯があるだけで、草野さんと二人で酒を飲む機会は無かった。草野さんはすぐ酔ってしまった。『繁寿司』のオヤジさんは「先生も弱くなったねえ、お銚子は十本ですよ。十本であれだから」と言った。まあ、ふつうなら、一升飲めば酔っぱらってもいい。(「禁酒 禁煙」 山口瞳) 戻
宮廷の花宴における饗宴の儀
桜花を観る「花宴之節」は、つぎの行事次第で進行した。まず、花見、遊覧、天皇出御後に漢詩賦詠があって、王卿以下に賜禄、退出となる。このように花宴の節は、饗宴をなかに挟んで前に文学行事、後に芸能行事が行われた。ここで注目すべきことは、花を愛で、その心を詩歌に詠い、管弦唱歌に託して興じた花宴は、享楽的で、非生産的な遊びの中に停滞していたように見える。しかし、実は、民俗的な春の山入り神事の中の遊興と饗宴の部分がとくに強調され、儀式化したことが理解できよう。(「日本の酒5000年」 加藤百一) 戻
拳相撲
具体的にいうなら、自分は五本出し、相手も五本出すだろうと思えば「トウライ(十)」といいながら打つ。その時、相手が三本出しながら「ハマ(八)」といえば、結果は合計八本だから、相手の勝ちになる。自分は一本も出さない、つまりぐうの形にするつもりで、相手は三本出すだろうと推定しながら二本出して「ウウ(五)」といえば、結果は合計二本だから、こちらの勝ちとなる。こんな方法で勝ち負けを決めても、結果は単純なジャンケンで決めるのと大差ないような気もするが、実際は、素人が名人と対戦したのでは勝ち目はなかったそうだ。未経験者が考えると、こんなゲームを練習すればうまくなるということさえ不思議な気がするが、文化六年(一八〇九)刊行の”拳会相撲図会”には、プロを目指す拳士が「拳を上達せんと思はば、毎日拳数を五、六百拳もつとめて、日数を六十日ばかりも打て」それから十日休んでまた六十日打つというように修行すれば「自然と上達」すると書いてある。ただ勝ったり負けたりするだけではなく、酒席では、負けた方が罰杯として一杯飲まされる。酒席に侍する芸者などは、拳が弱ければ大量の酒を飲まなくてはならないので、師匠について真剣に稽古した。(「大江戸番付事情」 石川英輔) 戻
美娘と秦重
進み来て秦重に相見る。此この言は秦重が耳へも一々入たれども、佯(いつわり)てきかぬふりをする。美娘は秦重へ礼をなし、側に坐して秦重をみて甚(はなはだ)疑ひ、心の内喜ばず、黙々として無言。○○(こめろ ママ)をよんで酒をとりよせ、大盃にてのむ。鴇児(くわしや 妓家の下男)云、客あり自らのむことよろしからず。九媽云、「爾(なんじ)酔たるあひだ、少しのむべし。」美娘は合点せず。「我酔はず」と十来盃(じつぱいばかり)も連(つゞ)けてのむ。これ酒後の酒、酔中の酔、自ら覚(オボユ)脚もたゝず。○○(しもをんな)を呼で寝屋へ燭をあげさせ、頭のかざりもとらず帯もとかず、其まゝにて臥し倒る。鴇児美娘が此体(このてい)をみて意に叶はざれども、秦重に対して云、「小女平日我まゝ(わがまま)にて、今日訳(わけ)はしらねども心の内何かまかせぬことありとみえたり。爾(なんじ)の事にはあらざれば腹立玉ふべからず。」秦重が道(い)ふ、「何がさて心づかひし玉ふな。」鴇児又秦重に数盃をすゝめ臥房に入て分付(いいふくめ)て云、「那(かの)人酔たり、あたゝかに休み玉へ。」(「通俗古今奇観」 淡斎主人訳 青木正児校注) 中国明末の小説を江戸・文化年間に翻訳したものだそうです。売れっ子女郎琴棋(美娘)に、大金を払って登楼した油売りの秦重が、楼主の九媽の手引きで会ったときの場面です。 戻
飲まぬ酒に酔う
【意味】わが身におぼえのない事の結果があらわれること。「飲まぬ酒には酔わぬ」の打ち返し。(「故事ことわざ辞典」 鈴木棠三・広田栄太郎編) 戻
日本酒の原点
この陸稲は、焼畑農耕を伴った後期照葉樹林文化が西日本に展開した際、粟、稗、麦、豆に混じって渡来した。このことは、長崎県島原市礫石原(くれいしばる)遺跡出土の晩期縄文土器片の籾殻圧痕がヤポニカ系陸稲であったこと、また、長崎県雲仙岳山腹の上原(うえのはら)遺跡、原山遺跡、大分県恵良野(えらの)遺跡、熊本市ワクド石遺跡から、炭化米や籾痕のある晩期縄文土器が出土したことから確認できる。さらに、福岡市板付遺跡、四箇東(しこひがし)遺跡、有田遺跡、唐津市宇木汲田(くんでん)遺跡などの晩期縄文遺跡からも炭化米や籾が出土し、金沢市近岡遺跡、高知県中村貝塚では晩期縄文土器の下層土から稲の花粉が検出され、なお広島県名越岩陰遺跡、千葉県根田貝塚、青森県剣吉(けんよし)遺跡などからは籾痕のある晩期縄文土器が発見された。これら出土例のすべてが陸稲でないにしても、西日本、とくに九州における陸稲の栽培はまず間違いない。とすれば、つぎの提言が許されよう。日本酒は、米を原料とした醸造酒であると定義するかぎり、これまでの考古学的知見から、日本酒の原点は、弥生時代の水稲ではなく、縄文晩期における陸稲または水稲を原料とした酒づくりである。(「日本の酒5000年」 加藤百一) 戻
焼きめしとウイスキー
赤瀬川 東海林さん、食べものはわりとオールマイティーでしょ。
東海林 うん、嫌いなものはない。
赤瀬川 本の中に、焼きめしでウイスキーを飲むとかって書いてたけど、いまでもやってるんですか。
東海林 やりますよ。(笑)
赤瀬川 あれって、うまいんですか。
東海林 あれはおつまみであり、かつ、ごはんなんだよね。だから焼きめしをつまみにして酒飲んでると、いっぺんに済んじゃうんだよ。(笑)
赤瀨川 うーん、完全食品。そうねえ、野菜とかも入ってるしね。(「うまいもの まずいもの」 赤瀬川原平 東海林さだお 奥本大三郎) 戻
造り酒屋
「ナント八助殿、貴様と申し合せて、地酒を造らうではないか」八介「いかさま、よからう。そして入用はどうしやう」「まづ貴様、米を出しなさい。わしは水を出しませう」八介「そして米の勘定はどううしてわりつけさつしやる「イヤ外にわりあいはいらぬ。酒が出来たら、貴様は米の糟(かす)をとらつしやい。わしは水をとりかせう」(笑顔はじめ・天明二)(「江戸小咄辞典」 武藤禎夫編) 戻
しとぎ
以上のように、東南アジアから中国、朝鮮、日本にかけて、しとぎが広く分布していて、日本でも神祭りにおいて重要な役割を占めていることがわかる。渡部忠世氏のいわれるアジアの稲作の起源がアッサム・雲南であるとする学説にしたがうと、おそらく、稲作は雲南から江南を通り、栽培化されて、海上を経て日本に来たことになる。このとき、江南地方から「しとぎ」「口噛み酒」の風習を持つ越人らが日本に渡来したものであろう。日本における神社での神饌としてのしとぎの調査結果から、縄文人の文化の痕跡が色濃く残るとされる東北地方や九州地方に生シトギが密に分布しているのは、しとぎからつくる口噛み酒がわが国の酒づくりの尖兵として入ってきたからだろうと考えられる。また、しとぎで餅麹をつくっている神社が数社あるのは、おそらく、二~三世紀頃、朝鮮からもたらされた餅麹を用いた酒づくりのなごりであろう。(「日本酒の起源」 上田誠之助) 戻
センダイムシクイとホオジロ
スズメより小さいセンダイムシクイという夏の渡り鳥がいる。黒と白のツートンカラーの粋な姿で、鳴き声は「チプチプジュウイ」とも「チョチョジイー」とも聞こえる。このチプチプジュウイが山家の酒好きの樵(きこり)には「焼酎一杯グイー」と聞こえるそうだ。-
陸上競技場と野球グラウンドの境の桜の梢(こずえ)からは、スポーツ好きのホオジロがさかんに若者たちに声援を送って「源平つつじ白つつじ」と鳴く。そして旧専門部の道路沿いにあるハクウンボクの枝のホオジロは、大学通りのスナックを横眼でチョロチョロ見ながら「一杯飲みますべぇか」と鳴くのである。(「酒の肴になる話」 矢口純) 戻
酒は少し飲んでたばこはやめる
養生法として、酒は少しは飲んでも、たばこはずっとやめてすわないようにする。沢庵和尚の小出吉英に贈る書に、<御手前(おてまえ)此の頃は御無病に候哉(そうろうや)。御持病も発(おこ)り申さず候由、旧冬より承り、珍重存じ候。御酒は少しずつ参り候とも、タバコは此の度永く止(や)められ、御断ち候わば、御長命の端たるべく存じ候>とある。(「飲食事辞典」 白石大二) 戻
清酒一升とスルメ一匹
昭和十九年三月末、わたしは召集令を受けた。前年秋に京都太秦の興亜映画が閉鎖、従業員の処分が行われて、わたしは松竹大船脚本部に引きとられた。溝口健二に師事して、興亜映画の脚本部ということになって月給をもらっていたので、大船脚本部に転籍できる幸運に恵まれたのであった。大船脚本部は新人シナリオライターとしては憧れのメッカだった。といっても、昭和十九年には戦争はいよいよ深刻になって、撮影所は開店休業というありさま、わたしなど新人には仕事はなかった。間もなく在籍わずか半年ばかりで戦争に行くことになった。前年夏に妻が死んだので、東京に戻って椎名町のアパートに住んでいた。近所に美術時代の師であった水谷浩美美術監督が住んでいたので、送別会をそこでやることになった。召集令がくると隣組から清酒一升とスルメ一匹が配給される。集まったものは大船脚本部員柳川真一、事務長の野坂さん水谷さん、友人の八木仁平さんとわたしの五人、スルメを囓って酒を酌み交わした。(「うわっ、八十歳」 新藤兼人) 戻
初鰹
蜀山人の「仮名世説」に「江戸にて初鰹をめずる事、北条五代記にみゆ、天文六年(1537)の夏、小田原浦近く、釣舟おほくうかびたるを、此(この)よし氏綱(うじつな)聞し召し、小舟に召され、海士のしわざを御見物、珍事の御遊、盃酒に興じ給ふ所に、鰹ひとつ御舟に飛び入りたり。氏綱喜悦に思しめし、勝負にかつをと御祝詞なのめならず、此時酒肴に用ひらる。(中略)諸侍(そざむらい)戦場の門出の酒肴には、鰹を専ら用ひ侍りぬとあり。」とある。北条氏の政策や方針を踏襲した徳川氏が、武士の都江戸において鰹をめでたい魚、縁起のよい魚とした点はうなずける。こうしたことが、鰹をますます賞味するようになっていって、それが江戸市民に普及していったのであろう。(「江戸風物詩」 川崎房五郎)
9対1
田沼時代料理茶屋の発展と共に酒の入津(にゅうしん)量も飛躍的に増加し、九十万樽から百万樽にのぼったため、明和初年には減少したといってもなお七十六軒の酒問屋があったが、天明七年(一七八七)の大飢饉に酒造高三分の一という制限令が出たため、次第にその影響をうけ、定信の寛政改革に当っては、酒造高の制限は厳しく励行する様つとめたため、寛政二年(一七九〇)には四十八軒に減少した。この影響で相ついで減少の道をたどり、文化十年十組問屋の株仲間成立にあたっては三十八軒に減じてしまった。しかし株仲間が杉本茂十郎の努力で成立して以来、これが独占的な組織となったため、この人員が下り酒問屋の定数となり、冥加金千五百両を納めて、幕末には地廻り酒十万樽に対し下り酒九十万樽と圧倒的に下り酒が多く、江戸における利益を独占した。この頃になると酒問屋は三十八軒中二十八軒が茅場町霊岸島新川辺に集中して、呉服町だの伊勢町だのと元禄頃中央市街近くに勢力をもっていた酒問屋の姿は一変し、ただの一軒もみられなくなってしまった。(「江戸風物詩」 川崎房五郎) 戻
星
星新一が日航ホテルの地下のバーに行くと、その店が「星」というので、酒をはこんで来た時のコースターにも、星と大きく記してあった。それを貰って来て、うちに客が来て飲む時、それを使うのだった。(「最後のちょっといい話」 戸板康二) 戻
下戸の知らねえ、うめえ味だなァ。
<解釈>下戸、つまり酒の飲めない人には、酔いざめの水のうまさはわからない。<出典>近代、竹柴其水(きすい)(一八四七-一九二三)作の歌舞伎「神明恵和合取組(かみのめぐみわごうのとりくみ)」<解説>「神明恵和合取組」は、明治二三年(一八九〇)三月、東京・新富座上演。文化二年(一八〇五)、江戸・芝神明社の境内で起こった角力(すもう)と鳶(とび)の者の喧嘩(けんか)を題材にした歌舞伎で、「め組の喧嘩」の通称で知られる。その主人公の鳶の頭・浜松町の辰五郎が言うせりふ。角力との命がけの喧嘩を決意した辰五郎は、いとまごいに行った親方の家で別れの酒をすすめられ、酔って帰宅する。女房お仲は、酔って帰ったのを見て、辰五郎が角力に仕返しをする気がなくなったものと、そのふがいなさをなじる。辰五郎は、生返事のまま、子どもに湯呑みに水を運ばせ、一口飲む。そして、女房にもすすめるが、女房は、私は酔っていないから飲みたくないと拒む。そこで辰五郎は、子どもにすすめると喜んで飲み、母親にもすすめるので、女房もしぶしぶ一口飲む。それを見て、辰五郎がつぶやくのがこのせりふである。そして、「浮き世の夢の酔醒めに、それといわねど三人が、呑むは別れの水盃」との下座の語りとなる。酔いざめの水と称して、本心をかくしながら、愛する妻子と別れの水盃を交わす、江戸っ子辰五郎の万感の思いがこめられた名せりふである。(中森博)
(「食の名言辞典」 平野・田中・服部・森谷 編) 戻
大叔父メッケル
デュッセルドルフのホテルにとまっていたときのことであった。メッケルという青年がたずねてきてくれた。かれは親日家で、同地の日本総領事館に机を一つもっていて、日独経済についての親善的なしごとをしていた。会うと、かがやくような好青年だった。「どうして日本がお好きなんですか」「大叔父の縁です」と、かれは、同姓の十九世紀のドイツ軍人の名をあげた。大叔父メッケル少佐が、明治初年の陸軍の教師だったことを知る人はすくなくない。ライン川のほとりの醸造家の家にうまれたメッケル(Klemens
Wilheim Jakob Meckel 一八四二~一九〇六)はドイツ参謀本部の逸材だった。明治初期の日本は、陸軍の軍制をフランス式からドイツ式にきりかえるべくドイツ政府にたのみ、人選もまかせた。参謀少佐メッケルがえらばれた。当初、かれは気がすすまなかったらしく、「私はモーゼル・ワインのない国には行きたくない」などといって、しぶっていたらしい。ところが、明治初年の日本では、すでにモーゼル・ワインは、横浜や築地で入手できた。日本からの使者がそういうと、少佐はことわる理由をうしなった。着任したのは、明治十八年(一八八五)で、同少佐の四十三歳のときであった。かれは日本の参謀本部顧問、陸軍大学校教師として満三年間、精力的に講義をし、助言をした。(「愛蘭土(アイルランド)紀行Ⅰ」 司馬遼太郎) 戻
伊豆酒
翌年三月帰洛までの駿府の(山科)言継(ときつぐ)の生活は今川家の家臣たち、新光明寺の住職との交際、今川義元との対面、和歌の会、酒宴の有様などが詳細に記されている。食物の面では海に近い暖国だけに、京都とはかなり違うし、尾張よりも種類が豊富である。名物の浜名納豆、醤、茶、蜜柑、生椎茸などがよく出て来るし、新鮮な魚介類も多く、いなだ(ぶりの幼魚)、かつお、さわら、あんこう、生樽鮑、海老など、加工食品では干しふぐ、かまぼこ。また産地名を冠した食物には「富士海苔」、「浜名納豆」、「伊豆酒」などがあるが、「伊豆酒」は後に「江川酒」として有名になった酒のことであろう。饅頭、羊「食甘」(羹)も籠入りを度々贈られている。油物とは天麩羅のことだろうか。また鳥類の汁もよく賞味したし、弘治三(一五五七)年正月九日には既に鉄砲を用いた狩猟の記録もある。(「日本の食と酒」 吉田元) 戻
町内の若衆
ある人、座敷を立直し、近所の人を新宅へ申入れてふるまひける。酒半ばに内方出て「何もござりませぬが、新宅の御馳走に、酒一つ参りませ」といはれければ、一座「さりとてはお物入りでござらうが、結構な御普請でござる」といふ。内方「うちの力ばかりではござらぬ。みな近所の衆のお蔭じゃ」といふ。与茂作帰りて話しけるは「それどのの内儀は、さりとてはくわをいはぬ理発な人じゃ。あの身代で誰に合力を得られうぞ」と賞めける。女房「それほどの事がいはれぬものか」といひけるが、十四、五日経て喜びをしたり。七夜の祝ひとて、近所の衆を呼びたり。「今日はめでたし。御内儀も喜びでござらう。安々と御平産。ことに男子でござる」などといひければ、女房まかり出て「亭主ばかりの力でできたではござらぬ。みな近所の若い衆のお蔭じゃ」(枝珊瑚珠・元禄三・人の情)(「江戸小咄辞典」 武藤禎夫編) 戻
三月十七日(金)〔花月劇場第七日〕
ブランデー一杯、薬用アルコールを少々、橙皮シロップ少々、これに湯を入れて飲む。ブランの鋭い臭味と、アルコールの薬品的臭味とが、互いに作用し、橙皮の甘さと香りとで塩梅されて、おろしき飲みものとなる。肴は、牛蒡、うどの天ぷら、それに宇和島の鯣(するめ)を焼く。口にふくんだだけで、これは上等品と分る味の濃やかさ。但し、いくらいたわって噛んでも、歯と歯の間にギュウギュウとするめの埋まるのは気色が悪い。ピチンピチンと奥歯で噛みきり、噛みこなした昔が思い出される。英子が来ていて、例の如く、この戦争がはやく済めばいいという。十年はダメだよ、と私は答える。(「夢声戦争日記(抄)」 徳川夢声)
昭和19年です。 戻
豆腐食い
長瀬(喜伴)とわたしの小屋は、なだらかな山の斜面に同じ方向に向いていたので、ベランダも北を向いて並んでいた。長瀬が、ベランダの端に立って「しんどうヤン、コーヒーがはいったぞ」と呼ぶ。彼は学生時代はラグビーをやったこともあって、堂々たる体躯をしていた。おまけに美食家で大食いで太鼓腹を突き出していた。蓼科をこよなく愛し、籠ってシナリオを書いていた。「しんどうヤン、こないか、豆腐食いに」と誘ってくれる。吉原の郭近くに育った彼は、自慢の豆腐料理を知っていた。鍋に豆腐を二丁入れ、日本酒でぐつぐつと煮て鰹節で味つけをする。これをつまんで食う。吉原堤の土堤で、朝帰りの客目あてに屋台で食べさしたという。屋台は料理屋の台所から出てくる残飯で工夫したということだ。(「うわっ、八十歳」 新藤兼人) 戻
伊豆酒
翌年三月帰洛までの駿府の言継(ときつぐ)の生活は今川家の家臣たち、新光明寺の住職との交際、今川義元との対面、和歌の会、酒宴の有様などが詳細に記されている。食物の面では海に近い暖国だけに、京都とはかなり違うし、尾張よりも種類が豊富である。名物の浜名納豆、醤、茶、蜜柑、生椎茸などがよく出て来るし、新鮮な魚介類も多く、いなだ(ぶりの幼魚)、かつお、さわら、あんこう、生樽鮑、海老など、加工食品では干しふぐ、かまぼこ。また産地名を冠した食物には「富士海苔」、「浜名納豆」、「伊豆酒」などがあるが、、「伊豆酒」は後に「江川酒」として有名になった酒のことであろう。饅頭、羊「食甘」(羹)も籠入りを度々贈られている。油物とは天麩羅のことだろうか。また鳥類の汁もよく賞味したし、弘治三(一五五七)年正月九日には既に鉄砲を用いた狩猟の記録もある。(「日本の食と酒」 吉田元) 戻
死人に口なし
希代の酒好きが死んだ。遺言により 棺のなかには故人がことに好んだ林檎酒を何本かいっしょに入れ、さて野辺の送りとなった。墓地ではいまし厳かな埋葬式。威儀を正した坊さんが、読経よろしくあって聖水を棺にそそぎ、いよいよ墓穴に棺をおろそうとするとき、棺のなかが暑かったせいか、理由のほどはつまびらかではないが、林檎酒が醗酵し、コルク栓がポンと飛んだ。坊さんびっくり仰天し、一歩うしろへ飛びさがったが、もうそれきり何事もないので、改めて棺の上に十字を切ろうとすると、ポン!と第二の音がした。坊さん真っ青になり、しりごみしつつ、よく見れば棺からチョロチョロ流れ出す。「たいへん!さっきは屁をひったが今度は小便じゃ。今に糞をする。早く死人を引きずり出せ!」(「ふらんす小咄大全」 河盛好蔵訳編) 戻
強清水
料理に工夫をこらしていることでは、さいごに訪れた東京方面への峠にある、ドライヴ・イン・強清水(こわしみず)が一番だった。この看板を見て気がついたのだが、そういえば昔の茶屋は現在ではドライヴ・インに当たるのだろうか。茶屋で出された力餅や団子やあるいは棒ダラ、田楽が、現在ではラーメン、カレーライスに変わったことだけのことだが、ドライヴ・イン・強清水ではさすが茶屋の伝統を残していて、ジンギスカン焼ののかにスルメの天プラ、饅頭の天プラ、身欠きニシンの天プラ、などの郷土料理を出している。これらはいずれも美味、というにふさわしく、ソバも会津御寮に劣らぬ出来である。強清水の由来は、茶屋の前の崖から清水が湧きだしていて、これを孝行息子が汲むと諸白(酒)になり、親不孝の子供が汲むと清水のままであるというが、ぼくが汲んだときは不当にも、清水のままであった。(「美味めぐり」 宇能鴻一郎) 会津若松市河東町八田字下ノ家だそうで、本来は、父が飲むと酒で、息子が飲むと水だったという伝承のようです。 戻
ビールのアワからノーベル賞
ニュートンは、リンゴが木から落ちるのをみたのがキッカケで「万有引力の法則」を発見したといわれますが、ビールを飲み、そのアワを見てノーベル賞をもらった人がいます。アメリカの物理学者グレイザーがその人。ビールのアワを凝視しているうちに、「うーむ。うまい。うまい」とビールを飲み続け、酔っ払い寝込んでしまうのはタダの人ですが、このグレイザーは、「このアワには一定の法則がある」と気がついたのです。ビールに砂粒を落とすと、その跡に沿ってアワができます。そして、グレイザーは、ビールを液体水素に置きかえ一定の状態をつくり、素粒子を通過させるとその進路に沿ってアワができることを発見。素粒子観察のアワ箱装置を発明し、ノーベル賞をもらったのです。(「雑学おもしろ百科」 小松左京・監修) 戻
固めの盃事
旧当番(大当番・相当番)と総代たち、新当番と総代たちが向いあわせで並ぶ。その中間の上座に神主、脇に荒神集落の代表(現代は、自治会長とする例が多い)。下座に酌人の若い衆が二人。座の中央に、三方(さんぽう)が二台。ひとつに、瓶子(へいし)一対。もうひとつに、白磁の平盃が三個。ここでは、御飯(ごくう)は出ない。「ただいまより、当番渡しの儀とりおこないます。一同、御礼(ごれい)」ここは、神主がすべてとり仕切る。まず、これまでの当番・当番組の面々を前に、式年祭が無事完了の謝礼とそれまでの任務への慰労の言葉を述べる。続いて、次の当番・相当番・当番組の面々を前に、向う七年のとどこおりなき担当を依頼する言葉を述べる。「今般の当番渡しは、旧慣にしたがい固めの盃事をもって成就といたします。立会人として自治会長の○○氏、酌人として受当組の○○氏と○○氏をお願いいたしました」「まず、本当の大当番さんから順に盃をおもちください。大役成就のお祝いとして、受当の大当番さんから御神酒(ごしんしゅ)をすすめていただきたい、と存じます。本来なら、近く進んでおすすめいただくのですが、酌人が控えておりますので酌人にお任せいただきたく存じます。よろしゅうございますか」酌人が大当番の前に進み、ひとりが盃を渡し、ひとりが酒を注ぐ。一盃に三度注ぐ。それを、大当番が三口で飲む。その盃を三方の上に返す。「本来なら、念には念をいれよとして三つの盃を用いて三三九度の固めといたします。いかがいたしましょうか」そのようにいたします、と答える人もいる。また、一盃で十分に御念がいりました、と答える人もいる。こうして、これまで当番組の面々に新しい当番組から敬意の酒を贈るのである。それがすむと、その立場が交代する。「それでは、受けの大当番さん、お覚悟の盃をおもちください。旧の大当番さん、これまでの荒神様のお守りからして引渡しに忍びがたいお気もちがあるでしょうが、ここは当番渡しの席でございます。快く御神酒をおすすめいただきたく存じます。酌人も控えておりますので、その役の代行をお任せいただけないでしょうか」酌人が三度酒を注ぐ。「この盃は、大当番引受けの誓いの盃となります。ご苦労もご覚悟のうえ三口で飲み干してください」「本来なら、念には念をいれよとして三つの盃を用いて三三九度の固めといたします。いかがいたしましょうか」一盃ですませるにせよ、三ツ盃を重ねるにせよ、飲み干したところで新大当番が挨拶を行う。「たしかに、大当番引受けました。どうぞ、よろしゅうお願いいたします」また、受けの当番組の面々に盃が巡る。そのつど、神主も簡単な仲介の口上をはさむ。そして、盃を受けるその当人も、たしかに相つとめます、と答えるのである。最後に、神主と立会人が一盃ずつ。これは、見届けの盃である。そして、酌人同士もそれにならう。「以上をもちまして、当番渡しの盃事、とどこおりなく納めおきました。おめでとうございます。当番組の皆様方も、どうか今後とも荒神様のご機嫌をそこないませぬよう、よろしくお世話くださいますよう、お頼み申します。ありがとうございました。一同、御礼」それからのち、当番幣(御幣)の受渡しや書類の引継ぎなどがあるが、盃事はこれで終了である。(「三三九度」 神崎宣武) 神主である著者の郷里、岡山県美星町にある荒神社での当番交代風景だそうです。 戻
歯のこと
スキーをして、アゴが一番疲れるという話は、私にとっても奇妙だったが、それをおかしがっている今日出海君にも、変わった経験があるのを、当人からじかに聞いた記憶がある。酔って帰宅したある晩、今君は美人に背中をかまれる夢を見た。それも一度や二度でなく、追っても突き放しても、しつこく寄ってきてかみつく。素晴らしい美人だから、はじめはうれしくないこともなかったが、一晩中逃げまわって、さて眼を覚ましてみると、どうしたものか敷布団に自分の義歯が落ちていて、その上に背中を当ててもがいていたことがわかった。と、いうのである。試みに、義歯の上に寝てみたら私はどんな夢を見ることであろうか。(「カレンダーの余白」 永井龍男) 戻
とっときの酒
(昭和)二十一年の三月ごろの日記を見ると、朝四時半に起きて「かぼちゃ」の穴を掘ったと書いてある。それに厨芥(ちゅうかい)を入れしもごえを入れて順々に埋めていったわけだが、そのころは朝四時半ごろから三時間ほど畑をやり、「おつゆ」みたいなものをのんで役所まで四十分ほどの道を歩いて出勤し、夕方からかえってきてまっくらになるまで畑をやった。役所にいかない日曜などは、朝は「おつゆ」、昼は菜っ葉みたいなものを食べて、暗くなるまではたらき、夜はとっときの酒を茶碗に一杯のんで、はじめて米の飯を食べて、天下を取ったような気で寝たものだった。(「侍従とパイプ」 入江相政) 戻
大槻磐渓と頼山陽
(大槻)磐渓(ばんけい)青年は、京都で頼山陽に会う。父玄沢(げんたく)の知己の蘭学者に紹介状をもらって訪ねるのだが、はじめはこの青年をすげなく扱っていた山陽が、青年の差し出す文稿を読んで気に入った。若年でこれだけの漢文が書ける者はいない。山陽は磐渓を書斎に招いて、酒を飲み、詩文を語った。明日は平野へ花見に行くからつきて来ぬか、という。翌日、山陽は、愛人や叔父ら数人に磐渓を加えて、日の暮れるまで花の下で酔い、語り、夜は茶屋に席を移し、庭に数十の灯をかかげて飲みつづけた。頼山陽は『日本外史』をようやく完成しようとしていた。ほぼ成稿と言える原稿を、前夜山陽の書斎で、磐渓青年も見せてもらっている。いずれ帰京の前にゆっくり読ませてもらう約束もしていたのだが、酔った勢いで磐渓青年が『日本外史』の批評をはじめた。修辞上の小さな問題には山陽もうまずいていたのだが、全編の構成にかかわることを難じだしたのには山陽が怒った。二十数年来の自信の作である。若僧がなにを言うか。「山陽大声一喝シテ曰ク、是レ腐儒ノ論ノミ。余[磐渓」、瞠然(ドウゼン)トシテ言ナクシテ罷(ヤ)ム。」怒鳴られてびっくりした青年の顔が見えるが、のちに頼山陽は磐渓の評を採って、『日本外史』の構成上の改訂を行った。磐渓は文彦ら子供によくこの話をした。「わしが一時の妄言(ぼうげん)に暗に山陽を助けないでもなかった。」(「言葉の海へ」 高田宏) 磐渓は、「言海」を著した大槻文彦の父だそうです。 戻
のけて通せ酒の酔い
【意味】酔っ払いには、かまわぬのが安全である。【参考】よけて通せ酒の酔い ○堅石(かたいわ)も酔人を避くる〔古事記〕(「故事ことわざ辞典」 鈴木棠三・広田栄太郎編) 戻
お流れちょうだいとお酌
中世的宴会の前段では儀礼的な酒の飲みまわしの形式をとる。上座から下座まで、しばしば同じ杯がまわされるのである。その形式は茶の湯にひきつがれたし、現代の「お流れちょうだい」という杯のやりとりにも残っている。自分勝手に酒をついで飲むことは許されず、自分の順番がきてまわってきた杯に酒がつがれるのを待って、はじめて飲むことができたのである。そこで、後世になっても酒の席には、酒のつぎ役である「お酌」がいることが必要となったのである。(「食事の文明論」 石毛直道) 戻
メリー女王
メリー女王は十六世紀の歴史を騒がせた女性ですが、女だてらに大酒飲みで、その飲みっぷりには誰もが惚れ惚れし、特にファンが多かったといいます。女王は、美貌な上に多才で、音楽、詩作に長けており、数ヵ国の言葉を自由にあやつったと申します。それだけでも魅力いっぱいなのに、お酒を飲んでほんのりと頬を染め、適度に怪しげなろれつで男性に迫るのですから、誰もが悩殺されてしまいました。女王は近づいてくる男たちを煽動して、女王エリザベス暗殺の陰謀に加担した科(とが)で捕えられフォザリンゲー城に拘禁されます。そして一五八七年二月のある日、十六年の幽囚生活のあと処刑されました。十六年に及ぶ獄中生活の唯一の楽しみは酒でありました。ワイン、ビール何でもいいから酒を-と求めるメリー女王を預かっているシュリュスベリ伯爵は困り果てて、エリザベス女王あてに手紙を出しています。「スコットランド女王の勘定として、拙者が負担せねばならぬ本年度の経費は莫大に達しました。実際を申しあげますと、一ヵ月二桶の葡萄酒では女王の普通の飲用にも不十分なのです。どうぞ、お助けください」と書き送りました。女王はビールも好きで、バートン・オン・トレント産の鳶(とび)色のビールをノドをならして飲んだそうです。私もイギリスに行ったとき、メリー女王のビールを探したのですが、残念ながらめぐり会えませでした。ともあれ、女酒童メリー女王は、酒と共に生き、酒と共に死んでゆきました。死刑執行の朝、これまで、世話を焼いてくれた者たちすべてを召し寄せ”ありがとう”の杯をあげてギロチンの台に上ったといいますから、なんともみごとな最後というべきでしょう。(「今宵も美酒を」 佐々木久子) 戻
大飯食いまつり
この嫁入り祭りの翌日、三月二日から大飯食いまつりが行われる。われこそは大飯食いだと自負する二十二人の選手が、二手にわかれて大食漢ぶりを競う。料理は精進料理で、御飯は大きな椀に山のように盛りつけられざっと八合はある。それくらいなら出場してみようかなんて御人もあろうが、これを三杯食べなければならないのだから、腹がパンクしないうちにやめた方がよさそうである。もっとも精進料理は消化が良いが、それも程度問題で人間にとって楽しかるべき食事が、この時ばかりは苦痛になるのである。第一回目は、二杯は必ず腹におさめなければならない。ダウンした場合は、罰として二杯の酒(約六合)をたて続けに飲まなければならない。吐き出しそうになるのを必死にこらえて、無理に腹につめ込む連中も、ダウンした連中も大変なことである。それを見てワイワイはやしたてる観衆も、野次馬もいいとこである。一回目の神事が終わると、しばらく休憩して第二回目に入る。二回目は残りの一杯を食べるのである。休憩中の選手は、腹をこすったり、消化剤を流し込んだりと、腹すかしの妙技を演ずる。一杯八合として、三杯で二升五合もの御飯を半日がかりで食べるのだから、食いだめなんて代物ではない。(「日本の奇祭」 湯沢司一・左近士照子共編) 島根県隠地郡岩見の岩根神社で行われる祭りだそうです。 戻
ニッカウヰスキー
ニッカはウイスキーをウヰスキーとして発売している。なぜだろうと思って尋ねたら、この酒のきめてはは一にも二にも水で、それも井戸の水がいい。だから、ヰと書きますという返事であった。(「最後のちょっといい話」 戸板康二) 戻
乞食
前市長、ジミー・ウォーカーは、セントラル・パーク・カジノを出たところで、一人のやつれ果てて見るかげもない男に声をかけられた。「ミスター・ジミー」彼は懇願した。「何か食べ物を買いたいから二十五セント玉一つもらえんでしょうか?」「コロナがあったけな」チョッキのポケットをさぐりながら市長がいった。「煙草はやらないんで」このルンペンは断言した。「ただ、食べ物を買う二十五セントが欲しいんで」「わしといっしょに中へおはいり」市長はうながした。「ウィスキーを二杯ばかりおごろうじゃないか。そうすりゃ元気が出るだろう!」「あっしは飲まないんでがすよ」というのが答だった。「あっしの欲しいのは食べものだけなんでさあ」「じゃあこうしよう」ウォーカーはいい張った。「わしは明日、バーモントへ行く。ちころでわしは、たまたま有力な勝ち馬を知ってるんだ。だから、お前のためにそれに二ドル賭けることにしよう」「ノォ!ノォ!」乞食は叫んだ。「あっしは賭けごとなんざ考えてもいませんや。おねがいですから、つまらんことをいうのは止めにして、あっしにほんの二十五セントくざせえよ!」「よろしい」市長は不承不承に同意した。「だが、まず第一に、わしといっしょに来て家内に会ってもらわにゃならん。煙草もすわず、酒も飲まず、賭けごともやらんような男がどういうことになるか、わしは彼女に見せてやりたいんだ」(「ポケット笑談事典」 ベネット・サーフ) 戻
タダ酒
春三月、大学の卒業式には学長告辞がある。東大総長の場合など、とくに、新聞にのって一世の警句となったりする。そのいくつかをひろってみると、「ミルトンよ、汝いま生きてあれかし、日本は汝を要す。彼女(日本)はいま汚水の沼なり」(昭29・東大・矢内原)、「他人からタダ酒をご馳走になるな。いま、政界や官界の汚職は、すべてタダ酒を飲む習慣から起こっている。酒を飲みたかったら自分のゼニで飲め」(同・京大・滝川)、「諸君を真理のための戦士として世に送り出す」(昭32・矢内原)、「ただ教養をアタマの中にたくわえておくのではなく、だれでもができる”小さな親切”を、勇気をもってせよ」(昭38・東大・茅)、「東大の卒業生にとってなにより必要なことは出世コースのすわり心地のよさに負けないことである。ふとったブタになるよりはやせたソクラテスになれ」(昭39・東大・大河内)など。この「やせたソクラテス」は流行語になった。大河内総長はほんとうはこのようなことばは言わなかったという。総長はその後、同年四月十五日付の朝日新聞にこう書いた。「私も驚いたが、それ以上に私の告辞を実際に聞いた卒業生たちが驚いたろう」。夕刊に間に合うように、予定原稿で各社の記者に渡されたものが新聞にのったのであった。(「ことばの情報歳時記」 稲垣吉彦) 戻
宴会
りっぱな宴会での席上、ヒブス夫人が給仕頭を呼びつけてたずねた。「カクテルを回していた、あのきれいなウェイトレスはどうしたの?」「申し訳ありません、奥様」給仕頭はあやまった。「飲物をさがしていらしたんですか?」「いいえ」ヒブス夫人は答えた。「私は主人をさがしていたのよ」(「ポケット笑談事典」 ベネット・サーフ) 戻
紅葉にはたがをしへける酒の間
「たが」=「誰が」、「をしへける」=「教えける」。「間」は「燗」と現代風にしないと、一般の理解に余る。いやこれでも一読すべて了解とはいかないか。白楽天の漢詩と『平家物語』が踏まえられているまことに贅沢な句である。まずは白楽天。「林間に酒を煖めて紅葉を焼(た)き/石上に詩を題して緑苔(りょくたい)を掃う」がそれで、つぎは『平家物語』巻六の一節。野分の吹いたあくる朝、高倉院が愛でている紅葉の落葉を、衛士が集めて残らず捨ててしまった。蔵人(雑事係の役人)はびっくり仰天してオロオロするばかり。そこへ高倉院が出御してくる。切羽詰まって蔵人はありのままに奏聞するよりなかった。以下は原文で。「(院は)天気ことに御心よげにうち笑ませ給ひて、『「林間に酒を煖メテ紅葉ヲ焼ク」といふ詩の心をば、それら[衛士」に誰が教へけるぞや。やさしうも仕りけるものかな』とてかへつて御感に預かりし上は、あへて勅勘なかりけり」左様か、紅葉で酒を温めたのか。それにしても「たがをしへける」風流ならんや、とお怒りはなかったという話。高倉天皇の立派なことよ。(「其角俳句と江戸の春」 半藤一利) 戻
西洋の湯たんぽ
たとえば、[2]~[4]をご覧いただきたい。[2]は現代のイギリス製湯たんぽ、[4]はフランス製の湯たんぽである。そして、これら一群の縦長・円筒形の湯たんぽの姿に目を凝らしていると、やがて彷彿として脳裏に浮かび上がってくる道具がある。そう、[3]の「陶製酒瓶(bottle)」なのである。[2]は、スコットランドの産業都市グラスゴーで製造された湯たんぽだが、これを見ていると、一八~一九世紀、北海道より北にある寒い国=イギリスの人々は、台所の片隅や酒場の裏にゴロゴロしていた陶製のビールやジンの空き瓶をブリコラージュして湯たんぽを生み出したのではないかと思えてくる。なにしろ、湯たんぽの英名は[hotwater-bottle]。湯(hotwater)を満たした酒瓶(bottle)が[湯たんぽ]なのである。(「おまるから始まる道具学」 村瀬春樹) 戻
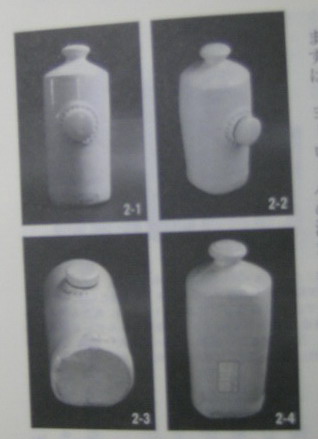

2 4
日本の湯たんぽ
ところで、[10]の写真を見て何か気がつかないだろうか?そう、この湯たんぽには「底」が二つあるのだ。あの英国グラスゴーの湯たんぽのように。一つは「豚」のお腹にあたる四本足を生やした面、もう一つは注ぎ口がある側の円い断面。こちらには「ざらつき」を残したリング状の高台(陶磁器の底の台輪)まで付いている。一個の湯たんぽに二つの「底」-これはいったい何を意味するのか?この品を垂直に立ててみるともっとよくわかるだろう。[11]をご覧いただきたい。そうなのだ。草創期の陶製湯たんぽを観察していると、その誕生の背景に例の「器用仕事(プリコラージュ 手近なものを何でもあれこれ利用し、再生すること)」が発揮されたのではないかと思われる痕跡が見えてくるのだ。この湯たんぽが商品化されて発売される以前に、湯を入れて身体を暖める暖房具として、ある種の道具が
「転用」されていたのではないか?そして、それがヒントとなって国産の陶製湯たんぽが開発されたのではないか?そう思えてくるのだ。そのある種の道具とは、[12]の「通い徳利」である。酒が量り売りだった時代、酒屋が客に貸し出した容器-別名「貧乏徳利」と呼ばれる酒瓶だ。(「おまるから始まる道具学」 村瀬春樹) 戻


上11 下12 10
ことわざ(2)
酒屋の門に三年立てども呑まぬ酒に酔うたためしなし(酒を飲まなければ決して酔うことはない)
酒屋の歳暮で粕ばかり(粕と貸すにかけた地口)
酒の上から剣の舞(酒で乱酔の上刃物三昧となる)
酒は井戸掘(ほり)ほど飲む(酒呑は井戸水をくみ出すようにがぶがぶと飲む)
酒は酒屋にあり布子(ぬのこ)は質屋にあり(飲みたい酒は酒屋へ行けばいくらでもあるが、かんじんの銭はなく着物はとっくに質屋に入質してどうにもならない)
酒飲みは遅れて来る(遅れて来て、かけつけ三杯とかいって余計飲む)
盃と真言(しんごん)繰(く)る程よい(この場合の真言は念仏で、念仏講中で大数珠繰りをして百万遍念仏を唱えることをいい、盃も大いに廻すことの方がよい)
(「日本酒のフォークロア」 川口謙二) 戻
アブサン禁止
第一次世界大戦(一九一四-一八)が始まると、フランス政府はアブサンは国民の精気を奪うものとして、一九一五年三月一日に飲用を禁止した。アブサンが不妊症をもたらし、人口の減少につながると考えたためである。そうしたことから、フランスでは一時飲酒する者が減少していたワインが勢いを盛り返したとされる。スイスでも、国民投票の結果、アブサンの製造が禁止され、イタリアもそれにならった。現在、アブサンの風味を引き継ぐ酒「パスティス」がつくられており、フランスの国民的アルコール飲料として飲まれている。「パスティス」は、アブサンに「似せてつくる(ス・パスティゼ、se
pastiser)」の意味である。たとえばペルノー社は、禁止された生のニガヨモギを使わずに、ニガヨモギの葉とつぼみを陰干ししたものを使い、四五度と六八度の二種類の「ペルノー」をアブサンの類似品として製造、販売している。「ペルノー」は、水を加えると白濁せず、緑色を帯びた黄色に変わるという特色がある。(「知っておきたい「酒」の世界史」 宮崎正勝) 戻
ヤマブドウの酒
一九五三(昭和二八)年八月、この井戸尻遺跡群の一つ、高森新道(あらみち)第一号住居跡から奇妙な形をした土器が出土した。この土器は高さ三三センチメートル、口縁が平たく、首の部分に輪をはめたような鍔(つば)があり、鍔には一〇個あまりもの穴があいている。これが考古学者のいう有孔鍔付(つばつき)土器である。この土器と同型土器の内側にヤマブドウの種子を見つけた発掘者の一人、武藤は、ヤマブドウなど液果類を仕込んだ容器と推定した。その傍証資料であるかのように、同一住居から飲酒器らしいカップ状土器や、神への供献具と思われる小椀形土器が、また井戸尻四号竪穴住居跡からもカップ状土器が出土した。こうした発掘品を収納・展示しているのが駅から南へ一キロメートルの井戸尻考古館である。同館展示の縄文土器は完品だけで二〇〇点以上、中でも有孔鍔付土器はどれも大型で、五〇~六〇リットル容もあろうか、ヤマブドウの七〇~八〇キログラムは仕込めそうである。(「日本酒5000年」 加藤百一) 三内丸山遺跡 戻
【ゆだねる[委ねる】
ところが、運転するようになってから、むしろ酒がぴったりと身についてくれるようになった。飲み方が計画的になったせいかもしれない。飲むためには、家をでるときからそのつもりで、車を置いてでなければならないから、仕事や健康の都合で、自制したいと思っていながら、ついずるずると深酒してしまったなどということは、まずありえない。すくなくとものんでいるあいだは、心おきなく、酒に身をゆだねていられるというわけだ。おかげでますます、酒が好きになり、こういう飲み方にはどうやら日本酒が一番むいているらしく最近はもっぱら日本酒ばかりたしなんでいるような次第である。(安部公房・雑誌「酒」)-
解説とウンチク 本来。車の運転と飲酒は相性が悪い。もちろん、酒を飲んでの運転は法律を犯すことになる。しかし、異才・安部公房は、「運転するようになってから」むしろ酒がうまくなったというのである。理由は、冒頭引用文の通りである。人はある制限がつくと、かえってその楽しみ喜びが強調されることがある。終電を気にしつつのむ酒、会ってはならぬ人と会う逢瀬、ダイエット中のケーキ、などなど。しかし、その禁忌や制限がとりはらわれたときこそ、心おきなく、自分の好きなものに身をゆだねられるというわけだ。それにしても人生、心おきなく身をゆだねられることの機会や対象物の、なんと少ないことか。また、それだけに、身をゆだめることの快楽や陶酔は貴重なものとなる。(「『酒のよろこび』ことば辞典」 TaKaRa酒生活文化研究所:編) 戻
酒楼へ
大名が金を借りる時には必ず大阪の豪商に借りた。その談判は必ず藩の留守居役がやったのである。これはどの藩でも同様であった。各藩の収入では普通の参勤交代等の費用を弁じ得るだけで、その他の臨時費となると、とてもその収入では出来なかった。それに太平が続いて、段々世が贅沢になり、物価が騰貴するに従って、いよいよ豪商に頼る必要頻々と起って来た。借りて、元利を幾分かずつ支払って行く大名には、豪商も直ちに需に応じたが、返し得ない貧乏藩が沢山あるので、そういうのに対しては、たやすくは応じなかった。藩の足もとを見ては豪商は少しでも利を高く取ろうとした。大阪の留守居はこの談判をうまくせねばならぬ。談判の際大抵豪商とは直接にしないで、番頭を相手に交渉するのであるから、その事なき平素から留守居は時々番頭に贈物をしたり、また酒楼へ連れて行ったりして、機嫌を取るのに汲々としていた。因(よつ)て金貸の豪商に対しては、武士の威厳も何も無く、番頭風情に対しても、頭を下げて、腫物にさわるようにしていたのである。かかる次第であるから大阪の豪商は暗に天下の諸大名を眼下に見下していた。貸してくれた際には、別に扶持米を与えあるいはそれを増すこともあった。(「鳴雪自叙伝」 内藤鳴雪) 戻
夜明けあと
慶応四年 パリ万国博に出演した日本の手品師たち、ブダペストでも興行したが、強い酒を日本酒の調子で飲み、酔って大失敗(万国)。
明治七年 天皇、二十三歳。新しい侍女と深い仲になり、皇后ご立腹。岩倉具視、その和解のために苦心。なんとかおさまり、酒宴となる。その帰途、岩倉は食違坂で暴徒に襲われ、あやうく命を失うところだった。
明治七年 浅草・伊勢屋弥兵衛、浜町の美人芸者と結婚。新郎新婦とも洋装、馬車へ乗る。ワインをグラスについで、三三九度(東日)。
明治八年 講談の神田伯山、帰宅の途中、若い男が追ってくる。あなたの財布をすったやつを見て、つかまえて、とり戻したと。ご親切にと、酒と食事をおごる。あとで財布のなかを調べると、十銭札が一枚(曙)。
明治九年 浅草雷門の車引き。男に声をかけると「タダなら乗ってやる」と。面白半分、深川まで乗せる。男は、気に入ったと、酒食をおごり、泊まってゆけと。翌朝になり、車代として二円を渡した(郵便報知)。(「夜明けあと」 星新一) 戻
大粒の雄町
雄町の品種の特徴をまず申し上げておくと、酒造好適米の第一条件である大粒であること、歴史上これほど大きな米はなかったろう、といわれるほど大粒であった。あった、と過去形で書いたのは、現在の『雄町』はもう精力が衰えて、昔のような大粒に実らないこと、機械農業化して昔のように田に力がないこと、堆肥を使わず化学肥料を使用している弊害がでておりこと、などが原因して、小粒化してしまったらしい。それでも私の目からは、今の雄町がかなり大きく見えるのであるから、最盛期の雄町はどれほどの大きさであったか、関係者の話を聞いても、昔の雄町はこんなものでなかった、と異口同音に答えてくれるのである。色々専門的に教えて下さったが、受け入れる側の知識が乏しく、「ほんとうに大きかったんだな」という感触だけは理解できたにとどまった。現在の好適米『雄町』の作付の水田の大半は、命名の由来の岡山県雄町にはない。雄町では一度は作付がゼロになってしまったらしく、滅びゆく幻の米を惜しんで、なんとか復活できないものかと、地元の農家の有志が『雄町振興会』を結成して努力しているが、会員二十数名がすべて高齢者であったり、その他にも難問が多く、はかばかしく進展してはいないようだ。(「異見 文化酒類学」 桜木廂夫) 戻
北島雪山
元禄のころ、名高い書家北島雪山は、わざわざ雨天を選んで花見に出かけ、傘をさして降る雨の中を立ったまま、門人たちと酒を汲みかわし、酔いがまわってくると、「桜の花から落ちるあの清らかな水を浴びてみたい」と言って、花の下に裸になって立ったという。
(「日本史こぼれ話」 奈良本辰也ほか) 戻
向嶋の花見
明治三十一年の頃には向島の地は猶全く幽雅の趣を失わず、依然として都人観花の勝地となされていた。それより三年の後明治三十四年 平出鏗二郎(こうじろう)氏が東京風俗誌三巻を著した時にも著者は向島桜花の状を叙して下の如く言っている。「桜は向嶋最も盛なり。中略三囲(みめぐり)の鳥居前より 牛ノ御前 長命寺の辺までいと盛りに 白鬚(しらひげ) 梅若の辺まで咲きに咲きたり。側は縹渺たる隅田川の川音青うして 白帆に風を孕み 波に眠れる都鳥の艪楫(ろしゅう)に夢を破られて 飛び立つ羽音も物たるげなり。待乳山(まつちやま)の森 浅草寺の塔の影 いづれか春の景色ならざる。実に帝都第一の眺めなり。懸茶屋(かけぢゃや)には衣被(きぬかつぎ)の芋 慈姑(くわい)の串団子を陳(つら)ね 栄螺(さゞえ)の壺焼なども鬻(ひさ)ぐ。百眼(ひゃくまなこ)売 つけ髭売 蝶々売 花簪(はなかんざし)売 風船売など 或は屋台を据ゑ 或は立ちながらに売る。花見の客の雑沓狼藉は筆にも記しがたし。明治三十三年四月十五日の日曜日に向嶋にて警察官の厄介となりし者 酩酊者二百五人 喧嘩(けんか)九十六件、内負傷者六人、違警罪一人、迷児(まいご)十四人と聞く。雑沓狼藉の状(さま)察すべし。」云々(「日和下駄」 永井荷風) 戻
花見の薬
「上野の花もはやすぎ、亀井戸のしば、つくつくし、よめな、つばなの一ふさ面白けれど、今年の桜見ずにくらけり」などといふ。「しからば、牛嶋の禅寺に珍しき花あり。これへ参らん」とて急ぎけり。ほどなく門になれば、番の者立出で「その吸筒は酒そうな。酒はこの内へは入れぬ」といふ。「しからば飲みて見ん」といふ。やがて大茶わんに一つあたへければ「この薬には大分地黄が入たさうな」といふて通しけり。さあさあしすましたぞと、思ふよふに見物して、大酒にゑい、はや帰らんと思ふ所に、又番の者来りていふやう「さきほどの薬の二ばんは、まだあがりませぬか」といふてきた。(かの子ばなし巻一・元禄三・花見の薬)(「江戸小咄辞典」 武藤禎夫編) 戻
花折(はなおり)
▲住持 これは、当庵の住持でござる。新発意(しんぼち 小僧)あるか。 ▲しんぼち お前に。 ▲住持 やい、けふはさる方へ行くほどに、留守をせい。又、花を見物にござらうとも、禁制ぢやと云うて見せな。やがて戻らう。 ▲しんぼち はあ。 ▲花見の者 これはこのあたりの者でござる。昨日は、東山の花を見物致したほどに、今日は、西山に参らうと存ずる。さあさあござれ。 ▲つれ さやうでござる。 ▲花見 いや、これでござる。いざ、弁当をひらきませう。 小うたをうたふ。 ▲しんぼち いや、なうなう、そこで花を見たより、これでは何とござらう。 ▲花見 さてさて、それはかたじけなうござる。 ▲しんぼち さあさあござれ。 ▲花見 心得ました。はあ、見事なことでござる、 ▲つれ さやうでござる。 又うたひうたふ。 ▲花見 御坊も御酒まゐらぬか。 ▲しんぼち なるほどようござらう。なうなう、一つ受持つたほどに、肴が望でござる。 ▲つれ 心得ました。 小舞あり。 ▲しんぼち 戻しませう。 ▲花見 いたゞきませう。御新発意(ごしんぼち)ひとつうけてござる。何ぞまはせられい。 ▲しんぼち 心得ました。 しんぼちまひ、 ▲花見 えいや。 ▲しんぼち 殊の外酔ひました。 ▲花見 もはやおいとま申します。 ▲しんぼち それならば、花を進上いたしませう。 ▲花見 かたじけなうござる。 しんぼち、酒に酔ひてねてゐる。 ▲住持 只今帰りてござる。これはいかなこと。みどもが大事の花を折りをつた。これはいかな事。やい、そこなやつそこなやつ。 ▲しんぼち まだ、花がほしいか。これこれ。 ▲住持 あの、横着者め。やるまいぞやるまいぞ。 ▲しんぼち ゆるさつしやれゆるさつしやれ。(「狂言記」)全文です。 戻
サイダサクラ
財政学の和田謙三、歌人の大町桂月たちがうちそろって東京の荒川堤へ花見に出かけた。「茶店の酒はだめだよ、まずくって飲めたものじゃない」「サイダーはどうです」「サイダサクラになぜ駒つなぐ」とやったのが和田垣。それでも酒なしではすまないので茶店からまずい酒とサザエを取った。勘定が高い。「サザエは一個いくらかね、いったい」「二十五銭です」「ササイ(些細)じゃないね」これも和田垣。大正なかばのことだ。(「日本史こぼれ話」 奈良本辰也ほか) 戻
酔せた先を呵(しか)る女房
酔いすぎた亭主をしからずに、酒をのませた先方の家を恨む。女の身びいきである。
生酔は畳たやうにかしこまり
自分ではしっかりしているつもりで座るのだが、物をたたんだようにがくんと体が折れ、ぐにゃりとそてしまう。そして<生酔ハおとかすやうなおくびをし>(『柳多留』)たりするのだ。この前句は「きたなかりけりきたなかりけり」で生酔いは嫌われるはずだ。
つまる所居酒屋か為の桜咲
花見には酒がなくてはかなわぬ。
(「『武玉川』を楽しむ」 神田忙人) 戻
小金井桜
そのころ、江戸では花見が最大の年中行事だった。将軍から町人まで、みんなこぞってサクラに浮かれた時代だ。名所も上野、向島、御殿山、飛鳥山…と、実に多かった。だから、ふうさいのあがらない奥多摩の馬子が「小金井桜がいいのなんのってまあ、いちど云ってごらんなせえ」-いくら吹いても、二つ返事で乗ってくる人は少なかった。が、何年も経つと「ひとつ来年は趣向を変えて」「小金井にでも行くか」という”奇特”な衆がぼつぼつ現れてきた。さてその春-小金井桜のつぼみがほんのりとふくらみ、やがて一分咲き、二分咲き、三分咲き。いつしかちょうど見ごろになると、江戸から遠出の花見客がやってきた。彼らは上水の土手に立って、ざっと二千本というサクラ並木にまずどぎもを抜かれた。「うーん、こりゃお見事」馬子の言葉にウソはない、と思った。人影もまばらで、あっちに一組、こっちに一組、と近在の百姓がゴザの上で調子よく浮かれているだけだった。江戸の衆は、この新名所がすっかり気に入った。ここじゃいくら騒いだって、おとがめはあるまい。江戸一番といわれる上野の山は、寛永寺に宮様や幕府のオエラ方がくるので、鳴物入りはご法度。上野ばかりではなく、町人はどこでも、武士に気がねしながら、ちいちゃくなって花見酒を飲んでいた。「いやぁ、ここはおもしろうがす!」やってきた連中は、扇子でポンとおでこをたたいた。小金井はドンチャン騒ぎができる-ウアサがぱっと江戸中に広がった。それから毎年、押すな押すなの盛況だ。代官所は、あわてて「一つ、上水に棒きれや汚物を投込むべからず。二つ、物を洗うべからず、三つ、サクラを折るべからず。四つ、ケンカすべからず」という高札を掲げたが、それでもこわい目つきの見回り役人がいる江戸のサクラ名所より、ずっと”町人天国”であった。のち、小金井桜は、江戸で有数のサクラの名所にのし上がった。記録によると、小金井桜は「立春より五十四、五日に開花し、六十日目が満開、七十日目に落花」した。(「武蔵野むかしむかし」 朝日新聞社編) 宝暦(一七五一-六三)の半ば頃のことだそうです。 戻