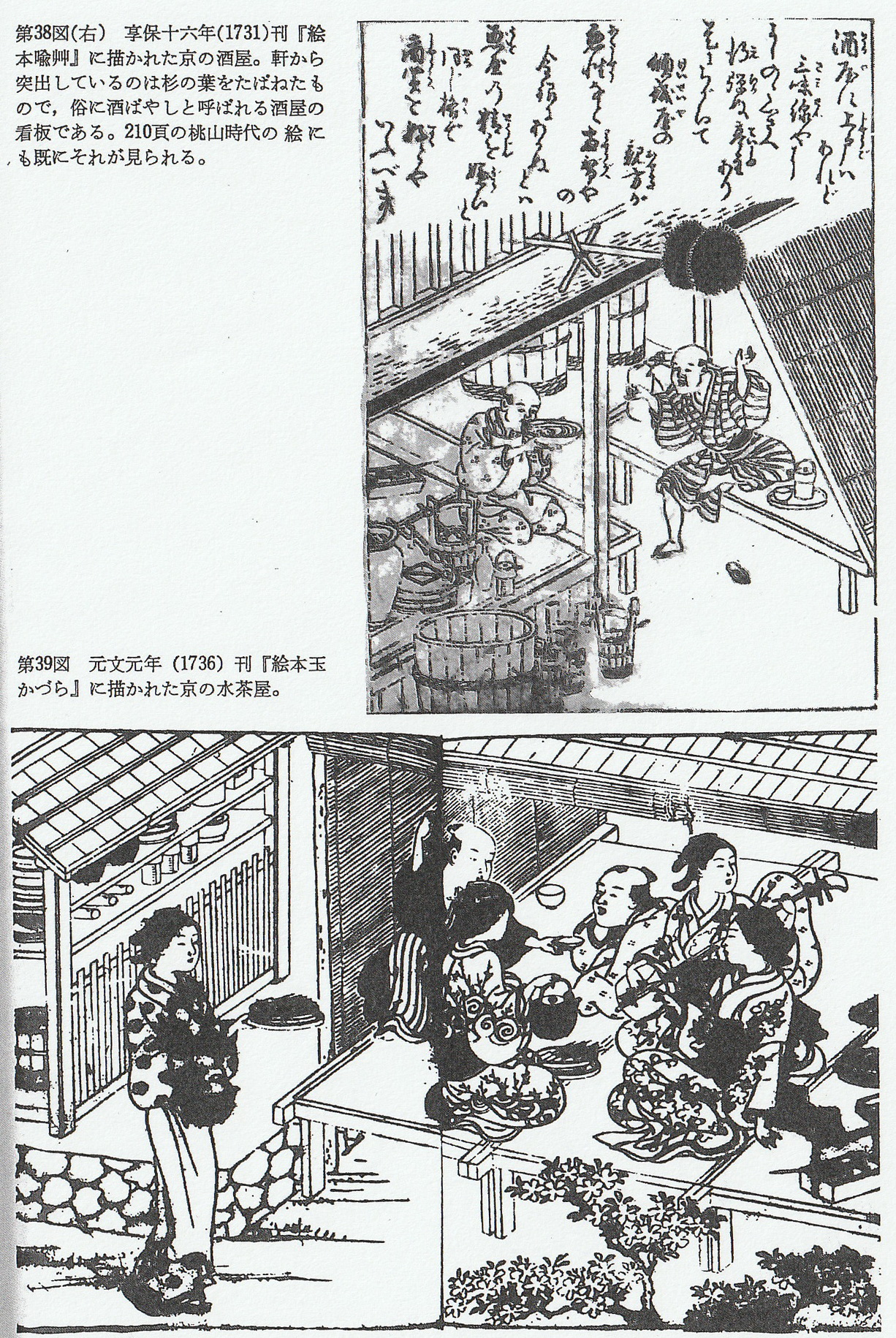
酒の飲みくらべ 一茶の酒句 はなゆ【花柚】 彦助・明日葉・まるい 漱石の酒句(5) 好気型こうじ菌 ちろり酒 花柳かづらに折りし梅の花 御題「祭」 阿佐ヶ谷界隈 のんべ(飲兵衛) じゃこご飯 下戸の屁理屈 ずっと馬鹿でいなよ 課長 人参党 あい子さん 魔術用の酒 〇生姜酒十一 童蒙酒造記解題 酒造るに吉日・凶日の事 せんべろ作法 第七 飲酒を慎む にようぼう[女房] 470方法は簡単 和平どん ざんぐり ベロベロの神様 和らぎ水 当世こうた揃 しめサバ 酒漬けに水も尽く 古今夷曲集 ご下賜の盃 えうてうとたをやかにして茶椀酒 両国「ほそ川」 お酒飲んで芸者上げると ベトンベトン 酒の専売制度 きゅうりもみの粕和え ある人の断酒満願の日に 七、酒の肴としての肉料理 樽酒 あぶないチャンポン 食味文化人 あかねいろ マキノ親父 子どもはどんな理由でお酒を飲むのか うわさ話は美味しい肴 焼酎麹 吟醸古酒の発見 防衛大学校の酒 新政、秀よし、日の丸 飲酒楽 会津娘 飲中八仙 とんぶり 大吟造り 文党根岸派 千鳥 玉子酒の味 嫌酒薬 清酒・李白 絶景と言うは樽肴ありてこそ 明智日向守 四毒(1) 吉原小歌鹿の子 玉子盃、熊がへ、武蔵野、吹よせ 御酒御酒御酒 少し甘めの酒を 美人酒、妖艶な美女 <割烹> 台所から裏まで タイの加減酢かけ 酒屋へ走る 戦国(楚) BC二三九 人の顔色を見ない 一品料理屋 西荻窪「鞍馬」 魚屋宗五郎 暑気払い 杜甫の酒 三田佳子 田崎早雲 私の洋酒ノート 大酒大酔の悪しきといふ事 [酒麯魚] 酒の唄 鹿狩の樽酒 下野家令 「やってくる」もの 県外出荷用銘柄 ワンカップのウオッカ 絶対味覚 蒸留酒製造法の伝播経路 初午生酔 粗相コール 酒茶会 新婚当時の梶原 「もろはく」を楽しむ お酒で元気をつける フキノトウ味噌焼き 愛と誇り 千紅万紫(2) 酒病偶作 江村杜氏 宝暦以前 「段平」 追剥ぎ 酒屋の秋刀魚の胴抜き 469無茶いうな 酒諺集 ぬかしながらの ニューカヤバ 天竺酒濫觴之事 吟醸香はなぜ果実香がするのか 塚田家覚書 紀文が涼の酒盃 魔法つかい 酒を飲んで絶対に乱れない女 花より団子 二日酔 ふぐ刺しと鍋 某月某日 はまぐりの潮汁 のんだくれ(飲んだくれ) 阿佐ヶ谷会 ジャワの日本酒 ある程度飲んでやめておく 畠中頼母(銅脈先生)(2) 初代川柳の酒句(10) 世代別消費 蓴菜(じゅんさい) ○酒好 洗米 漱石の酒句(4) 「こだわりの店」の担当者 はなのまく【花の幕】 ぶどう いっとちゃん 土佐日記 大衆食堂 再び酒を飲み初め アジの焼きサンガ 果(くだ)物さかな 損だけど マルセウ本間商店 松ちゃん 周 BC一一〇〇頃 酒が語る日本史 がんもどき 中山千夏 梅酒(うめしゆ) 国民的勝利 一寸能い処あり 花岡技師 竜舌蘭の酒 秋刀魚 大根の酒粕煮 うたびと [かすづけ瓜の作り方] 山内容堂 ホームバー ガスライト・クラブ ずいぶん手が上がって 親の膳 ざぶん/どぼん/焼き鳥 塩っぱい肴 一八才で離脱症状 落書 至福の夜 後悔の朝 陣鍋 酒病偶作 千紅万紫 佐賀 九州にあって日本酒人気の地域 じゅん菜(じゅん菜、三杯酢) 466気はたしか 適正価格 酒痕狼藉旧衣裳 市川段平 銀盤 お燗番 呼び鈴 士道不覚悟 和朝酒濫觴之事 買い酒と牛の尾は につぽん[日本] パックキープ 十六夜月 残業 佐久の草笛 飲んべエ健康法 フツカヨイ 子孫制詞条目 燗 土屋文明の酒歌 立野信之 プラタナスの葉 フマール酸 のみすけ(飲み助) 薄くした酒 ねぎま鍋 置き忘れ事件 タケノコの刺し身 酒の統計 畠中頼母(銅脈先生) 二十献の饗宴 良い酒となる理由 その他のおすすめカクテル 初代川柳の酒句(9) 古米鑑別法 〇胡瓶 取材を申し込む瞬間 漱石の酒句(3) 34どぶろく祭 ラク酒 村酔 酢の物(キュウリ、シラス、大葉) 福島 人気銘柄が続々登場する元気ある県 神主のいない神社の神殿 正式の会の名称 よし寿司 酒席でしばしば粗暴な振る舞い 銀行振込みの請求書 五百万石 きき酒資格 465決死隊 フルメイ、マツリゴト 〇酒の肴に 酒を飲みながら 三つ割り 新酒(植物)(地理) 手堅く手堅く 風流狂歌盃報条 [瓜菜を糟(ぬか)づけする法] 煮物 すみつかり 昭和21年12月23日 師走の酒 酔いがさめて ホップの抗菌作用 両関 銘柄はナイショ ついてはここで 街裏 大黒図への賛 お母さま 雪の夜は熱燗と美女の匂い 酒の詩集 殷 BC一六〇〇 或る日の酒父像 嘉納治右衛門 宵の間に
酒の飲みくらべ
〇酒の飲みくらべ、昔よりあれど、慶安の頃、地黄坊樽次が底深と酒戦の事、『水鳥記』を記して世に聞えたり。樽次・底深は作名也。樽次は実名茨木春朔とて、江戸大塚に住めりしとかや。底深は『水鳥記』に、「大師河原に池上太郎左衛門底深」とあり。『洞房語園』に、「県升見といふ医師大師河原甚哲と酒戦の事」をいへり。甚哲はもし太郎左衛門入道しての名などにや。その酒戦に用ひし杯は、蜂と竜とを蒔絵にしたる大杯なり。さすのむといふ謎の絵也(文化十二年十月廿一日、千住宿中屋六右衛門といへるもの、六十の年賀に酒の飲みくらべしたり。其時諸方の詩歌を求めけるに、おのれも狂歌一首かきてやりぬ。七里の賑のみか飲ことは鯨にまさる人の酒もり)。(「嬉遊笑覧」 喜多村筠庭) 長谷川外校訂
一茶の酒句
27盃(さかづき)に散れや糺(ただす)のとぶほたる (寛政句帖)
留別(りうべつ)
90とそ酌(くむ)もわらじ(ぢ)ながらの夜明(よあけ)哉 (さらば笠)
214掌に酒飯けぶる今朝の霜 (享和句帖)
236酒菰(さかごも)の戸口(とぐち)明りやみぞれふる (享和句帖)(「一茶俳句集」 丸山一彦校注)
はなゆ【花柚】
柚の花のこと料理の付合せに用ひられる。「江戸向の岡」に『柚の花は是酒中花の盛なり』とある。
酒中花も花柚も鉢の水すまし 盃洗の中に浮ぶ(「川柳大辞典」 大曲駒村)
彦助・明日葉・まるい
審査委員会(委員長は私、委員も私)を設け、議論が風発したが結論が出ない。「それでは…}ということで、今月行った店の中から3店を選んだ。まずは前のページでも触れた「彦助」-。この店、場所は遠いけど、何を食っても唸るのは、ご主人・後藤一郎さんのセンスとひたむきな努力のお陰である。これまであんこう鍋、トンカツ、牛タン…色んな料理を食べて来たが、何を食べても水準を遙かに越えている。こういう店は滅多にはない。そして、今回食べたのは、すき焼。あまりの旨さに溜息が出る。幸福感で身体が、心が満たされる。次に釣ったばかりの魚が食べられる「明日葉」-。釣りライター・柳葉魚としても活躍する柳良明さんが奥さんと二人で営む。柳さんは釣り歴五十数年。今でも時間の許す限り自分で釣りに行くが、顔なじみの船頭さんや河岸の特別ルートから鮮魚を仕入れる。この店、一匹丸々選んで、魚のすべての部分を色んな料理に作り分けるので、二~三人か、それ以上の人数で予約を入れるのが好ましい。そして最後に選んだのが、我々が居酒屋に求めるさまざまな要素を殆ど備えていると思う「まるい」-である。まずご主人のお客に対する対応が抜群、実に感嘆するほどの研究熱心で色んな料理を産み出す…数え上げればキリがないが、こんなに場所が悪いのに、毎晩満員盛況であることが、いい店である立派な証拠であろう。メインはモツ焼きだが、シロ、皮をとったタン、軟骨のホイル焼き…上げればキリがないが、美味しさの秘訣の一つがご主人、伊東明さんが元肉屋さんであったことだろう。あったかい酢飯で馬肉を握ったさくら寿司、仔牛のレバー刺し、馬肉のステーキ…もう食べたい料理のオン・パレード。というわけで1年間を費やして書き上げたこの「居酒屋日記」もなんとかかんとか完成した。さあて、今日は思いっきり食って、イヤッというほど呑むぞ。最後まで付き合っていただいた読者の皆さんみんなを連れて行きたいなあ。では「GOODBYE」で御座る。(「東京居酒屋はしご酒」 伊丹由宇) 彦助(新羽)横浜市港北区大尾町2091、明日葉(表参道)港区南青山5-9-1、まるい(押上)墨田区業平3-1-1
漱石の酒句(5)
三河屋へひらりと這入る乙鳥(ツバメ)哉
呑口に乙鳥の糞も酒屋哉
十月二十日松根東洋城宛の手紙の中より 四区
酒少し徳利の底に夜寒哉
酒少し参りて寐たる夜寒哉
酔過ぎて新酒の色や虚子の顔(「漱石全集」)
好気型(こうきがた)こうじ菌(きん)
こうじ菌が単位時間当たりに消費する酵素量から育成型を好気型,中間型および嫌気型に分ける.ツァペック改変培地に培養した菌体100mgの単位時間当たり(30℃5日間)の酸素消費量が、60μl以上を好気型,20~60μlを中間型,20μl以下を嫌気型といい,QO2μl/100mg=60のように表示する.市販の種こうじ菌は一般に好気型または中間型に属する菌を適宜混合したものである.好気型の菌株を使用すると,こうじは造りやすく,栗香高く,アミラーゼ力は強い.他方,褐変物質のドーパの生成も多い傾向にあり,黒(くろ)かすの原因につながることがある.
嫌気型(けんきがた)こうじ菌(きん)
酸素消費量が少なく糖分の取込みは多いがエネルギー利用率が悪く,少量の菌体しか構成できない.その糖は嫌気的に分解して多くはアルコール発酵に向かうものと考えられている.この型のこうじ菌は繁殖が遅く酵素力が弱いため清酒用の種こうじ菌としては利用されていない.(「灘の酒用語集」 灘酒研究会)
ちろり酒
俗諺に「山の芋変じて鰻となる」というのがあるが、あるはずのないことが実際に起こることで、物がよく変わることの譬(たと)え。一方、昔、お坊さんは殺生戒のため、葷酒(くんしゆ)も魚・獣肉も食べることを許されなかった。そこでウナギを山の芋と称して、ひそかに寺内に取り寄せ、蒲焼きにして賞味したとも言う。古川柳にも、
山の芋鰻に化ける法事をし
とある。
自然薯の発掘談やちろり酒 小満ん(「にっぽん食物誌」 平野雅章) お寺での酒の隠語は般若湯です。
花柳かづらに折りし梅の花誰(た)れか浮かべし酒杯(かさづき)の上(へ)に 壱岐目村氏彼方
太宰帥大伴旅人の主催した梅花の宴の歌の一首(巻五・八四〇)。梅の花を酒杯に浮かべることは、他に八五二、また旅人の妹坂上郎女の歌(一六五六)にも詠まれるが、いずれも次のような詩の表現と繋がりをもつものであろう。
玉椀(ぎよくわん)花の落つるを承(う)け、花落ちて椀中芳(かんば)し、酒浮べて花没(しづ)まず、花含まれて酒更に香し(周明帝「和二王褒摘花詩」『芸文」類聚』木) 落花時に酒に泛(うか)ぶ(『遊仙窟』)
『万葉集』の酒には、唐の国の香りがある。(「酒杯に花を」 大谷雅夫)
御題「祭」
昭和五十年一月新春御歌会始の儀に召人として献歌を命ぜられる
新年同詠祭応制歌(としのはじめにおなじくまつりということをおおせごとによりよめるうた)
いそしみて いや醸(か)み継がむ にひなめ(新嘗)の まつりのには(庭)の しろきくろき(白酒黒酒)を(「坂口謹一郎酒学集成」)
阿佐ヶ谷界隈
なぜ阿佐ヶ谷界隈において、新しい文学が芽吹いたか、この問いには、なかなか容易に答えられない。だが、これまで紆余曲折しながら書いてきたことをふりかえってみるのも方法であろう。といって、私の頭の中で想はうまくまとまらない。私のこだわる阿佐ヶ谷界隈にしたところで、これといった特色はない。関東大震災後に発展した郊外の新開地である。街並は雑然紛然としたものだ。そこに住む人もまた街並と同じように、いろいろさまざまといったところか。プロレタリアの作家たちの大部分は、高円寺から吉祥寺の間に住んでいた。対して新興芸術派の文士たちも、おおよそ同じゾーンの住人たちであった。それより遅れて登場して来た文士たちも、やはり阿佐ヶ谷界隈に集まっていた。これらの人々は酒場で、あるときは銭湯で顔を合わし、互いに影響しあっていた。そうだ、この雑然紛然とした人間関係、思想を異にした混沌が、時代の作家を育てていった。私はふとそう考えついて、阿佐ヶ谷界隈にこだわる自分の気持ちが少々整理できたような気分になった。(「阿佐ヶ谷界隈」 村上護)
のんべ(飲兵衛)
[名]「のんべえ」に同じ。◇『カツドウヤ紳士録』遠くへ飛びたがる女(1951年)<山本嘉次郎>「新橋随一の呑ンベといわれた年増芸者と」
のんべえ(飲兵衛)
[名]酒好き。<類義語>うわばみ・飲み助・飲んだくれ。◇『東京語辞典』(1917年)<小峰大羽>「のんべい(呑平) 酒を飲んで、しまりなきもの。『のんだくれ』に同じ」(「日本俗語大辞典」 米川明彦編)
じゃこご飯
大根の葉は内側のやわらかいものを使います。具だけを多めにつくってガラス容器などに入れ、冷蔵庫に保存すれば3~4日持ちます。
●材料(2人分) ご飯400g じゃこ大さじ4 ひじき少々 大根の葉100g ごま油大さじ1 醤油大さじ1/2 酒小さじ1
●作り方 1ひじきは水で戻して洗い、さっと茹でてザルにとり、刻んでおく。 2大根の葉は、よく洗ってみじん切りにする。 3ごま油で大根の葉を炒め、じゃこを加えて炒め、醤油と酒を加えて火を止める。 4炊き上がったご飯に、ひじきとじゃこを混ぜ込む。(「おうちで居酒屋」 YYTproject) 仕上げのご飯です。
下戸の屁理屈
いずれの場合も、酒を注ぐ側に廻るからいけないと考えつき、去年の九月だったか、「道元の冒険」という拙作芝居の千秋楽に、飲む側に廻って、酒をがぶ飲みしたところ、たちまち大愉快の気分になり、劇団の人たちに片っぱしから口論を吹っかけ、とうとう全員の前で「本日をもって劇団をやめさせてもらう」と宣言し、大威張りで家へ帰った。翌日、素面にもどり、事情を聞いて仰天し、詫びを入れて元の鞘に戻ったが、これは情けない上にだらしがなかった。(「酒中日記 下戸の屁理屈」 井上ひさし)
ずっと馬鹿でいなよ
「先生、めでたく担当を解任されました」「そりゃ、めでたい。これでオレも枕を高くして眠れるよ」「先生、ボクみたいな馬鹿がいなくなると、淋しいよ」「確かに、あんたは馬鹿だったよ」「僕は、先生に育てられて、本当にきちんとした馬鹿になったよね」「偉い。誉めてつかわす」「『レッツラゴン』終わるよ」赤塚は、立って行き、冷蔵庫からハイネケンを二缶持ってきて、机の上に置いた。二人は、缶を合わせた。「武居がいたから『ゴン』がやれたんだよ。武居がいなくなったら、終わっていいんだよ」僕は、何かくだらないこと言わなくちゃ、と思いながら、ビールを喉に流し込む。くだらないことって難しい。才能がなけりゃ言えない。「タリラリラーン」というしかなかった。「タリラリラーンてね、馬鹿のことなんだよ」「あ、そうなんだ。知らなかったよ。そういえば、『山の音』って映画あったね」「原節子と山村總ママの出る映画だろ」後が続かない。静寂が怖い。赤塚は、再び立っていって、ひばりのレコードをかける。〽丘のホテルの赤い灯も 少しホットした。しかし、二番の歌詞が良くない。〽いつかまた逢う 指切りで 笑いながらに 別れたが 堪えきれなくなった。僕の口が勝手に動く。「先生、これからは、編集に頼るのやめな。アイデアマン、自前で作らなくちゃ駄目だよ」最低のこと言ってる。「わかったよ。あんた、うるさいよ」二人は、ひばりの唄を聞きながら、ひたすらビールを飲む。もっと強い酒が欲しい。僕は、立っていって、ダルマと、グラスを二つ持ってくる。グラスになみなみと、ウイスキーを注ぐ。僕の記憶は、ここまでだ。その夜のことは、ほとんど覚えていない。かすかに覚えているのは、赤塚の言った次のセリフだ。「ずっと馬鹿でいなよ。利口になりそうになったらね、『お〇○こ』って、大声で一〇八回叫ぶんだ。そうすると、また馬鹿に戻れるよ」(「赤塚不二夫のことを書いたのだ!!」 武居俊樹) 武居は少年サンデーの編集者です。
課長
頃合いに 宴席立って 名課長 平総代
割り勘と 素直に言えぬ 「長」が付き ひでお
強妻
飲み屋でも 女房の方が 顔がきき 面痴菴
均等法
平等法 女もストレスためて飲み 万年娘
健康診断
検診の 結果でるまで 飲み続け 隅田川(「平成サラリーマン川柳傑作選 一番風呂・二匹目」)
人参党
私も人参党になってかれこれ二ヵ月だが、たしかに効き目はある。最初はあの土臭い甘い匂いがハナについたが、ふしぎなもので、だんだんその味に魅せられ、いまでは旅行の際、魔法びんに入れて携行する始末である。私事で恐縮だが、慢性疲労症、それも重症の私であったが、このコリのような疲労素が最近はほぐれてきたような気がする。そして困ったことに女の子がキレイに見え出してきたことである。物理的に、朝の充血が回復したことも顕著な効き目といえるだろう。それと宿酔(ふつかよい)のとき、たしかに特効ありといいたい。土瓶に、五合くらいの水をいれ、そのなかに、人参二~四本を入れ、約二時間、とろ火で煎じる。この煎(い)り薬を繰返し服用していると、あの執拗な宿酔から次第に解放される。脱宿酔に、この人参はたしかに薬効ありと断言できる。(「置酒歓語」 楠本憲吉)
あい子さん
ボクの失敗談の一つ。二年ぐらい前、新宿で飲んでいた時の話。すでに、四軒ぐらいハシゴをして、一人でいきつけの店にふらっと入って、またウイスキーをあおっていた。すると、作家でボクの飲み友だちの中山あい子さんが、ある編集者を連れて入ってきた。「まあ、はらサン、しばらく…」「やあ、どうもどうも」なんて、あい子さんと和気あいあいのあいさつ。あい子さんもボクも、酒量は相当だったもので、連れの編集者をおっぽり出して話に興じていた。ボクと同い年だそうな。その男、いきなり、「馴れ馴れしくするんじゃない、このヤロウ」とタンカを切ってしまった。「いや、これはすいませんです」って、ボクもはじめは丁寧だった。それからものすごく悪い酒が入って、ね。で、やっぱり、そのうちぶつかった。やりましたよ、ボクも。それまで飲んでいた酒の勢いが、いっぺんに出ました。先手必勝ですよ。ケンカは。ただし、ケンカでも、なぐったら損です。怪我をさせてしまったら、損。それにすぐ、翌日の朝刊に、「漫画家はらたいら(三七、本名原平)新宿で酔っ払いケンカ。被害者は、頭部打撲など合わせて全治二週間のケガ」なんて出たら街も歩けなくなる。とにかくそうならない程度にやりました。ところがその間、あい子さんは、小さくなっているんです。それで、男二人がだんだんのっぴきならなくなってきたら、「サヨナラ、サヨナラ、…」手を振って、帰っていくではないですか。その後、あい子さんとまた飲んだ時、「最近ね、私、喧嘩もできなくなったから、つまらないわ」(「シャレと遊びと人生と」 はらたいら)
魔術用の酒
料理用の酒には、フツカヨイはないのであるが、魔術用の酒には、これがある。精神の衰弱期に、魔術を用いると、淫しがちであり、ええ、ままよ、死んでもいいやと思いがちで、最も強烈な自覚症状としては、もう仕事もできなくなった、文学もイヤになった、これが、自分の本音のように思われる。実際は、フツカヨイの幻想で、そして、病的な幻想以外に、もう仕事ができない、という絶体絶命の場は、実在致してはおらぬ。太宰のような人間通、色々知りぬいた人間でも、こんな俗なことを思いあやまる。ムリはないよ、酒は、魔術なのだから。俗でも、浅薄でも、敵が魔術だから、知っていても、人知は及ばぬ。ローレライです。太宰は悲し。ローレライに、してやられました。情死なんて、大ウソだよ。魔術使いは、酒の中で、女にほれるばかり。酒の中にいるのは、当人でなくて、別の人間だ。別の人間が惚れたって、当人は、知らないよ。(「不良少年とキリスト」 坂口安吾)
〇生姜酒十一
鹿門筆記云、生姜酒を風邪に用る事、宜き法なり。孫対薇が丹台玉案、といふ書に出たり、神仙粥と号(ナツケ)たり。」按ずるに、丹台玉案は、明の崇禎丁丑。孫氏の自序あり。丁丑は、皇朝の寛永十四年なり。それよりさき、酒飯論に、冬の寒くてこゞえたる、はじかみ入たるわかし酒のめば、風こそよりつかねとあり。酒飯論は、後成恩寺殿兼良公の御作なりとぞ。此殿八十歳にて、文明十三年四月二日に薨じたまひしよし、摂関補任次第、宣胤卿記等に見えたり。寛永十四年にさきだつこと百五十余年なり。されば、ふるく唐土の書に、此事有べくおもひしに、医方類聚に、瑣砕録を引て云、卒ニ感二風寒ヲ一。用二生薑汁一調。熱酒一盞。則発散。とあり。陳振孫の書録解題に、瑣砕録二十巻。温革撰。陳昱増レ之。[割注]孫奕示児編には陳曄とあり。周輝清波別志には宣政貴人所レ纂也。」と見えて、宋朝の書なり。(「梅園日記」 北静廬)
童蒙酒造記(どうもうしゅぞうき)解題
一七世紀の酒造法を詳細に記述した教科書的な酒造技術書で、江戸時代最高の酒造技術書といわれる。「童蒙」とは、まだ知識も理解力も十分ではない子どもという意味だが、子どもでも理解できるほど懇切ていねいに書かれているという意味か。延年五年(1677)から貞享三年(1686)までの米価と酒価の記述があることから、貞享四年以後、遅くも元禄(1688~1704)の早い時期の成立と考えられる。著者も不明だが、「当流と号するは鴻池流なり」とあることから、当時、隣の伊丹と並ぶ諸白の先進地であった鴻池で酒造りに従事していた技術者が書いたのではないか、と推定される。鴻池流を中心に、奈良流、伊丹流、小浜(現在の兵庫県宝塚市)流など各流派の酒造法、酒造道具、酒造用語など、酒造り全般にわたって詳しい解説を加えている。全五巻。(「日本酒百味百題」 小泉武夫監修)
酒造るに吉日・凶日の事
一、あやふ(1) 酒に大吉祥日なり
一、おさむ(2) 酒に大悪日なり
酒造りの吉日と凶日
〇あやぶむ(1) 酒造りには大変めでたい日である。
〇おさむ(2) 酒造りには大変わるい日である。
(1)あやふ 暦の語。高いところへ登ったり、船に乗るのは凶日だが、酒造、家造、婚礼には吉日とされる。 (2)おさむ おさん。暦の語。諸事に吉日とされるが、酒造には凶日。(「童蒙酒造記」 吉田元 翻刻・現代語訳・注記・解題)
せんべろ作法
相棒カツヤンは、初めての立石で女友達と酒場でおしゃべりに夢中になっていたら、「食べないなら帰っとくれ」とおんだされたトラウマがあるの…」らしいが、飲まず食わずで話に夢中など、この町の酒場では無粋の極み。おんだされて当然のろくでなしである。「ホントにうまくて安い店は原価ギリギリでやっているわけです。人件費を抑えてお客を回転させなきゃ潰れちゃうわけです。貴方のように喫茶店代わりに使う輩はせんべろ酒場の敵。猛省を促す。大丈夫、ちゃんとしてれば怖くないから!」とせんべろの母のごとく叱咤と激励を繰り返しカツヤンを単身で送り込んでみた。(「女2人の東京ワイルド酒場ツァー」 漫画・カツヤマケイコ コラム・さくらいよしえ)
第七 飲酒を慎む
昔しは酒に耽(フケ)り国を亡(ホロボ)したる王もあり。故に酒には狂薬(キヨウヤク)の名あり。淫源(インゲン)の称(トナ)へあり。実に悪行の原因となるものなれば、仮令(タト)ひ性質之(コ)れを好むものと雖(イエド)も、必(カナラズ)適度を越るべからず。近来西洋には禁酒の会盛んに行はれ、我が邦(クニ)にも既(スデ)に其(ソノ)会あり。若し自(ミズカ)ら度を守ること能(アタ)はざれば、此会に入りて禁酒を守るも可なり。西賢の戒(イマシ)めに云く。「この下等なる歓楽に耽(フケ)る者は真正の福祉を失ひ、徳善(トクゼン)の行(オコナイ)を損し、剛毅(ゴウキ)の志を失ひ、健康の身体を害す。洵(マコト)に怕(オソ)るべくして戒(イマ)しむべし」と。
明治三十年十一月二十六日、即(スナワチ)開業満三十年記念日 古屋家二世 徳兵衛謹みて識す(「家訓集」 山本眞功編註) 東京松屋初代・古屋徳兵衛の古屋家家訓です。
にようぼう[女房]
正しくは宮中の女官上﨟・中﨟・下﨟の総称で、おのおの一人住いのの部屋を賜っている、江戸城大奥の局(つぼね)に当るものでこれを女房と言い、転じて女官の別称となつたのだが、いつの頃からか一般の妻女の俗称になつてしまつた。川柳には女房の句が非常に多いので、ここには代表的なものを挙げて置く。
⑩女房の謡よつぽどひどく酔ひ (樽四)(樽一一)
⑱あくる朝女房は管をまき返し (樽一七)
⑩女房の謡が出るようでは、大分頂戴している。類句-よつぽどのきげん女房の謡なり(樽一四)(樽三九)。-⑱酔つて帰つた翌日は女房にきめつけられる。類句-腹の立つすそへかけるも女房也(樽三)。(「古川柳辞典」 根岸川柳)
470方法は簡単
その男は、余り肥え過ぎになって来たので、医者に相談しようと決心した。医者は、その男の言うことを聞いていたが、やがて静かに言った。「貴方にお誂(あつら)え向きの方法が一つあります-それは運動です」「でも先生、私は運動が嫌いなんですよ」医者は頷いて、「そんなに疲れるようなものではないんですよ。ただ頭をゆっくり左右に振るだけのことですよ」その男は一寸嬉しくなって、「で、それを、どの位やればいいんですか?」「そうですね、誰かが酒を飲まないかッて誘った時だけで宜しい」(「ユーモア辞典」 秋田實編)
和平どん
又、晩春の頃だった。爺やが風邪で寝ていた為、浦賀造船所へ納めている同地の雑貨店へ、卸し売りの白酒を、荷車に一荷積んで、和平どんが前を曳き、僕が後押しして行ったことがある。浦賀街道の山道までかかると、和平どんは一ぷくしようと云い出し、車を止めて休んだのはいいが、そのうちに「おまえ、店へ帰っても、喋るんじゃないぞ。いいか、途中で壊(こわ)れたと云っとくんだから」と云って、四打(ダース)入りの箱をコジ開け、中の白酒を二本ほどラッパ飲みしてしまった。そして残りをぼくにくれた。ぼくは眼がくらくらし出した。いや、それ所ではなく、和平どんはすっかり酩酊してしまい、それからの峠の下りを何べんも転びかけた。また崖へ車をぶつけたりして、あと白酒のビンを何本も破り、白酒を道々撒いて歩いた。どうなる事かと、ぼくは尾いて行くばかりであり、あんな困った事もないが、面白かった事もない。(「忘れ残りの記」 吉村英治) 横浜の食料、洋酒、雑貨を商っていた続木商店での丁稚時代のエピソードです。
ざんぐり
ようやく現れたのは、料亭か高級割烹のごとく、漆(うるし)の盆に盛られた、色も形もきめ細かく美しい料理だった。ひと口食べたら、さらに驚愕した-こんな古びた「四富会館」で、こんな小さくてファンキーな「焼き魚バー」で、あの大きな体の店主が、これほど繊細な味の料理を出すとは!きっと全国を探し歩いても、似たような店は見つけられないだろう。しかも、千円もしないではないか!「これぞ穴場!!」と叫びたくなるほど興奮したことを、いまも鮮烈に覚えている。当時は、「四富会館」も「ざんぐり」も、まだタウン誌やネットなどで取り上げられる前だったし、開店してからの日も浅かったので、偶然ながら本当に我々が発見したという気持ちでいた。それから一年間、何度も通い、店主と親しくなるにつれて分かったことだが、彼は岐阜県の高校を卒業してから板前の修業のために京都に移住し、約二十年間市内の料亭の厨房で経験を積んでから、独立して「ざんぐり」を開いたそうだ。そう聞くと、あの料理の質自体は驚きに値しないかもしれない。しかし、店舗と言い、立地と言い、そして周囲の街との極端な違いと言い、いまでも全国でもっとも異色な居酒屋の一つだと思う。ただし、いつまであの価格で、ごく少数の客を相手に店を続けられるか、やや心配である。(「日本の居酒屋文化」 マイク・モラスキー)
ベロベロの神様
なんと、高知でのラジオ収録の当日は「おきゃく」イベントの興奮がピークに達する最終日前日。取材対象が酒宴そのものだから、万事休す。僕と相棒の谷本美尋(たにもとみひろ)アナウンサーは、マイクを手に酒浸りたちの海へ漕(こ)ぎ出した。帯屋町(おびやまち)を中心とするアーケードは、飲食用の枡席(ますせき)、卓席が設けてあり、おでん、牛ステーキ、トマトなどの売り場も混在。酒場に縁日を重ねたような賑(にぎ)わいだ。多人数を相手に乾杯となるのは必至、もう酒量に歯止めがきかん。辿(たど)り着いたのが、メイン会場の中央公園入口。ほろ酔い眼(まなこ)を見開けば、"ベロベロの神様"が青面に鎮座しているではないか。頭に徳利(とっくり)を載せ、酔っ払った目はロリポップ風うずまきキャンディー、フィギア作家のデハラユキノリ氏のデザインによるユニークな像だ。素っ裸でピンク色の座敷童(ざしきわらし)を連想させる。相変わらず乾杯の嵐は続いていた。交わす笑顔はみなチャーミング、飛び抜けた美女の多さに酔いも極まる。酒という名の利尿剤が溜(た)まればトイレに走る。また乾杯、またぞろ走るの繰り返し。タッチの差で滴(しずく)が洩(も)れても気に留めてなどいられない。今度は白ワインで隣のご婦人と"カンパーイ"。あれっ、ここは雲上の天国。それとも機内?斑(まだら)に抜け落ちる記憶を物ともせず、閑散とした羽田(はねだ)空港へ降臨した。手押しのカートを蛇行させてトイレへ走り込む。どうやら、僕は"ベロベロの神様"に憑依(ひようい)されっぱなしだったらしい。(「酒は人の上に人を造らず」 吉田類)
和らぎ水
「和らぎ水」とは、日本酒を楽しみつつ合間に飲む水のこと。ウイスキーとともに出される「チェイサー」と同じである。最近、日本酒を頼むと、この「和らぎ水」をともに出してくれる店が増えてきた。深酒を防ぐ、酔うスピードを緩和させる、口のなかをすっきりさせるといった効果が生まれるという…。曖昧な表現にならざるを得ないのは、わたくし自身、水があってもなくても、あまり酒量が変わらないため。すっきりするのは確かだが、結果、覚醒してさらに呑んでしまっているような気もする。また、「和らぎ水」の力を借りると、二日酔いにならないという噂も…。これまた断言できないのは、日頃から二日酔い知らずで、実証できていないから。重ね重ね頼りにならず、申し訳ないが、周囲ではその効果を実感する人は多いようだ。(「ニッポン「酒」の旅」 山内史子)
当世こうた揃 新なげぶし
▲三輪の神かや よろ/\ナ 通ふひるは 人目のナ しげければヤン 人目のナ ひるは昼は 人目のナ しげければヤン
▲さんやどてぶし(土手節)
「ゆめの、うき世に、さ〻(笹=酒)の(飲)うで、遊べ、あすはこひしき、昨日の、むかし、たれからとせの、月日をおくる、今宵かぎりと、いよでたをのこ(男)、強きお酌(しやく)にいかなる下戸もつがばおのまさんせのも酒を(「当世こうた揃」 塚本哲三編輯)
サバのつまみの大常番 しめサバ
材料(4人分)
サバ…1尾 塩…カップ1 (甘酢)酢…カップ1 砂糖…カップ1/2 塩…大さじ…1 昆布…30cm1枚
作り方
①三枚におろした-サバは、腹骨をすき取り、たっぷりの塩を両面にまぶし、約3時間おく。
②分量の調味料を合わせて甘酢を作り、①のサバをサッと水で洗い、水けをきって昆布とともにつけ込み、約30分間おく。しめ加減はサバの身の周りが白っぽくなる程度。
③酢から上げて血合い骨を取り、皮を頭のほうからむく。
④5mmくらいのところに浅く飾りの切れ目を入れて次にまた5mmくらいのところを切り、一つの切り身の幅が1cm弱の八重造りにする。
⑤つまを添えて器に盛る。
このつまみに、この一本
雑賀(さいか) 純米無濾過生原酒/和歌山 日本酒度…+4 酸度…1.8 価格…3000円(1.8l) ●難しくて悩みましたが、まずサバは、塩と酢で臭みが消されている。ならばなれ寿司感覚で、麹の風味が色濃く、魚のコクを増す「雑賀」で、新鮮な酸味と苦味が、後味を爽快にする。(来会楽)(「新・日本酒の愉しみ 酒のつまみは魚にかぎる」 編集人 堀部泰憲)
酒漬(さけづ)けに水も尽く
色茶屋で遊興にひたっていては、ついに水も飲めなくなる。その果てには家に帰り着かざるを得ないことを掛ける。近松門左衛門(ちかまつもんざえもん)(一七二四)の『心中重井筒(しんじゆうかさねいづつ)』に、<酒漬けに水もつくかやわが宿へ、かえりこん屋の徳兵衛いそがしげに立ちかえり、>とある。(「飲食事辞典」 白石大二)
古今夷曲集
貞徳
売ためて銭口おほく結ぶべし 是ほと酒がいつみなりせば
題しらず 淡路守宗増
座頭衆すゞみとなれば酒盛の てうしを請て平家かたれり
玄康
朝酒をおぼく呑 ばくるゝまで 只是槿花一日の酔
月のもとの酒宴 三政
世捨人かいや夜は捨ず月の本の 酒にこゝろがうき蔵司なり
九月九日に 種好
君が代にすんでとくりの菊の酒 くめば珍重陽てうれしき(「新群書類従」 市島謙吉編)
ご下賜の盃
また、松平幸千代[後に出羽守]は、これも十一歳で初めてお目見えなさった。御家衆の初めてのご対面には、御盃を賜るのが恒例であるから、幸千代にも御盃を下されたところ、お小姓が誤って、幸千代の手にしたかわらけに、お酒をつぎすぎてしまった。そば仕えの人々もこれを見て、気の毒に思ったけれども、ご下賜の盃のことであるから、こぼすわけにもいかず、そのまま手にもっている。それをごらんになって、上様から「こぼせよ」とのおことばがあった。そこで近臣が立ち寄って、三方(三)を幸千代の傍に寄せて置いたところ、幸千代はそれにかまわず、盃をおしいただき、一口飲んで、そのあとは自分の左の袖へざぶっとこぼし入れなさった。そのようすがことのほかみごとで、その座の人々も大いに感じ、有徳公(徳川吉宗)もご機嫌うるわしくあられたということである。
(三) 神仏や貴人に供物を奉る木製の台。(「翁草」 神沢貞幹原著 浮橋康彦訳)
えうてうとたをやかにして茶椀酒
えうてうは窈窕(ようちよう)、美人の形容であろう。たおやかなる美人が茶椀酒をあおっているのだが、美人は何をしてもさまになるのだ。これが男だと、<小判にて飲めば居酒も物すごし>荒れた感じになって、「コウ、とっつぁん、酒くれ。金はある」と目を据えて、チャリンと小判を落されると、「いいのかえ、あれ」とみんな、こわごわ、遠まきに見る感じでぶきみ、今なら赤軍派くずれかと怖がられる。小判といえば「末摘花(すえつむはな)」に、<急なこと夜鷹に小判金で買ひ>というのがあり、こんなことはウソであろうけれど、ほんとうらしくいうところが笑わせる。夜鷹は最低の娼婦で、価もぐっとお安く二十四文(もん)、<股倉を四たびまくつて百になり>というのは四回九十六文で、これは百文に当るからである。そんな安ものを小判で買っておつりをもらおうというのもすさまじい、ともかく、「こちゃ急(せ)いとんねん」というところであろうか、誇張のおかしみの句である。私、思うに小判をつかんで夜鷹を買いにいくほど切迫しているのだから、独りものであろう。<たまさかに煙を立つる独りもの>、ろくに家では炊事もしないだろうし、一人で盃を抱いていてもしかたがない、やっぱり、酒はさしつさされつか、それとも家で、子どもをからかいながら飲むのが、健全な市民としてはまことに理想的。ちょっと酔ってくると、
とつさんのなまゑひやいと母へ逃げ
かわいい句である。小さい子供が「ワーイ父ちゃんのよっぱらいヤーイ」とはやしたてて、おっ母さんのうしろへにげこんでいるのだ。「こら坊主」などと熊さんか八っつぁんか、たいそうごきげんである。子どもはみんな、こういう西も東もわからぬ無邪気なのがよい。(「酒飲み月」 田辺聖子)
両国「ほそ川」
新店舗は、京壁の和とモダーンなテーブル、チェア、照明器具が意外に調和しており、落ち着いたゆったりした空間を形成している。まずわさび醤油漬けと焼きみそを注文。九平次と合わせる。わさび醤油漬けは、わさびのつんとした味がよいアクセントとなり酒が進む。焼きみそは氷砂糖のような綺麗な模様の石にのせて提供され、美味しさだけではなくお洒落な色彩が食欲を誘う。細川さんは器好きでもあり、新進の陶芸家のものなどを使っている。-
せいろはつるつるしていて、上品な香味と食感のバランスがいい。鮮烈なインパクトはないが、食べるほど口のなかに旨みが広がってくる。汁のバランスもとてもいい。-
快適な空間で、酒を飲みながら質の高い酒肴、蕎麦を食べられる下町の隠れ家として、細川はいろいろ利用できる。(「蕎麦屋酒」 古川修) 東京都墨田区亀沢1-6-5
お酒飲んで芸者上げると
鈴木(三郎助) いま花柳界というと、一般サラリーマンなんか近づけないような高いお金がかかる、その当時はどうだったんです?
三田(政吉) 昭和十年頃僕が遊びに行った当時、神田の講武所のところで、八円から十円持って行ったら豪遊できましたね。もちろん一人で。
鈴木 当時の十円ねぇ。大学出の初任給が…。
三田 五十円くらい。東大はいくら、私学はいくらとランクがありました。私学がちょっと安かった。官学を出て六十円近いものでしたね。その時代、料理は高級なところで三円から五円ですよ。昭和の初めで私の家が、つまり「濱田屋」で三円五十銭だった。ここの家(浜作)はいつ出てきたのかな。
鈴木 昭和三年。
三田 そのじぶん、ここの家は三円から四円だったでしょう。
鈴木 お酌を入れてですか。
三田 いやいや、お料理だけ。お酒飲んで芸者上げると五、六円くらい。
鈴木 飯時代でしたね」(笑い)。(「友あり食ありまた楽しからずや」 鈴木三郎助対談) 三田は明治座社長です。
ベトンベトン
わしなんか若い頃は、上げるまで飲みよったよ。もう、ベトンベトンンになるまで 小倉のタクシー運転手さん
運転手さん名言集の第二弾です。もう、かれこれ十二年ほど前のこと、はじめて北九州の旅仕事をしたときです。夏の暑い時期に、酒屋の店内で飲ませる「角打(かくう)ち」の特集を担当させていただきました。飲んで歩くだけの仕事、というとウソみたいですが、本当にそんな感じで、ただ、二泊三日、朝から晩までよく飲んだから、終わったときはヘロヘロになった。カメラマンとふたりして、帰りの北九州空港まで、タクシーに乗せてもらいました。運転手さんが話しかけてきたきっかけが何であったか、記憶にない。けれど、角打ちをめぐってきて、これから締めに、空港でまた焼酎をやってから東京へ帰ろうと思っている。そんな心積もりを、伝えたはずです。「わしも、昔はよう飲んだよ」「ああ、そうですか、焼酎ですか」「なんでも」「私も日本酒だろが焼酎だろうが、なんでも行くほうで」「そうかあ、わしなんか若い頃は、上げるまで飲みよったよ」上げるというのは吐く、ということだと気づくのに、ほんのちょっとの間があったのですが、運転手さんはその間隙を逃さなかった。「もう、ベトンベトンになるまで」ベトンベトン…。べろんべろんなら聞いたことがありますが、ベトンベトンは初めてだ。思うに、べろんべろんと言うつもりだったのが、「上げる」話をしたものだから、ベトベトのイメージが入り込んで、なんとも言えないひと言に仕上がったということなのでしょう。同行の写真家が笑いをかみしめ、「ベトンベトンって…」と呟くのが耳に入るや、私も笑いをこらえられない。「今も、ベトンベトンになるまで飲まれますの?」笑いながら訊くわけです。小柄で、胡麻塩頭の運転手さんは、いやあ、と言って左手で、じょりじょりしそうな後頭部を撫でながら答えたものです。「あのね、もう酒を飲んだらいかんというところまで飲んだからね。あの、アルコールをやめるところに入ってね。それで酒をやめたのよ」「断酒会みたいなやつですか?」「そう、あれで、すっぱりやめた」「今は大丈夫なんですか」「飲まないからね」すごい話だな。と思う。それだけ飲んだ人がすっぱり縁を切るすごさがひとつ。もうひとつは、今、運転を仕事にしているってこと。私と写真家は、なぜか、深く納得した。人生、どこの世界にも、上には上がいるものなのだ。そのことに、深い深い二日酔いのど真ん中で、気づかされた。(「酔っぱらいに贈る言葉」 大竹聡)
酒の専売制度
時代:新 年代:建国二 洋暦:一〇 酒の専売制度実施(『漢書』「食貨志」下)。同一記事に、原料使用量と出酒量の説明があり、玄米二斛(こく)、麹一斛から酒六斛六斗得られる。これ以後、酒を専売にした政府は多いが永続していない。(「一衣帯水」 田中静一)
きゅうりもみの粕和(あ)え
神亀酒造 小川原さん他のお勧め
簡単に作れる一品です。あとひと品おかずが欲しいときに作ってみましょう。
●材料(5人分) きゅうり 2本/塩 少々/踏み粕 適量
●作り方 ①きゅうりは千切りまたは輪切りにし、塩もみして水気を絞っておく。 ②踏み粕で和える。
◆好みで踏み粕に砂糖少々を加えたり、みりん・醤油・酢で味つけしてもいいでしょう。またきゅうり以外の季節の野菜を塩もみして和えてみましょう。(「酒粕の凄い特効」 滝澤行雄監修)
ある人の断酒満願の日に 昭和二十九年六月一日 於舞子(まいこ) 吉川英治(よしかわえいじ)
酒は愛(かな)しめ酒憎め
のむな飲むべしさまざまに
人はいうなれ酒談義
真似(まね)ぶ君にはあらねども
世にあだ言(ごと)をためさんと
別れの約もいつかひと年
ゆくりなく
こよい舞子の宿の灯は
淡路(あわじ)に近くふるさとの
母もゆるすと君のいう
など杯(さかずき)にとがあらん
約も解けたりいざ酌(つ)がん
酒愛(め)で給(たま)えいのちぐすりに(「酒の詩集」 富士正晴編著)
七、酒の肴としての肉料理
[生肺]獐(のろ)の肺を上となし、兎の肺これに次ぐ。もしなければ山羊の肺これに代ふ。一具全く損ふなき者、口をして血水1を「口匝」(ぬぐ)ひ尽くさしめ、涼水を用て浸す。再び「口匝」(ぬぐ)ひ再び浸し、血水を倒し尽くし、玉葉2のごとくにして方に可なり。韭汁(きようじゆう)3・蒜泥(さんでい)4・酪・生薑の自然汁を用て塩を入れ、調味し匀へ、滓を濾し去り、湿布を以て肺の氷「氵月+上:八、下:天」を蓋ひ、灌袋(かんたい)を用てこれに灌(そそ)ぎ、務めて充満することを要す。筵上(えんじよう)5に就きてこれを割(さ)き散ず。
①血水=血液 ②玉葉=玉のように美しい葉。ここでは、玉のように半透明になるまで血液を吸い出した肺のこと。 ③韭汁=ニラの汁。 ④蒜泥=ニンニクをすりつぶしたもの。 ⑤筵上=宴会の席。
[生肺]のろの肺が最もよく、兎の肺が二番目。もしそれがなければ山羊の肺で代用する。架けているところのないものを用いて、口で血をすいだし、冷水にさらし、もう一度ぬぐいひたして完全に血をぬき、玉葉のように半透明になればよい。ニラの汁・ニンニクをすりつぶしたもの、発酵乳、しょうがの汁の中に塩を入れて味を調える。滓をこしさり、湿った布で肺の氷「氵月+上:八、下:天」をおおい、灌袋で肺に前の汁を一杯に入れるのが大事である。宴会の席でこれを割ってわける。 (「食経」 中村璋八・佐藤達全)
樽酒(たるさけ)
樽酒を取しか、二三人寄合(よりあひ)てはなしけるハ、ヲレハ八千代(やちよ)を買(かつ)た。甘(あま)いと云。〽ひとりハ、ヲレハ若竹(わかたけ)を買(かつ)た。辛(から)いといふ。〽行過(いきすき)ナ下女聞(きい)て、けしからぬ。女郎ヲ買に、(三十九ウ)ナメテ買(かい)なさるそふだ(「稚獅子」 武藤禎夫・編)
あぶないチャンポン
焼酎→日本酒→ワイン 翌朝地獄
平和なチャンポン 翌朝スッキリ
ビール→日本酒→焼酎(「晩酌パラダイス」 ラズウェル細木)
食味文化人
「牡丹雪のやうに溶け」るバサシの名セリフが丸谷さんなら、吉田健一さんにも、かなり名表現はある。この人は、酒も食べ物のうちと書いているが、まったく、食い物も、酒も同等に扱っているところが面白い。さて、吉田さんの名セリフは「上等な酒であればある程、最初に口に含んだ時の味は真水に近いものなのだ」とくる。どうもこの言葉は、なかなか考えさせられる。エジンバラで飲んだティオ・ぺぺのシェリーも、新潟の酒「今代司」も、吉田さんに言わせると、谷間の清水に近いのだ。酒にかけても、食い物にかけても、口うるさいことにかけては超Aクラスの吉田さん。飲むにしても、食べるにしても、銘柄がうるさい。吉田さん好みの特定銘柄きりお口に合わないのだが、人によばれ宴会などで、出された酒の肴はつまんでいるが、決して、うまい、まずいと口にはしないらしい。そういえば、吉田製の食い物随筆には、まずい、という字をあまり見ることはない。この辺は、英国紳士のこの人らしい見事なエチケットなのであろう。丸谷才一さんが、作家が書いた食い物の本の中から三大名著の一つにあげているのが、吉田さんの『私の食物誌』だ。この中にも、まずいという字は少ない。「羽越瓶子行」(『落日抄』読売新聞社刊)は、新潟と酒田へ、河上徹太郎さんと二人で行ったことを書いた飲み食い旅行記だが、これは心にくい名文である。それには、卓子いっぱいに並べられたご馳走も、あまり頭に浮んで来ないで飲んだ日本酒(「初孫」)が旨かったことが頭に浮んでくるとか、部屋にどんな大家の名作だという絵がかかっていても、酒の肴にしていたい気持ちになれる絵はなかなかないとか、書かれているが、これが食味文化人吉田さんのユニークなところだ。それでいて、乾した蛍烏賊の土産は、客に自慢して出せる、と味の方も、キチンのいきとどいているのである。それに、この種の文で、地方の店の名をあげると、たちまち人が押しかけてその店が迷惑するのが最近の定石とばかり、吉田さんは、酒の名は書いても、店の名は書かない。まったくいきとどいた食味紳士である。(『週刊読書人』昭和四十八年一月二十二日)(「作家の食談」 山本容朗)
あかねいろ
二十九の秋、私は侍従になった。その翌年の正月だから、三十になるやならず、菅平さんの年ごろのこと。元日の昼、先輩がついでくれた。そんなに飲ませると、まっ紅になって使いものにならなくなるからといったのに、なに正月だもの、かまうもんかという。結果は定石通りの灼熱の色。なにしろ勤めてまだふた月にしかならない今参りのことだから、フロックコートを着て、いまのいままで手にしていた朱盃そのままの色になって、侍従候所の片隅に、身も世もあらずちぢこまった。そこへなんと陛下が出御になった。こっちもびっくりしたが、陛下もお驚きになったにちがいない。なまやさしいことでは御覧にもなれない不思議な色と化して、新米の侍従がコチコチになっているのだもの。古参の侍従とお話になりながら、時々チラチラと目をおそそぎになる。身の置きどころもないとはこのこと。「まあこの色を御覧あそばせ」なんて解説まで付けられて。そんなにたくさん飲んだわけでもないのに、その雰囲気を人一倍好むものである。奈良漬にも、とか、笹の葉の露にも、とか、そんなしおらしい下戸ではない。酔いつぶれた思い出もないし、宿酔に苦しんだこともあんまりない。いたずらに楽しく、うたかたの如きことを口走り、笑い過ぎて、あくる日、あたら美声が枯れはてたのはいくたびか。大の男がまっ紅になって、のたうちまわって笑っているのなんて「さま」にもならないわけなのだが、下戸か上戸かと迫られれば、まあまあ上戸のたぐいででもあろうか。もし紅くさえならなければ、盗み酒はいくらでもできる。もったいないからそんなことはしもしないが、五、六本飲んだからといって、随筆の一本や二本書けないこともないし、ちょっとした演説ぐらいぶてないわけでもあるまいに、なんにしてもあまりにも紅くなるものだから、第一、世間が信用してくれないのである。(「余丁町停留所」 入江相政)
マキノ親父
《金色夜叉》のどこがいけないかといえば、例の熱海の海岸の場面で貫一がお宮を蹴とばし「今月今夜のこの月をボクの涙で…」とやる、あれがけしからんというのである。「男が女性に暴力を振るうのは男尊女卑の封建思想につながるもの。よってカッとせよ」だった。「そんなアホな」とマキノ光雄は尾崎紅葉の名作であることを説明すれば、アメリカさんも納得するだろう…と、兄貴のマキノ正博(現・雅裕)監督の尻を叩いて撮影はすでに進められていた。「えらいこっちゃわ。どうでも殴る蹴るはいかんといいおる」京都・木屋町の料亭の座敷で私がマキノ親父にインタビューしている席に光雄プロデューサーがとびこんできた。分からず屋のGHQは熱海の海岸をカットしろときかないというのである。「そんなアホな、それじゃ《金色夜叉》にならんでえ」敗戦国の貧しさを、進駐軍からたぶらかしてきたジョニーウォーカーでまぎらしていたマキノの親父は、もう足もたたないほど酔っていたが、「こうなったら、熱海の海岸で貫一がお宮をしてしまうしかないのとちがうか」これには、さすがの光雄プロデューサーもあわてた。いくらなんでも貫一お宮に“青カン”させるなんてわけにはいかない。「かまへん、アメリカさんの気に入るように二人で接吻させたるわ。熱海のキッスや」マキノ親父の反骨精神は酒の勢いで燃えあがり、前代未聞の《金色夜叉》が出来上がった。熱海の海岸とおぼしきあたりで別れのキッスを演じさせられたお宮は、当時マキノ親父の夫人だった轟夕起子、貫一は上原謙だったのである。風が吹いたら飛びそうな痩身で小柄なマキノ親父だったが、その硬骨な抵抗精神とチャレンジャーとしての情熱は人一倍だった。(「いい酒 いい友 いい人生」 加東康一)
子どもはどんな理由でお酒を飲むのか
私達の調査の質問項目の中に、「どんな理由でお酒を飲みますか」という質問があります。中学生においては、おいしいと思うからという答えが一番多く、四二%を占めています。高校生においてもその答えが一番多く、三七%を占めています。子どもがお酒をおいしいと思うのは実は不思議な現象で、「それがどうしてもわからない」と一人の女性から私は質問されたことがあります。多分その人は、お酒がおいしいものだと感じたことが一度もない人だったのだと思いますが、実は大人達の中には、そのような人がたくさんいます。それはもっぱら昔はお酒の味が大人向きに作られていて、子どもにはとても飲めないものだったからでしょう。中年の私達が子どもだった頃、甘酒やお屠蘇や梅酒、赤玉ポートワインは子どもにも飲めるお酒でした。それでも、それをほんの一口飲ませてもらえるのは一年に何回もありませんでした。しかし今は口あたりのよい、子どもも抵抗感がなく飲めるお酒が多量に出まわっているのです。一時爆発的にはやったドライビールも、口あたりがちょうどコーラを飲んだ時の炭酸ガスの刺激に似ていて、私などは、あれはコーラになじんだ若い子にはやらせようとしたものだと考えているくらいです。次に多いのが、高校生では「盛り上がったから」という回答です。これは仲間同士で飲みに行ったり、コンパや打ち上げで、ワイワイいいながら飲んでいる姿が目に浮かぶようです。-
私から見てさらにリスクの高い飲み方があります。「悲しかったり、寂しかったり、つらかったりした時に飲む」と答えた高校生は一一%存在し、「緊張したり、神経質になったり、困ったりした時に飲む」と答えた生徒は二%に存在し、それを合計すると一三%に及びます。つまり、こうした子ども達は情緒的に混乱した時に飲む子どもですが、そのような子ども達が一割以上に及んでいることです。これは精神安定剤としてアルコールを使うことであり、こうした飲み方は、仲間で飲むにせよ、一人で飲むにせよ深酒になることは明らかです。(「子どもの飲酒があぶない」 鈴木健二)
うわさ話は美味しい肴(さかな)
先日、粋な料理と酒を出す隠れ家みたいな酒場で、例年になく早い山菜と純米酒を楽しんでいたら…。店長が「土倉さん、先日の宴会はこぢんまりとやったそうですな」と言う。びっくりした。「あれ、別の店なのに、なんで知っているの?」そう、私の生息する界隈は、とっても情報伝達が早いのだ。だれがどこでデートしたとか、だれが酒を飲んで寝ぼけていたとか、やたらに早い。恐ろしくてうかつなことは言えないし、落ち着いて酔っぱらえやしないのだ。たとえば一次会で酔っぱらって大騒ぎしたら、三次会へ行くころには「土倉は今日は酒乱だ」とリアルタイムでうわさになるほど早い。それが後日になると「土倉はいつも酒乱だからそばに寄らない方がよい」と尾ひれが付く。まあこの程度はご愛きょう。でも、私はこの情報伝達組織?をひそかに「〇〇界隈ネットワーク」と呼んで恐れている。いつも紳士的におとなしく(自分で思っているだけだが…)酒を飲んでいるのは、このネットワークを意識してのことなのだ。しかし、酒を飲んでいると、人のうわさはおいしい肴になる。よりおいしい肴を求めて店を徘徊(はいかい)する。でも私がいない場所では結構、肴にされているんだろうなあ。(「さしつさされつ」 中田耀子・土田裕之)
焼酎麹
実は気温が高いと、酒を腐造させる腐敗菌や有害な雑菌が活発に活動するので、日本酒造りはそれらの微生物があまり活動しない冬の間だけ行われる。いわゆる「寒仕込(かんじこ)み」である。ところが焼酎造りは、一年中気温が高く、暑い沖縄や九州南部の地方で、年間を通じて行われている。なぜそんなことができるのだろうか。それは、今述べた、非常に高い醪の酸度がそうさせているのである。そのメカニズムは、一次仕込みの原料である焼酎麹に含まれている多量のクエン酸の防腐効果に関係しているのである。焼酎用麹菌は、世界中でこの日本の焼酎製造にしかみられない特殊な性質を持っていて、蒸した米に繁殖して米麹をつくる際、多量のクエン酸を生産し、それを米麹に置いていくのである。日本酒用の麹菌はこの性質がないので、日本酒用の米麹を口に含むと大変に甘く、甘酒などという美味な飲料も造れるが、焼酎麹を口に含むと、そのあまりの酸っぱさにびっくりする。一次仕込みの際、容器に水と米麹を入れると、麹中からクエン酸が溶出してきて酸度が二〇~二五ミリリットルにもなり、pH(水素イオン指数)も三・一~三・三という強い酸性状態を示す。ところが、自然界に生息していて空気中を浮遊している有害な腐敗菌は、pHが四・〇以下になると増殖が困難となり、生息できない。その上、都合のいいことに焼酎用酵母は、そんな低いpH領域でも純粋・健強に生育することができる特性を持つので、雑菌侵入の心配もなく、アルコール発酵を営む焼酎酵母だけを純粋に培養することができるのである。(「銘酒誕生」 小泉武夫)
吟醸古酒の発見
だが、東力士には古い吟醸酒が残っていた。どうしてかはつまびらかではない。社長の島崎利雄氏の話から類推すると、四五年の酒は品評会で好成績を収め、他の酒と混ぜてしまうのはあまりにも惜しかったようだ。そこで杜氏に「オレが飲むから取っておけ」と命じる。計算では年間に一升瓶の一〇〇本くらい飲める。だが現実には外で飲むことが多く、ほとんど減らない。次の年も良かった。前年のを取っておけといった手前、この年のものも取っておかせた。貯蔵量は膨らみ、杜氏はそれらの置き場に苦労していたほどであった。そこに出入りしたのが飲んべえ設計屋の私。好奇心も旺盛である。この現場は交通の便が悪い。打ち合わせが終わっても適当な列車の時間までぶらぶらしているしかない。それを見かねて島崎さんが「こんな酒があるんだが」と出した。それは私が知っている吟醸酒とは別な品質であった。香りも味も枯れた感じで飲めるのだ。私は大いに気に入ってしまった。酒がもっている余計なものを削ぎ落とし、香りも味も一点に凝縮している。酒をゆっくりと味わうと、その中に封じられていた時間がゆるりと溶け出す。その貴重な体験に、酒を褒める言葉もなく無言で飲み進んだ。小一時間ぐらいで二人で一本空けてしまった。酩酊の気分もすこぶる良かった。そしてそれが現場通いの日課になる。仕事をうまく切り上げ、酒を飲む時間をちゃんと残した。次のは別な酒が出た。その次もその次も別な酒。それがそれぞれの変貌、変態を見せてくれる。最初の枯淡を感じたものは最も古いものであり、貯蔵年数が変わると、あるものは媚態を、あるものはくすぐりを、懐かしさ、暖かみを覚えさせるものもあった。もって生まれたものと、時を経て身にまとったものとの複雑な化合があらしめたものらしい。これはたいへんなものを発掘してしまったと思った。(「「幻の日本酒」酔いどれノート」 篠田次郎)
防衛大学校の酒
たとえば、長髪、茶髪、ピアスはダメ、夜間外出ダメ…そして酒については、当然のごとく防大構内は寮内もふくめて飲酒禁止となっている。ところが、その防大の購買部で、日本酒が売られているのである。なぜ、構内では飲めもしない酒を、わざわざ売っているのか?この矛盾する妙な事情を説明すると、話は一九九二年にさかのぼる。この年から、防大が男女共学になったことは先に記したとおりだが、その際、何か記念品をつくろうと、防大のいわば“親”にあたる自衛隊の購買部・防衛弘済会の発案で新潟の銘蔵元「菊水」に、その名もズバリ「防衛大学校の酒」という銘柄の日本酒をつくらせたのだ。ビンのラベルには若い男女のイラストを描き、防衛大学校のネーム入りの箱におさめた特注品である。その酒が自衛隊関係者の間で大好評だったため、防衛弘済会は、以後、毎年、つくることにした。また、初年度は防衛庁と各自衛隊の購買部だけで販売したが、「銘柄が『防衛大学校の酒』なのに、防大で売らないとはおかしい。学生は飲めなくても、入学式と卒業式に訪れる学生の両親向けに…と、防大内の購買部でも酒を売ることにしたというわけなのだ。(「酒のこだわり話」 博学こだわり倶楽部) '97の出版です。 自衛隊の酒
新政、秀よし、日の丸、
たとえば東京方面の酒通の間でよく知られている秋田市の「新政」。これを「しんせい」と読めば笑われてしまうが、本来はこう読むのがホントだったことを知る人は少ないだろう。明治維新政府の施政大綱の中にあった「新政厚徳」がその由来。後に「あらまさ」と改めた。このほか、おもしろい名前の由来では、中仙町の「秀よし」もある。元禄二年(一六八九)創業で、当初の銘柄は「初嵐」。当時藩内では「清正」という酒がよく飲まれていた。ある時、藩主佐竹侯に酒を献上したところ、ことのほか気に入られて「清正よりうまい、清正の上だから秀吉にせよ」と、酒銘をいただいたのが由来。〽銘酒秀よし だれが名をくれた 出羽秋田の 佐竹様 こんな酒屋唄が残っている。増田町の「日の丸」も酒銘としては変わっている。元禄時代創業の古い酒蔵だが、日の丸の旗にあやかって明治四十二年に商標登録したという。(「あきた雑学ノート」 読売新聞秋田支局編)
飲酒楽 酒を飲む楽しみ 聶夷中
(一) 日月 事有ルニ似タリ 月日(つきひ)は仕事で忙しさうに
一夜 行キテ一周ス 一夜運行して一周する
草木猶ホ須(すべから)ク老ユベシ 草木でさへも老いねばならぬのだから
人生 愁無キヲ得ンヤ。 人の生(よ)に愁無きことが出来ようか。』
(二) 一飲 百結ヲ解キ 一たび飲めば胸の結ぼれを解き
再飲 百憂ヲ破ル。 二たび飲めば百の憂ひを破る。
白髪ハ貧賤ヲ欺(しひた)グルモ 白髪(しらが)は貧乏人を虐(しいた)げても
粋人ノ頭ニ入ラ不(ず)。 粋人の頭には生えはしない。』
(三) 我願ハクバ東海ノ水 我願はくば東海の水が
尽ク杯中ニ向ツテ流レンコトヲ。 尽く杯中に向つて流れ込まんことを。
安(いづく)ンゾ阮歩兵ヲ得テ 何とかして阮籍のやうな酒豪を友とし
同ジク酔郷ニ入ツテ遊バン。 共に酔郷に入つて遊びたいものだ』
◎作者聶(テツ)夷中は咸通十二年(西紀八七一)の進士である。 〇阮歩兵 魏の阮籍。官は歩兵校尉に至る。竹林七賢の一人。酒を愛し、常に酔にまぎらして時世の危険を免がれた。(「中華飲酒詩選」 青木正児)
会津娘 あいづむすめ 高橋亘(わたる)さん 高橋庄作酒造店(福島県会津若松市) 6代目蔵元・杜氏
昭和47(1972)年、5代目の長男として生まれる。東京農業大学農学部醸造学科卒業後、東京の酒販店「味ノマチダヤ」、保坂酒造店(現・武勇)で学び、平成8年に藏に戻り、自営田で本格的な酒米の有機栽培を始める。平成10年から製造と栽培の責任者。会津高校在学中には伝統の白虎隊剣舞を舞い、吟者も務めた。趣味は二輪車。池波正太郎、布袋寅泰、沖縄民謡を愛好。
語録 「テ-マは“土産土法(どさんどほう)”。地元会津の米、人、手法で酒を造る」 「有機栽培だからといって酒の味が劇的に変わるわけではない。変わったのは僕の意識。目指す味に合う米を選ぶのではなく、目の前にある可愛い米にとってベストな醸造方法を考えるという思考に変わったのです」
最も自分らしい酒 「会津娘」特別純米酒 無為信(むいしん) 五百万石(会津有機栽培) 精米歩合60%
著者コメント:「会津娘の原点であり到達点」と高橋さん。素直で充実した旨味やほっこりとした温かみ、清潔感があり惣菜の味を生かす。日常の中で上質感を味わえる究極の1本。
著者の視点 伸びた背筋、短く刈った髪、農作業で日に焼けた肌から真っ白な歯がこぼれる。折目正しい清廉な日本男児である。市街地から近い場所にありながら、酒蔵が田園風景に囲まれているのは、先代の働きで市街化調整区域に認定されたから。環境問題に意識の高い父、庄作さんと共に“土産土法”を実現すべく邁進。使う米の9割が地元産。(「めざせ!日本酒の達人」 山同敦子)
飲中八仙
知章
井戸ばたの 茶椀酒にて 馬の耳 風ふきおくる 猪の牙の舟
沙陽
酒の香の 匂ひくるまの かうじ町 十三丁や よだれたらさん
左相
聖人の たのしみ酒も はかりなく 日には 十貫文の入用(にふよう)
宗之
盃の ひかりもさすが 男へし くねりまはらず 皎(かう)としてたつ
蘇晋
さけをのむ 長斎坊主 めでたしと 布袋(ほてい)一ふく 床にかけ物
李白
勅諚(ちよくぢやう)と いつても一斗 詩百ぺん 百ぺんよべど しら川夜舟
張旭
柳髪 すゞりの池に ひたしつゝ むかふ旭の からす羽の文字
焦遂
五斗/\と どもるどもりも 銭ごまの はだしで逃る くだをまき舌(「千紅万紫」 大田南畝 浜田義一郎編集委員代表)
とんぶり(トンブリ、長イモ、ノリ)
ナガイモ 千切りにする
とんぶり 湯通ししてざるにあけ水分をしっかり切っておく
ナガイモの上にとんぶりをふりかけ、針のりをおく
しょう油と化学調味料で食べる。カラシじょう油、ワサビじょう油でもよい。(「酒肴のネタ本」)
大吟造り
大吟造りが始まると、藏うちの空気からして違ってくるわ。それぞれ、普通酒とか本醸造酒とか担当もあるわけだんが、そういうがんでも、手が空いてれば、大吟のほうも手伝わんばならん、だすけ、藏全体の空気がぴりぴりしてくるのさね。大吟が始まると、毎日、毎日、蔵人の頬がこけてくるのがわかるというぐらいで、体力があるはずの若い衆でもよれよれになってさ、そんげな酒が大吟だ。だから、何本も造れんのさね。二本か三本も造ればくたくたになる。ほんとに他の酒の一〇倍も二〇倍も手間をかけ、神経をつこうてつくるのさ。大吟は。とにかく酒を造るということだけを考えて造る酒なんだ。酒蔵も商売でやっているんだから、売るということを考えて酒をつくらんばならんわけだが、大吟だけは、そうではないんだ。(「杜氏千年の知恵」 高浜春男)
文党根岸派
前にも述べた如く、地理的関係から自然に結成してゐた文党根岸派を、硯友社の結盟に対抗して現はれた文士の朋党のやうに見るものもあるが、それは全然当時の事情を知らない徒輩の観察で、彼等は、決して党を結び、勢いを文壇の一角に払うなどとする野心なぞは少しももつてゐなかつた。聚まつた人柄からいつても、罪のない饗庭篁村や、洒落な鈴木得知や、高踏的な幸田露伴、高橋太華、宮崎三昧等の面々で、たゞ相互の住宅が根岸を中心に、下谷、谷中方面に点在してゐた関係から、自然往来が頻繁になつたのによるのであつた。寧ろかう頻繁に往来した所以は、互ひに愛好する酒が結ぶの縁になつてゐた、と見る方が正しいかも知れない。根岸派と称ばれた文人連の員外団として、川崎千虎の如き洒脱な人物や、天心の如き詩人肌の豪酒家が加はつてゐたので一党は常に酒を蒙つてたあいもなき清談を楽しんでゐた。彼等の会合する場所は、いつも鶯渓の伊香保か、庚申塚に近い音無川畔の鶯春亭で、殆んど連日連夜に亘り、飲み続けてゐたやうである。それも、多く天心が主動者となつて、彼等の誰彼を誘い出す場合が多かつた。必ず酒の席に誘ひ出されてゐた饗庭篁村の酒量は、天心の十分の一にも足りなかつたが、酔ふと、たあいもなく童心に戻るといふ酔ひ振りであつた。天心は、童心に返る篁村の酔態を喜んで、必ず酒を酌む席上には、『饗庭御前』と書いた手紙を飛ばし、その出席を誘つてゐた。(「父天心」 岡倉一雄)
千鳥
ゆきかへり 友よびかはし なき上戸 顔もあかしの 浦千鳥あし 臍穴ぬし
眺め侍るとて
ぼうだらに なりて海辺を ながむれば 月かげさむし 宵の口塩 四方赤良
朝日さす 人もなければ とりもちの さほの河原に ねぶる水鳥 奈良早起
雪中酒宴
盃の 手もとへよるの 雪の酒 つもる/\と いひながら飲む もとの木網
神楽
禰宜どもは 寒さしのぎに かん酒の 匂ひかぐらの 下つゞみ打つ 加陪仲ぬり(「徳和歌万載集」 野崎左文校訂)
玉子酒の味
私は、例の食満(けう)南北から、夙(つと)に「うまいものの極みというものは、遂に、鰒に止(とどま)るなア…」とすすめられていたが、その機会がなかった。というより、鰒とは、やっぱり十代の好みに遠いものがあったのではないか。二度までも、博多の正月に行きあいながら、しかも鰒の席へ招かれながら、私一人だけ、鯛の刺身か何か食べていたのは、天邪鬼(あまのじやく)というより、十代の好みでなかったからではあるまいか。怖いというのではない事は、白子酒をふんだんにのんで、それが玉子酒の味にすぎなかったのが、のちに白子の旨さを知るにおよんで、今でも惜しくてならないのだから。-つまり子供だったのである。(「味の芸談」 長谷川幸延)
嫌酒薬
初対面の時、たまたま氏の故郷の酒が手許にあったのでプレゼントに持参した。「敏馬(みぬめ)の浦(うら)」というその酒は兵庫県は灘の「沢の鶴」の製品で、酒蔵のある西郷(にしごう)の海に面したあたりの地名に因んだものだった。氏は懐かしげに、「幼い頃は、この敏馬のあたりでもよく遊んだものです」といったものの、目下断酒中とのことで、そこでは口にせず提げて帰られた。後で分かったのだが、その時に氏は嫌酒薬を服用していたらしい。この薬にはなんでもアルコールを分解するのを押しとどめる作用があるそうで、嫌酒薬を飲んだ後でアルコールを口にすると、それこそ七転八倒の苦しみが起こるとか。薬そのものは無味無臭で水のようなものながら、これをほんの三ミリリットルほども服用しておけば、丸二昼夜ほど効果が持続するらしい。野坂氏はかつてある外国人から、嫌酒薬を飲んでいると突然死に至ることがあると聞かされたことがあった。「嫌酒剤とも抗酒薬ともいわれるシロモノを服用、その効験にたよって、酒を断つのは危険、突然死をまねくおそれがあると記したが、この危険性を教わったとき、実に暗然たる思いとなった。そもそも飲酒歴五十年。まずその四十年間はなんとかまともな部類であると、自分では考えていた。しかし、五十半ば過ぎて、肝臓がおかしくなる、心臓に変調を来すなんてことより、飲めば、自分ではさして酔ったつもりではないのに、廃人風となって、もとよりヘロヘロしているときは気がつかない。翌朝、大体が記憶を失っているが、あれこれ断片をとり集め、また一緒に飲んでいた御連中の話をうかがうと、これはもう人間じゃない。しかし、もはや自己嫌悪に陥るだけの、理性というか自制心すらなく、また飲んでしまう。これは病気に違いない。だから、薬を用い、どうにか少しずつ人間らしくなりつつあると、自分では安心していた。ところが副作用としての突然死に至ることがあるときかされて、これはもう副作用の範疇を超えている」(『大往生-あれこれ思うこと』東京新聞出版局)と述べていた。さらに後日、その道のある権威から聞かされたところでは、「かの薬の副作用は人によって反射神経が鈍くなるくらいで、突然死はない。安心して服用して酒を断ち、いい小説をお書き下さい」と笑いながら教えられたという。かくして氏は時折、この薬を用いていて、私と麻雀卓を囲んだ時がその薬の服用中だったのである。(「知って得するお酒の話」 山本祥一郎)
清酒・李白
中国の詩人で「酒中の仙」と自ら称した李太白にあやかって酒銘を「李白」と名づけ、近年とみに名を挙げているのが松江市石橋町の醸造元、李白酒造有限会社である。「李白」を醸す田中家は、明治十五年酒造りをはじめた。創業の時から備中杜氏、道広亦造氏を迎え、四十五年の長きにわたって誠心誠意の酒造りをやってもらい、松江に「李白」あり、と世間に名声を高めてきたのである。道広杜氏は、岡山県浅口郡寄島町の出身で、その酒造技術の優秀さで多くの後進を育てた功績を高く評価されて、寄島町の八幡神社の境内に顕彰碑が建立され、その功績を讃えられている。昭和二年、道広杜氏は六十五歳で勇退することになった。その時、李白酒造は千五百円という大金を送って、その労をねぎらっている。備中杜氏によって基礎を作った李白酒造では、道広杜氏のもとで育った出雲杜氏(旧秋鹿(あいか)杜氏)が、その後を継いできた。「李白」という酒銘は大正十五年、松江が生んだ政界の巨星、若槻礼次郎(一八六八-一九四九)によって命名された。若槻礼次郎は、明治、大正、昭和と激動した政界にあって、常に中枢を歩きつつけ「真の平和愛好者」といわれ、二度も内閣総理大臣を経験した人物である。故郷の松江をこよなく愛した若槻礼次郎は、詩を愛し、酒を愛し、「李白」を酌みつづけ、昭和五年、ロンドンで行われた軍縮会議にも「李白」の菰樽を持参し、朝夕愛飲したという。(「酒の旅人」 佐々木久子)
絶景と言うは樽肴(たるさかな)ありてこそ
★「酒なくてなんのおのれが桜かな」に相通じる一句。
ないとこつもりの高天原(たかまがはら)
★酒席でお積りのさい、高天原の神主が鈴を振るように、おもむろに徳利を振って酒を飲み終えたと告げる仕種。→おつもり
濁り酒は髭に付く
★転じて、粗末なものには欠点がある、と。(「日本の酒文化総合辞典」 荻生待也)
明智日向守
明智日向守(ひゅうがのかみ)の逆心は、本心から起こったのではない。その原因はみな信長公が作られたことであるという。あるときの酒宴に、七杯入りの大杯を柴田勝家が持っていたのを、信長公が、「明智へさせ」とおっしゃった。明智は、下戸(げこ 酒嫌い)なので、「いかにしてもいただくことはできません。お許しくださいますよう」と申し上げる。信長公はご機嫌をそこなわれ、「是が非でも飲め」と、明智日向守を押し伏せて、こらしめられた。光秀は、是非なくその大杯で酒を飲んだが、もともと下戸であるから、前後不覚に苦しみ、錯乱して、まるで病人のようになった。(「翁草」 神沢貞幹原著 浮島康彦訳)
四毒(1)
ある時、ユトクと弟子たちは激しい悪寒と下痢を伴う病(マラリヤ熱)に倒れたネパールのハダル王から往診を依頼された。招待状を受けたユトクが弟子たちとともにネパールに着くと、彼はそこでネパールの医師シュリー・シンハに会った。二人の医師が王の脈を診た後、ユトクが言った。「あなたがたネパール人はこの病気を熱性であると診断しますが、われわれチベット人は寒性病として処置します。病気になる前に、王は食物とともに塩を摂ることを制限されていたので下痢をしたのです。ですからこれからは、塩を少しずつ食事に加えてください」するとネパールの医師が言った。「塩はいかなる病気にも合いません。患者は四つの毒から遠ざかるべきです。四つの毒とは、一、患者の骨を傷つける塩、二、患者の肉を傷つける酒、三、患者の皮膚を傷つける太陽光線、四、患者の体力を奪う女性です。もし人がこれら四毒なしですませたならば、その人の体力と健康は増進され、病人はすぐに回復するでしょう。その人の寿命は太陽や月の寿命と同じくらいになり、その体力は野人を凌駕し、そしてその動きは風よりも速くなることでしょう。(「ユトク伝」 中川和也訳)
吉原小歌鹿の子
一さす盃は三世の機縁(きえん)、二世まで契るさすぞ盃
一うつ〻か夢か幻の身をもちながら、遊べや歌へ酒(ささ)飲みて(「近代歌謡集 吉原小歌鹿の子」 塚本哲三編纂)
玉子盃、熊がへ、武蔵野、吹よせ
〇『元禄曽我物語』、「友禅絵に白うるしの玉子盃」。『世帯形気』に、「杯は国春といへる女筆のまき絵、十かへりの松に鶴亀をかゝせ」。『誰袖海(たがそでのうみ)』、「むさしのはおくゆき浅し。笠さかづきはかさびく也。とかく熊がへ」といへり。これをみれば武蔵野は大なれども浅き也。くまがへとは、編笠にあり。其形したる也。落葉色々もやうに付るを吹よせといふ歌より、吹よせといふ盃ありとか。(「嬉遊笑覧」 喜多村筠庭)
御酒御酒御酒
それで、その焼鳥屋に入ったことは、
御皿 小鳥焼 大根卸 御酒
によって明らかである。次行に「同」の字が四つばかり並んでいるのは、一皿では足りなくて、あるいは、その日の鶫(つぐみ)が殊の外うまかったので、追加を注文した意味である。これには御酒の追加が伴う。その次に、中略と書いてあるのは、これは註釈する必要がある。要するに、焼鳥屋でお代りを頼んだまでははっきりしているが、それが重なるうちに、あとはどうしたかよく解らなくなったということなのである。そういうふうになるまでそこにいたのだから、かなり長時間その店を出ようとしなかったと僅かに推定されるので、そのあとに直ぐに家に帰ったとも思えない。恐らく、また何軒か廻ったに違いないとすれば、御酒御酒御酒、だけは確かである。その揚句に、電車を乗り越さなかったとしたらさいわいであると、我ながらこの献立表を見て思わざるを得ない。これが東大寺での宴会だったならば、坊さんがこっちの足許を観察して、その晩は泊めてくれただろうし、その点、都心から二時間もかかる所に住んでいるものの結解料理は何と言っても不便である。「あまカラ」を読まなくても、この頃は東京に帰りたくて仕方なくなっている。鎌倉にもビヤホールと支那料理屋と焼鳥屋位はあるだろうと言うものがあるならば、それは鎌倉のような文化都市の性格を知らない人なのである。(「続酒肴酒」 吉田健一)
少し甘めの酒を
ここのところ、そんな米そのものの甘味を美しく表現した酒が増えている。明るい甘やかさ、ふっくらふくよか、ふわりと包まれるようなやさしさ、優雅な煌めき、ぐっとくる力強いパンチ、穏やかな余韻。それぞれに個性は異なるものの、透明感や軽やかさがあり、べたべたとしたしつこさはない。そして、旨いっ。一方で辛口と呼ばれる酒も、一世を風靡した「淡麗」ひと筋から多様化。味わいのなかに程よく甘味を含みつつも、すっきりとしたキレの良さで魅せる技があり、これまた、旨いっ。すなわち、「辛口の酒を」と言い切ってしまうのは、幸せを逃しかねない注文なのだ。ちょっとだけ勇気を出して、「少し甘めの酒を」と言っていただきたい。新たな至福への道が拓けるはずである。(「ニッポン「酒」の旅」 山内史子)
美人酒、妖艶な美女
ひところ、広島の酒味は総じて甘口の“おんな酒”と評された。けれど甘く感じる酸味も、味に深みをもたらす大切な要素。美酒の味わいには欠かせない。軟水の仕込み水を使うと発酵がゆっくり進み、ミネラルを含む硬水の仕込み水だと発酵が速い。前者は甘口の“おんな酒”。後者を辛口の“おとこ酒”と呼ぶ。土佐の淡麗辛口の酒に“おとこ酒”を冠することがある。けれど僕の知る大手酒造会社の酒造りは広島杜氏(とうじ)によって醸され、しかも仕込み水は軟水。本来なら広島と同じ甘口の“おんな酒”となっても不思議はない。となると、“おとこ酒“”おんな酒”を区分けする基準は曖昧(あいまい)なのかもしれない。酒は、その土地の風土、作り手によって多種多様の味わいを持つ。僕も飲んだ酒味のイメージが膨らむと、擬人化して評することもある。たとえば新潟県の口当たりのすっきりした酒は“美人酒”、福島県の旨口(うまくち)の地酒を“妖艶(ようえん)な美女”といった具合だ。(「酒は人の上に人を造らず」 吉田類)
<割烹>
小料理屋に比べ、割烹は判別しやすい。まず、「割烹」と名乗るのが普通である。店頭に提灯をぶら下げているとしたら、割烹は赤ではなく白い提灯を使うことが多い印象がある。一般的に、普通の赤提灯に比べ敷居も値段も高く、それが店の外側からでも一目瞭然である。高級感を表すのにきれいな上質の縄のれんを用いる。布のれんの場合は定番の紺色の代わりに白色やくすんだ淡い色のものが多く、しかも生地には明らかに高級な素材が使われている。「当店は何においても品質と品格にこだわっておりますので、ふさわしいお客様のみに入店していただきたい」と言わんばかりの態である。店内は小綺麗で、照明は柔らかいが明るく、健全な雰囲気を醸し出している。カウンターの内側では、ピシッとした白い調理服を身に着けた板前が背筋を伸ばし、入店する客を歓迎する。彼はさしみや一品料理などをこしらえ、のれんで仕切られた奥の厨房では、別の店員が焼き物や天ぷらなど火を使う料理を作っている。内装や外装に金をかけているのみならず、割烹は原則として既製の料理は一切使わず、また一品一品、相当に手の込んだ料理をこしらえるだけに、値段もそれなりに張る。赤提灯に比べ、カウンターの客席は間隔が広く、ゆったり座れるようになっているから、いっそう高級感か醸し出される。さらに、座敷や、ふすまで仕切られている個室がある店もめずらしくない。合席や、詰めて座らなければならないような<共有>部分の多い大衆酒場とは対照的に<私有>の味わいに重点がおかれるのが割烹の特徴のひとつだと言えよう。以上は、私の限られた割烹体験を踏まえた印象論に過ぎない。ところが、割烹の中には、やや高めの居酒屋とさほど値段が変わらないのに、大変美味の酒とつまみを丁寧に出してくれる店もある。しかも接客姿勢も意外に気さくだから、懐に多少余裕があり、落ち着いた環境で一流の板前でなければ作れない料理を味わいたいとき、ごくたまにではあるが、割烹に入りたくなることもある。あるいは、ちゃんとしたコース料理をランチに出す割烹に行くという手もある。(「日本の居酒屋文化」 マイク・モラスキー)
台所から裏まで
酒狂の父はどうかすると、真夜半ごろ、とつぜん布団の上に起直って、深い腕ぐみをしていたり、天井へ向かって独り言を吐く。そんなことがよくあった。貧苦と添乳(そえぢ)に疲れきって、くたくたに寝入っている母を「おいく、おいく」と、無理に呼び起こし「おれだってな、この儘では終りはせんぞ、いいか、意地でももう一旗上げてみせるつもりだ。貴さまあ、昼間おれにむかって、何かと、口ごたえしたが、そうこのおれを馬鹿にするなよ、この俺を」と、云い出したりするのである。父のそうしたひがみと、憎てい口は、自身の酒量が増してゆく比例に連れて、つのって行った。往々、子のぼくにさえ「馬鹿にするな」と怒ったり、「稼ぎを鼻にかける奴だ」と、忌み嫌う容子を見せた。ぼくには実際のところ、そういうふて腐れを父には露骨に見せたことが無いとはいえない。けれど母はそんな気持ちの人ではない所か、貧しくなればなるほど、この良人も子供も捨てて自分だけの生きる途などは考えもしない人であった。父がそんな嫌みを云って母を泣きもだえさせたり、無茶な暴言の限りを浴びせて、酒気芬々(ふんぷん)としているのを見ると、ぼくは自分も狂気しそうになり、幾たびか父を撲りかけたくなった。酒の上の心理状態などは子供のぼくに理解はできなかった。酒狂の父そのままを、父の人間と考えつめ、母と共に部屋の隅っこで慟哭した。いくたびか、ぼくはぼくだけで、よそへ出て生きる途を探しますと叫んで、台所から裏まで、跳び出したこともあるが、母に追いすがられて「英ちゃん、おまえが居なくなったら、このお母さんはどうしたらいいの」と云われると、ぼくは一歩も動けなくなってしまった。それでも父へは、ややもすると、母に代って、つい突ッかかりたくなった。そして母に泣かれて又、台所で足を拭き、家の中へ戻って、心にもなく父の前に謝った。そんな例は、前後何べんあったであろうか、今、思い出そうとしても思い出せないほど度々だった。(「忘れ残りの記」 吉川英治)
タイの加減酢かけ
作り方
①タイは薄切りにする。
②大根とにんじんはせん切りにして、サッと水にくぐらせる。
③加減酢を合わせる。
④皿にタイと大根、にんじんを盛り、加減酢をかけていただく。
材料(2人分)
タイ(刺身)…1人前 大根…10cm にんじん…1/2本
(加減酢) 薄口しょうゆ…大さじ1 だし…大さじ1 酢…大さじ1/2
このつまみにこの一本
奥播磨(おくはりま)品評会出品別仕込
大吟醸/兵庫 日本酒度…+5 酸度…1.5 価格…10000円(1.8ℓ)
●激戦区灘にあってここ何年も鑑評会金賞を受賞しているこの酒は、眉目秀麗、馥郁とした香りに四味のバランスが見事。上品なタイの甘味をほどよい酸味でいただく一品に。(来会楽)(「新・日本酒の愉しみ 酒のつまみは魚にかぎる」 編集人 堀部泰憲)
酒屋へ走る
酒屋へ急いで行く。近松門左衛門(ちかまつもんざえもん 一七二四年)の『薩摩歌(さつまうた)』に、<それ茶の下を、吹きはちゃっと酒屋へ、浄盤台(はしり)にみずがなさそうな。吸い物に何を醤(しよう)油か。いやざっと薄味噌(みそ)を、鯣(するめ)炙(あぶ)れ。>とある。「浄盤台(はしり)」は、清浄な盤(ばん)台(板台)。台所の流し。「走り」を掛ける。「吸い物に…」は、吸い物に何をしようか、しょうゆか、いやざっと薄みそをする。するめをあぶれ。(「飲食事辞典」 白石大二)
戦国(楚) BC二三九 酒。紹興酒の起原。『呂氏春秋』BC二五〇年比に会稽(現在の紹興)の酒の記事あり。(「一衣帯水 中国食物史年表」 田中静一)
人の顔色を見ない
酒がいちばんいいね。酒というのは人の顔色をみない。貧乏人も金持も同じように酔わしてくれるんだ 古今亭志ん生
結城昌治『志ん生一代(下)』(小学館)
古今亭志ん生(ここんてい・しんしょう)落語家。一八九〇~一九七三年。神田生まれ。落語界を代表する名人。大酒飲みで知られた。古今亭志ん朝は次男。
この人の高座(こうざ)を見たことがありません。一九七三年に他界したというから、私はそのとき十歳。まあ、仕方がないことなのかもしれませんが、間に合いたかったな、と思わせる名人であった、らしい。(「酔っぱらいに贈る言葉」 大竹聡)
一品料理屋
三田(政吉) いや同朋町です。池の端から松坂屋のある上野広小路を中心としたところですね。「伊予紋」という店が松坂屋脇にあったと聞いています。大きな料理屋です。それから左手のほうには「同花」という花屋があり、上野公園下に「山下」、こういう有名な日本料理屋がたくさんあった。
鈴木(三郎助) いまはみんなないんですか。
三田 いや「山下」は現在営業しております。それから「世界」という中級の店があった。ここは肉のすき焼き…。
鈴木 「世界」は聞いたことがある。
三田 上野同朋町の「花家」、「山下」、「世界」、そのほか終戦まであった「雨月荘」という中華料理店。当時は支那料理といってね、下町の支那料理のハイクラスだった。これらの店を俗に須賀一家といって上野の名家です。
鈴木 神田のへんにも色街があったんですね。
三田 あそこは幕府の講武所、武道修練の道場のあった所です。神田明神裏の崖下一帯です。今の花柳界は昌平橋を渡って上野池の端に向かって二百メートル行った左側の通り裏で、今でもうなぎの「神田川」があります。講武所で指南した人は、山岡鉄舟とか、高橋泥舟とかいう剣術・槍術の名手、この人たちが講武所の師範だった。学問は朱子学の宗家、林家の一党で、湯島聖堂、あれが幕府の学問所ですね。
鈴木 お詳しいですね。
三田 いいえ、幕末は尊皇攘夷で町道場も盛んで神田お玉ヶ池の千葉周作道場とか九段の斎藤道場には桂小五郎が師範代でいたことからもわかるように、幕府の公的道場が講武所だったのですね。
鈴木 そういうところの人が遊びに行って酒を飲むとき、どういう料理屋を?
三田 さあ、今でいう簡単な一品料理屋だったと思いますね。講武所のあたりは、昔からきちっとした花柳界だったわけですよ。前のNHKの会長の坂本さんの家が神田明神境内の、「開花楼」で、その下に「花家」という店もあった。(「友あり食ありまた楽しからずや」 鈴木三郎助対談) 三田は明治座社長です。
西荻窪「鞍馬(くらま)」
鞍馬の営業は午後四時までなので、平日に蕎麦屋酒を楽しみに行くのは、普通のサラリーマンでは難しいかもしれない。玄蕎麦から仕入れて脱皮と製粉を毎日行っているが、住宅街では深夜の作業が難しいので、この時間に閉めざるを得ないようだ。鞍馬で酒を飲み、最後に蕎麦でしめくくる楽しみを考えると、外出の用事を入れる、あるいは、休暇をとっても通う価値はある。特に女性が一人で昼から酒を飲むには、もっとも適した店とも言える。店主の吹田正己さんは機械打ちの町場の蕎麦屋をやっていたが、達磨・翁創始者の高橋邦弘さんに傾倒して小淵沢の翁に通い、手打ちの蕎麦の技術を高めた。最初はつなぎを二割入れていたが、あとからそば粉十割で手打ちをするようになった。西荻窪駅からほど近い商店街に鞍馬はたたずんでいる。角にある入り口の引き戸を開ければ、清楚で小綺麗なしつらえが目に入ってくる。そして、店内には大きな石臼が、これはわざとではなく、本当は裏に置きたいが、スペースの関係でやむなく客席近くに置いているとのこと。鞍馬は、あくまで蕎麦を美味しく食べるための地酒の提供というシンプルなサービスに徹している。鞍馬に行ったら、まずは四季桜、田酒、豊の秋などの地酒を、突き出しの焼き味噌をなめながらちびりと飲(や)ることになる。この焼き味噌は味のバランスがよく、杯が進む。お酒を追加すると山葵のたまり漬けも提供される。こちらもきりっとした味わいで、酒とよく合う。他に酒肴は置いていない。「蕎麦を食べていただきたいから」と吹田さん。鞍馬は女性客が三割と多く、大きい声の酔っぱらいは迷惑になるから居酒屋のような酒肴は置かない、という配慮である。でも、もう少し酒肴がほしいという客には、大もりの天麩羅だけを先に持ってきてもらうという裏ワザもある。最後の蕎麦の旨さは本物。最近、茨城県の農家から契約栽培の玄蕎麦をとるようになり、さらに蕎麦のレベルが向上した。この手間隙かけて栽培した蕎麦は甘みが強く、輪郭がはっきりしている。箱盛そばは細長い箱に盛られて提供される。その端正な姿を見て食欲が呼び起こされ、味わいと喉越しの感触に酔いしれることになる。おろしそばも秀逸。大根おろしの白とかいわれの緑、柚子の黄と彩り鮮やかである。以前は冬場の限定メニューだったが、人気が高いので通年メニューになった。大根おろしがさっぱりと蕎麦の旨みを引き出し、寒い季節には身体が温まる。酒を楽しみ、蕎麦を味わい、ささっと切り上げる。鞍馬は、そんな江戸の粋を意識しながら楽しむには絶好の店である。(「蕎麦屋酒」 古川修)
魚屋宗五郎
「浄るり六歌仙は菊五郎の文屋の康秀妙を極め一日の観を縦(ほしい)ままにしたり、六歌仙は六人が出べきものなるべけれど、喜撰法師の件(くだり)だけが大いに行はれて文屋さへ出るのが稀だが今度は菊五郎三津五郎で文屋と喜撰を出したのは嬉しい事なり。」とあるので知れることは、六歌仙で文屋がそれまで閑却されていたらしいことである。三津五郎が死んだ時、聞いた話だが、菊五郎が、喜撰では三津五郎にかなわないと言ったという、久保田万太郎氏のお話、感に堪えたる芸談であった。私どもの見ていたころからは、いつでも二人の名優が並んで文屋と喜撰を踊り、いずれ劣らぬ妙技であった。そして私などにとっては、喜撰よりも文屋の方が面白い。本当に「一日の観を縦ままにしたり」で、ありがたい時代に生まれたものであった。竹の屋曰く「三津五郎の喜撰法師これ又他に類なき上喜撰、浮かされても夜も眠れぬほど面白し、大当り/\。」中幕は「小磯ヶ原」、「昔の小屋者と町人との交際(まじはり)違(ちが)ひをハッキリさせねば、お賤の嘆きも礼三の苦心も十分にあらはれぬ様だが、併し宗之助のお賤はよく演(し)てゐたり、菊五郎の心情(まごころ)も十分、わが子をいたはる気持も仕ぐさも十分にて、又五郎の千代松もあどけなくて可愛し。」二番目は「魚屋宗五郎」、樽を振り上げて花道へかかったときの六代目は本当に酒乱の相で凄かったが、竹の屋先生は酒乱はいけないが「少しくらゐは、ホイ病後の薬用(くすり)忘れては相成らずと惜い狂言を序幕だけで退いた」とある。(「芝居むかしばなし」 福原麟太郎)
暑気払(しよきばら)い
暑気を払い、健康を保つための焼酎(しようちゆう)や梅酒などを飲むことである。「暑気下し」ともいう。
為(な)すなくて強(し)ふ豪雨下の暑気払 本宮銑太郎
半眼に来信受くる暑気下し 渡辺七三郎(「俳諧歳時記」 新潮社編)
杜甫の酒
酒を飲む瞬間は、生きつづけたその人の到達したある一点である。そのひとの全生活のある一刹那、その刹那にはこれまでの生活のあらゆる影と光がただよい、未来の計画と希望と共に不安と恐怖は盃の中にさえ動いている。盃の中と外には、社会と天地が厳として存在し、酒飲む人の手先をも支配している。泥の如く酔った人のかたわらで、人は死に、国は亡び、友は去り、火は燃え、水は大地を蔽うのである。酒飲む人はまさにその場所で飲んでいる。その場所を意識するかしないかは、その人の性格によるけれども、その場所をはずし、席をあらためることは何人にも許されない。その場所を意識し、その場所のありていを自覚した人は、酒飲みつつも、その意識自覚をはなれ得ない。むしろその意識自覚が酒を飲ませるのである。杜甫の場合それはヤケ酒ではなく、ガッカリ気落ちしての酒でもなく、しがみつき、もりかえす自信のある酒である。生活の場所、おのれの生命の不安の場所に感じ入って涙もろくなる場合もあるけれど、杜甫の酒の詩にはジッと堪え得る理知のきらめきがあり、消え入るばかりの優しさと見せかけて、実は明確に一語一行を決定していく老練さが目立つ。酒を殺して飲むけちくささは全くないが、酒でつぶってしまえない眼光がキラキラして、泥酔といい酔歌といい酔眼という文字がかえって、人の良いだらしなさより、油断のならぬ強人の緊張を示すように想われる。 (「杜甫の酒」 武田泰淳)
三田佳子
若いころの三田佳子は、ひたすら悲しげで、ストイックな線の細い女を公私ともに演じていた。だから、三田佳子とはじめて飲んだときは、その根っからの明るさと、のりの良さには驚かされた。「ワッ、うれしい。もう一軒いくんですか。ホントに…」かなり盃を重ねても、ほとんど顔に出ないひとだが、飲むほどに酔うほどにキャッキャと騒ぐ三田佳子と六本木界隈を飲み歩いたのは、もう二十年も前だが、三田佳子とチークダンスを試みたときの、あのしなやかで吸いついてくるような感触は、それ以後、私を妙にくすぐるのである。(「いい酒 いい友 いい人生」 加東康一)
田崎早雲
暁斎の酒友に田崎早雲がいる。早雲は文化十二年(一八一五)の生まれであるから暁斎と十七歳の開きがある。しかし二人は酒友であり画友であった。ある本によると、酒を飲むとき必ず二人は誘い合っていたという。早雲の酒量は「晩酌一升」といわれていたし、暁斎も「猩々狂斎」ともいわれたほどだから好敵手だったろう。ある時二人は暁斎の家で酒を飲んだ。痛飲数刻の後、暁斎は筆を執ると「猩々舞の図」を描き猩々狂斎と署名して、勝ち誇ったように早雲の前に突きかけた。すると早雲はその猩々の絵に大亀を描き加え、正覚坊梅渓と署名し「猩々も正覚坊には及ばぬそうだ」と大笑いしたという。早雲は、浅草伝法院前火の見横丁で愛妻の菊子を失い、文久元年(一八六一)、四十七歳で郷里足利に移った。(「河鍋暁斎」 落合和吉編)
私の洋酒ノート
『婦人画報』の元編集長であり、現サン・アド常務取締役でサントリーの宣伝に専念している矢口純氏の酒の本が、『私の洋酒ノート』(大泉書店刊)だ。これには、ウイスキー、ビール、ワイン、ブランデー、ジン、リキュールなどの酒の知識と筆者の酒体験が、さながらサンドイッチのように織りこまれている。例えば、ビールのページには、大佛次郎、火野葦平さんらビール党の話が出てくる。そして、そこには「火野さんは、その気質からいっても、ビール飲みにうってつけであり、ビール飲みの名人であった」とくる。火野氏は胸が厚く、「ビールを飲んだらこんなにオッパイがふくれてきた」ともいう。ここで矢口流の解説が入る。”これは冗談でなく、ビールのなかのホップのせいだ。ホップには女性ホルモンが含有されている。ビールを飲むと不思議に乱れる女性がいるが、これはおそらく、そのホップの女性ホルモンが女の血をかきたてるのかもしれない”。さらに、矢口さんは「ビールは繁盛している酒屋を選んで買え」のアドバイスをしている。どんなにすぐれたビールでも、ビールは生き物だから、製造されて長い日数がたつと微妙に変質するというのだ。なるほど、まったく面白く有益な本なのだ。(『夕刊フジ』昭和四十八年六月十七日)
大酒大酔の悪しきといふ事
されば何程生れ付丈夫にても求て不養生なる事をせず何程弓馬等芸達者(たつしや)にても求て危(あやう)き事をせず、平日は身体髪膚(しんたいはつぷ)をも毀傷(きしよう)せずして、戦陣には万人にすぐれ勇を振(ふるは)んと心掛候こそ、真の剛の者とはいふべけれ。扨右に類したる事にて、大酒大酔の悪しきといふ事は、人〻承知の事に候へども、知(しり)つゝこれに溺るゝ者なきにあらず。是亦士道不覚悟の至と存候。士は平日の心掛大切にて、一寸門を出候にも覚悟あるべき事と承り及候。然るに沈酔(ちんすゐ)して身体もよろけ、本心をも失ふ時、万一不慮の事あらんには、如何なる智者も分別出申間敷(ふんべつできもうすまじく)、武人にても心外の不覚をとるべし。其上喧嘩争論等、多分酒の上より起る事にて、武士たる者酒に使はれ喧嘩等いたし候は,恥辱なる事ならずや。前にもいへる如く、君父の恩義を忘れ、口腹(こうふく)の為に不養生し、身体もうみ、武士の働(はたら)きも自由ならず,剰(あまつさへ)大切の身命を縮(ちゞむ)るに至るは、何とも惜き事ならずや。されば常〻心掛、酒にかぎらず,其身を慎(つつし)み士の覚悟を不レ忘様致度(わすれざるよういたしたき)事に候。(「告志篇」 徳川斉昭) 藩主に就任した時に家臣に示した文書です。斉昭は全くの下戸だそうです。
[酒麯魚]
大きな魚をきれいに洗って一斤用意する。それを手のひらの大きさに切り、塩二両・神麯の粉末四両・椒百粒・葱一握・酒二升を加えて、よくまぜて密封する。冬は七日、夏は一晩で食べられる。
[酒蟹]
九月のうちに肉づきのよいもの十斤を選ぶ。炒めた塩一斤四両と上等の明礬の粉末一両五銭を用意し、まず蟹を洗い浄めて竹製のかごに収め、封をして風の当たる場所にかける。半日か一日ほどで蟹が乾いたらちょうどよい。上等のもろみ酒五斤を塩と明礬にまぜ、その中に蟹を入れる。しばらくしてから取り出し、蟹一匹につき花椒一個を腹の中につめ、かめに収めて貯える。更に花椒をその上に入れ、紙で包み、竹の皮でくるんで泥で塗り固める。取り出す時には灯にあててはならない。また、上等の酒を糟に入れ、塩・磐とかきまぜてもよい。その時に糟は五斤用いる。
神麯=薬の名、盛夏に、小麦・赤小豆・杏仁等の粉末に青蒿・葈耳(おなもみ)等の汁液を混ぜて製した消化剤。 椒=さんしょう。 花椒=落葉の灌木で,山野に自生し、香気が強く、実及び茎の皮はみな香料となる。山椒。 (「食経」 中村璋八・佐藤達全)
酒の唄 ヰリヤム・バトラ・イェーツ 西条八十訳
酒は唇(くち)よりきたり
恋は眼(まなこ)より入(い)る。
われら老ひかつ死ぬる前に
知るべき一切の真はこれのみ。
われ杯(さかずき)に唇をあて
おんみを眺めかつ嘆息す。(「酒の詩集」 富士正弘編著)
鹿狩の樽酒
明くれば嘉永二年(1849)の初、将軍家一代の盛事と聞えたる小金原の鹿狩を、三月十八日に催さるべきに定まりて、幕府は予(かね)てより準備に忙し。烈公は身親しく盛儀に与(あずか)ることは叶(かな)はずとも、せめては奉公の誠をつくさばやと、正月半より、親(みずか)ら所蔵の記録を渉猟し、歴代将軍家の典故を抄録して二冊となし、二月十九日阿部伊勢守を経て家慶公の左右に見せらる。又将軍家の盛徳を仰がしめん為、臨時台慮より出でたる恩恵として,狩場にて勢子(せこ)を勤めし百姓等に、樽酒を賜はらん事を建議し給へり。家慶公書を得て大に喜ばれ、侍臣をして読ましむるに、代々の将軍家が猟場の盛儀、今も目に賭(み)るが如しとて深く感賞あり、建議の一条も吻合(ふんごう)せりとて、亦採納せらる。是等の事いたく将軍及び老中の心を動かしけん、鹿狩に先だつこと数日、恩命は遂に水藩に下れり(新伊勢物語)(「徳川慶喜公伝」 渋沢栄一) 謹慎は解けたものの、まだ藩政に復帰できなかった時のことです。
下野家令(しもつかれい) 末廣酒造 新城希子社長夫人のお勧め
茨城県の郷土料理すみつかりは、各々の家庭によって味つけや具、呼び名が違うものです。こちらの下野家令(しもつかれい)もその一つで、大豆を柔らかくなるまで煮込んだタイプです。また塩鮭の頭からだしもしっかりと出ています。
●材料(5人分) 塩鮭の頭 1つ/大根 1本/大豆 1/4カップ/人参 1本/油揚げ 1枚/板粕 130グラム
●作り方 ①塩鮭を洗い、ぶつ切りにして火を通す。 ②鍋に焼いた塩鮭を入れ、身が隠れる位まで水を入れ、骨が柔らかくなるまで約1日煮込む。 ③煮えたところに大豆を入れ、板粕を溶かし入れる。 ④おろした大根と人参、細かく刻んだ油揚げを入れ、中火で約3時間煮込む。
◆好みにより踏み粕で作ることもできます。(「酒粕の凄い特効」 滝澤行雄監修) 煮物 すみつかり
「やってくる」もの
ところで、一緒に飲むとなぜか二日酔いになりやすい相手というのもある。私の場合、某レコード会社のナメカタ部長、某出版社のニシムラ編集長、某病院のコンドウ医師、そして某ロック歌手のジュエリーデザイナーだった主婦サッチャンの四人が要注意人物である。そうした人物にはある共通点がある。まず、飲むほどに調子づく後引き酒であること。そして、私よりもちょっとだけ強くて飲むペースが早いこと。それらの人と一緒に飲むと、お互い同じように調子づいてもう一杯、もう一杯と盃を重ねるのだが、私よりも早いペースに、つい一緒についていってしまう。最初から太刀打ちできない、とわかっていればこちらも無理はしない。しかし、ちょっとだけというのがミソで、負けてなるものかという気持ちがムクムクと湧き上がってきてペースを合わせてしまい、結果、それが仇(あだ)となる。自分のペースを上回って飲むのは実に危険で、かなりの確率で二日酔いになる。晩酌で二日酔いになりにくいのは、こーした相手がいないからでもある。この危険な四人には、それぞれ特に記憶に残る二日酔いの思い出がある。ナメカタ部長には、最後の一軒に赤坂のワインバーに連れていかれてひどいめにあった。先ほどの注意事項、“締めに飲むワイン”である。案の定、翌日、夜になっても回復しない猛烈な二日酔いに襲われた。ニシムラ編集長とは、寿司屋で日本酒を飲んだあと、銀座のバーで、カクテルやスピリッツを記憶をなくすぐらいめちゃくちゃ飲んで、翌日、胃袋が何度もひっくりかえるような地獄を見た。コンドウ医師とは、阿佐ヶ谷のジャズバーでウイスキーを飲んだとき、うっかり彼についていって、翌日、全身からウイスキーの臭いを発散しながら死体のように横たわるしかないというすざまじい二日酔いになった。サッチャンとは、荻窪の寿司割烹店でしこたま日本酒を飲んだあと、駅前の立ち飲み屋で酎ハイを飲み、さらに中華料理屋で紹興酒を飲み、最後に昭和レトロ居酒屋でビールを飲むという典型的チャンポンはしご酒をして、翌日、昨夜の自分を筆頭に、目に映るすべてのものを呪いながらのたうち回ることになった。これらはすべて自業自得、相手にはなんの責任もない。用心を怠った私のせいだ。しかし、あとから思い起こすと、いくら気をつけても抗えない不可抗力が働いているとしか思えない。もしかしたら、二日酔いは「なる」ものではなく、「やってくる」ものではないか。(「晩酌パラダイス」 ラzyウェル細木)
県外出荷用銘柄
県内酒造家を中心にした県外酒追放運動で、昭和初期には県外酒の姿は消え、逆に県外、特に北海道、東北各県や東京方面への“輸出”が積極的になった。ところで、酒通のみなさん、「八重寿」「秋田桜」「栄冠秋田」「秋田城」「秋田鶴」「雪国」「秋田一」-といった銘柄をご存じですか。聞いたことはあっても、飲んだことのある人はほとんどいないはず。「秋田の名が付いているから秋田の酒だろう」という推理は正解。実をいうとこれらの酒は県外“輸出”用のラベルなのです。「栄冠秋田」は平鹿郡の酒蔵の県外用統一銘柄。昔から売っている銘柄のほかに、県外用のラベルを新設した酒蔵も多い。横手市・阿桜酒造の「かまくら」も当初は県外用だった。が、現在はこちらの方が有名になっている。東京の酒通が「雪国」を地元で飲みたいと来県したら、どこにも売っていなかったという笑い話もある。大曲市の「八重寿」は最初から東京方面に売り出すために仙北、平鹿の酒蔵が共同出資で作った会社。東京駅八重洲口から名を取ったという凝りようだった。(「あきた雑学ノート」 読売新聞秋田支局編)
ワンカップのウオッカ
アルミのフタがついたプラスチック製カップに、四〇度のウオッカが二〇〇㏄入りで値段は約六〇円だそうである。このワンカップ・ウオッカが新発売されたのは、一九九五年の夏のことだったので、売れ行きはたいしたことはなかった。ところが、気温が下がるにつれ、ワンカップ・ウオッカの売れ行きは逆に急上昇。何せ「防寒対策の定番は、毛皮のコート+ウオッカ」というお国柄だ。木枯らしの吹く一一月にもなると、街角にワンカップ・ウオッカの露天商が続々と店開き。道行く人々の間で飛ぶような売れ行きになったのである。(「酒場で盛りあがる酒のこだわり話」 博学こだわり倶楽部編)
絶対味覚
絶対味覚というものはあるのだろうか。私は同一環境の中では絶対味覚が成立すると思っている。環境が異なればそれは成り立たない。成り立たない方を説明すると、国や風土、時代や体の使い方などが変わればそれぞれの人たち(民族とかグループ)の食べ物の嗜好、要求の方向が変わってくる。その違いを超越してまで絶対味覚は通用しない。酒は嗜好品だという。日本人の食環境は広がり嗜好は多用ママになった。だからいろんな酒があって当然である。だがその範囲の中で絶対味覚が成立しているらしい。きき酒能力を問わないとといい、酒質に対する情報をブラインドしたまま飲み進めていくが、酒の減り方が違ってくる。いい酒の方が減りが早いのだ。飲んでいる方はある銘柄の瓶が空っぽになっても気にもしないが、たまたま例会に蔵元が来ている場合は彼らは気が気でないだろう。(「「幻の日本酒」酔いどれノート」 篠田次郎)
蒸留酒製造法の伝播経路
以上、さまざまな角度から本邦への蒸留酒製造法の伝播経路について考証してきたが、結論的に述べれば、南海諸邦、とりわけシャムから琉球国を経由して薩摩に伝わってきたというのが無理のない経路であろう。その後、薩摩で造られた焼酎は、試行錯誤を繰り返しながら肥後や日向、豊後などへと伝わっていったのだろう。(「銘酒誕生」 小泉武夫)
初午生酔 節松嫁々
初午や しるしの杉を 神垣に まがへてをれる さかきげん(酒機嫌)かな
曲水宴 馬屋厩輔
曲水の 宴にひかれて 三日月も ともにながるゝ 盃のかげ
菊花泛酒 銀杏満門
一りんに 千とせをちぎる 花ぶさは よはひのぶると きくの盃
十三夜月 あけら漢江
きく月の 月見はもち(望・餅)の 月ならず 籬(まがき)に花の さけや(咲けや・酒屋))さかづき(「徳和歌後万載集」 野崎左文校訂)
粗相コール
学生たちがコンパのとき自己紹介を間違えると「粗相、粗相」とはやし立ててビールや酒を飲み干させること。「イッキ飲みは古いしイメージがわるい」由。(「新語×流行語小辞典」 稲垣吉彦)
酒茶会
そのうちに、彼らも茶道に深い関心を寄せはじめた一般的な知識はあっても、上っ面だけに中途半端な理解に終わっている。茶道を習いたいいい出す者もいたが、忙しいスケジュールに縛られている人たちなので、実際には実行が難しい。そこで、皆が好きな酒に焦点を合わせて考えた。茶道の正式な集いである茶事では、懐石の食事にはじまって濃茶と薄茶を飲む。その食事の段階で酒が出るが、飲み方や順序には決められた作法がある。歌舞伎役者や舞踊家にとっては、酒を飲む所作は関心の的の一つだ。そこで、時どき集まって茶事の真似事を提案したら、皆大賛成であった。懐石の部分では、酒を注いだり飲んだりするところだけは正式な作法に従い、それ以外の部分は簡略にし、その後で濃茶は省略して薄茶だけというかたちにした。酒の作法もかなり確立されたものがあり、それだけでも皆の興味を引くのに十分である。例えば、山海の珍味を肴としてすすめるときは、まず先に酒を注いでからにする。このときの酒客の献酬は、盃が千鳥の歩き方のように主と客の間を行ったり来たりするので「千鳥の盃」と呼ばれている。元来、盃を頂くというのは、目上から目下に下さるものである。目下から目上のほうに盃を持っていくことはない。茶道ではその点に従ったうえで、多少簡略化した作法にしている。また「預け徳利」といって、その都度ホスト役である主が注ぐのではなく、客同士がお互いに注ぎ合えるように、酒の入った徳利を客側に預けることもある。どうもこの部分がいちばん皆の気に入ったようであるが、結果的には「酒飲み集団」であったから、当然のことである。作法の順序だけではなく、注ぐときや飲むときのかたちも重要な要素だ。しかし、伝統芸能の道に優れた人たちであるから、飲みこみも早い。和気藹々(わきあいあい)のうちに格好をつけながら酒を飲む場となった。自分の好きなようにくつろいで飲むのも良いが、きちんと定められた作法に従って飲むのも気持ちがよい。気取って飲んでみるのも面白いものだ。この会を「酒茶会」と名付けた。この会のお陰で、それまでは知らなかった分野の人たちと、打ち解けた話ができた。「茶」の中の「酒」が大いに役だった結果となった。料理屋などで一緒に食事をして飲んだときよりも、ずっと深い交流が可能であった。「かたち」の中で「かたち」に従って飲むほうが、乱雑な話にならないだけ、要領を得た話をしようとする。それだけ相手のことを考えるコミュニケーションになっているのかもしれない。ルールという秩序の中で、酒というコミュニケーションの触媒がうまく働いた例である。(「酒を味わう 酒を愉しむ」 山崎武也)
新婚当時の梶原
十九歳の新妻は、いい奥さんになろうと懸命だった。酒好きの梶原は、毎晩ビールやワインを飲みながら、四時間もかけて夕食を採る。好物はステーキ、鰻(うなぎ)、鍋(なべ)もの、鯵(あじ)の酢の物、コハダ、シジミの味噌汁(みそしる)、アサリの吸い物。山芋と川魚が嫌いだった。篤子はそれらを料理した後、梶原が最後にご飯にお新香で締めるまで、ずっとテーブルについてコーラで付き合った。そこで洗い物が後回しになり、いつも翌朝の朝食作りに手こずった。翌昭和四十年の新春、長女花実が生まれる。初めて父親になる喜びに、梶原は上擦っていた。「子どもが生まれるんだから、今の部屋じゃ狭すぎるだろ」篤子が臨月に入った頃、梶原は彼女に何の相談もせず、大泉学園の建売住宅を購入した。事後承諾を求める説明に、篤子はうれしさと不満、驚きがごっちゃになった複雑な表情を浮かべたが、梶原はそれには気付かないふうだった。出産は予定日を大幅に遅れ、引っ越しの最中に陣痛が始まった。朝までには生まれそうだという夜、梶原は真樹と飲みに出た。梶原がたびたび病院に電話するのに白けた真樹が皮肉ると、「この気持ちがお前なんぞにわかるもんか」梶原は本気になって怒り、二人は深夜の路上で大立ち回りを演じた。(「梶原一騎伝」 斎藤貴男)
「もろはく」を楽しむ
「もろはく」を広辞苑で調べてみると、「掛米と麹の両方に精白米を用いて醸した酒。江戸時代は上質の酒の総称」とあった。これと同じ名を持つ※日本酒バーが札幌東急インのそばにある。カウンター正面の冷蔵庫には私の知らない日本酒がずらりと並ぶ。さぁどうだ、とばかりに魅力を放っている。その隣にはたくさんの焼酎が、こっちもおいしいよ、と手招きしている。バカラなど美しいグラスで出される酒は、まるでドレスをまとった美女のよう。どれも素晴らしく、酒のミスコンテストにでも紛れ込んだ気分である。バーなので食事の種類はそんなにないが、メニューに「肴(さかな)」のページがある。紅豆腐、シシャモ燻製、ツブ燻製、ホタルイカ一夜干しなどなど、酒がいくらでも飲めそうな品々が厳選されている。変わり種ではピザや豆もちなどがあるが、これもけっこう酒に合う。店では定期的に「もろはく会」を開催。利き酒やらさまざまなイベントに日本酒ファンはご満悦となる。とはいっても、中年男の酒オタクがとぐろを巻いているような店ではない。若い女性も一人で来て、涼やかに飲んでいたりする。しゃれた雰囲気のバーだ。遅くまで営業しているが、私は早い時間に行って、いかついオーナーとの会話を楽しむことに決めている。なぜなら酔っぱらってから行くと酒の味が分からないし、調子にのって飲みすぎるのである。
※「もろはく」は札幌中央区南3条西6丁目インフィニ桂和22ビル6階 電話011・232・0689(「さしつさされつ」 中田耀子・土倉裕之)
お酒で元気をつける
私が治療を行った登校拒否の高校生は、私の外来にはほとんど来れず、母親が主に現状報告に来て、彼の気持ちを私と母親の二人で推測し、彼に対する援助をどうするかを話し合うのが主な治療でした。彼は中学時代に友達関係の中で孤立したことが心の中で大きな挫折感、もっといえば心的外傷体験になっていて、高校に進学しても、そのことが解決できないままに高校生活で取り残され、学校に行けない状態になりました。彼は何人かの中学校の友達と細い糸のようなつながりを持っていましたが、登校拒否の初期においては、彼の家に会いに来た友達とも会うこともできず、友達との電話にも出られない状態でした。半年くらいたってから、彼はやっと家族と普通の会話ができるようになり、顔色も明るくなって、家庭の中で笑顔が出るようになりました。その頃から彼は友達から誘われると外で会えるようになりました。ところが実は、友達と会って何をしていたかというと、二人でテレビゲームをするかお酒を飲んでいたのです。友達と会う度に泥酔して帰宅するようになり、一度は二人でベロンベロンに酔っ払って帰って来たこともありました。余りにひどいので彼の父親が注意したところ、彼はまたしばらくの間家族と顔を合わせなくなり、自分の部屋に閉じこもってしまったということがありました。(「子どもの飲酒があぶない」 鈴木健二)
フキノトウ味噌焼き(フキノトウ、信州味噌)
酒肴に季節感は大切な要素。そこで春の訪れを真っ先に告げるフキノトウを使った絶品中の絶品をご紹介しよう。まず、新鮮なフキノトウを細かくきざみ、信州味噌を加え、さらに少量の酒を加えて、ていねいに練り合わせる。酒はカンざましでも充分。ポイントは根気よく混ぜ合わせること。ドンブリ鉢などに入れ、時間をかけてまんべんなく混ぜるようにする。混ぜあがったら、アルミホイルにぬり、それを焼いて食べるのだ。焼き加減は好みでいい。香ばしいのが好きな人は表面を焦げるくらいに焼いてもいい。味噌も好みでいいが、フキノトウは香りが強いので、甘口の味噌の方が相性がいいようだ。香りと風味がうれしい一品になる。(「酒肴<つまみ>のタネ本」 ホームライフセミナー編)
愛と誇り
また、二〇一〇年には、世界的に著名なニュージーランド人のマスター・オブ・ワイン(ワインの評論、アドバイスをする資格)のボブ・キャンベル氏が、酒蔵を視察するために来日しました。石川県や静岡県、京都府など9蔵の酒蔵を見学した感想を尋ねてみると、「どの酒蔵のSAKEも、個性をはっきり持っていて、堪能しました」と興奮した顔で話してくれました。「複雑で高度な酒造りの技術は、ほかの国に無い素晴らしいものであり、長い歴史に培われた文化であることを感じました。繊細で微妙な味わいの差を、もっと理解できるようになりたい。そのためにこれからも多くのSAKEを味わいたいと思います」と言うのです。日本酒や本格焼酎など、日本で生産される「国酒」を「SAKE」として世界市場に売り出そうと官民一体となったプロジェクトも動き始めています。一方、国内では伝統的な酒蔵を観光資源にして、内外から人を呼び込もうと、観光庁が音頭を取った「酒蔵ツーリズム推進協議会」も発足し、「SAKEからの観光立国」をスタートさせています。外国の飲食関係者や食通たちが、熱い憧れを抱く日本酒。一番冷めた目で見ているのは日本人かもしれません。海外で人気なのは嬉しいことですし、日本酒を目当てに日本に来てくれるのも大歓迎です。でもその前に、まず、私たち日本人が、日本酒をもっと愛し、もっと誇りを持ってもいいのではないでしょうか。(「めざせ!日本酒の達人」 山同敦子)
千紅万紫(2)
菊の花かきたる盃に
酒のめば いつも慈童(じどう)の 心にて 七百歳も いきんとぞおもふ
七賢人のゑに
竹林に 藪蚊の多き ところとも しらでうか/\ あそぶ生酔(なまゑひ)
葛飾蟹子丸(かにこまる)大のしやにてたはれ歌人をつどふまゝ、一筆かいて君奈斎(くんなさい)のもとめいなみがたく、右に筆をとり左に盃をとりて、諸白(もろはく)のすみだ川にうかばんとなり
みさかなに 大のしあはび 蟹よけん かつ鹿早稲の にゐしぼり酒(「大田南畝全集」 浜田義一郎編集委員代表)
酒病偶作 二日酔ひして、ふと作る 皮日体
鬱林ノ歩障 昼 明(メイ)ヲ遮リ 森林の図の衝立(ついたて)で昼間の明(あか)りを遮り
一炷ノ濃香 病酲ヲ養フ。 一炷(ひとたき)の濃香で二日酔を静養していると、
何事ゾ晩来 還(ま)タ飲ント欲ス 何(どう)した事か夕方になると復(ま)た飲みたくなつた
牆ヲ隔テテ聞ク蛤蜊(カフリ)ヲ売ルノ声。 垣根越しに蛤蜊(あさり)を売る声が聞こえる。
〇鬱林 未詳。鬱鬱たる茂林の図を歩障に画いてあるのか。 〇歩障 衝立(ついたて)のたぐひ。 〇蛤蜊 アサリのたぐひ。酒の肴にしようと云ふわけかも知れぬ。(「中華飲酒詩選」 青木正児著)
江村杜氏
「笹一」の酒質がよくなったのも、越後杜氏の江村文雄さんがやってきてからである。江村文雄杜氏は、昭和五年五月十九日、新潟県中頸城郡吉川町大字河沢の農家に生まれた。O型。昭和二十三年三月、新潟県立吉川農林学校を卒業して群馬県の酒蔵へ出た。父上も杜氏であったというから付し二代の杜氏である。三十九年十一月、杜氏に昇格して千葉県の藤平酒造に勤務していたが、五十四年十月、乞われて笹一酒造へ勤務することになる。天野社長がいう。「江村杜氏は、二十八年から四年間、蔵人としてうちの藏にいたことがあるんです。前の杜氏がやめるということで、江村杜氏に来て貰うことになりました」「私は、五人の杜氏と一緒に酒造りに携わってきたのですが、残念ながら思うような酒質にならないので無念に思っていたのです。それが江村杜氏のおかげで、全国鑑評会で三年連続の金賞を受賞できたのです」江村杜氏は、平成二年三月、笹一酒造株式会社の取締役製造部長に就任している。当然といえば当然だが、季節労働の請負杜氏ではなく重役として参与し、「笹一」の全製品に責任をもっているのだから意気込みも違う。江村部長は、まことに研究熱心で、杜氏としての職責は淡々とこなし、新製品の開発に取り組むと脇目もふらずにやるという。「勤人とか雇われているとかいうのではなく、俺の仕事だ、と経営者的な考え方でやってくれるので、本当に助かります」と天野社長は江村部長に全幅の信頼をおいているのである。江村部長がいう。「この蔵は自然環境に恵まれているので、よその藏のように仕込水に心配しなくてもいいし、原料米も契約確保しているので、本当にいい酒を造ることに専念できます」(「酒の旅人」 佐々木久子)
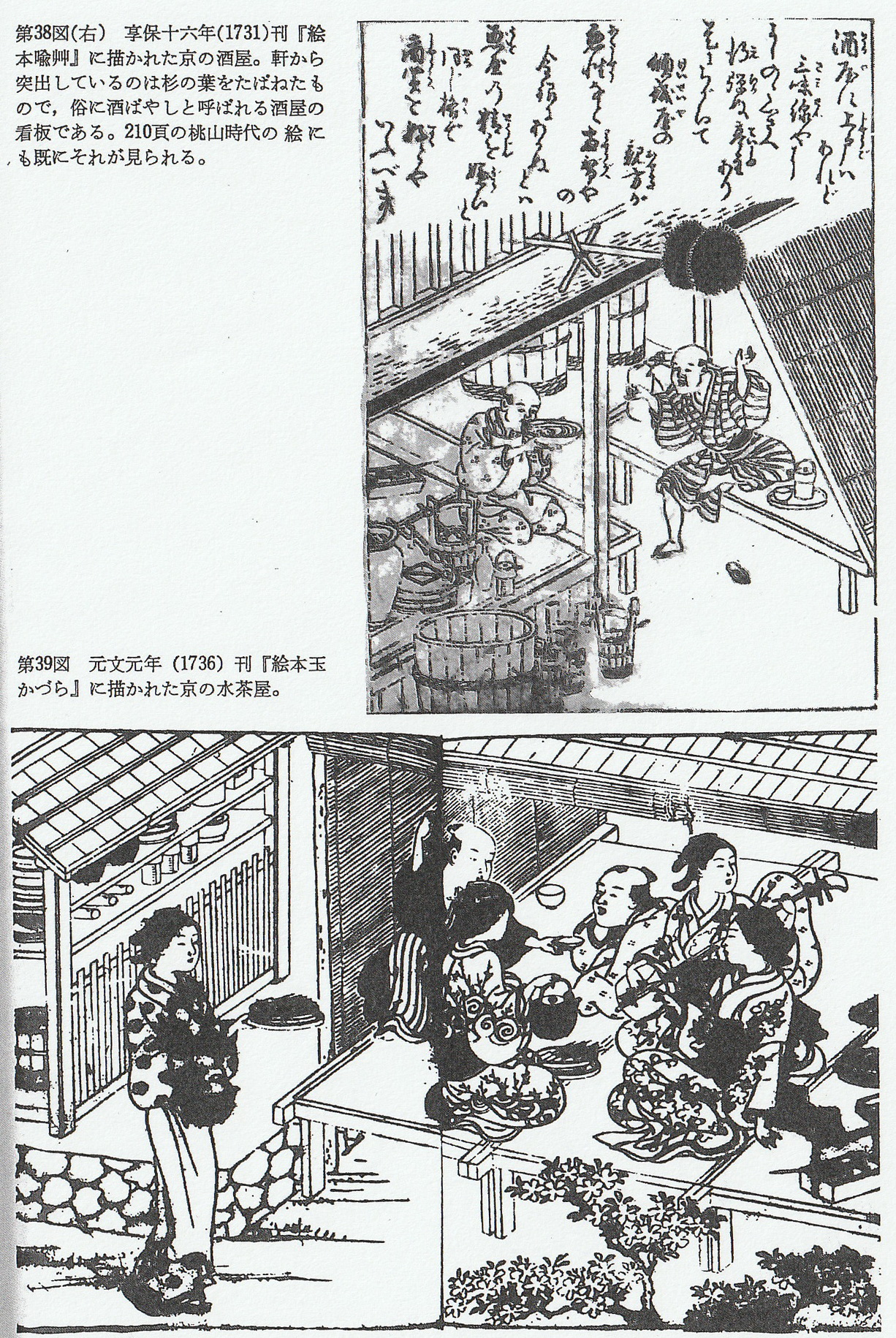
宝暦以前
では宝暦(一七五一~一七六四)以前、外で食事をするにはどうしていたかというと、そういう場所がないから用意よく自分で弁当を持って出たのである。腰掛茶屋(後の水茶屋)というのが享保(一七一六~一七三五)以前からあって、そこで休むこともできるし、酒ものめなくはなかったが、これも浅草寺境内や両国などと限定されている。とにかく不便であった。しかし上方ではとっくに料理茶屋風の水茶屋が発達している。第三八図は享保十六年(一七三一)の京都の酒屋の風景、店頭で居酒させているところでちょころでちろりが見える。第三九図は水茶屋で、やはり京のもの、元文元年(一七三六)の刊本の口絵で、これもちろりと鉄銚子が見せる。当時はまだ上方の方が文化的に江戸より一歩先んじていた。こうした風俗が次第に江戸にも流行してくるわけである。(「時代風俗考証事典」 林美一) 縄暖簾の居酒屋
「段平」
その「段平」は、翌月の有楽座に上演され、大阪、京都、名古屋でも再演、映画にも三度なった。その「段平」が、のちに東京明治座で再演される事になった。私は、それについて新しく、書き足りなかった場面を加え、段平の苦心になった「月形半平太」の三条磧の場も、いわゆる劇中劇の形で生かし、これへ段平自身を登城させようという案を立てた。そのために、「段平」をすすめてくれた「月影」の作者である行友李風にも会って、いろいろ話を聞きたいと思った。私は、そのために大坂へ出かけた。(どこで会おう…)その場所についても、いろいろ考えた。二人で段平を語るに、もっとも相応(ふざわ)しいところをと考えた末、法善寺横丁の「正弁丹吾(しようべんたんご)」の二階をえらんだ。法善寺横丁は、おそらくは、かの段平も、酔歩蹣跚(すいほまんさん)として、よろめきながらしばしば通ったところであろう。正弁丹吾は、その時分からの古いのれんである。果して老李風は「なつかしいなあ」と、卓を叩いて「あの当時、私は、段平を何度もここへ連れてきてやったものです。あいつはちょっと泣上戸で、ここの茶椀酒で泣いたもんです」といった。もっともその頃は、この店も今のように立派ではなく、南側にのれんを吊ったかんとだき屋で、食べ物はおでんしかなく客は皆立ったまま、湯のみ茶碗で酒をのんだ。のれんの間から、その客たちの足だけが何本も、のぞいていたのが、今では鍋井克之が描いてくれた画だけに残っている。その足の中に、段平も、若い日の李風の足も酔っていたのである。(「味の芸談」 長谷川幸延)
追剥ぎ
さらでだに学窓時代から酒を嗜んでゐた天心は、その頃では晩酌に相当の酒量を傾け、時間もかなり晩くまでかゝつてゐた。対手も時によつていろ/\変つてゐたが、明治二十年の暮から、同二十一年の春へかけては、毎晩のやうに訪ねて来る狩野芳崖を青眼に迎へて、献酬を重ねながら、美術論に口角泡を飛ばして、夜の更けるのも忘れるといふ有様であつた。二十一年の春まだ浅き一夜、例によつて議論がはづみ、夜半を過ぐる頃、芳崖は辞去して本郷西方町の寓居に帰らんとして出で立つたが、三〇分ほど経つと、襦袢一枚でわな/\打振へながら、再び池之端の家へ引返して来た。ことこと/\と門を叩くのに呼び醒まされた天心夫妻は、「先生どうなさいましたか」と、異口同音に玄関先きで訊ねると、「弥生町の切通しで追剥ぎに会ひました。奴等は二尺ばかりのダンビラを私の鼻の先へ突きつけて、身ぐるみ脱げと言ふから、着物と持物はやりました。然し殆んど、一糸も纏はない裸なので、それ以上の道中は出来ません。已むなく引返して来た訳です。どうか今夜は御厄介になりたい。」(「父天心」 岡倉一雄)
酒屋の秋刀魚の胴抜き
蔵人の飯の世話をするのも姉様の仕事だったが、その頃は、食べるものは主人も蔵人もみんな一緒。「酒屋の秋刀魚(さんま)の胴抜き」という言い方があるが、おらとこの藏はそういうことはなかったんですて。若い衆には、秋刀魚の頭と尻尾ばかり食わせて、おいしい胴のところは主人が食う。そんげのを「酒屋の秋刀魚の胴抜き」というんですて。おらたちのような古い酒屋もんは、よくそんなことを言っていたもんですよ。だすけ、いい酒を造る、造らないは、結局、主人次第ということになるんですて。(「杜氏千年の知恵」 高浜春男)
469無茶いうな
酒呑み「水は、酒よりも有害なり」
禁酒論者「御冗談でしょう」
酒呑み「疑う者は、先ず洪水を見よ!」(「ユーモア辞典」 秋田實編)
酒諺(しゆげん)集
九合(くごう)にして酒人を呑む ★「一升」としないところがミソ。
杯(さかずき)の沼 ★盃中の酒を飲まずに置いておくこと。右(杯に孑孑がわく)にほぼ同じ。
酒神は軍神より多くの人を殺す ★飲酒への警告
新酒でも今がよい ★新酒は味わいが浅く酒通はあまり歓迎しないが、それでも振舞ってくれるなら、古酒になるまで待たず今のうちがよい。飲み助の心情をたくみに言い表している。
炭をなめて酒を飲めば鬼になる ★早いとこ酔っ払えるよう伝えられた俗信。(「日本の酒文化総合辞典」 荻生待也編著)
ぬかしながらの 昔ながらの口合い。
①禁酒ぢゃとぬかしながらの山ざくら(拾一二)
①禁酒したといつたクセに花見のころとなればやつぱり飲まずにはいられないやつ。千載集巻之一春上よみ人知らず-さゝ波や志賀の都は荒れにしを昔ながらの山ざくらかな、の文句取り。この歌、実は平忠度の作で都落ちの際狐川から引返し、平素から書きとめておいた歌集を師の藤原俊成に手渡し再び帰らぬ戦場へ馳せ戻つたのだが、のち千載集の勅撰があつたとき故郷の花として前記の歌が入選したものの、朝敵だというので本名を憚り読み人知らずとした。謡曲・忠度は同人討死の時鎧の下に秘めてあつた-行きくれて木の下蔭を宿とせば花や今宵のあるじならまし、をテーマにしてある。- 類句-付けざして禁酒を破るはしたなさ(逸)
②禁酒を断つて御用を追かける(樽一九)
③禁酒の曰く飲まうかなアみりん(樽八九)
②禁酒、えッやめちまえと御用聞きを呼び戻す。③みりんは酒でないな。(「古川柳辞典」 根岸川柳)
ニューカヤバ
ガレージの軒先に吊るされた大きな赤提灯には堂々たる「冒険酒場」の文字。昭和39年に酒屋さんが始めた立ち飲みだ。創業約半世紀だけれどもその名は“ニュー”カヤバ。その昔、女一人で来たら入れてもらえぬことがあった。常連のおじいちゃんによると「女将がやきもちやくのヨ」という説もあるし、男湯のような空間に紅一点まじるのは色んな意味でデンジャラス(ナンパまたは逆ナンはあってはならぬから)という説もある。ニューカヤバだけではなく、一大歓楽街池袋では、海外から来た商売ギャルが立ち飲み屋で営業活動に勤しむため、、女一人客はお断りという暗黙のルールの店もあったっけ。個人的にはこの古びた習わしが案外嫌いではない。こんな事情でもないと、殿方にエスコート願うチャンスは当方の場合ないのである。特等席は奥の大きな焼き台である。炭がパチパチと燃えている。ここに生のままのねぎまやつくねをカウンターで買ってセルフで焼くのだ。調味料もタレ壺もスタンバイ。焼ける間にカウンターに並ぶ200円から300円の色とりどりの惣菜、煮こごりに鴨のスライスにぷりぷりのタコ刺しにつぶ貝などを選び会計する。お酒は年代物のレトロな自販機で。さつま白波からトリスまで100円を投入するとチャーッとコップに注がれる仕組みだ。これが面白くて仕方がない。世にもワルい自販機だ。家にあったら一家破滅だ。にしても、ずいぶんニューカヤバは発展している。泡盛で割る「ハイサイサワー」にハイッピーだってある。「自分が食べたいものしか食べない」と自ら築地までチャリンコで買い出しに行くといっていた女将は元気かしら。今夜はお姉さん一人が店番である。そろそろ串が焼けたかと手を伸ばすと、「あなたのはそっちですよ」とお隣さん。おっと失礼。そういえば焼き鳥の焼き方はここの“隣人”に習った。「塩で食べる場合は、焼く前と焼き上がり直前に塩こしょう」「タレで食べるときも焼く前にどぼん、食べる直前にまたどぼん、好みで山椒か七味」。萱場町サラリーマンには驚くほど焼き鳥奉行が潜在している。あまりの人気か「焼き鳥はお一人様4本ぐらいにしておいて」の貼り紙も。ふと、店内に風が吹いた(気がした)。厳かなオーラを放ち姿を見せたのは名物女将。常連があちこちから声をかける。このお方に嫌われまいとこの店じゃ皆背筋を伸ばして正しく酔う。帰り際、前から気になっていた壁の大タコの魚拓を「これは…?」と尋ねると、「だんながとってきたの。大きいでしょ」と女将がちょっと誇らしげにいう。夫婦善哉である。それはすごいと大げさにいいながら、そういやだんなとニューカヤバを訪れたカツヤン。仲いいねというと、「帰りの電車でなぜか大げんか」という珍答が帰ってきた。レトロ自販機で飲みすぎか。夫婦、恋人と行かれる皆さんは飲み過ぎにご注意を。(「女2人の東京ワイルド酒場ツアー」 漫画カツヤマケイコ・コラムさくらいよしえ) 萱場町「ニューカヤバ」 東京都中央区茅場町2-17-11
天竺酒濫觴之事
一(4)、天竺ニハ弥多羅王(9)十九代之時、免甲(10)ト云者作始也。
インドの酒の始まり
〇インドでは弥多羅王(9)朝の十九代のときに、免甲(10)という者が酒を作り始めたのである。
(9)弥多羅王 不詳。 (10)免甲 不詳。
[書き下し](四)天竺弥多羅王十九代の時、免甲と云う者作り始むるなり。(「童蒙酒造記」 吉田元翻刻・現代語訳・注記・解題)
吟醸香はなぜ果実香がするのか
したがって、そのような高度精白米の蒸米を使ったもろみ中では、酵母は栄養源が乏しいため活発に活動することができなくなる。また、吟醸酒造りでは、麹も突き破精(はぜ)型の特別なものを手造りして使用するが、この麹はもろみ中の蒸米をゆっくりと溶かすのに理想的な麹であり、酵母のアルコール発酵を緩慢にさせる条件となる。そして、一〇度C以下という徹底した低温は、蒸米をさらに溶けにくくすると同時に、酵母の活動も抑えることになる。こうした、いわば寒冷地に飢餓状態で置かれた状態になると、酵母は細胞膜内にある芳香エステル生成系と呼ばれる酵素を使って、自らエネルギーをつくり初める。こうして吟醸酒には、エステル類が構成する果実香がつくられることになるわけだが、酵母にも吟醸香が出やすい種類がある。また、この芳香成分は、もろみの発酵の途中である高泡期に放出される炭酸ガス中にも含まれているが、いったん消えてしまい、末期になると再び出てくる。ただ、吟醸香は吟醸造りをすれば必ず出るとは限らず、その出方は杜氏(とうじ)の腕にかかっているといわれる。(「日本酒百味百題」 小泉武夫監修)
塚田家覚書(つかだけおぼえがき)
⑦一、酒は百薬の長といへり。勤仕(ゴンシ)之もの外(ホカ)に欝散(ウツサン)の事なく候間(アイダ)、たまには食事前、膳の上にて相用ひ可レ申(もうすべし)。必ズ数盃を傾くべからず。尤(もっとも)客来(キヤクライ)有レ之(これあり)候節は、無心呑長する事不レ宜(ヨロシカラズ)候。(10)大酒は身を亡す礎と、故人も申シ伝へ候得ば、前後を忘るゝほどに呑(ノム)べからず。
(10)「欝散」はうさばらしの意。「無心呑長」の「無心」は何の考えもないことを意味するので、この語は何の考えもなく長々と飲酒をし続けるという意であろうが、読み方は不明。アルイハ4ムシンドンチョウか。以下の文中の「礎」はモトイと読ませたいのではなかろうか。「故人」は古人の当て字か。あるいは「先代」のことか。(「家訓集」 山本眞功編註)
紀文が涼の酒盃
大浪云、江戸座の俳諧宗匠神田庵小知が家に、紀文が涼の酒盃と称する物を納めてありしを、予も往(いに)し年見たりしが、工せる事もなき朱塗の盃にて、世に云所の小原の形したり。内は鉄線からくさを描画(まきゑ)にしたるもの也き。神田庵主の話に、昔紀文盛なりし頃、一年、夏の事なりしが、その日紀文、浅草川に船遊びするよし、世間にいひもてふらせしかば、いかなる遊びをかするならんと、是を見物せんとするともがら、その日に至りぬれば、われおくれじと競ふて舟にとりのりしかば、川の面は水のいろさへ見えわかぬ迄に所せくもやひつれ、今や紀文が舟は来なんとて待居たりしに、夕日かたふく頃にもなりぬれど、夫れぞと覚しきも見えねば、後にはこゝかしこや舟をさゝせて、尋めぐるも多かり。やゝともしさす頃にもなりぬるに、こゝにも盃こそ流れよりつ、かしこにもとりあげたりなど、いひのゝしりて、頓て舟どよめきつ。後は酒のみ歌諷ふ事もせで、川面をのみ守り居て、いづれの舟にても、たゞ盃の流れよらんことを待て、夫のみあらそひ興じける。こはまさしく紀文がなせるわざなるべし。いざ水上を尋ねばやと、舟を隅田綾瀬の辺り迄もさしのぼせ、至らぬくまもなくさがしもとめけれども、其夜はさらに紀文が舟をば見当らざりければ、夜更(よふけ)興つきて皆人帰りぬとぞ。紀文はその日、船あそびに出るとのみ、云ふらせぬる斗(ばかり)にて、みづからは家にありて、盃ばかり流したるよし、後に人伝聞て、其風流を称せしと云々。(「後は昔物語」 手柄岡持)
魔法つかい
太宰の晩年はフツカヨイ的であったが、又、実際に、フツカヨイという通俗きわまるものが、彼の高い孤独な魂をむしばんでいたのだろうと思う。酒は殆ど中毒を起こさない。先日、さる精神病医の話によると、特に日本には真性アル中というものは殆どない由である。けれども、酒を麻薬に非ず、料理の一種と思ったら、大マチガイですよ。酒は、うまいもんじゃないです。僕はどんなウイスキーでもコニャックでも、イキを殺して、ようやく呑み下しているのだ。酔っ払うために、のんでいるです。酔うと、ねむれます。これも効用のひとつ。然し、酒をのむと、否、酔っ払うと、忘れます。いや、別の人間に誕生します。もしも、自分というものが、忘れる必要がなかったら、何も、こんなものを、私はのみたくない。自分を忘れたい、ウソつけ、忘れたきゃ、年中、酒をのんで、酔い通せ。これをデカダンと称す。屁理屈を言ってはならぬ。私は生きているのだぜ。さっきも言う通り、人生五十年、タカが知れてらァ、そう言うのが、あんまり易しいから、そう言いたくないと言ってるじゃないか。幼稚でも、青くさくても、泥くさくても、なんとか生きているアカシを立てようと心がけているのだ。年中酔い通すぐらいなら、死んでらい。一時的に自分を忘れられるということは、これは魅力あることですよ。たしかに、これは、現実的に偉大なる魔術です。むかしは、ギザギザ一枚にぎると、新橋の駅前で、コップ酒五杯のんで、魔術がつかえた。ちかごろは、魔法をつかうのは、容易なことじゃ、ないですよ。太宰は魔法つかいに失格せずに、人間に失格したです。と、思いこみ遊ばしたのです。もとより、太宰は、人間に失格しては、いない。フツカヨイに赤面逆上するだけでも、赤面逆上しないヤツバラよりも、どれくらい、マットウに、人間的であったかも知れぬ。(「不良少年とキリスト」 坂口安吾) フツカヨイ
酒を飲んで絶対に乱れない女
男が、嫌いでない女性と酒を飲んでいるとき、何を考えているか?ホンネは決まっています。「彼女を酔わせて、そして…」そんな時、「私、少し酔ったみたい」待ってましたとばかりに、男は、勇気リンリン。もちろん、表面は、紳士然として介抱これ努めます。ところが、女性もしたたか。口では酔ったと言っても、ほんとうに酔ってはいない。男に「酔った」と言って、彼の出方を試している-これは、ツライんだなあ。ボクら飲んべェの男には…。酔ってしまいたくないのなら、飲まないこと。飲むなら、酔うほどに酔うほどに。
恋する者と酒のみは地獄に行くと言う、
根も葉もないたわ言にしかすぎぬ。
恋する者や酒のみが地獄に落ちたら、
天国は人影もなくさびれよう!(ハイヤーム「ルバイヤート」より)(「シャレと遊びと人生と」 はらたいら)
花より団子
Without bread and wine, even love will pine.直訳すると、「パンと酒とがなければ愛も衰える」。すなわち、色気よりも食気、日本流にいえば、「花より団子(だんご)」ということになる。Pudding
rather than praise. ことばだけでほめられるよりも、むしろプディングでももらったほうがよい、との意。Bread is better
than the song of birds. Fine words don't fill belly. Fine words butter
no parsnips ともいわれている。No sport, no pie. というのもある。 酒なくて何のおのれが桜かなという川柳もあるように、洋の東西を問わず“花より団子”的な考え方はたいへんに一般化し、きわめてポピュラーである。実利実益を尊重するきわめて現実的な考え方をいったもので、「詩を作るより田を作れ」、あるいは「花の下より鼻の下」などともいわれている。また「一中節よりカツオ節」というひねったのもある。「心中より饅頭(まんじゆう)」となると、徹底した実利主義を端的に示した諺となる。「お情けより樽(たる)の酒」「思し召しより搗いた飯」「案じてたもるより銭たもれ」「座禅組むよりこやし汲め」などと、これに類した諺は非常に多い。「花より団子」この場合の「花」は桜の花に限られる。 酒を妻、妻を妾の花見かな くさまくら、まことの花見してもこよ という句も生まれる。(「置酒歓語」 楠本憲吉).
二日酔
会費分 飲んで翌日 二日酔 どけちマン
無礼講
おい課長! 酔ったふりして 呼びつける 陣太郎
無礼講 言いつつ座る 上の席 ジャッキーロウプ
持ち歌
持ち歌は 「悲しい酒」と 「廻り道」 ドサ回り
飲めません 唄えませんは 最初だけ ドラゴン(「平成サラリーマン川柳傑作選」 山藤章二・尾藤三柳・第一生命選)
ふぐ刺しと鍋
かくして、怖いお兄さんと、小股ちゃんは逮捕された。しかし、二人には、××組がバックについている。復讐を恐れた赤塚は、逃亡者になった。〽追われ追われて~落ち行く先は~ とりあえず、新宿抜弁天のふぐ屋・三浦屋の二階に身を隠した。悪いことに、「どうか御内聞に」という赤塚の頼みを、国家権力は裏切り、新聞記者に洩らしてしまう。こんな面白い事件を、追わない週刊誌があったら、どうかしている。しかし、赤塚漫画を自社の雑誌に掲載している、週刊ポストや週刊現代や週刊文春は書きにくい。三誌の歯ぎしりが聞こえてくるような展開だ。かくして、この「美人局」事件については、週刊新潮の一人舞台になる。××組のやくざに追われ(ていると思っている)、敏腕記者(だろう、多分)にも追われた窮鳥・赤塚は、三浦屋に巣ごもりした。このふぐ屋の主は、三浦清。元、東洋バンタム級チャンピオンだ。赤塚と三浦は、竹馬で知りあった。ある時、三浦は、ふぐ屋をやりたいんだが資金がないと、赤塚に話した。赤塚は、金は貸してやる、返済にはふぐを食った代金をあてる、という話になった。三浦屋で仕事をすることになって、喜んだのは編集者だ。僕達は、赤塚が三浦屋にいた一ヶ月、仕事があってもなくても、夕方になるとふぐを食いに行った。三浦屋のふぐは、毎日食っても飽きなかった。こんな日が永遠に続けばいい、と僕は思っていた。持つべき友は、ヤクザや週刊誌に追われて、ふぐ屋に逃げ込むマンガ家だ。毎夜、ひれ酒を飲みながら、ふぐ刺しと鍋を食らう。つまみは、赤塚だ。-
しかし、実はヤクザは、「小物」の赤塚など追ってはいなかったのだ。かくして、この逃亡劇で得をしたのは、毎日ふぐを食った僕達だけという大団円を迎えた。(「赤塚不二夫のことを書いたのだ!!」 武居俊樹)
某月某日
無口な男でほとんど話をしないが、私が行くとよくサービスしてくれる。梅毒と知って食べに行く私に好感を抱いているのかもしれない。スピロヘーターは癩菌同様極端に弱いうえに、経口でも空気感染でもない。ただ一つ粘膜感染だから彼が握った寿司くらい食べたところで罹(かかる)るわけはない。だが、以前K社の人を此処へ誘って寿司を食べたあと、病気のことを教えたらひどく怒った。大丈夫だと説明してもその夜一晩中、何度も唾を吐いていた。ころころと酒の上に載せて飲む。舌は胃についでアルコールの吸収腺の多いところだから、こうしていると酔いが早い。三本で可成りいい気分になる。最後に軽く腹ごしらえして新宿南口の「萌」へ、此処のママは大柄な美貌である。入ると常連の関根弘氏がいる。ここで倉島斉、女性一人と待ち合わせ、ウイスキーを重ね、揃ったところでK社の人ともども、阿佐谷へ。朝日の草野氏宅へ行く。彼は元陸軍大尉で、私は中国での戦争体験について聞く目的がある。此処ではくま焼酎と海胆(うに)を馳走になる。捕虜の試し切りの話をきくうちに、酔いにわかにまわる。皆と別れ、最後に女性と二人になったが泥酔にて気力なし。(「プラタナスの葉」 渡辺淳一)
はまぐりの潮汁
貝に砂をはかせるときは、蓋をするなど薄暗くして貝を安心させます。あまり冷たい水だと殻を閉ざしてしまいます。
●材料(2人前)
はまぐり(中なら1人前2~3個) 昆布10cm角 塩・酒少々 ウド・木の芽適宜
●作り方
1 はまぐりは1%の塩水(水300ccに対して塩小さじ1/2)に浸して、一晩砂を吐かせる。
2 鍋に、昆布とともにはまぐりを水から入れる。
3 煮立ったら昆布をとり出し、貝の口が全部あいたらアクをとって塩と酒で調味する。
4 薄切りにして酢水につけておいたウドを加える。
5 器に盛って、木の芽を浮かす。(「おうちで居酒屋」 YYT project編)
のんだくれ(飲んだくれ)
[名]いつも大酒を飲んで酔っぱらってだらしない人を罵って言うことば。(江戸)<類義語>うわばみ・飲み助・のんべえ。◇『いたずら小僧日記』(1909年)<佐々木邦>「桶屋の酒飲親爺(のんだくれ)」◇『東京語辞典』(1917年)<小峰大羽>「のんだくれ(泥酔) 酒を嗜みて、身の修まらぬ人。『隣の亭主は-だ』」◇『漫談レヴィウ』アルコオル哲学ドブで眠る(1929年)<徳川夢声・岡田時彦・古川緑波>「これが大変ノンダクレで、毎晩ヘベレケになって」(「日本俗語大辞典」 米川明彦編)
阿佐ヶ谷会
外村繁は将棋会の幹事でありながら、勝負には加わらなかった。本人は幹事だから加われないと強調したが、もし出場していたら最下位まちがいなしだったという。戸村のお目当ては、その後に開かれる酒宴だった。青柳瑞穂は、将棋をぜんぜん指さなかった。が、将棋会には必ず参加して、雑務係を引き受けていた。彼もまた、仲間といっしょに酒を飲むのを楽しみにした人である。太宰治は「阿佐ヶ谷会」となると、その日は朝から落ち着かなかった。たとえば午後五時から始まるというのに、三時には井伏鱒二を誘いに来る。が、家には入ってこず、家の前を「えへん」「おッほん」と、彼の存在を井伏が気づくまで咳ばらいを続けながら、何遍でも行ったり来たりしたという。上林暁もまた落ち着かない組で、「阿佐ヶ谷会」には早目にやって来て、こう語ったという。「阿佐ヶ谷会というと、朝からそわそわして、落ち着かず何も手につかないんだョ」とにかく阿佐ヶ谷界隈の文士たちは、一堂に会することを楽しみにした。将棋を指し、酒を飲み、雑談をする。これがすべてだった。この会には、まったく堅苦しさというものがなかった。(「阿佐ヶ谷界隈」 村上護)
ジャワの日本酒
日本酒がジャワあたりに来ている英国人や蘭人たちの間で愛好されたらしい記録は、すでに二百年くらい前の弘化年間に日本へ来たツンベルク(ツンベリー)の紀行に見られる。この人はスウェーデン生まれで有名なリンネの跡を継いでオランダの大学の先生になった。日本へ来た蘭船の帰りの積荷に酒を、当時ワインの足りなかった、ジャワあたりの西洋人のために積んだようである。日本酒のコハク酸の味がシェリーなどの代用をつとめたのかも知れない。近頃世界的に人気のあるシェリーなども昔は料理用が多く、これを飲むのは世界中で英国人に多く、昔の日本ではシェリーの愛好者はイギリス帰りと知られていたものである。(「愛酒楽酔」 坂口謹一郎)
ある程度飲んでやめておく
大岡 日本お酒は酔うための酒か、それとも例えば良寛の酒みたいな、あの人は酔っぱらっている状態の歌って何にもないんですね。だけど酒なしにはいられなかった感じがするぐらい、とにかく酒の蓄えがなくなると、自分のパトロンの一人がお米屋さんで、そこに女中さんがいて、女中さんに手紙を出して、黄金の水を一寸…。そうすると女中さんがぶつぶつ言いながら、仕方がないわね、でもしようがないわって持ってきてくれる、というようなことがしょっちゅうあったみたいですね。それでいくと、酒は絶対必要なんだけれども、良寛は酒を飲んで酔っぱらうためとか、そういうことは何もないのね。むしろ頭が冴えてくる。飲んで頭が冴えてくるということは、生理的にはないと思うけれども、でも、酒飲みの状態としては、そういうことってあるんですね。ある程度飲んでやめておくという状態はすごくいいんですね。坂口謹一郎さんの酒がまたそうなんです。
網野 そう思いますね。
大岡 そういう酒の飲み方というのは、非常に日本では上等な酒飲みという感じがある。麻薬で酔っぱらった状態になるというのと正反対なものを指向しているような気がしますね。
松岡 そうですね。雪舟が絵を描くときにやっぱり酒を飲むんですよ。もちろん前例があって、北宋の「宣和(せんな)画譜によれば、王洽(おうこう)という人が酒を飲んで描いた。これは、沈酣(じんかん)して描いた、つまり酔っぱらっちゃって描いたというんですけれども、雪舟の場合は半器に酒を酌むような、半分ぐらい酒を飲んで、それから尺八を吹いて、歌を歌って、漢詩を朗吟して、それからいよいよということで描いていくというんですね。
大岡 精神集中の一つのテクニックなんですね。(「座談会 酒の日本文化」 大岡信・網野善彦・浅見和彦・松岡心平)
畠中頼母(銅脈先生)(2)
そこで何はともあれ酒。銅脈先生の最初の戯文は、『片仮名世酔記』と題する小冊子に始まる。第二狂詩集『勢多唐巴詩(せたのからはし)』の出た翌年、明和九年(一七七二)の刊行。当時二十一歳の著者の筆にかかるこの狂文は、全編これ古今の酒に関する知識を網羅し、酒の徳を讃える書である。著者の戯号は樽見無底、序には平原督郵銅脈の名を記す。平原督郵とは『世説新語』の故事からでて悪酒の意。いずれも酒にゆかりの狂号である。序にいわく、「亡底(ソコナシ)先生嘗テ曰ク、浮世ハ是レ三分五厘。乾坤ノ間、唯酒有ラバ足レリ。願ハクハ天ニ在リテハ酒星ニ流(ヨバ)イ、地ニ在リテハ酒泉ニ臨マン。鐘ヲ被リテ釣瓶落シニ死シテモ何苦之有(クルシフゴザイマセヌ)ト。遂ニ世酔記一篇ヲ著ハシテ予ヲシテ之ガ序ヲ作ら令メント欲ス。」思えば、その銅脈が『勢多唐巴詩』の序中で、「世ヲ挙(コゾ)ツテ皆醒めたり。我独リ酔ヘリ」と反語的にうそぶいたのは、前年の明和八年のことであった。人間は時として醒めるために酔うことがある。酔いのうちにのみ顕現する何か冴え冴えとしたものを求めて痛飲することがある。銅脈はたしかに酒中に韜晦したにはちがいない。しかし同時にまた、酒宴たけなわにいたってもなお自分が韜晦しているという意識が念頭から去らなかったのではないか。(「江戸人の昼と夜」 野口武彦) 畠中頼母(銅脈先生)
初代川柳の酒句(10)
神酒(みき)をすゝめて 手習子 いとま乞 眠狐 寺子屋の卒業風景
耳だらい あけたを下戸ハ おんにかけ 鼠弓 大きな耳ダライで飲めと言われた下戸を助けて飲んでくれた
下戸の礼 棒であるひて 帰る也 亀遊 下戸は新年の挨拶でべろべろ
梅屋敷 まだ生酔の 顔を見ず 五雀 梅の季節は寒くて酔えない
下戸が出て 弐百引ヵせる 初鰹 十口 悪い鰹に酔うという表現があるので値引きを交渉(「初代川柳選句集」 千葉治校訂)
世代別消費 団塊の世代は酒飲み 総務庁「家計調査」より
●団塊の世代は家への支出が多い
家計調査をもとに1968年以降の酒類消費支出を見ると、現在50~65歳の世代が、常にほかの世代よりもお酒に多く支出してきたことがわかる。
●1980年代後半から始まる若者の"酒ばなれ”
世帯主が35歳未満の世帯では、1988年をピークにお酒への支出が減少している。ちょうどバブル景気のころだ。ほかの年齢層では、その後も支出が減っていないことから、1990年前後に若者の“酒ばなれ”が始まったといえそうだ。
●65歳を境にお酒が減る?
年をとるとお酒が飲めなくなるというが、家計調査でもその傾向ははっきり見られる。どの時期を見ても、65歳を超える世帯では酒類への支出が平均を下回っている。(「酒席に役立つ読む肴」 酒文化研究所編) 2001年の発行です。説明の基礎になる統計に記載された最後の年は1998年です。
蓴菜(じゅんさい)
面白く塗ばしすべる蓴(ぬなわ)かな 一我
古名ヌナワは「沼縄」の意で、水面の若葉を引くと、ぬらぬらとした若茎が長く縄のように引かれて出てくることからの命名である。『万葉集』や『古今集』『延喜式』にも登場し、食用の歴史はかなり古い。箸休めの外、汁の実、酢みそ和(あ)えにしても、酒客によろこばれる。(「にっぽん食物誌」 平野雅章)
○酒好
酒がの(飲)ミたいか、銭がないとくやむゆへ、女房きのどくニ思ひ、髪(かミ)の内をくるりとそり、(十五オ)廿四文ニ売、酒を買、ていしゆ(亭主)ニ出ス。是ハどうふして買たといへバ、余りおまへかの(飲)ミたいといわしやるゆへ、此通と、中そりをみせれハ、扨(さて)もそちハしんせつなものと、なみだを流しながら、まだ十六文ほどハ有(「茶のこもち」 武藤禎夫・編)
洗米
白米を水洗することで、白米の表面に付着するぬかを除くことを目的とするが、洗米中に白米の表面が摩耗し、二次精米の効果を兼ねており、その量は白米の1~2%といわれる。また、カリウム、蛋白(たんぱく)質等が流出し、約20%の水分が米に吸収される。大正年間には手洗い、足洗いが行われ、米とぎ唄を歌いながら70回、50回、30回といわゆる七五三洗法で行った。手洗いから機械手廻し、次いで連続洗米機、ソリッドポンプが使われるようになった。ソリッドポンプは洗米と同時に輸送を行うことができる。洗米の水量は通常白米量の3倍から10倍量である。(「改訂灘の酒用語集」 灘酒研究会)
漱石の酒句(4)
明治三十二年 正岡子規へ送りたる句稿 その三十二 元日屠蘇を酌んで家を出づ
金泥の 鶴や朱塗の 屠蘇の盃
正岡子規に送りたる句稿 その三十五 十月十七日 修学寮
頓首して 新酒門内に 許されず
明治四十年 十月『日本美術』
酒買いに 里へ下るや 鹿も聞き
手帖の中より 二十九句
門に立てば 酒乞ふ人や 帽に花
大正三年 手帖の中より 百十四句
酒の燗 此頃春の 寒き哉(「漱石全集」)
「こだわりの店」の担当者
「こだわりの店」の担当者は、多くの場合、新人の編集者である。これは、その編集者に「旨い物」を食わせながら、ベテラン・ライター(つまり私というオッサン)に編集部だけでは身につかない人との付き合い方や社会を外部から教育して欲しいという編集長の思惑だと私は思っている。だから、難しいと思う店は、わざと交渉をやらせる場合もある。このコラムを担当してきたことで、現在担当の板谷君の編集者としての腕は、確実に進歩してきたと思う。(「東京居酒屋はしご酒」 伊丹由宇)
はなのまく【花の幕】
花見の宴に張り回はす幔幕。蕪村の句に『花の幕兼好を覗く女あり』とある。
内々で茶碗のくゞる花の幕 酒をあけた茶碗
大詰は生酔の出る花の幕 幕に大詰の結び(「川柳大辞典」 大曲駒村編著)
ぶどう
「ワイン」という言葉はラテン語の「ウィヌスム」、ギリシア語の「オイノス」に発しているが、その原型である「ウォイノ(ス)」という言葉がどこから出たかは明らかではない。しかしごく古くに地中海沿岸か、地中海の島々に住んでいた人たちが使っていた言葉に相違ない。ブドウ酒の母体であるブドウはギリシア語でポトリュスといわれるが、これもオイノスとともに外来語とされる。ではブドウが最初に栽培されたのはどこだろうか。植物学者★ドゥ=カンドルは今日のブドウ自生地(地中海沿岸各地)から推定し、その発生地はカフカス・カスピ海南岸のあたりとしている。しかしごく古い時代にギリシア人・ローマ人に伝えられ、ブドウから作られるブドウ酒が愛好されるようになっていった。ところでギリシア語の「ポトリュス」の起原は古いイラン語ではないかと考えられるが(中世ペルシア語ではブドウ酒を「バーダグ」、今のペルシア語では「バーデハ」というのと関係があると考えられる)」、この呼称は中国語に入って「葡萄」、すなわち日本に入って「ぶどう」となったらしい。なお、日本には七一八年(養老二年)に僧行基が伝えたという。
★ドゥ=カンドル(一七七八~一八四一)-スイスの植物学者。植物自然分類法を著わす。(「世界風俗じてんⅡ 衣食住の巻 アジア」 矢島文夫他)
いっとちゃん
ともすれば1ヵ月のうち半分は、スーツケースを片手に旅しながら、日本各地のあちらこちらで呑み歩いている。その多くは、正真正銘、れっきとした仕事だ。仕事なのだから、一生懸命に呑まなくてはならない。酒蔵や朝市の食堂で、早いうちから酒気帯びとなるのは珍しくない。アルコールを摂取しても顔が赤くならないため、機会が許されれば遠慮なくたっぷりいただく。ときには許されなくとも、こっそりと。夜は新たな美酒との巡り会いを求め、熱心に居酒屋のはしfごを重ねる。ぐうたらな性格だが、こと酒に関しては、努力を惜しまない。メチルアルコール以外、なんでもウェルカム。呑めば呑むほど、元気が湧いてくる。二日酔いは、これまでの人生においてほぼ皆無。どんなに呑んでも食べても、翌朝は空腹で目覚める健やかで強靱な胃腸が自慢だ。したがって、記憶の一部が失われて少々の不安を覚える(ちゃんと支払ったかしらなど)以外、呑みすぎに対する反省はない。巷では、一升一斗の「いっとちゃん」と呼ばれている。というのもかつて、取材やイベントなどが重なり、1週間で文字通り一斗の酒量を達成したためだ。とりわけ頑張ったワケではなく、ごく自然の積み重ねだった。ちなみにγ-GTPの数値は、基本的にヒトケタ…。(「ニッポン「酒」の旅」 山内史子)
土佐日記
古くは平安時代前期の歌人、紀貫之(きのつらゆき)が著した『土佐日記』に、土佐人の酒宴好きを垣間見(かいまみ)ることができる。仮名文字で書かれた日記は、承平(じようへい)四(九三四)年十二月二十一日から、翌年二月十六日に京へ戻るまでの五日間の旅が綴(つづ)られている。紀貫之は帰京の旅に要した日数の半分以上を土佐の地で過ごしている。土佐国府(現在の南国(なんごく)市)から土佐湾に沿って海路で東に移動し、室戸(むろと)岬の手前にある室津(むろつ)港を目指す。土佐湾の海岸線の三分の一ほどの行程となる。距離の割には移動日数が甚だ多い。けれど、単に海が荒れての足止めばかりではない。手間取った最大の理由は、「餞(はなむけ)」と称する送別の酒宴が連日のように催されたからだ。果ては、舟航中に酒肴(しゆこう)を持って追いかけてくる者や、舟へ差し入れする者までいた。国司の任を終え、人格的円熟期にある紀貫之といえども、土佐流のもてなし攻勢に呆(あき)れ気味の様子を匂(にお)わせる。また、貫之は土佐国での在任中、最愛の娘に先立たれている。そんな痛哭(つうこく)の思いを秘めた歌仙・紀貫之に対する人々の人気は高まり、送別会へ押し寄せたことが想像される。師走(しわす)から年明けにかけての日記は、漢詩や和歌の記述が増え、歌人らしい側面を見せている。けれども下手な歌を詠む大人に興ざめさせられるかと思えば、歌の上手な子供が座を沸かせたりと、おかし味を込めての日記内容。とにかく室津から出港する一月二十一日まで、風流と酔いのカオスが混在する土佐流送別会は続いた。(「酒は人の上に人を造らず」 吉田類) 土佐日記
大衆食堂
大衆食堂は大衆酒場と同様に、下町や工場が近い街に多い。浅草の「水口」、町屋の「ときわ食堂」、そして立石の「あおば」がその数例である。また、筑地の魚市場周辺にも「呑める食堂」が数軒あり、仕事を終えたばかりの男たちが朝から酒を呑んでいるのをよく見かける。競馬場・競艇場・競輪場周辺の「おけら街道」にも、呑み屋の間に大衆食堂があり、メニューの「カツ」を「勝」に書き換えていたりする(カビが生えた洒落(しやれ)とは言え、場内に入る前ならまだ笑えるかもしれない)。立地はどこであろうと、「食堂」や「定食屋」を自称していようと、呑んでいる客にとっては、けっきょく「呑み屋」である。当然のことながら、酒を呑まずに普通に定食を食べに来る客もいる。どちらも歓迎されるところは(たいていの)居酒屋とは違うし、またその違いこそ大衆食堂のおもしろみのひとつだと思う。とりわけ下町にあるような大衆食堂では、定食を食べている親子のすぐ隣のテーブルに、競馬新聞を凝視しながらハムカツをつまみに酎ハイを呑んでいる男もいたりするわけだから、通常の呑み屋に比べて客層は広い。各自がマイペースで別々の世界を占めている。そのように重層的な時空間で成り立っているところが、大衆食堂の魅力のひとつだと思う。多様な客を受け入れ、それぞれのニーズに応える柔軟性および寛容性が、大衆食堂の特徴だというわけである。
再び酒を飲み初め
父はやっと健康をとりもどしたらしい容子に見えたが、同時にこの頃からまた、ふと酒を飲み初めるようになった。家に帰った当座の父は「煙草だけはどうも廃(や)められないが、酒だけは、これがいい機会だから、こんりんざい、もう廃(や)める」と断言して、母を感激させ、母はうれし涙をながさぬばかり、その事をぼくらに迄何度も告げてよろこんでいたが、それが結局、つかの間だったわけである。「おいく、もう二合ばかり買いにやれ」とか「おいく、もう一本つけろ」とかいう、ありきたりな大酒癖の常套語が、毎晩の貧しいランプの灯が、気のひけるほど石油を吸うのが同じように、毎夜、母の財布に血を絞る思いをさせた。それでも「はい」と云う返事しか知らないような母は、勝手の小暗い隅にたたずんで、明日の米代としている小銭を悲しげに数えた。そして小銭と酒瓶とを持たせられて、ぼくは毎度、夜更けてからも使いに行った。晩秋の薄ら寒い風の中を、酒は手に抱いて帰りながら、焼芋屋のあたたかそうな煙は空しく横目に見て、そして家に帰れば、母は手内職の夜なべをしているし、ぼくも小さい弟妹たちも空き腹でいるのに、父ばかりが飽くなき独酌をつづけて居、しかも何か鬱々と不機嫌を内に溜めている姿を見ると、子供心にも、父の矛盾と非情に、堪らない不平を掻き立てられた。こうして父へのあきらかな反抗心を知ったのは、父が再び酒を飲み初めて、母の苦しみを加速度にして行った頃からのことであった。(「忘れ残りの記」 吉川英治) 或る日の酒父像
アジの焼きサンガ
作り方
①三枚におろし(-)、皮を取ったアジを細切りにする。
②長ねぎとしょうがはみじんに切り、味噌とアジを混ぜ合わせる。器に平らに盛り、焼き網にかぶせて表面を香ばしく焼く。
材料(2人分) アジ(刺身用)…2尾 長ねぎ…1/4本 しょうが…1/2片 味噌…大さじ1
このつまみに、この一本 西の関 美吟純米/大分 日本酒度…±0 酸度1.4 価格…5540円(1.8l)●燗をすることで、さらなるコクが生まれる酒。口あたりはさわやかで、のど越しには、軽い苦味が残る。甘さ、辛さ、酸味、苦味、渋みの五つの味が、絶妙のバランス醸し出す。(三献)(「新・日本酒の愉しみ」 堀部泰徳編集人)
果(くだ)物さかな
木の実などや酒のさかな。木の実などを、酒のさかなにした。清少納言(せいしようなごん)の『枕草子』に、<殿の御(お)前に、宮司(みやづかさ)召して、「果物、さかななど召させよ。人々酔はせ。」など仰せらるる。まことに皆酔ひて、女房と物言ひかはすほど、かたみにをかしと思ひためり。>とある。(「飲食事辞典」 白石大二)
損だけど
夢中で話しても、泥酔後だと忘れていることが多いので、おんなじ話を何回もしたり、おんなじ質問を何度もしたりすることになる。私の友人たちはみなこういったことに寛容だが、一度友人に、「なんだか前に話した時間が存在しないみたいでさみしいね」と、(嫌みではなく)しみじみと言われたことがあって、本当にそうだ、と思った。話しても話しても、あるところに戻ってしまう。初対面の人と盛り上がったのに、盛り上がった部分だけ覚えていなくて、次ぎに会うともじもじしてしまうことも多い。そういうとき、双六で後戻りしている気がする。人より確実に損をしている。でもしかたない。必要なのだから。そして混沌としたいくつもの「覚えていない」泥酔時間を思い出すと、覚えていないながら、なんとはなしにしあわせな気持になってくるのだから、うん、酒が飲める大人になってよかったと思うことにしておこう。(「泥酔懺悔 損だけど」 角田光代 )
マルセウ本間商店
しっかりした酒を仕入れるには、いい銘柄を揃えていて熟成にも理解がある小売店となじみになる必要がある。私が最近一番懇意にしているのは、笹塚の十号通り商店街にある「マルセウ本間商店」である。本間さんは、石数が大きく有名な蔵元の銘柄は置かない。造りのしっかりした小さな家族経営の蔵元を大事にし、何度も蔵を訪問して親交を深め、酒の意見交換を行い、消費者と蔵元をつなぐパイプ役になるという明確なポリシーで商売している。(「蕎麦屋酒」 古川修)
松ちゃん
松岡(きっこ) それから博多に行くたびに行くのは、中洲の入口で、屋台の「松ちゃん」。
鈴木(三郎助」) 行ったことない。
松岡 そこでは良いものしか置いてないんです。お肉もお刺身用、生きている海老しか置かないし、一流の料亭でいただくものと同じです。「今日はカレイがいいよ」とまだ生きてピンピンしているのを見せてくれる。この店の蓮根はなぜかおいしいんですよ。蓮根を天麩羅にするんですよ。
鈴木 人見知りするんじゃないかな。僕なんかが行くと、今はないよ、といわれるかもしれない(笑い)。そんな店に限って料理はうまい。
松岡 すごく偏屈で、お酒をあてにしてくる人には、予約だから、といって断るんです。おいしいものをおいしく食べてもらいたい、そのついでにお酒を飲んで、という人は歓迎するんですが、お酒が第一で料理は何食べても同じという人はだめなんです。私がいる間に四組くらい、今日はすみません、と断りましたよ。なかには、「お酒ある?」とくる人には、「うちはお酒置いてないよ」(笑い)。偏屈ですね。(「友あり 食あり また楽しからずや」 鈴木三郎助対談)
周 BC一一〇〇頃 『周礼』の食物関係官職名の主なもの 酒正(酒官の長) 酒人(酒造を司る)(「一衣帯水 中国食物史年表」 田中静一)
酒が語る日本史
山口さん、富士さん、高橋さんと酔話の極意ばなしがつづいたが、和歌森太郎氏の『酒が語る日本史』(河出書房新社刊)は、酒に関する教養書といっていいものである。この日本史は、古代貴人の酒、平安公卿の酒、源平武将の酒、信長と秀吉の酒、元禄太平の酒、酒に徹する奇人たち-と目次を拾っても、なかなか魅力的な内容がつづく。これは、題名通り、酒をポイントとした日本史である。酒がどんな飲まれ方をしたのか、どんな人が酒豪であったのか、エピソードの積みかさねでこの本は成り立っているが、それがまことに手ぎわよくまとめられている。わかりやすいのもよい。例えば-上杉謙信は酒豪であった。一応酒盛りがすむと、別の部屋に、相手によい武将とつれだって入り、二次会を開き、三合入りくらいの大盃で酒を愉しんでいたという。その大酒のたたりで、せっかく信長との対決のため出陣準備をととのえていた天正六年(一五七八)に、脳卒中で、厠のなかでたおれてしまった。謙信が二次会が好きだったとは面白い。(「作家の食談」 山本容朗)
がんもどき
お酒はあびるほど好きでも、絵についてお酒をあがらんことがあります。五代目菊五郎の「茨木」を描かれた時、翌日もう一遍その絵を観たいと、自分の描いた絵を見直しに見えたので「サァ御酒」というのを「今日は何といっても飲まない」とお茶でとくと一覧、手落ちのないのを確かめて帰られたというお話です。総州の景色がお気に召して、新川の鹿島家の茶室の襖へ描かれた時も、お酒を寄せつけず素面で描かれました。この襖のはがしが後に百五十円もしていました。先生はどんなに酔っ払って夜遅くお帰りになっても、朝の間にしっかりした絵を描かれました。お酒は剛の者でしたが、喰べ物は少しもお構いなくお好きな物はがんもどきなんですよ。ですから毎朝本膳のお平を拵え、長芋、椎茸、がんもどきをおつけするんで全くお好きでした。夜遅く朝早く、奥さんは寝る間がないといったあんばいでした。(「河鍋暁斎」 落合和吉編)
中山千夏
中山千夏と『話の特集』の編集長・矢崎泰久、放送ジャーナリストのばばこういちはいずれも私の親しい仲間だが、この三人が麻布のレストランあたりで会食している姿は、まことに面白い。矢崎、ばばの両氏は全くの下戸である。、千夏ちゃんといえば痛快なる飲み助なのだ。上物のワインなどを抜いてグイグイいっている中山千夏の前で、うんざりした顔でジンジャーエールなどを時折り口に運ぶ中年というよりは初老の二人の男は、遅れて参加した私の顔を見たとたんに、ほとんど絶望って顔になる。ご機嫌になりはじめた千夏は、下戸を相手じゃ話にならないと思い始めていたところに私である。喜色満面で「飲もうよ」ってことになる寸法。矢崎・ばば両氏は「こりゃダメだ」と眉をしかめるのである。「飲んべえは(時間が)永くてやだよなァ}矢崎・ばばの両氏の気持ちもわからなくはないが、酒の楽しみ方に無縁とは、なんとも哀しい話ではないか-と同情しきりでもある。(「いい酒いい友いい人生」 加東康一)
梅酒(うめしゆ) 梅焼酎
焼酎に実梅や氷砂糖を入れて製した酒。甘く爽やかで夏日の飲に適する。暑気中(あた)りや下痢に効果があるともいう。一般に「梅酒」というが、「梅焼酎」ともいう。
梅酒嗜(たしな)む幾分しのぎよき日なり 及川貞
雨の日々梅酒色よくなりにけり 鳥越すみこ子
妻留守のさがす梅酒の置きどころ 土方秋湖(「俳諧歳時記 夏」 新潮社編)
国民的勝利 ブリア・サヴァラン 関根秀雄訳
いよいよデザート。それはバタとチーズとココア豆とヒコリ(インド産くだもの)とであった。ここがいよいよ乾杯の時期で、われわれは王様の権威のために、人民の自由のために、また婦人の美しさのために大いに飲んだ。特にウィルキンスン氏のためには、かれがジャマイカ島第一の美人だと自負するかれの娘マリアの健康を祈った。ぶどう酒の次にはいわゆるスピリッツ、すなわちラム酒を初めいろいろなブランデーが出た。スピリッツが出るとともに放歌高吟、いよいよたいへんなことになりそうだった。わたしはかねてこのスピリッツを心配したので、それをかわしパンチを求めた。リットルじいさん自ら前もって用意してあったのだろう、ボールに一杯それを持ってきた。それは四人分くらいはいりそうなやつで、フランスではこんなばかげたでかい器は使用しない。それを見るとわたしはまた元気が出た。きわめて新鮮なバタを塗った焼きパン五つ六つ食べると、にわかに気力が出てくるのを感じた。そこでわたしはあたりをながめまわした。まったくわたしは、最後はいったいどんなことになるかと、そろそろおもしろくなってきたのである。仲間のふたりはかなりけろりとしている。かれらはヒコリの実をつまみながら飲んでいた。ウィルキンスンは赤黒い顔をし、どろんとした目つきでもう相当参っているらしく見え、その友のほうは黙ってはいるが頭の中は煮えたぎったなべみたいらしく、大きな口は雌鶏(めんどり)のしりみたいだった。私はいよいよカタストロフィーが近づいたぞと思った。実際ウィルキンスン氏は、はっと目がさめるといきなり立ち上がって、かなり大声で『ルール・ブリタニカ』を歌いだしたが力が続かず、どかりと一ぺんいすに腰をおろすと、そのまま食卓の下に伸びてしまった。それを見るとかれの友人は何やらわめきながら、かれを助けおこそうとかがんだなり、これまたその場にころがってしまった。この突然の結末を見、それまでの緊張が解かれて、わたしがいかにうれしかったかそれは言葉に尽くせない。私はベルを押した。リットルが上がってきた。型どおり「これらの紳士がたを十分介抱してあげてください」と言いつけたうえ、われわれはパンチの最後の一杯を干した。やがてウェイターがやって来て、みんなしてthe
feet foremost*のおきてに従い、かれら敗残者の足をつかんで連れて行った。友人のほうは死んだように動かなかったが、ウィルキンスン氏の方は絶えず『ルール・ブリタニカ』を歌いかけた。 *the
feet foremost(足を先につかんで)というのは、英語で死体や酔漢を運ぶ時に使う慣用句である。(原作者注) 翌日ニューヨークの諸新聞はかなり正確にその晩のありさまを報道したし、それを次々に転載した諸新聞も事件以来ふたりのイギリス人が病気でいると書き添えていたので、わたしはかれらを見舞にいった。友人のほうはひどい消化不良のためにぽかんとしており、ウィルキンスン氏のほうはひどい神経痛が起きて寝台にしがみついていた。たぶん飲みすぎのために持病が再発したのだろう。かれはわたしの見舞いの言葉に感激しいろいろと言ったが、特にこんなことを言った。「おお、あなたはほんとうに親切な飲み友だちです。だがわれわれにとってはあまりにお強すぎますよ。」《Oh!
dear sir, you are very good company indeed, but too hard a drinker for
us.》[訳者 せきね・ひでお(一八五九-)仏文学](「酔っぱらい読本・弐」 吉行淳之介編) ニューヨークでサヴァランがイギリス人に飲み比べを挑まれた話です。
一寸能い処あり
歌舞伎座はこの月、「井伊大老の死」という中村吉蔵の新作を演じている。歌舞伎座は何かしきりに新作を試みようとしていたらしく、五月には坪内逍遙の「名残の星月夜」を出している。これはしかし何かと大向の看客の故意的な故障が入ったりして正しい評価を求めることができなかった。そのような邪魔があったにもかかわらず、六月には、すでにこの「井伊大老」上演を企てたのだが、「水戸側の抗議から」(東京朝日、五月三十日)一旦中止し、大改訂の後にこの七月左団次一座が小山内・岡鬼太郎監督で上演することになったのであった。原本は四月の『早稲田文学』に出たというから、気が早い、何か急いで探しているものがあったと感じられる。たぶん時勢が新しいものを求めていたのであろう。その芝居を見ていて、ちょっと風格が感じられて捨て難いと思ったところがあった。二幕目、左団次の井伊掃部頭と相手は寿三郎か猿之助かだが、何か喜ばしいことがあって酒杯に託してにっこりとするところの情誼の表現がまことに巧くいった、と思った。まもなく東京朝日新聞に出た竹の屋評を見たら、「左団次の大老盃を取り上げて一寸(ちよつと)能い処あり」と書いてあった。なるほど「一寸能い処あり」くらいが丁度良いほめ方と、感心したのであった。(「芝居むかしばなし」 福原麟太郎)
花岡技師
大正九年ごろの話。当時、有名人は必ず泊るといわれた秋田市の石橋旅館(昭和四十三年廃業)でも、"一流旅館"のこけんにかけて?酒は灘モノしか出さなかった。花岡正庸技師は、この石橋旅館に地酒を使うよう熱心に勧めていたが、なかなか「うん」といってもらえなかった。そこである日、こっそり女中に手を回し、なじみの酒好きな客に「両関」を出させた。女中はおっかなびっくりだったが、客の反応は、「うまい酒だ。明日、おみやげに用意してくれ」。報告を受けた主人も「あの客がうまいというなら、うちも灘酒をやめて地酒にしよう」ということになった。花岡技師のエピソードをもう一つ。大正十二年秋の県清酒品評会の夜、宴会を終えた若い酒造家たちが秋田の川反に繰り出すと、ある料亭の玄関に灘酒のコモかぶりが山積みされていた。「何で秋田の酒を使わない」と怒った花岡技師は、コモかぶりを道路に投げつけ、料亭の玄関を酒びたしにしてしまった。荒っぽい話だが、こうした情熱が、昭和初期までに県外酒を"追い出す"原動力になった。(「あきた」雑学9ノート」 読売新聞秋田支局編)
竜舌蘭の酒
「情熱の酒」と呼ばれるテキーラは、メキシコの酒。竜舌蘭(りゆうぜつらん)という大型の常緑草を原料につくられる。蒸留技術の必要なテキーラは、一六世紀、スペイン人がメキシコにいってからつくられるようになったが、それまで、この竜舌蘭からは、「二十日ねずみ酒」という"伝説の酒"がつくられていたという。その伝説によると、一〇〇〇年も前、ある人が竜舌蘭の幹(みき)をかじっている二十日ネズミをみつけた。不思議に思ってその後をつけると、ネズミの巣に山吹色の液体があった。なめてみると、なかなかうまい。そこで、他のネズミの巣からも、この液体を集めて保管しておいた。やがてこの液体が発酵し、むちゃくちゃうまい酒になった。それを国王に献上すると国王も喜んで、この酒の製造を命じたという。現在も中南米には、テキーラとはまったく別の、竜舌蘭の樹液を発酵させてつくった酒がある。(「酒場で盛りあがる酒のこだわり話」 博学こだわり倶楽部(編))
秋刀魚
夏秋刀魚は、私などには脂が多すぎてちょっと鬱陶しい。おまけに値段も高いしね。やっぱり、秋刀魚には秋がよく似合う。塩をふってしばらくおいて、出てきた水分を軽くふいたら、もう一度塩をして、あとはレンジのグリルで焼けばいい。グリルで魚などを焼くときは、前に立って目を離さないのが鉄則だ。これまでその場を離れて、どれだけいろんなものを黒焦げにしてきたことか。ひっくり返したら、いそいで大根をおろす。スダチも切らなくちゃ。さあ、焼けたぞ。身が崩れないように用心して器にのせて、おろしとスダチを添えたら完成だあ!さあさあ、まずはどてっぱらのど真ん中を一口。うん、新鮮で熱々。ビールがうまい。次いで、ワタにいく。秋刀魚はワタを入れたまま焼いて、ワタごと味わえるのがうれしいね。秋刀魚のワタは、胃袋と肝臓に大別できるが、胃袋には、網で獲られたときに暴れてはがれたウロコを飲み込んだのが入っていることが多いので注意が必要だ。アレが口に入ると非常に興ざめだから。箸の先にワタをつけてチビッとなめる。ほろ苦さとコクがあいまって、思わずうっとりする。これはもう日本酒しかない。というわけで、広島の『白鴻』の純米吟醸を常温で。秋刀魚の時期というのは冷えた酒とお燗の中間、常温がいい。日本酒を含むと、はらわたの苦みとコクがさらにふくらんでいっそう美味い。あとは、おろしとスダチとワタと身を好きなように組み合わせてグイグイ飲む。ああしあわせじゃあ。(「晩酌パラダイス」 ラズウェル細木)
大根の酒粕煮
福光屋 中谷さんのお勧め
いろいろな野菜を粕煮にすることができる、応用のきくレシピです。
●(5人分) 大根 1/2本/酒粕 50グラム/薄口醤油 大さじ1杯/あさつき 適宜/だし汁 3カップ/みりん 小さじ1杯/砂糖 小さじ1杯
●作り方 ①大根の皮をむき、乱切りにする。 ②だし汁で酒粕を溶かし、鍋に入れて大根が柔らかくなるまで、落とし蓋をしながら煮る。 ③薄口醤油、みりん、砂糖を加えて味を染み込ませる。 ④器に盛り、小口切りにしたあさつきを持ったらでき上がり。
◆かぶなどでもおいしい粕煮ができます。いろいろな野菜で試してみましょう。(「酒粕の凄い特効」 滝澤行雄監修)
うたびと 林富士馬(はやしふじま)
昔 詩人は酒と女とのために
その歌曲を残して死んださうだ
そして いま近代のうた人達は
貞淑(ていしゆく)な妻と 子供のために
繍綵(しゆうさい)の詩作を織りなしたさうな(「酒の詩集」 富士正晴編著)
[かすづけ瓜の作り方]
量にかかわらず石灰と明礬を入れた湯で煎じ、一昼夜冷水に浸しておく。沸かした酒を糟と塩に加え、更に銅銭百文ほどを入れてよくかきまぜ、十日ほど漬けておく。取り出して拭い乾かし、別に上等の糟と塩、沸かした酒をまぜて用意していれかえる。再びまぜてカメに入れて収め貯え、くまざさの葉で口を蓋い、泥で封をする。(「食経」 中村璋八・佐藤達全訳注)
山内容堂
維新後は官を辞し、ひたすらに飲み、連日、新橋、柳橋、両国の酒楼に出没して豪遊し、ついに家産をかたむきかけたが、「むかしから大名が倒産したためしがない。俺が先鞭(せんべん)をつけてやろう」と豪語して、家令の諫(いさ)めをきかなかった。(「酔って候」 司馬遼太郎)
ホームバー
その頃の梶原は、銀行にとってはまたとないビジネスチャンスを提供してくれるお得意さまである。主人の不在がちな梶原家に彼らは日参し、留守を守る夫人の篤子に新しい家の建設を勧めた。寂しい篤子が、その話に乗った。仕事場がネオン街に近いのをいいことに遊びまくる夫が、そうすることで帰ってきてくれるかもしれなかった。ホームバーも作った。そうすれば何も外で高い金を払って飲む必要はない、はずだったのだ。篤子の思いは、しかし梶原にはまったく届かない。むしろ逆効果だった。当時の風潮だった「マイホーム」という観念を生理的に嫌悪(けんお)していた梶原は、豪邸に反発だけを感じたらしい。『わが懺悔録』に、こんな記述がある。」<うとましいのだ。オレはとてつもないものをブッ建ててしまって、一生この家に縛られるんじゃないかという恐怖感をもった。(中略)オレはグラスを叩(たた)きつけて、「ホームバーで酒が飲めるか!」そのまま六本木に直行だった。結局、なんのかんのといっても、早い話がホームバーには遊ぶ女がいないということだった。あのころはひどかった。地元の大泉界隈(かいわい)で、クラブやキャバレーのめぼしい女は全部ものにした。二階に篤子たちが寝ている、この家にホステスを連れ帰り、いっしょに風呂に入ったこともあった。常識ではとても考えられないことをしていたのであった>梶原の暴力や理不尽な浮気に堪えかねて、篤子はやがて家を出た。女友達の部屋で鎮痛剤に酔っていた篤子は、一度は連れ戻される。が、梶原はなお仕事に女に多忙で、雨降って地は固まらなかった。軍艦御殿には家出の前と同じような生活の繰り返しがあるだけで、篤子の心は癒(いや)されることがなかった。貰(もら)ったダイヤの指輪などをベッドの上に置いて、再び家を出た。二人の間にはすでに四人の子どもがいたが、昭和四十七年十一月、梶原一騎こと高森朝樹と篤子は正式に離婚した。当初は裁判沙汰(ざた)になりかかり、篤子の弁護士は六千万円の慰謝料プラス毎月の養育費が妥当と試算した。が、争いを嫌った篤子は話し合いに持ち込み、その結果慰謝料は四百万円だけが支払われた。(「梶原一騎伝」 斎藤貴男)
ガスライト・クラブ
もちろん禁酒法時代の様子は、古いアメリカの映画を見て想像するくらいであるが、似たような状況を垣間見させるような酒場があった。私がニューヨークで働いていた一九六〇年代によく通ったガスライト・クラブという会員制のクラブである。いわゆるキークラブの走りといわれていたが、会員は入口で実際に合鍵を使わないと中には入れなかった。ウエイトレスは水着風のコスチュームを着ていた。プレーボーイ・クラブがはじめたバニーガールのコスチュームは、ガスライト・クラブからヒントを得たものだといわれていた。クラブの中には、それぞれに趣向を凝らした部屋がいくつかあったが、最も人気があったのは「スピークイージー・ホーム」といわれるところだ。スピークイージーというのは、禁酒法時代のもぐりの酒場のことである。その部屋は最上階にあったが、扉をノックすると、小さなのぞき窓が開いて「誰がお前をよこしたのか」と聞かれる。それに対しては、合い言葉である「ジョー」の名前をいわないと、鍵を開けてくれない。名前を度忘れしたら、いくら懇願しても絶対に中には入れてくれない。中はまさに「喧噪の巷」である。それほど広くない部屋に低いステージがつくってあって、そこで生演奏している。トランペットやドラムなどの音は耳をつんざくばかりで、注文をするにも大声を張り上げなくてはならない。そこではドライマティーニであれスコッチ・オン・ザ・ロックスであれ、すべての飲み物は、白い陶器のマグに入れられる。警察の手入れがあっても、さっと飲み干してから、ミルクを飲んでいたといえるようにというアイデアだ。ショータイムになると、四、五人のウエイトレス全員がステージに上がってくる。音楽がはじまると早速に、一九二〇年代にアメリカで流行したチャールストンを踊る。彼女たちは皆いわゆる「フラッパー」風のドレスを着ている。スカートの部分が蛸の足のように線状に切れていて、激しく蹴るように踊るとひらひらする、チャールストンにぴったりのドレスである。外の世界とはまったく異なった一九二〇年代の禁酒法時代の不法な酒場を演出していたのである。隠れて飲むという雰囲気をつくることによって、酒を飲むことが一段と楽しくなったのである。よく「盗み酒はおいしい」などというが、それと一脈通じるところがある。(「酒を味わう 酒を愉しむ」 山崎武也)
ずいぶん手が上がって
「お正月の上に今日は宮様(高松宮宣仁)の御誕辰(ごたんしん)。お姉様(喜久子 高松宮妻、榊原喜佐子姉)濃紺の御洋装。お話しするうち)久美(喜佐子妹)様おいで。宮様も還御(かんぎょ)あそばされる。御祝酒三人にていただく。三笠宮様両殿下お成りにてお辞儀申上ぐ。お酌までしていただき、しばらく同じテーブルにてお話。お菓子など召し上がってお帰りあそばす。それより両殿下と我々三人と、御祝いの御膳につく。お話もはずむ。お姉様を中心に姉妹三人並んでおしゃべり。宮様(三笠宮)と盛んにお話の殿様(高松宮)も大分よくお酒を召し上がる。ずいぶん手が上がっていらっしゃるのでびっくり。『若い者の世、若い者出でよ』の話で皆大いに気勢上がる。が、宮様砲術学校の教頭におなりあそばしたとのこと。何ということだ。射撃のお稽古とはあまりにももったいない。惜しい!御力が埋もれて何とも申し上ぐべき言葉もない。中央へ!中央へ!必ず、若き世は来るであろうが…」(「徳川慶喜家の子ども部屋」 榊原喜佐子)
親の膳
中国の西端の山口県の見島には、親の膳という事が行われている。親の膳は、養子に出た息子や嫁に行った娘が、婚家から親元へ食膳とお神酒を贈ることである。正月・三月・五月・九月の節句と、大晦日に贈る部落もあるが、三月・五月・九月の節句と、七月の七日と、盆の十五日に贈る家もある。他家にくれた娘や、婿入りさせた息子の家から曲木の膳に、銚子一本・煮〆一皿・ボタ餅五つという風に、老いた親の口にかなう程のささやかな料理が届けられるのであるが、それを待ちかねる日の親の心には、想像以上のものがあろう。ささやかな隠居所にあぐらをかいて、「ばばあ××のはまだ来んか」と、一本ずつ捧げられる銚子を倒す事をこの日の楽しい義務にしているのである。生きている限り節日毎に親のやしないの膳を捧げてくれる子供の愛情に、子を育て上げるためばかりに終わった生涯の苦労も忘れられて、ただただ子を持った喜びだけが胸にせき上げてくるそうで、親の膳の数の多いのを誇りたい気持になるという事である。日支事変のはじまった年の夏、この島に渡って、親の膳のボタ餅を分けて貰って食べながら、もろ肌ぬぎになって、三人の娘から贈られた親の膳のお銚子と取り組んでいる老翁の喜びを眺めたのも、今ははるかな思い出になった。(「食生活の歴史」 瀬川清子)
ざぶん/どぼん/焼き鳥
日銀内部の隠語。裾に酒がかかるほどの軽い接待が「ざぶん」、文字どおりどぼんと身体ごと酒に浸るほどの高級料亭の接待が「どぼん」、融資を求める相手銀行にぎりぎりまで実行せず、いじめるのが「焼き鳥」。都銀などと日常的に接する業務局で七〇年代から使われている。「MOF担(モフたん)」に続く接待疑惑関連語。(「平成新語×流行語小辞典」 稲垣吉彦)
塩っぱい肴
ただ、吟醸酒だけを飲むようになったら、酒の肴に塩っぱいものを選ばなくなったのは事実である。酒の味が私をそうさせたのである。つまり酒が肴を選んだのだ。それが高血圧の家系なのに血圧を上げずにこれた原因の一つになっているらしい。私はその面でも吟醸酒に感謝している。(「「幻の日本酒」酔いどれノート」 篠田次郎)
一八才で離脱症状
私の所に一八才で、すでに離脱症状である手の震えや冷や汗が出現して、アルコール依存の状態で来た男の子は、高校に入学したものの学校の雰囲気が合わないと、しだいに学校へ行けなくなり、登校拒否の状態に陥った。一六才から、自分の部屋にこもったきり夜昼逆転の生活を送るようになり、起きている間はテレビゲームしかやらないという日が続きました。そのうちに家にあったお酒を、こっそり自分の部屋に持って行って飲むようになり、ビールやウィスキーも手当たり次第に飲み始めました。毎日ウィスキーのボトルを一本飲んでしまうという日が続きました。家にあるお酒では足りなくなり、お酒を買いに行く時だけ外出するようになったのです。親に酒代をせびり、母親が断わると暴力をふるってお金を出させ、それでも足りないので自分のファミコンソフトや果てにはファミコン本体まで売ってお金を作り、酒代に充てました。そうやって彼は自閉的に飲酒を続けることで、一年もしないうちに離脱症状、-が現れたのでした。このように、学校での何らかの挫折体験が発生した時に、子どもは引きこもりの行動を示すことが多く見られます。(「子どもの飲酒があぶない」 鈴木健二)
落書
同市(鹿児島県大口市)にある大口郡山八幡神社は一一九四年に建立された古い神社で、その後三六五年を経た永禄二年(一五五九)に社殿の改築が行われた。その時、工事にかり出された地元の大工と思われる作次郎と助太郎という人が、棟を上げる時に木板に次のような落書を書いて神社の屋根裏にはめ込んだ。 永禄二歳八月十一日 作次郎 鶴田助太郎 其時座主は大キナこすじをち やりて一度も焼酎を不被下候 何共めいわくな事哉(日頃からけちな座主は<神社改修の間>一度も焼酎をふるまわなかった。なんとも迷惑なことである)この落書は昭和三四年に同神社が改修された時、偶然に発見されたもので、その後しばらく話題にならなかったが、昭和四五年頃、醸造学者や郷土史研究者らの手によって、この落書がわが国の酒の歴史上、「焼酎」という字の初見であり、大変に貴重なものであることがわかった。一五五九年の時点で、すでに焼酎が、ふるまい酒として大工あるいは施主などに一般化していたとすれば、その伝来は木札に落書した日付の一五五九年をさらに遡ることになる。(「銘酒誕生」 小泉武夫)
至福の夜 後悔の朝
ススキノの真ん中にY※という店がある。のれんをくぐって引き戸を開けると、和服の粋な女将が笑顔で迎えてくれる。その笑顔もさることながら、飲み助のオヤジにうれしいのは、酒の肴(さかな)のあんばいが良いことだ。酒は「越乃寒梅」「雪中梅」などなど。焼酎も「魔王」「伊佐美」など、いわゆる「銘酒」と呼ばれる酒が決して偉そうでなく、普通の顔をして当たり前に並んでいる。さかなは板わさ、からし明太子(めんたいこ)、めざし、焼いた油揚げ、厚焼き卵、焼きみそ、それに昔懐かしいそばがきなどがちょこちょこ出てきて舌と心をくすぐる。そして、何と言ってもこの店のウリは女将自らの手打ちそばである。飲み終わって、そばを手繰って帰るころには、もう頭の中には「至福」の文字しか浮かばない。そば湯があるから、焼酎のそば割も楽しめる寸法だ。普通の居酒屋ではこうはいかない。先日もここで飲みながら、昔は酒の肴は油っこいものが好きだったのに、ずいぶん嗜好(しこう)も量も変わったものだと一人悦に入っていた。気づくとなぜか酔いが回っている。これはいかん、ついに酒量も落ちてきたのだろうかと慌てていたら、オンザロックで飲んでいた焼酎「宝山」の度数がウイスキーよりも強いのであった。「なんだ、これなら酔ってもあたりまえさ」と安心して杯を重ね、いつものように翌日後悔したのは言うまでもない。(土田)
※「夜噺庵」2007年1月に閉店。4月に移転オープン。 広島県広島市堀河町1-14第一レックスビル5階 電話082・249・4034(「さしつさされつ」 中田耀子・土田裕之)
陣鍋
文武の奨励は烈公の最意を用ゐたる所にして、天保元年、「文武は武士の大道なれば出精すべし」との諭書を一藩に頒ち、同三年には諸士をして海舟の乗りて鯨を銃撃し、以て海防の備を習はしめ、同八年よりは毎年二月十二日、自ら甲冑を著して東照宮の遺物を拝し、了りて藩士一同戎装して主君の前に出で、共に泰平を祝することゝ定め、之を小石川の後楽園に行ふ。此日は階下に陣鍋を設けて酒を温め、近侍の臣をして紅白の母衣(ほろ)を著け、長柄の銚子をもて之を酌みて諸士に賜はしめ、肴の如きも打鮑(うちあわび)・勝栗(かちぐり)を用ゐたるなど、全く戦陣の法に習ひ、治に居て乱を忘れざるの盛意を示さる。此式を始め行へる後数日にして、大塩平八郎暴発の警報府下に喧伝せしかば、人皆烈公が先見の明に服せり。十一年三月には追鳥狩を千坡原に行ひて、大に兵を練る、旌旗天に連り、鎧甲日に輝き、銃砲の声数里の外に聞ゆ、泰平日久しく上下安逸を思ふの時に当りて此挙ありしは、いかに一世を驚かしけん。(「徳川慶喜公伝」 渋沢栄一)
酒病偶作 二日酔ひして、ふと作る 皮日体
鬱林ノ歩障 昼 明(メイ)ヲ遮リ 森林の図の衝立(ついたて)で昼間に明(あか)りを遮り
一炷ノ濃香 病酲ヲ養フ。 一炷(ひとた)きの濃香で二日酔を静養してゐると、
何事ゾ晩来 還(ま)タ飲ント欲ス 何(どう)した事か夕方になると復(ま)た飲みたくなつた
牆ヲ隔テテ聞ク蛤蜊(カフリ)ヲ売ルノ声 垣根越しに蛤蜊(あさり)を売る声が聞こえる。
〇鬱林 未詳。鬱鬱たる茂林の図を歩障に描いてあるのか。 〇歩障 衝立(ついたて)のたぐひ。 〇蛤蜊 アサリのたぐひ。酒の肴にしようと云ふわけかも知れぬ。(「中華飲酒詩選」 青木正児著)
千紅万紫
狸酒かひに行かたかきたるに
払はずに としふるたぬき 酒かひに ゆくや化物 やしきなるらん
滝の画に、
さけかひに 李白や里へ ゆかれけん 三千尺の 長い滝のみ(「大田南畝全集」 浜田義一郎編集委員代表)
佐賀 九州にあって日本酒人気の地域
九州といえば本格焼酎の産地と思われがちですが、佐賀は日本酒蔵の方が多く、また県内での日本酒消費量も多い県。佐賀県産の米で造られた純米酒を対象にした原産地呼称制度管理を発足し、官民挙げて上質な純米酒を消費者に薦める活動も熱心に行っています。全国で知られる銘柄は「東一」「窓の梅」などに限られていましたが、一九九〇年代後半から「鍋島」「七田(しちだ)」「天吹き(あまぶき)」「万霊(まんれい)」などの新しい銘柄が立ち上がり、人気を集めています。また「鍋島」「七田」「天吹」「東一」「東鶴」の"サガン5"というグループ名で、イベントも行うようになっています。(「めざせ!日本酒の達人」 山同敦子)
じゅん菜(じゅん菜、三杯酢)
びん詰のじゅん菜をザルにあけ、よく水をきる。濃口醤油1、薄口醤油1/2、水5、酢10、砂糖(好みで)でだしを作り、コンブをひと切れ入れて火にかける。一度煮たったところで火をとめ、冷ましておく。これが三杯酢。じゅん菜を小鉢に盛り、だし(三杯酢)をかけ、好みでおろしショウガをのせる。三杯酢の作り方は、覚えておくといくらでも応用でき便利だ。一度煮たてるのが、プロのやり方。このあたりに手間をかけるのが、うまい酢の物で酒を飲むためには大切だ。よく冷えた酢の物は、酒飲みにはこたえられない舌ざわり。(「酒肴<つまみ>のネタ本」 ホームライフセミナー編)
466気はたしか
「お客さん、昨夜は真直ぐにお家へ帰り着けましたか?」電車の車掌が、馴染みの乗客に、ある朝、問い掛けた。「あ、ちゃんと戻れたよ、どうしてだい?」「だってさ、昨夜、貴方が立ち上がって婦人に席を譲られた時、電車の中には彼女と二人だけだったもんですからね…」(「」ユーモア辞典) 秋田實編
適正価格
おらも蔵に長くいるうちには、だんだんわがままになって、何かの拍子(ひようし)に、「おらとこの蔵は米が白いんだすけ、酒の値段もちっとぐらい、よその酒のよりも高くてもいいんでないかね」とこぼしたことがあるんだ。そうしたら、和雄さんに「馬鹿なこと言うな」って叱られたわいね。「酒というものは高くても売れないし、安すぎても売れない。手頃な値段が一番いいんだ」と言うんだわ。今になってみると、ほんとにそうだいね。高ければいいというもんでないし、安ければいいというもんでもない。造るほうも買うほうも納得するような値段が一番いいんだわ。だども、やる時にはやる人だったわいね。あれは昭和五十八年のことだったが、酒の値段も自由になっていたんですて、だすけ、自由に決められるはずだったのに、大手の酒蔵が値上げしないものだから、小さな蔵はとても値上げなんかできる状態ではなかった。そこへ、おらとこの蔵が全国の酒蔵の先頭を切って値上げを打ち出したものだすけ、大騒ぎになってさ。それもちょっとやそっとの値上げでないんだ。普通酒で一二〇〇円ぐらいのところを一八〇〇円ぐらいに上げたんだ。これには国税庁からも、どういうこんだという問い合わせが来たが、和雄さんは一歩も引かなかった。「おらとこの酒は原価が高い。合理化蔵とは違うんだ。酒もいい、原料でも何でも、元手をかけて酒を造っている。値上げしなかったら蔵が潰れる。酒の値段をあげると潰れるとあんたがたは言うが、同じ潰れるなら値上げして潰れたい」と説明してのう。その頃は値引きやリベートも横行(おうこう)していたんだわ。それで一番に値段をあげて、その後、日本中の酒蔵がついてきた。「値上げしなかったら、それでやっていける程度の酒だと思われる」というこんで、ついてきた衆もあったと聞くすけ、今でも、ちょっといい酒の値段は、この時の値段が基準になっているんですて。和雄さんが適正価格を守ったという格好になったわけだいね。それだけ品物に自信があったということでもあろうがの。(「杜氏 千年の知恵」 高浜春男)
高浜は、八海山の杜氏です。
酒痕狼藉旧衣裳
謙三和田垣博士は、明治の酒豪学徒として聞えた人であつたことは、世間周知のことである。同じ酒徒であつた天心は、飲酒の洗礼をこの人から受けたと、屡々その晩年に於て我々家人に洩らしてゐた。天心は大学在学時代に於て博士と机を並べ、これに兄事してゐたことが、全く左の一絶に依つても偲ばれるのである。
懐和田垣士謙
往事蒼涼怯思量 酒痕狼藉旧衣裳
有人淡月疎星夜 静倚梅花薫暗香
この詩は天心が社会人として巣立つてから数年後の作である。筆者は、博士が天心に招かれて五浦に来遊されたことを明らかに覚えてゐるが、、それは慥か国画玉成会招待会の当時、詳しく言へば明治四十一年の九月二十二日であつた。博士は当日、大いに飲み大いに酔つて、一聯の英詩を配られた素絢に残してゐられる。恐らくこれは、博士が天心と会合した最後ではあるまいか。(「父天心」 岡倉一雄)
市川段平
「こんな立ち廻りを、誰がつけたんだ?」むしろ凄愴(せいそう)ともいうべき三条磧の幕がしまると、観客席のどよもすような声々の中で、私は溜息まじりに訊いた。「それが君、(市川)段平なんだよ」「段平?」私は、自分の耳をうたぐった。「新国劇の頭取(とうどり)をしているという、あの段平かい」「そうなんだ」「あの男に、よくこんなタテが…」「それなんだよ」田辺(黄鳥)は、微笑の翳(かげ)を消して、「あいつ、一ぺん死にかけたんだ…」といって話した。段平は、本読みの席上で、一たん沢田(正二郎)からつき放されたが、彼は決してあきらめなかった。沢田のいった写実(しやじつ)、リアリズムに、わけ分らぬなりに獅噛(しが)みつこうとした。段平は、誰かれなしに、写実の意味を訊ねて廻った。そして「写実とは、事実ありのままを写すことや」と教えられた。段平は、リアリズムを研究した。そして、立廻りを工夫した。が、もとより沢田の夢には遠かった。大部屋の役者川上をつれて、リアリズムを求めて、毎晩のみ歩いた。へべれけになった。ある夜、地廻りの無頼漢(ごろつき)と喧嘩した。もとより此方は酔っている上に、弱い役者が一人ついているだけである。さんざんにのされた。怪我をした。血まみれになった。医者へかつぎこむにも、夜が更けていた。家まではつれて行けず、楽屋へつれて帰った。楽屋には、沢田がまだ帰らずにいた。独りで工夫をしていた。段平が喧嘩をして、怪我をしたと聞くと、階段をふみ折るように音たててかけ下りた。「段平、しっかりしろ」芝居のように抱起して「傷は浅いぞ」諧謔(かいぎやく)は、時に相手を勇気づけもし、はげましもする。沢田にはそんな一面もあった。(「味の芸談」 長谷川幸延)
銀盤
現社長の堀川勲氏は、機械にとりつかれた人で、酒造よりも機械いじりに熱中し、業界では変人だ、と陰口を叩かれてもいた。堀川社長は、大正十五年十一月四日、先代恒次郎氏の長男に生まれた。血液型A.。昭和二十年二月、武蔵工業専門学校を修了し、広島県大竹市の潜水学校へ入校、八月除校して、二十年から銀盤酒造へ入社、五十年八月、代表取締役社長に就任して今日に至っている。蔵を廻って気付くことは、蔵の中にコンピューター制御を備えたさまざまな醸造機械と、大型タンクが整備されていることである。堀川社長は語る。「原価をかけて、原料の良いものを使って、いい酒を造れば、当然コストが高くなります。高くついたのだから高く売ればいい、というのでは一般のお客はついて来てくれません。第一、高いお酒を誰が買ってくれます。一部のお金持ちだけが飲むお酒を造っていたのでは、一般の愛酒家に、はじき出されてしまいます」「私はそんなお酒は造りたくありません。質のいいお酒を出来るだけ普通の価格で売って、多くの愛酒家に喜んでもらいたいのです」こうした経営哲学をもつ堀川社長は、無駄の多い酒造りを徹底的にチェックして合理化し、人件費を節約するために機械に働いてもらおう、と考えた。そこで機械にとりつかれることになる。-
昭和四十八年から五十二年にかけて上昇気流に乗り利益が出はじめた。そこで思いきって四十億円を借入れて、高価な醸造機械を揃えた。麹室、洗米、蒸し、仕込などすべてがオートメーションでシステム管理されている。そのころである、堀川社長は「機械と心中するのではないか」という噂がささやかれた。どんなに高価な機械を入れても所詮は機械である。良いお酒ができるはずがない、と誰もが思った。しかし、世間の思惑とは違い、キレのいい玲瓏たる吟醸酒や、純米吟醸酒が、続々と誕生したのである。特に純米大吟醸「米の芯」が関東方面で大人気となり「銀盤」の名声は上がっていった。(「酒の旅人」 佐々木久子) 1994年の出版です。
お燗番
酒というと思い出すのは、私がまだ元気いっぱいの青年将校だったころのことである。甲州地方で行われた演習の合間の休日を過ごすために割り当てられた私の宿舎は、笛吹川沿いの造り酒屋の旧家であった。ところが酒が大好きだったその家の主人が、当時まだ皇族であった私が泊まるというので、大喜びして大酒を飲んだとたんに、脳溢血で急に亡くなり、そのため「お宿を辞退する」といってきた。あまりにもお気の毒なことであり、しかも私が原因でもあるので、亡くなられたご主人のお気持ちをお察しして、「もしご迷惑でなかったら、予定通りにお邪魔した方が仏さまが喜ばれるのではないでしょうか?」といったところ、ただちに「そうしてくだされば、この上もないことです」との返事があったので、その家に泊まった。その家では心のこもった歓待をしてくれ、なかでもさすがに酒のうまさが最高だった。造り酒屋とはいえ、どうしてこうまで酒がおいしく飲めるのかと不思議に思われた。明日お別れという晩に、相変わらず一ぱいやりながら、座敷の隅の長火鉢を前にお燗に余念のないその家の女主人にその理由を尋ねたところ、「お酒の上で大切なのはお肴とお酌だといいますが、ここは田舎で、ご満足はとても願えません。しかし、先日亡くなった主人はお酒をおいしくするのはお燗だとの一点張りで、お燗には随分泣かされました。それで私としてはお燗一途にご接待いたしたのですが、それがもしもお気に召したとしましたら本当に嬉しいことです」。そこで私は「この素晴らしいお燗の秘訣は?」と尋ねたところ、「一番大切なのは何んといっても最初の一本、これが熱からずヌルからず本当の上燗であることです。しかし、いくら上燗でも一本調子で続けてはいけません。飲むほどに酔うほどに、だんだん熱くしていくと本当においしくお飲みになれるものです。しかし、お顔がほんのり桜色になられたら、次第にお燗を下げていくと、これまたおいしく喉を鳴らすというものなのです。そしてお顔が猩々色となられ、お歌のひとつも出だしたら、思い切って熱燗にします。けだしヌル燗がもどかしくなったころの熱燗こそは、仕上げの大切なきめ手だからです」と。そういえば長火鉢の前で終始私の顔を見ながらお燗してくれたお銚子が、いつもいっぱいというほど入ってなく、それだからこそ頻繁に取り替えてくれていたお酒が、とてもおいしかったわけがわかって、ただただ感心した。(「雲の上、下 思い出話」 竹田恒徳)
呼び鈴
しかし、この大先輩(柏村信雄 元警察庁長官、現警察育英会理事長)の酒飲みは、日本全国津々浦々に鳴りひびいていて、よい酒の手に入りにくいあの時代に、課長の机の下にはいつも一升壜が並んでいた。課長の酒好きを知っている連中で地方在住者が、上京の途次手みやげに届けたものである。ところが、柏村さんは一人で自宅に持って帰って飲むというようなことはなさらない。昼間はあまり呼び鈴が鳴らないが、夕刻五時にでもなると呼び出しがある。当時の財政課長室は、現在の自治省財政局長室、内務事務官室は、現在の財務局指導課の部屋であった。「課長。お呼びですか」と課長室に顔を出すと、「ああ、暑気払いをしようじゃないか」というわけである。そこで同じように召集された西村勝さん(元川口市助役、故人)、安岡理さん(前出)などが課長の机の前で世間話を肴に冷や酒を酌む。今と違ってクーラーもなければ、そよ風もない敗戦直後の内務省の一隅で、あるときはGHQのやり方を批判したり、国民一般の風潮に悲憤しながら、大きい壜が三本机の上に並ぶまで飲んだものだ。二本目が空になるころから、大先輩の口ぐせが出る。「オレのような天下の英雄をこき使いやがって…」と大変ご機嫌になる。西村さんとボクが「課長このへんで」とキリをつける。足元のふらつくのを三人相いたわりながら、下落合の課長のお宅までお送りする。門まで行くと、今度は、「おまえらが心配だ」と言って坂を下りて私鉄の駅まで送って下さる。そこでまた申しわけないと、家のなかまでお送りすると奥さんが出てこられて、「アラ、また酔ってらっしゃるのですか、わざわざお送り下さってすみません」と挨拶される。この奥様の扱い方が実に堂に入ったもので、幼児を寝かしつけるごとく、天下の英雄もその体を軽く押されると奥のほうへ消える。そこでわれわれの任務も終了ということになる。ボクはこの令夫人の酒飲みの統御法に感心させられたものである。(「へそ曲り官僚ひとり言」 柴田護)
士道不覚悟
文久二年十二月、(横井)小楠は肥後藩江戸留守居役吉田平之助の妾宅に招かれ、同藩の都築四郎らと酒宴のさなか、刺客に襲撃されるのである。この頃の小楠は勤王攘夷浪士の怨嗟の的であり、いつ暗殺されてもふしぎとはいえない状況だった襲ってきたのは同じ肥後藩士三名で、「他藩の者に小楠を斬らせては肥後の名折れじゃ。斬るなら肥後人の手で斬ろう」と思い立ったらしいのだから、よくよく小楠は故郷に容れられない宿命だったのだろう。さいわい小楠は機敏な行動で九死に一生を得たが、暗殺されなかったことが今度は肥後藩の指弾を受け、「士道没却、許しがたし」として、あわや切腹の事態に立たされる。吉田平之助の斬死を見捨てて逃げたことが問題となったのだ。「士道不覚悟の横井小楠、このまま他藩に差しおきがたければ、直ちに引取り申すべく候」と肥後藩江戸屋敷は再三の使者を越前福井藩に送っている。引き渡せば即時切腹と知れているので、福井藩は八方嘆願し、小楠を福井城下へ去らせることで、ようやく同意を得た。郷党の風はあくまで小楠につめたい。天下に志を述べる折角のチャンスを、こうして小楠は逸してしまうのである。(「江戸の人物伝」 白石一郎)
和朝酒濫觴之事(わちょうさけらんしょうのこと)
一(二)、其後人王三十九代天智天王御宇、駿河国(5)富士郡竹叟(ソウト)云者愛レ竹。翁竹切、本ニ一節残タリ。色美也。鳥含レ米来テ、彼節ニ入タリ。連々積而後、受二雨露潤ヲ一成レ酒。味妙也。
〇その後、第三十九代天智天皇の御世に、駿河国(5)富士郡に竹取りの翁という者がいて、竹を愛(め)でていた。この翁が竹を切ったところ、その元に一つの節が残り、美しい色であった。そこへ鳥が米を口に含んでやってきて節に入れた。米がしだいに積もって雨露の湿り気を受け、酒になり、よい味になったのである。
[書き下ろし](二)其後人王三十九代天智天王の御宇(ぎよう)、駿河国富士郡の竹叟(ちくそう)と云う者竹を愛す。翁竹を切り、本に一節残りたり。色美なり。鳥、米を含み来りて、彼の節に入れたり。連々(つれづれ)積みて後、雨露の潤(うるお)いを受け酒となる。妙味なり。(「童蒙酒造記」 吉田元校注・執筆) 八岐大蛇伝説の次に記されています。
買い酒と牛の尾は届き次第
振舞い酒のさい亭主が挨拶代わりに述べた言葉。駆け合い秀句を弄した社交辞令の表現である。
香(こう)の物で酒を飲むと貧乏する
二極の解釈があり、①香の物は酒の肴に合わない ②(塩か生味噌が庶民の肴の時代に)香の物などの肴で飲むと酒も進み、飲み代がかさむ。
杯と真言は繰るほど良い
酒宴の席では杯を大いに回すべし、が真意。(「日本の酒文化総合辞典」 荻生待也編著) 「真言を繰る」とは、念仏講などで、参加者が輪になって念仏を称えながら大数珠を繰り回す行事のことです。
につぽん[日本]
(一)またはにほん。日本堤の略。正しくは二本堤だともいう。山谷から箕輪(みのわ)までの堤で、長さ約十二三丁俗に八丁土手とも土手八丁とも称す。明暦三年(1657)吉原遊郭を浅草へ移転させた時、荒川の水除けのため各大名に命じて築かせたもの。なお、土手を見よ。〇山谷より箕輪に至るまでさきは二本横たふ橋に似たれば二本堤といひはじめしと云ふ云々」(江戸砂子)-
⑩日本の地へふみこむと酒手なり (傍三)-
⑩足元につけ込む駕屋。酒手をはずまないと棒組との間で聞えよがしのイヤミを話したり、のろのろ歩きうしろから駕にどんどん平気で抜かれる。類句-担ぐと見えしが大門口になり(逸)。大門を四ッ人リじぎをして帰へり(同)-酒手をはずんだ四枚肩。四ッ手駕行くのゝ道でねだられる(樽六)。衣紋坂四ッ手勢ひさかんなり(樽一〇)。四ッ手駕さびしくかける定直(じようね)だん(樽一一)。直のいゝ四ッ手は空ラ手が二三人(樽一九)。急ぎ候ほどに田町からねだり(樽五一)(「古川柳辞典」 根岸川柳)
パックキープ
京橋銀座のサラリーマンが集う老舗角打ち「枡久」。角打ちとは地方によって呼び名は変わるがその場で飲める酒屋さんのこと。枡久の酒屋としての創業は江戸末期。もともと大通り沿いにあったが、路地に移ったのは2年程前。今度の店は穴場感漂う入り口で、一見ここが名角打ちとは誰も気づかない。さて。ここへ来る人々は皆、今も昔も一人で切り盛りするクールビューティな女将に恋をしている。涼しい季節は綿の袖なしワンピース。ふつうのおばちゃんが着ればムームーでも、女将だと避暑地の装いのごとく涼しげだ。移転前の店舗は奥行きのあるうなぎの寝床型だった。だから、「新米はまず入り口付近で飲む。中堅になるとやっと店の真ん中あたり。10年通ってようやく女将がいる奥の"番台"に辿りつけるのさ」とダンディズム溢れる常連にいわれたものだ。遠い。なかなか遠い旅路だ。と思っていたら新店舗は事情が変わっていた。女将の番台はちょうど真ん中、相変わらずダンディ班がぐるりと囲んでいるが、そこから女将が顔をちょこんと出し「丸テーブル使ってね」などと声をかける。嗚呼、贅沢。テーブル席は必然的に新米&中堅の席。席が決まれば奥の冷蔵庫からセルフでお酒を運ぶ。アサヒの中でお気に入りの「アサヒ・ザ・マイスター」の中瓶とスルメで450円。女将が番台に備え付けられた栓抜きでシュパンと栓を抜き、コップと皿を出してくれる。この一手間が嬉しいのでアール。などとカツヤンと話していると、テーブル席で日本酒を飲んでいるおっちゃんたちが「君たちどっから来たの。およよ、ビールなんか贅沢なの飲んじゃって」とコップ片手に乾杯を迫ってくる。毎夜、ここで"晩酌"をするのがお約束らしい。「ちなみにね、飲みきれなかった日本酒パックは女将がキープしといてくれんのよん」「なんとボトルキープならぬパックキープ…」「そ。ボクいつも女の子の話ばかりするからパックに"スケベ"って書いてとっといてくれる」と女将に熱い視線を送りながらいって、見事に無視されている。女将がそんな下品なこと書くわけがない。が、キープは本当だ。缶詰はサバやソーセージなど200円台のものから高いのでコンビーフ500円など。番台でのお会計で初めて値段がわかるのだが、予算1000円までが絶対ルールの隣のオッチャンたちは、つまみは100円前後の乾き物一本槍だ。(「女2人の東京ワイルド酒場ツァー」 漫画・カツヤマケイコ コラム・さくらいよしえ)
十六夜月 節松嫁々
かたぶけし きのふも 酒の二日酔ひ そらにいざよふ 盃のかげ
三股月 芳野葛子
さかづきの さす手ひく手に 三味線の かはにうつれる 影をみつまた
月前酒 から衣橘洲
さすかげの あかきは酒の とがながら 月にゆるしの 色とこそ見れ
九月九日 八張棟梁
此酒を のむはそくさい ゑんめいが そのふる事と きくの盃
菊 横道黒塗師
我がやどの きくの酒 手のけふごとに いく代つもりて 借銭の淵(「徳和歌後万載集」 野崎左文校訂)
残業
残業は お酒もでるのと 子に聞かれ 帰途残業者
遅刻
よく飲んで よく寝て今朝も 遅刻する 憲峯
のれん
縄のれん 「上役」という 肴(メニュー)あり 原丁八
のれん越し 上司の有無を 見て入り 調子者
二日酔
二日酔 会社で直し また飲み屋 健忘症(「平成サラリーマン川柳傑作選①一番風呂・二匹目」 山藤章二・尾藤三柳・第一生命選)
佐久の草笛
また、第三聯の終わりの方に「濁り酒」が出てくるが、明治三十一年以降は少量の家庭用とはいえ、ドブロクの醸造は禁止されていたという説もあるが、この濁り酒は地酒というほどの意味でドブロクであると限定して考える必要はあるまい。『万葉集』巻三の大伴旅人の讃酒歌、 験(しるし)なき物を念はずは一杯の濁れる酒を飲むべくあるらし の古歌ともひびきあっている趣が感じられる。藤村は、自分の詩に、曲をつけて、何んとか多くの人に歌ってほしいという念願を持っていたが、この歌は広ママ田龍太郎が曲をつけ、ベルトラメリー能子がソプラノで美しく歌いあげ、多くの人々に愛唱される名曲のひとつとして歌いつがれているのである。 草笛や空いつぱいに雲溢れ(「置酒歓語」 楠本憲吉)
島崎藤村の「千曲川旅情の詩」の第一聯です。
飲んべエ健康法
顔見知りの酒友だちが倒れたという話は、あちこちで聞くが実にイヤな思いをする。まるで、わがことのように聞こえてしまうのだ。「ああ、次はわが身か」と思ってはみるものの、酒量は相も変わらず。おかしなもので、倒れた人が自分と同い年だとヒジョーにビビるが、年上だと、"まあ、しかたないよ"という気になる。あの人もさんざん好きなことしてきたんだもの、ここらで休憩しておけば、また飲めるさ、と思う。年下だと、"あいつ、バカ飲みして。いい薬だよ"で終わる。同い年は、まずい。どうしても、わが身を考えてしまう。最近、同い年の男が酒場から姿を消したとき、とうとう"酒を医者から止められたときの飲み方"を考え出すに至った。[方法1]ビールだけにしようでも、あまり多く飲めないナ。ビールの味は単調だから。 [方法2]ワインにしてみよう。アルカリ性だから、からだにいいんじゃないかな。でもいきつけの店にワインなんて置いてもらえないし…。 [方法3]ウメ干しやトマトをつまみにすると悪酔いしないというから、食べよう。でもそんなの食べてるといい気分に酔えないんじゃないかナ。 [方法4]水割りをやめて、お湯割りにしよう。ホットウイスキーはからだが温まって発汗作用をうながすから、からだにたまらない。でも、飲みやすいから飲み過ぎるだろうね。 どうも、うまい考えが出てこない。もし、すばらしいアイデアがあったら、ぜひ教えてください。ボクは、あとはこれしかないと思っていますが、ね。 [方法5]飲んでまず、からだに痛みを植えつけよう。そのあと、また飲んで感覚をシビれさせて痛みを止めよう。(「シャレと遊びと人生と」 はらたいら)
フツカヨイ
太宰は、M・C、マイ・コメジアン、を称しながら、どうしても、コメジアンになりきることが、できなかった。晩年のものでは、-どうも、いけない。彼は「晩年」という小説を書てるもんで、こんぐらかって、いけないよ。その死に近きころの作品に於ては(舌がまわらんネ)「斜陽」が最もすぐれている。然し十年前の「魚服記」(これぞ晩年の中にあり)は、すばらしいじゃないか。これぞ、M・Cの作品です。「斜陽」も、ほぼ、M・Cの作品です。どうしてもM・Cになりきれなかったんだね。「父」だの「桜桃」だの、苦しいよ。あれを人に見せられちゃア、いけないんだ。あれはフツカヨイの中にだけあり、フツカヨイの中で処理してしまわなければいけない性質のものだ。フツカヨイの、もしくは、フツカヨイ的の、自責や追懐の苦しさ、切なさを、文学の問題にしてもいけないし、人生の問題にしてもいけない。死に近きころの太宰は、フツカヨイ的でありすぎた。毎日がいくらフツカヨイであるにしても、文学がフツカヨイじゃ、いけない。舞台にあがったM・Cにフツカヨイは許されないのだよ。覚醒剤をのみすぎ、心臓がバクハツしても、舞台の上のフツカヨイはくいとめなければいけない。芥川は、ともかく、舞台の上で死んだ。死ぬ時も、ちょッと、役者だった。太宰は、十三の数をひねくったり、人間失格、グッドバイと時間をかけて筋をたて、筋書き通りにやりながら、結局、舞台の上ではなく、フツカヨイ的に死んでしまった。フツカヨイをとり去れば、太宰は健全にして整然たる常識人、つまり、マットウの人間であった。小林秀雄が、そうである。太宰は小林の常識性を笑っていたが、それはマチガイである。真に正しく整然たる常識人でなければ、まことの文学は、書ける筈がない。(「不良少年とキリスト」 坂口安吾)
子孫制詞条目
一、⑮当日頃日(ケイジツ)、金銀融通を他に請(コ)ふに、金主手代(キンシユテダイ)之者を遊所(ユウシヨ)に伴(トモナ)ひ、美女を集て酒宴を致し、其座席にて事を談(カタ)る之由(よし)。元来金子(キンス)助力之義、勝手向不如意(フニヨイ)に付、他力を借(カル)。然(シカル)に数多(アマタ)之金銭を費(ツイヤス)事、意味深長有る事に候歟(カ)。未レ聞レ之(イマダコレヲキカズシテ)熟慮(ツラツラオモンミル)に、夫(ソレ)酒は過る時は乱て差別なきに至(イタル)、玆(ココ)を以て大金を費し、美女を集て酌を取らし、手代之者を酒狂人(シユキヨウジン)に仕立(シタテ)、其虚を計(ハカリ)て事をなすのはかりごとに候はん歟(16)仍(ヨツ)て手代之者、酒興に乗じて大言を吐き、万端己独(オノレヒト)り事を約する趣(オモムキ)にて、その事を承知す。酔醒(ヨイサメ)て後、前夜之公言(コウゲン)義理に窮し、始末宜様(ヨロシキヨウ)主人え取持(トリモチ)、其内主家為筋(ノタメスジ)(17)も有レ之候へ共、又不為筋も可レ有レ之(コレアルベク)候。双方都合宜(ヨロシク)物事(モノゴト)成就いたし候はゞ、兎もあれ角もあれ、己(オノレ)不為筋をも聞ながら、前夜之義理を以て、主(アルジ)を欺(アザムク)は奉公之道に背(ソムキ)、忠を以て成就せざる之時は、先(サキ)之費(つい)へ甚以(ハナハダモツテ)笑止なるべし。言葉を巧にし弁舌を震(フル)ふて云ひ逃(ノガ)るとも、独り心恥しかるべし。是他を批判致すにあらず、当家氏族之者、常に心得置て然(シカ)るべく候。
(15)「当日頃日」は今このごろの意。以下の文中の「遊所」は遊里などの遊び場。また「意味深長有る事」は言外に意味のあること。つづく文頭未レ聞レ之熟慮に」については、その方面のことにないまだにあまりよく通じてはいないのだが、つらつら考えてみると、という程の意か。 (16)「酒狂人」は酒に溺れる人の事。「其虚を計て」は、腑抜けにして正しい判断力を奪おうとしての意。 (17)「為筋」は利益になること。(「家訓集」 山本眞功) 鴻池家の家訓です。
燗
一般に、日本酒は温度を高くするほど舌触りが滑らかになり、甘み、酸味、苦味などのバランスがよくなって、より旨みを増すとされる。ただし、燗に向いているのは、もともと旨みや酸味の強い濃醇(のうじゆん)タイプの酒で、奥行きのある味でこくのしっかりとした酒質のものなら、常温でも旨みが際立つ。山廃(やまはい)造りなどの生酛(きもと)系酒母(しゆぼ)で造る酒は、もともと燗をして飲んでいた酒なので、最も燗に向く酒といわれる。ただ、現在は山廃吟醸など、生酛系の酒でも香りを重視した造り方をしている場合が多い。そういう酒は温度が高いと香りのボリューム感が強調されすぎることがあるので、通常の燗よりも低めにしたほうがよいという。反対に、旨み成分の少ない淡麗タイプの酒は、燗をすると水っぽくなってしまい、アルコールが舌を刺激するような傾向が強いという。本醸造酒や質のよい普通酒には、香味のバランスがとれていて、しかも安定しているものが比較的多く、その場合は、冷や、常温、燗のどの温度帯にも合う。また、熟成の進んだ古酒の場合も、燗にも冷やにも向くオールマイティータイプのものが多いようだ。(「日本酒百味百題」 小泉武夫監修)
土屋文明の酒歌
現代を代表する歌人、土屋文明氏(注3)(一八九〇-)は憶良に共感する歌をよんでいます。
糟湯酒(かすゆざけ)わづかに体あたためてまだ六十にならぬ憶良か-
文明は二〇世紀の激動の日本にあって、生活を直視した歌を多くよんでいます。-
君がため夕べの酒をさがさむと坂をゆきにき老人さびてき-
(注3)土屋文明自選『土屋文明歌集』岩波書店、六刷(一九八九)(「万葉集に見る酒の文化」 一島英治)
立野信之
阿佐ヶ谷駅に程近い成宗には、鹿地亘や立野信之が住んでいた。その近くには小田嶽夫も住んでいて時々行き会うのだが。「その立野や鹿地が、私には平家全盛時代の平家の一門のようにかがやかしく、又腹立たしい存在に思えた。そういう私は無論源氏の一門の心境であった」と、『青春文学群像』の中に書いている。立野信之は酒好きで、毎夜のごとくピノチオで飲んでいた。誰いうとなく酒好飲之だ、というようになった。そんな立野に誘われて、小林多喜二や他の左翼作家たちも、阿佐ヶ谷界隈で善く飲んだ。(「阿佐ヶ谷界隈」 村上護)
プラタナスの葉
早速明るいうちからまたビールに染まる。一時間ほど飲んだところで陽が傾く。暑さも少しやわらいだところで仲間と新宿へ向かう。船山馨(かおる)さんが僕のお祝いに北海道の仲間ともども御馳走して下さる、というわけである。ちなみに船山さんは札幌出身で私の大先輩である。駅ビルに近い「柿伝」という懐石料理店へ案内される。L型に坐り、上座の私の前には川端康成先生筆になる掛軸がかかっている。上品な女性の物腰に合わせて、初めは静々と飲んでいたが、酒の旨さと身内?の気楽さについピッチがあがり、最後の抹茶の頃にはすでにかなり酩酊(めいてい)。これで帰宅というのは殺生な話。船山さんともども西口の「茉莉花」へ。ここではウイスキー。結局この日も午前二時まで鯨飲、お目付役の船山さんの奥さんがいたから腰を上げたようなものだ。(「酒中日記 プラタナスの葉」 渡辺淳一)
フマール酸
その老酒には紹興酒のほか福建老酒、糯米酒、沈缸酒、醇香酒、加飯酒、善醸酒、花雕(彫)酒など多数あるが、いずれも油料理に負けない、しっかりとした香りと味を持っている。その理由はなにかというと、いずれの酒も酸味がかなり濃く、その上、奥深い熟成香が油の濃厚な味と非常によく似合うのである。この酸味が重要で、たとえば紹興酒の場合、酸度(酒資料一〇ミリリットルを中和するのに要する一〇分の一規定水酸化ナトリウムの量。数字が多いほど酸味は強くなる)は六、七ミリリットルである。これは日本酒の酸度である一・五ミリリットルより、実に四倍以上も高いことになる。-なお紹興酒を代表する黄酒に酸味が多いのはなぜかというと、使用する小曲に由来するである小曲は糸状菌のクモノスカビ(リゾープス)で造るが、この糸状菌はフマール酸という、酸味が強いが爽やかな味の有機酸を生成して小曲に蓄積してくれるのである。それが発酵中に溶けだしていって、酒に移行するというわけである。白酒の大曲もクモノスカビで造るため、大曲中にもフマール酸は多いが、白酒は蒸留酒であるために不揮発酸のフマール酸は蒸留されずに糟の方に残るから、白酒に酸味はない。(「銘酒誕生」 小泉武夫)
のみすけ(飲み助)
[名]酒飲み。[江戸]<類義語>うわばみ・飲んだくれ・のんべえ。◇『東京語辞典』(1917年)<小峰大羽>「のみすけ(飲助) 酒を嗜む者、飲んで底抜けのもの」◇『くらがり廿年』続くらがり二十年・42(1940年)<徳川夢声>「斯う条件が揃つちや、呑助は呑まざるを得ない」◇『縮図』時の流れ・九(1941年)<徳川夢声>「客は呑み助で夜明しで呑まうといふのを」(「日本俗語大辞典」 米川明彦編)
薄くした酒
変わった飲み方もすすめられた。スコッチはイタリアの炭酸泉水で割る。これは微炭酸がとても心地よい。またビールや赤ワインをブラッドオレンジジュースで割ったものもイケる。最近では日本酒に氷を入れて飲んでいる。ボディーのしっかりした酒は薄く感じず、味と香りがさわやかに変化するから不思議だ。でもって薄いからいつもの倍は飲めるとワクワクしていたら、大間違いであった。結局は飲みすぎていつもの酔っぱらいだ。倍になるのは酒の勘定だけなのである。(「さしつさされつ」 中田耀子・土田裕之) すすめた店は「なつ石」(札幌市白石区東札幌2条2丁目)です。
ねぎま鍋
中とろぐらいに脂がのったものが、この鍋には合います。煮過ぎないうちにあつあつを。
●材料(2人分) まぐろ1サク 長ねぎ2本 煮汁(だし汁2カップ みりん大さじ2 薄口醤油大さじ4)
●作り方 1まぐろのサクを厚めの平造り-にする。 2長ねぎは長さ4cmのぶつ切りにして、焼き網や石綿に乗せて焼き目をつける。 3煮汁を煮立て、まぐろと長ねぎを入れ、煮過ぎないうちにいただく。(「おうちで居酒屋」 YYTproject編著)
置き忘れ事件
その一週間後、マガジンの五十嵐が、『バカボン』の原稿をタクシーの中に置き忘れる事件が起きた。車内で原稿を脇に置き、金を払って、降車。タクシーは走り去ってしまう。車のナンバーも、会社名も判らない。五十嵐は、フジオ・プロに引き返す。手土産のサントリー・オールドを差し出し、赤塚に頭を下げる。アシスタントもまだ残っていた。赤塚は、五十嵐に言う。「明日の朝からやれば、昼までには上がる。それで間にあうんだろう?三時間ぐらい飲めるよ。行こう」同じ原稿を二度描くのは、辛いことに違いない。赤塚も、ちょっと間を置きたかったんだろう。原稿は、次の日の昼に上がった。割を食ったキングは、一日遅れた。失くなった原稿は、一週間後、タクシーの運転手が届けに来た。だから、同じ原稿が二つある。失くしたほうの原稿を、赤塚は五十嵐に進呈した。これが『レッツラゴン』だったらどうだろう。いきなり原稿に書いていく『ゴン』の場合は、ネーム用紙が残らない。後に、赤塚は、僕に言った。「五十嵐だったから、描き直したんだ。武居だったら、やらないよ」「それにしても、ダルマ一本持ってくるなんて、やっぱり五十嵐は八百屋の小倅だ。僕だったら、二本は持って行ったよ」「うん、それなら、武居のも描き直す」(「赤塚不二夫のことを書いたのだ!!」 武居俊樹)
タケノコの刺し身
竹藪の中に緋毛氈(ひもうせん)を敷いて、一杯やりながら、気のおけない友と四方山話に興じて待つことしばし。頃合いを見はからって藪の主人公は刺し身向きのタケノコを物色して回り、掘り上げるや間髪を入れず茹(ゆ)で上げ、刺し身としていただくわけだが、一部は椀だねにする。枯淡の味は比肩するものがなく、やわらかな舌ざわりは、魚とはまた別趣の味わい。この刺し身、どこのタケノコでもいいというわけではなく、技術ももちろんあるが、掘り置きのものは、まず失格。時間との勝負の珍味、佳味と言えよう。(「にっぽん食物誌」 平野雅章)
酒の統計
全体の消費量 1990年代以降は横ばい
最近5年間の酒類別消費量(販売数量)kl 1995年9,603,358 1996年9,657,200 1997年9,410,191 1998年9,455,556 1999年9,553,845
一人当たりの消費量 日本は世界で28番目
ひとり当たりの酒類消費量 単位l 1位ルクセンブルク13.3 2位ポルトガル11.2 3位フランス10.8 4位アイルランド10.8 5位ドイツ10.6 6位チェコ10.2 7位スペイン10.1 8位デンマーク9.5 9位ルーマニア9.5 10位ハンガリー9.4 28位日本6.6
ひとり当たりの消費量県別ランキング 総合第一位は東京 国税庁資料より
成人ひとり当たりの消費量(販売数量)県別ランキング 単位l 総計 東京127.5 大阪119.3 高知113.7 新潟113.7 秋田107.8(「酒席に役立つ読む肴」 酒文化研究所編)
畠中頼母(銅脈先生)
何をおいてもまず酒。借金が溜ってとうとう貸し売りをことわられたのに業を煮やし、酒屋の看板をはずそうとしたのには主人も閉口して酒を与えたという逸話の伝わる銅脈先生こと畠中頼母は、日として酒に暮れぬことはなかった人物だった。「世を翫弄し、生涯狂詩のみを諷詠し、日夜酒を嗜み、樽に対して懐をやる」とは、杉野恒の『典籍作者便覧』の評語である。安永七年(一七七八)の狂詩集『太平遺響』には友人の魚焦なる男が一篇を寄せて「酒ヲ見テ餓鬼ノ如シ。涎ヲ流シテ辛抱スルコト難シ」と形容している。享和元年(一八〇一)に五十歳で中風で死んだのも、酒が生命を縮めたとしか言いようはあるまい。(「江戸人の昼と夜」 野口武彦)
二十献の饗宴
松岡 原田信男さんが「日本の社会史」で書かれているんですが、「葛原(くずはら)文書」ですか、隅田一族の饗宴を書かれていて、あれが一献から始まって二十献ぐらいまであるんですけれども、最初の二献までは芸能が入ってこないんですよね。三献から「相生(あいおい)」要するに「高砂(たかさご)」が入ってきて、一献ごとに一つの能…これは舞囃子だという説もあるんですが、僕はそうじゃなくて能だと思うんですね。その頃は一時間ぐらいですから、だいたい一献一時間ぐらいで、二十四時間ぐらいの、朝までやる宴会。
大岡 これは体が丈夫じゃないと持たないな(笑)。
松岡 いや、それは「橋の会」で、バブルの頃、企業の後援で、二十四献ぐらいの宴会をやりながら能を見る会をやろうといっていたんだけれども、浅見真州さんなんて、冗談じゃない、俺たち能楽師にはそんなことできねえって言われて…。
大岡 できないよね。そんなのに付き合っていたら…。
網野 体が持たない(笑)。でも、隅田氏の話はほんとに面白いですね。
松岡 そうですね。ほかにも「三好亭御成記(さんこいうていおなりき)」とかいろいろありますけれど、一昼夜やっていて、最初の式三献には能は入ってこなくて、その次ぐらいから入ってきますね。それでこの一献がけっこう長いんですね。(「座談会 酒と日本文化」 大岡信、網野善彦、浅見和彦、松岡心平)
良い酒となる理由
よく尋ねられる問に、「良い酒とはどんな酒のことをいうのか」ということがある。私はいつもそれに対する答として「芭蕉が俳諧のことを問われた答に不易流行といっている。私のような素人にはよく諒解できないが、不易とは俳句の道を通じて、いかなる流派や作家の作を通じても良句であれば必ず持っていなければならぬ、諸流を通じての不変不易のスピリットであって、いわば優れたる俳句のシンボルともいうべきもので、流行とは流派や作者や時世のはやりのスタイルに応じて変化すべきスタイルであると解している」と答えることにしている。そしてそれを酒に当てはめると、世界中のあらゆる酒を通じて、いやしくも良酒といわれるものの備えている美徳、それは香味の調和と円熟とに帰する。すなわち「不易」である。音楽の交響楽やオーケストラを知る者にもすぐに諒解できることである。酒の場合この美徳は酒のエージングによってのみ到達できるのである。そのことは世界中の酒造りの斉しく知るところである。それにも拘わらず、その理由となると今まで誰にも判然とわからない。一番大切なことがわからないということは実にうかつなことでもあり、不思議なことでもある。アルコールの水溶液は、樽や壜の中に長期保存するとその味が慣れて円味を帯び、飲む時にも何のさわりもなくなる。それが良酒の美徳である。何人も知っていることだが、その理由は今日もはっきりしていない。ある研究者は容器の表面の作用(酸化還元、エステル化など?)だといい、他の人は樽の木質から溶け出すタンニンなどのフェノール物質であるというが、確証がわからない。決定的理論が出来ていない。(「愛酒楽酔」 坂口謹一郎)
その他のおすすめカクテル
風邪ぎみの時に 風邪をひいたときに飲めば、体が温まります。でも、飲みすぎには注意!
<材料> 熟成タイプの日本酒 グラス1杯 角砂糖1つ バター少々 レモンスライス1枚
<作り方> ①日本酒を軽く燗にする ②グラスに注ぐ ③バターを浮かべる ④角砂糖を浮かべる ⑤レモンスライスを浮かべる
いつまでも女でいたいあなたへ ざくろは、女性性を高める働きがあり、きれいになれると言います。日本酒のキレイパワーとダブルで、誰よりも美を手に入れましょう!
<材料> 香り高いタイプの日本酒 グラス1/3 ざくろジュース グラス1/2 氷
<作り方> ①グラスに氷を入れて、日本酒を注ぐ ②ざくろジュースを注いで、ステアする
いつまでも白い肌でいたいあなたへ アセロラとレモンには、ビタミンC が豊富です。ビタミンC の効果で、美白美人を目指しましょう!
<材料> 軽快でなめらかなタイプの日本酒 グラス1/2 アセロラドリンク グラス1/4 レモンジュース グラス1/4 レモンスライス1枚 氷
<作り方> ①グラスに氷を入れて、日本酒を注ぐ ②アセロラドリンクを注ぐ ③レモンジュースを注ぐ ④レモンスライスを飾る(「日本酒美人」 島田律子)
初代川柳の酒句(9)
下戸おんに かけ/\一ツ ぐつとのミ 眠狐(飲めない私が飲むのだからもうやめましょう?)
判取に 成りて見たがる 樽拾ひ 鼠弓 「判取を羨んでゐる樽ひろひ」(筥一・23ウ四・和桂)(集金の仕事を羨む樽拾いの丁稚)
月雪のまん中 生酔(なまえい)の 多さ 会木(雪月花の花をまん中と見れば、花見には生酔が多いとなりますが?)
こわくなひ 呑手(のみて)そろ/\ 涙ぐミ 綿(ママ)糸(泣き上戸なのでこわくない)
神酒(みき)をすゝめて 手習子 いとま乞 眠狐(寺子屋の生徒が師匠にお酌の儀をして卒業?)(「初代川柳選句集」 千葉治校訂)
古米鑑別法
古米と新米とは光沢、色調、香りなどの相違から官能的にもある程度鑑別できる。化学的鑑別法としては玄米の活性度からその新鮮度を見る発芽試験、亜テルル酸ナトリウム(TS)、またはトリフェニール・テトラゾリウム・クロライド(TTC)による呈色試験(還元法)、そしてグアヤコールによる呈色試験がある。また米は貯蔵中経時的にpHが低下することから米のpHを測定する方法としてMRとBTBの混合指示薬による呈色試験(2MB法、30MB法)あるいはBTBとPRの混合指示薬を含む0.001Nと0.005N
NaOH液による呈色試験等がある。(「改訂灘の酒用語集」 灘酒研究会)

〇胡瓶
酒瓶也 禁中節会に用らるゝものなり 江家次第(ごうけしだい)元日宴篇に曰はく 殿東軒廓 安二殿上酒台一 西第一間第一柱南砌上 舗二毯代一枚一 其上 立レ案(垂帳額) 其上舗二紺布一 立二胡瓶二口一(注云) 西向近例只有二一口金銅鳳瓶一也 其東立レ樽 〇同篇に当二幄北東西行一 舗二蘆「上:廾、下:弊」一枚一 其上立レ案(有台覆紺布掛同帽額)其上各 立二胡瓶二口一 〇同篇に南台盤 居二胡瓶二口一 註云 胡国瓶也 見二史書一 〇貞丈按ずるに右の註を合せ考ふるに胡瓶は本は胡国の瓶にして金銅を以て作り鳳瓶とも云ふものなり 年中行事の絵に 瓶の首を鳳の頭に造りたる物見えたり 即是れなり 元文大嘗会の絵にも此のもの見ゆ 〇胡瓶名目抄にコヘイと唱ふ 鳳の頭を色々に彩りたり(「安斎随筆」 伊勢貞丈)
取材を申し込む瞬間
食取材のコラムを書き始めて25年になるが、今でも緊張するのが、取材を申し込む瞬間である。最初の頃は、店の雰囲気や主人の性格を読み違えて随分断られていたものだ。断られる理由が分からなかったからだ。断られた時のジメジメとイジイジとザラザラとした気分は、他に譬えようがないほど厭なものだ。主人と私の間に冷気が走り、沈黙が訪れる。私の気分としては、せっかく捕まえそうになった犯人を逃し、また初めから捜査をやり直さなければいけないツラサと、”断られる"という具体的なツラサが入り混じり、なんともやり切れない気分に陥る。何度も何度も失敗しながら、「この店は、取材拒否だな」、「この店は時間をかけて口説いた方がカシコイ」などと判断出来るようになっていった。それでも失敗することがある。思いがけない不意打ちに合うこともある。主人が取材を拒否するには、必ず理由がある。それを雰囲気と会話によって感じ取るのは、相当なキャリアと勘が必要である。電話で取材を申し込むなどもっての他である。必ずその店の料理を食べ、何度か通って会話を交わし、こちらの顔を覚えてもらう。すなわち、断れない情況をつくってから申し込めば、相当な理由がない限り、断られることはない。それには、善意で臨むことが必要だ。お店にとっても、私にとっても、読者にとっても取材が"いいこと"であることが必要なのである(これを「三位<味>一体」という)。それでなければ、こちらも申し込みはしない。それでも「アンタに頼まれれば断るわけにはいかんなあ」と思わせるのはカンタンではない。そこで考えたのが「住所、電話番号は一切載せませんから」という言い訳である。(「東京居酒屋はしご酒」 伊丹由宇)
漱石の酒句(3)
明治三十年 有感
ある時は 新酒に酔て 悔多き[承露盤]
明治三十一年 正岡子規へ送りたる句稿 その二十八 一月六日
酒を呼んで 酔はず明けたり 今朝の春
甘からぬ 屠蘇や旅なる 酔心地
明治三十一年 正岡子規へ送りたる句稿 その三十一 十月十六日
落ち合ひて 新酒に名乗る 医者易者[承露盤]
憂あり 新酒の酔いに 託すべく[承露盤](「漱石全集」)
34どぶろく祭
春日神社 行方郡麻生町青沼
古くは旧暦七月二十八日に行われた例祭で、青沼に神を迎えた喜びをわかつため古代に酒を振舞ったことに始まり、明治以前は八石八斗八升のどぶろくを造った奇祭である。現在は十一月二十三日に行われているが、酒税法などの関係もあってどぶろくの製造は約一石である。税務署公認で十一月一日にどぶろくを仕込み、例祭前日の二十二日に税務署の検査を受け、同時に村内の長老により口利きが行われる。翌二十三日例祭当日は、早朝より神前に山海の珍味を供える。第一の神饌として、御神酒のどぶろくを四斗樽(だる)に満たし、周囲に注連縄(しめなわ)を張り巡らせて供える。また、第二の神饌として、粕香味(かすこうみ)という酒粕で大根の葉を漬けたもの。第三の神饌として、御爨上(おたきあげ)という玄米を炊き上げた御飯。第四の神饌として、御粢(しとぎ)という米粉の団子七個。以上四種は欠かすことのできないものとされている。どぶろくは、午前十時ころから一般の参拝者に振舞われ、終日多くの人々がどぶろくをご馳走になる。古くは祭典を丑の刻(午前二時)に行っていたが、昭和四十年代に改め、当番の引き継ぎは午後五時、当番組内のしかるべき家において、宮司、総代立ち会いの下に行われ、終って直会の儀を行う。午後九時、新しい当番の組内の肝入りにより、社殿において例祭が執行される。古儀においては、「吐普加身依身多女(とほかみえみため)」の祝言が唱えられ、次いで種蒔(たねまき)、苗取(なえとり)、御昼食、田植という神事が行われていた。種蒔は、総代の一人が小さな袋(俵)三十六個に種籾を入れたのを田の中と見物人に投げる。苗取は宮司が榊の小枝を数本拾い、それを早苗に見立てて田植の所作をする。御昼食は総代二人が田の中に飯櫃(めしびつ)を運び出し、飯を盛った椀を田の中に入れようとすると、見物人が泥をつかんで櫃の中に投げる。泥が櫃の中に多く入った年は豊作とされる。現在の祭典は神社祭式によって行われ、このような農耕所作は伴わなくなったが、どぶろく醸造をはじめ特殊神饌は変わることなく続けられている。(行方貞男)(「茨城の神事」 茨城県神社庁編)
ラク酒
トルコで「ラク」、アラブで「アラック」、ギリシアで「ウゾ」と呼ばれる酒は、いずれもニガヨモギなどの薬草を入れたブドウ酒を、何度も蒸留してアルコール度を高めた強い酒である。こういう薬草入りのリキュールとしては、フランスのアブサンが名高いが、ラク酒の方が味も香りもアブサンよりずっと強烈である。ラク酒は無色透明だが、少しでも水を加えると、溶けている薬草成分、特にアニス油が水分と結びついてコロイド状態となり、酒全体が白濁する。その色も、水の加え方が少ないと薄桃色を帯びた白色となるが、さらに水を注ぐと純白色に近づき、水で割りすぎると灰色になってしまう。そういう具合に色の変化が楽しめる酒なのである。ラク酒のアルコール度数は新酒でも最低四五度はあり、古酒になると七〇度を越すこともある。ラク酒もウィスキーやブドウ酒のように、年月がたつほど味にコクが出てくるし、ブランディーと同じく貯蔵中にアルコール度が高まっていくのである。中央アジアにいた頃のトルコ人は、馬の乳からクムズという酒を造っていたが、中近東へ進出してブドウ酒の製造法を学んだ。次いで、アラブ人がヤシ酒を蒸留してアルコール度を高めたり、薬草を加えたりするのにヒントを得て、今日のラク酒の先祖を誕生させたらしい。(「世界風俗じてんⅡ衣食住の巻アジア」 矢島文夫他)
村酔 村で酔ふ 盧仝
昨夜 村飲シテ帰リ 昨夜 村で飲んで帰り道
連倒ス三四五。 続けさまに参四五度倒(ころ)んだ。
摩「上:沙、下:手」(マシヤ)ス青莓(マイ)苔 青苔(こけ)を摩(さす)りつつ云ふ
嗔(イカ)る莫(なか)レ汝ヲ驚著ス。 こらへてくれよ、お前驚(びつく)りしただらう。
◎作者盧仝は韓愈が河南の県令たりし時、其の詩を愛して之を厚礼したと云うふ。 〇摩「上:沙、下:手」 摩擦。 〇莓苔 莓も苔である。(「中華飲酒詩選」 青木正児著)
酢の物(キュウリ、シラス、大葉)
酢を使った酒肴のうちでいちばんオーソドックスなのが、キュウリをベースにしたもの。キュウリは小口に薄く切り、コンブをつけた塩水につけ、しんなりしたところでザルにあげて、かたく水をきる。シラスはざっと水洗いして砂抜きしてから、ザルにとって水きりする。大葉は2枚に切ってから、せん切りにしておく。酢6、醤油1、みりん1の割合であわせ、3杯酢を作る。ポイントは酢を一度煮たてること。こうすることで、ツーンとする酢の刺激がやわらかくなる。煮たてた酢がさめたところで醤油、みりんを加え、あわせる。キュウリ、シラス、大葉を3杯酢に入れ、よくあえればできあがり。冷やして食べる。(「酒肴<つまみ>のネタ本」 ホームライフセミナー編)
福島 人気銘柄が続々登場する元気ある県
主に首都圏向けに二級酒を造る量産県で、酒造レベルを測るひとつの基準でもある全国新酒鑑評会で金賞を獲得した蔵の数は全国でも最低レベルでした。そこで吟醸造りで先行した「末廣(すえひろ)」、「國権」ほか、量から質へ転換を図る蔵元たちの働きかけで、蔵の跡継ぎたちを対象とした清酒アカデミーが開講。平成十七年に初めて金賞数1位になり、その後毎年上位を維持しています。人気銘柄も多く、二〇〇〇年頃「飛露喜」が全国ブレイクしたのに続き、「会津娘」「奈良萬」「あぶくま」「天明」「人気一(にんきいち)」などが続々名を上げ、生酛の「大七(だいしち」が気を吐いています。さらに「寫楽」「会津中将」「ロ万」「一歩己(いちぶき)」など三十代の若手が立ち上げた銘柄も、ファンから熱く支持されています。(「目指せ!日本酒の達人」 山同敦子)
神主のいない神社の神殿
鹿児島県出身の彼が高校生の時、一三年前のことですが、彼は仲間ととことん飲もうと計画し、神主のいない神社の神殿にビール三ダースと焼酎の一升びんを一ダース運び込み、すき焼きをするために、携帯用のガス器具と鍋と大量の肉と野菜を用意したそうです。そして、いざ始めようとした時にお巡りさんが来て取り押さえられ、宴会はおじゃんになったのだそうです。それは、大量にお酒を買った高校生の行動を不審に思った酒屋の主人が、交番に通報したためだったそうです。そこには新聞記者もやって来て、大量のお酒とすき焼きの用意を写真に撮っていき、翌日の地方新聞に写真入りで載ったそうです。その頃は、彼の高校にはコンパという言葉はまだなかったといっていました。その男性はそれにも懲りずに、高校時代からどんどん飲酒し、卒業後東京に就職してからは、言葉の訛などで同僚ともうまくなじめず、お酒を飲むことだけが楽しみとなり、アルコール依存症となって、会社から治療命令が出て病院にやってきたわけです。(「子どもの飲酒があぶない」 鈴木健二)
正式の会の名称
「幻の日本酒を飲む会」と正式に名乗ったのは、昭和五三年一二月にNHKテレビに出演することになり、正式の会の名称は?と聞かれ、こう答えたのである。会の命名はどうでもよかった。集まってくる人たちがおいしいといって飲んでくれればそれで目的は達せられた。酒造組合が吟醸酒を「これこれの原材料と精米で、いわゆる吟醸造りをしたもの」とわけのわかからぬ定義をしたのは昭和五〇年であった。彼らの定義は飲み手には通じなかったようだ。(「{幻の日本酒」酔いどれノート」 篠田次郎)
よし寿司
初めて「よし寿司」に入ったとき、当日の品書きを指しながら「きょう、ここの漁港から揚がったものは?」と訊いたら、「全部」と答えが返ってきたのをよく覚えている。味は高級な寿司屋にも負けないと感じられるのに、さしみと地酒を思う存分頼み、最後ににぎりをお好みで〆ても、支払い額は東京のちょっといい居酒屋と変わらなかった。-
偶然ながら気仙沼の「あさひ鮨」にも、宮古の「よし寿司」にも、それぞれの地元産の「男山」という日本酒がおいてある。(「日本の居酒屋文化」 マイク・モラスキー)
酒席でしばしば粗暴な振る舞い
続いて検察側の冒頭陳述。水野(検事)は梶原の家族関係から学歴詐称(さしよう)、極真会館との関係の推移などを次々に指摘した後、こう結んだ。「数多くの人気作品を創作してマスコミから持て囃(はや)され、収入面でも作家の長者番付に載るほどになった被告は、次第に驕(おご)りの気持ちが強くなっていった。他方、映画の製作をも手がけるようになり、その資金捻出(ねんしゆつ)のため勢い多作を余儀なくされたことなどから作品の質が低下、思うような作品が描けない苛立ちから、酒席でしばしば粗暴な振る舞いをするようになっていった」この間、わずか三十分。傍聴席に集まっていた二十人ほどの報道陣は、盛り上がりのない法廷劇の前に、すっかり拍子抜けしていた。この八日後の七月二十八日、梶原は三千万円の金を積んで保釈された。この間、二度にわたる保釈請求が却下されている。留置日数六十五日間は、梶原が犯した事件に比べ、異例の長さだった。-捕まったおかげで心身ともに元気になった。梶原は後に、そう公言していた。なるほど精神衛生上は、見事にリフレッシュすることができたようだった。だが、と真樹日佐夫は唇を噛む。「体の方はそうはいかない。勢いづいていた人間ほど、いったんガタッとくると駄目になる。精神病理学者のそんな話を聞いたことがあるけど、まったくその通りだと思うよ。何事もなければ、兄貴は百歳まで生きられる体に産んでもらっていたんだ」(「梶原一騎伝」 斎藤貴男)
銀行振込みの請求書
お茶屋や、料理屋のおかみさんに及べば、逸話も多いが、感心させられるのは、その貸度胸のよさである。これに、心利(き)いた仲居でも居ようものなら(ここの家(うち)、勘定いらんのんかいな…)とさえ思わせる店が少なくなかった。先月の払いが残っていようが、月を越えて遊びに行こうが、忘れたような顔である。そうして、そんな店であればこそ「え、貸し倒れ?そんなもんおますかいな」と笑っているし、じじつ、私にしてかが、お茶屋や料理屋に、はらい残しなど一切ない筈である。ところが最近、昔馴染みの飲み屋が島の内へ進出したので、お祝いのつもりで友達を誘って出かけた。ある料理雑誌にも、いささかほめて書いておいた。ところが、さっそく請求書が来たのはよいとして、何んとその金額を、××銀行の口座へ払込んでくれというのだ。「…」飲み屋の請求書もすすんだものとびっくりした。それでもいいつけ通り、払込んだが、一足違いに督促が来るというしまつ。それでも、その店から年賀状をくれた。しかも、アテ名印刷である。しかし、そのアテ名印刷で、またあの銀行払込みの請求書が来るかと思うと、未だに腰が重い。かくて、大阪かたぎも、こういう一角から崩れるかと思うとかなしい。-と書いてから、この話を友人にすると、、この頃そういう銀行振込みの請求書はザラだという。(「味の芸談」 長谷川幸延) 昭和42年の出版です。

銘酒づくししんばん
近世後期になると、外食産業の発達によって、新しい名物、名産が生まれ、急速に人々の食生活を変えていった。たとえば酒をみると、井原西鶴の『西鶴織留』にもみられるように、一七世紀の後半には伊丹の酒造りの中心であったが、生産量では灘・今津が伊丹・池田を追い越した寛政期の江戸入津高を比べても、伊丹・池田は灘・今津の約半分である。(柚木学『近世灘酒経済史』、ミネルヴァ書房、一九六五年)。これだけ灘・今津の酒が大量に江戸へ出荷していても、番付に記載されていない。そこには確立されたブランド力があったものと思われる。新興勢力の灘・伊丹は、伊丹のブランド力を利用することもあった。たとえば、剣菱は伊丹で使用されていた銘柄であったが、明和・安永期になると灘・今津の酒造家が使用した。伊丹では再三にわたり、「類印」や「似寄焼印」の禁止を幕府に求めていくが一向におさまらない。さらに、知多の酒造家でも剣菱が使用されるようになる。そこには伊丹酒の剣菱というブランド力の強さがあった。天保期に作成された「銘酒つくぢぢんばん」(番付7)は、上位は圧倒的に伊丹・池田が占めており、名産としての灘酒のイメージはまったくない。天保一四年(一八四三)の灘・今津の江戸送り酒高は、五三万樽であり、伊丹・池田の約三倍である。番付7の東大関に記されている坂上の銘柄マークが剣菱である。(「番付で読む江戸時代」 林英夫・青木美智男) 写真に「番付7 銘酒づくししんばん 三井文庫蔵」とあります。
五百万石
新潟産米「五百万石」は、昭和十三年、新潟県農業試験場で作られた。酒米に適した大粒種を目指し品種改良を二十年もつづけ、三十二年、県の奨励品種に採用された。この年、新潟米の生産高が五百万石を突破した。これを記念して「五百万石」と名づけられたという。(「酒の旅人」 佐々木久子)
きき酒資格
日本地ビール協会認定の「ビアマイスター」、日本ソムリエ協会の一般向けワイン専門家資格「ワインエキスパート」、日本酒では知識や利き酒、料理との相性を判断する能力を問う「きき酒師」という資格。これらの総称。ここ数年人気を集めている。(「平成新語×流行語小辞典」 稲垣吉彦)
465決死隊
サーカスから一頭のライオンが脱走した。そして、物凄い勢いで町の周辺部めがけて走って行った。ついにライオンを射殺するために決死隊が駆り出された。出発の前に、全員を市長は官舎へ招き、勢いをつけるための酒盛りを催した。ところが、一人の頑丈そうな青年だけが、酒盛りに加わらない。そこで市長が、「おい、君も一杯、景気づけにやりたまえ」というと、その青年、「いやよしときましょう。一杯やると、元気がつきすぎますから…」(「ユーモア辞典」 秋田實編)
フルメイ、マツリゴト
酒盛りは共に酔う必要のある時の大切な行事で、これには唄と鳴りものがつかなければならない、という古い感覚を持っている島や山中の村がある(長崎県久賀島・徳島県祖谷山)。新潟県の佐渡では祭礼のことをフルメイといって、祭に来いということをフルメイに来てくれという。祭以外でも目出度(めでた)い饗応はみなフルメイで、子供らのママゴトもフルメゴトという。あそこの家では「ドタフルメイがあった」というのは、大がかりな酒宴があったということである。鹿児島県の硫黄島では又酒盛をマツリゴトといって、権現様に踊を奉納する日や雨乞・厄払・四大祝日がそれである。家の集落・入営・誕生祝・厄払祝・二十三夜待など個々の家の酒宴も凡てマツリゴトというそうであるが、酒盛-酒を飲むことが祭であった古風を保存していておもしろい。(「食生活の歴史」 瀬川清子)
〇酒の肴に、種々の雑伎、さるがう、古へよりあり。『酒飯論』に、「管弦・乱舞・白拍子、立舞・居舞・東舞、今様・古柳・しをりはぎ、神楽・催馬楽・其駒(そのこま)と、猿楽・物まねいろ/\に、声わざ・骨わざ・力わざ、つくさぬ事こそなかりけれ」(声わざは『著聞集』に「福大神といふ狐人につきて、朗詠・さいばらなどの声のわざ」とも見えたり)。『伝家宝』三集に、本像科(身ぶり声いろなり)・聱声(ごうせい)科・即急口令(早言也。いひにくきことを口疾(トク)いふ也)・鼓嘴(こし)科・開口科(ものまね)・転運科(順にいひ逆にいふ言也)・数絡科(やま売のまねなり)。猶酒令にはさま/"\あり。骰子(サイ)をふりて酒を飲むことあり。景象如意また花紅柳緑また清風明月、なになりとも其時の思ひ付に定めてするにや。喩(たと)へば清風明月は六を風、幺(よう)を月と定め、骰六つをふりて幺と六とを出さむとす。出ざれば酒を飲みて骰と盆とを送る也(景象如意などは晴和日なり。日を幺に定め骰一つを用幺をふり、得ざれば酒をのみ盆を送る事同じ。童べのするピンころがしといふ事に似たり)。(「嬉遊笑覧」 喜多村筠庭 長谷川・江本・渡辺・岡・花田・石川校訂)
酒を飲みながら
オペラ、バレエ、芝居、コンサートなどを鑑賞している場合、大きな盛り上がりがあったりするときには、一緒にいる人と感想を述べ合ったりしたいと思う。しかしながら、周囲の人の迷惑になるので、それは諦めざるをえない。休憩時間や終演後まで待たなくてはならない。もちろん、開演中の飲み食いは以ての外である。舞台芸術であれ何であれ、人を楽しませようとするのであるから、広い意味の「娯楽」である。見にきたり聞きにきたりする人は、それに対して金を払っている。最も満足のいく方法で楽しみたいと思っている。「鑑賞」を客に押しつけるニュアンスが一般的な傾向となっているが、この点に関しては、ある程度は再考の余地があるのではないか。飲食をしながらであればもっと楽しめると考えている人は多いはずだ。ナイトクラブのショーなどは、その欲求を満たす典型的な例である。そのあたりに、舞台芸術などの原点の一角がある。もちろん、ほかの観客や聴衆に対する迷惑という点も考慮しなくてはならないが。相撲の場合は、実際に相撲を取っている時間でも飲食ができる。さらに、それ以外の時間は、見ている人の裁量において、完全な「幕間」にすることが可能である。その幕間は完全な酒宴の場と化することができる。「花より団子」ならぬ「相撲より酒」の人もいる。その人のとっては、相撲が「つまみ」である。そういったとしても、相撲を軽んじているわけではない。ただ、酒飲みとしては何をするときでも「酒を飲みながら」できれば最高なのである。
三つ割り
天璋院(てんしよういん)さま[十三代将軍家定夫人]もこのごろは一つ飯台(はんだい)で大勢の女中と一緒におあがんなさっていたが、のちにはおれなども同じ部屋でご馳走になることもあった。すると酒でも三升徳利か何かに入れて、ああいうふうな処(ところ)へ置いて、少しずつ出してお飲みになるから、「それは何というけちくさいことです。三つ割り[四斗の三分の一の量を入れる樽(たる)]お取り寄せなさるがよろしい」といって、おれが自分で立っていって注文するのさ。そうすると、お付きのものは、「勝さまは気が大きい。気が大きい」といって驚くし、天璋院さまでも、やはり三升徳利の方がうまいと仰せられたそうだ。それからは、お菓子などでも箱を一々あけて紙に包んで天井へつるしておくというようなふうに、万事倹約主義になって、大奥がむつかしいなどということはけっしてなくなったよ。(「氷川清話」 勝海舟) 大奥に倹約を定着させるために勝が行ったやり方です。
新酒(植物)(地理)
独酌
栴檀の実の飛びこみに新酒哉 嵐外
一里松までは新酒のにおひ哉 龍千(西華)
初萩の花の雫に新酒哉 沙明
住吉の升も間にあふ新酒哉 柳居(故人五百)
新酒出て山や紅葉のにはか照 津宜(句鑑遣)
山中や別当殿の今年酒 暁台 (「分類俳句大観」 正岡子規編著)
手堅く手堅く
蔵の建物なんかの話も少ししておこうかいの。鉄筋蔵の後、昭和三十七年には二号蔵を建てて、鉄筋蔵を一号蔵というようになったわけさ。そして、昭和四十六年から四十九年にかけて、三号蔵を建てた。この三号蔵は今では「吟醸蔵」と呼んでいるが、それに加えて、最近、吟醸蔵の横に新しい蔵を造ったすけ、今は全部で四つの蔵があるわけだいの。そんげなふうに継(つ)ぎ足(た)し、継ぎ足しで蔵を大きくしてきたから、口の悪い人間は、化け物屋敷なんていうだんが、南雲家は、いきなり大きな蔵を建てるようなことはせずに、手堅く手堅くやってきたんですて。設備のほうもそうですよ、造る石数(こくすう)が増えて、使う米の量も増えてくると、精米屋に頼んでいたのでは間に合わなくなるすけ、昭和四十二年には、このあたりの五つの酒蔵が集まって、共同精米の会社を始めたんだわ。この共同精米は今でも続いているが、その後、やっぱり自分のところにも精米所がほしいというこんで、昭和六十二年に自前の精米機を入れたんだわ。こういうやり方を見ても、手堅いのがわかるんでないかね。(「杜氏千年の夢」 高浜春男)
風流狂歌盃報条
そも盃の濫觴(らんしよう)は、ちよくらちよとこれをかう持て、三日月なんどの形を表し、左のきくは天の道、そこをしたむは地のきよめ、天地のあいは手本となる。人と生れて酒のまぬは、玉の巵(さかづき)かつちりのごとし。見ぬもろこしには金屈巵(きんくし)、わが日のもとには内ぐもり、其土器(かはらけ)のすなほなる、ためしを今に引盃。また三組の三指より、候べく候のべく盃、小原たつもゝ(辰股)とらまへて、酒7のませんとの一興には、狂歌をよもに過さるべしと、例の赤良の筆をかり、すゝむる酒の徳孤(こ)ならず、かならず隣の松蔭も、今一しほの色をそふ、枝も栄て葉もしげる、千代のこの/\盃が、まはつて来たは/\。まはらぬところは御目長に、御覧の通り狂歌盃、よいもわるいも御手にとつて、たゞよい/\と御評判奉希候以上。(「四方の留粕」)
[瓜菜を糟(ぬか)づけする法]
多少に拘らず、石炭・白礬(はくばん)15を用て煎じて湯とし、冷やし浸すこと一伏時16。煮たる酒をして糟・塩を泡立たせしめ、銅銭百余文を入れて拌(ま)ぜ匀(ととの)ふ。醃(しおづけ)すること十日にして取り出し、拭(ぬぐ)ひ乾かす。別に好「酉曹」・塩・煮たる酒を換(か)へ、再び拌ぜ、「缶覃」(かめ)に入れて収め貯へ、箬葉(じやくよう)17もて口を扎(さつ)し、泥もて口を封ず。
⑮白礬=明礬。 ⑯一伏時=一昼夜。 ⑰箬=くまざさ、たけのかわ。
[かすづけ瓜の作り方] 量にかかわらず石灰と明礬を入れた湯で煎じ、一昼夜冷水に浸しておく。沸かした酒を糟と塩に加え、更に銅銭百文ほどを入れてよくかきまぜ、十日ほど浸けておく。取り出して拭い乾かし、別に上等の糟と塩、沸かした酒をまぜて用意していれかえる。再びまぜてカメに入れて収め貯え、くまざさの葉で口を蓋(おお)い、泥で封をする。(「食経」 中村璋八・佐藤達全訳注)
煮物 すみつかり 浦里酒造店 浦里晴美さんのお勧め
茨城県の郷土料理です。初午の前夜に作り、お赤飯と一緒に氏神様に供えます。また初午以外の日に新しく作ることは忌み嫌われたので、追加したいときはこのときのものを少量取っておき、鍋を洗わず作り足します。
●材料(人分) 大根 1本/人参 1本/油揚げ 1枚/いり大豆(節分の残り) 1/4カップ/板粕 130グラム/砂糖・醤油 少々/お酢 少々
●作り方 ①いり大豆は皮をむいておく。 ②大根と人参を鬼おろしでおろす。 ③油揚げを油抜きして、細切りにする。 ④鍋に、おろした大根と人参、大豆、油揚げ、酒粕、おろした大根と人参の順に敷きつめ、砂糖、醤油で味つけしてさっと煮る。 ⑤火を止めたらお酢を入れる。
◆郷土料理で、各々の家庭によって味つけが違います。(「酒粕の凄い特効」 滝澤行雄)
昭和21年12月23日
「浜清」は見違えるほど立派に成っている。最初来たときは一間きりだった。それがいつか二間に成っていたが、久し振りに来てみると、二階が出来ている。女中も二三人いて、「いらっしゃいまし」と迎える。階段を昇りながら、驚嘆するのだった。大変な建築費だろうが、-食い物屋は恐ろしい。つくづく思うのだった。川端さん、武田未亡人-等、みんな揃っている。新田、渋川、伊藤、小林(圭)、小林(美)、和田、鍛代、三島、小野、それに「六興」から矢崎、石川、大門の諸君。全集第一回刊行記念の集まりだ。日本酒を五六杯飲んだ。新田、小林(圭)君等、ウイスキーで酩酊、新田が、「小島政二郎が二百円で、俺が六十円。ひどいねえ…」例のユーモアのある声でそう笑い、一座はどッと笑った。小林君は「ロマンス」の記者をやっている。その稿料である。「あんまり、差をつけるなよ」どッとみな、笑う。「二百円じゃなかった。百円だった」と小林君が言う。「今になってそんなこと言ったってダメだ」と新田。愉快な会だった。(「終戦日記」 高見順)
師走の酒
年の瀬には誰もが忙しくなるのは常識で、眼が廻りそうで正月が来ることなど信じられないことがあるが、それでも酒を飲むのは年の暮が一番落ち着くようである。一年間の仕事がとにかく、もう終りに近いと思うからだろうか。年の瀬が勝負の職業も無論、少くはないだろうが、一年をこつこつ何かやって過ごす仕事で食っているものにとっては、年の暮はもうその年が終ったのに近い。文字通りに、年の暮れであって、それだけに、酒の味に、普通はない何かが染み込む。あるいは、酒の味がそう変わらなくとも、自分が酒を飲んでいる姿が一歩離れた所から眺められると言っていいかも知れない。そしてそれまでにあった年の暮のことが頭に浮かんで来る。(「続酒肴酒」 吉田健一)
十九日 晴、常陸下妻に至らんと欲し、夙に起きて程に上る。田畝村落の間を行くこと七里、未後水海道に至る。浪門善六の家に就いて飯を喫し、去りて下妻の里程を問ふ。路人曰く、五里にして遙かなりと。三人相謀りて曰く、日晷(ひかげ)に路遠し、詰朝(きつちよう)兼行走趨するに若かずと。乃ち浪門家は旧角抵家、頗る任侠を以て自負し、之れに酒を喫せしむ。善く飲み、酔後劇団縷々(るる)、夜三更にして臥す。
念(二十)日 宿酔未だ醒めず、日晷(ひかげ)て起く。主人酒饌を供し、亦雄談大酌、蹌踉(そうろう)として程に上る。主人は子を携えて送り駅外に至る。晩間風寒く、雪の下酔ひ頓(とみ)に醒む。夜下妻に至り、鯨井勇吉の家に投宿す、主人は吾婁と相知れるを以てなり。小酌して寝に就く。此の日酔中他の奇観を記(カ)し得ず。祇(ただ)鬼怒川(きぬがわ)の潺湲(せんかん)と流れ、筑波峰の歩々相近きを見るのみ。(「東北遊日記」 宮部鼎蔵) 嘉永4年12月の日記で、吉田松陰と同行の旅ですが、この時はまだ松陰と合流していません。
もう一日分あり
酔いがさめて 崔道融(さいどうゆう) 前野直彬(まえのなおあき)訳
酔いがさめて灰の中からかきおこす残り火
いまこの時のわびしさは測り知れぬ
炉ばたでひとり酌(く)み また酔いに沈む
真夜中の窓を打つ風まじりの雪(「酒の詩集」 富士正晴編著)
ホップの抗菌作用
中世ヨーロッパでペストが大流行したとき、ある町の神父が「水は飲むな、ビールを飲め」と指導した。当時、人々にとって、神父の指導は"神の声"。素直にしたがって、水の代わりにビールを飲んでいると、その町の人々だけペストから助かったのである。大量の死者をだしたペストを前に、被害を最小限にくい止めたことは奇跡に近いこと。当然、その神父は、ビールに抗菌作用のあることを知っていたのだろう。じっさい、ビール製造につかわれるホップには、抗菌力がある。そのためビールには、有害菌の侵入感染を妨(さまた)げる作用がある。有力な感染源である水を飲まずにビールを飲んだことが、ペストから逃(のが)れることになったと考えられるのだ。ビールの抗菌力は、古代エジプト時代から知られ、流行病の予防や治療に薬として用いられていた。また、中世アラビアの名医イヴン・スィーナーは、ビールの飲用をすすめているし、当時、有名になった『養生訓』には、ビールの利尿効果も紹介されている。明治の文豪、森鷗外が、留学先のミュンヘン大学で研究したのもこのビールの利尿効果で、明治時代の日本ではビールは薬局で売られていた。(「酒のこだわり話」 博学こだわり倶楽部編)
両関
そのころ、酒好きのある大臣(一説には宮様ともいう)が来県した。当時の伊藤恭之助・県酒造組合連合会長は、秋田の酒を宣伝する絶好の機会と、昼の歓迎会に「両関」を出させた。すると大臣は「今まで飲んだことのないおいしい酒だ」とえらくご満悦で、知事が「今晩は灘のいい酒を差し上げます」というと「いや、地酒を出せ」ということになった。その夜の二次会の会場は「秋田倶楽部」(料亭)だったが、当時は灘の酒しか置いていなかったので、あわてて方々の酒屋さんを探し、やっと湯沢の「両関」を買い求めて大臣に差し上げたというエピソードが伝わっている。現在、県外酒の売り上げはわずか1%。これほど地元の酒が飲まれている県はほかにない。が、ここに至るまでには、まだまだ苦難の道のりがあった。(「秋田雑学ノート」 読売新聞秋田支局編)
銘柄はナイショ
もうだいぶ前のことになるが、西荻窪の軍鶏(しやも)料理が看板の居酒屋で、黒板に書かれた酒の品書きの中に「ノーラベル」というのがあった。「いったい何じゃいな?」と思って、ためしにたのんでみたら、女将さんが取り出してきたのが、何のラベルも貼ってない丸裸の一升瓶である。蔵元が、ごく少量、特別に造った酒を縁故あるところに配るような場合、裸の一升瓶を新聞紙などでくるんで、その上から手作りのラベルを貼るといったケースはあるが、居酒屋でまったくの丸裸の瓶を目にするのは初めてだ。女将さんは、その瓶からグラスになみなみと注いで出してくれた。中身がわからないので、お燗だ何だとうるさいことは言わず、そのまま冷えた状態でいただいてみる。すると、これがキリリとしてなかなか美味い酒である。軍鶏鍋にもよく合って、結局、その日は最後までそれで通したのだが、銘柄が知りたくて、帰りしな女将さんに、「あれは何ていう酒?」と尋ねたら、即座に、「ナイショ!」ときた。酒の名を隠さねばならないどんな理由があるのかわからないが、そのキッパリとした口調に、それ以上食い下がるのはやめにしておいた。しかし、しばらくその銘柄が気になってしかたがなかったものだ。でも、今は酒の名を知らされないというのも、またいいものじゃないかと思う。最近は、ラベルや品書きに、銘柄だけでなく、種別、アルコール度数、日本酒度、酒造米や酵母の種類など、様々な情報があふれている。あらかじめ飲む前にそうした情報がインプットされると、どうしても先入観がはたらいて、純粋に味わえないことも多いのではないか。そう考えると、「銘柄はナイショ」、というのもかえって一興である。(「晩酌パラダイス」 ラズウェル細木)
ついてはここで
右の清岡君の先輩町田氏は風貌魁偉、文字通り南国の雄として斗酒尚益々弁ずる外、数日の流連を至芸とする御仁であった。一旦腰を据えて、酒盃を手にすれば、その家に少くとも三日は居つづけるのであった。仕事があろうと、大臣や次官から急の召集があろうと、文部省議の日であろうと、全然我は不関焉(かんせずえん)として、酒にのみ親しむ風であるので、流石頑固の岡田良平文部大臣でさえ「町田の酒は困ったものだ。やがて当人も健康を害ねて苦しむだろうに」と珍しくも、さじを投げていた。-
然るに当の町田局長は、給仕の少年に命じてひそかに、局長室の青いテーブルの下に日本酒、ビールなどを忍ばせておき、茶碗の茶を窓外に捨てては、朝から親しんでいた。盛夏の候、次年度概算査定で大汗、大童になっている最上君慰問と称して大臣官邸にのり込んだはよいが、註-其の年代には全国直轄諸学校の概算査定は最重要事件として文部大臣官邸内で先ず最上君がやっていた。「君が一切よくやってくれるので万事を任せて俺は安心だよ、課長と君とで局の仕事はよろしくやってくれ。ついてはここで一寸手を休めて、冷たいビールで乾杯しよう」と、概算査定の件など、振り向きもせず、専らビールの満を引く程、すべてが酒だった。やがて一年位の後、本物の胃腸障害をひき起して房総地区に一ヵ月半転地して静養した。又一年たって、宗教局長に変更された。これは門司氏の策動による左遷だと大いに痛憤していたが、やがて退職して、新興満州国に赴任した。(「文京の今昔物語」)
街裏 室生犀星
私はいまでも
一人きりになつてさびしい街裏をたづねてゆく
そこで静かに酒をのむ
誰とも行つたことのない
誰にも知らない湿々した小路の奥で
ひとり坐つたなりで
野に置かれたやうに長い時間をおくる
雨のときはぬかるみにかげをおとして
ぬかるみを拾ひ歩きして
うすぐらく
路地のおくをたずねてゆく
そこで私はがりがりと何かたべてゐる
むりに子供のくちへおしこむやうな食べものが私に強ひられる
さうして酒をのむ
いろいろな人間の心が其処にすわつてゐる時、みな浮きあがつてくる(「酔っぱらい読本・弐 街裏」)
大黒図への賛
先生、ぶらりと立寄った商家は、常に御出入りの顔馴染の穀屋であつた。広くもない店先へ腰をかけ、ふと奥の床の間を見ると大黒の図が掛かつてゐる。-然し自画には無印が多い、大酒の為に文化十年九月、三十七歳の有為の志を抱いて、あの世の人と成った。惜しむべき画人でもあり立派な人物であつた。と、一渉り話すと主人も喜び、座に招じて酒肴を調へ大に待遇した。東湖先生大分酩酊して「主人、吾に賛を入れさせて呉れまいか」と、言ふと、主人は賛なる者を知らぬ。夫れを説いて狂歌を詠じて之に題した。 大黒も米二俵では喰足らず 打出の小槌ふれやふれふれ 主人も喜び、先生も喜び、昏に帰つたと云ふ。水戸紀年(黒羽根三郎口語)にある、今此の画何処にか愛蔵されて居る筈だ。有れば千金の値である。(「水戸秘譚」 斎藤新一郎) 先生は藤田東湖、画家は林十江です。 林十江
お母さま
先生はあんなでいて親思い、師思いのご仁で、どんなに酔って乱暴をなさっていても、お母さまが顔をお出しになったが最後、柔しく静まり返ってしまっておかしいくらいでした。また師思いの点ではこんなことがありました。先生は駿河台狩野出身ですが、御本家は木挽町狩野ですからご本家を尊重されていましたが、御維新後ある時、上野公園を人力車で通ったら向こうから木挽町狩野のご当主栄徳さんがヒョコヒョコお歩きになって見えたので、慌てて車から飛び降り、その前へ行ってひれふしたので、ご本家も愕いてなんですかと聞かれ、「手前は駿河台狩野の洞郁です」と申し上げ「どうしていらっしゃる」と言えば、「扶持に放れて惨めなものだが博物館へ下絵を描きにいっている」と申されたので、先生は世が世であればと慨嘆されました。(「河鍋暁斎」 落合和吉編) 内弟子だった綾部暁月の思い出話です。
雪の夜は熱燗と美女の匂い
その角梨枝子とは度々ロケーションに付き合っていた。ほのかな想いが私の方にあったということだろうが、《放浪記》の尾道、因島ロケにも出掛けていった。尾道から夜汽車で大阪に向かう夜は、地元のひとたちが驚くほどの寒さで、夜更けに大阪に降りたら、季節外れの雪である。まだ看板をおろしていなかった梅田の一杯飲み屋に駈けこんだ私たちは、「ホテルに行っても、なんにもないから」と、店の親父さんに頼み込んだ。熱燗をつけてもらい、厚手のコップに注いでキューッと胃の腑に流し込む。煮こごりのつき出しも結構なものだったが、「アラ、みんなここだったの」と顔を出したのはヒロインの角梨枝子だった。たちまち角梨枝子を囲んで白木のカウンターは、私たち映画記者の熱気溢れる集会の場となった。さぞや親父さんとしては辟易としていたのだろうが、夜が白々と明けるまで角梨枝子も私たちと熱っぽく語っていたものだった。いま思えば、良き時代だった。いまスターといわれるレディたちで、こんな付き合い方をしてくれるひとは、ほとんどいない。プロダクションに所属し、マネージャーが逐一管理している状況では、彼女たちにその気があっても、世間が許さないってことであろう。グイグイ飲みながら、ポンポン本音をぶつけてきた角梨枝子の紅い唇がいまも忘れられないが、夜の明けた大阪の街は、珍しくうっすらと雪化粧していたのである。(「いい酒いい友いい人生」 加東康一)
酒の詩集
富士正晴氏の編である『酒の詩集』(光文社刊)は、これもまた愉しめる。この酒の詩のアンソロジーは、古今東西の酒の詩を、楽しむ酒、悲しむ酒、笑う酒、恋うる酒、旅の酒などの十二章に分類し、各章に編者の詩がついているが、これがなかなかよく、コクのある味だ。「勇み酒」の章にある富士さんの詩。
酒に対って歌わん!
えいや えいや えい ほう ほう
酒に対って歌わん!
えいや えいや えい ほう ほう
押し出せ 押し出せ 出陣だ
敵は幾万ありとても
押し出せ 押し出せ 出陣だ
おれらにかなうものはない
これは、まさに「勇み酒」だ。例えば、友人と家で飲んでいて飲み足りなくて外へ出かけようという時に、この詩は口ずさむのにふさわしいし、男の酒、男同士の酒の感じだ。(「作家の食談」 山本容朗)
殷 BC一六〇〇 河南省鄭州遺跡から酒造場跡を発見(『中国酒』一九七九)。
酒は糖質に酵母が加われば自然にできるものであるから人類以前から酒精飲料はあったと考えられる。中国で伝説上の酒の発明者は、夏時代の儀狄(『戦国策』)と周代の杜康(小康)となっている(『世本』)。酒は『周礼』に酒人、酒正などの職名が見られるほか、当時のほとんどの本に出てくるので人類とともにあったことはわかるが、醸酒法が具体的に見られるのは六世紀の農書『斉民要術(せいみんようじゆつ)』である。(「一衣帯水 中国食物史年表」 田中静一)
或る日の酒父像
見ると、父は、どろんこといっていいほど泥酔していた。フロックコートを着ていた。その洋服も帽子も、地面で寝て来たかと思われるほど汚れている。何か、ぎょっと人に映るような顔色と眼であった。どすんと、大きな物音をさせて、勝手元の何かにつまずいて、ぶっ仆れたのを、母が扶(たす)け起して、家の中へひきずり上げるように抱えこんだ。ぼくにも、ただならない父の容子が分ったのであろう、あわてて膳のそばを離れ、学校履きの草履袋を手に持つや否や、表からコソコソ出て行ってしまおうとした。すると、その背中から「英(ひで)っ」と、父の呼ぶ声がした。小さくなって、父の前へ戻った。父は座り直していた。父の顔や手にスリ傷があった。母にはもう何もかも分っていたのだろうが、そばで泣いていた。母の泣く姿も、今ではすでに母の仕癖(しぐせ)のように、右の袖口を、左の指先につつみ、掩っているのである。幾日も、酒へ酒をあびていたような匂が父のからだから発散する。「-おまえ は な」と、父は云った。息切れが聞こえるのである「…英、おまえはな、長男だ。お父さんは、訴訟に負けたよ。もう、おまえばかりでなく、こんな大きな家にはいられない。おまえは長男だから一番先に働きにゆけ。いいか」と、何度にも、息をやすめては云った。ぼくは「はい」と答えた。と答えるしかないし、またよく父のいう意味が分らなかったのでもある。だから、父のことばが終わると、また草履袋を持って、すぐ学校へ行こうとした。すると父は立ちかけるぼくを見て「まだ分からないのかっ」と、こんどは、いつも悪酒になると出る大声でどなった。そして、「もう、学校へ行かなくともいい。学校を退いて、おまえから先に働きに出るんだ。わかるだろう、お父さんの云っていることは」と、云い放して、梯子段を這うように、二階へ上がってしまった。それから、たった三日目か四日目に、ぼくはよそへ奉公に出ることになった。(「忘れ残りの記」 吉川英治)
嘉納治右衛門
〇長崎へ行く前、渋田と別れるときに渋田は、「万一、私が死んであなたの頼りになる人がなくなっては」といって、二、三人の人を紹介してくれた。が、その一人は嘉納治右衛門(かのうじうえもん)、これは治五郎(柔道・弘道館の開祖)の親に当たるので、灘(なだ)の酒屋をしていたのだ。のちにおれが神戸へいったときには、機械の類はみんなこの人に買ってもらったのだ。いま一人は伊勢の竹川竹斎という医者で、その地方では屈指の金持ちで、蔵書も数万巻あった。それからいま一人は日本橋の浜口、国会議員をしている浜口の本家であった。すべてこれらの人はそれぞれ一種の人物で、さすがに渋田の眼識は高いものだと、おれはあとで悟った。(「氷川清話」 勝海舟) 渋田利右衛門は貧乏時代の勝海舟を助けた北海道の商人です。
宵の間にちくと来よとのお情けを受けて一盃飲むよしもがな [銀葉夷歌集・七・恋]
作者、よしたか。「酒に寄する恋」。 ちくと=ちょっと。酒を竹葉(ちくよう)というので、これを匂わせるか。 受けて=さされた盃を受ける意を掛ける。
作者よしたかは、巻末の作者目録に、民部少輔嘉隆一首とある人。嘉隆ですぐ頭にうかぶのは、九鬼嘉隆(一五四二~一六〇〇)であるが、この人は右馬允、大隅守で、民部少輔ではなかったようである。『地下家伝』などにも、嘉隆の名は見当たらない。(「狂歌観賞辞典」 鈴木棠三)