船の新内流し 赤米・紫黒米・香り米 生酒の燗 マグロの梅昆布ばさみ ささやかな奇跡 婬・酒の二つは ばくろちやう【馬喰町】 もの食ひ、酒飲み 大酔 天明七年の珍事件 三低晩酌 まえがき 「お通り」の恐怖 オメガ のみすけ(飲み助) ふろふき大根の柚みそ 竹葉青酒 某月某日 同窓会 古谷、尾崎、壇 御授爵のお祝い 又六が門極楽と聞くからに 伊藤左千夫の酒歌 島井宗室遺言状 土熬鍋 モン・アサクサ 酒のエンゲル係数 東京湾岸のおでん屋 縄のれん にぢ あつ燗おでんだし割り 【隠し言葉】 お三方 アイラク 漱石の酒句(2) 根本正書 〇上戸を下戸にする事 新八 梅たたき 酒徳 いまトレンドの酒処 山形 幻の日本酒を飲む会(2) 精神安定剤としてのアルコール 岩の井 正弁丹吾 胆石 昼食の混雑時 お酒漬け 与次郎人形 モリ 464余計なお世話 ネクタイアル中 日本料理 大酔して醒めないとき 老舗企業設立年表 とっくり(に)すぎたヨシヨシ 新酒頌 田中先生 爛漫 ダリヤ 酒を楽しむことは人権の一部 オオバコ、ゲンノショウコ酒 飲み屋の中で 石狩粕鍋 三段返し カラスの女房 板粕 夫婦同伴で「お通し」の味を盗む 中国食物史年表(古代) 酒飲みの自己弁護 夕焼けってのは悲しい お酒のよいのを持って来る方 冷し酒 あの頃 酔小楠 くよくよ 熟成の裏ワザ 上機嫌な父 狗に肴の番 前の秋田の酒 子どもの飲酒があぶない 法善寺の味 昭和21年9月 子規の酒歌 南部美人 日本の酒のルーツをたどる 御酒被下 酒に対して喧嘩腰 酒痴末法 セックスアピール ぶり照り焼き 干酵 のみコン 食べ物を描かない宴会 腕相撲 結婚披露宴 数あれど… 集団の性質と飲酒の習慣 泉石老人 ◆蒸しがんも 食と酒 懐風藻 関矢さんのお酒の世界 蔵癖、場所癖、容器癖 月見酒 観戦記(3) なまよひ[生酔]酔ッぱらい。(3) 私の知っていた吟醸酒 玄い米で醸す純米酒 解悶 茄子の田楽 鳥七(大井町) 〇一休和尚の歌 水戸黄門光国卿示ス二家臣ニ一条例 漱石の酒句 酒を温むべし 茅台酒 死の行軍 【地口】 のめどもつきぬ おい癌め酌みかはさうぜ秋の酒 節税酒 463 えっ? わかれのおみき 製造石数半減 疲労が極度に達しているとき 小玉 此君盃の記 福光屋 二〇、食べて毒なもの 肥後の赤酒 イトマと聖者バミバ 居酒屋の披露宴 正宗の一合壜 八海山 「酔郷記」仮に終2 凝りに凝った焼き豚 思いをはらすために 相手の左側 ドリンク・デスマッチ 居酒屋は社会をうつす鏡 酒袋 王手飛車 忘年会と文相の死 天井のバラ 酔ってはいなかったワ 食べる話に飲む話 <ある調査結果> 孟宗汁 ワサビの粕漬け 甘酒 一夜酒 一番仕事をしたぞ 飲みっぷりの良さ 酒はいつだって おふくろの後など追うな 低精米の酒 タマキは大きくなったら 長春清酒 梅北国兼 禁酒法廃止案成立 物を食い酒を飲む 酔っぱらい 名うての酒豪 ギルガメシュ 酒失と帰国 送別 片岡市蔵 極楽寺殿御消息 ○不酔酒薬 み-わ【酒甕】 とみ廣 飲酒 足利義量 国菌 C.種麹(たねこうじ) 六月二十一日(土)晴 夏至 下戸一族VS飲酒派 しっかりと造られた酒 長期低温発酵 [鹿の角の酒] 賀茂茄子入り出し 滴酒 幻の日本酒を飲む会 酔郷記 シェーラブ・レティとイトマの出会い 上京記 イシドー・アインスタイン 高知のいい女 ぼくの父 大石良雄 小布施堂 四方の留粕の序 <和風バー> なまよひ[生酔]酔ッぱらい。(2) 観戦記(2) 土曜日の午前十時 県単位で開発した酵母 星の郷の銘酒「夢みて候」誕生 自分の稼ぎ 大瀁村の破屋へ疎開 スローフード、スロードリンクの時代 大雅堂 付妻玉蘭 牡蠣の磯焼き(串焼) さかづきあいさつ 酩酊 現代の徳利収集譚 利き酒師の講演会 文学と飲食 なわのれん(縄暖簾) 〇酒柄杓 酺 某月某日 敗北 井伏と田中 昼間の花見 黒ぬり、朱ぬり 共食 462ゆっくり後で ちいママ娘 のみくち【飲口】 竹酔日 コチ <山の神> 乱酔狂筆を揮いて捕縛せらる 永昌源 道楽 カウンター トム・アンド・ジェリー 一升入る壺は一升 居酒屋等のアンケート調査 登城前から二升ぐらい 中原早苗 二十四針 酒間の友 赤塚の移籍 トウモロコシ・ペプチド カモのウルカ *ビールを飲むとトイレに行きたくなる アジ 成田山新勝寺の禁酒絵馬 菜館 枯らし 徹夜酒 プレミア酒 酒で記憶をなくす 血による儀式をすてる 大人の濁り酒カクテル 下戸の猩〻 船がつきます百廿五艘 一杯は安多加の関の心地 大酒致候
船の新内流し
鈴木 昔のお客さんはたいへん粋(いき)だった、という話を聞いたんですけれどもね。お客さんたちで船を出して、新内流しなんかやると、玄人(くろうと)かと思ってお捻(ひね)りがきたというんですね。
朝じ そうそう、これは終戦直後に、お客さんが、「朝じ、ひとつ稼ぎに行こうじゃないか」、「そうね、いいわね」ということで、私が姐さんかぶりして三味線弾いて、もう一人、光子さんというのが上調子、そしてお客さんが船漕ぐわけですよ。そして漕ぎ手のお客さんのお友達が歌うんですよ。門付(かどづ)けで、「えー、今晩わ」(笑い)。そのとき二百円くらいご祝儀くれるの。
鈴木 その頃の二百円はたいしたものでしょう。
朝じ よその店のお客さんが「新内流(しんないなが)しか、珍しいな」ということでくれるのね。それから、「稲垣」さんの妹さんの「鈴川」さんに行ったら、「あら、朝じさんだわよ」ということでめっかっちゃったの(笑い)。今度はお酒になっちゃった(笑い)。
鈴木 当時お酒は、いくらくらいしたんです?
朝じ そうですね、一升四、五十円くらいじゃないかしら。お酒二、三本もらいましたよ。(「友あり食ありまた楽しからずや」 鈴木三郎助・柳橋芸者加藤はる(朝じ))
赤米(あかまい)・紫黒米(しこくまい)・香(かお)り米(まい)
紫黒米についての記録は定かでないが、赤米、香り米は元来野性的な米で古代から全国各地で栽培あるいは普通稲に交って生育していた。しかし、赤米、紫黒米は食味が悪く、白米に混入すると見栄えが悪いことから明治中期以降に水田から排除され、現在では祭神用に対馬、種子島等でごくわずか栽培されている。赤米の色素はカテキン、カテコールタンニンおよびフロバフェンであり、紫黒米の色素はアントシアニンで、炊飯するとこれらの果皮の色素のためおこわのように赤くなる。香り米は世界の稲作諸国に古くから広く栽培されてきたが日本では古くから高知県、宮城県等のごく一部で栽培されていた。炊飯時に普通のうるち米に数%混ぜて炊くとじゃ香(じゃこう)、あるいは香ばしい香りが発生し風味が向上する。近年復活のきざしがあり、みやかおり、キタカオリ、はぎのかおり、サリークィーン等の品種が育成されている。サリークィーンは長粒で香りが弱いため混米でなく単独で炊飯する。(「改訂灘の酒用語集」 灘酒研究会)
生酒の燗
生酒を燗するというのは、酒の常識からすると禁じ手ではあるが、造りのしっかりした純米無濾過生原酒であれば、燗が実に旨い。生酒を燗にすると酵素臭がすると酒業界のなかでは言われているが、しっかりとした骨格を持っている酒であれば、気になるレベルではない。筆者の感覚が鈍いのではと思われる業界の方もいるだろうが、これは高田馬場の地酒居酒屋の名店「真菜板(まないた)」でも通常やっていることで、そこに来ているお客から旨いという賛辞はもらっても、変な臭いがすると文句を言われたという話は聞いたことがない。もともと酒造りにおける火入れは生酒に燗をつける作業であり、自然な行為なのである。(「蕎麦屋酒」 古川修)
マグロの梅昆布ばさみ
作り方①マグロは、中央に切り込みを入れながら切る。 ②塩昆布は細切りにする。 ③マグロの間に梅肉と塩昆布と芽ねぎをはさんで盛り付ける。
材料(2人分) マグロ…100g 梅肉…大さじ1 塩昆布…2~3枚 芽ねぎ」…少々
このつまみに、この一本 手取川(てとりがわ) 吟醸/石川 日本酒度…+6 酸度…1.1 価格…2719円(1.8l) 吟醸王国、石川を代表する名蔵元「吉田酒造店」の気品あふれる吟醸酒。口にふくめば、まるで桃のようにみずみずしく、華やかな吟醸香が立ち上がってくる。マグロとの相性も良。(舶来亭)
マグロの目玉焼き
作り方①ボウルに水を入れ、マグロの目玉をサッと洗う。押さえるようにしてふき、酒をまわしかけ、塩をふる。 ②魚焼きグリルで両面に焦げ目をつける。 ③器に盛り、ラップなしで電子レンジで2分加熱し、中まで火を通す。 ④レモンのくし形を添える。
材料(2人分) マグロの目玉…1個 酒…小さじ1/2 塩…少々 レモン…1/2個
このつまみに、この一本 銀嶺立山(ぎんれいたてやま) 本醸造/富山 日本酒度…+5 酸度…1.4 価格…2040円(1.8l) パリ万博へも酒を出展したという由緒ある蔵。スキッとした旨味とキレを持つ上品な味わいが、マグロのゼラチン質のこってり感をすっきりと洗い流してくれる。濃い味の料理に。(舶来亭)(「酒のつまみは魚にかぎる 新・日本酒の愉しみ」 編集人・堀部泰憲)
ささやかな奇跡
保険証の入ったパスケース、クレジットカードの入った財布、携帯電話。この三つは、なくしたと気づいたときにはげしくへこむ三大神器だと思う。どこでだか財布をなくし、キャッシュ、クレジット含めカード関係をあわてて止めた。が、ともに飲んでいた人のぴかぴかの記憶力のおかげで、何軒目かの店で見つかり、案外早く戻ってきた。カードが又使えるように数社に連絡したのだが、いったん使えなくしたカードを使えるようにするには、ものすごい手間と日数がかかるのである。しかもクレジットカードは番号を変えねばならず、そうすると、かつての番号で登録していたものみな変更してまわらねばならず、「飲んでいて財布をなくした」だけのことに、まったく不釣り合いなほど労働が求められる。パスケースをなくしたときは警察に遺失物として届けた。入っているのはスイカカード、保険証、区役所で発行される印鑑カード、文藝家協会やペンクラブの会員証など。これはもう、さすがに出てこないだろう、保険証で何かされなければよしとするしかない、と思っていた。けれど二週間ほどたったある日、「警視庁遺失物センター」というところから、受付番号の書かれた葉書が送られてきた。そこで保管されているという。とりにいってみると、スイカも使われた形跡がなく、保険証も会員証も、もともとあったものはぜんぶあった。都心の駅構内に落ちていたのを、だれかが届けてくれたらしい。携帯電話もまた面倒くさい。携帯電話を飲食店とタクシー内に忘れたことが私は幾度もあって、ほとほといやになって、飲んでいるときには携帯電話を鞄から出すの禁止令を自分に課した。でも忘れて出す。都心方面でしこたま飲み、はっと気がついたら、自宅マンションの前に立っていたことがある。手にしているのは半透明のビニール袋ひとつ。なんだろうと思って中身を見ると、肉の入った透明のパックがひとつ、入っている。ああ、今日のレストランで食べ残した肉を包んでもらったのだな、とそれは思い出したが、ハテ鞄がない。肉しかない。鞄がないと、財布もなければ携帯電話もなければ鍵もない。くり返すが、肉しかない。ここで一気に酔いだ覚めた。夫が帰っていてくれますようにと、共同玄関のインターホンを鳴らす。返答なし。寝ていたらどうしよう。数度押すが、やはり返答なし。やむなく私はエントランス外の植えこみにしゃがんで夫の帰りを待った。一時間ほどのち夫が帰ってきて、植え込みから肉だけ持って急にあらわれた私に驚きながらも、あちこちに電話をかけて鞄を探してくれた。鞄はタクシー会社に保管されていることが、ようやく翌日になってわかった。それにしてもかつて私のなくしたパスケース、財布、鞄、お金もカードも保険証も、何ひとつなくならずに戻ってきたのだから、すごいことである。この三種の神器をなくすたび深く落ちこみ、無理だとわかりつつ、酒減らそうかと考えるのだが、未だになくしているのは、その都度それらが何もなくさずに戻ってくる、ささやかな奇跡に甘えているのかもしれない。(「泥酔懺悔 損だけど」 角田光代 )
婬(いん)・酒(しゆ)の二つは一時の快意に百年の定命を縮めるなり
色情と酒の二つは、一時気持ちをよくする百年も生きることに定まっている命を縮めて早死にさせる。松葉軒東井(しようようけんとうすい)の『譬喩尽(たとえづくし)』に掲げる。(「飲食事辞典」 白石大二)
ばくろちやう【馬喰町】
①昔は博労町と称へし処。「江戸砂子」に『馬喰町一丁目、小伝馬町の東丁なり。間には八丁堀あり、はたご屋多し。一丁目二丁目のよこ町に附木屋多し。江戸末の附木、おほく此所より出る。二丁目三丁目、両町共にはたご屋多し。両丁の北に馬場あり。三丁目のひがしは浅草御門にて行きあたる』とある。馬喰町と書くやうになつたのは、正保以降の事だと云ふ事である。-
馬喰町お捌(さば)きほめて酒を買ひ 公事に勝つた祝宴
もの食ひ、酒飲み
浅見 きちんと用例をとっているわけじゃないんだけれども、「今昔」などでは、通常は「もの食ひ、酒飲み」、あるいは「もの食はせ、酒飲ませ」であって、そうなると、お酒の作法としての飲み方は、肴というか、ものを食べてまず一献は何々で食べて、何々で飲むと。それで一献、二献、三献というふうになってたのかなと思っていたんです。
松岡 そ三丁目のあとはそれが…。
浅見 それこそ隠座に移ってしまえば別ですけれどもね。時々、「まづ酒飲み」て、という表現が出てきて、それはたぶん「今昔物語集」で藤原為盛かなんかがお米を滞納していたので、六衛府の官人が押し寄せたという話があって、炎天下でいぶされて、どうぞと招き入れて、そのわーっと入ってきた六衛府の人間が、まず「酒飲みて」というね…。(「酒と酒文化」 大岡信・網野善彦・浅見和彦・松岡心平)
大酔
私は酒を愛し酔いを楽しむ。否むしろ酔いあるがために酒を愛する。しかしながら、あの大酔をした人の自分に恵まれた天与の特権も忘れて他人の迷惑を顧慮せず、あらゆる精神のあるいは大脳のコントロールを失って、自らの心の醜さをさらけ出すような醜態に接する時は真に心の底からいきどおりを覚え、こんな馬鹿らしさを憎まざるをえない。私は酔いのために酒を愛するが、このようなひとりよがりの酔いは心から憎む気持ちにたえない。それ故私は自分は大酔しないことにきめている。鈴木大拙先生はその程度で、酔いは神人交流の境地であると述べておられるのは、適正な酔いの境地についてであろう。大酔だけは許されまい。本書パリのところで述べたフランス学士院のエイム教授は似たような麻酔的境地の研究をしており(二五頁)、リゼルギン酸化合物(LSD)という一種のアルカロイドを含む茸を食する儀式によって神に接するというメキシコのインディオ種族の研究について、その現実の儀式の様子を詳しく録画して来たのを見せられたことがある。茸も微生物の一種だから、この現象も、後にわが国で麦角菌という麦の黒穂の原因となる菌を使って、アルカロイド醗酵の名の下に、新しい醗酵として体系化されたのである。彼もまたこんな点では酒の鈴木先生と似たような見解であったかも知れない。こんなことから察すると、神様はひょっとしたら人間の行動をいつも理づめの大脳の理性下にのみゆだねておくことを望まないのではあるまいか、という大それた疑問さえもたれるのである。(「愛酒楽酔」 坂口謹一郎)
天明七年の珍事件
あたかもそれを象徴するかのような、じつに馬鹿馬鹿しい出来事が、天明七年(一七八七)正月十七日に、或る書院番の屋敷で起きている。当事者はみな西の丸書院番頭・小姓組番頭といった役職の旗本たちであり、新たに番頭になった水上美濃守正信なる旗本が、慣例にしたがい、古参の同役七人を自邸に招いて酒宴をひらいたというところからこの珍事件は始まる。 その時酒たけなはに及び、兼ねて遺恨や侍りけん、又は其坐のたはむれ事にや、大久保殿(接待客の一人-注)、水上殿の膝元に擦寄り、携へ来りし菓子取揚、是参らせ候と箸とつてはさまれしに、水上殿は其折しも盃ひかへ給ひし故、酒半(なかば)に候間、後刻頂戴仕らんとかたへに差置給ひしに、大久保殿是を見て声あらゝげ、(中略)扨(さて)此大久保殿の御言葉を初として、七人の御かた/"\おもひ/\に悪口し、後は各立上り、其日饗応に出されし将軍家より賜りし調度なんど初めとし、或は膳椀皿鉢まで手にあたる物を幸に打こぼち、踏潰し、又はつかんで投出し給ひし由。其中に甚しきは、大小便を席上にしたゝかになれちらし、又それを箸にて挟み、、そこらあたりへ打付給ふ御方も有し由。 いやはや、何ともすさまじい狂態である。右の引用はこれも『後見草』によるが、この事件が事実無根ではないことは、『徳川実紀』の同年二月廿三日の条が関係者の処分(二人とも番頭解任、残りは登城禁止)を記録したついでにこれをまるごと引いていることからもわかる『後見草』の筆者が、「凡(およそ)此御代治りてのち、人の頭(かしら)となる人の鄙下(ひか)下臈にまさりたる其非法狼藉、聞も及ばぬ事共也。是ぞ誠に人妖とも申べし」と感想を洩らしているのも当然であった。(「江戸人の昼と夜」 野口武彦) スカトロ宴会
三低晩酌
健康的にお酒を楽しむ方法として、私がおすすめしているのが、「三低晩酌」です。「三低晩酌」とは、低塩・低糖・低カロリーの料理とお酒を組み合わせる晩酌の方法ですが、単に「三低料理」を肴にお酒を飲むということではありません。晩酌を一回の食事であると考え、お酒も含めてトータルな目で見たときに、バランスのとれたものにしていこうというものです。お酒は種類や飲み方によってカロリーが異なりますから、まずはお酒のカロリーや糖分を知り(別表参照)、そのうえで自分の酒量を考えてメニューを決めるといいでしょう。たとえば、ややこってりした料理を食べるときにはウイスキーの水割りなど、なるべくカロリーの低いお酒を選ぶようにします。また、焼酎サワーなど甘みのあるお酒はやや高カロリーになりますから、薄味で糖分の少ない料理と合わせるといった工夫をすればいいのです。
お酒のカロリーと糖分の比較 ※」辻クッキングスクール調べ ●カロリー 日本酒 お銚子1本(180ml) 180kcal ビール 中ビン1本(500ml) 215kcal ウイスキー水割り シングル(180ml) 90kcal 焼酎サワー ジョッキ(500ml) 260kcal ●糖分 日本酒 お銚子1本(180ml 約9g ビール 中ビン1本(500ml) 約15g ウイスキー水割り シングル(180ml) ほぼ0g 焼酎サワー ジョッキ(500ml) 約11g(「低塩・低糖・低カロリーが現代人を救う」 味田節子)
まえがき
空高く澄み、菊の香がそこはかとなく匂ってくると、重陽(ちようよう)の節句。夫々水は
二盃から匂満ちたり菊の酒
と詠んでいるが、ひんやりとした菊酒の蝕味は、懐旧の情をそそる。風柳の
裸火に対し新酒の酔を吐く
酔ってはいるものの、目は冴えている。嵐雪にかかると、
我盛らじ新酒は人の醒め易き
芭蕉は、
草の戸や日暮(ひぐ)れてくれし菊の酒
いずれも芳醇な酒の香を漂わせ、上戸(じようご)の気分を表して充分。-
人事句に絶妙の冴えを見せた万太郎の
湯豆腐や持薬の酒の一二杯
という句は、わたしの哀惜おくあたわざる名句。水朗子の
鰭酒(ひれさけ)の怪しき光(かげ)を甜めにけり
など書いて行くと、おのずから食欲も湧き出ている。(「にっぽん食物誌」 平野雅章)
「お通り」の恐怖
同業者の会議が那覇で開かれた。外では暑い日差しに照らされてプールが手招きしている。何の因果で会議室にこもらにゃならんのか。しかし、会議が終われば待望の宴会である。古い民家風の居酒屋に直行し、オリオンビールで乾杯。ビールは苦手だが、オリオンなら大丈夫なのだ。うまい!昼間の不満がぶっ飛ぶ。出てくる料理はドゥル天、イラプチャーなど、まったく意味が分からない名前だが味は最高だ。となれば、当然酒は泡盛である。五年以上寝かせたものを古酒(クースー)と言うらしい。さっそく十年古酒のオンザロックを注文した。熟成された味が沖縄料理と相まって、とってもうまい。あとはひたすら飲み、食うだけである。そのうち、おもしろい沖縄式の乾杯を教わった。「お通り」といって、まず一人が杯を一気に干して右側の人に渡し、酒を注ぐ。渡された人はこれをまた一気に干して次の人にまわす。一巡して最初の人に戻って「一通り」である。二通り目は二番目の人から始まる。十人いれば最低十通りなのだ。やりましょうと言われたが、こればかりは固辞させていただいた。だって十二人もいたのだ。十二通りも飲んだらブッ倒れてしまう。沖縄の人が酒席で盛り上がると、この「お通り」が始まる。銀座のクラブでこれをブランデーでやって、金が足りなくなり、翌日「金送れ」の電話を入れるのは、日常茶飯事らしい。(「さしつさされつ」 中田耀子・土倉裕之)
オメガ
五月二四日、赤塚は、『天才バカボン』で第18回文藝春秋漫画賞を受賞。これまでの受賞者は、大人漫画の人ばかり。少年漫画からは初めての受賞だった。正賞は、オメガの時計。その夜、赤塚は、編集者達と銀座のバーでハシゴしている。そして午前二時頃、新橋あたりの小汚い安酒場に辿り着いた。中年のホステスと話をしていて、赤塚は言った。「オレ、文春漫画賞貰ったんだ。偉いだろ」「フーン、で、何貰ったの?」「この時計」と、赤塚は、持っていた手提袋から箱を出し、時計を見せた。「なんだ、時計貰っただけなの」「そう。だけど、これ、オ〇コじゃなくて、オメガだよ」「オメガだかなんだか知らないけど、時計なんか、時間が判りゃいいのよ」「その通りだよな。これ、アンタにやるよ」赤塚は、時計をホステスに渡す。彼女は、それをシゲシゲと見て言う。「高そうな時計じゃん。貰えないよ」「やるよ。貰ってくれよ」「そう?じゃ、貰ってやるわ」赤塚は、次の日、空っぽの箱を発見する。中身は誰かにやったような気がする。だが、どこで誰にやったのか覚えていなかった。赤塚は、そのことを綺麗さっぱり忘れてしまう。しかし、その時計は、一〇年後に赤塚の元に戻った。時計の後ろに赤塚不二夫の名前が刻まれていて、それを見つけたホステスが返してよこしたらしい。発送人の名前はなかった。(「赤塚不二夫のことを書いたのだ!!」 武居俊樹)
のみすけ(飲み助)
[名]酒飲み。 (江戸)(類義語)うわばみ・飲んだくれ・のんべえ。 ◇『東京語辞典』(1917年)<小峰大羽>「のみすけ(飲助) 酒を嗜むもの、飲んで底抜けのもの」◇「くらがり廿年」続くらがり二十年・42(1940年)<徳川夢声>「斯う条件が揃つちや、呑助は呑まざるを得ない」◇『縮図』時の流れ・九(1941年)<徳田秋声>「客は呑み助で夜明しで呑まうといふのを」
ふろふき大根の柚みそ
米を加えて煮ると白く仕上がり、甘味も加わります。 ●材料(2人分) 大根6cm 昆布(小)1かけ 米大さじ1 練り味噌(味噌50g 砂糖40g だし汁大さじ1) ゆずの皮適量 ●作り方 1大根を厚切りにして片側だけ面取り(-)し、裏に(面取りしていない側)厚みの半分ぐらいまで切り込みを入れる(隠し包丁)。 2鍋に昆布を敷き、大根を入れ、米を加えて水から煮る(-)。 3練り味噌の材料を合わせ、小鍋にとって強火で練る。 4味噌が冷めたら、ゆずの皮をすりおろして加える。 5大根に竹串が通るようになったら、火を止める。 6面取りしたほうを上にして器に盛り、ゆずの皮の千切りを天盛り(-)にする。 この練り味噌で、こんにゃくや里芋を食べても旨い。(「おうちで居酒屋」 YYTproject編)
[竹葉青酒(チユウイエチンチユウ)]
山西省汾陽県杏花村の汾酒厂で主に造られる天下の名品で、一九六三年に全国名酒に選ばれた配製酒である。基酒はもちろん汾酒。その歴史は古く、早くも三世紀には人々から称賛された酒であった。西晋(二六五~三一六)の初年、張華という人の『軽薄篇』の中に「蒼梧竹葉青酒」と出てくるのが初見だという。南北朝(四二〇~五八九)の簡文帝の詩にも、北周(五五七~五八一)の文学家、庾信の詩にも、唐代(六一八~九〇七)の大詩人、杜甫の詩にも竹葉青酒を詠んだ詩が見える。そして明代に書かれた有名な『水滸伝』にも、数回にわたりこの竹葉青酒が登場してくる。古代の竹葉青酒は黄酒の酒液中に若竹の葉を浸し、清々しい香味を得るといったもののようだが、その後、白酒である汾酒が出てくると、配入する葯材は大変多くなった。今日では、中国各地でこの酒が造られているが、やはり杏花村汾酒厂のものが最も優れている。私も何度かこの酒厂を訪れ、現地で貯蔵中の基酒となる汾酒や、できあがった竹葉青酒を唎酒したがすばらしかった。「青酒」と書くように、この酒の色はかすかに緑色を呈していて透明であるが、その色素は竹の葉から溶出してくる。芳香が馥郁としていて甘い香りがあり、口当たりは柔らかで、かすかに苦味がある。とにかく温和であって、強い刺激はない。汾酒と、葯材から侵出してきた薬効成分の特殊な匂いとが混じり合って、特殊な風格の酒であった。アルコール度数は四五パーセントで、適量な飲用は「内臓の疲れをやわらげ、気を通し、解毒作用があり、利尿効果を有し、肝臓をうるおい、脾臓を健やかにする」といっていた。汾酒厂の竹葉青酒醸造の重要点は、長期に熟させた最良の汾酒を基酒にすること、酒液に加える糖液は純浄であること、葯材の浸漬にはアルコール分七〇パーセントの高い汾酒を使い、冷温で浸漬させることなどであった。なお、使用する葯材について聞いたところ、代表的なものとして、竹葉、梔子(くちなし)、檀香(だんこう 白檀などの香木の総称)、零陵香(れいりようこう)、砂仁(さじん)など数十種であるとのことだった。(「銘酒誕生」 小泉武夫)
某月某日
相も変わらぬ顔と飲む。つまり亭主であります。色が黒いので、こっち向いているのか後向いているのかさっぱりわからない。いつだか司馬遼太郎さんに「ご亭主はどんな人や」と聞かれて「黒い人です」「腹黒いのか」「いや、顔」といったが、私は酒を飲むこと、酔って歌を歌うことを彼に教わった。西洋の賢人はいっている。「結婚は女たちに男の悪徳の数々を伝染させるが、男の徳は決して伝染させないという特質を持っている」ビール一本、お酒六合ばかしを二人で飲み、ごきげんになったので、東京の佐藤愛子さんに電話をかけてみる。「関西へ来えへん?来たら飲もうよ」「あしたまでに六十枚書かなきゃいけないのよッ」と愛子ちゃんは悲壮な声をふりしぼっていた。イヒヒ…。今度はお苑さんにかける。「いま旦那と飲んでるんだけど、こんどいつくる?神戸へ」「誰がいくもんですか、そんなとこ。こっちは風邪引きでそれどころじゃないわよ!」今度は陳舜臣さんにかけた。心やさしい陳さんはすぐ走ってきた。尤も三、四キロぐらいしか、家は離れてない。亭主と三人で三宮へ飲みにいく。柳筋の「しゃねる」で、黒部亨さんに会った。ここのママさんは扇千景ソックリ。でも、姉妹じゃないそうだ。ここにはマイクもあって、たいていは歌になる。私はマンガ家の高橋孟さんと「すみだ川」を唄うことにきまってるのだけれど、今夜は彼はいなくて、「明治一代女」を歌う。陳さんは「青葉しげれる…」と「一の谷のいくさ破れ…」という、源平合戦にゆかりのある歌を唄った。「神戸っ子やさかい、神戸に関係のある歌をおぼえさせられてん、小学生のとき」ということだった。私は陳さんの歌をはじめて聞いて、衝撃のあまり、高い椅子からころげ落ちそうになった。巧拙は論外、という歌なり。(「酒中日記 女同士の酒」 田辺聖子)
同窓会
同期生の顔、殊に同級生の顔は忘れようにも忘れられるものではなく、会えばすぐ昔の調子が出るが、二年も三年も卒業年度がちがう上に、ふとったり、禿(は)げたりしていては、誰さんであるか全然見当がつかない。そういえば杜甫の詩にこういうのがある。
羞(は)づらくは短髪を将(も)つて還(また)帽を吹かるるを
笑つて旁人に倩(こ)うて為めに冠を正さしむを
杜甫はある宴席につらなって、重陽(ちようよう)の節句の酒を飲んでいる。秋の風が吹いてきて、帽子を吹とばされでもしようものなら、そろそろ薄くなってきた頭髪が丸見えになってしまって、心臓の強かるべき四十男とはいえ、いささか恥ずかしいから、帽が風に吹き落とされないうちに、隣りに坐っている人にちゃんと直して貰ったというのだろう。同窓会に馳せ参じた面々を見ても、頭の薄いのが大分いる。見事に禿げ上がったのもいる。禿頭の地が天井の蛍光灯に照らされて、薄茶色に光っている。そういう私もすこぶる怪しい。笑って傍人に倩うて冠を正さしめるところだが、傍人は生憎(あいにく)今夜初めて挨拶を交した一年先輩の偉いお役人だから、たとい冠をかぶっていても、そんな不躾(ぶしつけ)なことはお願い出来ぬ。それに座敷の中だからみな頭はむき出しである。うしろに回られたら、わがアキレスの踵(かかと)は丸見えである。そのうち、みな、というのは禿げたるも、禿げざるも、また私のような禿頭を目ざして突進しつつある者も、酒に酔って一応はいい御機嫌になってきた。杯のそばに置いてある謄写版刷りの同窓会員名簿は酒の雫(しずく)を浴びている。そうだ、杜甫の詩の最後はこうだった。
明年この会知りぬ誰か健(すこや)かなる
酔ふて須臾(しゆゆ)を把(と)りて仔細(しさい)に看る
来年のこの会には、今ここに出てきた者の誰が健在だろうか。死んでいるやつもいるだろう。転任して、どこかよその土地へ行ってしまっているのもあるだろう。病院に入って、出席出来ないやつもあるだろう。須臾というのは何か植物の名らしい。重陽の節句にこの植物を身につけて、魔除(まよ)け厄除けにするということらしいが、さしてあるその須臾を抜いて、つくづくとそれに見入るというのだ。思い入れよろしくというところである。つまり私なら「酔うて名簿を把りて仔細に看る」というところである。酒席で、頃合いを見計らって、少しセンチメンタルになるのも、また酒興を増して一寸いいものだ。そんな時ででもないと、四十男はなかなかセンチメンタルになんかなりはしない。しかし「酔うて名簿を把」って見ていたのも束の間で、差される杯を受けているうちに、例の如くもうろうとして、翌日眼を覚ましたら、名簿を会場に置き忘れてきたことに気がついた。(「若気のいたり 年寄の冷や水」 高橋義孝)
古谷、尾崎、壇
それはさて、古谷氏の若い頃となると、尾崎一雄の小説「なめくじ横丁」の一節を思い出す。ここにちょっと引用させてもらおう。 徹夜のある明け方、私方の玄関の戸を叩き、「緒方さん!」と大声を出す者があった。聞いたことのある声なら、割りに判別を誤らぬ方の私には、それが古谷綱武だ、と直ぐ判つた。「そうだア。起きてたの?」「起きてるよ。精励恪勤さ。-だけど、君もまた莫迦に早いやないか、どうしたの」そんなことを云ひながら私は土間に降り、玄関を開けた。でつぷりした古谷に並んで、いがぐり頭の丈の高い若者が、紺絣で立つてゐた。「これ、檀一雄君です。緒方さん」と古谷が紹介した。酒の匂ひがした。「あのね、檀さんの小説、読んで欲しいんだ、今直ぐ。ここへ持つてきた」 古谷が壇を、尾崎のところに連れていったくだりである。それから古谷は、尾崎を呼び出し、壇の小説を読ませて批評させることになっている。そこのところも、引かせてもらおう。 戸塚通りの、何とか食堂といふ、早出の独身勤人や労働者が飯を食う柄の悪い食堂で、いくらか酸っぱい酒を何本か倒しながら、古谷綱武の長広舌を檀一雄と私とは、一時間以上も聞かされた。彼ら二人は、昨夜初めて顔を合はし、徹夜で飲んだと言ふ。古谷が偶然、小さな雑誌で『此家の性格』を読み、感心の余り、噂をたよりに西武線中井駅前の「ワゴン」といふ喫茶店で作者たる檀一雄をつかまえへたのだといふ。 若き日の古谷のことが、実にうまく書かれている。(「阿佐ヶ谷界隈」 村上護)
御授爵のお祝い
「今日は御授爵(ごじゆしやく)のお祝いで、五時半からご酒宴がございました。千駄ヶ谷のおじ様、おば様、池田のおじ様や顧問の方、お兄様、先生方や、表の人など、たくさんお客様があって、にぎやかでございました」(昭和四年六月三日)
大六天で一番大切なお祝い日は、御授爵記念日である。祖父慶喜公は明治三十五年六月三日に公爵を授与され、徳川宗家とは別に徳川慶喜家を創立された。この日を記念して毎年「御授爵の宴」が開かれたのだ。-
お祝い膳は三ノ膳まであり、ごちそうだった。きれいな口取りのお皿もあったが、私たちは「チクチク」といっていたサイダーを飲めるのが嬉しかった。なぜふだんサイダーを飲まないのかははっきりしないのだが、たぶんぜいたくとされたのだろう。宴も半ばになると私たちはお銚子を持って、皆様の席を順にお酌して回った。御授爵記念日というからにはなにか特別の儀式があると思われるだろうが、そういうものはなにもなかった。ただごちそうをいただき、お酒を酌み交わす、にぎやかでくつろいだ無礼講(ぶれいこう)の宴だった。日記には、ふだんいかめしい兄のお塾の山口先生も真っ赤なお顔でご機嫌だったとある。
又六が門(かど)極楽と聞くからに釈迦牟尼(さかむに)仏のいや尊とけれ [徳和歌後万載集・十四・釈教]
作者、世入道へまうし。「紫野のほとり酒うる家にやすらひて一休和尚の事など思い出し侍りて」。 釈迦牟尼=酒無二のしゃれ。
一休和尚は紫野大徳寺門前の又六という酒屋で大酒してそのまま寝込んでしまい、目をさますと、「極楽はいづくの程と思ひしに杉葉立ちたる又六が門」と詠んだという。一休和尚が極楽と銘打ったほどだから、酒ほど尊いものはないとの歌意。(「狂歌観賞辞典」 鈴木棠三)
伊藤左千夫の酒歌
子規の弟子、伊藤左千夫(一八六四~一九一三)は「酒」という題で次の歌をよんでいます。
やゝ酔(ゑ)ひて人をのゝしり痛く酔ひてわれと泣きつゝ独りごつかも
酔泣きは万葉の大伴旅人と現代の歌人で、小説『野菊の墓』の作者である伊藤左千夫を結びつけています。(「万葉集にみる酒の文化」 一島英治) 春の杯・春の盃 夏の酒 夏の酒(2)
島井宗室遺言状
一、酒を作りしち(質)を取リ候共、米は我ともはかり、人に計(ハカラ)せ候とも、少シも目をはなさず候て可レ然(しかるべく)候。かたかけにて(23)何たる事もさせ候まじく候。下人下女にいたるまで、皆/\ぬす(盗)人と可二心得一(ココロウベク)候。酒作リ候ば、かし(淅)米置キ候所を作、じやう(錠)をさし、こわいゝ(強飯)もぬすむ物にて、さまし候時、ゆだん(油断)仕まじく候(24)。
(23)「かたたけにて」は片手間での意。 (24)「かし(淅)米」は酒を醸造するための原料である米をといで水にひたしたもの。「こわいゝ(強飯)」は酒造りのために「かし米」を蒸し上げた状態のもの。(「家訓集」 山本眞功
編註) 戦国時代末期に博多の豪商だった鳥居宗室が、晩年に外孫で養継子にした徳左衛門信吉に与えた遺訓の一部です。
土熬鍋
燗についての文献上の初見は平安時代中期に成立した『延喜式(えんぎしき)』で、「土熬鍋」という記述がある。土熬鍋(どこうなべ)というのは小さな銅製の鍋だが、ここに酒を入れ、直接火にかけて温めていたと考えられている。このような酒の温め方を「直鍋(じきなべ)」または「直燗(じきかん)」という。燗という字の初見は江戸時代初期の『醒酔笑(せいすいしよう)』とされるが、初期から中期にかけての頃には、酒を温める専用の鍋として「燗鍋(かんなべ)」が登場し、井原西鶴の『好色一代男』には、「女郎の手つから燗鍋の取まはし」という条が出てくる。燗鍋の材料は鉄であったが、中世から江戸時代にかけて一般には、炊事用の鉄鍋が酒を温めるのにも使われていたようだ。
モン・アサクサ
タロちゃん(淀橋太郎)なども、興行師だから、私と飲んでいるうちにも、目の玉のギロリと見るからに一癖ある大人物の浪花節やら、漫才やらそんなのが膝すりよせてヒソヒソと何か打合わせに来たり、可愛いい踊子さんが役を頼みにきたり、それで私は大喜びで、「ちょッとちょッと」大慌てに、あなたは帰っちゃいけません、先ず、飲みましょう、とオシャクをして貰う。これが浅草のよいところで、一パイ飲みましょう、とたのんで、イヤだなぞと云う人は、昔から一人として居たためしがなかったのである。まことにツキアイがよい。ここが浅草の身上である。その代り、酔っ払って、口説いて、ウンと云ってくれた麗人は一人もいなかった。然し、決して男に恥をかかせるような素振りはしないところが、また、よろしいところで、男は酔っ払えば女の子を口説くに決まったものだと心得きっていられるところ、まことに可憐で、よろしい。浅草の男の子も、立派なもので、私がもっぱら女優部屋専門にお酒をのみに侵入しても、それが当然と心得ており、なまじ男優部屋へ顔をだすと、薄気味わるがるような仕組みになっており、お門が違いましょう、という面持である。(「モン・アサクサ」 坂口安吾)
酒のエンゲル係数
高校時代から、酒のツケをよく貯めていた。二階の教室で授業を受けていると、下から女の人が大きな声で叫んでいた。「たいらーッ、お金払って-ッ」いきつけのスナックの子が、借金の取り立てにきたのである。いまは、もちろんツケで飲むが、払いが毎日毎日だとメンドウなため、年間まとめて払うことにしている。そのためかどうか、ボトルに番号をつけていて、一本飲み終えるとマジックでママが書いてくれる店がある。で、昨年の年末に置いてあったボトルの番号は、№163。その店だけで、三日に一本以上空いていることになる。そんないきつけの店をハシゴする癖があるのだから、われながら酒量の多さにはびっくりする。開高健のエッセイ『酒瓶のつぶやき』(『白昼の白想』の一節)にある話だが、男は稼いだ金を三分割するという。「一つは水に流し、一つは大地に埋め、一つは敵に贈る」というのだ。水はもちろん酒のこと。大地に埋めるのは財産のようなものだろう。敵は女房のこと。つまり、三分の一だけ飲んでもいいことになる。はたと、自分の酒のエンゲル係数(?)なるものを考えてみた。昔は一万円あると一万円飲んでいた。翌日のことは考えない。その後、一万円あると九千円飲んでいた。結婚したからだろう。ずーっと、しばらく一〇分の九が続いた。子どもができて大きくなるにつれて、一〇分の七ぐらいになっていた。もちろん、その間、収入は年々上昇していた。しかし、大地に埋めるようなものは、どこを捜してもいまだにない。マンションの六階と八階に住んでいるせいだろうか!?(「シャレと遊びと人生と」 はらたいら)
東京湾岸のおでん屋
タクシーが行ってしまうと、街灯がついているだけの倉庫街に二人はとり残された。道に迷ったのは確かだったが、アナタは知らない場所に放り出された感じがそんなにイヤではなかった。酔っ払った心地よさが加わって、知らない道に迷いこみ、一瞬どこにいるのかわからないような気分。置き去りにされる感覚にも似ている。このまま誰もしらないところに行っちゃおうか。ふと、そう思う。何だかアナタは気が大きくなってきた。「後藤クン、悪いことしたなって思っているかい?」「ええ、少し」後藤はニヤッとした。「でもこっちに行けばいいんだと思います。必ず若いギャルがいますから。もういっぱいです。ちょいと見てきます」後藤は明かりの方に走り出した。アナタは、ふと自分の歩いてきた道を思った。人口がいちばん多かったから、いつも相手を蹴落としながら四十になった。同期の中にも、がんばってる奴、趣味だけに生きている奴、昔のゲバ棒の思い出だけが支えの奴、慣れぬ不倫にふりまわされている奴、ガンコでけむたがれる奴、ハゲてる奴、白髪になった奴…いろいろいる。何しろ人口が多いからね。やがて、老人ばかりの世界になる。どうなるんだろうとも思うけど、アナタはそれ以上は考えないことにしている。なるようにしかならないと思う。さっきのタクシーの中でしゃがれ声の男がラジオで歌っていた。アナタはぼんやりと聞いていたが、酔っているせいか体の中にしみこむような言葉があった。「もっと真っすぐに生きてえ」子供の頃におやじに同じようなことをいわれたのを思い出す。「真っすぐに生きねえとパンだってうまく焼けねえよ」なぜか思い出すんだ。真っすぐに生きる、多分、人にいったらバカにされるだろう。アナタだってそんなことずっと忘れていた。だが、おやじの言葉がこのごろよくわかるんだよ。簡単な言葉なんだけどなあ。アナタは酔っ払ったまま「真っすぐに生きるんだ」といいながら、真っすぐ歩こうとするのだが、すぐにふらついてしまう。街灯の下から後藤があらわれた。「すいませーん。なんだかここじゃなかったみたいです」二人は倉庫街をふらふら歩いた。「怒ってます?」「少しな」「あのう、もう少し行くとおでん屋があるそうです。そこなんかいいんじゃないでしょうか」後藤はニヤッとした。「東京湾岸のおでん屋ねえ」「ハイ。ちょっと趣向が変わりますけど」アナタはふらつきながら後藤をジロッと見た。「今夜のことは、黙っててやるぜ」笑いがこみあげてくる。後藤もそれにつられるように笑い声をたてる。人気のない倉庫街に笑い声だけが高く響いていく。東京湾の暗がりに大きな船があらわれる。船体を明かりの中にゆらめかせながら、ゆっくり横切っていくのが見えた。(「アナタの年頃」 永倉万治)
縄のれん
居酒屋でせめてツマミは出世魚 ハジメちゃん
赤ちょうちん串一本にグチ十本 帰宅恐怖症
根回し
つきあいと飲んで歌って腹さぐり 勇気マン
禁酒禁煙
意志強し死んでもやめぬ酒タバコ ごんぞう(「平成サラリーマン川柳傑作選①一番風呂・二匹目」 山藤章二・尾藤三柳・第一生命選)
にぢ
にじること。ねじ込むこと。強談判することなど。『本朝二十不幸』には言偏に横、『言海』には横という字をにぢと訓(よ)ませてある。
①女房は酔はせた人をにぢに行き
注 ①飲んだ者より酔わせた方に責任があるという女房のけんまく。 (樽初)(「古川柳辞典」 14世根岸川柳)
あつ燗おでんだし割り
裏メニュー②丸眞正宗あつ燗おでんのだし割り 50mlのメモリまで飲んだら熱々のだしを入れてもらう!! ワンカップ大関もあるんですけれど大関だと甘すぎてだしと合わないんですよね-断然「丸眞」がおススメですよー 私次飲んでみるー よし!だしくださーい 仕上げにそこにある"にんにく七味"入れるといいですよ! 七味…ますますカオス!! たっぷり入れちゃおー♡ うまさ予想K点越え!! ぬ!!ひ…一口ちょーだい!! がーん料亭顔負けの深い味…お腹いっぱいでもこれならいくらでも飲める… でしょー?ニコニコ さらに熱燗2本目からは1本目の空瓶をキープしておいて…50mlずつ移し
だし割を楽しむという技も!! なるほど-(「女2人の東京ワイルド酒場ツアー」 漫画・カツヤマケイコ コラム・さくらいよしえ) 丸健水産(北区赤羽1-22-8)です。
【隠し言葉】
伝承の慣用なぞなぞ句を「隠し言葉」といった。
甘酒屋の燗徳利で熱い/\
居酒屋の燗徳利で出たり入ったり
欠け徳利で口悪い
五合徳利で一しゃうつまらぬ
幽霊のお酌でおあし(銭)がない(「日本の酒文化総合辞典」 荻生待也)
お三方
それで思い出すのはかなり昔になるが、当時旭日(きよくじつ)のいきおいの三人の作家の先生方。酒場(みせ)があいたばかりの夕刻からほど遠くない時間、厳寒のさなかでフロアに暖房もゆきとどいていない静まりかえったところへ、お三方がうち揃ってみえたことがある。最初はしごく和気あいあいと一隅のテーブルで飲んでおられたのだが、そのうちホステスが出動してきたり、他の客もぼつぼつみえる時分になると、がぜんこの先生方の個性的な行動が表面化してきた。お一方はさり気なく席を立たれてカウンターへ。ぽつりと離れて坐り、グラスを前に電話か何かを待たれる風情。さらにお一方はまっ白いシルクのシャツの第四ボタン(第二、第三まではあっても、ここまでの方はめずらしい)までをさり気なくあけ放ち、ちらりと胸毛などをみせながらホステスに囲まれて呵(か)々大笑。のこるお一方はどうした訳かテーブルの下に潜りこんで、英国製の洒落たセーターを絨毯の埃に塗(まみ)れさせつつ、「××××したい!]と禁断の四文字を叫ばれる。もの覚えのよくない私が、この光景だけは名画のワンシーンのごとくありありと記憶しているのはどうしたわけか。たぶんそれは名画の一場面に等しいショックを私に与えたせいであろう。折りにふれあの夜の光景を思い出す都度、かのお三方のありようが、失礼ながらほとんどのほろ酔い人種の癖とパターンを代表していると思わざるを得ない。独り醒めるか、自らを誇示するか、自虐的に溺れこむか-やっぱり酔っぱらいは(但し男の)、可愛いものなのだろうか。ちなみにお三方のお名前は、五木寛之、三島由紀夫、野坂昭如の諸先生である。(「男はオイ!女はハイ…」 山口洋子)
アイラク
二〇〇〇年以上も前から、中央アジアの遊牧民のあいだに知られていた飲物「アイラク」というのはモンゴル語で、トルコ語を語源とする「クミス」という言い方の方が一般的である。モンゴルの年代記などには必ず出て来るもので、たとえば、ジンギス=カンの誕生からモンゴル帝国成立の歴史を描いた「元朝秘史」には、「イシク(エスク)」という名で出てくる。搾りたての馬乳を発酵させた飲料で、アルコール分は少なく、せいぜい一~三パーセント程度である。馬が乳を出す期間は、渡り鳥がやって来る六月末ごろに始まり、冬の寒さが訪れる十月に終る。したがってモンゴル人は、渡り鳥の姿を見て短い夏の訪れを知るとともに、青々と育ってきた牧草を求めて多忙になるのである。搾った馬乳を革袋に入れ、先が十字形や円形の撹拌棒でかきまぜながら、一週間から一〇日ほど経つと、乳酸菌やイースト菌の働きで馬乳が発酵してくる。前の年につくったアイラクを少し混ぜておくと作りやすいという。こうして同じ革袋でいく度も繰り返しアイラクを作るので、夏から秋に向かってだんだん濃くなり、アルコール分が強くなる。製法は各家伝来の秘法があって門外不出。三〇〇〇回位攪拌するというが、名人はかきまぜた時に馬乳の発酵する音を聞いて具合をみるのだという。十月までにはいくつもの大きな桶にアイラクを貯え、白い月(ツアガーン・サル)(陰暦正月)を祝うべく、これを凍らせて保存する。古い諺に<祭に歌があるように、祝いごとにはアイラクがつきもの>とあるが、どんな祝いごとにもアイラクが出る。老若男女いかなるモンゴル人にとっても、アイラクは最高の飲物なのである。アイラクにはビタミンCが多量に含まれ、血管の働きをよくし、新陳代謝をさかんにするという。昔から肺結核や壊血病の治療に用いられていたが、近年、中国でもこの効用に注目し、貧血症、骨髄炎などの治療にもアイラクの飲用を採用しているそうである。肥満症のためにもよく、昔から言われている通り、まさに<生命の水>なのである。(「世界風俗辞典Ⅱ 衣食住の巻 アジア」 矢島文夫他)
漱石の酒句(2)
明治三十年 正岡子規へ送りたる句稿 その二十二 一月
或夜夢に雛娶りけり白い酒[承路盤]
明治三十年 正岡子規へ送りたる句稿 その二十五 五月二十八日
五月雨や小袖をほどく酒のしみ
立見たり寐て見たり又酒を煮たり
明治三十年 正岡子規へ送りたる句稿 その二十六 十月
名月や無筆なれども酒は呑む(「漱石全集」)
根本正(ねもとしょう)書
酒(さけ)たばこ 雲井(くもい)の上(うえ)に 必要(ひつよう)は なしと宣(の)たまふ 民(たみ)に幸(さち)ある 御大典(ごたいてん)を祝(しゅく)し奉(たてまつ)りて 昭和三年(しょうわさんねん)(1928)十一月(じゅういちがつ) 根本謹書
皇室の御慶事と禁酒の問題について 伯爵 二荒芳徳
こゝに私が謹んで申上げたいと思ふのは、わが 聖上陛下の禁酒禁煙であらせられる事についてゞあります。また同時に、宮内省で天盃を下賜され、御酒を賜はり、煙草を賜はることがありまして、それが一見甚だ 陛下の思し召に矛盾するが如くに見えるのでありますが、私共としては、それについて、ひとつの見解をもつてゐるのでありますから、それを申述べたいと思ひます。陛下は、畏れながら今日に於ても絶対に御禁酒御禁煙であらせられます。然し、陛下にも、御盃をお挙げになるべき場合があります。例へば、御陪食の時には 陛下のお盃にもお酒を捧げます。また御誕辰の場合とか、大演習の場合等にもお盃にお酒をお接がせにならせられます。又天盃下賜といふ事が御座いますが 陛下にはかゝる場合にお盃に御唇をおつけになるだけで、御飲用は遊ばされぬと伺ってをります。これは強い節制心に富ませ給ふ 陛下に於かせられましては、畏れながら御必要の事でないと云ふ思召かと拝察いたすのでございます。陛下が未だ東宮に在せし折、私は或る時、「陛下には、お酒もお煙草もお召上がりになりませんが、お嫌ひであらせられるからで御座いますか。」と、お伺ひ申上げたことがあります。すると 陛下は、「予は、酒も煙草も必要がないから飲まないのである。」と仰せられました。何といふ有難い意味深長な御言葉でありませう と、未だにかゝる事を伺ひ上げたことを愧づかしく思つて居ります。絶対禁酒禁煙を 陛下が御厳守遊ばされてゐらせられることは、国民の一人として、私の常に、恐懼、感激を禁じ能はぬところでります。(「根本正書」) 根本正は、大正11年に未成年飲酒禁止法を成立させた衆議院議員です。和歌部分は、上の掛軸の左側、二荒の文は、右側にあります。この掛軸は、水戸市立博物館にあります。
〇上戸を下戸にする事
酒狂する者を酒を嫌ひにする事 本草綱目巻五十獣の部馬汗の附方に曰く 飲酒欲レ断制二馬汗一和レ酒服レ之(千金方)と見えたり 是の意は酒を禁じたく思はゞ 馬の汗をとりて酒の中にまぜて呑むべし 酒嫌ひになるなり(千金とあるは千金方と云ふ書にあると云ふ事なり) 〇又同書に弘景曰く 馬色類甚多入レ薬以二純白者一為レ良 とみえたり 是は馬の毛色は色々多し 薬に入るゝには白馬をよしと云ひてする事なり 白馬とは鼻ツラの色薄紅色にて黒からず蹄の色はうす黄に似て毛色は至りて白き馬なり 或人主人酔狂するを憂へて紙を以て白馬の口の中を拭ひ涎を紙にしめして其の紙を酒に浸してしぼり出し主人にのませたり 夜中胸わろくなり吐逆したり其の後酒嫌ひになり呑む事なし 此の事はその人の物がたりなり 然れば馬の汗にも不限(かぎらず)馬の涎よくきくなり 酒狂にて一生あやまつものあり 人の為になれば人にも伝ふべし(「安斎随筆」 伊勢貞丈)
新八
目立たない路地、目立たない照明、目立たない看板の奥に「新八」(153)はあった。しかし、まだ夕方6時半なのに殆どの席が埋まり、我々が案内されたのは二階であった。ビールで乾杯してから肴を選ぶが、どれもこれも飲み助のスケベ心を誘うような魅力的なメニューが並ぶ。「おっ、クエがある」「かさごの姿造りも是非」「鯵のなめろうもそそるなあ」。他にもとらふぐ皮刺し、熊本産馬刺し、めばるの煮付け、ナマコのこのわた…迷いに迷って注文する。日本酒は迷うことなく「神亀」。神亀のすべての種類がそろっているという。まずは純米生酒から入り、お次が大古酒昭和54年物。これがたったの1200円なんだから飲まずにおれようか。大古酒は、色、香り、味…譬えるならシェリーに似た風味を感じる。日本酒には古酒の伝統が稀少で(焼酎も同じ)、ごく少数の銘柄しか古酒は造っていないが、この大古酒、日本酒特有のカドがなく、丸く円熟して言うことなし。料理もそれぞれに旨い。居酒屋のランクとしては、かなり高い位置を占めるというのがメンバーの評定であった。(「東京居酒屋はしご酒」 伊丹由宇) 新八は千代田区鍛冶町2-9-1です。
梅たたき(梅干、長ネギ、大葉)
梅干しは種をとりのぞく。ネギ、大葉をみじん切りにして、梅肉と一緒に庖丁の峰でたたく。好みで化学調味料、砂糖を少し加えると味がまろやかになる。ポイントは丹念にたたくこと。すり鉢ですれば簡単だが、舌先でのトロケ具合、風味がまるでちがう。この酒肴にはバリエーションが豊富だ。アサツキ、白ゴマ、松の実、ワカメ、かつおぶしなどを、それぞれみじん切りにしてあわせてもいいし、変わったところでは、納豆を加えてもうまい。また本ワサビのみじん切りを加えると、風味は一層増し、ちょっとぜいたくな酒肴になる。盛り付けは少な目、二人前で親指ぐらいが最適。(「酒肴<つまみ>のネタ本」 ホームライフセミナー編)
酒徳 酒の徳 孟郊
(一)
酒は是レ古明鏡 酒は古の不思議な鏡のやうなもので
小人ノ心ヲ輾開ス 凡人(ぼんじん)の心を転倒し豁開する。
酔ヘバ 挙止ヲ異ニスルヲ見 酔へば挙動が違つて来る
酔ヘバ 声音ヲ異ニスルヲ聴くク。 酔へば声音が違つて来る。
(二)
酒功ハ此(カク)ノ如ク多ク 酒の功績は此のやうに多いが
酒屈モ亦タ以テ深シ。 酒の冤罪(えんざい)も亦之によつて深い。
人ヲ罪シテ酒ヲ罪スル免(なか)レ 人を罪して酒を罪するなかれ
此(かく)ノ如ク箴(しん)ト為ス可シ。 此のやうな点を戒めとするがよい。
◎作者孟郊は韓愈と親交が有つて其詩を称許された。年五十にして進士に及第して一官を得たが、職務を廃し、山水の間に放情して詩を賦し、一生不遇に卒つた。(「中華飲酒詩選」 青木正児)
いまトレンドの酒処 山形
酒処揃いの東北のなかでは目立たない存在でしたが、一九九〇年頃から「出羽桜」「米鶴」、一九九五年頃から「十四代」で注目されるようになり、「上喜元」「東北泉」「くどき上手」「東光」「楯野川」「鯉川」「山形正宗」「杉勇(すぎいさみ)」「麓井」「白露垂珠(はくろすいしゆ)」ほか、人気と実力を兼ね備えたスターがずらりと揃っています。熱血指導官で知られる山形県工業技術センター酒類研究課長の小関敏彦氏(現・県庁勤務)の存在も大きいでしょう。小関氏を中心に、センターと酒造組合がタッグを組んで、独自の酵母や、酒米の開発に取り組んだり、他県から講師を招いてセミナーを開くなど、官民挙げてレベルアップに努めてきたことが功を奏し、新時代の名酒処としての地位を確立。吟醸酒の割合が高く、香り良く、清涼感ある酒が目白押しで、蔵における品質管理も万全。山形の酒を選べば、品質の面で間違いがないと思わせるまでになっています。(「めざせ!日本酒の達人」 山同敦子)
幻の日本酒を飲む会(2)
「幻の日本酒を飲む会」の第一回目は一二月に開くことにしたが、当時は日本酒は不人気だったから、忘年会最盛期を外して月初の三日(水)を選んだほどであった。タイトルは「幻の酒を求めて・酒の評論で有名(実は無名)の醸児氏が集めた酒…」とあり、会費は一八〇〇円であった。五銘柄各二本、仕入れ金額は一万五千円ぐらいだった。客は一六、七人、乾き物か何かをつまみ、けっこう楽しく飲んで語った。仕上げにおむすびが出た。いくら二五年前とはいえ、会費がリーズナブルであったのがよかった。それで「集」は採算がとれていたのだろうか。初回から利益は期待していなかっただろうが、赤字にはならなかったと思う。酒席は部屋の一部をこれに当て、中央のテーブルに酒、きき猪口(きき酒用の陶製茶碗)、グラス、つまみを置いたセミ立食スタイル。講師が話をするときは周囲に並べた椅子にも座れる。」かつ、話題が枯れそうになると、店のマスター田中さんが巧みに話を振ってくれる。この飲酒スタイルも吟醸酒を楽しむににふさわしかった。後で書くつもりだが、「幻の日本酒を飲む会」の後半、着座のスタイルに変わっていって会が重くなったのは否めない。採算の責任は「集」が持ってくれているから、私は酒集めだけをすればいいので楽であった。酒はやや多めに仕入れる。参加者に合わせて適当な本数をテーブルに出し、飲み終えたら終わりとなる。飲み残しの分は、店の在庫となり、翌日からの普通営業に供する。時には一〇人も満たない参加者のことがあり、顔なじみは追加会費を出して飲み続け、高いタクシーで帰ることもあった。会の始まりに「乾杯」などの儀式がない。解散はサミダレ解散で、中締めのシャンシャンもない。例会では音曲は禁止である。飲みかつ語り、そして憩うだけである。それがいいという人だけが集まった。(「「幻の日本酒」酔いどれノート」 篠原次郎)
平成14年の出版です。
精神安定剤としてのアルコール
一人で飲む子どもの中には、このケースのように大きな挫折感から飲む子が多いのです。たとえば登校拒否の状態でひどい飲み方になる子もいます。ある母親は、高校生の息子がひどいお酒の飲み方をして困ると相談に来ました。その子は朝一杯の日本酒を飲んで登校するのだそうです。その家庭では父親も母親も飲酒する習慣はなく、たまたまもらったお酒があったのだそうです。よく話を聞くと、その男の子は、学校で緊張して友達と打ち解けることが出来ず、最近は遅刻したり、登校出来ない日が続いていました。そうすると彼はお酒を一杯飲んで、勢いをつけて登校するしかない追いつめられた心境にあると考えられました。彼は私の病院に一回だけ診察に来ましたが、その時も下を向いたままで視線を合わせることが出来ず、ぼそぼそと聞こえないような小声で話をし、明らかな対人恐怖症の状態にありました。この子どもの場合は、対人恐怖症のために、アルコールを精神安定剤として使っていたのでした。このように対人恐怖症や、恐怖症まで行かない対人緊張症とか人前でうまくしゃべれない子どもが、アルコールを飲むと緊張がとれて楽になるということで、飲酒を始めることは結構多く見られます。この場合は、しらふでいる時の自分は、緊張して惨めな自分自身への嫌悪感が強いために、飲んで明るくふるまっている自分の方が好きで自分らしいと考えるようになり、アルコールへの心理依存は非常に大きくなります。(「子どもの飲酒があぶない」 鈴木健二)
岩の井
なによりも御宿は、海の幸の宝庫という天恵がある。加えて、四百年余という長い歴史をもち、御宿と共にいきぬいて来られた岩瀬家のかずかずの遺徳は、今後も大きく光るはずである。今は亡き広島出身の池田勇人総理は、若い頃岩瀬家に通いつめて、アワビの踊り焼と「岩の井」を二升近くも平らげ、「絶品、絶品、これぞまさしく天下一の美酒佳肴だ」とほめそやしていたという。ことほど左様に、アワビは「岩の井」によく合う。日本一のアワビがあるから「岩の井」が生まれたのか。「岩の井」という磨き上げられた美酒があるからアワビが太平洋の荒海を越えて泳ぎつくのか…。いずれにしても神のなせる絶妙の取り合わせというべきである。(「酒の旅人」 佐々木久子) 千葉県夷隅郡御宿町久保1916の岩瀬酒造㈱です。
正弁丹吾
法善寺横丁を中心とするこの一帯、現在何軒あるか知らないが、腰かけ本位の料理屋で、いちばん繁盛しているのが「正弁丹吾」だという事は、衆目の視るところであろう。-が、ここのメニューは十二、三種にきまっていて、他のものは何も出さない。しぜん、仕込みも限定されていて、必ず売切ってしまう。だから材料はいつも新鮮であることも大きい理由の一つであろう。それにしても、判で押したように、きまりきっている手板(ていた)で、よく飽きもせずに客が来るものだと、これは私にとって不思議であるが…。しかし、もう一つの大きい理由は、ここの歴史で、一朝一夕に培(つちか)った人気ではない。今の人気は、むしろ惰力である。私はいつも、みどりとこことを法善寺での双壁として挙げたが、両方とも、私は断続しつつも四十年以上その酒にしたしみ、内容も知悉(ちしつ)しているからである。東京から来るいわゆる名士で、一、二度行った店を、その時の調子次第で、褒貶(ほうへん)の筆をとる人があるが、私にはああいう芸当は出来ない。その頃は、正弁丹吾とはいわなかった。なんという名であったか、現在の店の南側に、立呑みの関東だきであった。酒は一升-いや、もっと大きい徳利で燗(かん)をし、それを湯飲茶碗についだ。唇をつき出してうけると、茶碗の藍の色が、燗酒の中でゆれたのを覚えている。面白いのは、のれんから皆が足許だけを見せ、談笑の声を上げてのんでいて、声と足許とで、「ああ、××が来てよるナ」と、分ったことである。今、法善寺横丁という野暮くさい提灯のあるところに、古めかしい木戸があり、午前一時には戸がしまった。その木戸のすぐ内側に、小便タゴがあり、共用の用に足したが、人々は「小便タンゴのわきの関東だきへ行こ」といい、それが店の名をいつかしょうべんたんごとよばしめるようになったとは、すでに伝説となっている。近年、この表に西田当百の句碑が建った。 上かん屋ヘイヘイヘイとさからわず 場所も、句も、当を得ている。客あしらいの悪い横柄なおでんやや、のみ屋など以てのほか。(「味の芸談」 長谷川幸延)
胆石
昭和五十二、三年頃から、梶原一騎は胆石を抱えていた。酒を飲むと傷む。席を立って洗面所に行き、鎮静剤を飲む。効き目がなくなったら、痛みを麻痺(まひ)させるためにもっと酒を飲む。石を溶かす薬が内臓の粘膜を破壊しないはずがない。アルコールの回り方が異常になり、精神的なバランスまでおかしくなる。次の日はもっと痛みがひどくなる。この繰り返しだったようだ。にもかかわらず、ここまで暴飲暴食を積み重ねた男もいないだろう。連日のようにウイスキーのボトルを空け、ステーキや鰻(うなぎ)など、脂(あぶら)っこいものばかりを胃に放り込んだ。初めはPL教団が運営する渋谷の「PL健康センター」の人間ドックで胆石を発見された。何度も手術を勧められたが、梶原はいつもすっぽかした。忙しいからではなく、肉体的弱者が嫌いだったのだ。突き詰めていえばやせ我慢でしかないのだが、普通の人間なら七転八倒するほどの痛みに耐え、こわもての梶原一騎像を崩すまいとする努力こそが、梶原なりの美学だった。
昼食の混雑時
呑み屋としてのそば屋には、注意すべき特徴がひとつある-ひとり酒でも、テーブル席を独占することになりがちだということだ。確かに、カウンター席のない(または少ない)大衆酒場でも、一人客がテーブルに座ることはあるが、通常は相席になるはずだ。普通の居酒屋や寿司屋などでは、ひとり客はカウンター席に案内されるが、カウンターのあるそば屋は少ないので、ひとり客でもテーブル席を占有することになるわけだ。最後にそば、またはそばがきなどのいわゆる「食事物」で〆るつもりでも、テーブルをゆっくり独占する以上、せめて昼食の混雑時を避けて入るのが礼儀だろう。(「日本の居酒屋文化」 マイク・モラスキー)
お酒漬け
宴会が終わりに近づいて、ご飯を食べる段階になったとき、日本酒が残っていたら、それをご飯にかけて食べようとする場合もある。お茶漬けならぬ「お酒漬け」である。もっとも、これは酒が残っているかどうかには関係なく、わざわざつくって食べるほど好きな人もいる。炊きたてのご飯に燗をした日本酒をかけてその熱々を食べる。酒っ気が満々の蒸気が喉一杯に広がっていって、ちょっと油断するとむせてしまう。しかし、真っ白くふくよかな米粒の集合とまろやかさのある日本酒とが一緒になって奏でるハーモニーは、一見シンプルに見えて深みを感じさせる味になっている。日本酒も同じ米でつくられているので、相性がいいのは当然かもしれないが。(「酒を味わう 酒を愉しむ」 山崎武也)
与次郎人形
〇与次郎人形は、其向ひたる方の人 酒を飲(のむ)。この人形は児戯条にいへり。これもと飲席の具にて、いと古きもの也。『和名抄』に、「諸-葛-相-如(しょかつそうじょ)ガ酒ノ胡子ノ賦ニ云、因(よりて)レ木ニ 成二形象人質ヲ一、在二掌握ニ一而可レ玩、遇二盃盤ニ一而則-出(木でひとがたに作り、手でもてあそんで、盃盤に出す)」とあり。『墨荘漫録』に「飲-席 刻レ木ヲ為レ人、而鋭二其ノ下ヲ一 置二之ノ盤中ニ一。左-右ニ欹倒ス「イ欺」々然トシテ、如二舞状ノ一、久シテ之力-尽レバ乃-倒ル。視二其伝-籌ノ所レ至ル一、酬ルニレ之ニ以レ盃ヲ、謂二之ヲ勧-酒-胡ト一或ハ有レ不レ作二伝籌一、但-倒テ而指-者当レ飲二(飲席で木製の人形の下をとがらして盃の中で回し、倒れた方の人に盃を献酬する、これを勧酒胡という)」とある、是也。
モリ
このモリは村人の共同飲食のことで一般に酒盛のことをモリという。長崎県壱岐島でも頭屋(とうや)が講の宿をするのがお講モル。無尽(むじん)の宿をするのが無尽モル。無尽の創立総会をモリタテという(『続壱岐島方言集』)。東京都下の大森の野増(のまし)村では祖先の年忌の祭をして親族の家に餅などを配るのをモルという。奈良県宇智郡では酒食をおごることをオモルというが、名古屋市地方でもおごりなさいということをオモリアーという。いずれにしても酒食を饗するのがモルで、沖縄には酒もりばかりではない。塩もり、水盛りの行事があって、これも塩をなめ水を飲み合う儀礼である。招宴にしろ、出し合いの群飲にしろ、同じ器の酒を共にたのしむ間柄のものは親類・村人・同業者など親しい者でなければならないわけで、縁もゆかりもない者といたずらに酒肴をもり合う筈がないのである。岩手・秋田・宮城の諸県で、嫁の里方の両親をモリヤー又はオモライさまとよんで嫁方・親方の両親を互いにモリヤといいあったのは、互いに酒食を盛り合うほどの親しい仲であることを表明したものである。酒盛りはそのように正式の座に列席の資格のある人だけが相会して一定の方式によって酒をくみかわすことで、それによって将来される結果の大きい正式食事であった(『食物と心臓』)。(「食生活の歴史」 瀬川清子)
464余計なお世話
A「寒さすごしにウイスキーよりも、良いものを教えてやろうか?」
B「止してくれ、聞きたくない、僕にはウイスキーが一番にいいんだ」(「ユーモア辞典」 秋田實編)
ネクタイアル中
きちんとした身なりで仕事もちゃんとする。ところが連日大量の酒を飲まないではいられないホワイトカラーのアルコール依存症を専門家が呼ぶことば。以前はアルコール依存症患者というと一日中酒びたりで仕事もしない生活破綻者タイプが多かったが、この一〇年来、ネクタイアル中が目立ってきた。(「平成新語×流行語小辞典」 稲垣吉彦)
日本料理
私が日本料理を修業していたころ、よく「酒の飲めない料理人はだめだ」といわれたものである。これは、酒が飲めるということは日本酒(清酒)のおいしさがわかるということであり、そのおいしさに合わせた日本料理を作ることができる、ということを意味していた。つまり日本料理は、とくに料理屋の世界では、いつしか日本酒をおいしく飲むためのものになってきていたのである。日本酒は糖度の高い酒なので、その糖分に合わせるためには、それとバランスがとれるような日本料理が要求される。その要求に応えるように日本料理が変化せざるを得なくなると、毎日食べる惣菜のような料理ではなく、もっと日本酒の糖度にあった料理が必要とされ、研究されてきた。それこそ現在料理屋の料理として形成されてきたものの本質ではないだろうか。ということは、日本料理は日本酒のご機嫌をとって変わってきたようなもので、それによって今の料理屋の料理は多少偏った発展のしかたをしてきた。このため、日本酒に合わせるために日本料理が捨ててきたものも少なくないといえる。本当は日本料理はもっと豊かにおいしくできるのに、そうすると日本酒に合わなくなってしまう。日本料理の原点である家庭料理が消えつつあるのに料理屋の料理が何とか生き残っているのは、料理屋の料理を食べるということが酒席で人を接待することとして発達してきたからなのである。(「酒学入門」 小泉武夫・角田潔和・鈴木昌治編著)
大酔して醒めないとき
飲酒して大いに酔ひ、解けざれば、大豆の汁・葛花・椹子27・柑子(かんし)28の皮の汁は、みな可なり。
注 ㉗椹=桑の実、きのこ。 ㉘柑子=「味甘寒、去腸胃熱、利小便、止渇。多食発痼疾」。(飲膳正要巻三))(「食経」 中村璋八・佐藤達全訳注)
老舗企業設立年表
一一四一 永治元 須藤本家 酒造 里の誉 茨城県 友部町
一四八七 長享元 飛良泉本舗 酒造 飛良泉 秋田県 仁賀保町
一五二一 永禄年間 剣菱酒造 酒造 剣菱 兵庫県 神戸市
一五五〇 天文一九 小西酒造 酒造 白雪 兵庫県 伊丹市
一五五五 天文年間 千野酒造場 酒造 桂政宗 長野県 長野市
一六〇三 慶長八 司牡丹酒造 酒造 司牡丹 高知県 佐川町
一六一五 慶長年間 京口屋 酒類 愛知県 名古屋市
一六二五 寛永二 福光屋 酒造 石川県 金沢市
一六三五 寛永一二 村山本店 酒類 新潟県 村上市
一六三七 寛永一四 月桂冠 酒造 月桂冠 京都府 京都市
一六四四 寛永年間 初亀酒造 酒造 初亀 静岡県 岡部町
一六七三 寛文年間 多胡本家酒造場 酒造 岡山県 津山市(「老舗企業の研究」 横澤利昌) 酒関係だけの抜粋です。
とっくり(に)すぎたヨシヨシ
鉾田町菅谷では、疫病が流行したとき、また、その予防には前述した悪疫追い払いの各種各様の行事を行っているが、「とっくり(徳利)にヨシ(葭、葦)の葉とスギの葉をさして、門口に吊るし、疫病が通るとき『とっくにすぎたヨシヨシ』のよびかけ」としており、疫病が家の中へはいらないようにする伝承がある(玉造町、茨城町、大洋村も同じ)。水海道市大生郷では、とっくりにスギの葉とヤツデの葉をさして「ここのえは(ここの家は)とっくにすぎた」とのじゅ文のしるしとしている。ヤツデは九つの葉に分かれているので、この地方では別名ココノエの木と方言でいっているので、前述のような俚諺呪文となっている。(「民俗学と茨城」 外山善八)
新酒頌
酒酒、儀狄(ぎてき)つくり大禹なむ。ふるきはあたらしきにしかず、おもきはかろきにしかず。かろくすめるものは、暫時あたまにのぼり、重くにごれるものは、二日酔の枕となる。たちまち酔ひたちまちさむ。日々に新たにして、又日々にあらたなり。(「四方の留粕」 太田南畝)
田中先生
田中(哲郎(てつお))先生の指導は戦前から始まって亡くなるまで続いたわけだが、その後、一〇年ぐらい、やはり別の鑑定官の先生に指導してもらった。この先生は大塚泉(おおつかいずみ)さんと言って、やはり国税局の鑑定官をしておられた方だわ。だすけ、やっぱり大塚先生よりも田中先生の指導のほうが長かったせいか、八海山の酒造りは今でも田中先生の指導の影響が強く残っているんでないかね。田中先生流の造りの特徴は第一に、「硬い造り」というか、「酒が渋い」というか、そんげな造りだいね。だすけ、一年くらいは寝かしたほうがよくなる酒だ。また、きれいな酒だいね。そういう酒を造るために、田中先生は、いろいろなことを教えてくれたが、麹ひとつにしてもさ、少し若いぐらいの麹にして、使う麹の量もできるだけ少なくしろというふうだった。麹が若くて、使う量も少ないと、造りは難しくなるだんが、そのほうがきれいな酒になるすけ、おらたちも苦労して腕を磨いたわけさ。大吟醸酒の酛仕込み用の水麹(みずこうじ)を造る時は、若い衆が手でかきまわしているが、あれなんかも田中先生の言いつけ通りだいね。冷たいところに手を突っ込まんで、櫂(かい)でかきまわしていても、二、三日すれば平均に混ざるだんが、手でかきまわしたほうが、最初から平均に混ざるというこんで、今でも、田中先生の教え通りにやっているんだわ。大塚先生の造りはどうだったかというと、田中先生よりも、もう少し味を乗せるような造りだったな。だすけ、田中先生流の造りそのままというわけでもなく、田中先生流の土台の上に大塚先生流のやり方があって、そこに「野積(のづみ)流」というか、おらのやり方も入っている。そんげな具合でないかね。また、それが(南雲)和雄さんの好きな酒のタイプにぴったり合ったんだろうの。(「杜氏千年の知恵」 高浜春男)
爛漫
明治の末から本格的な酒の宣伝が始まり、東京方面への進出も同時に始まったが、これを徹底してやる会社が現れた。当時、秋田の酒を全国に売り出そうと、県内の業者が一致協力して設立した湯沢市の秋田銘醸株式会社。銘柄の「爛漫」も、全国から募集して選んだものだった。初代社長は、当時の県酒造組合連合会長の伊藤恭之助、専務は「両関」の伊藤忠吉、そして後に県醸造試験場の初代場長となる花岡正庸技師が相談役になるという、いわば秋田の酒の命運をかけた会社だった。そこでやったことは、まず一年間ぶっ通しで北海道の新聞に全面広告を出したことと、創業から十年間は全く株主への配当をせず、その分をすべて宣伝費に注ぎ込んだことだ。おかげで売り上げも順調に伸びたが、中には笑い話もある。有名な旅館、ホテルで使ってもらえば宣伝効果も大きいだろうと、東京の帝国ホテルに納品を申し込んだ。ところが「天下周知の酒でなければお断り」とピシャリ。灘の酒が最高とされていた当時のこと。くやしがった会社側は逆に発憤して品質向上と宣伝に力を注いだから、結果的にはこれでよかったのかも知れない。(「あきた雑学ノート」 読売新聞秋田支局編)
ダリヤ
ダリヤは夜深く机の上に見るがよく、コスモスは市街のはづれの小春日和を思はせる。鶏頭はまた素朴な花で、隠れ栖(す)む庭の隅などに咲くべきであらう。
動かじな動けば心散るものを椅子よダリやよ動かずもあれ
灯を強みダリやがつくるあざやけき陰に匂へるわれの飲料(のみもの)
眼にも頬にも酔あらはれぬ夜なるかな黒きダリヤの蔭に飲みつつ
はなやかに咲けども何かさびしきは鶏頭の花の性(さが)にかあるらむ(「秋草と、蟲の音」 若山牧水)
酒を楽しむことは人権の一部
ここで私は、酒を楽しむことは人権の一部だと考えることを提案したい。人権の一部だというのは、日本国憲法第二十五条の表現を用いれば、「健康で文化的な最低限度の生活」に含まれるということである。すべての人に保障されるべき生活水準の範囲内に、酒が含まれるということである。すべての人に保障されるべき生活水準からこぼれ落ちることを、貧困という。だとすると、酒が人権の一部だというのは何を意味するか。飲みたい酒を飲むことのできない状態は貧困であり、貧困の定義のうちに含まれるということである。「誰でも酒を楽しめることのできる社会を」これは、また豊かな酒文化を守り育て、安定した社会を維持するための要求であるとともに、人権保障の要求である。これを実現するためにまず必要なのは、格差を是正するとともに、人々が貧困に陥らないようにするための社会保障制度の整備である。しかし酒の問題についてとくに論じるなら、酒税法の改革も避けては通れない。詳しくは論じないが、少なくとも、本来は大衆酒であるはずのビールへの過酷な重税はただちに改められるべきだし、ソーダなどで薄めて酎ハイとして飲むのが主な用途である甲類焼酎の税率も、引き下げられるべきだろう。(「居酒屋の戦後史」 橋本健二)
オオバコ、ゲンノショウコ酒
まず、近くの土手や空き地で簡単に手に入る薬草として、オオバコからはじめてみるといいだろう。オオバコは刈られても踏まれても出てくる強い草で、子供のころ、茎をからませて引っ張り合い、どちらが強いかという遊びをしたことのある人もいるだろう。このオオバコ、古くからその薬効は知られていて、慢性気管支炎や高血圧症、利尿、排尿の作用があるといわれる。酒のつくり方は、花のある時期にオオバコを根ごと採取してよく洗い、これを天日に五日間ほど干す。そして、容器の半分量を入れ、砂糖を大さじ三杯加えてホワイトリカーを注ぐといい。中身は一〇日で引き上げ、三か月熟成させると、薬草酒ができ上がる。つぎに、下痢止めとして知られるゲンノショウコ。効き目が早いことから、「現の証拠」ということで、命名された雑草だ。これも花の咲いている時期に全体を採(と)ってオオバコと同様に干し、同じようにホワイトリカーに浸ける。熟成は二か月がめやすで、下痢、腹痛、整腸に効果があるという。(「酒場で盛りあがる酒のこだわり話」 博学こだわり倶楽部編)
飲み屋の中で 王績 前野直彬訳
一
洛陽」(らくよう)には居候(いそうろう)できるお屋敷もなく
長安(ちようあん)には世話してくれる人も少ない
いくら金を使ってもまだ足りないのは
おやじ お前の店のために貧乏しているのだよ
二
今日このように酔いしれたのは
養生の術を心がけるためではない
目の前にみんなが酔うのを見ては
おれ一人素面(しらふ)でいられるものか
三
酒を前にしたらただ飲むだけのこと
顔を合わせたやつを仲間にひき入れるまでもない
壚(ろ)にもたれればそれですぐにひと眠り
酒甕(さけがめ)を倒せばよい枕になるのさ
石狩粕鍋 夢心酒造 東海林伸夫さんのお勧め
酒粕は臭みを取ってくれるので、魚貝類を使った鍋ものによく合います。
●材料(5人分) 生鮭切り身 5切れ/酒の中落ちや頭(手に入れば) 1尾分/椎茸、こんにゃく、大根、ささがきごぼう、長葱、芹、春菊、しらたき、人参、白菜各適量/踏み粕 125グラム/白味噌 150グラム/昆布だし 8カップ
●作り方 ①だしの出る鮭の頭は、えらを取ってぶつ切りにしておく。身もぶつ切りにし、あらと一緒にさっと熱湯にくぐらせる。②野菜は食べやすいように切る。③白味噌と踏み粕をよく混ぜ、昆布だしを何回かに分けて入れ完全に混ぜきる。④味噌汁程度の濃さに溶いた味噌の地を土鍋にはる。⑤貝を入れて煮込んでいただく。
◆地は煮詰まらないように、薄めに作るとよいでしょう。(「酒粕の凄い特効」 滝澤行雄)
三段返し
春日君は大正末期に近い頃の東京帝大-新人会-の有力メンバーであった。この新人会とは当時第一次大戦の終末期に欧米に盛んとなったデモクラシー運動(今の民主主義である)を唱道した教官と学生の集団で、大内兵衛君や森戸辰男君などが助教授クラスの新しい人として牛耳っていたのである。会員の春日君は頭脳明晰、特に英語が達者で大酔すれば即席に英語で「落語」をやってのけるという男であった。尤もきいている方が凡そ、ペラペラやる英語の正誤をききわけ得る連中が少なかったので、当人安心してやっていたと思われるが!この男のトラは友人達が「春日の三段返し」と呼称していた。それ程までに鮮やかな三変化をやるのであった。先ず宴の当初少く共三-四合の日本酒がは入るまでは、誠に謹厳方直で、洋服の膝を窮屈そうに正座して、上司はもとより同僚にも一々「お流れを頂きます」と、言動頗るいんぎんを極めていた。やがて五合の酒量に達すると、他の列席の人々がさっぱり気づかぬ小瑣事に感激、興奮して、オイオイ大声をあげて泣きの段にはいる。特に春日君の海外出張中に、留守にしていた三女の母である彼の最愛の夫人が急性肺炎に冒された急電をうけて、ドイツからシベリヤ鉄道で急ぎ帰国した春日君は、文字通り一日遅れで、夫人の死目に会わずに永別した悲しいくだりが、五合の酒に誘われて同人の全部を占領するので、最初は「君の盃のくれ方が有難い」などと、いいつつ泣き出した彼は、やがて「つね子はなぜ死んだ」という号泣に変じるのが例であった。其の中にもコップか茶碗など手当たり次第に大型のもので酒の補給をつづけるので、やがて、一升の域に達する頃はいつの間にか泣き止んで、強度の近眼が光り出す第三段に入れば、「テメエーが文部大臣だなんて、チャンチャラ可笑しい、帝大の成績などよくもない癖にして大臣が勤まるか、今晩限りやめてしまえ」などとやり出して、大臣でも次官でも、同僚でも見境なくやっつけるようになる。もとより大あぐらである。「ヤイ、粟謙、お前が次官などやっているのは以ての外だ。唯今限りサッパリとやめろ、何一つうまく仕事が出来んじゃないか」という調子で列席苦笑の外なく、何とかなだめすかして「英語の落語」をやらせると、後はそのまま横臥して高いびきとなる事が多かった。(「文京の今昔物語」 出羽王堂)
カラスの女房
また、自分の作品で、申し訳ないのですが、堀内孝雄作曲、モーニング娘の中澤さんの曲で『カラスノ女房』。タイトルを聞いたとき、すぐに、犯人が解るんですね。多分、『カラスの女房』が犯人なんだろうけれど、何故、カラスの女房なのかはちょっとやそっとでは解らないんですね。これが、さっきの『哀しみ本線日本海』でしたら、女性がいて、失恋、不倫、旅、北国、夜汽車とが連想できますけど。『カラスの女房』だけじゃ、イメージがしづらくて、せいぜい童謡のカラスなぜ鳴くの、カラスは山に…でしょう。でも、そのカラスが山に…が、この推理ドラマの、犯人の顔をちらりと覗かせている所なんですね。カラスは山に…を、ピーンと、感じていただけママなら、この歌の世界に、つまり「事件」に巻きこまれてしまうんですね。まず、出だしの文句から紹介しますとね。「お酒を飲めば忘れ草 いいことばっかり、あんたはいって」と始まりますが、このお酒を飲めば忘れ草…で、男の人物像が浮かびますよね。たしかに、男たちはね、お酒を飲むと忘れちゃうのですよ、家のことも、仕事のことも、そして、彼女との約束もね。そして、また、飲むと、いい事ばっかり言っちゃうんですね。これが事件の始まりで、聴き手さんが勝手にイメージするんですね。これ!この歌、ひょっとしたら、オレのことかも知るれんぞ…とか、これ私の歌なのよと。そして、次の文句へ、事件が進むんですね。「カラスみたいに、どこかへ帰る それでも、心底、惚れているから」これでいよいよ、男の実像が見えてきましたね。カラスみたいに…ですから、きっと帰る家があり、子供がいて小さな倖せがある、なのに、この女性が好きなんですね。それでも、この女性はきっと、男を許し、その男を好きなんですね。そして、今度は、このダメ男に対する、女性の気持ちとか、心が表に出てくるんです。この男をどう思っているのか、どうしたいのか、そして、どうなってゆくのか、事件は山場に入ります。「一生このまま、待つだけの 電信柱でいいからさ」そうくるんですね、この女性の気持ちが痛いほど、出てきますね。一生このままでいいよ、好きだからさ、といっておいてね、その一生このままという気持ちを、電信柱のように、ずっとずっと待っている姿にたとえ、トリックとして使うんですね、この電信柱が、出てくるところなんか、さすがですね、もう、こうなりゃ、自画自賛ですが。(「おとこ町六丁目」 荒木豊久)
板粕
まずは板粕をひと口大にちぎって、レンジのグリルで両面を焼く。そして醤油をつけて食べる。すると、小学生のときに感じたのと同じ味わいで、なかなか美味い。酒粕そのものだから、当然、酒くさくて、さらにアルコールもたっぷり感じる。だが、焼くことによって別の味が出てくる。それは飯が焦げたときの香ばしい風味。ご飯のおこげやせんべいのような香ばしさである。ためしに晩酌の一品に加えてみた。たてつづけに食べると、さすがに酒くささが先立ってよろしくない。しかし、他のつまみの合間にちびっとつまむと、これが実にいい箸休めになるのである。何十年ぶりに食べてみたが、焼いた板粕がつまみになるというのは新しい発見であった。これまた、興味がおありの方はお試しいただきたい。「板粕をちぎって、両面を焼いて、醤油をつけて食べる」と、いたってカンタン。焦げる一歩手前ぐらいまでよく焼くのがコツである。このように、個人的に酒がすすまぬつまみを考察してきたが、納豆もカレーも酒粕も、よくよく探求してみるともっと美味しく酒が飲めるつまみに変身する可能性がありそうだ。(「晩酌パラダイス」 ラズウェル細木)
夫婦同伴で「お通し」の味を盗む
小料理屋では一般に「お通し」と呼ばれるものが出てくるが、このお通しがまずい店は必ずと言っていいほど客の定着率が悪いものだ。常連さんで繁盛する店というのは「お通し」がうまい。ある作家に言わせると、-「お通しのまずい店は、ミスミスお客を逃がしているようなものだ。私は、お通しがまずかったら、一杯だけ飲んですぐに席を立ってしまう」。さて、ご主人。あなたを常連にしている店に奥さんを連れて行ってはどうだろう。「オレの唯一の城を女房に知られるのはいやだ」なんて強情を張らないで、連れて行けばそれなりにいいことはある。ご主人がうまいと思う肴は、奥さんでもわかるはずなのだ。女というものは、必ず、そのつくり方をママさんに聞く。-「これ、隠し味に何を使ってるんですか」。するとママさんも、ふだんだったら「企業秘密よ」と言うところだが、ご主人の奥さんには親切に教えてくれるものである。べつに女性の味方をするわけではないが、「我が家の食事はまずい」などと言う男性にかぎって、奥さんと外で食事するなんて気配りのできない人なのである。酒の肴がうまくつくれる女房は、三国一の花嫁と言ってもいいのではないだろうか。年に何回かでいい。たまには夫婦同伴で飲みに行く。晩酌の肴の味がよくなれば、何よりではないか。(「酒飲みを励ます本」 志賀貢)
中国食物史年表(古代)
BC二八〇〇~二三〇〇 酒。黄河中流の竜山文化遺跡から、尊、斝(か)、盉、高脚杯、小壺などの、醸造、飲酒などの容器が出土しているので、酒は、当時すっでにあったことを証明している(『中国酒』一九七九、『辞海』一九七九)
BC一六〇〇 河南省鄭州遺跡から酒造場跡を発見(『中国酒』一九七九)酒は糖質に酵母が加われば自然にできるものであるから人類以前から酒精飲料はあったと考えられている。中国で伝説上の酒の発明者は、夏時代の儀狄(『戦国策』)と周代の杜康(少康)となっている(『世本』。酒は『周礼』に酒人、酒正などの職名が見られるほか当時のほとんどの本に出てくるので人類とともにあったことはわかるが、醸酒法が具体的に見られるのは六世紀の農書『斉民要術(せいみんようじゆつ)である。』)(「一衣帯水」 田中静一)
酒飲みの自己弁護
まずは、山口瞳氏の『酒飲みの自己弁護』(新潮社刊)だ。これは夕刊紙に連載された好読物だが、現在、文庫本で手軽に手に入れることが出来る。私は、連載中愛読していたが、一本にまとまったものをまとめて読んで見ると、また別の味がある。この本は、どのページを開いても、そこにキチンと酒の話が一つずつおさまっていて、実に愉しい。そしてそこには山口瞳さんという酒の苦労人の体臭がプンプンする。作者が外国旅行嫌いなのは、言葉が通じないという理由を除けば、もう一つあるという。それは、「今晩あたり、庭のミョウガをきざんでヒヤヤッコでなんて考えると、外国が吹き飛んでしまう」のだそうだ。食堂車は、新幹線上りなら横浜あたりで終りになる。「これが実に困る。こちらはホロ酔い。最後の仕上げと思っているのにオシマイ。あの二十分、三十分がとても辛い。むなしい」と抗議する。また、この人は「宿酔の時、迎え酒はビールに限る。それも小瓶一本が限度」と体験の披露もしている。教訓がいっぱい。甘い酒、ニガい酒、嬉しい酒、どれもが、読者にとっては憶えがあるのだ。そこから筆者と読者の共通の広場が広がる。一話ごとについている山藤章二さんのいじわるイラストも、ワサビがきいていて愉しい。(「作家の食談」 山本容朗)
夕焼けってのは悲しい
照れ屋でひとみしりする鶴田は、ごく親しい仲間にしか本音をみせなかったが、私などはその数少ない仲間の一人だったろう。飲めば、よくしゃべり、そしてよく泣いた。人情家の彼は、情にほだされて涙ぐむことがしばしばだった。「筋を通す」ことを生き方の根幹にすえた鶴田は、何度も裏切られ、そむかれたりもしたが、「いい出したらきりがない。でも、いったらしまいや、いわんのが男」と口許に笑みを浮かべながら、目に涙をためている姿を、何度となく私は見た。その意味では、鶴田浩二の酒は"情念の酒"であり、涙の酒だった。毎年十二月六日の彼の誕生日には、親しい仲間が彼の家に集まった。年々、その数はふくれあがり、鶴田の家は男どもの熱気でムンムンするのだが、海軍予備学生時代の制服に制帽姿の鶴田は豪快に飲み交わしながら、必ずといっていいほど、目には涙をためていたものである。鶴田浩二のとっては、歓びが大きければ大きいほど、若くして逝ってしまった友人たちが偲ばれ、歓びをわかちあえない切なさが胸をしめつけるにちがいないのだが。「夕焼けってのは悲しい。切なくてきらいだ」と語った鶴田がいまもありありと思い起こされる。(「いい酒いい友いい人生」 加東康一)
お酒のよいのを持って来る方
何を申すにも大根畑のお宅はお狭いのに、大勢のご仁が、絵の催促やら、借金の催促やら大変の人数で座敷の中にはだかって、先生の描いている絵を観ているんで書画会みたいな光景なんでござんす。そんな風で、なかなか絵が出来上りませんからムダを踏ませますところから、先生が根よく居残った方々に絵罰金だといって、チョイ書きの小さい絵を描いてあげるもんですからソレを喜んで持ってお帰りになります。その絵を溜めて持っていた方は、後の話ですが、二百何十円になったということでした。先生はお酒好きですから、絵を描きながらお燗酒をギューと一気にぐい飲みをなすってでした。お肴はトンと要りません。お酒のよいのを持って来る方にはたちまち絵をお描きになって、紙幣を並べてもなかなかお描きにならないので奥さんの方は歯痒いんでした。(「河鍋暁斎」 落合和吉編) 暁斎の弟子だった綾部暁月の話を篠田鉱造が記録した文章です。
冷(ひや)し酒(ざけ) 冷酒(れいしゆ)
夏は燗(かん)した熱い酒よりも、冷たい酒が口あたりがよい。それで冷たいままを飲む。近頃は氷で冷やして飲む。冷たい酒がきゅうと喉を潤すのはたのしい。
冷し酒夕明界(ゆふめいかい)となりはじむ 石田波郷
塩漬けの小梅噛(か)みつつ冷酒かな 徳川夢声(「俳諧歳時記 夏」 新潮社編)
あの頃
私は若い頃から、酒は余り飲めない方だつたが、砂糖がなくなると、糖分の不足から急に酒が欲しくなり、支那から帰つた人に白酒(ぱいちう)をビール瓶に一つ貰ひ、それに水を割つて飲むのだが、電車を降り、自家(うち)へ帰るまでの途で、その事を想ふと、ひとりでに笑ひが頬に浮ぶのを禁じ得なかつた。食通は薄味を喜ぶが、此時代は何んでも濃い味のものがよく、塩気の強いものがうまかつた。身体が要求するのだ。薄味がいいと云ふやうな人は働かずに栄養を充分蓄積してゐる者の云い草で、味覚の発達でも何でもないと思った。-
志賀先生(一八八三-一九六〇)が酒について書いたものは、この随筆と、少年のころ正月、友だちの家で屠蘇に酔って前後不覚になる話(「速夫の妹」)
と二つくらいしか無い。人が酒を飲むのには寛大だったが、酔っ払いには寛大でなかった。殊に酔ってからむ癖(へき)をきらい、そういう話を聞いただけで「僕なら最初から飲まさない」といやな顔をした。長与善郎さんが志賀家での夕食で御機嫌になられ、「あと一本」と所望するのに、「長与はもうだめだヨ」とにべもなく止めてしまわれるのを見たこともある。体質的に下戸だったが、そのくせ、戦後の窮乏時代私が、飲めさえすればいいので酒の味など分りませんと言うと、「そうかネ、酒のよしあしはハッキリ分るがネ」と言った。(阿川弘之)(「あの頃」 志賀直哉(酔っぱらい読本)) 後半は阿川の解説です。
酔小楠
「虚飾辻遠の学風をしりぞけ、実行に重きをおくべし」として常に学政一致を唱えた小楠は理想主義者が現実の世界でこうむる被害を、自分の郷里熊本で徹底的に受けたといえる。もっとも小楠の性格にも欠点はあり舌鋒鋭く訓話の旧学を批判し、徂徠学の功利性を叩き、相手の地位や身分を問わず、容赦することがなかった。おまけに「酔小楠」とかげ口されるほどの飲酒家で、酒癖がわるかった。藩命による江戸遊学は三十一歳の天保十年(一八三九)だが、他藩の士を交えた酒宴の席で大論争に及び政治批判を口走ったことを咎められて翌年にはもう帰国している。しかし藤田東湖をはじめ錚々たる水戸学の学者たちに接し、大いに啓発されたことは確かだった。西国の片隅で積み重ねてきた自分の学問が天下に通用するという自信も得て来たであろう。(「江戸人物伝」 白石一郎) 酒失と帰国
くよくよ
酒を飲むの理由は、実は前向きなものではなくて、かように後ろ向きなものだったと、三十代の半ばごろにようやく気づいた。好きなのじゃなくて、ちょっと切羽詰まった感じで必要なのだと気づくと、もう何も言い訳することもなく、休肝日も作ることなく、酒を飲むようになった。かような理由なら、ひとりでいるときには飲まなくてもいいはずなのだが、でも、飲む。「人見知りで心を閉ざし」ではなくて、「くよくよする」部分で必要なのだと思う。ひとりだとくよくよは深度を増すから。しかしながら、私には酒にかんして弱点がある。飲みはじめたら,途中でやめることができないのである。どうしてもどうしても、できない。それこそ二十年近く、きりのよいところで飲むのをやめようと試みて、できない。逆立ちで歩けないように、できない。とことん飲むしかない。そして、とことんへの過程で、記憶がなくなるのである。ある一定量飲むと、その後のことを覚えていない。その一定量がどのくらいなのか、わからない。時間にすると、七時から飲みはじめたとして、十一時以降があやしい。それでも最後まで居座って飲み、,タクシーで帰宅し、自宅で寝ている。起きて、昨日のことを思い出そうとすると、思い出せない。今にはじまったことではなく、酒を飲みはじめた若いときからそうだった。前の日のことが思い出せないと、従来の私の「くよくよ」部が活発に活動をはじめる。だれかに失礼なことをしたんじゃないか。食べものを口からこぼしたりグラスを割ったり、無様なことをしたのではないか。お金を払っていないのではないか。好きでもない人にべたべたさわったりしたのではないか。くよくよ、くよくよと考え、消えたいほどの暗い気持になる。昔は、いっしょに飲んだ人に,上記のようなことはなかったかいちいち訊いていた。大丈夫、とみんなが答える。なかったよ、じゃなくて、「だいじょうぶ」。その返事がまたこわくてくよくよする。一時期、私はこのくよくよがあんまりつらくて、酒を飲むのをやめようかと思ったことがあるくらいだ。もちろん、やめられなかった。(「損だけど」 角田光代)
熟成の裏ワザ
生酒の熟成どころか,常温熟成は通常なら無謀といわれるこれを実践していた地酒居酒屋「みつひさ」という店が以前渋谷にあった。そこの店主の橋浦さんは、常温熟成に向く酒とそうでない酒を区別し、しっかりした造りの酒は店のカウンターに置いて熟成させていた。そうでない酒はもちろん冷蔵保存である。私は自分の好きな銘柄だけを飲めればいいので、全て常温熟成に耐える銘柄を選んで貯蔵している。では、常識外れの常温熟成のメリットとは何か、熟成とは味のりの変化と酒質の劣化を伴うもので、その変化の度合いは温度が支配する。冷たいと劣化は少ないが味のりの変化も少ない。温度が高いと劣化も早いがそれ以上に味のりが進む。そして、特にしっかりとした造りの酒は、温度が高くても劣化の度合いが少なく、味のりがいいバランスで進むのである。以前、栃木県小山市の蔵元、小林酒造の造った鳳凰美田霞酒の四号瓶を、一本は冷蔵庫に入れ、もう一本は常温で床の上に転がして二年間放置する実験をしたことがある。その二本を小林酒造へ持ち込んで小林専務と一緒に飲んでみた。冷蔵庫で冷やしたものは中途半端な味のりで老ねが目立ったが、常温熟成したものは味のりが見事に老ねをカバーして、あまりあるほど旨みがあった。専務もこの実験にはびっくりしていた。(「蕎麦屋酒」 古川修)
上機嫌な父
父の酔狂ぶりと母の苦労を書けば限りもない。けれどその他の事も大体似たりよったりのものである。そして、結果においては父の酒癖がついに没落の因ともなり、晩年ずっと病床から起てない宿痾(しゆくあ)を作りつつあったのだが、然しまた、いついつも乱暴や無理難題を酒癖としている父でもなかった。茶屋へゆけば豪放な遊び方をして、おもしろい人だといわれていたらしいし、家庭で酔っても、どうかすると大機嫌で、大勢の子供や女中を相手に一晩中キャッキャッといわせて無事に横たわってしまうこともある。ぼくたちは、そんな上機嫌の父親を見すますと、父の膳を取巻いて、父へたかッてみせる。「後ろへ仆したら御褒美をやる」と云う父の後ろから、ぼくたちが大勢して、頭を押したり、喉くびを締めたりして仆そうとする。父と子供らと取ッ組み合いになる。父の髭にジャリジャリこすられると、ひどくこっちは痛い。そして、父の脂(あぶら)ッこい体臭-男親の匂いといえるようなものを、いやというほど酒の香りと一しょに嗅がされる。父親の匂いもまた、女親の涙のように、子供のどこかへ忘れ難いものになって深く沁みこむ。上機嫌な父を終日見たのは、父に連れられて杉田の梅林へ梅見に行ったときである。あちこちの腰掛け茶屋で一本飲み二本飲み、父はいつか泥ンこに酔ってしまった。乱痴気な酔漢を路上に見るのは珍しくない時代であったが、父の酔態は、そんな酔ッぱらいの多い梅見客の中でさえ人目をひいたほどだった。ぼくはまだ小ッぽけな少年だし、人目にもきまりが悪く、この父親を連れて帰るのにまったく当惑した。父は磯子のトンネルを出た所で、浜辺の草むらに寝てしまい、ぼくは夕焼けの海を見ながらベソを掻いていた。そのうちに、通りがかりの俥屋が訊(たず)ねてくれたので、所番地をいって、俥の上にかつぎ上げてもらい、ぼくも俥に乗って帰った。あとで考えると、この日の父の姿ほど、なつかしいものはなく、どこかにそうした放逸な風もあった人だったかと、ぼくがその当時、まだ父と一しょに酒が飲めない年頃だったのが惜しまれる。(「忘れ残りの記」 吉岡英治) おふくろの後など追うな
狗(いぬ)に肴(さかな)の番
犬に酒のさかなの番をさせる。犬の前にえさを置いたようなもの。太田方(おおたほう)(一八二九年)の『諺苑(げんえん)』(一七九七年)に掲げ、<白氏文集六十四、渇馬守レ水ヲ、餓犬(がけん)護(まも)ルレ肉ヲ>と注記する。
戦前の秋田の酒
大正十年の第八回品評会で両関が名誉賞に輝いたことは紹介したが、この時は同じ湯沢市の志ら菊(後に廃業)、福娘(現在の福小町)が優等賞に入った。同十三年の第九回には爛漫、第十回には末広、雄物川、花政宗、日出政宗、比羅夫、第十一回には新政、友鶴、第十二回には国万歳、太平山…というように、新たな顔ぶれが続々と登場して来た。この中には、戦時中の企業統合などで廃業してしまった酒蔵も多い。本県清酒のオールドファンのために、最後の品評会となった昭和十三年の第十六回までに優等賞に入った銘柄を挙げると-大の里、菊水、黄金井、秋田川、小野里、由利正宗、英雄、豊里、玉泉、館の花,千歳盛、宝生、福禄寿、天洋、秋田山、飛良泉、秀よし、国之誉、金時、蕗正宗、天寿、刈穂、勝平、金福、福の友-以上全部で三十八銘柄。優秀賞三回でもらえる名誉賞も十四銘柄に及んだ。(「あきた雑学ノート」 読売新聞秋田支局編)
子どもの飲酒があぶない
子ども達がいったいどのくらい飲酒しているか、まず私達の調査結果から紹介しましょう。表1を見て下さい。中学生の五七%、大学生の九四%はお酒を飲んだ経験を持っています。もちろんこの中には、日本の伝統的な文化であるお正月のお屠蘇や、親類の結婚式やお葬式・法事なんどで、周囲から勧められてやむを得ず少量のお酒を飲んだだけの子どももいると考えられます。あるいは、コンパという行事は、二〇年前は大学生の特権でしたが、一〇年前から高校生の間でもごくあたり前の言葉として広まっており、そのようなコンパや打ち上げの場に参加して周囲から勧められてやむを得ず少量の飲酒をしている子どもも含まれています。そういう子どもは、年に一~二回の飲酒ということになるのでしょう。年に一~二回の飲酒の子どもは中学生で三十%、高校生でも三十%、大学生で六%くらいです。そうするとそれ以上飲酒している子ども達、つまり月に一回以上飲酒していると答えた子どもは、もう立派に自分の意思で飲酒してるということになるでしょう。月に一回以上飲酒しているものは、中学生で二四%、高校生で四五%、大学生で八八%に存在しました。そしてもっと頻度の高い飲酒している者、つまり週に一回以上の飲酒をしている子どもは、中学生で八%、高校生で一四%、大学生では四三%存在しました。日本では大人でほぼ毎日飲んでいる人は、男性で四五%、女性で九%といわれています。むろん子どもの飲酒はまだ大人達と比較するとそんなに飲んでいるわけではありませんが、注目に値するのは、子どもの間では、男子と女子の間には大人ほどの大きな差が見られないことです。たとえば週に一回以上飲酒している生徒は、中学生の男子で一一%、女子で5%ですし、高校生でも男子で一八%、女子で七%、大学生になると男子で五〇%、女子で二四%ですから男女比では二対一の割合です。表1から子ども達がごくあたり前の感覚で飲酒しているということがおわかりいただけたと思います。(「子どもの飲酒があぶない」 鈴木健二) 表は1990-1992年に、全国の高校生1.4万人、中学生0.3万人、大学生0.1万人の調査結果だそうです。
法善寺の味
正弁丹吾は、この横丁(法善寺横丁)ではお職だからあとに廻して,東からかんざし屋の花宗の前を入って、まづ「お多福」からのぞいてみる事にしよう。私は、この「お多福」を大いに愛した。この横丁で、いちばん値段が安かったからである。酒は白雪。まん中のヘコんだ、坐りのいい三島手の徳利に、約八勺、それが十銭であった。あては五銭のつき出しから、三十銭まで、五銭きざみに、手板の品書が卓上に出してある。私はふところの淋しい晩はここにきめていた。という風に、この横丁の店々は安い、うまい、仲居が美しい、酒がいいなどと、それぞれの特色をもって、客に臨んでいた。-
さてその法善寺横丁でも、ことに特色のあったのは、いちばん大衆的で値段が安く、一応満足させてくれたのが「お多福」、天麩羅の味では梅月、天寅にも比肩するほど一流ぶりであった「鶴源」、仲居の美しさで一種の情緒をただよわせ、店の入口に生洲(いけす)を造ってこの横丁で一流を誇った「二鶴」、そして大阪のいわゆる関東(かんと)だき,煮込みおでんと茶椀酒の立ちのみで売り出した「正弁丹吾」-と、まづこの四軒にしぼる事が出来た。(「味の芸談」 長谷川幸延)
昭和21年9月
九月一日 -酒が焼酎だったため、悪酔。雷雨、寺沢君迎えに来てくれる。
九月二日 -一時、焼酎をのんで床に入ったが、ねつかれない。四時また起き出て、焼酎を飲む。
九月五日 -秋山君に誘われ,銀座の「銀扇」へ。松本和雄氏に会う。出版を始めると言う。円朝の話を聞く。遅れて山川氏来る。疲れのため酩酊。帰宅後直ちに寝る。
九月十日 -酩酊。「団十郎」に廻る。新橋駅で電車に乗ろうとすると、ドアがしまり、鞄を扉にはさまれた。取ろうとしたが、とれない。電車はそのまま出て行った。駅員室へ行き、処置を頼んだ。すぐ来た汽車で品川へ行き、駅員室へ行くと、鞄が取ってあってくれた。電車に乗換え。大船近くで窓からゲロを吐いた。
九月十三日 -十二時、焼酎を飲んで睡眠。
九月十六日 -「団十郎」へハシゴ。林、占部、それに「アヴェック」で会った佐伯孝夫と。
九月十七日 -船山、野口の両君泊る。
九月十九日 -そこで飲んで、「ブーケ」へ廻った。久し振りだ。北鎌倉駅に着いてから、ゲロを吐いた。
九月二十五日 -退社後、秋山君に誘われ、「みずち」へ行く。川端さんも一緒。先に松本君が待っている。「ブーケ」へ廻る。
九月二十六日 -退社後、木村、鍛代君と「アヴェック」へ。姫田君と落ち合う。この頃「アヴェック」は大変な人気。安直に飲めるからである。
九月二十八日 -島崎君を誘い、「アヴェック」で飲む。咽喉が痛く微熱あり、酔って不快を追払おうという所存。
九月三十日 -依然として咽喉が変で、気分悪し。大森、木村君を「アヴェック」に誘う。久米さんも貸本部のことについて一杯やりながら相談しようというので、「アヴェック」へ誘う。川端さんも一緒。日本橋からタクシーで。(五十円)「アヴェック」で、いろいろな人物に会う。新橋の「よし川」へ寄る。(宮内君が板前に入ったのだ。)乱酔。(「終戦日記」 高見順) はっきり飲んだと分かる日だけの抜粋です。
子規の酒歌
この歌を受けて,正岡子規-(慶応三~明治三五、一八六七~一九〇二)は明治三〇年に柹(柿)の歌として次の歌を発表しています。
世の人はさかしらをすと酒飲みぬあれは柹(かき)くひて猿にかも似る
子規が本気で歌を作りだしたのは、『歌よみに与ふる書』を発表した明治三一年以降といわれます酒をよんだ歌をあげます。
酒醒(さ)むる夜半(よは)のともし火風吹きて雁(かり)が音(ね)低し雨にやなるらん
長安の市の酒屋の桃咲きて李白(りはく)が鼾(いびき)日斜(ななめ)なり
わせ鮭のうま酒の酔ふ金時の大盃(おおさかづき)といふ楓(かへで)かも
八入折(やしほり)の酒にひたせばしをれたる藤なの花よみがへり咲(「万葉集に見る酒の文化」 一島英治)
南部美人
-どうしてなの?社長さん?「地方の小さな蔵が生き残るには、全国鑑評会に入賞しなければ地元の人に認めてもらえません。今は情報の時代ですから地方のマスコミにもどんどん話題を提供してゆかなければダメだし、消費者のニーズに応えるためにも、東京での入賞は格好の話題なんですね」山口杜氏は、南部杜氏鑑評会で連続優等賞に入り、とくに昭和五十四年、五十五年には首席となり大蔵大臣賞をうけている。全国鑑評会では、昭和五十一年から六十三年までの十三年のうち八回金賞を受賞し、平成元年度も金賞に入り、受賞率の低かった東北地区でのエースとなっている。また、山口杜氏は平成四年には、国の卓越技能者「現代の名工」を受賞された。なんともいえない良い顔の山口杜氏に見惚れながら、杜氏さんの酒量は?と聞くと意外にも全く飲めないという。-お酒が飲めないのでは、どんなお酒がお客に好まれるか、わからないでしょう?と、ややなじるように聞いてみる。山口杜氏は唯、にこにこ笑っているだけである。-ハハアン、わかった、女ですね。杜氏さんは若い頃、女性を泣かせたでしょう!!なにしろ、南部男に津軽女という土地柄ですものね。「いや、いや」と照れておられる。「女に興味がないようでは、艶のある良い酒は醸せませんよね」浩社長がカバーしてくださる。山口杜氏はいよいよ照れて、「南部美人」のもつ淡麗で芳醇、まろやかで深い味わいのある笑顔で座しておられたものである。(「酒の旅人」 佐々木久子)
日本の酒のルーツをたどる
まず「日本の酒は韓国からきたものなのか?」について考えてみる。第6編の監訳注記でも簡単に触れたことではあるが、いますこし敷衍してみよう。原書は「日本人の誇る酒、清酒のルーツは韓国である」と主張する。なにも難しく考えることはない、「その通り」である。むしろ、なぜ「違う」と言わなければならないのかが問題である。当今清酒は日本酒と呼ばれることが多いので、「日本人の誇る酒=清酒」のことを「日本酒」とする。「違う」論のほとんどは、「日本酒は類まれなる日本人の知恵の結晶である」と唱える人々である。これを仮に"日本酒国粋主義"と呼ぼう。私とて「日本酒が日本人の知恵の結晶である」ことにいささかの異議もない。しかし、日本人だけが今に至る日本酒をつくりあげてきたのか、他の国の人々の知恵の一滴も混じっていないと言えるのか、となるとどうだろう。洋酒系の酒については、かなり素直に歴史的事実を検証しているのに、こと日本酒となると神経質になるのはなぜだろう。これらは明治以降の「日本の近代化」の後遺症である。ヨーロッパ・アメリカに兄事することは躊躇なくとも、アジアにだけは傲然としていたいという「脱亜入欧」の固定観念である。こんな頑迷な意識からは脱却したいものである。それはともかく、ものごとの始原をたどるには、その本質を明らかにしなければならない。日本酒の本質とはなんだろう。本質とは、この場合<発生史的要因>とする。日本酒というものが発生したときの、それ以前のものとを分かつ物-「新たに〇○が違うようになって日本酒となった」の〇○である。日本酒を日本酒たらしめるものとはなにか?「日本の米でつくられたもの」か?、「日本人のつくったもの」か?まさか「日本人だけが飲んだもの」だからではあるまい。ことに学問的に厳密であるを要す。分類論として考えれば、日本酒は原料として「米の酒」であり、アルコール発酵の前段階としての糖化にカビを利用する「麹の酒」である。これらはいずれも日本において独創されたものではない。(「概説 韓国の酒造技術」 大韓酒類工業協会編 井出敏博監訳) 「監訳者あとがき」です。
御酒被下
大六天(小石川小日向大六天町)では年に何回か、主人も家来もわけへだてなく、表(事務所)も奥もいっしょになってする遊びがあった。私たち家族の誕生祝いなどにした福引きが、それだ。誕生日に限らず、他のお祝いの折にもやったかもしれない。実は私は十月、妹は九月生まれなのだが、それぞれのお祝いはせず、毎年二月に母といっしょに祝っていただくことになっていた。こういう日は夕方になると、家中の皆に「御酒被下(ごしゆくだされ)」といって、お酒が出され、表は表で二間を貫いてテーブルを並べ、中ノ口も内玄関脇の部屋でそれぞれ酒宴が開かれた。私と妹は自分たちのお祝い膳をいただいてから、表と中ノ口の人たちにお酌に行ったものだ。お誕生日にかぎらず、ちょっとしたお祝いにもこの「御酒被下」はあった。福引は、お酒が入って皆いいご機嫌になったころ、お客座敷の大広間で行われた。ごく内々の無礼講の集まりという気安さもあったろうが、軽口を言う者あり、冗談に笑う者あり、それはにぎやかだった。(「徳川慶喜家の子ども部屋」 榊原喜佐子) 佐喜子は慶喜の孫だそうです。
酒に対して喧嘩腰
外村繁もまた酒好きでは人後に落ちない。後にはアルコール中毒になっていた。「連日無休」という随筆のなかで、「二十歳の時、初めて酒を口にして、この世にこのやうな美味なものがあるかと思つた私であつてみれば、覚悟は既にその時に決まつたはずである。今更、酒の功徳を云々するつもりは毛頭もない」と書いているが、この言葉どおりに実践したようである。また外村の酒を飲む心掛けは変わっていて、酒に飲まれることだった。人はよく酒を飲むのはいいが、酒に飲まれてはいけないと説く。しかし、これでは何だか酒に対して喧嘩腰で、酒を本当に味わえない、というのだ。彼もまた酒仙の一人に数えるべきだろう。(「阿佐ヶ谷界隈」 村上護)
酒痴末法
この頃もやっぱりお酒を飲む。お酒もかかるし、お金がかかったって、お金がありさえすればそんなことは何でもないが、お金がないのにお金がかかるというのは少し変なもので、かかったという実態が即座には出ないのだけれど、あとになってじわりじわりとそのむくいが現われてきて、それが何ともいやで、一度にどかんとお金がなくなった方がむろん理想であるが、そのどかんと一度になくなすお金がないから、じわりじわりとむくいが出てくるのを不本意ながら待っているということになるわけで、それが実にいやな気持のものである上に、からだの具合もまことに面白くなく、来年の春の花には会えるだろうかなどと、庭の椿(つばき)を見ながらふと思っては宿酔(ふつかよい)の不快を抑えようがための冷水を二杯も三杯も飲んで仏頂面をしているというのが午前中のならわしとはなっているような有様なのに、頼まれたこととはいえ、お酒の雑誌のお祝いにこうして下らぬ文を綴っていれば天然自然とお酒のことが想われて、今こそもうお酒なんかというほどの気分のわるさではあるが、この調子では夕方になれば自ら酒杯をまさぐりかねない愚かな仕儀に立ち至るのは必定なりと、まだ飲みたくもないうちから、飲みたくなるだろうと目算を立て、いやその目算が立ちやすいようにお酒のことを筆に上す、酒痴末法である。(「若気のいたり 年寄の冷や水」 高橋義孝)
セックスアピール
昔から私はふしぎだったんだけど、どうして私は男の人が飲んでいる時より、食べている時の方に、よりセックスアピールを感ずるんだろう。そういえば、飲んでる所は見るけど、食べてる所はみんな、あまり見ない。食べるという作業はたいへんプライベートな部分に属する。尤も、私の知ってる男の人はみな飲みすけだから、食べるものがあっても手を出さず、お酒の方ばかり。野坂昭如さん、後藤明生さん、藤本義一さん、石浜恒夫さん、小野十三郎センセイ、みんなそう。ただ小松左京さんはよく食べる。よく飲み、よく動きまわり、すごいエネルギッシュな酒で、とてもついて廻れない。阿部牧郎さんも飲むばっかりの方かな。尤もこの人は大変な美点がある。いつか酔っぱらって私のウチに泊ったらあくる朝まっ先に何したか。電話にとびついて夫人を呼び出し「ゆ、ゆうべ、タ、田辺さんのとこに泊った」とオロオロ弁解していた。(「酒中日記」 吉行淳之介編 田辺聖子)
ぶり照り焼き
四角く木取って-、ふっくら焼き上げましょう。出世魚「ぶり」は、いなだ、わらさ、はまちと出世してきて、最高に脂がのって成長しきったもの。縁起のよい魚です。
●材料(2人分) ぶり切り身(焼き物用)2切れ 焼きだれ(醤油大さじ3 みりん大さじ3 砂糖大さじ1) 酢取りしょうが
●作り方 1 ぶりに焼きだれをまぶして、5分ほどおく。 2 水気を拭って、串に刺して焼く(グリルで焼いてもよい)。 3 火が通ったら焼きだれをぬり、焼いて乾いたら、さらにたれをぬる。 4 これを2~3回繰り返し、器に盛ってたれをぬる。 5 酢取りしょうが-などをあしらう。(「おうちで居酒屋」 YYT
project)
干酵
宋朝の時(九六〇-一二七九)朱翼中は『北山酒経』を書いた。その中には、それまでの製曲(製麹)の原料や操作をさらに学問的に進歩させた、非常に高度な技術が述べられているが、そのほかに最も顕著なものとして「干酵」という方法を紹介している。この干酵の製法は、正常に発酵している酒醅(発酵中のもろみ)を取って、曲の上に塗って風乾するもので、この乾燥した微生物製剤を「干酵」といったのである。酒醅の中には発酵中の酵母が多数存在しているから、明らかにこれは曲と酵母とが一体となったものでりあり、きわめて高度な発酵剤であり、スターターである。この干酵一つだけで、原料中のデンプンを糖化してブドウ糖にし、それを速やかにアルコ-ル発酵できるからだ。さしずめ日本酒製造における麹と酒母を一体化したものであり、さらによくよく考えてみると、この干酵は今日の乾燥酵素と乾燥酵母の原理ということができる。(「銘酒誕生」 小泉武夫)
のみコン[名]
(「コン」は「コンパ」の略)飲食しながら、友達を多数作るのが目的のコンパ。<関連語>菓子コン。◇『なにわOL処世道』各論1(2002年)<そのだちえ>「『のみコン』は恋人を捜すことが目的の『合コン』と違い、『飲食しながら、友達を多数作るのが目的のコンパ』。4月頃に盛ん」(「日本俗語大辞典」 米川明彦編)
食べ物を描かない宴会
『万葉集』の「巻第五」の八一五番から八四六番までの三二首は、ある宴会のおりに詠(よ)まれた歌である。しかし、そこでは飲食そのものはほとんど言及されず、その日のテーマである梅の花の宴会という時空間のなかでの美しさ(=風情)が、微(び)に入り細(さい)をうがって詠(うた)いこまれる。かろうじて飲食に言及した歌は三首(八二一、八二三、八四〇)のみ。いずれも酒に関するもので、そのうち一つは酒に浮かぶ梅の花である。もちろん当時の酒は日本酒であり、しかも酒を澄ませる清酒技術は室町時代以降のものであるから、このころの日本酒は白く濁っていて、そこに梅の赤い花びらが浮かんだ姿はたしかに風情があったに違いない。そして、この大伴旅人(おおとものたびと)が催(もよお)したとされる宴会の歌は「梅花(ばいか)の歌三十二首」とされ、あくまで梅見がテーマであった。ちなみに、当時、花見とは梅見のことで、桜が花見のメインになるのは平安時代以降である。ここでは、酒は風情を盛りあげる興奮剤だった。だから、あえて描かれるのは食よりも酒なのだ。酒の酩酊作用が、梅と、梅のある風景をより美しく感じさせたにちがいない。今でも花見は絶好の集団飲食の機会、とりわけ酒を飲む<口実>=<装置>である。毎年、万葉集以来の古き良き伝統にのっとって、どれほど多くの人が桜の木の下で酔いつぶれて、どんちゃん騒ぎをしていることか。しかし、現実には花見が口実であっても、ブログにはきっと酒や料理ではなく桜の風情が描かれるにちがいない。酒はあくまで桜のある風景をより美しくするために飲まれたのだ!(「「飲食」というレッスン」 福田育弘)
840の歌は、「春柳縵(かずら)に折りし梅の花誰(たれ)か浮かべし酒杯(さかづき)の上(え)に」です。
腕相撲
ずっと後の話だが、赤塚(不二夫)は、梶原一騎と腕相撲をやったことがある。梶原は、『巨人の星』や『あしたのジョー』の原作者で、一八〇センチを越す巨漢。空手の師範まで務めた男だ。銀座のクラブで飲んでいた時のこと。何故か、腕相撲で負けたほうが、今日の勘定をもつという話になった。店の女の子達は囃したてる。二人とも後に引けない。梶原は、チビの赤塚をナメ切っている。「ハッケヨイ、ノコッタ、ノコッタ」の、女の子の掛け声で、二人は、ガッチリ手を組みあった。赤塚は、梶原にアッサリ勝ってしまう。テーブルの下で、梶原は赤塚のスネを、革靴で思い切り蹴った。次の日、僕は、青アザになった赤塚の足を見せられた。梶原は、クラブの勘定を払うのが嫌だったのではない。沢山の女の子の前で、チビに恥をかかされたことが許せなかったのだ。(「赤塚不二夫のことを書いたのだ!!」 武居俊樹)
結婚披露宴 数あれど…
結婚披露宴の様式は日本各地でさまざま。茶産地として有名な福岡県八女の茶問屋の、ご子息の披露宴に招待されたときだ。まずびっくりしたのは人の多さ。招待制で三百人以上はいる。町中の人間が出席しているような多さだ。次に、しおり。それ自体は普通だが、中にA3サイズの席順が折り込まれており、なんと出席者全員の会社名と肩書きが表示されている・。さて着席。テーブルには巨大なお重が鎮座している。こんなに食えないと思っていたら「お持ち帰り用」だそう。新郎新婦の入場、来賓のあいさつと式は進み、乾杯。と、出席者がいっせいにガタガタと席を立ち、猪口(ちよこ)と焼酎の入った銚子(ちようし)を持って式場内の大移動を始めた。座っているのは私のようなよそ者くらい。ほとんど立食パーティー状態である。この地方では、酒は相手の猪口に注ぐのではなく、自分の猪口を相手に渡し、それに焼酎を注いで「飲み干させる」しきたりらしい。かわいそうなのは新郎だ。ほぼ全員から次から次に杯を重ねさせられる。また、銚子を置いていくものだから、目の前は酒だらけの酒林と化す。この状態はお開きまで続く。お色直しで新婦が戻っても、人垣が通路をふさいでいるから入城できない。司会者がマイクで叫んでも知らぬ顔である。さてお開きで帰ろうとしたら、やっと席に落ち着いた出席者が「おい、さけもってこい」酒宴はこれからが本番らしい…。(「さしつさされつ」 中田耀子・土田裕之)
集団の性質と飲酒の習慣
社会人類学的観点からみると、集団における酒席を設けることの頻度、ならびに飲酒の効用は、集団の性質に相関関係があることが指摘できる。まず、集団の性質を、集団内の人間関係が非常に確定的というか、不変のものである場合とそうでない場合とに分けることができる。前者の例としては、たとえば、家族などをあげることができる。親子やきょうだい関係は変更する可能性のないものである。このような関係によって集団が構成されている場合には、その集団結合のためにお酒の席などを設ける必要はない。それに対して、親しい人も親しくない人も含み、昇進、定年、新入などによって構成員ならびにそのお互いの関係が可変的である職場のような集団では、酒席はその場合、よりよい人間関係のために効果をもつ。たとえば、相談事とか、特定の問題について同僚、部下などの意見をきき、意思疎通をはかりたいときには、「一杯やろう」というのが常である。また、従業員のための慰労、特別に集団成員の努力を表したいとき、また、集団内で気まずい問題が起こったとき、士気が沈滞したような場合、一席設けようということになる。このような日本の慣習によくあらわれているように、すでに集団成員となっている人々の間でよく酒の席がもたれるのでる。これに対して、アメリカでさかんに行なわれている「カクテル・パーティ」は、同じ職場の人たちももちろん入るが、殆ど例外なく、異なる職場の人々が招かれ、また、同じ職場の人たちが全部招かれるなどということは特別の場合でなければない。招待者を中心とした特定の人たちからなるもので、客人たちは、はじめてそこで知り合う。あるいは名前を知っていてもそこではじめて話し合うといった関係が非常に多い。また、カクテル・パーティの楽しみの一つは、新しい人と知り合いになるということである。アメリカで異常なほどにカクテル・パーティが発達したのは、やはりアメリカの社会生活のあり方、社会組織に密接に関係していると思われる。(「酒と社会」 中根千枝)
泉石老人(せんせきろうじん)
泉石(せんせき)は浪速(なにわ)の人、つねに好んで能くほくす。
ついきけばきたなし庭は梅だらけ
真白(まつしろ)に真四角なり蔵(くら)の月
奢(おご)られてまたわびらるる紙子(かみこ)かな
暁に乞食(こつじき)を見て、
ねればねそあのこもひとへ霜(しも)ひとへ
性つねに酒をたしなみて物(もの)に拘(かか)はる事なし。ある時(とき)酒がいふと端書(はしがき)して、
飯蛸(いいだこ)のいひとかたらむ身のむかし
ことわりなるかな。万年先生博物多識(はくぶつたしき)にして、書法(しよほう)にも達(たつ)せられしこと、その頃知らざる者なかりしとかや。俳諧はまたその緒余(しよよ)なるのみ。(「俳諧奇人談 族俳諧奇人談」 竹内玄玄一 雲英末雄校注)
◆蒸しがんも
油で揚げずに蒸して作る。あっさりとした味わいのがんもです。とろみのついたあんが、しっかりとがんもに絡まるので、薄味に仕上げましょう。電子レンジを使えば、調理がとても簡単になります。
【材料四人分】木綿豆腐四百グラム、卵一個、芽ひじき五グラム、にんじん十グラム、煮汁(だし汁カップ四分の一、砂糖大さじ二分の一、薄口醤油小さじ一)、枝豆のむき身(ゆでたもの)二十グラム、あん(だし汁カップ三分の一、薄口醤油小さじ一、砂糖小さじ二分の一、しょうが汁小さじ一、片栗粉小さじ一)
【作り方】①芽ひじきを水につけてもどす ②にんじんは短めの細切りにする。 ③豆腐は熱湯で軽くゆでたあと、ふきんに包んで水気をよく絞る。 ④小鍋にあんの材料を合わせ、中火にかけてひと煮立ちさせる。 ⑤分量の煮汁で、芽ひじきとにんじんを箸でよく混ぜながら、汁気がなくなるまで煮る。 ⑥③の豆腐に⑤と溶き卵、枝豆をよく混ぜ合わせ、四等分してラップを敷いた耐熱容器に入れる。ラップの口は加熱中に開かないようしっかりとひねって閉じ、耐熱カップごと電子レンジに入れ、約三分間加熱する。 ⑦ラップをはずして器に盛り、④のあんをかける。(「酒席に役立つ読む肴」 酒文化研究所編)
食と酒
はじめに神は人間に「食」を教えた。人間はそれをすぐに「酒にする」ことを発明した。人間が山野の動植物を食べて生きて来たのは本能に従って自然の美味を求めたためであって、これはいわば種族保存のための神の教えである。そこへゆくと酒のようなものの味は、猿という説もあるが、人間の力で造り出されたものであって醗酵という技術によって造り出したものである。これは糖分からエタノールというアルコールを微生物の力で造り、その糖分はカビという微生物や麦芽や唾液(だえき)の酵素の力で澱粉を消化して造るのである。近頃は新しい醗酵の数も次第に増えて、有機酸醗酵、アミノ酸醗酵、核酸醗酵、ステロール醗酵、アルカロイド醗酵、抗生物質醗酵、石油醗酵などとその数も数えきれないくらいである。そしてその用途も食物のほか広く医薬や工業上にも使われるようになり、その学問は世界各国の中でも日本など進んでいるといわれるようになった。その中でも酒類は世界の民族がいずれもそれぞれ特色ある酒を持っていて、めいめいが国の誇りとしていること、これは周知の通りである。(「愛酒楽酔」 坂口謹一郎)
懐風藻
大岡(信) そうでしょうね。それでいえば、「懐風藻(かいふうそう)」あたり、紀元でいうと七五〇年ぐらいですからね。八世紀半ばですけれども、「懐風藻」は漢詩だから非常に具合がいいんですね。和歌だと全然出てこない話題がいっぱいありますね。とくに大勢集まってみんなで酒盛りして、時には遊んで、闘草なんかをやって賭をして、草花なら草花で、一番美しいのを誰が提出するかというのでいろいろ闘って、最後に負けたやつは身ぐるみはがれちゃう者が出てくるという話も書かれているわけですね。それがみんな天平時代、大伴旅人あたりと同世代ですね。旅人も「懐風藻」に出ていますから。そういう詩を見ると、酒を集団で楽しんで飲んでいる。そして精神状態としては、自分は「聖代の狂生」、気のふれた人間である、「吾は聖代の狂生ぞ」と書いているわけですね。それを書いているのが藤原の麻呂ですからね。不比等の第四子で、光明皇后の兄さん、最高の貴族です。それがそういう詩を作っている。いい詩で、洒落ている。長い詩です。そういうのを見ると、日本人がうま味に敏感だというのも、長期の文化的な蓄積からだんだんうま味を知る感覚も育ってきているという側面があると思うんですね。吾は聖代の狂生ぞ、なんてのは、デカダンスの味です。八世紀が現代と通じるところがある。(「座談会 酒と日本文化」 大岡信、網野善彦、浅見和彦、松岡心平)
関矢さんのお酒の世界
これまでみてきた関矢さんのお酒の世界には、いくつかの特徴がある。第一には、それまでの日本酒が、造り手側からの発想でのみ歩んできたことに対して、逆に飲み手側からのお酒を世に出した点である。もちろんこれまでにも、いくつかの消費者ニーズに立った動きはあった。無農薬のお米で造ったり、市価よりかなり安い価格のお酒などがその一例である。しかし、ここで見てきたように品質はもとより、価格からラベルに至るまで総合的な取り組みを開始したのは関矢さんが最初である。今日的な言葉でいえば、お酒の世界におけるパラダイムの転換である。それだけの画期的な変化が、ここから始まったと言っても過言ではないだろう。第二には、お酒も日本文化の大切な一つであると同時に、他の文化やそれを支える人々を結ぶ要(かなめ)の役割があることを、関矢さん自らが実証した。どんな文化とも、お酒は接点を持つことができる。お米や祭りなどのように直接関わっているものもあれば、小説や和歌などに間接的に登場して、文学の世界を広げてくれることもある。そして人の輪も広げる思想信条や老若男女などの違いを越えて、お酒はその橋渡しをしてくれる。もちろんあくまでも橋の役目でしかなく、お酒をただ飲んでいたら他人との交流ができるわけではない。たまにはお酒の場でけんかをして、人間関係が悪くなったという話を聞いたりするが、別にお酒に罪があるわけではない。橋のかけ方がまずかったのか、かける相手を誤ったせいである。どちらにせよ飲み手である人間の問題である。(「お酒に乾杯! 関矢健二の世界」 西村一郎)
蔵癖、場所癖、容器癖
蔵癖(くらぐせ)とは、酒蔵に何らかの特殊な癖があることをいう言葉だが、一般には、品質のよい酒を造りにくい蔵のことを意味することが多い。-
このような酒母の早湧きの原因として最も多いのは暖冬だったが、気候条件とは無関係の蔵癖として、まず「場所癖」がある。伝統的な木造あるいは土蔵造りの酒蔵はいわゆる「重ね蔵」が標準の形で、通常、酒母やもろみを仕込む「大蔵(おおぐら)」は北側に面している。通常は二階建てで、二階で酒母を造り、一階でもろみの仕込みを行なう。もろみの発酵は発熱を伴うため、別々にしてあるわけである。さらに、大蔵の北面には窓が設けてあり、冷たい季節風を取り入れて室内を低温に保てるようにしてある。ところが、蔵の建築上の条件が悪くて北風が十分に入らないとか、酒母を育成している酛(もと)桶の近くの壁に釜場の熱が伝導しているといった場合は、当然、酒母造りがうまくいかない。このような場合を「場所癖」といい、その欠陥を特定できれば改善が可能だが、桶などの容器が原因になっている場合(「容器癖」という)や、原因が不明の場合も多かったという。(「日本酒 百味百題」 小泉武夫監修)
月見酒
この頃になると決まって憧れる状景がある。風が冷んやりとしてくる頃、場所は田舎。ほどほどに、ひなびた田舎がいい。ともかく庭のある縁側にアナタはひとり座っている。月明かりだけがぼんやりとあたりを照らす。そんな状景だ。やがて庭先から「よお!」という声がして、男が酒壜をヌッと出す。酒を持ってきたのだ。彼とアナタが縁側に並んで、月を見ている。塩とキヌカツギ。それしか肴はない。やがて酒をゆっくりとくみかわす。ススキが揺れる。月がますます冴えわたる。アナタはあまりしゃべらない。男もしゃべらない。時がゆっくりと過ぎていく。女は出てこない。なぜか、そういう状景なのだ。自分でもわからない。酒を持ってくる男。これが誰だかわからない。自分で酒を用意すればいいと思うんだが、必ず"男"が持ってこなくてはいけない。そして、庭先のススキの穂の間から男が顔を出し「よお!」といわなければいけない。昔の映画の中ででも、こんな状景を見たのだろうか。この季節になるときまってその状景に憧れる。アナタは、まだ一度もイメージ通りに日本酒を飲んだことはない。(「アナタの年頃」 永倉万治)
観戦記(3)
新東海新聞の人が私の為にお酒を持ってきた。手合が終わってから、暁方のむから、夕食の時にはいらない、と私はことわっておいたのに、先方が親切すぎて、ムリヤリ持ってきて、すすめる。今のむのは、私の方はつらいのだ。なぜと言って、てんで分りもしない将棋を、一時間二時間の長考のオツキアイをする、前晩もねていないから、ずいぶんゼドリンをのんでいるのだが、ねむくて、たまらぬ。酒をのんでは、尚さら睡くてたまらぬだろう。すると新聞社の人が、私に見切りをつけて、升田八段に湯呑みを差して、疲れを忘れますよ、一パイ、とすすめる。升田八段、私を見てクスリと笑って、「酒を飲みおって、不謹慎やと、坂口さん、観戦記に書くのやろうなァ」と、てらながら湯呑みを受けとって、酒をついでもらった。そこで私もオツキアイをして、少し飲む事になった。二合ぐらい飲んだようだ。木村前名人は私のゼドリンを五粒のんだ。前名人はゼドリンとかヒロポンという覚醒剤を用いたことがないのだが、汽車の中での話に、徹夜の時は、年のせいで、夜更けになると頭がぼやけてくるとこぼしたから、私がゼドリンをすすめた。私のように連用するのはよろしくないが、棋士の方は五日に一度とか、一週一度の手合であるから、連用にならず、害もすくないであろう。(「観戦記」 坂口安吾)
なまよひ[生酔]酔ッぱらい。(3)
㉓やむことを得ず生酔をしばるなり(樽二〇)
㉔生酔も祭のあとのにぎやかし(樽二三)(樽三〇)
㉕生酔はつぶれる時に店を出し(樽二八)
㉖生酔の手や足四ツ手拾ひこみ(樽三五)
㉗生酔の水千両に直(ね)がきまり(樽四三)
㉘生酔本性たがはず釣を取り(樽四九)
㉙生酔が来ぬと名もない桜なり(樽五六)
㉚生酔にぼん/\つらを乱すなり(拾一二)
㉛生酔に一ト理屈いふ阿呆者(拾一四)
㉜云ふことを聞かぬ生酔木から落ち(拾二〇)(樽一五)
㉝生酔はぶちころされるやうに寝る(傍 初)
㉞一人逃げ二人逃げ生酔とうた(同)
注㉓乱暴すると縛り上げる。 ㉔祭酒に酔って、いつまでも御機嫌。 ㉕酔いつぶれて小間物屋。潰れると見世開きとの反語仕立ての狂句。類句-生酔の大のきまりはへどを吐き(拾一九)。大喝一声小間物屋を開業し(逸) ㉖手も足も自由にならぬ酔いどれを拾つた駕屋。 ㉗酔覚めの水の美味さヨ。 ㉘酔つては居ても、取るものは間違わずに取る。 ㉙上野清水堂の裏にある井戸端の桜に題した大目秋色(しうしき)女の-井のはたの桜あぶなし酒の酔ひ、で有名になつた秋色桜。類句-井戸端の桜でお秋名が高し(逸)。吟じざめせぬ秋色の酒の酔(同)。 ㉚生酔が来て子供の遊びが乱されたこと。ぼんぼんは子供の関西語。つらは連らなることで雁の連(つら)などと云う。 ㉛生酔に理屈をいつてもはじまらぬ。 ㉜生酔のふざけ過ぎた木登り。 ㉝辻切りにでもあつたような有様。 ㉞相手になるものが次第に逃げ去つて彼一人とろれつの廻らぬ彼の歌だけが残る。(「古川柳辞典」 根岸川柳)
私の知っていた吟醸酒
まず私が昭和三〇年代から知っていた吟醸酒というのは、酒の品評会(その多くは鑑評会という)に出品する酒であった。酒蔵が名誉をかけてつくる酒で、ひたすら品評会入賞、さらに上位入賞を目指したものであった。私は蔵の設計をやっていたが、その顔でも分けてはもらえなかった。口にすることができるのは、蔵が品評会出品の準備をしているときにうまくぶつかり、杜氏さんが「飲んでみるか」といった時、それから国税局や醸造試験所で品評会結果公開のためのきき酒会に出かけた時である。こちらも若かったから、晴れがましいところできき酒に参加する度胸もできていなかったし、きき酒可能でも心落ち着けて味をきき分けできなかったのが実情であった。飲めないものとなると飲んでみたくなる。四〇年代に入ると、吟醸酒を市販する蔵が出てきた。蔵は吟醸酒を自社の最高品質と自負していたから、当時の級別制度の特級酒より上の税制区分で商品化した。それは蔵出し価格の一五〇パーセントの税が課せられるものであった。設計を担当していた米鶴酒造(山形)と二北酒造桃川工場・当時の社名(青森)が商品化した。前者が「米鶴エフワン」一七〇〇円、後者が「桃川大吟醸」一八〇〇円である。同容量の特級酒は五〇〇円ぐらいだった。設計の注文をもらったつきあいもあって、ケースで取り寄せて飲んでいた。蔵への支払いが年末には五万円を超して懐に痛く響いた。昭和五〇年に酒造組合が各所の酒の定義を決める。これは酒類全般にいえることだが、級別で酒税額や率は決まっていたが、原材料の中身やつくり方などは野放しだった。それに対し公正取引委員会が消費者保護のため基準を作ろうとしていた。酒造業界は公取委の基準作成に先んじて「原材料と製造方法の自主基準」を決めた。臑(すね)の傷をほじられる前に体裁を整えたのかもしれない。それには吟醸に規定もあった。(「「幻の日本酒」酔いどれノート」 篠田次郎)
玄い米で醸す純米酒
ところが近年では、精米歩合80%、90%など、あえて米を削らず、玄米に近い玄(くろ)い米で醸す純米酒も続々と登場しています。こういった酒は、味の幅のある酒になることから、飲みごたえがあると人気が急上昇中です。山田錦など上質な酒米を使うようになったことと、精米や醸造の技術がレベルアップしたこと、さらには種麹の改良により、魅力に転じることができたのです。さらに良いものを求めようとする日本の技術者の意欲には、頭が下がります。(「目指せ!日本酒の達人」 山同敦子)
解悶 憂さを晴らす 盧仝
人生都(すべ)テ幾日ゾ 人生は合計幾日ぞ
一半ハ是レ離憂。 その半分は苦労の世の中。
但ダ尊中ノ物有リ ただ樽中の物が有るばかり
他ヲ従(はな)テバ万事休ス。 あれ(酒)を手ばなしたら何も彼(か)も休(しま)ひだ。(「中華飲酒詩選」 青木正児)
茄子の田楽(米ナス、八丁味噌、ゴマ)
米ナスを半分のヨコ割りにし、すわりをよくするために、へた、頭の先を切る。天ぷら油を180度くらいに熱し、ナスのシンまでやわらかくなるように5~6分揚げる。フライパンにゴマ油をしき、揚げたナスをサッと焼く。ナスにゴマ油の風味がとけ合う程度に、焼きすぎないようにする。鍋に八丁味噌2,あたりゴマ1,砂糖3,みりんと酒を同量ずつ混ぜたものを入れ、弱火にかけて水でのばしながら煮る。焦がさないようにヘラなどでかきまわしながら、10分くらい煮るのがコツ。水あめが流れるくらいのやわらかさになったら火をとめる。ナスを器に盛り、田楽味噌をかけて、色どりに木の芽、はじかみなどをそえる。味噌の香りが漂い、思わず盃がすすむ一品。(「酒肴<つまみ>のネタ本」 ホームライフセミナー編)
某月某日 モツ焼き紀行、その2-鳥七(大井町)
本日は、パソコン関係の会社「アーキテクチャー」の社長・新野氏の地元・大井町へと楽しい遠征。目指すは「鳥七」(148)、ここに決まってまんがな。知名度は低いが、ご主人・池内さんの焼きの技は天下一品である。「モツ焼きは鮮度がすべて」と、その日に入荷したモツは、その日で終わり。焼くのは当然備長炭。注文を受けてから切り、串に刺す。圧巻は焼き方である。厳密に火加減を調整しつつ、炭火を上に持ってきたり、鉄鍋に入れた炭火で炙ったりと、ありとあらゆる手法を用いて焼き上げる(私の知る限り、こういう焼き方をするのはこの店だけである)。パーツによって焼き方が違うし、焼く途中で何種類かの液体を刷毛で塗るのも秘法。「中身は秘密」と笑う池内さんだが、「素材がいいから、あまり凝らない方が旨い」。こうして新鮮な肉汁と旨みが封じ込まれたタン、カシラ、ハツ、レバーを食べると、これ以上何を望むか、という気分になる。トマトのチーズ巻きほか野菜も豊富で、それぞれオリジナルな手法で調理される。池内さんは一見、無愛想に見えるかもしれないが、それは違う。背中を見れば分かる。全神経をモツを焼くことに集中しているのだ。「絶対に手を抜きませんから、私は」。何とも清々しい店である。値段の安さは言うまでもないが、最後に女将さんの笑顔と言葉のやさしさ、すなわち居心地のよさも付言しておきたい。(「東京居酒屋はしご酒」 伊丹由宇)
〇一休和尚の歌
世の中はくうて はこして 寝ておきて さて其の後は 死ぬるばかりぞ(一休物語に見えたり はこするはクソひる事なり はこは糞筥(くそはこ)なりしのはこと云ふなり
又是をまるとも云ふ 丸く細長き故なるべし)げにも人の一生は食うてはこしてねて起るより外の事なし 此の事たやすくなりがたき事故 君につかふる人も有り
士農工商各其の家業を勤むるは 食ひてはこして寝て起きて 畳の上にて死ぬべきが為なり 然るに君にもつかへず 家業にもつとめず 手足を動かさず 人の実を目当にして好色大酒博奕して一生をおくらんとするものは
道路に倒れ死するか獄屋の前にて死するかなるべし(「安斎随筆」)
水戸黄門光国卿示ス二家臣ニ一条例
時頼(ときより)は其比(コロ)天下に執権にて、ケ様の無造作にして身の栄耀(エイヨウ)なき振舞(フルマイ)是(コレ)に過たる事や候べき。比類(ヒルイ)なき殊勝(シユシヨウ)の儀に候。時頼程の人にケ様のために異国にも不ルレ及バレ承リに候。土器に付キたる味噌をなめて酒を呑(ノム)やうの事は、今の世には下臈(ゲロウ)さへ不セザルレ仕事に候得ば、まして少しの所帯を持チ候者、思ひもよらず候。少し有(アル)酒を呑(ノマ)んとて早くも思ひ付キて呼(ヨバ)れしを、宣時(のぶとき)も嘸(サゾ)嬉しく可レ被レ思ワ候。惣じて物を送り候にも、振舞候にも、不図(フト)思ひ付(キ)て手軽く致シ候こそ誠の志(ココロザ)しは顕(アラワ)れ候。こと/"\く取繕(トリツクロ)ひたるは、軽薄とも見へて不二面白カラカラ一候。友達の交(マジワ)りは唯(タダ)礼儀正しく、しかもおのづから親(シタシ)みの有様(アルサマ)こそ幾度(イクタビ)もあかぬものにて、宣時が夜ともいわず直垂(ヒタタレ)を取リ求メしを、遅きにてはや推計(オシハカ)りて、其儘(ソノママ)参られよと言(イイ)おこせられし、其比(コロ)の風俗仮初(フウゾクカリソメ)にも左方の正しき事をしりぬ。亦時頼のい銚子土器自身に持出(モチイデ)られしこそ、是に過たる馳走やあるべき。扨(サテ)なへたる直垂着(ちやく)して、土器の味噌をなめし宣時が有様(アリサマ)、たぐゐなくやさしく覚へ候。人のしづまりぬるを起さざりしも、下(シモ)をいたわりしありさまに候。土の交(マジワ)りは今迚(イマトテ)もケ様に有度アリタキ)ものに候。(「家訓集」 山本真功) 北条時頼の酒
漱石の酒句
新酒売る家ありて茸の名所哉
放蕩病に臥して見舞を呉れといふ一句
酒に女御意に召さずば花に月
酒菰の泥に氷るや石蕗の花
送子規
御立ちやるか御立ちやれ新酒菊の花(「漱石全集」)
酒を温むべし
安政五年(一八五八)十二月十五日、小楠は竹崎律二郎・河瀬典次の二人をしたがえて越前藩士由利公正・榊原幸八・平瀬儀八の三人をともなって帰国の途についた。この旅行について由利公正は、「さて道中で、先生のわれにことさらに注意せられた忘れられぬことがある。宿へつくと一統をよばれて言はるるには、いづれも雪中でつかれたらう。早く食事を仕舞うてぢきに寝るから手配りせよ。おのれは酒は呑まぬと言ひつけられたゆえ、みなみな早々風呂に入り、食事したが、早々寝るべしと言ふことで床に入ると、しばらくして三岡(みつおか 公正の初姓)と呼ばる。われ前にでれば、曰く、酒を温むべし手配せよと言はれて、それから講習せられて夜半をこえた。大坂にいたるまで毎夜同様のことで随分つかれもしたが、その親切は実に厚いことであつた」(『由利公正伝』)というエピソードを記している。由利にたいする小楠の期待のほどを知りうるひとこまである。(「横井小楠」 圭室諦成)
茅台酒
中国の酒には、米・小麦・コ-リャン・豆類・トウモロコシなどを原料とする白酒と、もち米・キビなどを材料とする黄酒の二系統があるが、白酒で有名な茅台(まおたい)酒には、こんな故事来歴がある。清代の初めごろ、西鳳酒の本場の陝西省鳳翔県の塩商人が、行商の途中貴州仁懐県茅台鎮を通って、ここの景勝が気に入り足をとめたが、銘酒がない。そこで茅台鎮を流れる赤水河の水を使って西鳳酒の製法で酒をつくったところ、山西省汾陽県の<汾酒>に似た味のものができた。汾酒の原料がコーリャンであるのを思い出した彼は、今度は汾酒の製法でつくってみたところ、すばらしい味の酒ができた。やがて、この酒はしだいに評判になり、名酒の茅台酒として知られるようになったという。一九三五年一月、中国紅軍が名高い長征の途に出て、ここを通ったとき、酒のいけるものは心ゆくまで酔い、飲めないものは酒で足をこすって、急行軍の疲れをいやしたというエピソードがある。(「世界風俗ジテンⅡ」 矢島文夫外)
死の行軍
いちばん最近で忘れられないのは、名古屋でまる二日にわたるTVロケがあり、その一晩目の夜のこと。宿泊先のホテルで偶然ばったり(まさかおあつらえむきにそんなコトが起きるわけがないと思う方は、充分勘ぐって下さい)ちょいとオカ惚れした男と出会い、階上のバーでさしつさされつ痛飲してしまった。さぁもうどういうことになったのか、あとは闇夜の二日酔い。目ざめるとちゃんと自分の部屋で寝ていて、当然ながら送ってくれたはずの男の姿はない。おぼろ気にアゲタリサゲタリ(下着のことにあらず)した覚えはあって、洗面所の前にパンタロンスーツのズボンが脱ぎ捨ててある。みるとこいつが昨夜の不始末の名残りで、シミだらけの皺くちゃ。とても穿(は)けたものじゃないからあわててルームサービスを呼び、クイッククリーニングを頼んだ。モーローとしているところへTV局の人から電話がかかり、「エー、先生そろそろロケバスが出ますが、お支度の方ハよろしいでしょうか」「あの、それが」「なんです」「ズボンがないんです」「ヘッ、ズボン…}相手は一瞬絶句して、そりゃどういう意味ですと恐る恐る尋ねたが、説明のしようもない。前日の撮影の続きで下だけが変わっては、絵にもサマにもならない。やむなく上半身のみを映す急場しのぎで切りぬけたが、あっちのジューススタンド、こっちの自動販売機と二日酔いの渇きをいやす飲みものを探しながらの撮影は、ほとんど死の行軍だった。おまけに念願かなってあの男(ひと)とひとつ部屋に籠った一刻、いったい何があったのやらなかったのやら。なんだか耳たぶが痛いので触ってみると少々噛まれた跡があったけど、こういう顛末こそ、ぜひともはっきりした意識で覚えていたいものである。えらく損した気になったが、要するに普段飲めないものがたまに酔っぱらうとろくなことがないという証。以後謹んで、あれから何年たつことやら。(「男はオイ!女はハイ…」 山口洋子)
【地口】
地口は、よく知られたことわざや有名文句をなぞり、音通により洒落のめした言葉遊びの江戸語である。[ ]内は出典名。
畦(あぜ)は御酒(みき)連れ菜(な)は畑[神事行灯]←旅は道連れ世は情け
甘酒屋四銭(しせん)飲みます[駝酒落早指南]←山崎屋紫扇の三升(みます)
いいのを五合(ごんごう)酒呑には少ない[同右]←神功皇后武内宿禰
一座々々の散財が大分(だいぶん)めぐる酒(おつと)の気[同右]←吉三々々の三人が太鼓にめくる三つ巴
いつもうまいは妻と酒盛(さかもり)[行灯地口語呂合]←幾夜ねざめの須磨の関守
お酒の勘定[地口絵手本]←お釈迦の誕生
お酒の燗もちやんと[地口絵手本]←仏の顔も三度
面白機嫌の茶椀酒[同右]←落とした煙管のたたみざん(「日本の酒文化総合辞典」 荻生待也)
のめどもつきぬ【飲め共尽きぬ】
謡曲「猩々」の詞句。切地の『秋のしらべや残るらん』の下に『くめども尽きず、飲めども変らぬ』とある。
瀧水は 飲めども尽きぬ 和泉町 四方の銘酒瀧水
おい癌め酌みかはさうぜ秋の酒
この日から、八月一日、二日と小康を保つが、三日ごろから再び肺炎が悪化、例のブロンコの世話になるハメとなった。息苦しさが募り、あれほどいやがっていたブロンコのあとだけ、多少呼吸が楽になった様子だと勢津子はいう。しかし、こうした苦しみの中でも意識ははっきりし、筆談で訴えることの内容も明確なら、字もしっかりしていた。医師や看護婦に見せるメモの末尾に<嗄声(しやがれごえ)>と書くなど、ユーモアも相変らず。-そして、句も。 八月五日夜-
やよ酌(く)めよ冷(ひや)も吟(ぎん)もなき通夜の酒
あすをだれが予見できるか原爆忌
八月七日、多摩川花火の夜(毎年、この日に江國は親しい編集者などを自宅に招き、賑やかな酒宴の中で花火を見物していた。快気祝いを行なう目標の日だった)-
氷ふふむ快気祝ひの夜なりしに
そして八月八日金曜午前二時、ほかに誰もいない病室で、辞世となる句を「慶弔俳句日録」用の原稿用紙の裏側に書き付けた。敗北宣言
おい癌め酌みかはさうぜ秋の酒-
一九九七年八月十日、午後七時三十五分、江國滋は六十二年と十一カ月余の生涯を閉じた。(「おい癌め酌みかはさうぜ秋の酒」 江國滋)
節税酒
サッポロなどの節税ビールに次いで、サントリーが節税ウイスキーを発売。複雑な酒税法を逆手に取り、原材料比率や製法を変えることで税率を下げ、低価格を実現。(「平成新語流行語小辞典」 稲垣吉彦)
463 えっ?
巡査が、酒場から千鳥足で出て来た男に、「おい君、酔ってるな、歩いて家へ帰れまい?」「歩いたりしないよ。オートバイがあるんだから」(「ユーモア辞典」 秋田實編)
わかれのおみき
身内の者がなくなった場合には、生き残った者がこれに対して食い別れの式をする葬送の出棺時のデタチの膳というのがそれで、一杯きりの飯を食ったり、一本箸で食ったり、わかれのおみきといって椀の蓋で酒を飲んだり、ふだんは決してしない食べ方で死者のまわりで食事をして、今まで同じ火で炊いた同じ鍋の飯を食った死者に対して、もはや共食者ではないことを宣言する。(「食生活の歴史」 瀬川清子)
製造石数半減
〇昔は江戸にて多く酒を造りて、下り酒はなかりし。「寛文八年(1668)戊申(つちのえさる)九月、当春御改被成(なされ)候通、町中酒屋共酒造り申石高半分之酒桶に、来る廿日より焼印被仰付(おおせつけられ)候」。「寛文九年(1669)己酉(つちのととり)正月十四日、帳はづれの酒屋来月昨日より改之者遺し、少し共所持候はゞ酒道具共に取上、其身曲事(くせごと)可申付(もうしつくべく)候。勿論請酒も帳はづれの者共、向後(きようこう)商売可為無用云々」。「天和元年(1681)辛酉(かのととり)十一月、此度御焼印申請候桶数に造り込可申(もうしべく)候。石高書上可申候。御定之外一切酒為造申間敷候」(かゝりしかども、後には家資乏きのみにもあらずして、増酒をやむる者多かりしは、売れざりしか、利すくなかりしか)。(「嬉遊笑覧」 喜多村筠庭 長谷川外校訂))
疲労が極度に達しているとき
仕事で遅くなり帰宅し、疲労が極度に達しているときは、とにかく早く寝ること。食事はできるだけ軽くして、酒もまったく飲まないほうがよい。胃腸や肝臓などに負担をかけないことを考えるべきだ。それ以上身体を酷使しないようにする。身体を軽く保つことを忘れてはならない。疲れたときや疲れてはいけないときは、酒を飲まないことである。(「酒を味わう 酒を愉しむ」 山崎武也)
小玉
私は<小料理屋>というジャンルに一番ぴったり合う食文化圏は関西だと感じる。出汁がよく出ているおばんざいや、おいしい絹豆腐を主としたつまみなど、考えるだけでも新幹線に飛び乗りたくなる。関西の飲食文化を語るとき、どうしても京都と大阪の対立構造が話題の中心となり、神戸はおき去りにされがちだが、魚も地酒も旨い兵庫県だけに見逃せないと思う。とはいえ、神戸はまだ「小料理」と名乗る店には入ったことがない。その代わり、愛媛県今治市で、神戸出身の女将さんが営む小料理屋「小玉」に行った。そこはまさに関西風の上品なおばんざいを中心に味わえる店だった。いまだに忘れられないのが「小玉」で食べた鯛かぶとの煮付けである。瀬戸内海のごく新鮮な鯛の頭を必要最小限の味付けで出されたのだが、一口食べたら、後は夢中で貪るばかりだった。一片も残したくない貪欲さに駆られ、黙々と箸でつつき、骨をしゃぶり、たまに感動のあまり唸(うな)っていたようである。案内してくれた地元の呑み友が隣に座っていることもすっかり忘れ、猛烈に集中して食べていた。店を出てから呑み友が「あの鯛が来てから、一言も喋らなかったよ。二、三十分も喋らなかったんじゃないか」と繰り返していたから、相当に呆(あき)れていたらしい。(「日本の居酒屋文化」 マイク・モラスキー)
此君盃(このきみかさかずき)の記
道中双六のふり出しなる橋の辺(ほとり)にすめる月知とかやいへる人、四方赤良が書おける七賢図式を見て、ひとつの盃をおくれり。盃中に竹をゑがく。よりて名づけて此君といふ。それ盃はさま/"\ありて、羽觴(うしやう)、玉爵(ぎよくしやく)、あうむ盃、きんくし(金屈巵)など、見ぬもろこしの京物語にて、其かたちをだにわいだめず。我日のもとのいにしへは、「氵于」尊杯飲(うそんはいいん)の風すなほにして、かはらけのみもちひたり。されば、三ッ組のみつ指にて、左様しかればの挨拶も、候べく候のべく盃となり、引に引かれぬ引盃は、さいつおさへつあいの手もとに、入りくる/\大盃、百薬のてうどうけて、椰子の毒けしをたのみ、しつぽく台の一ッの隅をあげて、こつぷを三ッのすみにめぐらす。何某院の黒木の詠は、大原盃の製をのこし、難波江のうかむ瀬も、浅草川の淵と変ず。たとひ時酒うつりうまごとさり、たのしみかなしみゆきかふとも、天さへ酔へるはなの朝、あたまもふらつく月の夕、雨のふる日も月の夜も、日々酔て泥のごとく、一年三百六十日、一日も此君なかるべけんや。
此君は いずくよりぞと とふたれば わらつてこたへず 心かんなべ
君ならで たれかはくれん くれ竹の 色をも香をも さか月ぞしる(「四方の粕留」 大田南畝)
福光屋
石川県の「福光屋」は創業一六二五年(寛永二年)の造り酒屋である。伝統的な製造工程を踏み、手間をかけて嗜好品としての清酒作りをかたくなに踏襲してきた。しかし、食生活の多様化や食文化の成熟化によって消費者のお酒に対するし嗜好が変わりはじめたことで、ここ一〇年来、清酒の市場規模は横ばいから減少傾向にあり、老舗の酒造会社としてあぐらをかいているだけでは、今後も生き延びて行ける状況ではなくなってきている。このような背景のもとに、「福光屋」は経営の転換を図っている。ポイントはターゲットセグメンテーションによる商品開発とそれに伴う製造工程の見直しである。従来の熟練した杜氏や蔵人の技術に裏づけされた嗜好品としての清酒と、マスマーケットを対象にした低価格量販品を両輪として商品戦略を展開している。ここで注目されるのは、杜氏、蔵人を社内で育成しているということである。従来、地元農家の農閑期に季節労働契約として杜氏、蔵人を採用していたが徐々に社内人材への伝統技術の移転をはじめ、高コスト体質の改善を図っている。"社員蔵人"の誕生である。現在では、醸造部門の五〇人のうち半数以上が社内蔵人となっており伝統技術の社内蓄積が着々と進み、高品質低価格商品の実現にいたっている。つまり、熟練した「杜氏」「蔵人」から市場変化に合わせた商品作りのために社員が伝統技術を引き継ぎ、知識として時代への新たな対応を実践しているのである。(「老舗企業の研究」 横澤利昌編著) 平成12年の出版です。
二〇、食べて毒なもの
もし飲食して後、何物の毒、心煩4・満悶するかを知記せざれば、急ぎて苦参(くしん)5の汁を煎じて飲み、吐出せしむ。あるいは犀角(さいかく)の汁を煮てこれを飲み、あるいは苦酒6・好酒7もて煮て飲むも、みな良し-
菱角11を食ふこと過多にして、腹脹(は)れ、満悶なるときは、温かき酒に薑(はじかみ)を和し、これを飲むべし。すなはち消ゆ。-
馬肉を食ひて毒に中るは、杏仁16を嚼せば(かめば)すなはち消ゆ。あるいは蘆根17の汁及び好酒もみな可なり。
④心煩=心が煩わされる。 ⑤苦参=草の名、くらら ⑥苦酒=酢 ⑦好酒=美酒 ⑪菱角=ひしの実 ⑯杏仁=あんずの核の中の肉(薬用にする)。 ⑰蘆根=あしの根(薬用にする)。(「食経」 中村璋八、佐藤達全訳注)
肥後の赤酒
熊本に今もわずかに残る「肥後の赤酒」も有名な灰持酒(あくもちざけ)で、正月とか冠婚葬祭に用いられてきた.原料は糯米(もちごめ)、粳米(うるちまい)、麹、大麦、麦芽、木灰であり、普通の清酒と同様に酒母(しゆぼ)をつくり、添(そえ)、仲(なか)、留(とめ)と3回に分けて仕込みを行う.汲水歩合は60%前後とかなり濃厚仕込みである.約2週間醗酵の後に搾り、沪過を行うが麦芽は最後の留仕込みの時に加え、木灰は酒を搾る直前に加える.淡黄赤色で甘味が強く、粘稠な酒で、アルコール分10~18度、アルカリ性を呈する濃厚甘味酒である.今も熊本地方にわずかに残されているのは嬉しいことである.なお、この酒のように、東洋の酒文化の一大特徴である麹と、西洋のそれである麦芽との双方が、期せずして一つの容器の中で醸(かも)されるのはたいへんに珍しい例であろう-.
イトマと聖者バミバ
それからイトマは米から酒をつくったが、それは神の飲物である甘露(アムリタ)のようで、百のうま味があった。イトマは聖者(バミバ)が服用している丸薬をこの酒に浸して捧げた。聖者が一つの丸薬を口に入れてみると、それは百のうま味を生じていた。聖者はすべての丸薬を食べ、酔ったようになった。それからイトマは、着飾って装飾品を身につけ、米の酒を手にとって聖者のもとへ行くと、聖者はイトマに恋してしまった。しばらくして聖者が米の酒の酔いから醒めると、彼がしらふだった時に予感した行為をしてしまったことに後悔したが、しかしそれはもう起こってしまったのだった。聖者は考えた。「わたしはまだわたしの見識と本質を失っていない。わたしは誓約と大乗の本義を理解する輩(ともがら)として、衆生を除外するような矛盾した因縁に就くべきではないのだ。小乗の教えと自戒は、ただ成仏の因としてのみ正しかった。仏となるために真に受け入れるべきことは、まさに第三灌頂(楽と空の統一をもたらす無上瑜伽(むじようゆが)タントラにおける四灌頂の第三、すなわち般若智灌頂。般若[智恵]として受け入れる乙女との性交を通じて菩提心を上昇せしめ、それを菩提そのものとしての心、つまり悟りの智恵へと変容する行法)だったのだ。-
それから偉大なる聖者は自らの髪を編んでつくった二本のロープをイトマに与えたが、それはそれぞれの長さが九尋あり、太さがナスの茎ほどのものであった。聖者は言った。「おお、法統を継ぐ娘よ、自信を持ちなさい。堅固な信をもって婆羅門イェンラクタリンのもとへ行き、彼に教えを求めなさい。」(「ユトク伝」 中川和也訳)
居酒屋の披露宴
いろいろ溜(たま)っている『本の雑誌』の打ちあわせのために目黒考二と新宿の「梟門(きようもん)」へ。オリオンビール以外の生ビールをのむのは久しぶりだ。冷や奴、太刀魚の西京漬、特製コロッケ、イカソーメンなどを脈絡なしに注文。しばらく南の島の直射日光の下で暮らしていた体にクーラーのきいた新宿の薄暗い地下酒場は、かなりの異次元空間であった。その日は団体予約が入っていてどうやらそれは結婚式の二次会らしい。そうかうるさくなるんだろうなあ、とやや気持ちをヒルませつつ、生ビールをさらにあおった。団体の予約が入っているので店の中の八わりがまだあいたままだ。だから新宿のその場所のその時間にしてはおそろしく静かな状況だった。嵐の前の静けさというようなものだろうか。団体が入ってくる前の小一時間で生ビールを飲み、そのあと別のところへウイスキーでものみに行こうか…と二人で話していたのだが、いったん落ちついてしまった腰を持ちあげるのは、けっこう決断力がいる。間もなくその予約団体の人が店に入ってきた。なんとなく予想していたトレンド派手度八七%態度音声うるさ度七九%軽薄度九二%程度の若い男女サラーリーマンの群、というのとはちょっと違って、老若男女地味派手平均混合の割合静かめの一団であった。「文学座の人たちです」店のマスター今井ちゃんが教えてくれた。「ああ、なるほど…」ぼくと目黒はなんとなく頷いた。しかしなにが「なるほど」なのか、当人たちもわからない。間もなく判明しておどろいたのはそれが結婚式の二次会ではなく、どうやら結婚披露宴そのものであるらしい、ということだった。新宿の地下居酒屋での会費制の結婚披露宴…。親がかりの金銀キラキラ七色イルミネーションギラギラバカ派手の低能リッチ狂乱結婚式が氾濫している中で、このいかにも質素な披露宴はやがて静かに生まじめにはじまった。-
ゆまり彼らのそばで我々は我々のこみいった話を続けていられる程度の、それはきわめて落ちついた大人の宴であったのだ。-
-その日の文学座の結婚式は我々のまだのみ続けている間におひらきとなった。早めに解散、その場で二次会という段どりのようであった。帰りぎわ、その座を代表するようにして文学座の加藤武氏が「お騒がせを…」と挨拶していった。最後まできっちり大人の技を見せてもらい、ぼくと目黒は「これもあれも学ばねばいけない」とまた深く頷きあったのである。(「おろかな日々」 椎名誠)
正宗の一合壜
先ず甲州に入り、次いで信州に廻ったところ運わるく小諸町で病気に罹つた。そして其処の或るお医者の二階に二ヶ月ほども厄介になつてゐた。出立早々病気に罹つた事が、いかにも出鼻を挫かれた気持ちで、折角企てた永旅もまたイヤになつて東京へ引返して来、当時月島の端に長屋住居をしてゐた佐藤緑葉君の家に身を寄せた。初冬の寒い頃であつた。或日彼の細君から「若山さん、二円あるとお羽織が出来ますがねエ」と言つて嘆かれた事を不図(ふと)今思ひ出した。その前後であつたのだらう、北原白秋君の古羽織を借りたが借り流しにしたかの事も続いて思ひ出されて来た。それから再び『創作』の編輯をやることになり、飯田河岸の、砲兵工廠の真向ひに当る三階建の古印刷所の三階の一室を間借して住む事になつた。あのどろ/\に濁つた古濠の上に傾斜した古家屋の三階のこととて、二三人も集まつて坐りつ立ちつすればゆらつくといふ危険千万なものであつたが-実際小生が其処を立退くと直ぐその家は壊されてしまつた-その時はさうした変なところが妙に自分の気持ちに合つてゐたのだ。その前後が最も小生の酒に淫(いん)してゐた頃で、金十銭あれば十銭、五銭あれば五銭を酒に代へ飲んでゐた。イヤ、それだけでなく帽子が酒になり、帯までもそれに変つた。さうしてその頃小生の詠んでゐた歌は次の様なものである。
正宗の一合壜のかはゆさは珠にかも似む飲まで居るべし
わが部屋にわれの居ること木の枝に魚の棲むよりうらさびしけれ-
あゝした落ちつかぬ朝夕を送つてゐながら斯ういふ小綺麗な歌ばかりを詠んでゐたといふことが今から見るといかにも滑稽の感を誘ふのである。(「貧乏首尾無し」 若山牧水)
八海山
酒の名前の「八海山」というのも、浩一さんが酒造りを始めてからつけた名前というこんだ。蔵のすぐ近くに八海山があるから、そういう名前にしたんだわ。八海山は昔から修験道(しゆげんどう)の山でもあるし、有名な山だすけ、酒の名前としてはうってつけだいね。南雲家は代々の地主で、浩一さんの息子で八海山の酒蔵を引き継いだ和雄(かずお)さんから聞いた話では、浩一さんは人望があった人だそうだ。新潟県の県会議員をしていたこともあったぐらいで、政治が好きだったようだが、酒蔵を始めた頃には、県会議員もやめて酒造りに一生懸命になっていたというこんだ。酒蔵の他にも、地元で小さな水力発電所の事業をしたり、農業会の会長をしたりして、なかなか力のある人だったんだわ。その浩一さんが昭和二十八年に亡くなって、その後、奥さんの、カウさんという方がしばらく社長をなさっていたが、昭和三十五年に和雄さんが社長に就任し、その和雄さんも平成十二年に社長を退(しりぞ)いて会長となって、和雄さんの息子の二郎さんが社長になったというのが、これまでのいきさつだわ。残念なことに、和雄さんは平成十二年に亡くなられてしもうたがの。おらがこの蔵に来たのは昭和三十四年だから、ちょうど和雄さんが社長になった頃ということになるわいね。今は三万石(ごく)の酒を造るようになったが、その頃はほんとに小さな蔵で、造り石数(こくすう)も五〇〇石(こく)か六〇〇石ぐらいのもんだったわ。(「杜氏千年の知恵」 高浜春男)
「酔郷記」仮に終2
我(われ)幾本の酒に乱れて心たしかならず、そゞろに筆を取つて書出(かきだ)せし酔郷記(すゐきやうき)。さめての後(のち)に是(これ)を見るに恥かしや篇中の人物他所(よそ)にあらず、机に向ひて我しらず管(くだ)を巻(まき)し昨日(きのふ)の我なり。此(これ)に一念むか/\として懺悔(ざんげ)起るを如何(いかん)ともせん方(かた)なく、讀賣新聞(よみうりしんぶん)睨みつめて太き息つくばかり。流石(さすが)にあさましき物語りの後(あと)書(かき)つゞけん勢(いきおひ)は、日頃痩我慢(やせがまん)の強きに頼(たのみ)ながら我慢し難し、何として第三人第四人第百人まで記し得んやと、当惑の頭脳(あたま)の中麻(あさ)の如く縺(もつ)れて掻(か)き捌(さば)きたきやうなりしが、此処(こゝ)の苦しさ忘れたく又飲むや数陶(すうたう)の酒、酔(よう)て前後なく苦楽をしらず眠り臥(ふ)して、三更(さんかう)忽ち眼さむれば飲(のみ)たき水。起出(おきいで)て一椀(いちわん)の冷水(れいすゐ)を尽すに歯の根痛く覚えて腹具合(ぐあひ)あしく、夜着(よぎ)引被(ひつかぶれ)ど其(その)後(のち)眠り難く、四辺(あたり)を見るに小机(こづくゑ)ゆがみて書巻狼藉(らうぜき)を極(きは)め、灰吹(はひふき)の倒れかゝりたるは何時(いつ)の間にか脱捨(ぬぎすて)し袴と共に片隅にあるなど、見るさへ物うし。あまりの取散(とりちら)しに少し愛想(あいそ)つきてあらましをかたづけ、又寝るに寝られゝばこそ。(「酔郷記」 幸田露伴) 「酔郷記」を擱筆するに際しての文のはじめです。 「酔郷記」仮に終
凝りに凝った焼き豚
しかし、私が凝っているのは日本流の焼き豚です。これが、凝れば凝るほどのめり込んでいって、もうこのところどっぷりと焼き豚に染まってしまって、トンと足を洗えないほどです。凝りに凝ったそのつくり方ですが、フライパンに油を引いて、粗くつぶしたしょうがとにんにく各五片、五センチほどの長さに切った長ねぎ五本を入れて、キツネ色になるまで炒(いた)めます。次ににんにくなどはフライパンに残したまま、太い棒状に切った脂肪(あぶら)実の多いロース肉(だいたい長さ一七センチ、直径六センチぐらい)を一本ジャーッと放り込み、肉の各面に火を入れて表面を白く固めます。肉の全面が白くなったらば、あとは弱火でじっくりとフライパンの上で各面に火を加えながら、全体がキツネ色になるまで焼き上げます。次に肉やねぎを鍋(なべ)に移し、醤油(しようゆ)五合、日本酒二合を入れ、コトコトと弱火で一時間ぐらい煮込んで、出来上がりです。焼き豚の端の方を庖丁で薄くそぐように切り取って口に入れてみます。飴(あめ)色になった脂肪身がブヨブヨとしながら、口の中でチュルチュルと溶け出して、奥の深いコクが味わえます。(「ぶっかけ飯の快感」 小泉武夫)
思いをはらすために 羅隠 前野直彬訳
得意のときは大声でうたい 失意のときはやめて
憂愁も悔恨も いくらあろうと知らぬ顔
今朝酒があれば今朝のうちに酔おう
明日(あした)愁(うれ)いがおこれば明日愁いたらいいのさ(「酒の詩集」 富士正晴編著)
相手の左側
悪酔いの原因は、アルコールが体内で代謝(たいしや)してできるアセトアルデヒド。この濃度が、〇・五ミリグラム以上になれば、悪酔い状態になる。これを防ぐには、肝臓の処理能力を高め、アセトアルデヒドをさらに分解。できるだけ、アセトアルデヒドの血中濃度を高めないことが大切なのである。一方、カウンターで相手の左側に座れば、会話するためには、体を右にひねることになる。すると、肝臓につながる部分の脊髄(せきずい)が刺激され、肝臓の処理能力が活発になる。つまり、その状態なら、アセトアルデヒドの濃度があがらず、悪酔いもしないというわけである。(「酒場で盛りあがる 酒のこだわり話」 博学こだわり倶楽部編)
ドリンク・デスマッチ
絵を描いた中城健は、梶原とは『キックの鬼』以来の付き合いで、この他に『紅の挑戦者(チヤレンジヤー)』『四角いジャングル』などのコンビ作品がある。梶原にもひけをとらない巨漢で、酒も強い。生前の梶原と最も深く交流し、また対等の立場で話ができた希有(けう)な漫画家だった。-
『週刊サンケイ』の編集者を交えた酒席。何かで怒った梶原が、その編集者に本気でヘッドロックをかけた。編集者は涙を流して許しを乞うているのに、梶原はやめない。仲裁に入った中城は言った。「もうやめろよ。俺がオトシマエつけてやるから」オトシマエとは、酒のデスマッチだった。まず、銀座で朝まで飲む。次に赤坂に移動し、すでに閉店しているクラブを強引に開けさせ、専属のバンドも呼ばせた。時刻が正午を回っても、まだ飲んでいた。初めのうちは下世話だった話題が、酔うほどに真面目(まじめ)なものになっていった。中城は、梶原が真剣な表情でこう叫んでいたのを記憶している。「いつか俺は、人間の"死"を書きたいんだ」ドリンク・デスマッチは結局、午後三時まで続いた。先に酔い潰(つぶ)れた中城は梶原の膝枕(ひざまくら)で眠り、背負われて店を出たという。(「梶原一騎伝」 斎藤貴男)
居酒屋は社会をうつす鏡
格差拡大が進行していた一九九〇年代後半から、日本の居酒屋に異変が始まった。高級とはいかないが客単価が五〇〇〇円を超えるような居酒屋へ客が来なくなり、どんどん閉店していった。これに代わって、かつては労働者や年金生活者、貧乏学生などが集まっていた格安の居酒屋に、背広を着たサラリーマンや、通勤着を着たワーキングウーマンが集まるようになった。そして、労働者の姿は消えていった。格差拡大とともに、居酒屋の風景が変わった。サラリーマンやワーキングウーマンなど中間階級の人々は、小料理屋やレストランを敬遠して大衆酒場へ向かい、労働者階級は姿を消す。居酒屋は社会をうつす鏡であり、社会の変化を敏感に反映するのだ、と。(「居酒屋の戦後史」 橋本健二)
酒袋
輝く太陽の下、馬と芝の匂いをたっぷり嗅ぎながら、この酒袋からワインを飲む自分の姿を想像して、思わずにんまりした。特にその年は、あのハイセイコーがダービーに出走するというので、張り切っていたのだ。とりあえず水を詰めて、試してみることにした。胃袋でいうと、ちょうど食道につながる部分に、黒いプラスチックのネジ式の蓋がついている。ここから酒を入れる。その蓋の上部にさらにもうひとつ、やはりネジ式のキャップがついていて、これを外すと小さな穴があいている。ここが酒の出口で、つまり蓋が二重構造になっているわけだ。水を入れてみて驚いた。ぺしゃんこの時には想像もつかないほど、大量に入るのだ。それもそのはず、一リットル半といえば、普通のワインの二本分に当たるのだから。ずしりと重味が、肩にくいこんでくる。あの『日はまた昇る』によれば、この重い酒袋を腕いっぱいに伸ばして高くかかげ、革袋を手でぎゅっと締めるとある。すると、ワインは勢いよく大きな弾道を描いて口に入り、なだらかに、規則正しく飲み続けられるという。ところが、読むとやるのとでは大違い。まったく弾道が定まらない。中身の量や袋の締め具合で、まちまちの弧を描く。顔じゅうどころか、たちまち上半身が水びたしになってしまった。訓練あるのみ。そう決心して、ダービー当日に照準を合わせ、練習を重ねた。少し馴れてきたところで、水をワインに切りかえた。小説の中でも地元の樽詰めの安ワインを入れていたことだし、ぼくもスペインだけにはこだわって、コロナスというそれほど高くない瓶詰めの赤ワインを選んだ。そして、最初のシュート!第一撃は鼻に命中し、見事に失敗、どうしても、あのバスク人たちのようにはうまくいかない。ついにぼくは、競馬場へ持っていくのを断念せざるをえなかった。しかし、ボクから見事なコントロールで口に入った時のワインは、のどが快く刺激されて実にうまい。こぼすのが嫌さに、じかに口につけて飲んだのでは、そのうまさは得られないし、第一それでは飲む姿が情無い。(「今夜は何を飲もうか」 オキ・シロー)
王手飛車
たかがヘボ将棋でも、大阪と東京ではちょっとちがい、人間の味もちがって、そこが気に入っているんですけど、ある時、自称四段というオッチャンと、三番勝負をしましてね、一番五百円、を二連勝し、最後のということで、もう一番は千円、勝てば二千円、負ければチャラということでね。でも運よくボクが三連勝しまして、オッチャン、ポンと二千円くれまして、「お兄さんは、強いな。ほんまは何段?」と聞かれましたから、正直にね「連盟の二段です」と答え、免状のカードを見せたら「やはり連盟の二段はほんまもんやね」まあ、そんな風におだてられてね。ボクもそのオッチャン気に入り、串でもいきませんかと、そのオッチャンのなじみの店に入りましたね。串を食べ、ビールをやり、そして将棋論に花が咲き、いい気持になったころ、そのオッチャンが急に帰るというのでね。そこのお勘定はもちろんボクがオゴリということで、もう少し残りますというボクを置いて帰っていったんですね。それから三十~四十分、一人で飲んで、帰りのお勘定がけっこう高いんですね。串とビールですからせいぜい四千~五千円と思っていましたからね。そしたら、そこの店のおやじさんが、「焼酎のボトルも一本入っていますから」といわれ、あっ!と思いましたね。トイレに行った時、そのオッチャン、ボトル入れたんでしょうね。でもね、気分いいんですよ。やられた方がスカッとしてね。日本将棋連盟の二段は、町道場の四段より強かったかも知れませんが、最後の最後に逆転の王手飛車をやられたようでね。それでも、そのオッチャンにまた逢いたくてね。その後一度だけ、ジャンジャン横丁の道場も、その店にも行ったんですが、逢えませんでしたね。串を食べながら、お店のおとうさんに、四段のこと聞きましたら、あれから一度、店に来て、焼酎空けてそれからは顔も見せないけど、風の噂だと、病気で入院しているとか言っていましたけどね。どこかの病院でね、ヘボつかまえては例のような王手飛車をきっとかましているんでしょうね。(「おとこ町六丁目」 荒木豊久)
忘年会と文相の死
歴代文相中には逸話を残した人々も少なくないが、かの民政党の大幹部で文相在任中死去した梅田氏の如きは、トラ伝中の白眉であろう。彼氏は文相の仕事など副大臣たる政務次官の福井氏に一任して、自分は専ら党の機密を掌理していた。従って彼の前の幹事長たる大橋三太氏とも、親交あり、悪交でもあった。略々年配も同じく六十二才の暮にこの二人は忘年会をやった。所は大川端のシャレた一料亭で、往年大橋氏が、この家の大広間で乱酔のあげく、列座の芸妓に田植踊りをやらせると言い出して、女将がいくら留めてもきかばこそ。遂に十数丁の鍬をとりよせて、自身音頭をとり先範を示して、新しい青畳を片っぱしから、ザクリザクリと掘り返し、そこに苗の代りに紙幣を挟んで、後で芸妓共に全部くれたという程の大気果敢な男共であった。こういう人が二人揃って、オレ、オ前、でやる程に夜中もとくにすぎ、やがて二日目と相成って酒量六升を超えるに至っては、老令も何のその、昔の通りの腕白となった。窓の外には白雪霏々と降りしきっているのに、この六十余才の老人共は、一切の衣料をかなぐりすてて、裸踊りの演出となったという。いくらアルコールの燃焼があり、室もキチンとしまっているとは申せ、素裸の老人踊りの酔払が、すっかり参って横臥した頃は、梅田氏には十分に風の神が忍び込んでいた。其の後、風の神は仲間の肺炎菌を誘い入れた為、病む事三週間、翌年の一月二十一日には不帰の客となり、この世に暇を告げ、やがて二十三日の牡丹雪降りしきって、十メートル先もわからぬ大雪のさ中に葬式をやることになった。歴代文相中の尤もなるトラで御座ったのである。(「随筆文京の今昔物語」 出羽王堂)
天井のバラ
酒を飲むとつい大言壮語したり、人の悪口を言ってしまうものである。こればかりは止めたいが、人の悪口が一番おいしいツマミだなどとけしかける人もいるし、また実際そういうこともあるので、凡愚にはなかなかそれを慎むことができない。昔、ローマの宴会場の天井には、美しいバラの花が無数に描かれていたという。そのわけは「スプ・ウィノー・スプ・ロサー」(ブドー酒を飲んで喋ったことはバラの下のこと-つまり秘密にしておこう)ということだった。バラがなぜ「秘密」という意味になったかというと、キューピットがヴィーナスと恋をした現場を見つけたハルポクラテスにキューピットはバラの花を与えて、そのことは内密に、と口を封じた故事に由来する。たとえ天井にバラの絵が描かれた所で飲まなくても、酒の上の会話は、お互いに内密にして世の平和を図るのが酒飲みの仁義というもの。(「酒通たのしみ読本」 船戸英夫)
酔ってはいなかったワ
梶山(季之)が死んでから、私は銀座へ足が向かなくなった。その前から、三月四月五月と、一度も銀座へ出なかった。予感こそなかったが、今考えるといくらかは、練習もどきであったような気がするだが、今日は久しぶりに銀座に出た。-
そのはなしが一段落したあと、こんどは「魔里」のマダムが、私のとなりの席へきていった。「あれはね四月末のことよ。だから今思うと、ほんの亡くなる半月ほど前のことよ。突然、梶原がいい出したのよ。俺が死んだらわかっているだろうなって。それでね、なんのことって訊いてみたら、いったのよ。俺が死んだら田辺茂一には一滴も酒を飲ませないで、経帷子(きょうかたびら)をつけさして、ひと晩中、俺の寝棺の横に座らせて居くんだ、わかったか…必ずだぞ…。むろん、その代わり、茂一さんが死んだら、俺がその役をするんだ。わかったか、わかったネ、と念を押したのよ。そのときは酔ってはいなかったワ…」そういいながら、気丈な彼女の言葉が、少しずつ曇っていた。「でもそんなこと、私が申し上げる立場でもないしさ」「どうして、あのとき、あんなこと、急にいい出したんでしょう…」彼女の声が、次第にオロオロ声になっている。「もういい。もうよそう。つまらないはなしだ」と私は言った。故人の期待に背き、私はあることで虫の居所をわるくし、通夜の日も、葬式の日も、私はでかけなかったのである。しかし、そういう行為も私には自信があった。梶山だけが知っている。そういう自信が、私にはあった。すべては、二人だけの世界なのだ。(「茂一ひとり歩き」 田辺茂一)
食べる話に飲む話
これが菊正本舗から、二月二十二日は弊店の樽日につき、というような招待状だったとしたら、奥床しいのを飛び越して殺生な話になるが、酒の方で行くと、同じ「「あまカラ」の第六号には、飯島幡司氏が結解について書いている結解は「ケッケ」と読んで、奈良の東大寺で出すもの凄い御馳走のことだという説明は、どうでもいいとしても、その結解の見本に出ている献立表は一読の価値があるので、部分的に引用する。 (前略)飯櫃 素麺 御酒 御坪 吸物 煎餅麩針生姜 御酒 御重 御肴 薩摩芋揚物 御酒 (中略) 御酒 三ツ目椀 吸物 椎茸 御酒 棒の物にて 御重 御肴酢蓮根 煎餅麩と針生姜が入っているお汁なんてのもうまそうだが、この御酒、御酒、御酒と連続して出て来る所に何とも言えない風情がある。「結構な御酒で」「いや、もう、この頃の白鷹はとんと飲めたものではございませぬ」「何を馬鹿なことを。とてものことに、御酒をもっと所望でござる」というふうな雅びた調子の会話が耳に聞こえて来るようではないか。もっとも、この趣旨に徹すれば、財布の具合と睨み合せて、我々の並の結解料理の献立が出来ないこともない。 御皿 干鱈 御麦酒 御皿 小型豚腸詰 御麦酒 御丼 吸物 豚挽肉煎餅巻葱 御酒 御皿 豚挽肉煎餅巻揚 御酒 御皿 小鳥焼 大根卸 御酒 同 同 同 同 (中略) 御酒 御酒 御酒 御酒 一見して解る通り、これは我々が東京に出て来て、若干の金を握り、先ずビヤホールに飛び込んだ所を示す。干し鱈は南京豆と書いた方が妥当かも知れないが、この妙な代物は筆者がよく行くビヤホールで必ず出されるものなので、記念のために干鱈と書いて置く。それはともかくとして、生ビールがうまいので時々行くのである。しかしそんなものではもの足りないから、ウィンナ・ソセージを注文して(これも干鱈と同じで大してうまくはない)、ついでにビールのお代りを頼む。そしていい加減に切り上げて、外に出ると、まだ晩飯を食ってないので何となく空腹を覚えて、最寄りの支腹に力が入らない。那料理屋に入って注文したのが、吸物、豚挽肉煎餅巻葱、別名ワンタン、それから酒。ワンタンを食い終わってもまだ何となく腹加減が心許ないので頼んだのが、豚挽肉煎餅巻揚、俗に言うシューマイで、ついでに酒ももっと持って来させる。しかし支那料理屋などという所にねばっていても仕方がないから、ここを出て、しばらく歩いていると目についたのが焼鳥屋。ワンタン、シューマイではどこか支那っぽくて、腹に力が入らない。それで、その焼鳥屋に入ったことは、御酒 小鳥焼 大根卸 御酒 によって明かである。次行に「同」の字が四つばかり並んでいるのは、一皿では足りなくて、あるいは、その日の鶫が殊の他うまかったので、追加を注文した意味である。これには御酒の追加が伴う。その次に、中略と書いてあるのは、これは注釈する必要がある。要するに、焼鳥屋でお代わりを頼んだまでははっきりしているが、それが重なるうちに、あとはどうしたかよく解らなくなったということなのである。そういうふうになるまでそこにいたのだから、かなり長時間その店を出ようとしなかったと僅かに推定されるので、そのあと直ぐに家に帰ったとも思えない。恐らく、また何軒か廻ったに違いないとすれば、御酒御酒御酒、だけは確かである。その揚句に、電車を乗り越さなかったとしたらさいわいであると、我ながらこの献立表を見て思わざるを得ない。(「続酒肴酒」 吉田健一)
<ある調査結果>
新聞が、百人の男性からアンケートをとった。「真夜中にベッドから抜け出す理由は?」というといだった。それによると-。
二パーセントは、トイレに用を足すために起きる。一〇パーセントは、急に酒が飲みたくなって、冷蔵庫をのぞきにベッドを抜け出す。残りの八八パーセントは、我が家へ帰るために、彼女の温かいベットから抜け出す-という解答だった。(「酒飲みを励ます本」 志賀貢) ジョークです。
孟宗汁
富士酒造 加藤有慶社長のお薦め 庄内に伝わる郷土料理です。是非試してみてください。 ●材料(五人分) 孟宗(たけのこ) 1つ/厚揚げ 1枚/椎茸 4枚/だし汁 6カップ/味噌 適量/板粕 適量(1/2枚程度) ●作り方 ①厚揚げは短冊に、椎茸は4つに切っておく。 ②孟宗は適当な大きさに切り、だし汁で煮る。 ③孟宗が柔らかくなったら、厚揚げと椎茸も入れる。 ④味噌と板粕を溶かし入れ、じっくりと煮込む。 ◆好みで踏み粕を使ってもよいでしょう。(「酒粕の凄い特効」 滝澤行雄)
ワサビの粕漬け
どうやら、私はこれまで安物しか食べていなかったようなのだ。それをきっかけに、ちょっとワサビ漬けについて調べてみた。ワサビ漬けは江戸中期に静岡で誕生したという。なんでも、とあるワサビ屋の初代が、捨てられていたワサビの茎をなんとか利用できないかといろいろ試行錯誤をした結果、塩漬けにして、さらにそれを酒粕に漬け込むことによって辛味や風味が長持ちすることを発見したのだそうだ。なんと酒粕とワサビの取り合わせは、江戸時代からのもので、しかも大変な熱意と苦労の後に、「これしかない」とみちびきだされたものであったのだ。こう聞くと、なんだかとたんにありがたいものに思えてきて、それ以降、すっかりワサビ漬けのファンになってしまった。さらに、いろいろと料理に使えることもわかった。板わさのおともに、上等なやつならなかなかオツなもの。また、オイル&ビネガーに混ぜてドレッシングにするのもいい。いち押しは、バターとブレンドして、ステーキなど牛肉に合わせるというもの。これは特に美味い。(「晩酌パラダイス」 ラズウェル細木)
甘酒 一夜酒
餅米や粳米(うるちまい)の粥(かゆ)に麹(こうじ)をまぜて造る。六、七時間で醗酵(はつこう)して甘くなるので、「一夜酒」ともいう。甘くて女子供に喜ばれる。夏の宵、家の人達が集まって甘い甘酒をすするのはたのしい。暑い折ではあるが、熱い甘酒には格別の夏の味覚がある。
甘酒を煮つつ雷聞ゆなり 矢野挿雲
雨冷ゆる日の甘酒をあつうせよ 高柳碧川
学匠の庫裏(くり)に集(つど)ふや一夜酒 山田三子
ひとりすゝる甘酒はかなしきもの 清水径子(「俳諧歳時記 夏」 新潮社編)
一番仕事をしたぞ
父はあんな気性でいて大の雷嫌いですの。雷が鳴り出して夕立が始まると、お線香を立てる、蚊帳を吊らせるといった騒ぎでした。それからどんなに酔払って、夜遅く帰ってまいっても、朝は払暁に起きて仕事のかかっていました。ふつうは二時起き(夜中)で一、二月一、二月頃は堀江町(日本橋)の団扇河岸の問屋へ絵を描いてやりますので、朝早く一仕事して八時頃に私どもを起し「サアサア起きろ、おれは一番仕事をしたぞ」と一同を起され起されしました。(「河鍋暁斎」 落合和吉編) 娘・暁翠の「父暁斎を語る」にあるそうです。
飲みっぷりの良さ
はじめてのレコーディングでも「歌なんか飲まなきゃ歌えねえよ」とビール片手にマイクの前に立った。デビュー曲<狂った果実>がそれだが、以来、裕次郎のレコーディングにビールはつきもので、テレビに出演するときもビールかウイスキーの水割りは必需品だった。豪放で、底抜けに明るいが、湘南の坊ちゃん育ちの彼は、折目正しく学生気質が抜けない男だった。裕次郎の周囲には終生、学生寮か運動部の合宿といった空気がみちみちていた。飲みはじめたら、徹底していた。お気に入りのギタリストを呼び寄せて、一団となった飲み仲間は、ほとんど夜を徹して、転々と飲み歩いた。東京・渋谷の宮増坂上にある仁丹ビル裏の、"ドンキー"は、その終着駅によく使われたが、芸能人仲間のアジトとして、門外漢は入れないと頑固なまでに頑張っているおやじがいて、だから、タレントたちも安心して狭い店にひしめいていたのだが、ここで飲み歌って外の出ると、大抵は新聞配達が朝刊を配っている時間だった。かなりベロベロになっても裕次郎は、そんなとき仲間が消えるのをいやがった。ともに杯を交わしたら運命共同体…なにがなんでも最後まで付き合うというのが裕次郎自身の心情で、その飲みっぷりの良さは天下一品といってよかった。(「いい酒いい友いい人生」 加東康一)
酒はいつだって
白玉の歯にしみとほる秋の夜の酒はしづかに飲むべかりけり 有名な若山牧水の歌である。酒飲みで、この歌を知らないものは、まずいないだろう。だが、酒は一人静かに飲むとは限らない。国文学者の池田弥三郎さんは、気のおけない友人と二人だけで飲む酒を「対酒」と名付け、"うまい”と歓声を発するのは、この酒が多いと書いている。大勢でワイワイ騒ぎながら飲む酒だって悪くない。人によっては、ゴルフの後の一杯のビールのうまさ、風呂上りの一杯をあげる人もいるし、「夫婦でワイン」なんてテレビのCMだってあった。要は、酒はいつだってうまいもの、いいものなのである。(「作家の食談」 山本容朗)
おふくろの後など追うな
父は漸く男の四十代を踏みかけていた。遊行坂時代から清水町頃までは、会社も隆運にむかい、横浜埠頭(ふとう)を中心とする商社の内外人に顔もひろくなり、特に花柳界では商売上手な真似もしていたので、いわば得意時代の有頂天(うちようてん)にあったものだろうか。それに身長は五尺六、七寸の壮健な体躯であったから、医者の忠告に耳もかすことではない。母などは噯(おくび)にも、父の前では愚痴もこぼせなかったし、ふと顔いろに出してさえ、忽ち食卓が引っくり返された。父の酒の膳に見えたお菜の何かを、ぼくが喰べたそうに見ていたらしく、母の袖を引いたのだった。すると父はやにわに、膳の上の物を悉(ことごと)く中庭へ放り投げて、「酒がまずい」と云い「なぜ子供たちにもおなじ物をやっておかないのだ。喰べた気がしない」といって怒った。乱酔しているばあいは、そんな些事をきっかけに、母をそこにおいて、一時間も二時間も飲みつつ日頃の叱言や母の親類のざんそまでを並べるのである。もし母が口ごたえでもすれば「出てゆけ」となり、時には腕力をふるい出す。まったく手のつけられない暴君になってしまう。だから微酔のうちの上機嫌な父はいいが、怪しくなると、ぼくら子供を初め、家の内は颱風下の停電みたいなものになる。ぼくは十一、二歳だったからまだよかった。義兄の政広は優形(やさがた)の美青年である。「政広、ここへ来い」となると、父の荒い酒気の前におかれて、義兄は油をしぼられた。「大体、きさまは柔弱でいかん」というのが毎度のお談義の主題であったようである。何を怒られたのか、ある時は、「腹を切れ」とか何とか云われて、女形(おやま)みたいな義兄は蒼白になった儘、泣いているのを見たこともあった。家には刀剣もあったらしい。母は、万一を惧(おそ)れて、刀の隠し場所に、恟々(きようきよう)としていた。いちどなどは、十日も居所不明にしていた父が、やっと帰って来たと思うと、父が囲っていたお琴という関内芸妓や茶屋の女将などと一しょに帰って来、さらに母へ酒のしたくをいいつけた。日頃から父の取巻きらしいそれらの人々が散々馬鹿騒ぎをして帰った後で、母が何か一言父へ恨みを云ったとかで、父が立腹し出したことがあった。この時も父はどこからか刀を取出して、「斬ってしまう」と、それを抜いて母を脅した。母は裸足で裏庭へとび降り、幼い妹たちを抱えて夜半まで塀の外にかがみ込んでいた。そういう後では、父はさらに大酒を仰飲(あお)って「男の子は男親につくのだ。おふくろの後など追うな。外に出てゆくと家に入れないぞ」などと呶号し、僕はおろおろ泣くだけだった。(「忘れ残りの記」 吉川英治)
低精米の酒
神亀酒造は、昭和六十二年から全量を純米酒にするという当時では考えられない造りを採用した蔵元として有名である。その神亀酒造が最近精米歩合が八〇%の日本酒を造った。この酒は一部の愛好家には大変な評判となった。というのは、精米歩合が八〇%とはとても思えないほど雑味が少なく、味がしっかりしていたからである。このように、米を磨かなくてもちゃんとした造りをすれば綺麗で美味しい酒ができるのである。神亀に続いて、秋鹿酒造も同じ八〇%の磨きの酒を造り、切れ味鋭い美酒に仕上げた。吟醸酒とは正反対の考え方の酒造りは、蔵の技術力と手間隙を厭(いと)わない情熱がないと成立しない。吟醸酒は造りが難しいとよく言うが、低精白の米を使って吟醸酒並みに綺麗に造るのはその何倍も難しく、叮嚀さが要求されるのだ。(「蕎麦屋酒」 古川修)
タマキは大きくなったら
「社会に出たら酒を飲む機会も増えるやろうが」と、我が父が訓戒を垂れる。ビールはまだ二口目くらいなのに、早、血走った眼、ゆるんだ唇、金属系のカビ臭い吐息。痴漢みたい、とわたしは思う。「女の酔っぱらいほどみっともないもんはないゾ。ただし、二回は大きな失敗をしなさい。そしたら自然と飲む量を自分で量るようになるから」-男のひとで、酒の酔いかたについて注意してくれたのは、あとにも先にも父だけである。小料理屋の男女共用のトイレで戸を開けたら、目の前に、嫁入り前の娘のまる出しの尻があった、金隠しに覆いかぶさって腰抜かしとった、おおかた冷酒を調子に乗って飲んだのだろう、あれはあとから酔いがまわる、意識を失って、男のいいおもちゃになるのだ、などという恐ろしい話をして聴かせるんだった。父自身も、大きな失敗を二回、二十代で済ませたらしい。そのうち一回はブタバコ入りしたという。「タマキは大きくなったら大酒飲みになるゾ」毎晩、アサヒ生ビール一本のみ、それが規律ある自衛隊員の暮らしで、むっつり助べえだからタガが外れると、テーブルのしたで脚の指をつかって母のスカートめくりをし、もうシアワセの絶頂というふう、娘のわたしにはお酌をさせ、つまみの、カレイ・イカ・鮎の卵やら、イワシ・サンマ・鮎のはらわたやら、うなぎの肝、サザエのしっぽなど、いちばん旨い稀少な部位を、ざっくり箸でちぎり、口に入れてくれ、「こういうのばっかり欲しがる」上機嫌に笑い、「タマキは大きくなったら」とつづけるのだ。(「白に白に白」 大道珠貴)
長春清酒
日本の大陸進出時代に満州地区だけでも日本酒の製造会社は、五六社あり、酒の等級は一級から五級まであった(『満州国公定価格便覧』一九四一年)が現在中国で生産されている日本酒は、長春市醸酒廠の長春清酒だけである。精白米を原料とし、米麹と、酒精酵母を使用すると説明してある。(「一衣帯水 中国料理伝来史」 田中静一) 昭和62年の出版です。
梅北国兼
というのは筆者の想像だが、その後の三人の行動を見ると、突発的な計画であったとしか思えないのである。名護屋の秀吉の陣中にはおよそ十万人ちかい兵がいた。梅北国兼ら三人の率いる兵はわずか千五百人である。しかも名護屋の陣中には彼等の主君である島津義久がおり、朝鮮には義弘が渡海している。梅北らが叛乱を起せば、義久や義弘がぶじにすまないことは明かだった。それについて梅北は薩摩の宮之城に島津家末弟の歳久がいる、その歳久を主に仰げばよいとうそぶいていたと言われる。およそ計画性のない叛乱だったことが知れるのである。梅北と田尻、伊集院の三人は名護屋へは行かず、平戸に船をとめて上陸し、偽って後続の兵らを平戸へ招き寄せ、人数が二千人になったところで、秀吉討伐のクーデターを起こした。さすがに名護屋へ攻め入ることはせず、梅北は千二百の兵を率いて肥後の佐敷城を襲い、田尻但馬が八百余人を引連れて同じ肥後の八代城へ向かっている。この両城を拠点として九州の兵を募り、大挙して名護屋を襲う計画だったのだろう。しかしこの計画は第一歩で躓(つまず)いてしまう。八代城を攻めた田尻但馬が小西家の侍たちに迎え撃たれ、全滅してしまったのである。梅北国兼のほうは佐敷城を攻めて難なく手に入れた。加藤清正の支城である佐敷城には安田弥左衛門、境善左衛門と名乗る留守居の侍たちがいて、何の抵抗もせず国兼を迎え入れ、城を空け渡したばかりか、国兼の挙兵に協力を誓い、酒や女を供して大いに歓待したのである。梅北国兼という男のおかしさは、敵城の留守居たちの言動を疑いもせず、大いに喜んで酒を飲み、女をあてがわれて満悦してしまったことである。国兼が佐敷城に入った当日、同志の田尻但馬は八代城攻略に失敗して討ち死にをとげているのだが、国兼は数日後になっても、それすら知らなかった。そして入城して四日目、酒宴の酒に酔い痴れ、女を抱いて寝ているところを、加藤家がひそかに招集した兵たちに襲われ、あっさりと殺されてしまうのである。この梅北国兼のクーデターは"梅北の乱"と呼ばれて、島津家の存亡にかかわる事件となった。しかしあまり無謀な、かつ杜撰(ずさん)な計画と行動が秀吉の疑いを解き、結局は島津家の末弟歳久の首を討って差し出すという妥協案で、この事件は解決を見た。(「江戸人物伝」 白石一郎)
禁酒法廃止案成立
いちばん血の気の多い酒飲みも、二十一条(禁酒法廃止案)が各州で承認されたスピードにはびっくりした。一九三三年十二月五日、ワシントン・タイム、午後五時三十二分、ユタ州選出議員、S・R・サーマンは、三十五番目の州(ペンシルヴェニア)が承認し、ユタ州が最終評決に入ったことに満足した。七時、禁酒を訴えた婦人団体の圧力で成立してから、一三年十ヵ月十八日後に、ルーズヴェルト大統領は、この法の廃止法案に署名した。廃止は、一種のアンチクライマックスとしてやってきた。その日遅く廃止ということになったため、酒を運ぶトラックは、閉店時間前のナイトクラブやホテルに、たくさんの量を運ぶことができなかった。イギリス航路のマジェスティック号は、あらしのため航海が遅れて、積み荷の六千二百ケースは、朝まで運べなかった。非合法の十年を過ごしたたいていの秘密酒場は、このときから営業許可なしで営業する危険を犯すことになったが、風俗営業の係官は、どっと殺到してきた営業許可願の書類をさばき切れなかった。ニューヨーク州酒類統制局の局長、エドワード・P・マルーニーは徹夜で仕事をしたが、営業許可を千通書くのがやっとだった。マンハッタンのメリー・ゴー・ラウンドでは、経営者、オマール・チャンピオンがボタンを押して、バーの回転装置をとめ、金網をかけて、「酒類は売りません」という看板を出したので、客はいっせいにブーブーいった。「合法化されるまでは一滴も売らない」と彼はいったので、せっかくお祝いにかけつけながら、この日ばかりはあせった連中は、あわてて営業許可のある店を探しまわる始末だった。四十二丁目のミンスキーズ・バーレスクの正面に、ネオンサインで「ジン、あり」と謳(うた)ったが、タイムズ・スクウェアの雑踏も大晦日ほどうかれまわることがなかった。ニュージャージー州知事、ハリー・ムアは州の酒類統制基準は憲法違反として投票したため、ニュージャージーの人びとは合法的に酒を飲める時期が遅れたが、同時に、この知事はいったものである。「ニュージャージーでは、十三歳の人間に酒を売るのは違法であるが、もう数日、このままにしておいてもたいして害はないだろう」と。ニューオーリンズもこの種の除外例のついた廃止案をうけ入れたが、二十分後にはそれも廃止された。バルチモアで、思想家のH・L・メンケンはいつもの調子でいったのだった。「アメリカの政治家が民衆によいことをするなどというのは、あまり多くはない。こんどだけは、やつらも民衆に同意させられたのだ」と。ここで、なんとも皮肉に、グラス一杯の水を飲んで、いわく、「この十三年間で、はじめて水を飲んだよ」(「禁酒法はどのようにしてニューヨークで失敗したか」 ジョン・コブラー 中田耕治訳)
物を食い酒を飲む
物を食って酒を飲む。物を食ったり酒を飲んだりする。「酒を飲み物を食う」とも。『枕(まくらに)草子』には、「すさまじきもの」の段に、その一つとして、『除目(じもく)に司(つかさ)得ぬ人の家』をあげ、その官吏任免の儀式の前に、任官を望む人の家の様子を、、<物食ひ、酒飲み、ののしりあへる>と書いている。御ちそうを食べたり酒を飲んだりして、騒ぎあっている、と。『徒然(つれづれ)草』には、いなか者が賀茂の祭りを見物した時の様子を、<奥なる屋に、酒飲み、物食ひ、碁・双六(すごろく)など遊びて>と書いている。奥のへやで、酒を飲んだり物を食ったり、碁だのすごろくだのをやって、と。この場合の「物」は、広く食物をさし、間食、酒のさかなの類であろうか。何か祝い事や行事があると飲食する。(「飲食事辞典」 白石大二)
酔っぱらい
子供と酔っぱらいは大きらいという、あるプレイボーイ氏がいる。理由は「説明してもわからないから」だそうだが、この説には全く賛成である。ちょいと深く考えると聞きわけのなくなった女なんてぇものは子供や酔っぱらいより、なお厄介な代物ではないかと思うのだが、彼にいわせると、「いくら馬鹿な女だって、話せばとりあえずその場はわかるじゃない」 たしかに酔っぱらいは、日本語そのものの判別すらつかなくなるのだから、こりゃ面倒ですよ。全くむこうの手前勝手な一方通行で不戦勝、お手上げという感じ。へぇ、そんなことでよく酒場の女将なんか務まりましたねといわれそうだが、銀座なんてとこはアータ、くだまいて放歌高吟なんて酔客はめったにいない。あそこは酒場でありながら、どこかで醒めにいく場所なんですから。それに多少いい気持になっても、最後に出てくる勘定がきが、全ての酔いを一瞬にして醒めさせてくれる。それを腹の底で覚悟しつつ飲む酒で、グデングデンになれるという剛の者はめったにいない。もっとも故川上宗薫先生は、あの0の羅列をみてときおり逆上気味になるとおっしゃった。逆上は酔っぱらいより、なお始末のわるい錯乱状態ではあるけれど。(「男はオイ! 女はハイ…」 山口洋子)
名うての酒豪
ところで、こんな下戸である私が、たった一度、大変な酒豪だという評判をとった-それもお酒に強い鹿児島で評判をとったお話をしたい。終戦後間もないころであったが、鹿児島の小中学校の校長先生たちの会に、講演に招かれた。あす講演だという前夜に、吉例によって宴会がはじまった。「あしたの講演に差し支えますから」などと言いわけして逃げようとしても聞かばこそ。「鹿児島へ来て頂いただけで十分で、講演などはしてくださらんでもよかとごあんど」などと、南国らしい鷹揚(おうよう)なことを言って、さかんに酒を勧める。ここの酒は泡盛とかで特別にアルコール分が強いので、私は一口飲んだだけで引っ繰り返った。しばらくたって眼を覚ましてみると、まだ宴たけなわである。それ、先生起きなすった、とまた一口飲まされる。そうして引っ繰り返る。飲んでは倒れ、飲んでは倒れ、暖かい土地ゆえ風邪も引かず、とうとう明け方になってしまった。朝、講演がかりの人があいさつに来てみたら、先生がたは徹夜してお酒を飲んだので、おおむね正体なく眠りこけて河岸のマグロさながらである。私は、たびたび引っ繰り返ったのが幸いして、かつてお酒に酔うことを知らない、名うての酒豪の先生と差し向かいですわっていた-伝承によると、なお悠然として名残りの酒盃を酌み交わしていたというわけで、ことにその日の講演はちゃんとつとめおおせたので、あれは相当なものだという評判がたっているということを、私はしばらくのちに鹿児島を訪れたNHKの青木一雄アナウンサーから伺ったことがある。(「ケヤキ横丁の住人」 金田一春彦) 金田一さん
ギルガメシュ
まず、メソポタミアで最大の文学作品である「ギルガメシュ叙事詩」の第十の書板に、酒場の女主人らしい人物が登場する。物語の荒筋は、親友のエンキドゥが死んでから、不死の秘密を求めてさまよう主人公ギルガメシュが、はるばるマーシュの山をこえ、ブドウがみのっている場所(地中海沿岸?)にまで達したあとのところで、酒場の女主人公シドゥリ(この名はアッシリア語版にのみ出て来て、古バビロニア語版ではただ女主人となっている)はやつれた顔のギルガメシュを小窓から見て、その嘆きをきき、忠告を与える。「ギルガメシュよ、あなたはどこまでさまよい行くのです。あなたの求める生命は見つかることがないでしょう」「ギルガメシュよ、あなたはあなたの腹を満たしなさい。昼も夜もあなたは楽しむがよい」この女主人は、まるで今日のバーのホステスのようなことを言っている。(「世界風俗じてんⅡ衣食住の巻アジア」 矢島、加藤、川村、岡本、長、大島、奥、重村、林)
酒失と帰国
これよりさき、東北遊歴を計画して胸ふくらませていた(横井)小楠は、(天保11年(1840))二月九日、突然江戸留守居から帰国の命令をうけとった。その理由は酒後の過失であるという。江戸留守居沢村多兵衛が藩庁に出した報告によれば、「多兵衛見こみにては、禁酒のところもおぼつかなく、そのうへ内済に相成り候儀には候へども、彼方より反報躰の儀も計りがたく、かたがた何となく罷り下し候方しかるべしとのことに御座候」というのであった。-ちなみに、のち木戸孝允(たかよし)が小楠の舌剣と評したほど、小楠の政治批判は辛らつなものであった。とくに酒失のあったと推定される十二月二十五日に藤田東湖邸における忘年会のときの漢詩、そのあとの政治論が、スパイの手によって留守居にもたらされたとき、こと勿れ主義の藩役人たちがいかに驚いたことか、そして政治批判の芽を早急につみとることを決意したのであろう。小楠は酒が入ると舌鋒ますます鋭く、必ず口論をするくせがあった。それは学究にはありがちのこと、小楠自身もそうした酒癖を罪悪だとは考えていなかった。今度の事件に最も近い例に、かれより七年まえ同じく肥後藩から留学を命ぜられた沢村西坡(せいは)の場合がある。彼は過酒のため帰国させられ、天保三年(一八三二)許されて再び留学の命をうけたが、そのとき小楠(二四歳)は、「沢子寛かねて江戸に遊学するを送る序」をつくって西坡に同情をよせ、再び留学を命じた藩の所置を激賞している。(「横井小楠」 圭室諦成)
送別
道(い)ふなかれ長き別れと
束の間も長きはわかれ
水落ちて鮎さびぬるを
眉てらす月こそ憂けれ
舞ふべくも袖短かくて
綰(わが)ねたる柳ちり/"\
盃に泡また消えて
酒の味にがきか今宵
詩成れども唱へがたし
これは俳体詩にはならぬか。わからぬ処が面白い。如何。
-明治三十七年七月、高浜虚子宛て-(「送別」 夏目漱石)
片岡市蔵
その片岡市蔵が不幸な事故で七十五年の生涯を閉じたのは一九九一年六月三十日の早暁で、七月一日付の「朝日新聞」によれば、「二十九日午後八時三十五分ごろ、東京都文京区湯島三丁目の営団地下鉄千代田線の湯島駅構内でホームから落ち、取手発代々木上原行きの電車(十両編成)に右足をひかれ、東京大学医学部附属病院に運ばれたが、出血性ショックのため…」ということだ。酒をこよなく愛する、じつに気のいい人で、岩井半四郎、なくなった市川八百蔵とともに、銀座のゆきつけの店でよく飲んだものである」という『俳句・私の一句』の著者は、 なぜひとりで、飲んでいて、長い階段をおりてまで地下鉄で帰宅しようとしたのか、と不審に思ったが、逆にいえば、酔って気が大きくなるといった心理が、私にもないわけではない。つい、おのれを恃(たの)むのであろう。 と、この死を悼み、「初曾我」の句で偲んだのである。(「酒と賭博と喝采の日日」 矢野誠一)
極楽寺殿御消息(ごくらくじどのごしようそく)
一、酒(さけ)の座敷(ざしき)にては、はるかのすへざ(末座)までも、つね(常)にめ(目)をかけ、こと(言)葉ををかけ給ふべし。おなじ酒なれ共、なさけ(情)をかけての(飲)ますれば、人のうれしくおもふ事也。殊(ことに)/\ひらう(疲労)の人には、なさけかけてをく事なり。うれしさ限なきにより、人の用を大切にする也。(76)
(76)「ひらう(疲労)の人」は、おちぶれて不遇な状況にあるひとのこと末文の「人の用を大切にする也」は、上述のようにすれば心から用に立とうとするようになるの意。(「家訓集」 山本眞功編註) 鎌倉幕府二代執権北条義時の3男、重時の著です。
○不酔酒薬
本草綱目(巻五十一)狐膽(狐の肝)主治解二酒毒一(酒毒を解く)とあり 註に萬畢衍に云(いわ)く 狐血漬黍令人不酔(狐の血に浸けたキビは人をして酔わせず) 高誘註に云く 以狐血浸黍米麦門冬陰乾為レ丸飲時以二一丸一置二舌下一含レ之令二人不一レ酔也(狐の血を以てキビ、コメ、バクモンを浸し冬に陰干しし丸くして飲む時一丸を以て舌下に置いてこれを含めば人をして酔わざらしむ)(「安斎随筆」 伊勢貞丈)
み-わ【酒甕】
(補)酒を醸す壺。其壺の儘、地に掘りすゑて、神に献る事もある。みわは元、酒の事であるらしい。三輪の地名民譚が、三縈説に固定してからは、三輪の酒に関係ある部分は、忘れられて行つたのであらうが、古くは必、酒醸みの伝へがあつたであらう。大神(オホミワ)・神人(ミワビト)の氏の中には、必、酒に関係があつたのであるであらう。天ノ諸神(モロカミ)ノ命の後と言ふ御手代ノ首と同祖の神人(ミワビト)の一流は、もろ・かみなど酒に関係ある神名を思ふと、酒作りの家筋と思はれる。酒部(サカベ)は、大彦命の後と言ふが,恐らくは蕃種で、其以前の醸酒の家が、此神人(みわびと)であつたのであらう。酒人は進酒の役だと,栗田寛博士は区別してゐられる。或は宮中の酒の事に与つたのが、酒人で、神事に関するのが、神人であつた為、神の字を宛てたのが、次第に発達して、大神氏なども出る様に、なつたのかも知れぬ。みもろのもろ・みわなど言ふ語の,酒に関係ある事が、三輪と酒との関係を、深くしたのであらう
とみ廣
さて、今夜の飲み会は渋谷がいいということで、またもや必殺の店を紹介する。オトナの居酒屋「とみ廣」-である。昔は魚屋をやっていたというだけあって、泣けるほど旨い魚が食べられる。注文してから時間がかかるので、まずは、名物たらこ煮とやりイカ煮でビール。たらこ煮もさることながら、この日の生白子酢は絶品という名に値する旨さだった。このあたりで、ビールから日本酒へ。「本流手取川吟」、「王禄超辛純米」と飲む内に主役の登場。肝がたっぷりとついたかわはぎの刺身である。舌が大喜びする旨さだ。店内の雰囲気が柔らかいのは、ご主人の笑顔と女将の気配りのせいである。ジョン・レノンは「30歳以上のヤツらを信じるな」と言ったが、この店は「30歳以下のコドモは来るな」と言いたいね。(「東京居酒屋はしご酒」 伊丹由宇)
飲酒 酒を飲む 柳宗元
今旦 愉楽少シ 今朝(けさ)は気が浮かないので
坐ヲ起(た)ツテ清樽ヲ開ク。 座を立つて清樽を開き、
觴ヲ挙ゲテ先酒ニ酹(ライ)し 觴を挙げて先酒を祭り
我がガ為ニ憂煩ヲ駆ス。 我が為に憂(う)さを晴らしてもらふ。』
(自註。先酒トハ始メテ酒ヲ為(つく)ル者。) (作者の自註。先酒とは始めて酒を造つた者である。)(「中華飲酒詩選」 青木正児著)
足利義量
そのころ、応永二十八(一四二一)年六月二十五日、義持の息子で次の将軍を約束されている義量(よしかず)が、あまりにも大酒飲みなので、かれのもとに集まる近臣たちに酒を禁じることとした。周囲のものが禁酒すれば、義量もおのずから酒をひかえるようになろうとみたのである。そのために各近臣たちに禁酒を誓う起請文(きしようもん)を書かせた。熊野牛王(ごおう)の料紙にその旨を書かせ、三十六人の連判をとったのである。若君(わかぎみ)の義量はそのとき十五歳だったが、祖父義満と同様に酒の上でもたいへんな早熟だった。義持が、義量の大酒に溺れるのに呆れ案じていた通り、その癖はいぜんとしておさまらず、応永三十(一四二三)年に義持から将軍職を譲られてから満二年足らずで、同三十二年に死んでしまった。十九歳である。じっさいその直前の幕府要人たちの泥酔ぶりは尋常でなく、大御所としての父の義持にしても同じであった。息子が酒の祟りで病床につき、各社寺に治癒の祈禱をかけているさなかでも、禁中を訪れて大いに酩酊している。(「酒が語る日本史」 和歌森太郎)
国菌
麹菌は、醤油や味噌を造るためにも欠かせない、日本人にとって大切な微生物です。しかも麹菌は日本固有の菌で、世界のどこを探しても見つからないそうです。日本オリジナルの微生物として、日本醸造学会により、平成18年に「国菌」に認定されています。(「めざせ!日本酒の達人」 山同敦子)
C.種麹(たねこうじ)
種麹とは米に大量の麹菌胞子を着生させたもので、麹を造る際の種として蒸米に接種する.その製造工程は玄米に近い低精白米(精米歩合96%程度)を蒸して木灰(きばい)を混ぜ、麹菌胞子を接種する.約1週間の培養により十分に胞子を着生させた後、乾燥して製品とされる.種麹製造時に混ぜる木灰はツバキ、ケヤキ、カシ等の硬木の葉を蒸し焼きにしたもので、カリウム、マグネシウム、リンなどの無機栄養源に富む.木灰の使用は、胞子量が増加する、胞子の耐久性が増し保存性を向上する、雑菌を淘汰するなどの効果がある.種麹は全国7社ほどの種麹専門メーカーから配給され、清酒会社はいずれもそこから種麹を購入、麹を製造している.種麹が業として成り立ったのは古く、室町時代に幕府将軍からの許可を得て創業を開始した製造場が現在も営業を続けている.(「酒学入門」 小泉武夫・角田潔和・鈴木昌治編著)
六月二十一日(土)晴、夏至
四時半、『俳研』中西氏来。この数日のメディアからの接触や取材申し入れの一覧リストを持ってきてくれる。NHKは「クローズアップ現代」で扱いたいといっているらしい。句集はベストセラーにしましょう、という。これまで黛(まゆずみ)まどかさんの句集『B面の夏』が三万二千部で、句・歌集の最高記録といわれている、ぜひ三万五千部は売りましょう。-いや五万部といいたかったが、黙っておく。第二回分のゲラ直しを手交。さらに、ここ四、五日分の句稿も渡す。じっくり目をとおして「ますます句がよくなっていますね」と褒めてくれた。死が近づくと句が光るのだろうか、などと、ちらと考える。六時、夕食。ひき肉団子と野菜スープ、なすと油揚げ、すまし(はんぺん)、青菜、全がゆ、コーヒープリン。きのうワインがまずかったので、今夜は日本酒を冷やでひと口。やっぱり味がちがうし、風味もない。でも、ワインよりはいい。ひと口半、少しぼーっとなって、顔が赤くなる。食事は三分の二ほど。矢吹さんに電話。チーズ一個、日本酒ひと口、うまし!十一時半、アンベック坐薬、みん剤、安定剤、下剤。(「おい癌め酌みかはさうぜ秋の酒」 江國滋)
下戸一族VS飲酒派
しかし、母方はみな、下戸の一族なのだ。(「いままさに死なんとす」な祖母も含め)。粛々とお茶なぞ飲んでいる。缶ビールぐらい、だれか買ってきてもよさそうなものだが、そういう発想が端からない。しかたがないので、水っぱなを大量に流したり、飛び蹴りを食らわせてきたりするちびっこたちの相手をして、なんとか時間をやり過ごした。そうこうするうちに、祖母は亡くなった。大往生だったので、悲しみのなかにも晴れやかさがあるような、これまた奇妙なムードの葬儀となった。問題は、通夜のあとの会食だ。お寺の一室で、身内だけでケータリングの食事を摂った。もちろん、ビールやら日本酒やらも用意されている。しかし下戸一族だけあって、アルコール類には目もくれず、粛々とお茶なぞ飲んでいるのである。ありえんだろ。悲しみのときにこそ、酒を飲んでパーッとやりたいもんだろ。私は母の冷たい視線をものともせず、卓上の瓶ビールを自分のまえに集結させた。片っ端から空けていくぜ。すると、肩身の狭い思いをしていた酒飲み部隊が、次々に参加を表明した。私の父、いとこの妻や夫といった面々である。即席部隊は健闘した。弔い酒なのだから飲んで飲んで飲みまくり、ビールばかりではなく日本酒も何本も空けた。勢いは止まらない。夜も更けたころ、片手に数珠、片手に飲みきれなかった瓶をぶらさげ、「よーっし、もう一軒行くぞ!」ということになった。母の視線は氷点下まで到達していたが、かまうことはねえ。祖母も生前、「あなたの飲みっぷりだけは一人前ですよ」と、酔った私を介抱しながら褒めて(?)くれた。ここで飲まなきゃ、人間がすたる。いとこの奥さんと私は、夜の町へ繰りだした。飲みたらない父もついてきた。なぜか、下戸の叔父まで引っ張りだされた。総勢四名で小料理屋へ上がりこみ、酒盛りはつづく。叔父はお茶を飲んでいるのだが、ふだんから「べらんめえ」調なので、素面でも酔っ払っているようなものだ。「俺ぁよう、よかったと思ってんだ。母親(祖母のことだ)ももう九十四だったし、だれに迷惑かけるでもなく、眠ったまま逝っちまえたしさ。弔い酒じゃなく、祝い酒だな、こりゃ」「おじさん、飲んでないじゃん」「下戸だからよう」「そんなこと言って、お義父さん」と、いとこの奥さん。「おばあちゃんに連れていかれないようにしてよ。なんだかんだでマザコンなんだから」(「下戸一族VS飲酒派」 三浦しをん)
しっかりと造られた酒
このように、酒も醸造されたばかりの新酒では本来の味がわからない。熟成させ、燗をつける。これが日本酒の本当の醍醐味といえる。ただし、どの酒でも熟成させればいいものではない。熟成して旨くなる酒は造りのしっかりした酒である。しっかりした造りというのは、麹と酵母がちゃんと仕事をして完全発酵させることをいう。これは、米の蒸しという原材料処理をしっかり行い、麹菌を麹米のなかにしっかりとはぜさせ、かつ、酵母を培養するための酒母(酛)造りもきちっと手間隙かけて行っていることが最低限必要な条件だ。酒母造りでは、とくに「打瀬(うたせ)」という酵母を休ませる工程で温度を下げることが、いい酒造りのポイントとなる。日本酒の醸造は、並行複発行と呼ばれる複雑な過程で進行するため、蔵人が人為的にコントロールすることは難しく、麹と酵母の成り行きに任せることになる。このときに、雑菌に負けない強い酵母が残っている状態にして、思う存分に仕事をさせてやることが、いい酒造りとなるのだ。打瀬の温度を下げれば、弱い酵母は淘汰(とうた)され、強い酵母だけを残すことになる。このように、しっかりと造られた酒はいいワインと同じで、長期の熟成に耐えて本当に美味しくなる。わが家には十年以上熟成させた日本酒がごろごろしており、これがまたとても美味である。いろいろな銘柄で日本酒の熟成を試してきたが、最近わかってきたのは純米酒すなわちアルコールを添加していない酒が熟成に適しているということだ。アルコールを添加した本醸造酒タイプの酒は、吟醸酒といえども、熟成が進むにつれてアルコールが浮いている感じがはっきりすることが多い。(「蕎麦屋酒」 古川修)
長期低温発酵
留添えから、もろみを搾(しぼ)るまでの日数はどうかというと、おらとこの蔵では、普通でも二八日ぐらいかけてるわ。中には、二三日ぐらいで搾ってしまう蔵もあるし、もっと早く搾る蔵もあるようだが、おらとこの蔵は、これだけのもろみ日数をかけて、しかも低温で発酵させている。だすけ、それだけきれいな酒になっているわけだいね。もろみ期間を長くしようと思えば、もろみタンクの数も余分にいる。また、もろみを管理する手間も余計にかかってくるわけさ。長期低温発酵と一口に言ってもさ、簡単なことではないんだわ。-普通酒の場合で、もろみが最高温度になるのは仕込んでから一二日か一三日目ぐらいだんが、おらとこの蔵ではそれでも一三度から一四度ぐらいまでだいね。最低温度は七度ぐらいのとこだわ。これぐらい温度が低いと麹や掛米はもろみに溶けていくのもゆっくりになる。だから味が出すぎることもなく、ほどよく味が乗った淡麗辛口の酒になっていく、きれいな酒になっていくというわけですて。逆に言えば、そういう酒にしたいがために、長期低温発酵ということをしているんだわ。手間もコストもかけてさ。(「杜氏千年の知恵」 高浜春男)
[鹿の角の酒]
卒患の腰痛にして、暫転して得ざるを治す。
鹿の角(新しき者、長さ二三寸、焼きて赤からしむ)。
右の件、酒の中に内(い)れて浸すこと二宿。空心にこれを飲めば、立ちどころに効(き)く。-
(訳)[鹿の骨の酒]急な腰痛で、しばらく回すことのできないのを直す。鹿の角の新しいものを二三寸の長さにし、焼いて赤くする。それを酒の中に二晩浸しておき、空腹の時に飲めば、すぐにききめが現われる。(「食経」 中村璋八・佐藤達全訳)
賀茂茄子入り出し(賀茂ナス)
賀茂ナスを2つにタテ割りし、天地の部分を少し削っておく。金串で何ヶ所か(特にヘタに近い部分)突いて、火がとおりやすいようにする。天ぷら油を170度くらいに熱し、串でついてみて、楽にとおるようになるまでゆっくり揚げる。ナスをはしでつまむようにして、油をよくきって鍋からあげる。だしはだし汁、醤油、みりんで好みの味に作り、一度火をとおしておく。揚げナスを切り口を上にして器に盛り、おろしダイコン、おろしショウガ、きざみネギ、かつおぶしなどの薬味をのせ、熱いだしをかける。賀茂ナスが手にはいらなければ、米ナスでもいい。(「酒肴<つまみ>のタネ本」 ホームライフセミナー編)
滴酒(したミざけ)(三十六ウ)
乞食(こじき)、茶屋にて滴酒(したミさけ)を面桶(めんつう)に一盃(はい)貰(もら)ひ来り、道端(はた)にすハり、前に置、飲んとせしが、其昔(むかし)、捻上戸(ねぢじやうご)ゆへ、ひとり飲(の)んでハ旨(うま)からず。案(あん)じ居るところを、奴(やつこ)の供帰(ともがへ)りを見付けて、〽モシ奴(やつこ)さま。お願いがこさいます。〽なんだ〽私、その昔(むかし)ハ大(だい)の捻(ねじ)上戸でこさいます。只今此酒(三十七オ)をぐつと給(たべ)てハ旨(うま)からず、憚(はばかり)ながら、それくらへと仰(おつしやつ)てくださりませ〽それをのめ〽乞食是をたべますると、御座(おざ)にたまられませぬ〽はて、ぐつとのめ〽乞食それハ御無理(ごむり)でごさります。先刻(せんこく)の一盃(いつはい)さへ、漸(やう/\)たべました。もうごめんなさりませ〽そんなら此方(こつち)へよこせと、奴ぐちと飲(の)む(三十七ウ)(「飛談語」 武藤禎夫・編)
幻の日本酒を飲む会
日本酒は全体としてみるとここ三〇年ほど凋落を続けている。その中でひとり吟醸酒だけは成長し続けている。二五年前、吟醸酒が日本を代表する酒になろうとは考えても見なかった。私は、吟醸酒をおいしいという人たちを集め、それを二五年間飲み続けてきた。そのいきさつを記すことは、吟醸酒の魅力を語ることになるだろうし、なおかつ吟醸酒そのものが成長し続け、いわば発展途上にあることもご理解していただけるのではないかと思っている。二五年間、吟醸酒を飲み続けたアマチュアの酒の会「幻の日本酒を飲む会」のスタートはそれほどの準備もなく、暮を間近にしたある日、気構えもなく静かに始まった。二五年間も続く毎回胸をときめかせた三二八回の例会がゆっくりと滑り出したのであった。(「「幻の日本酒」酔いどれノート」 篠田二郎)
酔郷記
やかましき浮世(うきよ)の騒ぎ、一文(いちもん)の銭(ぜに)をあらそふて舌の先に剣(つるぎ)を舞はすあれば、半生の名に駆(か)られて胸の裏(うち)に要慎(えうじん)の楯(たて)油断なく備ふる奴等(やつら)が、是(これ)は悪い是は善いあれではいけぬ斯(か)うするに限ると面倒なる詮索(せんさく)。われは其(その)やうな事を一猪口(ひとちよく)の酒の泡(あわ)と消して徳利(とくり)の中に別乾坤(べつけんこん)に入れば、王様もなく敵国もなく戸長(こちやう)さまに叱らるゝ事もなく、聞苦(きゝぐる)しき向ふの婆(ばゞ)が嫁(よめ)いぢめる声も聞えず、よしや叔父上三郎兵衛(おぢうへさぶらうべゑ)どの借金取(しやくきんと)りに御来臨(おいで)なさるとも鶯(うぐひす)と心得てうけたまはれば、御異見もまたおもしろし。長閑(のどか)なりや長閑なりや、春風(はるかぜ)とこしなへに鼻の頭(さき)を吹き、彩雲(さいうん)脚下(きやくか)に起(おこ)る、身は此(この)まゝに真人と化(くわ)して、胸髭(むなひげ)ありながら心は総角(あげまき)の昔に返る嬉しさ、欲(よく)もなければ罪もなし、名もほしからねば徳も忘れつ。仙台平(せんだいひら)の袴(はかま)さや/\と音さして厳(いか)めしく四角に坐り、足に麻痺(しびれ)をきらす窮屈な礼儀なんぞは三千里外(りぐわい)に吹飛ばした後(あと)、半跏(あぐら)ゆたかに天真全(まつた)く片肌ぬぎの愉快、月白く花霞んで悠然(いうぜん)たる境界(きやうがい)、人間の休戚(きうせき)にあづからぬ気楽さ。極楽(ごくらく)は十万億里の其(その)さき隣(どな)りにあらず、蓬莱(ほうらい)も水煙茫々(ぼう/\)たる彼方(あなた)の果(はて)ならず、唯(ただ)これ酔郷(すいきやう)こそ極楽なれ仙島(せんたう)なれ、とは是昔時(むかし)の人の管(くだ)ぞかし。我今其管の孔(あな)より覗き見るに、酔郷も矢張(やつぱ)り浮世と同じ人さま/"\の体(てい)たらく、可笑(をか)しい哉(かな)/\と、我も其一人(ひとり)で有りながらトロリとしたる眼を光らせて、酒盞(さかづき)の中(うち)に面影蘸(ひた)す色〻の人を見て酔郷のありさまを覚束(おぼつか)なく写(うつ)し出(いだ)す。(「酔郷記」 幸田露伴)
シェーラブ・レティとイトマの出会い
その僧院では女や酒は禁止されていたので、用事があって出かける時は伴僧を同行しなければならない規則(きまり)であった。シェーラブ・レティは時折伴僧とともに使いに出たが、ある時道で美しく魅力的な乙女に出会った。そこで彼は心が揺らぎ、「このような美しい女性を妻にすることができたなら、どんなに幸せだろう」と心の中で考えた。彼は娘に尋ねた。「お嬢さん、何か望みごとがありますか?」娘は言った。「わたしはケーベー・イトマ。居酒屋の娘です。私はお酒を買ってくれる人を探しています」彼は言った。「私は金の入った宝の瓶をもっていますが、今は兄のところにあります。代金は後払いでもお酒を売ってもらえますが?」娘は言った。「もちろんわたしはそれで結構です」それでシェーラブ・レティは娘に続いた。インドではどんな居酒屋でも二階建にすることが許されなかったが、娘の家の地下には広くて大きな住居があった。彼はその一室に入り、その気違い水を飲んだ。しばらくして彼は思った。「イトマ(「美しさと教養を兼ねそなえた魅力的な女性」の意。推定梵語はハーリーティー。これは夜叉(ヤクシヤ)の王女の名で、日本では「鬼子母神」に相当する)はどこで寝ているのだろう。そこで一緒に寝てみたいものだ」その時、イトマは伴僧を一番奥の洞穴部屋に寝かせ、シェーラブ・レティには別の部屋にベッドを用意し、自分は竃口(かまどぐち)の近くで寝入っていた。伴僧が眠っている間に、シェーラブ・レティは娘のもとへ行き、そして言った。「イトマ、あなたは魅力的で、愛らしく、美しい!その躰(からだ)は若くしなやかで温かさにあふれ、その上知恵と知識をそなえておいでだ。その蓮花のような唇に触れる喜びは快く、あらゆる幸福を何倍にも増やすことでしょう。この思いを受け入れ、わたしに身を任せなさい」するとイトマは言った。「その喜びが、わたしの幸せを増やしてくださるかもしれません。でも、わたしは王の刑罰を恐れています。人の噂になった時のことを思うと心配なのです。お酒を飲んで何かしたのではないか。約束を交わしてもいないのに無益に行動する男、狂女の振る舞い、と」イトマがこう言うと、シェーラブ・レティは言った。「若いのに分別ある心をおもちだ。あなたはなんて魅力的で、愛らしく清らかな娘さんなんだろう。では、恨み心のない愛情を育みましょう。お互いの心を曇らすことのない関係になりましょう。お互いの心を温め合いましょう」するとイトマは言った。「婆羅門の息子、知恵をそなえたお方!わたしは美少女ケーベー・イトマ!あなたがわたしの望むことを何でもしてくださるというなら、あなたにわたしの躰を捧げます」それからイトマは彼の思いを受け入れ、愛し合った…。(「ユトク伝 チベット医学の教えと伝説」 中川和也訳)
上京記
牧暁村君-
河岸を変へよう、といふわけで其処を出、今度はもとの有楽町駅のあたりに出来てゐるバラックのカフェーステージといふのに移ってまたウヰスキイです。このカフェーの主婦といふのは死んだ板垣伯の姪だとかいふ人で新劇方面の人たちは大分この人に世話になつてゐるさうです。かなりの姥桜(うばざくら)だが、なか/\の美人です。肥後生れのO-氏、柳河生れの北原君、日向生れの僕、と三人とも九州人である事などが妙に話をはずませて従つてコップの数も無闇と加はります。其処へ、やァ、と言つて入つて来たのは仲木貞一君でした。君はこの人を記憶して居ますか、早稲田の教室で一緒だつた人、そしてその頃から級中一の美男子で通つってゐた人です。さう言へば思い出すでせう。いま中外商業だかの記者をしてゐるとの事でした。とかくするうちに酔も廻り、夜も更けました。いつどうしてそのカフェーステージを出たか、いつ何処で他の人と別れたか、とにかくそれから程経た頃飛びも飛んだり、大森海岸の料理屋茶屋といふのの三階に三人連になつて座つてゐました。三人とは北原と僕とH-君とです。「芸者を呼べ」「何を仰有(おつしや)るんです、もう午前の二時ですよ」などの問答があつたと覚えてゐますが、とにかくそのうちに今の詩壇がどうだとか小説が何だとかいふ話が始まり、とう/\この三人が主になつて来年早々雑誌を出さう、出して斯界を一新する様な鮮かな空気を作つてやらう、雑誌の名は何とする、乃公(おれ)もしつかりする、君もしつかりしろ、などと、果ては火も消えた様な火鉢を中に三人手を掴み合つてベソを掻くといふ始末にまで及びました。気がつけば隣の部屋に床を延いて捨てたまゝ女中などもう一人も部屋にゐなくなつてゐるのです。ただ徳利の林立があるのみです。トロ/\としたかとおもふと軒下を通つてゐる京浜電車の響きに眼を覚まされました。や、これはやかましい、もつと静かな家に行つて飲み直さう、とツイその筋向うの松淺といふのに移りました。ここの料理なども君の記憶にあらうとおもふ。君とは落合はなかつたけれど、佐藤とはよく来ました。昨夜も昔恋しくて初め此処に来たのだけれども、近来料理専業に改めて、お馴染みの古の家に行つたのでした。程なく風呂が沸き、日あたりの座敷のお掃除が出来、鍋だ天ぷらだ海鼠(なまこ)の酢だとごたくを並べて飲み始めました。いつか三味線の音じめが起り、朝日が西日になり、安房上総が海向こうにぼんやりと暮れかゝる頃になつて、えんやらやつとおみこしが上りました。-(「上京記」 若山牧水)
イシドー・アインスタイン
道化じみた外見に俊敏さを押し隠していたが、まるでマンガの主人公のような恰好で、疲れを知らず自分たちのあげた戦果を報告してきた。信じられないほど巧妙なゴマカシと変装をつづけて、五年間で五千人の違反者を検挙し、その大部分が有罪になったし、酒壜五百万本、千五百万ドル相当の酒類を没収した。一九二六年までニューヨーク市で検挙された禁酒法違反者は、イジーとモーの巧妙な捜査活動の成果が実に全体の検挙者の1/5に達した。イシドー(イジー)・アインスタインは、禁酒法の実施当時、四十歳、週休四十ドルの郵便局員だった。妻と四人の子ども、父が扶養家族だったので、いくぶん給料のいい禁酒法取締官にすぐ応募した。オーストリア系で、ドイツ語だけでなく、ハンガリア語、ポーランド語、ユダヤ語を流暢にしゃべったし、ロシア語、スペイン語、フランス語、イタリア語も理解できた。英語でも、たいていの外国語の訛りをわざとつけてしゃべるじょとができた。イジーの最初の目標は、ブルックリンの労働者階級の酒場だった。あぶらじみたコートを着込んで、住民の一人のあとを尾け、酒場に寄って、弱いビールを注文した。立つと五フィート五、体重が半トンもあって、頭は禿げているし、顎は二重にだぶついて、からだがまるまるしているので、パンダのように無害に見えた。「あんた、横から見ると取締り屋みたいだね」とバーの経営者が皮肉をいう。ウイスキーを飲んでいる常連にウケた。最近ニューヨークで雇われたばかりでこのあたりの習慣がわからないのだと説明したが、どう見てもGメンには見えない。値段が安ければ一パイントのウイスキーを買いたい、という。バーテンダーが一本売ってやる、と、イジーはやさしい、愁いをふくんだ声で、彼の基本的なリフレインになった台詞をいう。「気の毒な話だがね。あんたを逮捕するよ」(「禁酒法はどのようにしてニューヨークで失敗したか」 ジョン・コブラー 中田耕治訳)
高知のいい女
高知というところはびっくりするほど酔客の多いところで、夜ふけに大通りを行くと酒ですっかり機嫌のよくなったグループと沢山出会う。この街は南国らしくあっちこっちいろんなところに寛大で、地方都市には珍しく若い女が夜更けまでのんで酔って歩いてもすべてノープロブレムなのだ。酔いつぶれてそのへんに寝込んでしまうメスウワバミも沢山いるそうだ。だから高知の女はおしなべて酒が強い。いまはライト感覚がトレンディだから…などとやわなことをほざきつつ水割りとかナントカドライとかカントカライトなんてものばっかしのんでいる東京の若い男などはもうとうてい太刀打ちできないだろう。高知の宴席あそびに「べく杯」や「箸拳」というのがあって、以前料亭の女将(おかみ)におしえてもらった。べく杯はサイコロを使った大、中、小の盃の強制的のみくらべだ。これでしこたまのんで次に箸拳をやった。喧嘩腰とも思えるような凄い剣幕でびしびし攻めてくるその若い女将がかえってえらく魅力的だった。その部屋の屏風衝立(びようぶついたて)はリバーシブルになっていて、酔いが回ってきたところでくるりと裏がえされた、すると裏には昔のあぶな絵というやつが総天然色もので貼ってあり、なんだか頭も体もぐらぐらしてくる、という寸法なのだ。(「おろかな日々」 椎名誠)
ぼくの父
然し、ぼくらの内にある古めかしい骨肉感も決して親の威圧で植え込まれた残痕ではなく、否定できない肉体上の、分身の責任感から来るものなのである。つまり父の酒狂像も人間的短所も、ぼくら数人の子へ、まちがいなく多少ずつ遺伝分配されていたにちがいなく、父が現世でやった影踊りは、自分の影でもあるような羞恥を覚えるからだった。日本間なのだが、二階の父の寝室には、大きな西洋ダンスがおいてあった。あらゆる種類の舶来酒がその棚に並んでいる。父は、寝しなに限らず、枕元にもそれらのビンを並べさせて眠った。ぼくは真夜中によく眼をさました。そして、父の部屋でする微かな物音に耳をすましたものである。それは猫が舌ツヅミでも打つような怪しさに聞えた。ふと、深夜に眼をさました父が、寝床の中で腹這いのままジンやブランデーなどを独りでカクテルして飲んでいるのであった。二度でも三度でも、眼が醒めさえすれば飲む。それが父の習性だった。一升酒というが、父のは底が知れないと、母はよくなげいていた。朝の出勤前から父の姿には酒の香がぷんぷんしていた。自転車はまだ横浜でさえ珍しい物の一つだった。父はその自転車で通勤もし、よく乗り廻っていたらしいが、自転車の上でもポケットからウイスキーを出して飲み走っていたという噂などを母に告げる人もあった。そのくせ泥酔自転車で往来の雛妓を刎ね飛ばして入院騒ぎを背負ったり、八百屋や豆腐屋の店へとびこんで賠償を取られたり、のべつ手や顔に擦過傷をこしらえていた。(「忘れ残りの記」 吉川英治)
大石良雄
大石が浅野家再興の運動をすすめたやり方は、きわめて現実的だった。幕府の重臣や大奥へ手を回し、知り合いの僧侶を介して悪名高い護持院隆光や護国寺の快意などにも浅野家再興運動の枠を広げている。おそらく多分の賄賂(わいろ)も辞さなかったであろう。彼が京都の山科で寓居していた時期、祇園や島原、伏見などの遊里でお大尽遊びにふけった話は有名である。「うきさま」などと遊里で呼ばれ、小唄など作って悦に入っていたという。おそろしく派手な遊びだったので、後年、この内蔵助の遊興は敵方の吉良家の隠密の眼をごまかす苦肉の策であったと解釈されているが、どうやらそうとばかりも言えない気味がある。大石良雄はこの時期に京都の商人の娘を側妾として迎え、討入りの頃には娘は妊(みごもい)っていたらしい。主家再興への熱情と遊興とは大石にとって別に二者対立するほどの大事ではなかった。遊びは遊び、男の本来の仕事とはそれほど関係もなかったのだろう。育ちのよさからくる大らかな気性が大石にはあって、眼鯨(めくじら)立てて勇往邁進(ゆうおうまいしん)するなどという姿勢は、好みではなかったようである。(「江戸人物伝」 白石一郎)
小布施堂
同様の事例が、長野県の「小布施堂」にも見られる。同社は一七五五年(宝暦五年)、長野県小布施町に桝一市村酒造として創業した。古くから栗菓子製造が盛んな土地柄を反映して、同社も早くから栗菓子製造にも取り組んだ結果、同地を代表する老舗企業として全国的にも名声を得ている。同地の「小布施町並み修景事業」は、地元金融機関、町役場、小布施堂の三社が共同主体となって進められてきた地域再活性化プロジェクトであり、一九九八年の日本建築学会文化賞を受賞している。その代表者が小布施堂の市村次男社長である。自治体と民間が同等の開発者としてスタートした点に留意したい。六億円の投資規模を要し、県からの補助金が出る再開発事業にしてはどうかという誘いがあったにもかかわらず、それを断った。他人の金ではなく、あくまでも自前の開発としてこだわり続け、信念をもって町のアイデンティティ創りを貫いてきた。地域の発展が商店街を活性化し、自社の業績反映にもつながるという発想が、同社の積極的な参画につながったのである。(「老舗企業の研究」 横澤利昌編著)
四方の留粕の序
此あかは吾酒(あか)ならず、四方に知る赤良のうし(大人)の醸(かみ)し酒(あか)ぞ。うまらにをせさゝ、さゝをせ/\(さっさおせおせ)と流行唄(はやりうた)に浮(うか)れたりし、安永のむかし、はじめてこちけいの口をひらきて、狂やく(薬)好むたはれ人にすゝめ、手酔(てゝゑい)あしゑひ(足酔)酔(えひ)くるはせ、一筋の路(みち)をともじに踏(ふま)せしより、千鳥あしの跡久しくとゞまり、今も昔に仁宝鳥(にほどり)の、かつしか早稲(わせ)のうま口なる、うしの新醴(にひしぼり)もがなと、ふみのはやしの杉をしるしに、たづね来る人日々に絶(たえ)ず。げに戯(たはれ)もんざうは年月にさまかはりて、あらたなるをおかしと思ふ習ひなれば、何とかやの酒の十とせ(年)をへてそこねざるも、口なれたるはめづらしからず。然(さ)りとて酒つくる才(ざへ)なき人の、しぼり出したるは、新(にひ)しきも味(あじは)ひなし。かくて何をちからとしてたはれうたをうたひ、戯れ文をつくるべき。瓶(かめ)のつくるは罍(もたひ)の恥(はぢ)とか。いざたまへよきあか乞(こひ)にと、書屋(ふみや)とともにうしのみもとに参りて、此殿(との)の奥(おく)の酒屋のうはたまり、あはれ中酌(なかくみ)をだにとこひもとめたりしに、留粕(とめかす)といふ物四十枚(よそひら)ばかりとう出て、かう「白菐」(かび)くさきものながら、幸ひ接骨(ほねつぎ)くすしの泥鏝(こて)にもかゝらず、漬物店(つけものだな)の桶にも入らずて、爰に留粕のとまりて久しきが、さすがに人酔(ゑ)はすべき所(ところ)なんある。かの劉伶(りうれい)が寝むしろに敷(しき)、憶良(おくら)の太夫の寝(ね)酒にあたゝめけんやうに、からの大和のねごといひ出(いだ)すたねとなるべくは、そのしるをすゝり、その糟(かす)をくらひて、ふみ商人(あきびと)の腹(はら)をこやさせよと投(なげ)あたへ給へりしを、やがて寧楽(なら)の桜木にゑらせて、糟堵(かすかき)のかけず崩れず、幾久/\と南総館のあるじとゝもに、禱(ほぎ)くるほすもまづ粕の匂(か)に酔(ゑゝ)るなるべし。 四方歌垣真顔 文政二年己卯正月吉日(「四方の留粕」 大田南畝 浜田義一郎編)
<和風バー>
最近、ワインバーを意識した<日本酒バー>が増えつつあるが、概して値段も敷居も高く、つまみの限られ、そしていかにも「通向け」の演出がなされている傾向がある。これを新型の<和風酒場>と呼ぶことはできても、雰囲気は<赤提灯>からはほど遠い。通常の日本酒バーはワインや焼酎などをおかず、地酒と数種類のアテしか出さないが、新潟市にはこだわりをきめながら、例外的な店がある。醸造酒専門のしゃれたバー「Jyozo」は、県外ではほとんど見かけない新潟産の日本酒に加え、ビールや上質のワインもいろいろ揃え、叮嚀に保管してある。赤提灯のごとく気軽に立ち寄れる店とは言えないものの、静かな環境で県産の珍種を呑み比べるのもよいかもしれない(ちなみに、市内の赤提灯「案山子(かかし)」や「よもぎや」などにも、それなりの日本酒のセレクションがあり、しかも地魚をはじめ、つまみも旨くて手ごろだから、併せて訪れるとよいと思う)。(「日本の居酒屋文化」 マイク・モラスキー)
なまよひ[生酔]酔ッぱらい。(2)
⑬生酔を 大戸上げろと 背負つて来る(樽一〇)
⑭生酔を 踏み台にして 花を折り(同)
⑮渡船 とかく生酔 立ちたがり(同)
⑯生酔を かついで通る 俄雨(同)
⑰娘の生酔 褌 目立つなり(樽一二)
⑱生酔を 家内中出て 落手する(同)
⑲素人の 生酔 松の内斗(ばか)リ(同)
⑳生酔の 女房あたりで ほめられる(同)
㉑生酔は 面白がつて 掃き出され(樽一四)
㉒生酔を ひよッと押へて はなされず(同)
注⑬大戸は、店口の大きなおろし戸。類句-生酔を 家づとにする 花の暮(樽二九)。生酔を 巻きつけてくる 下戸の首(樽二九)(樽三五)。明キ樽と
生酔下戸の 荷厄介(樽五六)。 ⑭花見風景。 ⑮立つてはあぶないというのに逆らいたがる生酔の癖。 ⑯介抱しながら歩いてはいられない。 ⑰女の酔つぱらいの目立つところ。 ⑱家中総出で受取る。類句-生酔を
おや/\/\と 落手する(樽五一)。のし餅の やうに生酔 扱はれ(樽五五)。 ⑲素人の生酔とは下戸の生酔いという意味。 ⑳生酔の介抱は隣近所に知れ渡るので、女房はほめものになつている。 ㉑箒の先キに立つて面白がる。 ㉒おツと危いと押へたが最後、放されなくなる。(「古川柳辞典」 14世根岸川柳) なまよひ[生酔]
観戦記(2)
御両名をアジっておいて、アジリ放しという不手際な私ではない。両々共に強し、木村にして勝負は徹するの悟りを得たなら、又その力量底を知るべからず、めでたくマトメて、宿へ引上げる。又これからが大変。宿は葵荘というところで、ここが同時に明日の対局場でもあった。私は酔っ払ったから、もうねむたいのだが、前名人、碁をやろうといって、きかないのだ。前名人は碁の初段で、升田八段が、また、ちょうど同じくらいの打ち手なのである。私は二目の手合で、前名人に敗れ、升田八段に持碁であった。つづいて、木村升田の対戦となる。これがまったく、喧嘩腰の対戦、碁の方でも、オレが強い、なんの、お前なんか問題じゃない、両者なお酔っ払い、酒席のつづきで、敵愾心猛烈をきわめている。まったく、殺気立っているのである。この一局、木村名人の十目ちかい負けとなったが、口惜しがること、まことに無念の形相である。両々の敵対意識があまりスサマジイから、新聞社の喜ぶこと、私ももとより大喜び。大成会の関本氏まで、これは、明日は面白いですな、すごい敵愾心ですな、とよろこぶような始末であった。(「観戦記」 坂口安吾) 観戦記
土曜日の午前十時
土曜日の午前十時。二人の子供が小学校に行ったあとでアナタは、テレビの前に横になったままうたた寝をしている。寝起きに缶ビールを飲んだ。土曜の朝に、冷えたビールを飲むのは無上の喜びだ。いつもそうするわけではない。金曜の夜にあまり飲み過ぎたりせず、いくつかの良い条件が重なった時に飲む。仕事の上でのトラブルや不快な思いをどこにも引きずっていない。そんな憂いのない金曜の夜に、ノーカット版の深夜映画を観かけたあたりで眠くなるり、ビデオを録画にセットして(アナタの場合、録画したビデオを観る確率は、巨人に入団した時のバーフィールド選手の打率並。二割に届かない)、あとは泥のように眠る。ぐっすり眠ったその翌朝の午前九時半頃に、冷えた缶ビールを一本だけ飲む。オルガスムという言葉は、ノドには使えないのか。あれは至福の時だ。さらに、その憂いなき金曜の夜に妻の生理が重なったりすると、麻雀でいえば、役がイーハンついたような気分になるのが不思議だ。本当になーんの憂いもなく、泥のように、溶けるように眠りに落ちていく。ロード三連戦三日目の試合が雨で中止になったと知らされたロートル野球選手の午前十時頃の気分に、どこか似ていないか、とアナタは想像してみる。(「アナタの年頃」 永倉万治)
県単位で開発した酵母
(財)日本醸造協会から頒布されている清酒酵母(きょうかい酵母)はどれも優良な培養酵母なので、かつて酒造協会を悩ませた酵母が原因の酒の腐造問題はほとんどなくなった。しかし、酒の特色を決定づける要因ともいえる酵母の種類がわずか一三種類と限られており、酒の個性化という点では問題がないともいえない。そこで、それぞれの地方の特性を生かした酵母で酒の個性化、差別化を図ろうという働きが昭和五十年代後半から、まず県単位で始まった。以下、その主なものを挙げる。
・静岡酵母- ・秋田酵母- ・山形酵母- ・長野酵母- その他、広島県の広島2号、広島21号(2号の泡なし株)、せとうち-21(特定名称酒用)、佐賀県の佐工試1号酵母(SK-1、または「ヒミコ酵母」とも呼ばれる)などがある。(「日本酒 百味百題」 小泉武夫監修)
星の郷の銘酒「夢みて候」誕生
一九九一年の秋に関矢さんは、美星町オリジナル酒の開発仕様書を作成して辻本店に渡した。岡山県産の日本晴のお米を五八%にまで精米し、二十一日間かけてゆっくりと発酵させたお酒である。こうして誕生したお酒が、星の郷(さと)の銘酒「夢みて候」である。吟醸酒のほのかな香りと合わせて、スッキリとしたのどごしの良い淡れいなお酒である。関矢さんは、このお酒に寄せた基本的メッセージを、以下の内容に表現している。「吉備高原を駆ける一陣の涼風と、限りなきロマンに培われた美星の風土をテーマに、格調高い香りと、淡麗できめ細かな飲みあきしない味わいの酒質にコーディネート致しました。時代が求める高品質と、現代人の感覚と個性に迎合する展開が可能で、特に若い男女需要層を基本ターゲットとし、なを且つ幅広い層に受け入れられる新たな出会いの酒としたい」一九九二年三月二十五日には、町を挙げてそのお酒の発表会になった。その日は、前日までの雨がまるでうそのように晴れ渡った。会場となった町の中央公民館には、定刻の十一時になると予定した八十人ほどの参加者が集まった。招待を受けた関矢さんは、その時高校一年生になる長男邦彦君を連れて出席した。(「お酒の乾杯!」 西村一郎) ネーミングの楽しみ
自分の稼ぎ
大岡 それは今でも、バーやなんかでも、一流のバーで何人かは自分でやっている女性がいますね。店にいわば軒の借り料を払って、自分の稼ぎをする。あれは古い伝統じゃないかと思いますね。
網野 そうだと思いますよ。遊女の世界についてはいろんな複雑な問題が絡みますけれども、他律的な、売られた女性たちという捉え方をこれまでされてきましたけれども…。
大岡 違うんじゃないかな。
網野 少なくとも中世前期までの遊女については、売られて遊女になったという史料は一つもありません。今まではそんなふうに言われてきましたが、そうした文書は一つもないと思いますね。(「座談会 酒と日本文化」 大岡信・網野善彦・浅見和彦・松岡心平)
大瀁村の破屋へ疎開
昭和二十三年夏八月新潟県大瀁(おおぶけ)村鵜之木疎開先の庭にて大蔵省酒造講習会講師諸君の慰労の宴を張る。日暮涼風至り歓つくるなし
もろもろの 造りの神の集まりて 木の下かげに 酒ほがひする
酒造り 尊き神の かむつどひ この大瀁の 森にうたげす
えだ豆の 青きを酒の さかなにて さしつさされつ 飲めば楽しき
四羽の鳥 つぶして煮れど やせ鳥の 肉のあらなく 皮のみにして
大瀁の 森をとよもす 酒ほがひ 夕かたまけて にぎはひにけり
くせ舞ひの 手ぶり足ぶり をどけたる 友のをどりに 笑ひとどまらず
もろともに よき酒造り 教へつつ この世たのしく すごさなむかな(「愛酒楽酔」 坂口謹一郎)
スローフード、スロードリンクの時代
やはり私たちには、さまざまな意味で「ゆっくり」が必要なのだ。ゆっくり食べて、ゆっくり飲んで、食べたり飲んだりしたものを「おいしいね」と心から楽しむゆとりが必要なのだ。それができれば、一皿の料理が、一杯のお酒が、毎日の暮らしをもっと豊かで潤いのあるものにしてくれるだろう。イタリアで起こったスローフード運動は、自分たちの身近にある食の世界を改めて見直し、愛で、そのすばらしさを多くの人と分かち合おうという趣旨であり、ファストに対するスローということではないかもしれない。しかし、「スロー」というこのキーワードをきっかけに、私たちはいろいろな価値にたどりつくことができるのではないだろうか。だから、新世紀はゆっくりいこう。(「酒席に役立つ読む肴 サラリーマン酒白書」 酒文化研究所編) 2001年の出版物です。
大雅堂(たいがどう) 付妻玉蘭(つまぎよくらん)
池野秋平名は無名、字は貸成。京師(けいし)の人、画名古今(がめいここん)をおほふ。大雅と号(ごう)し、九霞山樵(きゆうかさんしよう)ともいふ。東牖子(とうゆうし)に云く、大雅堂は名をむなしうせぬ士なり。知命(ちめい)の春の歳旦(さいたん)に、
いくつじやと とはれて 片手 あけの春
芳野(よしの)の遊学(ゆうがく)の頃、
葛粉(くずこ)さらす 水まで 花の しづくかな
専門(せんもん)ならねば知る人まれなりと。妻玉蘭は徳山氏の女(むすめ)、画をよくし和歌をこのめり。つねに貧しかれども、貞操(ていそう)にしてよく夫に仕ふ。されば夫婦(ふうふ)衣をたがひにして悪(にく)むことなし。ある時夫(おつと)酒さかなを求(もと)め来(きた)りてともに楽しむ。妻裸(はだか)にして琴(こと)を弾(だん)ずるといふ。大典(だいてん)禅師その墓誌(ぼし)に、玉蘭夫ノ行ニ配ス、と書かれしも、これらの磊落(らいらく)をやいふなるべし。(「俳家奇人談 続俳家奇人談」 竹内玄玄一著 雲英末雄校注)
牡蠣の磯焼き(串焼)
醤油の焼いた香りは、日本人にはたまらない刺激。その醤油焼きした牡蠣に、海苔とゆずの香りがからみます。
●材料
むき牡蠣100g 酒小さじ1 醤油小さじ1 海苔1/4枚 ゆずの皮
●作り方
1 むき牡蠣を濃い塩水(水2カップに塩小さじ2ぐらい)でふり洗い-し、ザルにとって水気を切る。
2 醤油と酒を合わせたものに10分ほど浸けたら、串に刺して焼く。
3 もみ海苔、ゆずの皮の千切り、好みで七味をかける。(「おうちで居酒屋」 YYTproject編)
さかづきあいさつ
さて、ふるまい出(いで)てちうしゆ(中酒)もすミ、二こんめ(二献目)にていしゆ申さるゝハ、下座(しもざ)のおために、おしゆくらう様から、さんをかへておまわしくだされと申けれハ、こゝろへましたとて、中(なか)わんをとりあげ、いづれもしもざのわかいしゆ。らミせしめのために、さんをかへます。(「軽口はなしとり さかづきのあいさつ」 武藤禎夫・岡雅彦編)
酩酊
酩酊。当時の人間は頗(すこぶ)る酒食(さけくら)ひであつた。必ずしも下等社会に限つた事ではない。ポリンブローク卿抔(など)は夜通し飲みつゞけて、明る日役所へ出勤するときには、濡手拭(ぬれてぬぐい)を頭へ巻きつけて事務を執つたとちやんと歴史に書いてある。シェリダンとかピットとか、フォックスとか云ふ連中は一度に葡萄酒の壜を六本宛空けたとの話だ。いくら西洋人が酒が強いと云ても現今の人は是程飲めないさうだ。当時の政治家や何ぞが統計上長寿を保たなかつたのは全く飲酒過度の為だと云ふ人さへある。上流ですら斯うだから下層社会に至ると、無論激烈極まつた者である。かのginと称する酒が此仲間うちに流行(はや)り出したのも全く此世紀の始からである。尤(もっと)も是は外国(平川註、オランダ)から輸入した酒である。此酒が倫敦(ろんどん)の下層社会に突然と大勢力を振ひ出して、彼らは遂にgin狂とも云ふべき一種の病気に罹つた。ホーガースは『ビール街とジン小路』と云ふ絵を画いて其景況を今日迄伝へた位である。需要が斯うだから酒舗は次第に増加する。遂には五六軒に一軒位の割で町内に幅を利かせると云ふ始末になる。飲む奴は一片志(ペンス)で酔ふ、二片志で寝る。酒屋には台があつて其の上に乗つてぐう/\寝る様な仕掛に出来てゐた。労働者は夫婦共小供達を抛り出してジン屋へ入り込む。腹掛のかくしに銭が見当らないと道具一切手当り次第に売り飛ばして迄酔払つて見せると云ふ有様である。仕舞には政府でも大いに驚いた。已むを得ず法則を発布して、ジンに多額の税を課して、貧乏人どもが容易に飲む事の出来ない取締法を設けた。宴会の時などでも今日と違つて、大分乱雑であつたらしい。骨抔を手で取つてピチヤ/\しやぶつたと云ふ。夫れから一つ皿の肉を二人も三人もで、互ひに切つて食ひ合つた事もあつたので、ある時さる男が鶏を切つて、わが分を盛り分けやうとしたら、つい他(ひと)の指迄切つて仕舞つて、しかも御叮嚀に之を自分の皿の中に持つて来たと云ふ話さへ伝つてゐる。(「西洋文学と文明」 平川裕弘) 18世紀ロンドンの酩酊を書いた夏目漱石の文章だそうです。
現代の徳利収集譚
古陶器収集家Kは、先輩Aのもっている志野の徳利が欲しくてならなかった。その徳利は、伝世と思われる柳葉文の鉄絵のあるもので、肌色といい、姿といい、大きさといい申し分のない徳利であった。Kは先輩のAに、数年間にわたって徳利の譲渡方を依頼していた。しかし、Aは「他のものならともかく、この徳利だけは命から二番目のものであるから、いくら親しい貴殿といえども譲るわけにはゆかない」とがんばるのであった。Kはその徳利が欲しいばかりに、終始A先輩を訪問し、何くれとなく先輩の面倒をみてやった。AもしまいにはKの誠意、熱意にほだされてか、「私の生きているうちは渡せぬが、私が死んだら貴殿に譲る」というまでに至った。さて十年ほどして、老齢のAはその徳利を枕元になくなった。徳利を譲ってもらえる約束になっているが、葬式がすんですぐではあまりにも遠慮がなさすぎると思って、一ヶ月ほどしてから未亡人宅を訪れた。未亡人はすっかり気を落としていたが、年来の友人が来てくれたので喜んで迎えてくれた。まずは一献とて酒肴が出された。あの徳利が出たのである。Kは思わず息をのみ、手が出そうになったが未亡人のいうようには「この徳利は主人の命から二番目にたいせつにしていたものです。この徳利を主人と思って、これからのわずかな余生を送るつもりです」。Kとしては、A先輩との約束を夫人同席でしておかなかったことを悔いたが、さすがにその場はいい出せずに帰った。しかし、どうしても気がおさまらない。Aとはあれほど固い約束をしたのだから、未亡人に話せば判ってくれるにちがいない、と意を決して、また出かけていって未亡人にそのことを話したのである。聞き終わって未亡人は、眼に涙を浮かべながら「判りました。それとは知らず失礼しました。ここで改めてKさんにお願いしますが、私もこの年で余命いくばくもありません。私の死ぬまでこの徳利を私の胸に抱かせておいていただけませんか」というので、Kも言葉が返せず、承知してそのかわり、その旨文章にしてもらってきた、というのである。この話は進行形である。Kも未亡人も生きている。kは今や毎朝ランニングにはげみ、くこ茶を飲んでは健康増進にこれつとめている。Kは「なんとか長生きして、あの徳利を手にしなければならないが、どうして神さまは男より女を長生きさせるのだろうなあ」となげくのであった。(「徳利と盃」 小松正衛) 昭和50年の出版です。
利き酒師の講演会
すすきのの飲食業にかかわる方たちの「アラ!あずましい会」が主催する「すすきのの活性化試飲講演会」に行ってきました。今回は、もっと日本酒をということで、講師は女性ソムリエの佐々木恵さん。日本酒の利き酒師でもあります。会場には「バーやまざき」の山崎マスターのダンディーなお姿も。八十三歳(2004年)にしてバリバリ現役バーテンダー。数年前には利き酒師の資格も取られたとか。お話は原料米の種類や仕込み水のことなど、日本酒の基礎知識から始まりました。日本酒ならではの特性も面白く、熱燗(かん)のシャーベット状の酒まで、飲用温度帯の幅がこんなに広い酒は他にないこと。アルコールは身体を冷やす効果が高いのに、日本酒はそれが低くて身体に優しい酒だとか、知っていると飲む楽しさも倍増しそうです。そのほか、料理のマイナス面を引き出すことが少ない。お米が原料だからアミノ酸が多く、活力を与えてくれる。美白効果が高い。高度な醸造技術が必要で、伝統的価値が高く、日本の食文化の粋とも言える存在であることなどなど、日本酒好きな私には、ひとつひとつ納得のいくお話。帰り道、「夕食は日本酒の飲める店へ行ってみます」と、楽しげな山崎マスターのお話。でした。マスターのパワーの素のひとつには、こんな若々しく、好奇心のあふれるお気持ちがあるからなんだと、またまた納得の私でした。(「さしつさされつ」 中田耀子・土倉裕之)
文学と飲食
これに対して、、日本では、飲食場面が描かれている作品となると、かろうじて中世の『宇治拾遺物語』から、開高(健)もさきほどのエセーであげている江戸時代の西鶴や芭蕉まで飛んでしまう。もちろん、日本にも飲食文化はあったし、世界的にみてもめざましい江戸期の外食産業の発達や、世界各地まで出かけて釣りあげたマグロやカニを競って食べさせる現在の盛り場のにぎわいを知る身には、たぶん、食べたり飲んだりすることに禁欲的なプロテスタント系のアングロ・サクソン文化より、そうしたことを楽しむカトリック系のラテン的文化に近い<心性>があったとさえ思う。日本人は思いのほか<食べたり飲んだり>を享楽する民族なのだ。さらに、こうした物語として造形された文学作品以外の、日記や書簡などの私的分書には、しばしば飲食の記述がみられることも忘れてはならない。たとえば、室町時代初期から戦国時代末期にかけて、京都の公家(くげ)山科(やましな)家の一族が親子四代にわたり残した日記が活字化されており、それは当時の風俗を知る貴重な資料となっている。これをもとに時代の飲食を酒を中心に復元し解説した吉田元の『日本の食と酒』を読むと、当時の貴族たちが祝いごとや行楽のおりに、じつによく酒を飲んでいるだけでなく、そのことを真剣に書き記していて、そのまめぶりにあきれるほどだ。ところがである。そのように楽しげな飲食が行われていたにもかかわらず、その文学的表現となると、今度は読むほうがかなりこまめに探さないと見つからないのである。(「「飲食」というレッスン」 福田育弘)
なわのれん(縄暖簾)
[名]安い飲食店。現在は居酒屋。飲み屋。🔶『東京風俗志』中の巻・第八章(1899~1902年)<平出鏗二郎>「酒屋はもと酒を売るを主とし、特に客をひいて店頭に飲ましむることなし、其のこれあるは所謂縄暖簾[此類の飲食店の習として門口に縄暖簾を懸くるを以て此称あり]にして」🔶『かくし言葉の字引』(1929年)<宮本光玄>「なはのれん(縄暖簾)下等な飲食店のことをいふ」🔶『安城家の兄弟』微罪(1931年)<里見弴>「縄暖簾を掛けた表口に立つて案内を乞ふと」(「日本俗語大辞典」 米川明彦編)
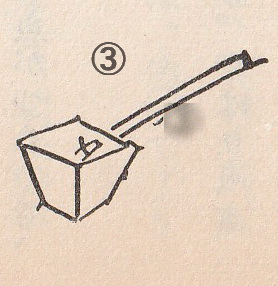
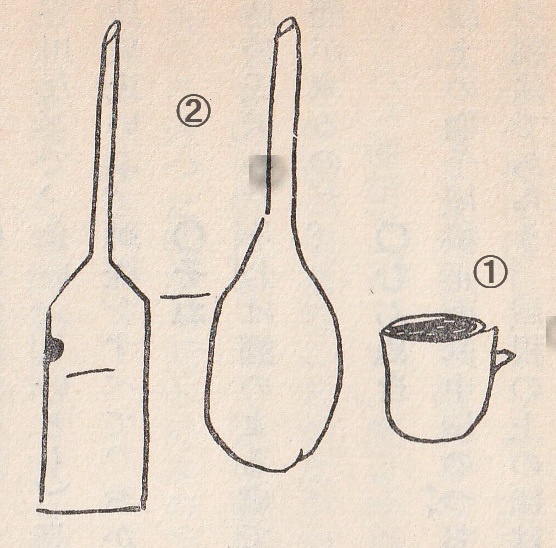
〇酒柄杓
酒柄杓には三種ほどある。新式のは此形の酒にーぶ(①)である。ぶりきで作る。此は、近頃よほど少なくなつたちぶる瓜(瓢箪の一種)でこさえる所謂(いわゆる)ちぶる(②)である。かう言ふのから出て、陶器製の黒ぬりで、片口に近よつたものもある。南山の神あしやげの大城家の主人は、おまちいににーぶとりをつとめる。神たちに上げ、神人等にももつてやる役である。その杓とりの柄は大和風(③)のものである。(「沖縄採訪手帖」 折口信夫)
酺
また、漢の文帝(在位前一八〇~前一五七)以後の帝王はいずれも常に大酺の挙をしており、中でも武帝(在位前一四〇~前八七)は、その一代で五回もの大酺を発している。「酺(ほ)」というのは「大いに酒を飲むこと」であり、「大酺」は群衆が大いに飲むこと、「酺五日」というのは群衆が会合して五日間にわたって酒を飲むことである。これら酺や大酺が行われるのは、時の王朝(王室)の大きな慶事の都度であり、いわば「ふるまい酒」のようなものであった。これらのことを見ても、当時の酒造りの規模はかなり大きかったようだが、このことはまた、以前に増して国を挙げて酒を飲む機会が多くなっていることを示しているものである。(「銘酒誕生」 小泉武夫)
某月某日
起き抜けに山に登り、帰宅してしばらくすると、大阪新聞の亀井氏から電話があり、酒をテーマにした随想四枚書けと要求された。題が題だから、これはらくに書けるであろうとOKする。雑誌『酒』から速達が来た。創刊十五周年記念号に随筆を書けという。この雑誌の主宰する文壇酒徒番付けに小結に推された義理がある。OKの返事を出すことにした。午後、小説現代から電話があった。『酒中日記』を書けという。こうなれば、酒のことならなんぼでも書けそうな気がして、OKと即答する。あとで静かに考えてみた-いったいなぜ、こんなに酒のことばかり私は書かなければならないのか?(「酒中日記」 吉行淳之介編)
敗北
ところでお酒だが、机の向かって左の、一番上の抽斗(ひきだし)には少々入っている筈だ。ふと名案が浮かんだ。長男に持ってこさせよう。彼は目下浪人中である。しかしたまには親子で一杯やるのも面白かろう。実は身長五尺八寸強、足袋は十一文半という大男の、白皙(はくせき)の長男が自慢でないこともない。ひとつここにいる若い女性たちに、この長男を見せて、大いに己の威信を高めてやろうという色気が手伝った。そこで家ヘ電話をかけさせて、長男に金を持参させた。酔っているから、どの位経って長男がやってきたかわからない。気がつくと大男が私の向うにかしこまっている。一杯注ぐと、ぐいと飲む。また注ぐと、ぐいと飲む。蛇が蚊を飲むとはこのことだろう。若い頃は最初のうちはどんなに早く飲んでも平気なものである。まわりの女性たちに向かって、これは己の長男だが、構わぬからどしどし注げといった。気がつくと、私のまわりにいた女性たちはみな長男の方へ行ってしまっている。彼は女性たちにかこまれて、顔を少しうつ向け加減にして、注がれるままに、ぐい、ぐいと飲んでいる。女性たちはしきりに彼に何か話しかけている。彼は言葉少なに答えている。時にはただ「ええ」とか「いいえ」とかしかいわない。そして、ぐい、ぐいと飲んでいる。私の杯は空である。誰もこれに酒を満たしてくれようとはしない。そこにいた女性たちは全部長男の方へ行ってしまった。私がその店に通い始めて一年の月日が経つ。長男はその晩初めてここへ来たのである。一年の客は、空の杯を見つめている。一夜の客はまわりからわいわい騒がれて、ぐいぐいと酒をあおっている。酔中ではあったがこの時ほどわが身の老いをしみじみと味わわされたことはなかった。威厳もへったくれもない。相手が若い女性である場合、若さには絶対かなわない。翌朝、私は女房に向って宣言した。「己はもう決して××と一緒に飲みに行かないぞ。」女房は「どうしてでございますか」といってから、少し笑った。(「若気の至り 年寄の冷や水」 高橋義孝)
井伏と田中
井伏鱒二は飲みはじめると長期戦となる。杯を飲みほす間隔が、人より悠長のようだ。それだけ酒を味わっているのだろう。だが井伏に最後まで付き合える酒豪はそういない。いつの間にか酒宴から脱落していく仲間を見て、井伏は「一人去り、二人去り、か」と淋しがるのだという。そんな井伏も、文壇に頭をつっこんだ当座は、あまり悠長にいかなかったらしい。田中貢太郎をはじめて訪ねたときは、酔いつぶれて人力車で下宿まで送りとどけられた。しかし、その飲みっぷりを田中が認めて、こういったという。「ほほう、君はなかなか飲むきに、みどころがある。さうじや、大いに飲め飲め」以来、田中とはよい飲み相手であった。それが深いえにしとなってか、井伏が結婚したとき、仲人には田中がなった。田中も井伏も日本酒を好んだ。井伏の故郷は酒王国である。銘酒もそれだけ多く、いわゆる酒のお国自慢を、彼は篠原文雄に語ったことがあったという。「酒は、呉市の千福、西条の賀茂鶴、三原の酔心と旭正宗、福山の三吉正宗などが代表的といえよう。ずっと以前、西条に明魂というすばらしい酒が出来ていた。この酒を口に含んだときは水のように淡く、飲みくだすときいい匂いと味が伝わってくると、すぐ顔のあたりが暖かかくなる。芳醇というのはこんな趣のものではないかと思う。生前のころ、酒仙の田中貢太郎さんが、はじめてこの酒を一口して"いい酒だなあ"と泣き声を発した。確かに泣いていた」(『日本酒仙伝』)酒のうまさに泣きながら飲むとは、まさに酒仙というべきだろう。そんなときはついつい深酒になってしまう。
しかし井伏は大酒を飲んだ翌日も仕事を怠るようなことはないらしい。そんなときはノルモザンを飲んで、ぬれたタオルで頭を冷やしては一行書き、また冷やしては一行書き、といったふうに書くのだという。(「文壇資料阿佐ヶ谷界隈」 村上護)
昼間の花見
そのうちに、シャンペンも飲み尽くし日も陰って寒くなってきたので、花見の宴もお開きとなった。私の相手の人たちは、それから会社に帰ってしなければならない仕事があるので、いずれにしても、のんびりとしているわけにはいかなかった。花見の宴の鮮やかな光景はいつまでも記憶に残っている。それほどに楽しかったのである。そこで、この次の年には同じ場所で夜ゆっくり集まろうではないかという提案が出てきたが、私は反対した。楽しさが大きかったのは、時間が限られていたことが理由の一つである。それに、ほかの人たちが選べない時間帯に集まったことも、もう一つの理由である。私以外の人たちは、仕事を抜け出してくるというやましい気持ちを抱かなくてはならない。そのちょっとした後ろ暗さの中に、小さなスリルがある。私自身も、ほかの人ほどには組織に縛られてはいないが、花見の時期とはいいながら、昼間おおっぴらに酒を飲むというのは、多少気が引ける。私にも程度の差はあれスリルがあるのだ。世間の常識から少し外れるところが面白い。外れすぎては、周囲のひんしゅくを買うが、「ちょっと」という度合いが重要である。また「たまに」という要素も必要だ。いつも常識を無視していたのでは、単なる「風変わり」の人といわれるだけである。(「酒を味わう・酒を愉しむ」 山崎武也)
黒ぬり、朱ぬり
〇黒ぬりの杯、むかしの物にあり。彼香炉木に倣(なら)へるものか。されど朱ぬりは、猶貴きもの也。『西宮記』、十月朔日旬条下に、「延喜十六年四月廿八日宣旨、無二侍従一者為二出居一、此ノ日親王四人参-上、太子以二朱器ヲ一為二飲具一、無レ蓋」。これ朱漆の杯なり。かく記せるも、杯は常に土器を用る故也。『塩尻』に、「或人問、古へ我国の盃如何。答云、上古盃は土器のみ、漆ぬりは中世已来か。相州鎌倉教恩寺(時宗也)に、昔平重衡、千寿の前と酒宴せし盃とて、寺宝あり。大さ今の平ざらの如くにして、浅く薄し。内外黒にして梅花まき絵、是中古の酒杯也云々」(といへれど、朱の飲器、前にいへるがごとし)。(「嬉遊笑覧」 喜多村筠庭)
共食
口割りは馬に轡(くつわ)をはませる意味だろうが、同県(新潟県)北蒲原郡でも旧二月一日の奉公人の出代わりの日に団子粥を食わせて、これを轡団子又はクチワリ団子といった。ここでは結婚の約束酒もクチワリザケというそうである。三三九度の盃を軽率にとりかわす者がないように、一緒に飲みかつ食うということは相互の親近性を生じさせ、相互の連帯性を確認させることである。事業をはじめる時の契約の食事、友人同士が一緒に飯を食おう、お茶を飲もうといって、共食によって友情をあたためている風景は現代でも至るところに展開されていて、まことに物いりではあるが、将来の食生活においてもこの面が特に考えられなければならない点だろうと思う。
462ゆっくり後で
青年「僕、お宅のお嬢さんと結婚したいのですが、…」
父親「君はお酒を飲むかね」
青年「有り難う御座います。でも、このお話の方を先に決めて戴きましょう」(「ユーモア辞典」 秋田實編)
ちいママ娘
スナックやクラブでママを補佐するちいママと同じように、家事手伝いで母親を助けるといって、家でブラブラしながら、気が向いたら父親の世話もしている独身の娘。大学を出て二、三年は会社勤めをしていたのだが、周りの友達が結婚退職で次々と会社を辞めていくので、自分も結婚を名目に退職、家にいるのも結構居心地よく、週末には父親の晩酌につきあい、ビールをついだり水割りを作ったりサービスするところなど、まさにちいママ。(「新語×流行語小辞典」 稲垣吉彦)
のみくち【飲口】
酒を飲む事。『今夜は飲み口がある』又は『近来飲み口がない』等と云はれるのである。
飲み口があると羽織を借りて行き 余所行の羽織持たず(「川柳大辞典」 大曲駒村編著)
竹酔日(ちくすいび)
竹植える日 旧暦五月十三日は竹酔日といって、この日に竹を植えると必ず活(い)きるといわれている。今は廃れているが、竹酔日という言葉も面白く、古い題として一応存する。
降らずとも竹植うる日は蓑(みの)と笠 芭蕉
竹植ゑる日も人の来て遊びけり 志朗
聖賢の徒にあらねども竹を植う 下村非文
竹植ゑて即(すなは)ち無為を楽しめり 大橋越央子(「新改訂版 俳諧歳時記 夏」 新潮社編)
コチ
コチは夏が旬の白身魚で、マゴチという。そのまま刺し身で食べてもいいが、洗いにすると涼しさも加わってことのほか美味。「洗い」は刺し身を氷水の中でかきまわして、余分な脂や魚臭さを抜き身を締めるという、実に夏向きな手法である。しかし、かの北大路魯山人大センセイは、「洗いには氷水ではなく、井戸水を用いるべし」とおっしゃる。冬温かく夏冷たい井戸水は、氷水ほど冷たくなり過ぎず、洗いには最適なのかもしれん。でもなあ、井戸なんてウチにはないんだよ。コチは魚体が台形をしていて、シロートがおろすのはむずかしいので、サクになっているのを買ってくる。それをなるべく薄~くそぎ切りにして、氷水の中でかきまわす。水気をふいたら、氷を敷き詰めた器に盛って完成。私はこれを、スダチ醤油もしくはレモン醤油で食べる。そして、軽く冷やした吟醸酒を合わせる。。日頃、常温や燗を愛する私であるが、洗いにはさすがに冷たい酒がいい。(「晩酌パラダイス」 ラズウェル細木)
<山の神>
夜ふかしの好きな男が二人、ウイスキーグラスをかたむけながら、打ちあけ話をしていた。「さあて、帰るとするか。しかし、山の神がいると思うと気が重いな。君んとこは、遅く帰ると奥さんなんて言う?」「ぼくには女房、いないよ」「エッ!、それじゃ、なぜ遅くまで飲んでるんだ?」(「酒飲みを励ます本」 志賀貢)
乱酔狂筆を揮いて捕縛せらる
明治三年(一八七〇)十月六日、東京下谷不忍弁才天の境内にある割烹店林長吉の店で、俳人其角堂雨雀という人が書画会を催していた。飲み友だちの(河鍋)暁斎は席上の揮毫を頼まれて、朝早くから書画会へ臨んだ。其角堂も酒豪だったので、客の顔も見えないうちから、さっそく盃を廻し始めて、人が集まる頃は二人で三升(五・五リットル)余りも飲んでしまった。暁斎は大酔していたが、席上揮毫が始まると依頼に任せて闊達に筆を揮った。人々は暁斎に頼む時は盃の代りに茶碗や丼を差し出して「先生一つ献上致します」と言って扇面や唐紙などを出して染筆を乞うので、六升飲んだか七升飲んだか、暁斎は鬼灯提灯のように赤くなって筆を揮い続けた。そんな時傍らに高声で話す者があった。「今日王子へ行ったところ、一人の外国人が騎馬で来て茶屋へ入るんだ、女中どもが今日はお一人ですかと言うと、外国人は、一人ではありません。馬鹿を二人伴れて来ましたと答えたので妙なことを言うと思って見ていると、遅れて髭を生やした官員が騎馬でやって来たのには驚いた」と。その話が暁斎の耳に入ると暁斎は筆を執って、足長島の人物に二人して靴を履かせている図と手長島の人物が大仏の鼻毛を抜いている図を描いた。この外国人に仕えている人物の顔が当時廟堂に立っている大官に似ていた。しばらくして、警官が踏み込んで来て席上大混乱のうち暁斎は捕えられたが、暁斎は泥酔していて縛られたのも知らず、陽気に踊りながら引かれていった。獄舎で千悔万愧したのは酔が覚めてことの次第を聞いてからだった。同月十五日、呼び出されて糺されたが泥酔していて覚えがないと答えたので再び禁錮された。翌年正月三十日、百十日ぶりで赦免された。
永昌源
日本人が本格的に中国酒に親しみ出したのは昭和に入って、日本人が大量に中国大陸に進出した頃からである。特に満州国が成立し、戦線が大陸に広がった時代、開拓民、兵士などが組織的に大陸に渡った。これらの人々は貧しく、大陸で高価な日本酒には手が出ず、日本酒よりはるかに安く買えて、酒度の高い、当時日本人間でチャンチュウと呼ばれた中国酒に酔いを求めた。(日本酒一升二円、中国酒一升八四銭、一九四一年『満州国公定価格便覧』)。このようにして、中国酒の味になじんだ人々が一度に日本に引き揚げ全国に散って行った。このような中で、満州奉天(現在の東北瀋陽市)の酒工場で働いていた木村仁一、田中亀蔵、柏倉俊世、青柳正次氏らが昭和二十三年、埼玉県の深谷市に永昌源という中国酒専門工場を開設、老酒、白酒、杏仁酒などを製造、需要も増え、大工場になって現在に及んでいる。二〇〇〇年に及ぶ日中交流の中で、日本における中国酒の第一号工場である。(「一衣帯水」 田中静一)
道楽
道長がどの位出世したか、詳しいことは忘れたが、何でも関白太政大臣あたりまで行って外戚になれたという程度のことだったように覚えている。しかし道長は、それでもういいと思ったので、これはまた、大臣になることを命と取り換えても有難がる俗物根性とも違っている。要するに、足りることを知るときに満足するのであって、それは出世したあとでも構わない。そうすると、顔回の一瓢の飲も、どうせただの水だったのだろうが、申し分がない一つの例になる。孔子によれば、顔回はそうして道を楽しんでいたことになっている。道とはどういうものなのか、これも確かなことは解らない。しかし顔回が酒も飲まず、おでんも突っつかずにこれが楽しめたのならば、本当のに楽しんだ以上、それはもうこの頃は余り聞かれなくなったいわゆる、道学者流の道とは別なものだったに違いない。そう言えば、道楽という言葉がある。何かの道を楽しむのがもし道楽ならば、顔回の道楽などは相当凝っている方で、我々も時々はおでん燗酒でこの境地に近づくことがある。つまり、その酒がただの水で、おでんがおかずなしの御飯でも楽しめたのなら、顔氏がこの道の達人だったと見るべきではないだろうか。孔子と、少なくともその直弟子達は確かに楽しむことを知っていた。楽しむことが一番いいのだと孔子自身が言っている孟子がつまらないのは、彼には道楽の精神が全く欠けているからである。(「続酒肴酒」 吉田健一) 論語にある「子曰、賢哉回也。一簞食、一瓢飮、在陋巷。」(しいわく、けんなるかなかいや、いったんのし、いっぴょうのいん、ろうこうにあり)の一瓢は、酒ではないようです。
カウンター
ところで、鮨屋さんのカウンターも、男のバーのカウンターも、たとえやき鳥屋さんのカウンターでも、あのカウンターは、ただ食べ物や飲み物を置くだけのものじゃないんですね。そこに、この間、ふっと気づいたんですが。いろんなカウンターがありますが、幅が広くても四、五十㎝ぐらいが普通なんですね。その幅が、お店とお客との礼儀だったり、立ち入ってはいけない距離だったりしているんですね。だからあくまでも、客としての立場と、お店としての立場を乗り越えない方がいいんですね。居酒屋から、縄のれん、そしてバーから、いろんなカウンターが数多くありますが、鮨屋さんのカウンターは、男を磨く、王様のカウンターですね。(「おとこ町六丁目」 荒木豊久)
トム・アンド・ジェリー
急に秋めいてきたせいか、風邪をひいた。売薬をのみかけ、ふと思いついて玉子酒をつくることにした。玉子酒といっても、ぼくのは洋風。トム・アンド・ジェリーという名前の、ちょっとハイカラな玉子酒なのだ。つくり方を簡単に説明しよう。まず玉子を一個用意し、黄身と白身に分けて、別々に泡立てる。そして黄身の方に砂糖を加え、ツヤが出るまでさらに泡立ててから、白身と合わせる。そこへラムとブランデーを注ぎ、全体をステア。あとは、温めておいた耐熱グラスに移し、熱湯を注ぐだけである。-
このトム・アンド・ジェリーは、かつてのアメリカではクリスマスに飲む酒だったという。一時はすごい人気だったらしく、ラニアンも"クリスマスとはこの酒を飲む口実に発明されたものだと信じてる者さえいるんだ"と書いている。-
諸説あってひとつは英国の作家ピアス・イーガンが書いた『ライフ・イン・ロンドン』の中に登場してくる、トムとジェリーという酒好きの人物に因んだというもの。あるいは、ドライ・マティーニを創作したジェリー・トーマスが発案したカクテルで彼の名前に因んだという説もある。ぼくは、この酒の前身とでもいいたいようなカクテル、グロッグが英国生まれであることから、ロンドン説の方に信憑性を感じている。(「今夜は何を飲もうか」 オキ・シロー)
一升入(はい)る壺(つぼ)は一升
一升はいるつぼは、一升ははいるが、それ以上ははいらない。物・人、共に限度がある。松葉軒東井(しようようけんとうすい)の『譬喩尽(たとえつくし)』(一七八六年)に掲げる。「一升入るふくべは一升」の項参照。
一升入(はい)るふくべは一升
一升入りのひょうたんは、はいるのは一升だけ。太田方(おおたほう)(一八二九年)の『諺苑(げんえん)』(一七九七年)に掲げ、<一升入りふくべは大海へ入りても一升」ともいう。<論衡いう、器受クルニ二一升ヲ一、以(もつ)テスレバ二一升ヲ一、則(すなわ)チ平ラナリ。受クルコトレ之(これ)ヲ如(も)シ過グレバ二一升ヲ一、則チ満溢也(まんいつなり)。沙石集いう、一升入り餅(もち)はいずくにても一升入りといいける。>と注記する。「一升入る壺(つぼ)は一升」の項参照。(「飲食事辞典」 白石大二)
居酒屋等のアンケート調査
人々が支出できる飲酒代がこれだけ減ったのだから、居酒屋の経営が苦しくなるのも当然である。-
居酒屋・ビヤホール等の売り上げは、九二年一兆四六二九億円をピークに減少を続け、一三年には一兆九六億円と、ピーク時の七割以下にまで減った。外食産業全体が低迷しているが、なかでも居酒屋・ビヤホール等の落ち込みは激しく、外食産業全体に占めるシェアは四・二%にまで減少している。居酒屋の減少も著しい。経済センサス(二〇〇六年までは事業所・企業統計調査)によると、二〇一四年時点の全国の酒場・ビヤホールの数は、一二万五二八一店である。二〇〇四年は一五万七一九店だったから、わずか一〇年間で二万五四三八店、率にして一六・九%も減っている。残った居酒屋も経営難であることが多く、また高齢化と後継者難が深刻である。二〇一四年の「個人企業経済調査」によると、飲食サービス業の事業主の三八・三%が六〇歳以上、さらに二七・三%は七〇歳以上である。後継者がいるのはわずか一四・七%に過ぎない。今後については、「廃業したい」との回答が一五・八%あった。これは飲食店全体についての集計結果だが、外食産業全体に占めるシェアが低下傾向にある居酒屋が、さらに厳しい状況にあることは容易に想像がつく。(「居酒屋の戦後史」 橋本健二)
登城前から二升ぐらい
そんな政局を一人で取り捌かなければならないのだから、(阿部)正弘は激務から離れられなかった。健康を害しても無理はない。傍目も憔悴が激しかった。安政四年の五月頃には、会って話をすると正視が憚られるほどげっそりしていて、絵に描いた幽霊のようだったといわれている。それなのに、人はまたしても心ない噂を広めるのだ。口さがないお茶坊主たちは房事過多と飲み過ぎのせいにして「十五歳の新しい妾が出来たので励みすぎだ。酒も登城前から二升ぐらい飲んでいるそうだ」と面白半分に喋り立てる。(「大江戸曲者列伝」 野口武彦)
中原早苗
もはやベロベロに近い中原早苗が電話でしきりに口説いている相手は、新進気鋭の監督・深作欣二である。「すぐに来い」と呼びつけられた深作欣二は、練馬の撮影所から深夜の道をタクシーをとばしてやってくるのだが、いくら深夜でも原宿までは小一時間。「欣二、遅いじゃないか。愛してないのかよ…」あたりはばかる神経など、もうとっくの昔に早苗の脳から消えている。全くシラフの深作欣二は早苗に叩かれたり、つねられたりしながら微苦笑を浮かべ、居合わせた私たちは、この二人にあてられっぱなしだったのであった。それにしても中原早苗の痛飲ぶりはすさまじかった。女性が酔うと、その開放ぶりってのは男の比ではなく、抑圧が一気に解けて、感情はストレートに現れる。早苗にほれてる深作欣二はいいだろうが、周囲はたまったものじゃない。大原麗子はよく我慢していたものだと思う。間もなく二人は結婚した。深作夫人となって、にわかにしおらしくなった早苗に戸惑いながら、まぶしい思いで二人を見たのも、もうかなり昔の話である。(「いい酒いい友いい人生」 加東康一)
二十四針
「ある(台湾の)ホテルのレストランで、中国の古典音楽が演奏されていたんです。あちらの礼儀に従えば、静かに聴いていないといけない音楽だったんですが、梶原先生と私たちの席はウワーッと盛り上がっていた。すると、他の席にいた雲をつくような白人の大男三人が-アメリカの軍人か船員でしょうねえ-やってきて、『シーッ』。静かにしろと言うんですね。『シーとは何だ!』と梶原さんは怒りましたが、お忍びだから騒ぎになっちゃまずいからって、押さえてもらったんです。すると…」しばらくして、梶原がトイレに立った。が、なかなか戻ってこない。心配になった藤岡が見回すと、梶原はトイレの方角から自分の席に向かわず、先の白人たちの席に歩みを進めているではないか。先方も気配を察し、拳(こぶし)を固めて身構えている。「先生-っ」引き止めに行った藤岡は、たちまちワンツーパンチを食らってダウン。かけていた眼鏡も、どこかに吹っ飛んだ。梶原は三人の大男を向こうに回して、かなり健闘したらしい。相手が二人だったら勝っていたかもわからないという。だが、残る一人が梶原の後ろから、彼の脳天に椅子(いす)を叩(たた)きつけた-。…梶原は藤岡とともに病院に運ばれ、包帯で頭をぐるぐる巻きにされたが、何としても縫合をさせない。「死んでも責任は持てませんよ」と医者に言われてホテルに帰ったが、そこでまた酒盛りを始めた。そこに警察が来た。梶原は隠れ、藤岡が警官に賄賂(わいろ)を掴(つか)ませて、これで台湾国内では一件落着。もはや長居は無用、と翌日朝の飛行機で帰国したが、大変なのはこれからだった。梶原はなんと、二十四針(一説には二十七針)も縫う重傷だったのである。縫合手術の次の日、藤岡は梶原の電話を受けた。受話器の向こうで、梶原は笑っていた。「人に言うなよ、オイ。俺よう、酒の飲みすぎで、麻酔が全然効かねえんだよ!だからよう、もう痛くて痛くて、正直言って涙が出たぜえ。といって俺、極真の幹部だしよう、人前で弱そうな顔、できねえじゃねえかよう!」(「梶原一騎伝」 斎藤貴男)
酒間の友
その「ラモール」を終え、今度は日航ホテル裏の「眉」へ。時計は十一時を過ぎていた。だけどまだ早い。「もう一軒どうだい」私が誘ったが、「これ位に今晩はしておこう」と彼が言った。無理に誘うことではない。「おれはもう少し、じゃここで別れとするか」と私は腰をあげた。私だけひとり数寄屋橋通りの裏へ。知ってる顔の女性に会う。「アンドリュース」のホステス嬢であった。先方から声をかけてきた。「そこへ今度、新しい店を…」と指さしている。みると開店のお祝いの花がいっぱい並び、地下二階の「京ずし」というのであった。祝い袋も持たなかったが、誘われるままに、その新規開店でいっぱい戴く。意地悪く材料を吟味しながら飲んだのである。そのあと「美弥」「美舟」と回って、渋谷の自宅に戻ったのは午前二時であった。ふだんは飲み疲れたあとは、足どりは重いのだが、その夜にかぎって、それを感じなかった。爽快であった。そのとき気づいたことは、一緒の友達が良かったからだ、と思った。数時間を一緒に楽しく飲むということは、ありそうでいて、滅多にないことなのだ。どんな人間にも、個人の我があり、癖があるから、わずかな時間ならもつが、長時間はつづかない。酒間の友というものは、難しいものだ。両者に差があってはいけない。私の昨今の酒のつまらないのは、同年代はすでに飲まなくなっているし、若い世代とはやっぱりどこか違っているところがあるからである。通り一辺のあいさつ以上の、会話と取り組もうとすると、それがダメなのである。説明し難いが、ひと夜東郷青児と飲んで、私の内になんの抵抗なく、有無通じ、年を忘れ、無邪気に振舞えたことが、私を爽快にしたのである。(「茂一ひとり歩き」 田辺茂一) 東郷青児の酒
赤塚の移籍
今夜も二人は、新宿の酒場にいる。相変わらず、五十嵐は赤塚達と飲んで、以前のように靴で撲りあっている。僕と五十嵐といえば、靴で撲りあう時、以前よりちょっと力を込めるか、ちょっと力を抜くかの違いが生じただけだ。酒は酒。仕事は仕事。抜かれたら、抜き返すだけ。だが、五十嵐は、ある情報を耳に入れてくれた。『バカボン』は、講談社漫画賞にノミネートされ、受賞が決定していた。しかし、サンデーに移籍した『バカボン』の授賞は、急遽取り消されたというのだ。「フーン、講談社も大人げないことするんだな」僕は、五十嵐に言った。でも、小学館が同じ立場だったら、やっぱりそうするよね、と思った。僕は、赤塚に言う。「先生、バッかだなあ。講談社漫画賞貰ってから、サンデーに来れば良かったのに。何でもくれる物は、貰えばいいんだよ。な、五十嵐」「しようもない人だなあ。先生、こいつ撲っちゃおうか」「五十嵐、許す。武居を思い切り撲っちゃえ」と赤塚。僕は、五十嵐の前に頭を差し出す。五十嵐は、思い切り、僕の頭を撲る。「痛えなあ。五十嵐、オレになんか恨みでもあるわけ?」「ないことも、ないことも、ないよ」五十嵐も酔っ払っている。「先生、講談社漫画賞なんてケチなことを言ってないで、ノーベル賞取ろう!」いつもの馬鹿騒ぎ。新宿は、間もなく夜明けだ。(「赤塚不二夫のことを書いたのだ!!」 武居俊樹) 五十嵐は、武居(小学館)のライバル・講談社マガジンの赤塚担当者だそうです。
トウモロコシ・ペプチド
しかし、そんな彼らを救済するため、酔い止めドリンクなるものが登場した。ドリンクの原料はトウモロコシ。これにふくまれるペプチドが、アルコールの吸収をおさえ、代謝を促進する効果があるというのだ。事実、動物実験でアルコールを摂取する前にトウモロコシ・ペプチドを与えると、飲酒後三〇分経過したときの血中のアルコール濃度が、ペプチドを与えられなかった場合に比べて半分以下におさえられていることがわかった。また、悪酔いの真犯人といわれるアセトアルデヒドの血中濃度も、同様におさえられた。さらに、トウモロコシ・ペプチドは、お酒と同時に摂取しても効果は変わらず、急性アルコール中毒の発生を防ぐという結果も出ている。(「酒のこだわり話」 博学こだわり倶楽部編)
カモのウルカ
ある日、先生のお宅へ幾人かでおしかけた。奥様のおいしい手料理と酒と先生の漫談が目あてだった。その日、見馴れぬ得体の知れぬものが各自の前に出された。ほんの少量だがドロッとして茶色のものだった。不思議そうに眺める私たちを見まわしながら、先生は何だかわかるかいとニヤニヤ。誰ひとりわからない。「これはだ」ト先生は得意顔。「これは鮎のウルカならぬカモのウルカだ。こんな珍味はない。これが賞味できる幸せをかみしめて味わってごらん」恐る恐るハシの先に少量くっつけて舌でなめる。何とも異様な味でなま臭く、アワテテ酒でながしこむ。酒は山梨は塩山の「旭菊」だった。「こういうものは通人は何よりと言って有難がるものだ。なんだい君たちの顔は。不通人の顔だ。なにしろシベリヤをとび立って二週間何もたべず、日本海を飛び続け、陸地が見えてヤレヤレこれで餌がたべられると気がゆるんだところを鉄砲でズドン。そういう鴨のワタだから綺麗なものさ。通人になりたかったらほらもっとたべろ」と先生はけしかける。一同顔をしかめて互いに顔を見合わせるばかり。こうして宴がはじまり、大騒ぎした後、帰りぎわに先生の前を見ると、先生のぶんのウルカには箸が全然ついていなかった。(「酒通たのしみ読本」 船戸英夫)
*ビールを飲むとトイレに行きたくなる
ビール飲みはトイレに駆け込むことで有名だとされている。ビール酒場に三時間も座って、体重の三倍のバドワイザーを飲めば、そのほとんどはトイレ行きということになる。というのは、ビールを飲む人ならだれでもわかるように、ビールは「体の中をさっと通り過ぎる」ものだからである。しかし、それが体を通り過ぎる理由と、液体の量とはあまり関係がないということは、ビール飲みでも知っている人はあまりいない。それは、バソブレシンというもの、もっとわかりやくくいえば、利尿ホルモンADHの作用である。視床下部で作られるADHは、尿の生産を調節し、間接的に血液中の水分の量に影響を与える。体内に水分が少ないときには、そのホルモンが腎臓に、尿の生産をやめるように合図を送る。そうすれば、血液は水分をより多く保持することになり、血漿に塩水が集中して死んでしまうというようなことはなくなる。このように、ADHは、われわれが体内の水分と塩分のバランスを健全に保つための助けになっている。これがなければ、われわれは大変な病気にかかってしまうことになるだろう。しかし、中には、ADHの分泌を妨げる物質もある。そういう物質が体内に入ると、腎臓は尿の生産をやめることができなくなり、何も不都合なことなどないといわんばかりに体から水分を取り続け、膀胱を一杯にし、体の持ち主をトイレに送り込み、さらに体から水分をとり続ける。そうなのだ、そのADHの分泌を妨げる物質の中にアルコールも入っているというわけだ。したがって、ビールを大量に飲むと、腎臓は有効に働かなくなる。ADHからの指令がなければ、腎臓が超過勤務をするので、膀胱は常に一杯という状態になる。また、ビール酒場で過ごすその三時間を、バーでウィスキー・サワーをがぶ飲みして過ごしても、停車場でコーヒーをすすりながら過ごしても、全く同じことが起きるだろう。カフェインもアルコールと同じくADHの分泌を妨害するもので、たくさん飲めば同じように腎臓の働きをだめにする。このように、尿の量が増えるのは、ビールのせいではなく、アルコールのせいなのである。今までの説明から、酔ったときの主な症状のひとつが、脱水症状であることは明らかである。実際、のどの渇きは、二日酔によくある症状である。それは体が、前の晩に水分を出し過ぎて干上がってしまった、と知らせているのだ。二日酔を軽くするには、バーから帰った後、水をたっぷり飲むのがひとつの方法であるのはそのためである。あなたが考えているような、寝る前の軽い食事というわけにはいかないだろうが、そうすることで失った水分が補給され、翌朝、それほどひどい気分にならなくてすむだろう。(「うそ?ほんと?小事典」 タッド・トゥレジャ 刈田元司訳)
アジ
辛口の日本酒や焼酎(しようちゆう)、ウイスキーといった酒の時の肴には断然から揚げ。油の煮立ったところに、水気を切ったアジを入れ、よく揚げてしょうが醤油(等量のだし汁と醤油を合わせ、一割ぐらい酒を加え、おろししょうがのしぼり汁を適宜加える)で食べます。「アジとは味なり」。まさに夏はこの七字に尽きますなあ。

成田山新勝寺の禁酒絵馬
(「成田山新勝寺の絵馬」 大野政治・大倉博編修) 奉納、但向(ただしむこう)三年間、三十四才とあります。杯の中に鍵が描かれています。依存症のこわさがまだはっきりと認識されていなかった頃なのでしょう。このほかにもいくつか禁酒などの絵馬があります。
菜館(さいかん) 沢田瑞穂(さわだみずほ)
韮(にら)のもえぎの一皿に
酒をふくめばさびしさよ
まちのめしやの古すだれ
みぞれうつ日も掛かりたる(「酒の詩集」 富士正晴編著)
枯らし
酒蔵の中には、出麹をその日に使ってしまうところもあって、そういうのを「出麹使い」、おらとこの蔵のように、枯らしてから使うのを「枯らし使い」と言うんだ。どっちがいいかはともかくとして、「枯らし使い」のいいところをもうひとつ言えばさ、一晩枯らしをすれば、その分だけ、米粒の表面が固くなり、もろみに使っても溶けにくくなるわけさ。とくに、後のほうで話す大吟醸酒では、「粕(かす)の裏打(うらう)ち」が出るほうがいいと言われているぐらいで、もろみをしぼった布に、まだ溶け切っていない麹が点々と残っているぐらいがいいとされているんだ。そこから考えても「枯らし」ということの大事なことがわかるんでないかね。(「杜氏 千年の夢」 高浜春男) 麹室(こうじむろ)で出来あがった麹を室から出すことを出麹(でこうじ)といいます。
徹夜酒
徹夜明けに、風呂に入り、寝る前に飲むビールのうまさなんてキザなことをいっているけれども、部屋にこもる日が一週間もつづくと、私は徹夜酒がやりたくなってくる。こんな夜は、二時までなんて誓わない。でも、「おしげ」では、ママに「今度、田舎(静岡)へ帰ったらわさび漬け買ってきてよ」なんていって飲んでいる。この店のわさび漬けを食ったら、とても外のものは口に入らないのだ。いつもは、この「おしげ」か、「郁」からスタートして、時間によって、「チャオ」をはさんだり、「偏見屋」を入れたりして、最後は「摩耶」になる。この店は、客がいれば朝の七時頃までやっている。しかし、十時頃から店をあけるのでどうしても最初の店というわけにはいかない。「鼠がゴキブリを食べちゃうのよ」、「バラも食べちゃうの」という女主人の話を聞きながら、私はビールかウイスキーを飲んでいる。話は鼠とゴキブリじゃ、色気のないことおびただしい。時時、彼女は野菜サラダをつくってくれるが、これはいける。「もう、ビール七本目よ」なんて言われると、そこからは水割りに切換える。かくて、朝がやってくるのである。マスターやママたち、それに飲み仲間たちと話が弾むと私は按配よく酔えるし、気分がいい。重い頭も自己嫌悪のない朝もあるが、ご婦人とは遠ざかった。大体、朝まで飲んで、それから-なんて気になれない。私は、何杯飲んだなんて考えないことにしている。これが、いちばん健康にいいのだ。あとは、ただ眠るだけだ。そのうちには仕事の電話がかかってくる。すると、もう十一時近いのである。(「作家の食談」 山本容朗)
プレミア酒
このような、いまでは多量の生産を行っている酒造場の銘柄を珍重し、ディスカウント店などで不当に高く売られているものまで買ってしまう消費者が多い。ディスカウント店では、これらの銘柄はだいたい定価の二倍から三倍で売られているが、例えば越乃寒梅を定価で買いたければ、西荻窪の「三ツ矢酒店」のような良心的な小売店で予約すればよい。白ラベルが定価二千四十円で購入できる。何故ディスカウント店が高い値段で売るかというと、彼らは正式な流通経路ではこれらの銘柄を入手できず、酒屋などで買ってくるからである。その酒屋も人気が高い銘柄だとプレミアをつけていることが多く、さらにプレミアが倍加されていくというわけだ。このような不当な高価格で、しかも温度管理もちゃんとできていないディスカウント店で購入するのは、知識先行で自分の舌で美味しい酒を選択しない消費者の責任でもある。(「蕎麦屋酒」 古川修)
酒で記憶をなくす
酒の話をするのはつらい。自らの恥について語るのと同義だからだ。三十代になってから、泥酔すると記憶を失うようになった。特に、ビールやらワインやら焼酎やらを飲んだあと、最後に日本酒が来ると危険だ。あるときは、深夜に知人の家に押しかけたらしく、目が覚めたら寝袋に収められていた。「しまった、やらかした」と思い、知人に詳細を聞くと、私は家に押しかけたのではなかった。迷子になって夜中に知人に電話をかけ、どことも知れぬ街道までタクシーで迎えにきてもらっていたのだ。迷惑の度合いが、より高い。知人の家に到着しても、蛇のごとく床を這って逃げるので、足をつかんで寝袋に収納したとのこと。ほんとにすみません。蛇といえば、便器を守護する大蛇のように、トイレの床にとぐろを巻いて横たわっていたこともあった。しかも、用を足したあとに力つきたようで、下半身裸だった。(ジーンズとパンツはトイレの外に脱ぎ捨ててあった)。このときは、下半身の衣服とともに前夜の記憶も完全にすっぽ抜けたらしく、目が覚めた瞬間パニックに陥った。ドラマや漫画における記憶喪失の表現として、「ここはどこ、私はだれ」というセリフがあるが、実際に記憶を失うと、そんな論理的な思考はとてもできない。なにがどうなって、トイレにて下半身裸で目覚めるに至ったのか皆目わからず、脳内は「※〇95ネ#%めケ!?」という感じになった。次に思ったのは、「女の子の大事なものをなくしてしまったのかしらん」ということだったが、尻が冷えていたのみで不審な点は見当たらず、社会的信用以外に失ったものはないようであった。あー、よかった。のか?日本酒を一升ぐらい飲んでもピンピンしていたころは、「酒で記憶を失う?そんなバカな」と思っていた。酔ってタクシーの運転手さんを殴ったけれど覚えていないとか、電車内で痴漢をしたのに酔っ払って記憶にないとか、そんな事件が報道されるたび、「嘘つくな、ごるぁ?酒飲みの風上にもおけんやつめ」と憤っていた。いまも、酔いを理由に不届きな言動を許す必要は微塵もないと考えているが、しかし、「酒で記憶をなくした」というのは必ずしも言い訳ではなく、本当に覚えていない場合もあるんだろうなと、身をもって思い知ったのだった。加齢とともに酒に弱くなり、かわりにひとつの知見を得たというわけだ。(「下戸一族VS飲酒派」 三浦しをん)
血による儀式をすてる
そして、酒を飲むことによって起こる陶酔感は、他の多くの現象を超越するほどの神秘としてとらえられ、しばしば、神-宗教的儀礼-酒という関係を結びつかせるものであった。とくにこの関係で興味あることは、狩猟時代には神事儀礼の供えものには生贄(いけにえ)や血をそそぐ風習であったのが、農耕を知る時代に入ってからは、血による儀式をすてて酒を供えるものに変わったことである。したがって酒を持ついずれの国でも、酒の神は農業や収獲の神であり、また酒と神が一体となった収獲の神事を多く見ることができる。日本でも、農業祭や新嘗祭(にいなめさい)は酒と収獲が一体となった行事で、白貴(しろき)・黒貴(くろき)の二種の酒を収獲米を用いて造り、神に供える。このように初期の酒は、人間と農耕の神を密接に結びつける重要な媒体であった。(「酒学入門」 小泉武夫・角田潔和・鈴木昌治編著)
大人の濁り酒カクテル
これも蔵元に教えてもらったカクテル。「常磐壽」(鈴木酒造店・福島県浪江町、長井蔵・山形県)蔵元の鈴木大介さんは、クラッシュアイスに、日本酒度-(マイナス)22の甘くて旨味がたっぷりした活性濁り酒「標葉(しねば)にごり」を注ぎ、ダークラム(ダーク・ラム)を2~3滴垂らして飲むと旨いと薦めてくれました。なお、この濁り酒は夏に出荷されるのですが、ぬる燗にして飲むと、身体にやさしく染み通って、飲んだあとにシャッキリ。夏バテ防止にぴったりでした。さらに鈴木さんは「温かい牛乳で割ってもいいし、冷たい牛乳でも美味しいですよ」と教えてくれました。牛乳と聞いてゲテモノと思ったあなた、試してびっくりしないように。
下戸(げこ)の猩〻(せう/"\)
出格子(でがうし)に、唐(から)ぞめ指南所(しなんどころ)と看板(かんばん)かけたるものあり。ある人、弟子入(でしいり)して、羅紗(らしや)、猩〻緋(せう/"\ひ)、毛氈(もうせん)の染様(そめやう)をたづねけれバ、猩〻緋ハ猩〻をとらへて、よき酒にかた紅(べに)を入、酔(ゑふ)ほどにのませて、その血(ち)にて染(そむ)る。毛せんハ少(すこ)し、次(つぎ)の酒をのませ、すわうをせんじて、酔(ゑ)ふほどにのませて、その血にて染む。萠黃(もへぎ)らしやハいかにとたづねけれバ、是ハちとむつかしい。随分下戸(げこ)の猩〻をとらへて、雛(ひいな)様の餅(もち)をくはせる(五オ)(「万の宝」 武藤禎夫・編)
船がつきます百廿五艘(そう)
積んだ荷物は米と酒(淡路船歌)
うちの父さん酒に酔うてこけて
赤い手拭い土まみれ(若狭盆踊唄)
酒は剣菱男山
一杯のんだらとてつるてん(大阪安楽坊)(「日本の酒」 住江金之)
一杯(いつぱい)は安多加(あたか)の関(せき)の心地(ここち)なり。
*高杉晋作『甲子残稿』(元治元年・一八六四) 酒席での議論のおもしろさを、歌舞伎『勧進帳』の弁慶と関守のやり取りになぞらえている。「安多加の関」は、安宅の関。奥州へ落ちのびようとする源義経主従は、ここでとがめられるが、弁慶の機転により救われる。(「日本名言名句の辞典」 尚学図書辞書編集部・言語研究所)
大酒致候
去る四日ニは八郎へ、甚四郎、宮内、八郎兵衛、曽我又左衛門、松田又兵衛、、金五郎、浪人ニ独楽と申者同道ニて花街へ参、帰ニ船ニて大酒致候。十五日ニハ川手屋敷へ孔子弟子(儒者)共寄合気ヲ誥(告げ)申候。十六日ニ川手屋敷へ出家(僧侶)客御座候て野郎共、二、三人参、又大酒致候。十八日も十六日同前ニ御座候。十八日ニハ船ニて、与レ風、本多出雲守、横田甚衛門乗合、出家衆ノ船へ参、又々酒成申候。明後日廿九日ニも出家野郎参会の筈ニ御座候。下官(光圀)事頃日(けいじつ)ハ宗旨賛野郎と度々参会申候。おかしき公義少々も懸二御目一申度(おめにかけもうしたく)候。 以上(「小城(おぎ)鍋島家に残された義公書状の特色について」 伊藤修)